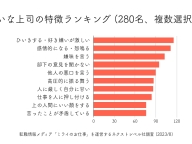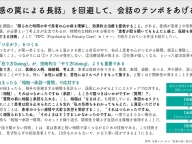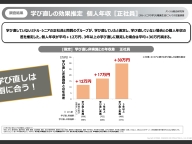幼稚園からプログラミングを始め、小学生でゲーム170本を制作
――最初にエンジニアになったきっかけを教えてもらえますか?
ネオキャリアCTO(以下、CTO):僕が幼稚園の年少だった頃が、ちょうどファミコンが発売されていた時代なんです。僕が父親に「ファミコン買ってくれ」と言って「おし、買ったるわ」と言われて家に来たのが、パソコンだったんですよ。
――(笑)。
CTO:当時のMSX(1983年にマイクロソフトとアスキーによって提唱された8ビット/16ビットパソコン用の共通規格)みたいなもので、「ぜんぜんファミコンとちゃうやん」と思ったら、父親に「いや、これでファミコン作れるから」と言われたんですよ。
いわゆるBASIC(入門用プログラミング言語)の本とパソコンを渡されて、「お前、これでファミコン作れ」と。5歳か6歳の頃だったので、「ぜんぜん意味がわかんないですけど」って。
――(笑)。お父様は、エンジニアさんなんですか?
CTO:もともと父親は技術技官なんです。その絡みで、いろいろなメーカーさんとお付き合いがあったので、家にもパソコンやオフコンが転がっていたわけです。それが家にあったりしていて、小さい時から趣味で触ってたわけなんですけど。
みんながファミコンで『ドンキーコング』とかをやっている中で、僕は真っ暗な画面でテキストだけの世界の中に入っていくわけですよね。みんなの話についていけず、もう1年間は泣き続けて、がんばってBASICを勉強して。小学校1年生の終わりか2年ぐらいの時に初めて、自分でドンキーコング風のゲームのプログラムを1つ完成させたんです。そこからハマりだして、小学校6年生までで170本ぐらいのゲームを作ったんですね。
――自分で考えてですか?
CTO:自分で構想を考えて、コードを書いて、設計……。デザインはできないので、もう線画みたいな感じで、設計構築のフローチャートを作って、コードを書くようなことを1人でやって。
――すごいですね!
CTO:いや、もう意味わからないですからね。「何これ? INPUTって何?」みたいな、「IFって何?」「関数?」って、もうぜんぜんわからなかったです。
でも、だんだんおもしろくなってきて、小学校3~4年生の頃は、電波新聞社の『マイコンBASICマガジン』にソースコードを投稿するマニアだったんですよ。毎月毎月5本とか10本とか送って、そこに掲載されたら喜びを感じる、という。父親がパソコンを買ってくれていなかったら、たぶんこの業界に来てないと思います。
夏休みの研究課題は「タイムマシンをどうやって作るのか」
CTO:あと、もう1つは映画なんですよ。1985年に『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を見て、ドクになりたいと思いましたから。それもあって、コンピュータってすごいなと思ったんですね。
――御社の人事の方から事前にCTOの情報を少しいただいていたんですけど、デロリアンを持っていらっしゃるって本当ですか?
CTO:はい、カリフォルニアで買いました。今は東京にあって、全部メンテナンスしたので、ちゃんと走ってますよ。日本で本当にちゃんと動くデロリアンは、たぶん20台ぐらいしかないと思います。
その映画を見たのが小学4年生の時で、夏休みの研究課題で「タイムマシンをどうやって作るのか」というテーマで(レポート用紙に)400枚ぐらい書いたのかな。実際の特殊相対性理論をベースにして、時空というものが3次元の中でどういうふうにやればできるのか、勝手な解釈と理論をもとに書きなぐって。
――それ、先生が理解できていないですよね。きっと(笑)
CTO:担任の先生がわからなくて、京都大学の物理学の先生にわざわざ持っていって見てもらって、「これは70パーセント正しい」「ちなみにこれを書いたのは大学何回生の子なの? どこにいる子なの?」と言われたらしくて。
――10歳という(笑)。
CTO:担任が「うちの小学生です」と。「この子、やべえ子になるんじゃないか」って言われて、ちょっとうれしかったんですけど(笑)。それで、01の世界と時間というものを考えられる人間の脳はすばらしいと思ったんです。
将来はモノづくり屋さんになりたいと思っていて。母が飲食店の給食などをやっていたんですけれど、ものすごく非効率な働き方だと思っていたんです。それで中学1、2年の頃に、母が給食で作っていたレシピを自動化できるようなデータベースを作ってあげました。例えば、焼き肉定食が140食出るとしたら、データを集計して、「月曜日と火曜日にはこれを売ったほうがいいんじゃないか」というものがわかるようにして。
母に「すごく役に立った。ありがとう」と言われて、「なるほど、こういうサービスもあるんだな」と。ただ、小・中でひたすらコンピューターの基礎をやっていたので、友達がいなかったですね。
――じゃあ、もう家に帰ったらすぐパソコンを開くという少年だったんですね。
CTO:いや、もう学校からかもしれない。小学校5年生か6年生ぐらいに、エプソンが出した14キロぐらいのラップトップを持っていっていました。みんな休み時間になったら外に遊びに行ったりするけど、僕はずっとパソコンをやっていたので。
AIを作りたくて医学部へ進学
――それだけ魅了される理由はなんですか?
CTO:僕、ハマったら行き着くところまでやりたいんですよ。小さい頃は余計にそういう性格が強かったので。たぶん魅了というより、コンピュータとしゃべっているような感じです。プログラムを書いて、「このとおり動いてね。あっ、動いた」「動かない。えっ、何? バグ出てる。えっ、なんで?」というのをずっとやっていた感じです。
――すごいですね。これも事前情報で医学部に進学されたとおうかがいしたのですが…最初は医者になろうと思われたんですか?
CTO:人間の感情や学習記憶能力、コミュニケーション能力に興味があって、「なんで脳1つでこんなことができるんだろう?」と。そこからAIを作りたいなと思ったときに、工学系がいいか人間の脳を勉強するかというので……。要は、人間の脳のロジックがちゃんとわかって、それをどうプログラミングすればいいかを考えたほうが効率がいいんじゃないかなと思って、医学部へ行ったんです。
――すごいですね。全部つながってるんですね。
CTO:だから、僕はたぶん生まれてから18歳までは1つのことしかやってないですよ。脳ができることの100パーセントは無理かもしれないけど、20パーセントでもコンピュータでできるようになれば、プログラムはすごく簡単になるし、誰でもコンピュータが使える時代が来る。もっと簡単に誰でも触れて、音声で応えてくれるようなものもできてくる。今はもうそんなの当たり前でSiriとかもありますけど、そういったことができる時代がくるんじゃないかと思ったのが90年代ですね。
――医学部に行ってみていかがでしたか?
CTO:いや、勉強ばっかりで超大変でしたね。「医学部ってこんな大変なの?」と思うぐらい。めちゃくちゃ勉強量あるなと思いました(笑)。
――大学時代は医学を勉強しながら、「なんかこれ違うんじゃないかな?」という違和感はあったんですか?
CTO:いや、ぜんぜんなかったです。超楽しかったですね。人間の身体ってやっぱりすごくおもしろかったですし、「まだぜんぜん脳のことをわかってないな」と改めて思って。今ここでしゃべっているのも、3〜5パーセントぐらいの脳しか使っていないし、「本当に100パーセント使い込んだらどうなるんだろう?」ってすごく思う。
量子コンピューティングとかいろいろ出ていますけど、そういったものが本気で動き出せばもっとやばい世界観が来るなと思いますし、イーロン・マスクやホーキング博士が「AIはやばい」と言っているのはすごくわかります。本当に究極までいくと、間違いなく人間を超えてくるでしょうね。人間よりも効率よく考えるし、感情に邪魔されることもないから、AIが自分でプログラムを書こうとするとやばいですよね。
結局家庭の事情や、私自身も早くIT系の事業を行いたいという思いもあり、4年後に中退してしまいました。父からは大激怒されましたし、勘当もされましたが実際問題実家からのお金の問題もあり、中退せざるを得ませんでした。
20代半ばでパソコン週刊誌及びコンテンツの強さを実感
――医学部中退後はどこに就職されたんですか?
CTO:いくつかお話をいただいて、すごく悩んだんですけど、どベンチャーのIT書籍を手掛けている出版社です。幼稚園の時からパソコンには興味がありましたし、声をかけてくれた代表の方に昔からもすごく興味がありましたから。
その会社の中でいろいろなITの人たちの出会いがありました。関連会社には研究所のようなところがあって、動画配信やAIのようなものの実証実験、画像解析などをやらせてもらっていました。
僕は週刊でのパソコン専門誌の編集部に入って、当時のいろいろなITベンチャーの経営者の方々にお会いし、パソコン専門誌を週刊で出すことの大変さやコンテンツを生み出す力というものもすごく勉強しました。
毎週コンテンツ企画を出して、編集長に判断を仰ぎ決まったらすぐに記事にするということを繰り返して行いながら、実際に記事になり読者からの反応を感じるというおもしろさとシビアさを感じていました。コンテンツの強さという部分に感動した感じでした。
――出版というコンテンツを生み出す力については、どう思われていたのでしょうか??
CTO:編集長には、「編集者は企画がすべて。企画が出せなくなったら、それは編集者でもないし、おもしろいものが作れるわけがない。エンジニアが企画を出せるから、パソコン誌はおもしろくなる。もっと頭の中から汗をかくぐらい考え抜いて企画を出せ」とよく言われました。
やはり、企画を出してそれを形にするという力を本当に鍛えられた会社だったと思いました。ここがあったので、エンジニア×サービスというものを作れるようになったんだなと思いました。
その後、僕はスタートアップのベンチャーに行きました。そこでいわゆるインターネットTVみたいなものを作ってくれと言われて、新規事業をやることになって上場したんです。上場したら時価総額が7,000億円ぐらいまでいって、その時に200社以上の会社を買いました。
「その経営戦略をお前が見ろ」「技術デューデリをやれ」ということをいきなり言われて、IT会社がジョインすると、僕がその会社に放り込まれて技術デューデリをしたり、子会社を作って動画配信系の事業を作ったり。テレビ局に動画配信のテクノロジーを提供したり、たぶん日本の動画配信の技術テクノロジーはほぼ全部、その会社でやらせてもらっていたんですよ。それだけで300億ぐらいの売上があったんです。
動画配信を基軸にいろんなことをやり続ければ、絶対にビジネスマネタイズできると思ったので、ケーブル局さんとビデオオンデマンドのはしりみたいなものをやったり。あと、全国のホテルで動画を見られる仕組みも、技術特許は全部僕個人のものです。
30代でスマホアプリ専業のベンチャーを立ち上げ
CTO:僕は「スマートフォンがくる」という情報を得ていたので、「社長、これからiPhoneきます。スマートフォンというものがくると思います。なので、もうガラケー捨ててスマホでやりましょう」と言ったんですけど、経営陣は全員「ガラケーだ」となってしまって。
「じゃあスマートフォン専業の会社を別で作ります」と言って独立して、初めてスマホのアプリ開発及び、携帯電話向け動画配信、バーチャルリアリティ専業のベンチャーを作ったんです。iPhoneのアプリ開発ベンダーとして、いろんな受託を受けさせていただいて、今でいうアプリの受託開発屋さんみたいなものでした。
また、日本でもスマホがまだまだこれからの普及していない時代に、バーチャルリアリティが来ると思って、その開発を行うことと、もともと動画配信をやっていたので、プラットフォームを作って販売する事業を作りました。
――それは何歳くらいの時ですか?
CTO:今から……30歳か31歳ぐらいですね。
――なぜネオキャリアだったんですか? たぶんどの会社でも望めば行けたじゃないですか。
CTO:結局、受託のほうが目先のお金になる。でも、大きなお客さんを取ると入金までのタイムサイクルが増えるので、キャッシュがしんどくなるんですよね。だから、受託もやりながら自社プロダクトを持てるような組織を作りたいと思っていたんです。
それで会社を抜けてから、MBAをとるために大学院に行ったんですよ。ずっと理系で来たので、「自分の経営センスや経営マインドは正しいのかな?」という思いがあって、経済や経営を体系的に学びたかったんです。イギリスで2年間、MBAをみっちり勉強してから日本へ帰ってきて、嫁に「仕事をちゃんとしろ」って言われて。「遊んだでしょ、2年間」「そうですね」みたいな。
――(笑)。
6年前のネオキャリアとの出会い
CTO:それで、知り合いの紹介でITアウトソーシングサービスの会社に、いちエンジニアとして入社しました。でも、3ヶ月で「お前、事業部作れ」と言われて、その時にオフショアを勉強したんですよ。
その会社は中国にオフショアを持っていたので、それを使って開発ベンダーを作ろうと思って、中国と日本の開発をやって、140本ぐらいのお客様に受託させていただいて、オフショアのやり方を学ばせてもらいました。それからソーシャルネットワーキングサービスの会社に誘われて、BtoCビジネスを学んだり、不採算事業部の立て直しをしたりして(笑)。
そうこうするうちに、誘ってくれた役員が辞めてしまったので、僕も辞めてフリーでいろんな会社と仕事をする中で、ネオキャリアとの出会いがあったんです。それが今から6年前ですね。
ネオキャリアの専務の加藤と初めて会って、事業やビジョンの説明をしていただいたんですけど、その時に「2030年に1兆円になる会社をつくりたい」と真顔で言われたんですよ。僕の人生の中で、まじめに1兆円やりたいといった人はあんまり知らなくて。
1,000億円という人はいたんですよね。でも、1兆円はいなくて。リクルート創業者の江副さんは、はなから「世界に目指す100兆円企業をつくる」と言っていたのと、「1兆円の物流をつくる」と言ったダイエーの中内さん。あと孫さんですね。
僕が知っているのはその3人ぐらいで、みんな成功してるじゃないですか。その4人目として、加藤が真顔で、しかも具体的に「2030年までに1兆円にしたい」と。
――例えば、大手の会社に行った方が1兆円は近道じゃないか?とは思わなかったんですか?
CTO:いや、逆に興味を持って。人材系の中でも本当に異端児だし。
やりたいことができる環境と将来性があるかどうか
CTO:そう感じた時に、ネオキャリアは、絶対おもしろい会社を作れるんじゃないかと思った。いろいろ考えたんですよ。やっぱりITは人でしか成り立たないビジネスなんです。
だから、人材を集めたり、なんらかのかたちでマネタイズできる会社なら、そこには絶対にAIやテクノロジーが必要だし、そういったサービスをバンバン作れる環境が今の世の中になかなかないなと思ったときに、「1兆円やりたいです。好きなことをやってください」「テクノロジーがぜんぜん足りていないから、そこをテクノロジードリブンで変えていきたい」と言われて。
6年前のその当時は弊社サービス「jinjer」の構想もなかったし、なにもなかったんですよ。だから、「この人だったら、もしかしたらなにかやらせてくれるんじゃないかな」と思って。そしたら面接の時に「来週からちょっと東南アジアへ行ってもらっていいですか?」と言われて。「何の話ですか?」みたいな(笑)。
――(笑)。
CTO:「いや、東南アジアでもグループがいっぱいあるんですけど、なにか新規事業を考えたいので、いっぺんちょっと経営企画の人と一緒に、2週間くらい東南アジアを回ってきてもらっていいですか?」といきなり言われて、「この人なんやろう」と(笑)。
テクノロジードリブンで人事部を変えていく
CTO:でも、その翌週から、実は社員でもないのに、ネオキャリアの経営企画の人と4人で、ベトナム・タイ・インドネシアを回ったんですよ。それでいろんな事業モデルとかをみんなでしゃべりながら、なにができるかを一緒に考えていって。
2週間後に帰国して、加藤に出張報告と「こんなビジネスができるんちゃうか」という話をさせてもらったんですよね。それが、いろいろ調べた結果、「出版をやったほうがいいんじゃないですか」という意味のわからない提案になって(笑)。
「いや、出版はちょっとさすがにかけ離れてますわ」と言われて、「そうっすよね。でも、出版が一番儲かると思うんですよね」という話をちょっとして。東南アジアをいろいろ回ったら、まだぜんぜんITリテラシーがないし、自社メディアを作ってそこに広告モデルを作ったほうがおもしろいんちゃうかなと思って提案したんです。
ちょうどキュレーションメディアが流行っていたので、「求人×情報・ニュース」みたいなもののキュレーションメディアを作ったらおもしろいんじゃないかと。今のIndeedみたいなもので、6年前には早すぎたんですけど。
そういうものを作ったら、加藤が「こんなに速く作れるエンジニアがいるんだ」と、「じゃあどんどんエンジニア領域をやろう」と言ってくれて、ちょうど3年前に「jinjer」の話を始めたんです。
要は、勤怠サービスみたいなものと、採用管理をやらなきゃいけなかったので、最初は新卒領域のいわゆるATS(採用管理システム)みたいなものを作るところからスタートしました。
僕は、母が飲食店で働いていて、勤怠管理ですごく困っていたから、「採用管理でもいいですけど、勤怠もあったほうがいいんとちゃいます?」という話をしたら、「じゃあ、勤怠やってください!」という話になって、「jinjer」を作りました。
――御社が「jinjer」をリリースされた時にちょうど私もそれを見て人材企業のネオキャリアがHRTechを始めた「この会社はどこへ向かっていくんだ?」という驚きがありました。
CTO:そうですね。当初から加藤と話していたのが「jinjer」は勤怠だけじゃなく、給料も含めて採用管理も人事管理も労務も全部1つでできるようなものをやると。「jinjer」でいう「1Master 1DB」という構想があったので、そこをネオキャリアの一番の売りにしたんです。テクノロジードリブンで人事部を変えたいと思っていたので、それをやりだしたという感じですね。
――ネオキャリアがテクノロジーの力を得て進化していく、まさにCTOはその火付け役だったわけですね。