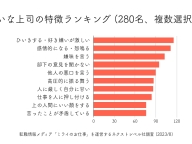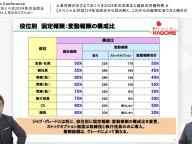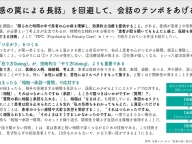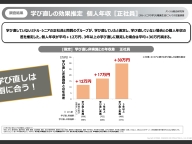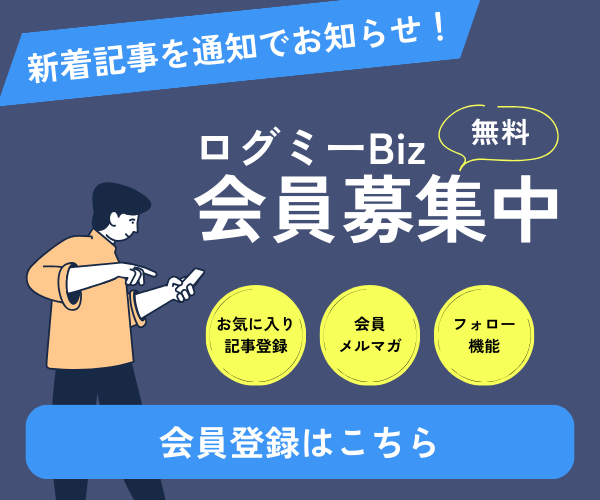生い立ちと対局時の過ごし方
司会者:それでは加藤先生にご登場いただきますので、盛大な拍手でよろしくお願い申し上げます。
(会場拍手)
加藤一二三氏(以下、加藤):これから話をはじめたいと思うんですけれども、まず今回、本当にいい本を出版していただきまして、非常に感謝しているところです。率直に言いますと、今回のこの本の出版ですけれども、この1年間で本を書く約束をですね、20社としてるんですが、すばやく仕事をしていただきまして、はっきり言ってね、ごぼう抜きにこの本を出していただいたということです。
あらためて僕、思うんですけれども、やっぱり仕事というのは素早く、テキパキと、やや強引なぐらいにしていくのが、よろしいですよね。というので、本当に素早くテキパキと私に取材をしていただきまして、その結果、本日、このような非常にうれしい記念講演会をすることに至りまして、深く感謝してるところです。
私は、昭和15年に福岡県の稲築町というところに生まれ育ったんですね。今は市町村合併で嘉麻市になっておりますけれども、ときどき思い出しますと、私はやっぱりあらためて、日本は文化国家だと思うんです。
昭和15年生まれで、小学校に入ったとき、平小学校と言うんですけれども、今でもありありと覚えてますが、バッハやヘンデル、ハイドン、それからモーツァルト、ベートーヴェンなどなど、クラシックの天才たちの肖像画が、その教室の上に立てかけてありました。
私はそのとき、1年生だったんですが、「お、この人たちは音楽の天才たちで、たぶんこの方たちの素晴らしい名曲を、のちに聴く日がくる」というふうに私は思ったんです。のちに(実際に)私は彼らの名曲を、よろこんで聴くことになりました。
将棋の対局の過ごし方は、そうですね……。将棋の研究を2、3時間して、それから好きなクラシックの音楽を聴いて、とくに結婚してからは、いわゆる勝負の対局の前日の食事は、妻が長年にわたって、ビーフステーキを焼いてくれました。
もちろん肉だけとは違って、ほかにいろいろと野菜がついてるわけですけれども、対局の前の日は、妻の料理で心身を整えるというのが、長年の習慣でした。
小学校4年生で「プロになれる」と思った
加藤:それで、思うんですけれども、小学校の4年生のときにはじめて、朝日新聞の将棋欄を読んだんです。今でも朝日新聞の将棋欄はありますけれども、そこでは名人戦の予選の順位戦という戦いの模様を、観戦記者が描写していたんです。
4年生ではじめて、その順位戦の観戦記を読んだときに、こういう文章がありました。Aという棋士が素晴らしい攻めの手を指したんですね。いい攻め方をすると、「Bという棋士はそれに対するいい受け方がない」という表現をするんです。
あの、受け方としては5通りも10通りもあるんですけれども、どういうふうに受けても、この指された手に対して対抗することができない、そういう文章を読んだときに、私は「お、そうか。将棋というものは要するようするに、いい手ばかりを指していけば勝てる世界だ」と悟ったんです。
当時、私は4年生だったんですが、そのときに私はですね、プロになれると思った。「あ、これは自分に最も向いている世界だ」と悟りまして、これがですね、実現いたしました。
本や偉人から学んだ幼少期
加藤:私が4年生のときにはじめて将棋の本を、父母に買ってもらって読みました。私の生まれ育ったのは稲築町というところで、ある意味地方都市です。けれども、近くに本屋さんがあったんですね。
ですから、この近くにあった本屋さんで、例えば詰将棋の本を買ってもらって読んだし、それから懐かしい思い出で、月刊誌を家では取ってくれていました。今でも覚えているのが、その月刊誌に偉人伝というのが出ておりまして。
その偉人伝のなかで、今でも覚えてますけれども、例えば野球の沢村投手(注:元プロ野球選手 沢村栄治氏)とか、スターリンとか、それから歴史上の人物では、僕はのちにカトリック教徒になりますけれども、ジャンヌ・ダルク。
ジャンヌ・ダルクという方は、今でも覚えてますが、天使のお告げによって、メッセージを受け止めて、救国の英雄として、フランスの国のために戦って、見事に成功するんだけれども、残念ながらあとは悲劇に終わる。カトリック教会では聖人のひとりにあげてますが、すでに小学生4年のときにはジャンヌ・ダルクのことは知っておりました。私、思うんですが、地方に生まれ育った私なんだけれども、1年生のときに絵の時間に、チューリップの花を描くことになって、チューリップの花を見たんです。
そこで「チューリップの花というのは、素朴で美しい」と、そう思ったんです。それで「この世の中のことはできるだけシンプルに、素朴に考えてもいい」というふうに「招かれてる」と感じたんです。2年生になったときですね、今度はグラジオラスの花を描くことになりまして、前のほうに飾られてるグラジオラスの花を見たときに思ったんです。
1年のときに見た花では、素朴にシンプルに、あまり複雑に考えなくてもいいというふうに「招かれた」と思って、それはまったく100パーセントそうなんだけれども、グラジオラスの花を見たときに「この世の中は、深く物事を考えられる、考えるように招かれる」と思ったんです。
そこでその瞬間、私は心の底から「いいところに生まれた」と思いまして、なにか私の身辺に、暖かい風が吹いておって、私はその暖かいものに包まれていると思いました。これは小学校1年生、2年生の体験ですけれども、その私の考察は、今でも真理だと思っています。
以後ですね、私は77年の人生を今まで送ってきましたけれども、私はやっぱり思うんですよね。物事の考え方っていうのは、シンプルに素朴に考えてもいい場合も非常に多い。同時に、やっぱり深く深く考察をしていく、深く考えないといけない。この両方から成り立ってるということ、この悟りは、今でも私は真理だと思っております。
「この子、凡ならず」と称された小学6年生
加藤:それで、小学校4年のときに新聞の将棋欄の文章を読んで、プロになれると思って、具体的には小学校の6年生のときに、すでに私は大阪の奨励会というのに入っておりました。たしか小学校の6年生のときだと思うんですけれども、あるいは、もしかしたら中1のときかもしれませんが、こういうことがありました。
大阪の将棋会館で、板谷四郎八段という先生に飛車香落ち(注:一部の駒を取り除いて対局するハンデキャップの一種)で教えてもらっていたんです。ありがたいことなんですけれども。プロの大先生が、単なる1人の子どもをつかまえて将棋を指しましょうと言ってくださるなんてことは、あらためて思うと、やっぱりたいへん、ご厚意のある方の行いですよね。
私は、板谷先生に飛車香落ちで教えてもらっていたんですよ。そこで、かれこれ1時間ぐらい指したんです。そのとき、この戦いが終わる時間のころに、なんと気が付いたらですね、升田幸三、当時の八段、のちの名人がいらっしゃっていたんです。
当時の将棋界っていうのは、名人は木村義雄名人の時代。その木村名人をですね、追っかけるというか、はっきり言って引退に追い込むホープとして升田八段、それから大山康晴先生がいらっしゃって。
この升田、大山が将棋界の次世代を担うホープとして注目されていたのです。升田先生は当時八段で、板谷先生と私が対局し終わったときに、私のことを「この子、凡ならず」と、こう言ったんですよ。
私はけっこうね、ある部分強気な人間でして、次世代の名人という大先生が「この子、凡ならず」とおっしゃってくださったときに、私は「そうか。升田先生は私のことを非凡だとおっしゃってる」というふうに悟りました。
升田八段がハンデなしで将棋を指してくれた
加藤:升田先生にはそのときが最初の出会いです。以来、升田先生はその後も私と平手で(注:ハンデキャップをつけない通常の対局)、よく指してくれました。それはつまり、こういうことだと思うんですね。
当時、急戦矢倉という戦法が流行していまして、升田先生は将棋界のホープで急戦矢倉が得意だったんですけれども、まだ私はプロの初段になってなかったんです。でも時々ですね、私と会うと先生から申し出て、先生の強い希望で私と将棋を指してくださいました。
思うんだけれども、八段と初段レベルですから、普通であれば、まず飛車香落ちと言いまして、飛車と香車を升田先生が引いて、つまりハンデをつけて対局するのがちょうどいい手合いなんですよ。
正確に言うと、飛車と香車を落とされていい勝負ぐらいの実力差があるんですけれども、升田先生はあえて平手で指してくださいました。でもやっぱりおもしろいですよね。私もなかなかのもので、平手で先生と戦って指しても、そう簡単には負けませんでした。
だからこそ升田先生は、私と将棋を指すことを、はっきり言ってね、貴重な時間だと思ってくださってたんですよね。だってね、普通だったらですよ、八段と初段の間柄で指そうなんてことは、プロの大先生にとっては、まったく時間の無駄に決まってますよ。
だけれども、先生はあえて僕と将棋を指すことに、大きな喜びを覚えていらっしゃったんですよね。今から思うと、升田先生と僕とで将棋を指したんだけれども、どうも会話というものをまったく覚えていない。つまり、どうやら升田先生も僕も、無言で指して、一切会話なしでやってたというのは、不思議ですよね。
名人戦の誕生と、将棋連盟の発展
加藤:我々の世界っていうのはおもしろい世界でして、升田先生とはこの小学校のときに出会ったわけですけれども、それ以来、私が四段になってプロになってから、公式戦で約60局戦っています。それから、だいたい同じぐらいの時期に大山康晴名人、当時はまだ名人ではなかったんだけれども、大山先生とは私が四段になって以来、公式戦で125局戦っています。
だいたい棋士というものは、特定の人との対局は、生涯で、まあ多くても50局というのが平均です。それなのに大山先生とは125局戦ったし、それから二上達也九段とは99局戦いましたし、それから中原誠名人とは100局以上戦ったし、米長邦雄さんとも100局以上戦いました。
いわゆる100局以上、あるいはその前後戦ったライバルがいるんだけれども、つまりそれは何を表してるかと言いますと、お互いが実力者同士だから、ということです。
長年にわたって多くの対局に勝っていきますと、そのライバル同士は最後にタイトル戦で激突いたします。タイトル戦っていうのは、だいたい7番勝負、あるいは5番勝負が多いんです。ですから、例えば私と大山先生がタイトル戦をたびたび戦ったんですけれども、7番勝負はどちらかが4勝すれば勝敗が決まるので、1つのタイトル戦で平均すると6局戦うんですが、その結果ですね、生涯に125局戦ったということになったんです。
升田先生や大山先生の思い出を語ると、いくらでもお題はありますけれども、一応ですね、そもそも将棋の世界というのは、名人というのがありまして。「名人戦」というものが、昭和12年に毎日新聞社によってつくられまして、それで将棋界は発展の礎ができました。
つまり、「名人戦」という根幹になるタイトル戦ができたことによって、我々の先輩棋士たちは、生活がまず安定いたしました。たぶん間違いじゃないんだけども、昭和12年に毎日新聞社が、我々の先輩棋士たち、いわゆる将棋連盟っていう団体に、契約ですから、当然契約金を払ってくれたわけなんです。
いわゆるその名人戦のリーグ戦に参加した棋士は、だいたい約10名。今でもそうだけれども、A級の八段の棋士10名で戦って、名人を決めるということになったんだけれども、その名人戦に出た10人の、リーグ戦に入った棋士たちは、たぶん間違いがないんだけども、家が1軒建ったんです。
ですから、今でもそうですが、我々の先輩の棋士たちと年賀状の交換をしたんだけれども、多くの先輩棋士たちの住所はだいたい、いいところなんですよ。
(会場笑)
四段のプロ入りから「ノンストップ」で八段へ
加藤:でも本当にね、それによって棋士の生活が安定して、それから将棋連盟という母体も発展していきまして、それが今日に至っている。つまり将棋の棋戦は名人戦がはじめてできて、今、竜王戦や棋王戦、王将戦など、タイトル戦がいっぱいあります。
それらはすべて将棋連盟と新聞社との間で契約を交わしまして、我々は素晴らしい、(ほかの)誰も指せないような将棋を指すことによって、いわゆる謝礼として契約金を新聞社からいただいて、今日に至っております。
今のところ、そういったタイトル戦というものが、かれこれ大まかに言って10はあります。それらはだいたい50年、60年、70年と歴史があって、今に至って途中でなくなった棋戦はありません。ということで、それが将棋界の、我々棋士の根幹になっております。
私は14歳で四段になりまして、それからノンストップで、18歳でA級の八段になったんですね。A級の八段というのは将棋界で言うとこれが最高のクラスです。
なぜならば、A級の八段のなかからリーグ戦でトップに立った棋士が、時の名人に挑戦することができるんです。私は18歳でA級の八段に昇ったのですが、四段でプロになって、そのままノンストップで八段になった人はほかにいません。これは至難の業で、たぶん普通に言って、今の藤井聡太四段もかなり難しいでしょう。
なんでノンストップでいくのが難しいかと言いますと、これはもちろん、まわりも粒ぞろいの強敵だし、順位戦というものは制度が、10局を戦うんですけれども、例えば藤井聡太さんが、これから先ね、9勝1敗したとしましょう。
ところが、順位戦の制度というものは、聡太さんが9勝1敗だとしても、上位に2人、9勝1敗の人がいると、聡太さんは順位が下だからあがれない。だから、すごい成績をとっても、同じ成績のときは順位によって、上の人があがるという制度ですから、なかなかこれは至難の業と言えるわけです。