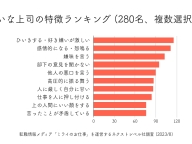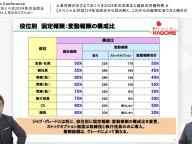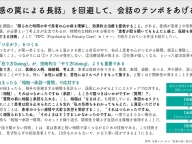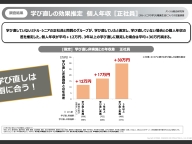アヴィニョンの演劇祭でオープニング公演
森隆一郎氏(以下、森):さて、急に東京の話をしてみたいと思います。そうだ、先ほど宮城さんの話を聞いていて1つ思い出したことがあります。ミュージシャンの大友良英さんが語っていたことで、私たち(アーツカウンシル東京)と一緒に事業をやっているんですけれども。
その絡みで、ハフィントンポストでインタビューをしてもらったんです。そのときに、大友さんが「フェスティバルってなんだ?」という話をされました。そのときに、「フェスティバルはみんなで作るものだったんだけれども、ここ最近はチケットを買ってフェスティバルに行くようになった」「みんなで作るものだったんだけど、それを購入するようになってきた」と。
それで、そのチケットを買って参加するフェスティバルはいいんだけど、楽なんだけど、楽しいんだけど、たぶんその分なにかを引き換えに差し出している。その差し出しているものは、生命力じゃないか、と大友さんはおっしゃっていました。それを急にちょっと今、思い出しました。
さて、そのチケットを買うという行為は消費ですけども、この消費の場所として大都会という東京があって。いろいろな人がいろいろなことを消費しているんですけれども、そうじゃなくて、無料で提供するということが1つのドラスティックな、あるいは単純な方法なのかなと思うんです。
あまり私が話すとあれなんですけれども、アーツカウンシル東京でアンケートをとったんですね。「どういう芸術文化体験をしたいですか?」と聞いたら、「広場などで行われている無料のものを見てみたい」というのが、49パーセントだったかな。そういう方がいらっしゃいました。
そういう質問を書いたからもちろん丸を付けるので、質問を作っている側としては若干そのあたりは恣意的な部分はあるんですけれども。でも、まあそうだよねというのももちろん頷ける。そこに対してネットの反応は、よく見に行ってる方々は「そうなのか、東京という都市ですらそこにお金を払おうという人たちが50パーセントなのか」と。逆にひっくり返してみると、というところで落胆する声はありました。
それは一部の見方なのでなんとも言えないと思うんですが、そんなここ東京で新しい芸術祭をはじめようとする。
というところで、宮城さんは先般、アヴィニョンの演劇祭でオープニング公演を。これはすごいんですけども、なにに例えるといいですかね。野球に例えるとなんでしょうかね、中井さん。
中井美穂氏(以下、中井):(笑)。野球は規模が小さいですよ。
(会場笑)
ごめんなさい。配信されている(笑)。サッカーのワールドカップで日本が優勝するようなものです。
森:すごい。
中井:でも、そのぐらい本当にすごいことだと思います。しかも、おやりになった場所がオープニングの作品で、法王庁中庭。
森:法王庁。
中井:すごい快挙ですよね。
森:アジア人初で、しかもスタンディングオベーションを受けるほど成功されたということで。そのアヴィニョンフェスティバルがどういうものなのかといったことを少しご紹介いただければと思います。
アヴィニョン演劇祭の根底にある思想
宮城聰氏(以下、宮城):アヴィニョン演劇祭って、ちょうどカンヌ映画祭やイギリスのエディンバラ映画祭とほぼ同時期、1947年ぐらいにできています。つまり、第2次世界大戦の反省というかな、それから生まれている。
これは、例えばユネスコなんかもそうだけど、「なぜこんなにひどいことになっちゃったんだ?」と。なぜヨーロッパはこんな焦土と化したのかを考えたときに、結局「相手の文化に対するリスペクトというか、興味がなかったからだ」「相手の文化に興味がなければ、滅ぼそう、ぶち壊しちゃおうと平気で思える」と。
「だけど、もし相手の文化のファンだったら、そう簡単に爆弾は落とせないだろう」と。だからユネスコ憲章にそう書いてありました。「戦争は人の心に起こるものだから、人の心に平和の砦を築かなければいけない」と冒頭に書いてありますよね。
ユネスコ憲章って、何人が起草したのかなって。ユネスコの本部がパリにあるからフランス人が起草したのかと思ったら、起草した人はアメリカ人なんだそうですね。日本国憲法も同じかもしれないけど、1945年の頃の人々の反省というかな。悔恨。どれだけ悔やんでいたかということを、よく表していると思うんですけど。「どうして人間はこんなにひどいことするようになっちゃったんだ?」ということを、けっこう世界中の人が思っていたと思うんです。
そのなかで演劇祭、あるいは映画祭、芸術祭というものが生まれてくる。つまり、自分たちとは異なる文化を持った人たちのことをもっと知りたい、ということだと思うんですね。
それで、47年に(アヴィニョン演劇祭が)できたときには、たぶんそういう自分たちとは違う文化を知ろうと。実は、その2~3年前、1943年ぐらいに、本当の一番最初のアヴィニョンフェスティバルが行われているんですね。アヴィニョン演劇祭と言われているけれど、公式名称は単にアヴィニョンフェスティバルです。
その名前になる前段階では、美術家なども参加しているフェスティバルだったらしいんです。なぜ43年くらいにアヴィニョンでフェスティバルがはじまったかというと、すでにその頃には、パリはナチス・ドイツに占領されていたんですね。いわゆるヴィシー政権という傀儡(かいらい)政権。ドイツの傀儡の政権が、パリを治めている時代です。
ただ、そのヴィシー政権の勢力が、フランスの一番南の端っこのアヴィニョンまでは及んでいなかったんだそうです。そこで、そのあたりのアーティストがフェスティバルのようなことをはじめた。
なんて言うんだろうな、中央という言い方をするのは、現代の言葉としては相応しくないかもしれないけども、辺境だからこそ国という塗り絵に入らないで済んだ。あくまで1つの地域とか、1つの町として生き残れたというか。
そこからスタートしていることが、アヴィニョン演劇祭のポリシーというか思想の根底にあるような気がしていて。つまり、国対抗演劇祭ではないんですね。国旗対国旗が争っているのではなくて、覇を競っているのではなくて。あくまでとても小さな町、小さな地域。そこが固有の輝きを持ってるぞ、というところからスタートしている。
集まってくる作品のパンフレットを見ると、作品のあとに国名は書いていないんですよ。ジャパンとかブラジルとは書いていなくて、その都市名しか書いていないんです。だから、「アンティゴネ(静岡)」と書いているんです。
そういう、とても小さな地域というか人間集団というか。そういうものが固有の輝きというか、文化を持っていて。それが出会っていくのがこの演劇祭、フェスティバルですよという考え方が、おそらく根底にある。それで、例えば冷戦期のようなものを乗り越えて、今日もその意味を保ち続けているんじゃないかな、ということを思いますね。
つまり、かつてのベルリンオリンピックのように、結局のところ国対抗で、ベルリンオリンピックにも芸術競技があって。どの国が優れた芸術を持っているかということを争った。芸術競技でメダルを出していたんです。
そういうものとは、本来的にまったく正反対の発想で作られている。それがアヴィニョン演劇祭のいいところだな、と思ったりします。
寛容は社会の歴史のキーワード
森:はい。先ほど島原さんのレポートの寛容社会のなかで、今で言う国ですよね。国ができたきっかけが、いわゆるウェストファリア条約。
島原:そうですね。
森:ちょっと受験勉強の頃を思い出してくださいね。
島原万丈氏(以下、島原):17世紀に、ヨーロッパで三十年戦争がありましたね。これが、歴史上初の世界大戦と言われています。
ヨーロッパ中を巻き込んで戦争をしていたわけですけど、「いい加減、30年も戦争するのはやめようぜ」となったときの和睦の条約がウェストファリア条約といいます。
このウェストファリア条約を結ぶ前に、真っ先に確認したのが信仰の自由です。30年戦争からさらに90年ぐらい遡って昔に、アウクスブルクの和議というものがあったんです。これは要するに、ルターの宗教改革以来プロテスタントとカトリックが争っていた時期に「互いに異端を認めましょう」という合意でした。
当時は異端裁判や魔女狩りなんか酷いこともやったりして大変なことになっていた。それをもういったんお互い認めよう、お互いに口出しするのやめましょう、という話をしていたのに、なんとなくうやむやになって、神聖ローマ帝国、今のドイツの国の中の領邦同士が「お前のところの宗教は気に入らん」と干渉しあっている間に戦争になっちゃったんですね。だから、「もう1回信仰の自由に戻ろう」という再確認の上にでき上がったのがウェストファリア条約です。
寛容という、英語で言うとtolerance(トレランス)なんですけども、哲学者が哲学で語りだしているのが17世紀ぐらいからなんですね。三十年戦争の悔恨とともに語られてきていているようなんです。
「寛容とは何か」について、もっとも的確に表しているのが、『寛容論』という有名な本を書いているヴォルテールという人です。
ヴォルテールには、「私はあなたの意見には反対だ。だが、あなたがそれを言う権利は命がけで守る」というふうに……本人は言っていないそうなんですけど、本人が言ったことになっているらしい言葉があります。それがどうやら寛容の核心みたいな感じですね。
よその国の宗教には口出ししない、プロテスタントでもいい、と認めるということは、実は当時のヨーロッパではすごいことでした。なにがすごいかって、ローマ教会からの独立ですよ。つまり、国がはじめて自治権を持った。政教分離も個人の基本的人権も全部ここを出発点としている。
それが近代国家のもとになっているというぐらい、寛容が社会の歴史のキーワードというか、重要な技術として共有されてきたということですね。
不寛容は生物学的な恐怖?
森:寛容は技術だったということが、その肝なんですよね。さて、現代。日本なんかとくにみなさん宗教にはだいたい寛容です。自分にも寛容ですよね。ではなにに対して寛容じゃないのか、という問いを投げかけたいんですけれども。これは、どうでしょう。中井さん。
中井:なにに対して寛容じゃないか?
森:旦那さんとかそういうことじゃなくて。
中井:はは(笑)。でもやはり、自分の知らないものですね。得体の知れないもの。あとは違和感を感じるものに、本能的にちょっと力が入るというか、心を開けない。身構えるというか。でもそれがなにか、見たことのないものや嗅いだことのないにおいといった生理的現象からもきているとは思うんです。
森:においはそうですね。
中井:なにか、生物学的に注意喚起を促されるというところはあるかもしれないですね。知らないもの、じゃないですかね?
島原:僕も、知らないものや異質なものに対して、ちょっと恐怖みたいな警戒感があるんだと思いますが、最初に宮城さんがお話しした「あいつらこっそり得してる」みたいな。そういうものに対しての攻撃が激しいような気がしていて。
例えば、最近お母さんが働くことは当たり前になってきたんだけども、ベビーシッターを雇って旦那さんとデートに行っている、ということをTwitterに書いたら「母親失格だ!」というバッシングを受けた女性タレントがいましたよね。
森:ありましたね。
島原:不倫に対してはどうコメントしていいかわかりませんけども(笑)。それも考えてみれば、「毎日、テレビが騒ぐほどのことか?」ということを散々やっていますよね。ちょっとした逸脱に対して、それも単純にルール違反だからまずいというよりは、やっかみ半分で叩いているのが、今の社会風潮なんじゃないかなと思っています。
森:そういう意味では生きづらいですよね。
島原:息苦しいですよね。
森:息苦しいですね。ちょっと会場にアンケートをとってみます。SNSをやっている方、どれくらいいらっしゃいますか?
(会場挙手)
けっこういますね。では、SNSは息苦しいと思ったことがあるという方、どうでしょう?
……あれ? いない。あ、小さく手が挙がりましたね。そんなに大手を振って言うことじゃないので。
あと、リア充という言葉も、ひっくり返せばやっかみでしょうね。そういう分断や不寛容もまだまだ払拭されたわけではない。たぶん、宇宙人が攻めてくると、みんな団結する。そんなSFみたいなことを言ってもしょうがないですが。
自分たちが持ってない“美”というものに興味を持つから人間は生き延びた
森:では、宮城さん。「わからないことに対して人は不寛容になる」「より過剰になっている」ということですが。
宮城:たぶん、人間の種の保存や自分自身の生命の維持に対する脅威を感じれば、それは身構える。そういう生き物でしょう。だから例えば、単純な言い方をすれば「これ腐ってるね」と「これ発酵してるね」の違いは、化学上はないけれども、人間にとって食べて当たりそうなものは「腐っている」、あまりいいにおいじゃないと感じるようにできている。
食べても大丈夫なものは、発酵しているにおいだと感じるようにできていますよね。これはもう、蓄積としてそうなっている。そうすると、「この手の感じは、自分にとって脅威だ」、あるいは「自分の種の保存にとってなんらかの脅威になりかねない」というものに対して身構えるのは、生物としては当然あるわけです。
しかし同時に、人間がほかの動物と違うのは、異なるカルチャーや感覚、美意識を持っている人と向き合ったときに、それをおもしろいと思う。これも本能に近いものを持っているんですよね。これは、本能と言っても過言ではない。
なぜならば、おもしろいことに、世界の歴史を見ると彫刻や絵、音楽など、自分たちの文化になかった美が入ってきたときに、興味を持たない国はないんですよね。
例えば日本で見ても、安土桃山時代に音楽学校を作った大名がいます。これはつまり、当時の宣教師が持って来た音楽って、日本になかったわけです。その和声が日本にはなかった。これを「綺麗じゃん」と思う。そして、「子どもたちにも教えよう」と思っちゃう。これは別に、その大名だけが特別だったわけではなくて、多くの人が、はじめてヨーロッパの讃美歌を聞いたら綺麗だと思ったということですよね。
こういうことは世界中で起こっています。例えばそれこそ、先ほどの2,500年前のギリシャも、歴史の授業では例えばギリシャの美は8頭身とか習いますけど。別にギリシャ人が突然あれを思いついたわけではない。ギリシャの美術館に行くとわかりますけど、先住民やそういう人たちの美意識のなかから、いいとこ取りみたいにして残っていくわけですよね。「自分たちが持っていないものだけど、これおもしろいじゃん」って。
食べ物でも、最初は「これは変なにおい」と思ってもドリアンとか、だんだん広がっていくし。
中井:いったん受け入れたら、くせになりますよね。
宮城:そうそう(笑)。そうなるじゃないですか。だから文化でもまったく同じで。「え?」と最初に思っても、「でもこれ綺麗かも」「ちょっと自分でもやってみようかしら」と思う。そういう本能もあり、そのおかげで文化というものは混じるんですよね。
そうじゃなかったら、文化が混じるわけがないんですよ。文化って必ず混じるじゃないですか。100パーセント混じるんです。異なるものが出会うと100パーセント混じる。混じって、洗練というか進歩をしていくんですね。
これを考えると、「自分たちが持ってない文化に興味を持つから人間は生き延びたんだ」と言えると思いますね。もしそれが人間になければ、とうに人間は滅んでたんじゃないかと。
それはそれで人間の本能と言ってもいい。そうすると、種の保存を脅かされるような危険に身構えてしまうと同時に、異なるものに対して興味を持つこと、両方とも、我々人間は持っている。それがずっと続いてきた人間を成り立たせていたのに、最近なぜ不寛容のほうが浮上してしまうのか。例えば、1930年代のドイツでなぜ不寛容のほうが浮上してしまったのか。
僕が思うに、やはり不遇感というものが広がったからじゃないか。つまり、「自分は何か損して割を食っている」というバイアスというか前提があると、急に異なるものに対して受け入れる気持ちがなくなって、「出ていってくれよ」という気持ちが強くなるんじゃないだろうか、と思います。
不遇感があるからこそ、先ほどのやっかみのようなことが起こる。嫉妬は別に、昨日、今日はじめてあれするわけじゃなくて、神様でもみんな嫉妬してましたよね。それぐらいだから人間は逃れようがないじゃないですか(笑)。
しかし、なぜそれが不寛容というところにまできてしまったのか。不遇感が広がると、やっかみやバッシングが起こるんじゃないかな。「なんであいつらだけ遊んでるんだよ」「あいつらだけ得してるんだよ」「あいつらだけ美味しい目にあってるんだよ」ということになる。
だから不遇感の拡張に対してなにかしら手を打てないと、この不寛容はいい方向に向かわないんじゃないかなと思います。だからもし我々のフェスティバルなるものが不遇感ということに触(さわ)れるならば、それはとても意味があると思うんですけどね。