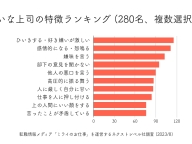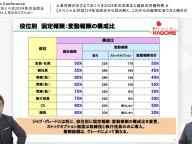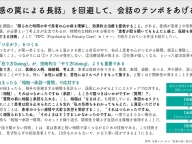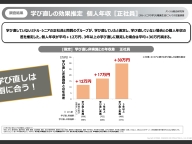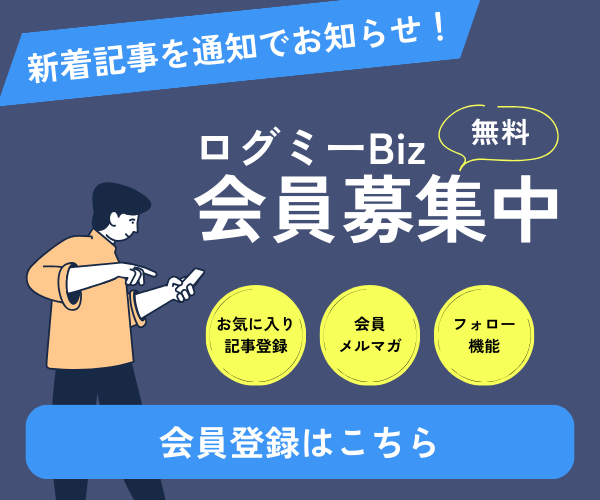フランス映画の現在の傾向
中井圭氏(以下、中井):はい。ということでございまして。我々から、今回フランス映画祭のなかでピックアップしておすすめしていったということなんですけど、いかがですかね?
今回、フランス映画祭もそうですけど、フランス映画の現在の傾向というか、フランス映画祭のラインナップからもなにかしら見てとれるものがあるんでしょうかね?
矢田部吉彦氏(以下、矢田部):1つ、ちょっと単純な点ですけど。女性監督が増えているというのは去年からも言えることで。今回も、4人、5人の女性監督がいらっしゃいますよね。それは1つの大きなうねりみたいなものが、去年ぐらいからフランスで顕著になってきたような気がします。
中井:女性監督ですか。これ、世界的な流れとしてはどうなんですかね?
矢田部:えー。増えていると思いたい。
中井:思いたい。
矢田部:日本でもとても強力な監督を挙げていくと、必ず女性監督がいますし。
中井:そうですね。
矢田部:エマニュエル・ベルコさん、『太陽のめざめ』の監督ですけど、彼女も去年からフランスですごく勢いのある人になっていますし。わりと世界的な傾向としてあります。ただ、まだまだね、少なすぎるというようなことで、声を上げている国、人たちも多いですけれども。僕は増えてきているんじゃないかなという気はしています。
スタッフ:圭ちゃんね、これは、毎年のフランス映画祭のラインナップよりも実話物がちょっと多いんじゃないかなという印象を受けたのよ。
中井:確かに。
スタッフ:フランス映画と言ったら、小説原作であったり、もう少し、そういう物語中心のイメージがあったんだけど、今回は実話物がすごい多いのかなと。どうなんですか? 矢田部さん。
矢田部:僕ね、これこそ世界的傾向かなという気がちょっとしますね。フランス映画も多いですけども、カンヌとか行っても、これも実話。Based on true storyで始まる作品がけっこう多いなという。やっぱり実話って言われると、感動がちょっと2割増しくらいになるのかなっていうのがありますかね。
中井:要は、無視できないものが世界に増えているってことも1つあるんですかね? フィクションではなくノンフィクションであるというか、世界で起きていること自体、「目を背けちゃいけないんじゃないですか?」と提示しなればいけないものが、ものすごく増えているってことがあるのかもしれないですけどもね。
矢田部:そうですね。さっき中井さんがおっしゃっていた社会性のようなところを追及していくと、実話から着想を得たものっていうのが必然的に増えていくっていうのはあるのかもしれませんね。
『パレス・ダウン』はものすごい映画
スタッフ:ただね、圭ちゃんね。例えばハリウッドで実話ものってなるとさ、実際の話を積み上げていくっていうさ、リアリティだったりするじゃない。でも、フランス映画って実際にあった話に人々がどう感じたかっていうのを描いてるような気がすごくしてて。
松崎健夫氏(以下、松崎):今回(のフランス映画祭で上映された)、『パレス・ダウン』ってテロの話なんですけど。
中井:インドのね。
松崎:これ、ハリウッドで撮ったら、テロのあったホテルから脱出するって話になると思うんだけど、この映画がすごいのは、テロにたまたま遭遇した女の子がもしその建物にいたとしたらどういうふうに感じるかってことしか描かない。ハリウッドだったら大アクション映画になっていて。
中井:まったく派手さがないですもんね。
松崎:たぶんブルース・ウィリスが出るんですよ(笑)。
中井:壁をよじ登って(笑)。
松崎:よじ登って。「娘、助けに行くんじゃ!」と言って。でも、そういうことじゃなくて、実際その建物にいて、事態を目の当たりにしていなくても、そこにいるとどういう音が聞こえて、自分はどういう経路で助けられるのかっていうのを客観的に描いている。
でも最後に見せるカットを見ると、それによってなにを感じるかということによって社会性も描いているので。これ、ものすごい映画だなと思って。
福永マリカ氏(以下、福永):しかも、なにかが起こる前から不穏な空気っていうのがちゃんと漂っていて。起こることが問題じゃなくて、なにを感じているのかがその序盤ですごく感じて。私、前情報を知らないで観てたんで「なんかすっごい不穏だな」ってずっと思ってたら、起こるべくして起こって、そこがすごくいいなと思ったんですけど。繊細だなって。
中井:僕、あのステイシー・マーティンがかわいすぎて(笑)。「めっちゃ見たことあるけど、めっちゃ綺麗やな」と思ったら『ニンフォマニアック』の人だったというね。まったく違うタイプの作品に出てきたっていうのがありますけども。
フランス映画には多様な愛のあり方がある
松崎:僕が今回見て思ったのは、家族のあり方みたいなものが多様性を引っ張ってくるんですけど、今回のなかでも、テーマが夫婦だったり親子だったりっていう映画がほとんどかなって気がすごくしてるんですよね。
そのことと、さっき僕が挙げた『奇跡の教室』みたいに教育が絡んでくることで、子供を育てることもそうだし、教育ってどういうことなんだって、ちょっと広がりを持った話になっていったりとか。
あと、夫婦に関しても、もう1本のイザベル・ユペールが出てる『愛と死の谷』とか『モン・ロワ』とか、『アンナとアントワーヌ』とか、夫婦が別れる時にどういう選択をするかって時にそれをプラスに考えるのかマイナスに考えるのか綺麗ごとにするのかってのか、それぞれ監督の色がすごく出てるんですけども。
例えば、『アンナとアントワーヌ』。この映画。
クロード・ルルーシュ、『男と女』の監督の久々の作品。
中井:ジャン・ルイが出ている(笑)。
松崎:そう、そのジャン・ルイの『男と女』の監督が久々に撮った作品ですけども。
『男と女』の場合は、夫婦の片方がいなくなった者同士が恋愛に落ちるっていう話だったのが、今回はよくよく考えたら不倫の話なんですけど、綺麗に描いている。一方で泥沼的な、『モン・ロワ』とか『愛と死の谷』みたいなものもある。
そのあたりの幅の広さからもフランス映画って愛を描くってよく言われるけども、そのあり方も世の中多様性だと言っているのと同じように、この12本のなかでもいろんな描き方があるなっていうのは見たらおもしろいと思います。
中井:なるほど。フランス映画祭、これから始まりますからね。ぜひ、行っていただきたいと。本当に早めに観れますし、さっき健夫さん言ってたように傾向も見れますし、見ていただきたいなと思います(注:すでに終了)。
みんなの好きなフランス映画
せっかくなんでね、みなさん今お話ししてるんで、フランス映画、お好きだと。
スタッフ:いいね。「シンクル」(注:コミュニティアプリ)でも、フランス映画好きすぎるっていうタイトルでトピックスが立ってるんで。みなさんのやつも見て、後に今日登壇のゲストのみなさんの声を聞いていただける。
(シンクルの画面が表示される)
福永:なにが好きなんでしょうね?
中井:なるほど。クロード・ルルーシュね。
矢田部:『男と女』、やりますからね。
中井:今回、フランス映画祭でリヴェットの作品やってましたよね?
福永:『冒険者たち』。
矢田部:『軽蔑』大好きですね。
矢田部:『カミーユ・クローデル』、おお。
中井:『まぼろしの市街戦』いいですね! なんとなくあれなんですかね、ヌーヴェルヴァーグ界隈の作品が。
松崎:『キス・オブ・ザ・ドラゴン』!
中井:『汚れた血』!
いろいろとみなさんおすすめがありますけれども、これ難しいですね。これは悩ましいですね。
名作、レオス・カラックスの『汚れた血』
福永:(「シンクル」のコメントを見終わって)みんな体勢が変わりましたね。あー(だらん)って(笑)。
矢田部:1本?
中井:1本ですね。僕からさらっと言っておくと、もう出ちゃったんですけど『汚れた血』すごい好きなんですよね。
松崎:ラストカット、なんべんも見た。
中井:たぶん最近の、『フランシス・ハ』とか観た人だと、女の子が走り出すシーンあったと思うんですよね。デビィット・ボウイの『モダン・ラブ』かかって走り出すシーンとか。あれってもともとは『汚れた血』からきてるわけで。
ドニ・ラヴァンが飛び出してって、ラジオで『モダン・ラブ』が流れて来て、うわーって走っていく情動のあるシーンなんですけど。本当に僕観た時に久々に「かっ飛んだ人出てきたな」って印象だったんです。レオス・カラックスに関してはその感覚があって。そのなかでも『汚れた血』がすごい好きですけども。みなさん、いかがですか?
矢田部:(シンクルのコメントを見て)『ポン・ヌフの恋人』のほうがいいって人もいますけど、僕も『汚れた血』派ですね、やっぱりね。
あの頃の一連のカラックスは、『ボーイ・ミーツ・ガール』も含めて衝撃的でしたね。これはすごい人出てきたなと。ちょうどただあの頃、ヌーヴェル・ヌーヴェルヴァーグって言われてた3人が出てきて。あ、でもここでタイトル言っちゃうと僕の1本になっちゃうんですかね?
中井:あ、いいですよ。大丈夫ですよ。
矢田部:あの頃は本当に『汚れた血』と、前衛と興奮を兼ね備えた映画と平行して、僕は『ディーバ』って大好きですね。
松崎:べネックス?
矢田部:べネックス。それはやっぱり賛否あったんですけど、僕はやっぱりやられたクチで。パリをモペットバイクで走りたいとすごく思いましたけど。ただ、これは僕の1本ではないです。
中井:1本じゃないぞと、はい。
ジュリエット・ビノシュ派orジュリー・デルピー派?
矢田部:健ちゃん、『汚れた血』は?
松崎:ヌーヴェル・ヌーヴェルヴァーグって呼ばれた当時の若手監督のなかに、リュック・ベッソンが入っていたんですよ。奇しくもリュック・ベッソンも『最後の戦い』をモノクロで撮ってから『サブウェイ』ではカラーで撮りましたよね。
カラックスも最初は『ボーイ・ミーツ・ガール』をモノクロで撮り、この『汚れた血』をカラーで撮りましたよね。そういうような段階を踏んで撮っていたと考えると、リュック・ベッソンって本当はそういう監督なんですよって言いたいんですけど(笑)、『汚れた血』は当時まだ僕が中学生になった頃で、こういう画撮りたいって思いました。
中井:単純に、かっこいいって思いましたよね。
松崎:映画についてあんまり深く考えてない頃に、「なんかすごいもん観た」って感じしましたね。当時。ジュリー・デルピーが好きだった。
中井:あ、出ましたね、ジュリー・デルピー派。ジュリエット・ビノシュではなく、ジュリー・デルピー派。フランスのなかでも、ドニ・ラヴァンをあれで観てて、「あ、これでもいけるんやな」って、そのルック的にこの癖があってもいけるんやなってすごく思いましたけどね。
松崎:ジュリー・デルピーがこの後『天使の接吻』って映画に出演しているんですけど、これが日本で観れないんですよ。いや、日本どころか世界中でソフトになってなくて、レーザーディスクくらいで止まってるんですけど。どっかソフトにしてくれないかな。
中井:WOWOWに頼むしかないですね、これは(笑)。では、マリカちゃん。いく?
フランソワ・オゾンの登場はインパクトがあった
福永:じゃあ、ちょっと女代表ということで『8人の女たち』。
中井:(フランソワ・)オゾン。
福永:どうですか?
中井:いい映画ですよ。
福永:キュートですよね? とても。お洋服がすごく好きで。「着たい、それ」とか「この髪型で着たらむっちゃかわいいのに」とかいう純粋なね、そういうのもありますし。あと、女の子もかわいいですね。妹。
矢田部:妹? リュディヴィーヌ・サニエですね。
福永:最高にかわいい。憧れますね。
矢田部:新旧大スター競演で、とっても華やかでしたね。
中井:フランソワ・オゾンの登場ってけっこう僕のなかではインパクトあったんですけど。
矢田部:ありましたね。けっこう短編時代から観てて、すっごい短編映画もおもしろかったんですよね。長編をけっこう心待ちにしたのが、90年代なかばから後半くらいか。で、それから一気に天下取るまであっという間でしたからね。
中井:あっという間でしたよね。日本でも立て続けに公開になってた印象がすごくあるんですけど。
矢田部:そうですね。
松崎:監督がカッコいいっていうのもよかったのかも。作品のイメージと監督にルックスが一致してたっていうのがすごくよかったのかもしれないですね。
矢田部:すごくセクシャリティっていうのをちょっとブレイクスルーしたような1人ですね。
松崎:そういうのをちゃんと早めにカミングアウトしたから、作品もそういう視点で観れたっていうのもあると思いますけれども。
初めてカラーで観た『太陽がいっぱい』の思い出
中井:確かに。じゃあ、健夫さん。
松崎:僕は、生まれて初めて観たフランス映画。これはもう忘れないですけど。3歳から2歳になるくらいの時に観た作品です。
中井:なにをしとったんですか!? 普通、3歳から2歳ってしゃべりだすか否かぐらいの時じゃないんすか(笑)。
松崎:(笑)。いや、2歳の時から「東映まんがまつり」とか映画館に連れてってもらってたんですよ。映画館に連れてくと、子供たちがギャーギャー騒いでいるのに僕はおとなしく観てたらしいんですよ。
うちは最初、モノクロテレビだったんですが、カラーテレビ来た時に最初に画面に映ったのが、『太陽がいっぱい』だったんです。だから、忘れない。
中井:なるほど!
松崎:後になってそれが『太陽がいっぱい』だったってわかるんだけれども、最初にテレビで観たカラーの画が『太陽がいっぱい』だった。で、それを小学校の2、3年生の頃に観た時に、「ああ、この映画だ!」と思った。
そういのたまにあるじゃない? ワンシーンしか覚えてないけど、後になったらこの映画だったってわかるっていうの。
中井:ありますね。
松崎:そのなかの1本で、とくに僕のなかでは初めてテレビの画面でカラーで観たものが『太陽がいっぱい』だったっていうのがあって。2、3年生の頃にはもうすでにいろんな映画を観ていたけれど、フランス映画みたいなものは観たことがなくて。
『太陽がいっぱい』の終わり方って、たぶんアラン・ドロンが最後捕まるんだろうけども、そこを映さない。警察が「あの人を呼んでくれ」って店員に言った時に、アラン・ドロンは全部うまくいったと思って「最高だ!」って言ってるんです。
ところが、観客は最高じゃないことを知ってるんですよ。アラン・ドロンは最高だと思ったまま、画面からフレームアウトして映画が終わるんですよ。「こんな終わり方、あんのか!」って思って。
中井:小学校2年生健夫少年が(笑)。
松崎:ほんと、しびれて。だから、すべてを描かなくても観客に想像を委ねることができるし、すべてを知ってるのが観客だってことがあるんだと思って。ものすごいインパクトを持ったんですよ。
中井:むしろ、アラン・ドロンは(幼少期の健夫さんに)「なんや、この観客は?」って思ったと思いますけどね(笑)。
松崎:自分が他人になっていくための方法とかを、まったくセリフを介さずに行動だけでみせていくんですよ。サインを真似ていくとか。
そういうのも後になって気付くんですけど、「あ、セリフないや」とかっていうこととかの原体験としてラストシーンもものすごく鮮やかに覚えています。『太陽がいっぱい』って今でも大好きです。やはりフランス映画ですね。