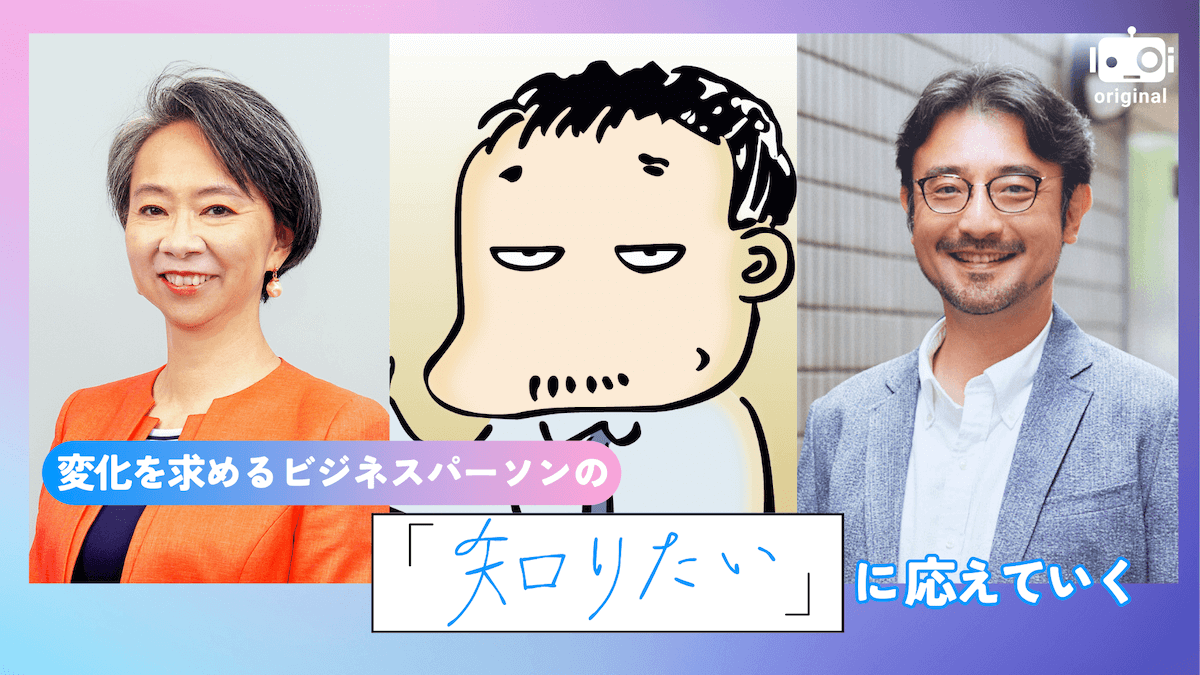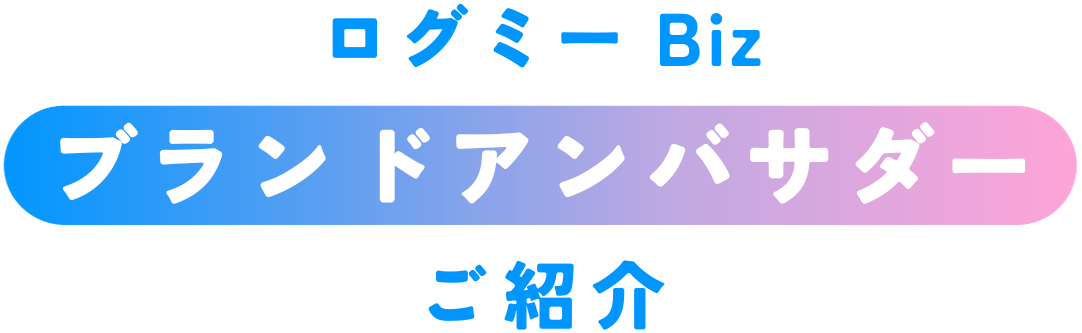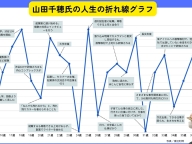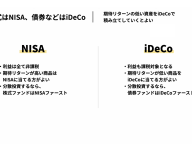マッキンゼーは「仕組み」がすごい?
瀧本哲史氏(以下、瀧本):他のコンサルティングファームの人たちに話を聞くと、みんな口を揃えて言うのが、「とにかくマッキンゼーは仕組みがすごい」ということです。人材育成から評価システム、クライアントへのフォローまで。そのあたり、山梨さんはどう思われますか?
山梨広一氏(以下、山梨):人材育成の話で言うなら、もちろんマッキンゼーにはグローバル単位、リージョナル(地域)単位、そしてそれぞれの国単位で、トレーニングのプログラムが整備されています。ここはかなりシステマティックです。
でも、いちばんの学びは、本人たちの「観察」にあると思います。たとえば何人かで集まって世間話をしていても、そのうち誰かが立ち上がって、ホワイトボードにあれこれ書き込みながらカンカンガクガクの議論がはじまりますよね?
瀧本:はじまります(笑)。
山梨:そこでリーダー的な立場にある人間が、どうやって議論を引っぱっていくのか、どこに課題を見つけ、どう解決していくのか。雑談の中からもそういうエッセンスを学ぼうとする、本人の意欲が問われる職場ですね。あとは、よく言われる「so what?」。
瀧本:はい。ちょっと語られすぎて誤解も多い言葉ですが。
山梨:つまり「それで結局、どうするんだ?」「それで結局、お前はどう考えているんだ?」を突きつけられる文化が根づいている。
瀧本:なにかのデータを持ってきて、「こういう情報があります」と報告するだけでは意味がないんですよね。
山梨:たとえそれが希少性の高い情報であっても、「それできみはどう思ってるの?」「きみはどうしたいの?」までが問われる。マッキンゼー出身の安宅和人さんが書かれた『イシューからはじめよ』という本がありましたよね。
瀧本:あれはいい本です。
山梨:まさに彼が書いていたとおりで、最初に考えることは「イシュー」の発見であると。「なにが課題なのか?」を探すことであると。そして課題がえらく大変だったり、難関だとしても、絶対にへこたれない。というのは、「お前たちの仕事は、課題を解決することなんだ」と刷り込まれているわけです。
瀧本:いわゆる「so what?」的な問いによって。
山梨:そうです。逆にいうとコンサルタントの仕事というのは、課題があってはじめて生まれるものなので。課題がどんなに大きなものであっても、「それをどうやって解くか?」を考える。この2つ、課題の「発見」と「解決」を意識する訓練は、日常的に続けていますよね。
マッキンゼーがマッキンゼーである理由とは?
瀧本:だからこそ「まあ、このへんでいいんじゃない?」というブレーキがいっさい働かない。とことんまで問い詰めるし、考え尽くす。正直な話、クライアントの顧客満足度を高めることって、そんなにむずかしくないんですよ。
山梨:どういうことですか?
瀧本:つまり、顧客の期待値を下げておけば「ほどほどの成果」でも満足してもらえるんですから。
山梨:ははははは。まあ、そういうコンサルタントもいるでしょうね。
瀧本:でも、マッキンゼーで一線級とみなされる人たちは、絶対にそれをしない。クライアントと向き合いながら、同時に自分自身のバリューを高めようと考えているから。「ほどほどの成果」でクライアントが満足しても、自分が満足できないんです。その意味では、ビジネスエリートというよりも、研究者や職人のアプローチに近い。
山梨:おかげで自己満足に見えてしまったり、オーバースペックな提案があったりという負の側面は否定しませんが、そこを無くすと強みもなくなってしまう。マッキンゼー時代の瀧本さんなんかは、とくにそうだったように思います。
瀧本:本づくりをしていると、いつも編集者さんから驚かれます。「ここまでやるんですか」「そこまで厳密に、細部までこだわるんですか」って。それはある意味、マッキンゼーでは常識的なアプローチなんです。
山梨:しかも瀧本さんのこだわりは図抜けていますから。
瀧本:もし、僕が他のコンサルティングファームに入っていたら、こういう研究者的な資質も矯正されていたかもしれません。「そこまでやらなくていい」「仕事には妥協も必要なんだ」と。
ところがマッキンゼーには、つまらないブレーキをかける人がいないし、みんなが「もっとよくできるんじゃないか」「まだまだやれることがあるんじゃないか」と粘り続ける。
山梨:だから昔は、とんでもない長時間労働になっていた(笑)。
瀧本:まさに研究室ですよ。マッキンゼーで学んだものの大きさと異質さは、会社を離れたあとになって、より強く実感しますね。こんなアプローチで仕事に取り組んでいる人たちは、良くも悪くも圧倒的少数ですから。
山梨:そのあたりの「マッキンゼーがマッキンゼーである理由」について語るのは、なかなかむずかしいですね。ロジックツリーとかマトリクスとかってツールも、コモディティ化してるし、決して本質じゃない。ポイントは「人」ですよ。
理想の学校づくりは、「尖った人材」を集めるところから
瀧本:それでいうと今回、僕は『ミライの授業』という本をつくっていく中で、理想の学校づくりについていろいろと考えてみたのですが、結論は「リクルーティングに力を入れる」だったんです。
山梨:へええ。
瀧本:たとえばマッキンゼーでも、社内の「人」から学ぶことって多いじゃないですか。たぶん山梨さんの世代だと、国内の大企業でポテンシャルを発揮しきれなかった「尖った人たち」が、マッキンゼーに流れていた。
だから正直、同じマッキンゼーでも山梨さん世代のほうが、尖った人は多いです。若い世代になっていくと、「優秀なんだけど、優等生どまり」という人の割合が増えていきます。
山梨:うーん、僕らもそんなにほめられたものじゃないですけどね(笑)。
瀧本:でも、そういう尖った人たちを採れなくなっている現実はある。いまではマッキンゼーが「MBAに行って、マッキンゼーに行って、数年後には起業して」といったキャリアステップの一部になってきているので。
これって、進学校が抱えるジレンマとまったく同じ構造なんです。だから、もしも僕が校長になったら、「尖った生徒たち」のリクルーティングに全力を尽くすと思います。どんなにすばらしい教育システムがあったとしても、最終的に組織の強さを担保するのは「人」なので。
山梨:カリキュラムを変更するとかじゃないんですね。僕は『ミライの授業』を読んで、こんな授業があったら本当におもしろいと思ったし、学校や教育、授業という言葉を見事に再定義した、画期的な一冊だと思いましたが。
瀧本:もちろん授業の中身にも手をつけていきますが、生徒にとっていちばん刺激になるのは「いい先生」や「いい授業」よりも、「いい仲間」の存在ですから。
企業は「ほしい人材がわかっていない」から伸び悩む
山梨:それは企業もまったく同じですよね。いかにして「いい人材」を確保するか。しかも、「いい人材」を採るとなれば、自分たちにとっての「いい」とはなんなのかを定義して、発信していかなければならない。
瀧本:そのとおりです。
山梨:企業が伸び悩むときの大きな要因は、どういう人を求めていて、どんな働きをしてほしいのか、自分たち自身がわかっていないことですよ。それで結局、学歴や学外活動の実績、あるいは面接の印象だけで採用してしまう。
でもね、たとえばマッキンゼーと大銀行だったら、やっているビジネスも違うし、社風も違うし、求められるスキルもまったく違う。そのへんを「優秀な学生」というひと括りで採用してしまうのは、とても危険なことだと思います。
瀧本:致命的ですね。
山梨:これはコンサルタント時代に、たくさんの経営者や人事担当者とさんざん議論していた話なんですけど、まあ噛み合わないですね。
やっぱり、「うちはこういう会社だから、こういう特長を持った人材を求めています」と表明して、実際にその基準に見合う人だけを採用するのって、かなりリスクが高いことなんですよ。それよりは漠然と「優秀な学生」を採ったほうがいい。そのロジックはよくわかる。でもね、もうその時代も終わったと思うんですよ。
瀧本:大学レベルでいうと、多様性のある人材確保という名目ではじまったAO入試が、うまく機能していない現実があります。
それに対して、もっと大学を透明化して、オープンにして、「うちの大学にはこんな教授がいて、こんな講義をやって、こんな研究に取り組んでいます」という情報を発信していく動きがはじまっているんです。
山梨:僕らがクライアントに提案し続けてきたことですね。
瀧本:だからこそ『いい努力』に書かれていたように、常に自分の仕事、自分の会社(組織)を定義づけしておかないといけないんですよ。
マッキンゼー的アプローチの弱点
山梨:だけどね、瀧本さん。僕らには1つだけ大きな弱点がある。
瀧本:なんでしょう?
山梨:プライベート、特に家族に対してマッキンゼー的なコミュニケーションをとっていると、ものすごく嫌われるんですよ(笑)。
瀧本:(笑)。
山梨:瀧本さんもよくご存じのある同僚がね、家に帰って奥さんの愚痴や相談を聞いているとき、急に話をさえぎって「わかった。結局きみが言いたいことはなんなんだ?」と、思わず「so what?」を出して怒られたんだって。「わたしはあなたのクライアントじゃない!」って(笑)。
瀧本:ああ、目に浮かぶようです。
山梨:僕もそうですよ。奥さんの話を聞きながら、つい「わかった。結局きみが言いたいことは、この3点だろ?」とやって怒られてしまう。もう、職業病ですね(笑)。
瀧本:わかりました。以後、気をつけます。今回はどうもありがとうございました。
山梨:こちらこそ、どうもありがとうございました。