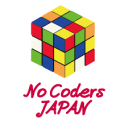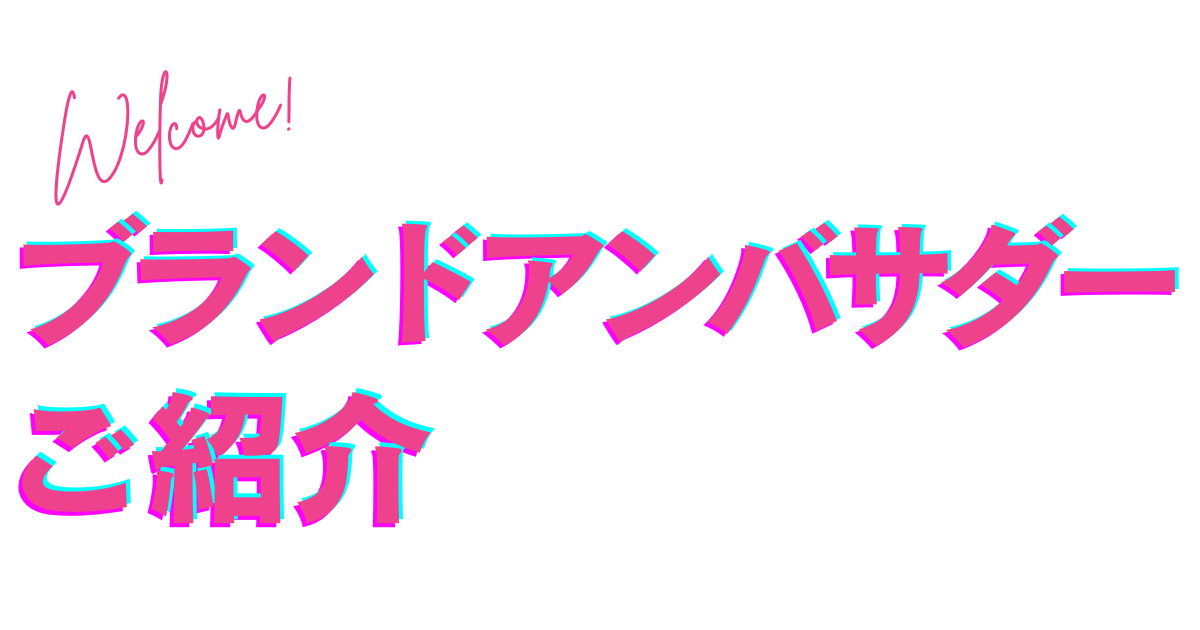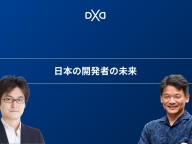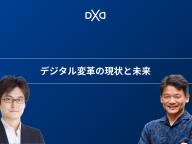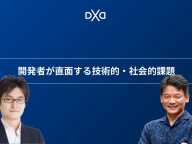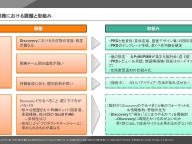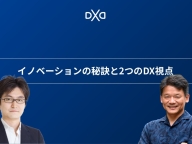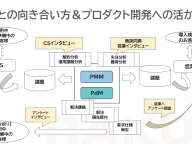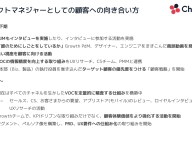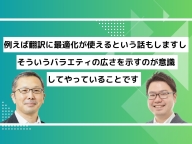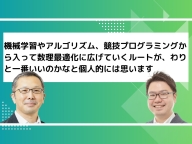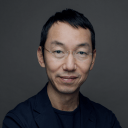手段がNoCodeによって民主化された話
高木俊輔(たかーぎ)氏:今回の私の登壇としては、NoCodeというツールを使って、一度諦めてしまった事業をNoCodeの力で復活させたという話です。これのサブタイトルとしては「手段がNoCodeによって民主化されたよね」みたいな話をしていきます。お願いします。
今回のこの登壇、セッションの結論から言うと、NoCodeの力でみんなが今まで手に入れられなかった手段、要はエンジニアリングというものをNoCodeは民主化させてくれるすばらしいツールだなというのが、今回のこの登壇のテーマになります。
去年の夏頃にプロダクトを作っていたんだけど、それはそれこそ机上の空論のまんまで全然リリースまでいけなかったよと。あえなくクローズしてしまったんだけど、あるときにNoCodeに出会って、NoCodeのツールを勉強しました。その期間も2ヶ月ほどしかなかったんですけど、全然2ヶ月程度でサービスをリリースすることができて、「これがNoCodeの使いやすさなのか」みたいなことを思ったりもしました。
このセッションを通して伝えたいことが最後にあって、「NoCodeでプロダクトを作るというのはどういうことなのか?」「手段の民主化がどんどん進んでいった先にどのような未来があって、私たちはどのように先回りすることが……なんだろう、最も市場価値の高いじゃないですけど、どうしたらもっと戦いやすくなるのか?」みたいなことを紹介していきます。
次に自己紹介です。髪型は全然違います。今伸ばしてます。今17歳で、N高等学校という通信制の高校に在籍しています。通信制なので、学校へ行かずにパソコンで授業を受けることができるんですよ。高校卒業単位も全部これで取れます。
一応会社で働いていて、ハッシャダイという会社で、今回作った進路サポートのプロダクトや、まだ出していないですけど、事前登録を開始している睡眠学習のアプリを作っていたりします。ヒューマン・コンピューター・インタラクションという、UIとかUXとか、デザインみたいなことをちょっとやっていたりとか興味があったりしますが、まだまだがんばります。
このスライドは後ほどSpeaker Deckに公開したりとか、あとはスライドとか全然スクショしてもらってもかまわないので、拡散してくださいという感じです。では、いきましょう。
コードが書けず、サービスリリースに至らなかった経験
今日の結論を申しますと、NoCodeによって、エンジニアリングがものすごく大変だったものが、みんな使えるようになりました、民主化しましたよという話です。
テクノロジーだったり、NoCodeとかはどこまでいっても手段なんですね。ただ、唯一無二のものとして目的というものがあって、要は「NoCodeを使ってどのような未来を手に入れたいのか?」とか「どうなっていきたい?」みたいなところは全然民主化されないです。持ってる人のほうが少ないので。
じゃあNoCodeによってエンジニアリングだったりとかテクノロジーだったりとか「『これができたらいいよね』みたいなものが民主化されたあとに、どんな人たちがこの世界を作っていくのか?」みたいな話をちょっとしたりとかもします。
もともと僕は学生で、ものすごいいろんな進路に興味があって、「どういう進路がいいんだろうな?」ってめちゃめちゃ悩んでたんですよ。「そういえば進路選択をサポートとするのってあんまりないよな。塾とか学校とかいってもみんな進学率とか就職率とか気にしてて、それって全然自分のためにならんやん?」みたいな、「学校の測り方がそれっておかしくない?」みたいなことはものすごく思ってて、それらの進路選択のツールは全然使いものにならなかったんですね。
私は「そういや、ちゃんと自分が選びたい進路をエンパワーメントしてくれるサービスってないのかな?」みたいのを思ってメチャクチャ調べてたんですけど、まぁ、ないと。ということで、上京して、中卒・高卒を対象にインターンをしているハッシャダイという会社に今いるので、これを事業として作れないかなと思ってサービスを作り始めました。
要件定義したりとかプロトタイプ作ったりとか、学生さん向けに「進路選択、こういうふうがいいよね」とか「自己分析こういうふうにやっていこうよ」みたいなワークショップを主催させてもらったりとか、Googleフォームでどんな悩みをもっているのかをいろんな高校生、それこそ同年代とかに聞いて、いろんな……検索とかをしてたんですけれども、結局サービスリリースまでは全然ありつけないと。
根本的な原因として、僕コード書けないんですよ。コード書けなかったら結局プロダクトをデプロイ、世界に配列すること、並べること、世界に実装することができなくて、なんか「やっぱコードを書けなきゃいけないのかな……」みたいのを思ってて、半分もう泣いてました。
ある日突然NoCode に出会う
いつもどおりTwitterをしていたところ、ある日突然NoCodeというツールに出会いました。「なんだなんだ、この人は?」と。これ左側の画像、しんじさんなんですけど、「NoCode School」というYouTubeを運営されている。
この方のツイートを見て、「あれ、なんかコードを書かずにプロダクトを作れるらしいぞ。しかもけっこう簡単らしいぞ」「なんかこの人Uberのモックアップみたいのを作っててすごいね」みたいなのを思ってたんですよ。そう、今コメントをしんじさんがされてますけど、「しんじです。ありがとうございます」って。
この方のYouTubeを僕はひたすら見てたんですよね。「こんなプロダクト作れるんだ?」みたいな。「コードって絶対いると思ってたのに、こんなサクサクマウスだけでプロダクトってリリースできるんだ」と思って、NoCodeについて興味がありました。
下にロゴがあるように、BubbleだったりとかWebflowだったりとか、あと、知っている人もいるかもしれませんが、IFTTTだったりとか。ほかにいろんなNoCodeツールがあるんですよ。
例えばサービスをリリースするのに向いているものだったりとか、スプレッドシートの進化版だったりとか。マーケットプレイス、要はメルカリとかそういうのを作るのに向いているWebサービス、NoCodeサービスとかだったりとか、そういうのがいっぱいあって、いろんなものを幅広く試しています。
NoCodeの特訓で、2ヶ月でサービスをリリース
こちらです。「NoCode School」。こちらはしんじさんのYouTubeで、こちらは「ノーコード ラボ」さんというTwitter。あとでリンクを貼っておきますね。「ノーコード ラボ」さんのブログなど、そういうのを見て「どうやったらこういうプロダクト再現できるんだろうな?」と思いながら作ってました。2ヶ月……あっ、これはちょっと置いておいて。
このツイートにあるとおりに、しんじさんのYouTubeでUberみたいなWebアプリを作れるみたいなカリキュラムがあったんです。それを3日間だけ真剣にやったら、作れちゃったんですよね。このときに「あれ、なんか俺、天才になったのかな」って正直思いました。このあと圧倒的なNoCodeの闇の部分、いざ自分で作るとなると全然わからないみたいなところがあったのは、あとでちょっと言いますね。
そんな感じで、いろんなNoCodeのプロダクトを触ってみたり、「こういうふうにやったらデータベースって作れるんだ」とか「アカウントってどうやったら作れるんだ」みたいなのをいろんな試行錯誤しながらやってました。
もともと進路選択のプロダクトを作りたいと言ってたんですけど、それをNoCodeで作ることに決めて、2ヶ月ほどNoCodeを特訓したあとに実際にこうやってサービスリリースできました。こんな感じですね。
このサービス自体はもうすでにリリースしている、デプロイしているものです。「ハッシャダイ」という会社の名義で進路選択のプロダクトを作っています。
例えば自分の行きたい進路に合わせて履歴書のフォーマットをあげたりとか、インターンを探すことができたりとか、あとはカリキュラムがあったりとか。これはインターンの抜粋とかなんですけどね。
「自分に合った進路って何なんだろう?」と思うなかで、「仕事に興味あるけど、どんな仕事がいいのかな?」みたいな感じで、インターンを探せる機能があったりとか。こんなふうに。
これはスクレイピングで取ってきてます。スクレイピング自体も全然コードを書かずにできたので、もう本当にNoCodeですね。
あとは、やっぱり実際に就職だったり進学だったり、それはなんかどっちでもいいんだけど、本人にスキルとかあったりとか「自分こういうのやりたいんだけど、どうやったらいいのかわからない」「プログラミングしたいんだけど、プログラミングってどうやったらいいのかわからない」みたいな人たちに向けて、こういったサービスを作ったりだとか。
あとは奨学金。奨学金って、今ものすごく救済としての面が大きいと思うんですよね。ただ、それって「なんか別に未来広がらないじゃん?」っていう。「もっと高いところいけるよね」という意味で、自分たちをエンパワーメント、押し出してくれる奨学金。
奨学金は、みんなけっこう倍率が高いんですよね。こういうのを使って海外に留学、無料で行けたりとか。けっこう給付とかも多くて。貸付というのは返さなきゃいけないタイプの奨学金なんですけど、給付というのはもうもらうだけです。まぁ、レポートとか書いたりすることもあるんですけどね。
そんなプロダクトを、もともとは作れなかったんですよ。僕1人の力じゃ。だけど、NoCodeというツールがあることで、私はこのサービスを1人で完成させることができました。NoCodeって、やる気さえあれば誰でも社会に実装できるんだなって。
だって、いざプログラミング学んだら、それこそ半年ぐらいかかるじゃないですか。「どの言語がいいんだろう?」とか「環境構築で周りに知っている人いないからもうなんか死亡しました」とか、「誰にも聞けないよね」みたいな状況があったりします。
だけど、NoCodeならものすごくビジュアル要素が強いんですよ。要は文字じゃなくて絵で覚えるので、YouTubeとかのチュートリアルがものすごくわかりやすい。そういう意味でしんじさんのYouTubeとかブログとかはものすごく参考になりました。
みんな自分のつくりたいものをつくれる
「NoCodeでプロダクトを作って学んだこと」。私はNoCodeを使って2ヶ月間でプロダクトをリリースできたんですけど、リリースしたときに「あっ、もしかしたらもうコードを書かなくていいのかもしれないのかな」と思ったときもありました。
ただ、それってよく考えたら、最初のコンピュータって全部文字でしか動かせなかったんですよ。だけど、今はこうやってマウスがあったりとかトラックパッドがあったりとか、ものすごくビジュアル要素になってきてるんですよね。これって最初は文字だったのが絵になったよね。だけど、パソコンはみんなまだ全然使ってるし、「あれ、それだけの違いなのかな?」って。
これは私が翻訳した、要はソフトウェアがどういうふうに進化していったかみたいな話なんですけど。
最初はハッカーと呼ばれる技術色が強い人たちだけ。このときはほとんど文字列でパソコン操作する感じでした。だけど、それがいろんな人が自分たちでソフトウェアを作っていって、文字から脱却することができたりとか、これはインターネットがものすごく世に広まって、「みんな使えるんじゃん」「同時に編集できるじゃん」みたいな感じになってきます。
これが最後の、みんながハッカーになるというイメージで全然間違ってないと思うんですけど、要は、私たちは初めてこれだけわかりやすくプログラミングができるようになったんです。ビジュアルで。NoCodeというもので。BubbleとかWebflowとか、まぁ、たくさんありますけど。
そういうものを使ってみんなが自分たちのつくりたいものをつくれる世界になったときに、みんな何をつくりますか?
みんなもうこれで学ぶ時間はあんまりいらないんですよ。それこそつくりたいプロダクトがあれば「こういうふうに作るのか」みたいに失敗しながら学んでいって、「おっ、なんかYouTubeめっちゃわかりやすくない?」みたいな、「全然いけんじゃん?」みたいになって、全然1人でサービスってリリースできるんですよ。
ってなったときに、技術力のあるエンジニアよりも、めっちゃめちゃ野心なバカなほうが全然いいんですよ。僕どっちかというと後者なので。というのはものすごい新しい波なのかなというのを感じたところで、それが、私がNoCodeというツールに惚れた理由になります。
一応スライドとしてはここらへんなんですけど、僕もTwitterめちゃめちゃやってて、日々ツイートしてたりとか、noteというブログサービスで海外の記事を翻訳したりとかもしているので、ぜひご覧になってください。
みんなが起業家になるみたいな感じ
ちょっと時間余っちゃったので、どうしようかな。
Bubbleはどっちかというとアカウント作ったりとかログイン・ログアウトとかがあるタイプのプロダクトにものすごく使いやすいWebサービス、NoCodeサービスなんですけど、もう1つWebflowというサービスがあって、それはどちらかというとLPだったりとかペライチだったりとか、そういうものに特化したサービスなんですよね。
ハッシャダイのやつなんですけど、これ最近私がリリースしたサービスで、これもWebflowで作ってるんですよ。でも、これ1行もコード書いてないんですよ。 《https://nerugaku.hassyadai.com/》
けっこうヌルヌル動く感じとか、インタラクション、単純に下に進むだけじゃない、引っかかるこの引っかかり感とか、こういうのってコードを書くとけっこう面倒くさかったり、ほとんどのNoCodeWebサービスはめちゃめちゃやりにくかったりします。(画面をスクロールしながら)ほら、これね、もう動きがエロい。
そういうのもWebflowにはテンプレートがあって、これは3日ぐらいで作っちゃってます。こういうのを見た瞬間に「これだけNoCodeでできるんだ」みたいな。これだけあれば、みんな全然いけるんだなみたいのがあって。
それを知ってから「NoCodeってもうちょっとメジャーになっていいんじゃない?」と思い、いろんなこういうイベントに出させてもらったりとか、こういったいろんなサービスを作ってTwitterで発信してみたりしています。
要は「これがあれば絵が描ける」みたいな感じなんです。みんななんか今まで「筆、高くね?」みたいな感じだったけど、「えっ、鉛筆でいいじゃん?」みたいな。鉛筆で出たとき、絶対全部うれしかった。
そんな感じで、誰でもものが作れるように。これが最初に挙げた技術の民主化、手段の民主化というものなんですけど、「じゃあみなさんはどのようにして自分が生きたい世界線に旗を立てるか?」みたいな、「みんなが起業家になるみたいな感じなのかな」というのはものすごく思っています。
これを機に日本のNoCodeコミュニティが活性化して、あとはNoCode Japanのコミュニティもありますし、「No Code Founders」というアメリカのものすごく大きい世界中のNoCoderたちが集うところもありますし、それも日本語のチャットもあったりとかします。
英語が苦手という方でも正直ノリと気合でいけたりとか、あとは実際にJapanコミュニティの人もたくさんいたりとかするので、ぜひみなさんやりたいことをどんどんやっていきましょうという感じです。僕でも全然できるので、たぶんほかの人なら全然できると思います。
以上になります。ありがとうございました。