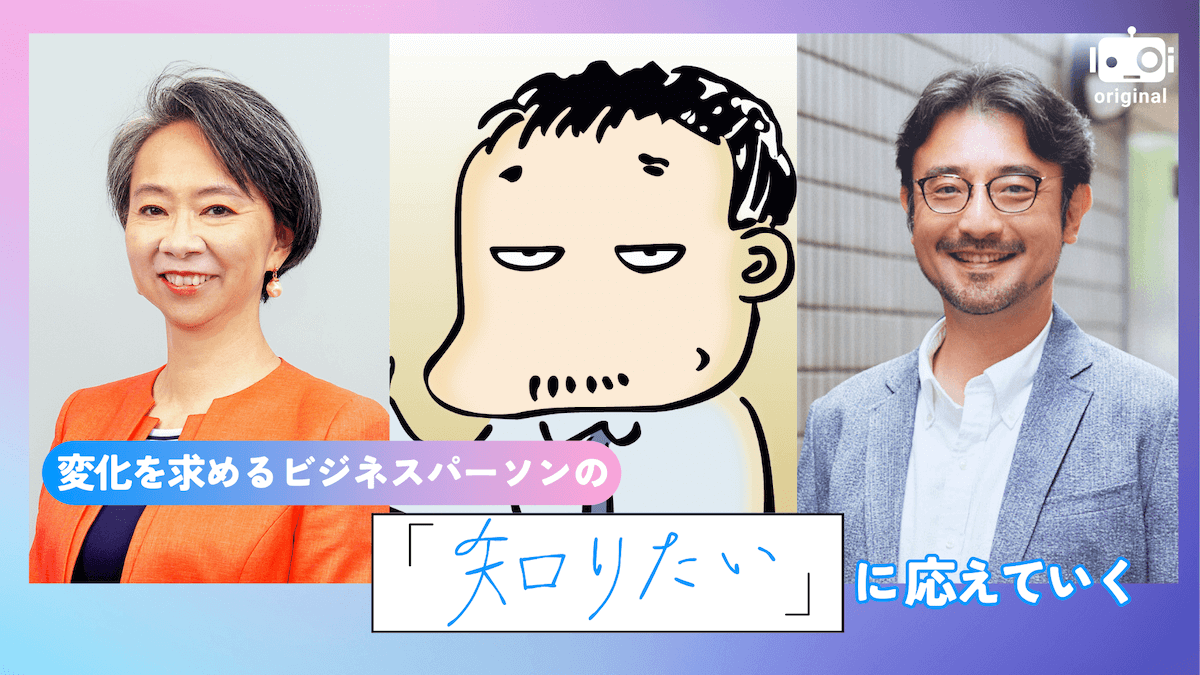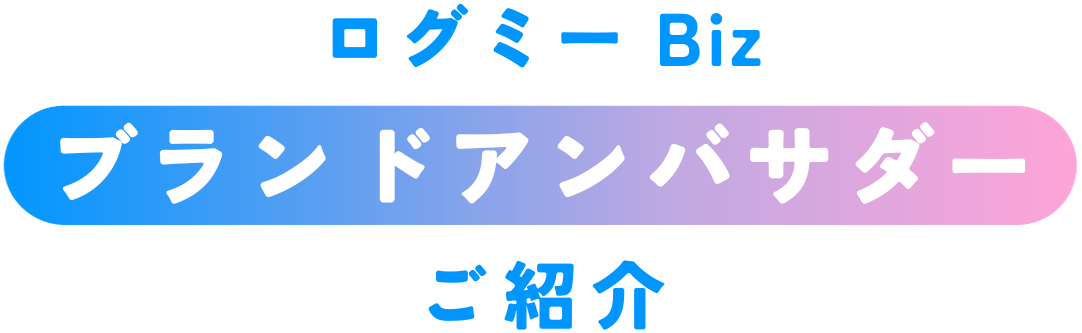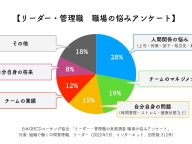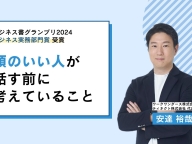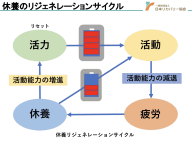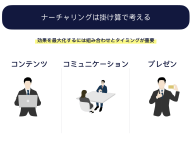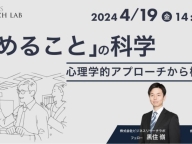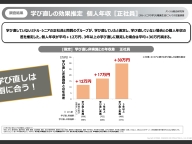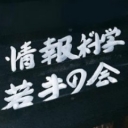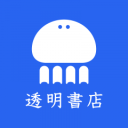コンピューテーショナルデザインに注力する建築家・豊田啓介氏
小林佑樹氏(以下、小林):ここからは「Special Session 2」と題しまして、本日は建築家の豊田啓介さんとエンハンスの水口さんと一緒に、これからの建築系のARであったり、もしくはコモン・グラウンド、それからARの可能性について、3人でディスカッションできればと思っています。
すでにご登壇されていますけれども、みなさんもう1度拍手をお願いします。
(会場拍手)
それではお2人から、ご自身がどういったことをやられているのかというのを、資料をお見せしながらお伝えいただければなと思います。まず豊田さんからお願いします。
豊田啓介氏(以下、豊田):みなさんこんにちは。noizの豊田と言います。よろしくお願いします。ディスカッションのつかみということで、いくつか乱暴にネタを投入できればと思うんですが。
僕は建築の設計事務所をやってまして、建築家という肩書きにはなるんですが。「コンピューテーショナルデザイン」という言い方をするんですけれども、デジタル技術を使って設計とか施工とか、その前後の使い方とかがどう変わっていくのかに注力しながらやっている建築の設計事務所として、noizを東京と台北の二拠点で二人のパートナーと一緒にやっています。
もちろん、いわゆる建築として建物を作ったりするのが本業なわけですけども、プログラミングだけ納品したりとか、インスタレーションみたいなことをやることも多くて。
(モニタに流れるデモを指して)例えばこれはBAOBAOさんのちっちゃいショーウィンドウのディスプレイだけなんですけども。なぜかBAOBAOさんから、この柔らかくて伸びるLEDスクリーンを使ってくれという、ぜんぜん根拠のない依頼があって(笑)。どうしようか迷ったんですが。
もう4年くらい前なんですけどね。「伸びる」というおもしろさは使わなきゃいけないけど、まだ開発中の商品だったので解像度低いわ、発色悪いわで、どうしようみたいな話で。
結局BAOBAOのロゴとちょうど解像度が合ったので、こう自律的にどんどんロゴが自壊していくようにプログラムをすることにしました。その上であえて柔らかいディスプレイの下にファンを付けて。ファンがたまにランダムなタイミングで風を送ると当然ディスプレイがはためくんですが、同時に映像もその風で飛んでいくように、あえてロゴも勝手に飛んでいくみたいなことをやっています。
これはもちろん、のれんみたいに風が吹いてバサバサやるっていうのは物理現象で、でもロゴが風を受けているみたいに飛んでいくのは、当然物理シミュレーションをやっているので計算の話です。実際にはインタラクションしてないんですが、そういうことをやればあたかも情報と物理がインタラクションしているような、情報としてのデジタル画像のほうが物理的な素材感を持つ、みたいなことができるんじゃないかと思っています。
高次元の情報を高次元のまま記述して、外部化できるようになった
豊田:僕ら建築家は当然物理世界を扱う職能なわけですが、情報と物との境目みたいなものがどんどんなくなっていく可能性というのも、デジタル技術をきっかけにしてできるんじゃないかというようなことをnoizでは特にやっています。
情報と物質の境界というものがどんどんなくなっていくみたいなことをやっているんですが、普段は1時間くらいかけてなんとかお伝えする内容を、今回10分くらいでパーっとやるのでかなり強引なんですが(笑)。
(スライドを指して)このダイアグラムをよく使わせてもらうんですが……右下ですかね。建築家っていわゆるXYZの……あ、これはうちのWebページでもダイアグラムを公開してるので、今撮らなくても大丈夫ですよ。
(会場笑)
興味のある方は言ってください。建築家ってXYZの物理空間を扱うプロフェッショナルというのが古来より数千年来続いてきたわけです。でも実際には3次元だけでなくて、例えば工程っていう時間の因果関係とか、素材とか構造とか、いろんな情報として扱える次元を扱うわけですね。
おそらく3次元どころか10次元、20次元、50次元、100次元っていうのを扱っているんですが、その高次元情報というのは、どうやっても他者と客観的に共有しようがないんですね。結果的には、3次元くらいまでのものの組み合わせでしか我々人間とこの世界では客観的な共有ができないと。
それを僕らは、2次元の図面か、せめて3次元の模型というものに、本来はある高次元情報をダウングレードして共有していたんです。そのプロセスを洗練させることで3次元のオブジェクトを作るというのが数百年来の建築の正しい道だったと。
でもプログラミングができることで、高次元情報を全部……とは言わないけれども、高次元のまま記述して、外部化して流通させてグレードアップして、みたいなのができるようになりつつある。これってけっこう画期的なことです。
それを使っていくと高次元を記述するプロセスモデル、いわゆるグラフィカルコーディングみたいなことを感覚的に使ったり、それで出てくるかたちを見て、またフィードバックをして、みたいなことができるようになってきました。これまで勘とか経験とかいうあいまいなものとしてしか扱えなかった高次の知の体系が、外部化して共有できるようになってきているわけです。
情報的相対自体が建築だとして、建築家はその技術体系を手にしているのか
豊田:さらに、それを使ってできたかたちを無理矢理作るのは難しいっていうのが、例えばザハ・ハディドの新国立競技場だったりするんですが。今であれば、例えばデジタルファブリケーションとかいろんなものが出てきてますし、変な形を変な形のまま出すほうが、むしろ合理的な作り方だっていうのはあるかもしれない。
そういうものを開発するというのも建築の世界の仕事だろうと。左上のデジタルファブリケーションっていう、道をもっと開こうよといったことにいろんな機械を使っていたり、そこの開発に投資するのが今建築や都市領域に必要なことでしょと。さらには、それでできたものを使っているデータとか、新しく環境が変わったときにそれをスキャンして、また取り込んでデータをアップデートして、またそれを作ってみたいと考えていくと、できたものはできて終わりじゃないと。物理世界の変化する情報をいかにデジタル世界に取り込むかっていう、センシングやスキャニングが今、すごく大事になってきてるんです。
そして使っているうちにまたフィードバックして、上から新しくなってっていうアクティブなフィードバックループがあるとすると、そのより広義な情報的総体みたいなものが実は本来建築のあるべき姿で、建物という物理的な構造物は実は氷山の一角でしかないのかもしれない。
情報的総体こそが本来あるべき建築だとしたときに、我々建築家がそれを扱うノウハウとか技術体系を持ってますかというと、たぶん持ってないよねっていう意味で、その拡張した領域をちゃんと扱える建築というのは何があるのかな、みたいなことをいろいろやっています。
さっき言った道、デジタルファブリケーションくらいまではだいぶできてきたんですが、もう一度、できたものとか現実にある状況をどう取り込んで、今度はデジタル側に持ってきて、もう1回さらにアップデートするために必要なのがスキャニングとかセンシングとか、群データの制御みたいなところになってくるわけですね。ここがクリティカルですと。
そうなると、もう建築の世界は参照できなくて。例えばゲームとか映画の世界が参照先になるんです。
僕たちは建物を死体として扱っている
豊田:今ってもう、映画の撮影はこんな感じなわけですね。
ベネディクト・カンバーバッチがモジモジくんみたいなスーツを来てるんですが、全身にマーカー付けて、声と動きと表情も全部モーションキャプチャしているわけです。
『トイストーリー』の最初のころというのは、顔をいくつかのパッチに分けて1個1個スライダーで表情を作っていたのが、今はモーションキャプチャーで何百万点も同時に扱えるようになってきている。複雑すぎて、すべてのパッチにスライダーを付けて手で入力するなんていうことは逆にできなくなってしまってるわけです。
そうなると、カンバーバッチを雇ってモーションキャプチャーのスタジオを作って、機材を使って一発撮りするのが一番安くて合理的な手法になるわけですね。
ということで、ある技術の分水嶺を越えたときに、なにが安くてなにが高いかみたいなものがどんどん変わってくる。そういう扱いの仕方っていうのが、例えば映画とかエンタメの世界に先に入るんですが、本来はこれ建築がやらなきゃいけない話なんじゃないかと思うんです。
例えば身体についても、モーションキャプチャーとか骨格・筋肉のシュミレーションで、僕の身体がジャッキー・チェンみたいな動きをすることもできるようになる。人体だとそれくらいセンシングとかシミュレーションの研究進んでるわけですが……例えばこの建物にセンサーがどれだけ付いているかというとぜんぜん付いてないですし。そもそも動いたり変化したりする前提ないから、シミュレーションがどれだけできますかっていってもできないですし。
なぜか僕らは、建物は死体として動かない、センシングもしないものであることを、当然のように諦めて納得しちゃってるんですが、もっとできてもいいんじゃないかと。もっとセンサーがあって積極的に動いていいんじゃないか、みたいなことを考えるわけですね。実際、技術としてはできるはずなので。
20年後の都市計画に必要なノウハウ
豊田:例えば筋電義手みたいなものがかなり実装に近づいてきています。(モニタに流れるデモを指して)このおじさんは腕がない方で、筋電のセンサーを複数入れておいて、もちろん練習は何度もしなくちゃいけないんですが、練習すると、考えるだけでこの腕が動いて水を飲んだりできるようになると。
これができるということは、普通の人間の能力をどんどん超えていく可能性がある。腕が3本あってもたぶん動くわけですし。4本あっても動くし、5本くらいはたぶん動かせるんじゃないか。こういうことができるという前提になったときに、いわゆる不足を補う技術というよりも、能力を拡張する側に技術が展開し始める。例えば腕が肩に付いている必然性はないわけですよね。
まったく同じ原理で床に付いてたって腕は動くし、玄関に付いててドアを開けてくれるようにしたっていいわけですし。タクシーに付いてれば運転できるかもしれないと。要はどこまでが自分の体で、どこから先が環境かみたいな、これまで哲学的だったような問いまで、普通の市販品が問い直すような状況起り始めているわけです。
技術で身体や物理環境そのものが実装環境でありインターフェースでもありのような形でどんどん曖昧になっていくようになったときに、なにをもって建築で、なにをもって自分の体で、誰がどれを制御するのかみたいなことを、僕らはガチで建築の環境として設計しなきゃいけない段階になっています。
でも、それをどう制御したらいいかというノウハウを僕らは持ってないわけですね。そのへんをもっと建築という世界に閉じずに考えてなきゃいけないと。
人流とか物流とか都市の交通とかっていうのも、例えばAmazon Robotics(アマゾン・ロボティクス)みたいなところでやってますが。まだ倉庫と単体の制御しやすい環境ですが、今これができているということは、たぶん10年後の都市の交通とか物流とかっていうものが、複合的にこういう群知性というか、個別制御ベースなのに全体最適するような新しいシステムでの制御をせざるを得なくなるわけです。
それを前提にしたときに、どういうセンサーがどういう範囲で付いていて、それに対してどういうスケールや密度、形式のシステムを街が持ってなきゃいけないのか。そのノウハウを僕らはやっぱ持ってなくて。でもこれがないと、たぶん今は都市計画ってできないはずなんですね。20年後の都市計画なんて、今普通に始めないといけないのに、です。
2025年、大阪万博でのインタラクティブな会場計画
豊田:それをやるにあたって、当然エッジ側の開発はいろんなメーカーさんがやっているので、僕ら建築側としてはエッジが認識しやすいデータ形式で、ある程度汎用的な環境をあらかじめしておいてあげるというのが重要だろうと考えているわけです。複数のサービスに共通する環境側のデジタルプラットフォーム化ってどういうことで、そこにどういう単位で、どういうマーカーが、どういうセンサーが入ってると彼らが動きやすい環境として汎用化できるのか、みたいなことを設計事務所としてやっていたりします。
今の建築ってBIMっていう結構な精度の3Dデータを環境として作るんですが、ただBIMはあくまでも建設という閉じた世界にしか特化してないので、いろんなサービスの環境データとしての能力は非常に低いんですね。
これをどう環境データ化してあげるか。もしくはBIMがないところを点群スキャンして環境データ化してあげるか、みたいな。いわゆる点群と、たぶんゲームエンジンがベースになるんですが、BIMデータっていうものをどうシームレスにつないであげるかみたいなことを開発したり。
ゲーム中での各種のキャラクターAIとか、ゲームの世界で使うようなAIみたいなことを参照して、実世界でいろんなエージェントとか環境が主体的に動ける状態を作っていくための参照や実証実験をしてみたり。
とりあえず芸大のキャンパスをまず点群スキャンして、これをどういうデータ形式で、どうすれば半自動で変換できるか、みたいなことをやったりしています。そういうのを「コモングラウンド」という言い方をしています。
コモングラウンドっていうのはわれわれ物理世界の住人にも認識ができて、同時に自律走行モビリティやロボット、ARアバターなどいろんな形のデジタルエージェントにもちゃんと物理世界が認識ができるような、情報と物が重なり合っているような世界のことを言っているわけですが、そんな環境をまず作ることからしか、そこから先へは行けないだろうみたいなことを最近言ってるわけですね。で、それって以外なくらいに新しくゼロから作らないといけない領域なんです。
その実装機会として、2025年に万博が大阪に来ることが決まったんですが、その会場計画にも僕はかかわっていて。とりあえずコンセプトとしての誘致段階の計画段階では、配置の決定やバランスの制御もインタラクティブです。作ったあとも、もちろん建物は動かない部分が多いんですけれども、いろんなレイヤーで考えたときに、高次元に考えればインタラクティブであるとか、機能の定義や所有の形態が状況に応じて移動するとか、さらには会場や会期というものに制限されない、いろんな高次元のインタラクションのかたちというのを、いわゆる広義の会場計画としてデザインしなきゃいけないみたいなことをやったりしてます。
ただそれではあまりにも複雑すぎるので、いろんな入り口から徐々にできることの組み合わせを示して、いろんなプレイヤーに徐々に開発と実装を進めてもらわないといけない。その一環として(スライドを指して)例えばこんなものを考えました。解体がきまってしまった昭和の名建築で「都城市民会館」というものがあるんですが、その建物をいろいろな方に協力してもらってスキャンして……3Dスキャナーやレーザースキャンを使ってデジタル化して、複数のデジタルデータとして後世に残すっていう価値の提示もアリじゃないかと。今ちょうどスキャニングの作業が済んでいて、昨日このポケットAIみたいなもののアプリが公開されたところです。
これをいろいろダウンロードして、今ちょうど解体が始まった建物はどんな使い方ができるのかな、みたいなものを遊んでみたりしています。建築って、たぶんモノとして以外にもいろんな価値の生み方があるはずで、その辺がまさにARとかそういう世界と繋がるんじゃないかと。とりあえずまとまりがないですが、ネタの投入ということで。ありがとうございました。
効果音が音楽になり、その音楽を視覚的に見るという不思議な体験
小林:ありがとうございます。お話ししたい内容をけっこう詰めていただいた感じですけれども、けっこうARとかの深い部分でこのあといろいろお話させていただければと思います。続きまして、水口さんお願いします。
水口哲也氏(以下、水口):水口と言います。エンハンスという会社の代表をやっているんですが、2014年に起業したばかりのまだスタートアップ……でいいんですかね。実はアメリカで起業しまして、東京で研究開発をしています。マーケティングとかビジネスの拠点はアメリカに持っているということですね。
その理由は何かと言うと、2013年から2014年くらいでしたかね、「VRからXRが始まるぞ」みたいなときに、どうしてもやっぱりアメリカの会社のプレーヤーが多いじゃないですか。
新しいテクノロジーがシリコンバレーからガンガンやってくるので、日本にいるとすごく時間がかかっちゃうんですよね。契約事もそうだし、交渉も。なのでアメリカにいるとアメリカの会社としてすぐに交渉ができるということで。日本にいると、日本の法人を通さなきゃいけないという変なルールが多い会社がたくさんあるんですよね。それでアメリカで起業しました。
あとシナスタジアラボ(共感覚ラボ)。シナスタジアって共感覚という意味なんですけど、ここのラボの主催もやっています。
僕自身はいろんなゲームを今まで作ってきたんですけど、とくにエンターテインメントの世界で時間をいっぱい使ってきて。(モニタに流れるデモ動画を指して)これはKinectを使って、2011年に発表した「Child of Eden」というゲームですね。どんどん音がシンクロして、音楽化していくっていう。指揮者のように遊ぶっていうものです。
2016年にエンハンスとして起業して一発目に作ったのが、この「Rez Infinite」というゲームです。プレイステーション4とプレイステーションVRで遊べるようなかたちでスタートして。そのあとPCとかOculusとかで展開していきました。
今日はちょっと音が出ないので少しさみしいですけど(笑)。効果音をどんどん音楽化していくのを3Dで見るという、音楽を目で見ていく、視覚的に見ていくという、そういったちょっと不思議な体験を目指しています。
なぜテトリスをVR化したのか?
水口:エンハンス自体は、共感覚的でまったく新しい未曾有の体験を作るということを念頭に置いてまして。それを言語に関係ないグローバルで、世界中の人が体験できるというようなコンテンツ作りを続けています。
最近、去年ですかね、テトリスをVR化しました。VR化するというときに多くの人が「え?」って。「なんでですか?」みたいな(笑)。
小林:テトリスってめっちゃ2次元じゃんみたいな(笑)。
水口:「別にテトリスをVRにする理由がないんですけど」みたいなことをみんな最初は言うんですけど、実際にやると「あ、そういうことだったんですか」というね。
これは作る前のアートとかからスタートするんですけど、実際に1つひとつのアクションの効果音が音楽化して、テトリスを揃えるのがまるで演奏するような気持ち良さに変わっていく。周りの世界がどんどん変化していきつつ、ストーリーテリングになっていく。
これを3Dで見ていますので、フレームのない3Dの世界で体験すると、かなりオーバーウェルミングな体験になるというところは、いろいろと実証できたかなぁ思っています。
あとはゲームの周辺で、アート系のこともいろいろと試していて。(モニタに流れるでも動画を指して)これはMedia Ambition Tokyoという、毎年六本木ヒルズで2月から3月に行われるメディアアートの祭典みたいなのがあるんですけど、そこでシナスタジア・スーツというのを発表しました。共感覚スーツってやつですね。
触覚(ハプティック)デバイスを26個、全身に配置して、VRでゲームをやって、ゲームプレイと完全にシンクロした音楽を、テクスチャー付きの触覚で全身で感じるとどうなるのかってことを試してみたかったんですね。
例えばキックとか、バスドラムがバーンバーンバーンときて、それがドラムで本当に叩かれているような触感が下半身にきたり。肩にハイハットが来て、例えばドッドッドッと感じたり。触覚が音ともに全身を動いて体験するっていう、ちょっとみなさんが体験がしたことのないような未体験ゾーンというのを試してみたかったということですね。
ARグラスで体験する共感覚
水口:(モニタに流れるデモ動画を指して)これまたちょっと違う試みなんですけど。VENTっていうアートエキシビジョンで、我々がやってるようなパーティクルを無数に出して、それを音楽とフィジクスを連動させるっていうような、そういうインタラクティブなアート作品を作りました。
大谷石採掘場ってありますよね、宇都宮のほうに。横11メートル × 縦35メートルの大きい天井にプロジェクションして、Kinect的を使ってインタラクティブなメディアアートをやってみようということでやりました。これが去年ですね。
これが最後なんですけど。「シナスタジア X1 – 2.44」という、椅子も実は作ってしまったんですね。これはハプティックチェアなんですけど、どういうふうになっているかと言うと44個の振動組織を全身に配置して、音楽とともに触覚が全身を動くんですね。
ちょっと音を今聞いてもらえないのが残念なんですけど、想像してみてください(笑)。これで体験すると、実はビジュアルは光しかないんですけれども、かなり共感覚的な新しい体験ができる。MESONの梶谷さんは「これもARだ!」ってブログに書いてくれましたけど。
こういうところから、実際にAR的なグラスをかけてどういう共感覚的な体験ができるかみたいなことも、今ちょっと実験を始めています。ということでした。以上です。
感覚を五感だけに担わせるという壁
小林:ありがとうございます。僕もシナスタジア体験しましたけど、視覚とはまた違う拡張体験みたいなものがありますね。豊田さんは体験されました?
豊田:はい。Media Ambitionと、この前に体験させてもらいました。あんまり気持ちよすぎて僕はついつい、こう(眠たくなってしまって)……。
小林:ははは(笑)。そうなんですよね。
豊田:普段感じない感覚の組み合わせだから、感覚が起きる部分と、「フ~」っとなるのと両方があって。
小林:音楽を聞くということを違う五感の組み合わせで表現しているのかなというふうに思ってて。感じるじゃないですか、ああいうのって。
その中で目をつむると像が浮かび上がってきて、でも僕らが今まで聞いてた歌詞とかはないのに、なぜか像が浮かび上がってくるというのが、僕の体験としてはすごくおもしろかったなと思っています。
水口:人ってやっぱり、音は耳で聞くものだっていう先入観というか、最初からそう思ってますけど。実はぜんぜんそんなことなくて、ふだんも五感どころじゃなくて、本当に何十っていう感覚が複合的に絡み合って生きてるわけじゃないですか。
それを五感というかたちで抽出しちゃうのはけっこう乱暴な話で。ここから先の解像度が上がっていく世界って、なにか新しい体験をクリエーションするって考えたときに、やっぱり五感というのがすごく壁を作ってる気がしたんですよね。
「ARは視覚!」みたいな。視覚はもちろん大事なんだけど、それだけではないっていう。その体験設計をどうするかというのはすごく求められてくることですね。
小林:そうですよね。コモン・グラウンドの話とかもそうですけど、先ほど豊田さんが「建築って死体として扱われている」みたいなお話をされてたじゃないですか。今まで僕らがいわゆる当たり前と思ってたことを、もう1回塗り替えなきゃいけない時期に来てるのかなって思っています。
3Dで感じていることを2Dのフレームに当てはめる不自然さ
小林:豊田さんがさっきお話されていたこともそうですし。水口さんがお話しされていた「テトリスをなんでVRでやるの? 2次元でいいじゃん」みたいなことも、僕らは2次元が当たり前だという一種の刷り込みをされてたところに、AR/VRとかいろんな技術が出てきて、もう1歩次元を……僕はけっこう「次元を超える」という話をするんですけど、次元を超えるステップになってきてるのかなというのはけっこう感じるんですよね。
水口:そうですね。本当のパラダイムシフトってここから起こるのかなっていう気がするんですよ。ちょっとメディア的な歴史の視点で言うと、たぶん今の状態って、500年か600年続いてきたかもしれない。
最初にどなたかが言ってましたけど、2Dの時代がようやく終わるというか。四角のフレームの本とか絵とか映画とか、2Dで切り取ってっていう。実はこれが最も不自然だったんですよね、人間からすると。
小林:そうですね。
水口:僕らは3Dの中で生きていて、すべてを3Dで感じているのに、抽出して記録するためにとか、伝えるために2Dにするのは面倒なことじゃないですか。ずいぶん不自然なことだったんですよね。
それがようやく統合できて、VRでなんとなくそれがわかってて、それをARでようやく僕らの生活している現実の世界に、それをシンセサイズできるようになるっていうところが、実は本当に600年ぶりの大転換だと。大きなイノベーションが起こるっていうことを感じて、たぶんみんな集まってると思うんですよね。
小林:まさにそうですよね。それは建築の部分でいくと、やっぱり今おっしゃられているようなことがあると思うんですけれども。豊田さん自身はそういうことをどのくらいの時期から考えられているんですか? 何をきっかけに考えられたのかなと思いまして。
豊田:どうなんですかね。今コンピューテーショナルとか言いながら、一応出身は安藤忠雄建築研究所出身で、コンクリートの塊の中で物理的に殴られて育ってきたから。旧世代の建築家という立場なので。
小林:ははは(笑)。
水口:安藤さんって殴るんですか?
豊田:あの……オフレコで。
(会場笑)
オフレコかオンレコでちょっと答えが変わってくる。まあ、いろいろね(笑)。バーチャルじゃなくてリアルなことも。
根源にあるのはヴァナキュラーなものへの憧れ
豊田:例えば建築って、いわゆる2次元の図面っていうものを出して、その洗練でいかにいいものを作るかっていう、社会的な洗練の度合いをどう上げるかっていうのが数百年来やってきた世界なので。それはそれで、すごい解像度と機知の体系があるんだけれども。
安藤事務所って2000年くらいになっても、いまだにT定規の勾配定規で書いてたので、当時でも遅かったくらいなんですけど。ものすごくグリッド状に沢山部材がならんでいる建築のパースを書いていて、コンマ何度の角度を正確に書かないと絶対間隔とか同じにならないんですね。「絶対コンピュータで書けるじゃん!」と思いながら徹夜で書いてたときに、なんか他の手段あるだろっていうのはそのころから感じてたんです。
小林:なるほど。一種その2Dの中で作業する違和感がけっこう出てくるのかなと。
豊田:それは物理的なというか、効率にかかわる話で。同時に、これもよくいろんなところで話す話なんですが、僕は埋立地育ちで、全部が直交形の計画された土地で、すべて人工じゃないですか。千葉なんですけど、国道14号線を挟んだ向かい側に稲毛とか検見川とかの昔の漁師町があって。漁師町って地形に沿って土地があって、昔からの何百年来の家があって。なんか雰囲気あるじゃないですか。
でもあれは、形態だけでコピーしてまったく同じものを作るとハウステンボスになっちゃって、折角のおもしろさがなにも残らないっていう。創発される質みたいなものっていうのを、不特定多数がやっと作れる意志の力みたいなもの、あれが建築のすごく大事なものだと考えたときに、それはたぶん僕らデザイナーが図面では書けなくて。
それを作る集合知の間接的なメタなデザイン、ある量とかあいまいなものを扱うみたいなものが今できるとすると、むしろデジタル技術みたいなもののほうが近いんじゃないかな、みたいなのはたぶん昔からあって。それでこっちに来たっていうのはあると思います。ヴァナキュラーなものへの憧れとか、そういうもののほうがこれの根源のところにあると。