人材獲得競争が激化する今、一度退職した社員を再雇用するアルムナイの取り組みが注目されています。今回は、トイトイ合同会社 代表社員/元ニトリホールディングス 理事 組織開発室 室長の永島寛之氏にインタビューしました。本記事では、日本企業における「退職者の質」の変化や、元社員の「出戻り採用」で成功/失敗するパターンについてお伝えします。
企業がアルムナイに注目し始めた背景
——売り手市場で人材獲得競争が激化する今、一度退職した社員を再雇用するアルムナイ採用が注目されています。企業がアルムナイ(退職した元社員のコミュニティ)に注目し始めたのはいつ頃からですか? また、そのきっかけを教えてください。
永島寛之氏(以下、永島):僕が知っている限り、僕がまだニトリの人事の責任者だった時に初めて、ニトリを辞めた人を集めた「モトニト会」というのを始めました。「元リク」というリクルートさんの退職者の関係性を意識して、コロナの前ぐらい、たぶん2019年から始めました。
日本では2010年代後半から2020年にかけてアルムナイという言葉が認識され始めて、退職者の集まりが注目され始めた時期だったと思います。
欧米では、普通に退職者コミュニティというかたちはあったし、コンサルティングファームでは、組織に所属していた時と同じような関係性を退職後もそのまま続けていくというのが当たり前にありました。日本とアメリカでは組織(と従業員)の関係性の持ち方がそもそも違うので、同じようにはいかないのですが、日本でも退職者の集まりに関心が高まってきた。
2010年代から「退職者の質」が変わってきた
永島:多くの会社がアルムナイを始めたきっかけは、いわゆる人手不足からくる人材不足というところが大きかったと思います。ただ、リーマンショック後の2010年くらいから、もう1つ大きな労働市場の変化があって、優秀な人から会社を退職するケースが目立って増えてきたということがあります。
昔は優秀じゃない人が(会社を)辞めていたから、退職者の価値に目を向ける人が少なかったのですが、そこが変わってしまった。「262の法則」で、企業の中で上から超優秀な人2割、普通から優秀な人6割、ちょっとついていけない人2割という時に、昔は下の2割の人が辞めているのが日本の組織だったのですが、上の超優秀な2割が辞めるようになってきた。
2000年代に入ってから、転職市場が活発になり、働いている人の選択肢が増えてきた結果、今まで組織に残っていた、上の超優秀な人たちが動き始めた。一方で働き方改革の潮流でホワイト企業が増えてきたので、それまで退職していたような、組織についていけない人たちにとって居心地のいい会社になって、残るようになったんですよね。
だから、退職者の数が急激に増えたというよりは、退職者の質が変わってきたのが2010年代からなんです。よって企業は、今まであんまり退職者を気にしていなかったし、裏切り者扱いすらしていたのですが、優秀な方がどんどん抜けていく中で、「その後もつながり続けたいよね」という発想に変わっていったんだと思います。
アルムナイを取り入れて成功するケース、しないケース
——転職が当たり前になり、優秀な人材が辞めてしまうという課題感から、アルムナイを取り入れる会社が増えていったんですね。アルムナイの取り組みで成功する企業の共通点はありますか?
永島:まずうまくやっていないところは、アルムナイのイベントを始めたんだけれども、単純に辞めた人のリストから声を掛けて集めているだけという会社ですね。イベントをやっているだけで、同窓会みたいなことを繰り返している会社さんが大半です。
うまくやっているところは、例えば出戻り採用だけではなく、その後の関係性を続ける中で、「退職者の価値を出戻り採用以外にも広く活かそう」という考え方があるんですね。
例えば出戻りの採用もそうですし、その後のビジネスパートナーとして人を紹介してもらったり、情報交換したり、オープンイノベーションの企画に入ってもらったり、ブランドの価値を上げるような発信をしてもらったり。良い関係性を築いているところはうまくやっているんですよね。
私が聞いている中では、例えばディー・エヌ・エーさんはすごくうまくアルムナイを活用していると思います。アルムナイを通じて元社員の方が起業をすると、出資や事業協力などの支援などをしており、とても良い関係を築いています。その仲間は、ディー・エヌ・エーマフィアなどと呼ばれたりしています。
「出戻り採用」を目的にするとうまくいかない理由
——なるほど。アルムナイというと出戻り採用を目的とするイメージがありますが、それだけではないんですね。
永島:先ほどお伝えした「262の法則」で言うと、(アルムナイのイベントで)普通に飲み会をやって、「久しぶり、(再入社は)どう?」って言って戻ってくるのは、上のほうの人ではないですね。要は「外に出ていったけど、うまくいかなかったよ」という方が中心になります。
一方、ちゃんと関係性を持ってお互いの情報交換したり、頻繁にそういう場を持ちながらアルムナイを運営している企業については、やはり上層の人ほど戻ってきたり、あるいは別のかたちでビジネスの関係性を持ったりしています。
アルムナイで(元社員が)戻ってくるということを目的にすると、あんまりうまくいかないんじゃないかなと思います。ベースにあるマインドとして、「(辞めた人を)戻したいからやる」というのだと、戻りたくない人は来ないですから(笑)。
——先ほどおっしゃったような、優秀な方ほど外に出ていってしまうということですね。
永島:雇用関係という意味では、一度は関係性がなくなるわけです。アルムナイというのは、「そこに新しい関係性を築こう」ということなんですよね。いったん、フラットでフェアな関係性に戻るわけです。
もちろんビジネスパートナーとしてですけれども、関係性の種類はたくさんあるわけで、「雇用契約に戻そう」というのは、そのうちのごく一部ということですよね。
社員が出戻りするかどうかは「上司との関係性」が大きい
永島:もう1つだけお話しすると、私がいる中央大学の企業アルムナイ研究会では、(アルムナイ採用が)できている会社のインタビューを行っています。そこでわかったことが、その人は、上司との関係性の中で戻ってきているんですね。要は、(出戻りされるのは)前にいた上司と関係性がそのまま継続している方のケースが圧倒的に多いんですよ。
だから、社員が戻ってくるかどうかは、「アルムナイをやったから」というよりは、「あの上司の下でもう1回やってみたい」とかが多いので、過去の関係性で戻ってきているんですね。アルムナイをやるのであれば、そういう関係性を作っていくことを意識しないと駄目なんですよね。
上司との関係性や会社との関係性が壊れないまま続いているのが、例えばソニーだったり。彼らは別にそんなかたちで囲わなくても、自然とアルムナイ状態になっているんですよね。
だからアルムナイというのは、何か(コミュニティで)イベントをすることではなくて、関係性を持ち続けるということなので、その関係性がある人たちには別にあえてやることでもないと思います。
ソニーのアルムナイに1,000人が集まるわけ
——永島さんも元ソニーでいらっしゃいますが、ソニーでは会社が制度としてアルムナイを導入したのではなく、有志のコミュニティが大きくなって、今では1,000人規模のコミュニティになっているんですよね。
永島:そうなんです。有志でやっていき、それに企業が少し支援したりという感じなので、非常におもしろいかたちですよね。ソニーの場合、企業がガチガチにやっているのではなく、時々のテーマで人が集まってきているというようなアルムナイですね。
——ここまでアルムナイが活発化しているのは、なぜなのでしょうか?
永島:そうですね。基本的にはソニーブランドが嫌いになって辞める人は少ないというのが前提にありますよね。ソニーの上司や事業との関係が嫌で辞めるというよりは、どちらかというとやりたいことがほかにあって退職しているというのと。
全部が全部じゃないですけれど、比較的社内でも自由に働いている人が多いので、中にいるのと外にいるのとで、水温が変わらないんじゃないですかね。
——自由な働き方ということですが、どんな特徴があるのでしょうか?
永島:働き方自体はそんなにほかの企業と変わらないと思いますが、自分の声を上げていろいろと移っていったり、新しいところにチャレンジする場が用意されているので。そういう制度を使わない人はほかの会社で働くのと変わらないんですけど、自分で何かチャレンジしたり、関係会社に行ったりとかが比較的自由にできます。
僕は5年の在籍だったんですけど、海外のグローバルマーケティングの担当から始まって、ソニーマーケティングっていう日本のマーケティング会社で勉強させてもらいました。その後マイアミに2年間駐在させてもらったので、その5年の中で10年分ぐらいのことが学べました。みなさん比較的そういった点では自分の考えで動けることが多いんじゃないかなと思います。
出戻り採用で活躍できる人の条件
——新しい挑戦ができたり、声を上げることがしやすい社風だからこそ、辞めた後も、企業と元社員の間で良い関係性を築いていけるんですね。
先ほど、優秀な社員ほど外に出て行ってしまうというお話がありましたが、企業にとって戻ってきてほしい人材とは、具体的にどのようなスキルや経験を持つ人だとお考えですか?
永島:そうですね。これは企業によってちょっと違いはあるとは思うんですけど、基本的にはアルムナイの人に戻ってきてもらう良さは、即戦力ということなんですね。
即戦力というのは、まずスキルの前に、企業文化を理解したり、その会社での働き方を理解しているので、オンボーディングが要らないんです。だから、その企業の働き方が自分の体にフィットしていて、そこで働くことに抵抗感がない方がまず1つと。
もう1つは、やはり出たからには何か社外で得た専門のスキルや知見、視点とかを持った状態で戻ってきてもらいたい。つまり、本来であれば出ていった時の報酬よりも高いグレードで迎えられるような人材に戻ってきてほしいんだと思います。ただ、人が足りていない会社からすると、「誰でもいいから戻ってきてくれ」みたいなところがある(笑)。
とはいえ、合わない人を戻してしまうとまた退職してしまいますので、やはりカルチャーを理解していて働き方もマッチしている方が、最低条件だと思います。
企業の変革時に活躍する「越境」経験者
——新入社員のオンボーディングがうまくいかず、「せっかく入社したけれど早期退職してしまう」というリスクを回避できるのは大きいですね。
永島:というのと、一般的に企業が新しいことを行って変革する時は、みんな抵抗するんですよね。その点、その会社のことがわかっていながら、社外で専門スキルを得ている人は、説得力があるんですよ。社内でも社外でも働いた経験があると、比較ができるので。
ちょうど一昨日登壇したイベントなんですが、京都市の事業で『地域企業「担い手交流」実践プログラム』というのがあるんですね。要は大企業の方が中小企業に行って1年ぐらいプロジェクトをして戻ってくるという、越境プログラムです。
一番大事なのは、帰ってきた後にちゃんと経験してきたことを活かせるかどうか、活かせるチャンスをもらっているかが一番大事なところです。そういうのをちゃんともらえている人は、やる気を出していろんな新しい価値を生み出したりしているんですけれども。そういう機会をもらえていない人はまた辞めちゃいますね(笑)。
だから、外に行ったけどあんまりうまくいかずに戻ってきたという人は、どんな仕事をもらっても何も考えずに仕事を進めてしまうので、単純にただ1年間休んでいただけとか、2年間休んでいたのと同じになってしまう。
一方、アルムナイで戻ってきて新しいバリューを発揮している人は、ちゃんとそれ(自身の経験やスキル)に合った仕事をアサインされていますよね。
組織が拡大して「合わなくなった」ケースも
——越境経験があって、そのスキルや知見を活かせる方は、企業の変革においても重要ですね。そうした方でも、実際に戻ってきて「合わなかった」というケースはあるんでしょうか?
永島:1つは、会社が変わってしまっているケースですね。在籍時はスタートアップだったけれど、そこからちょっと大きい組織になっていたので、戻ってこようと思っても合わなくなっていたり。その逆もあると思いますけど。あとは、やはりその企業文化や目指す方向ですね。価値観の理解ができていない方が戻ってきても駄目だというのはあります。
もう1つ、たまに聞くのが、さっきの企業を変革する人の悪いパターン。「外ではこうだったよ」と押し付けるばかりだと、みんな「じゃあ、戻ってこなきゃよかったのに」って感覚になるので。
つまり、社内のみなさんも正しいと思ってやっているので、今の日本の企業だと、戻ってきた方は伝え方を工夫するような、ある程度のコミュニケーション能力は必要なんだろうなと思います。
——他の会社で得たスキルや知見だけでなく、社内の人とうまく折衝していく力も必要なんですね。
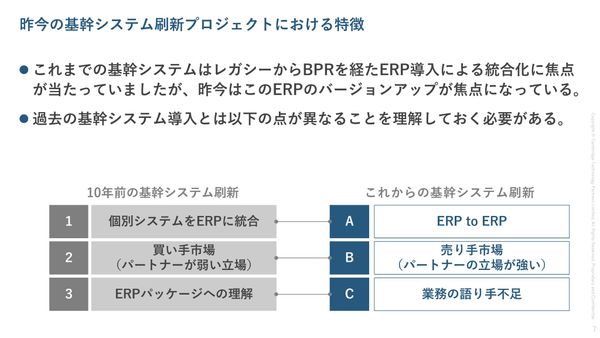 PR
PR



















