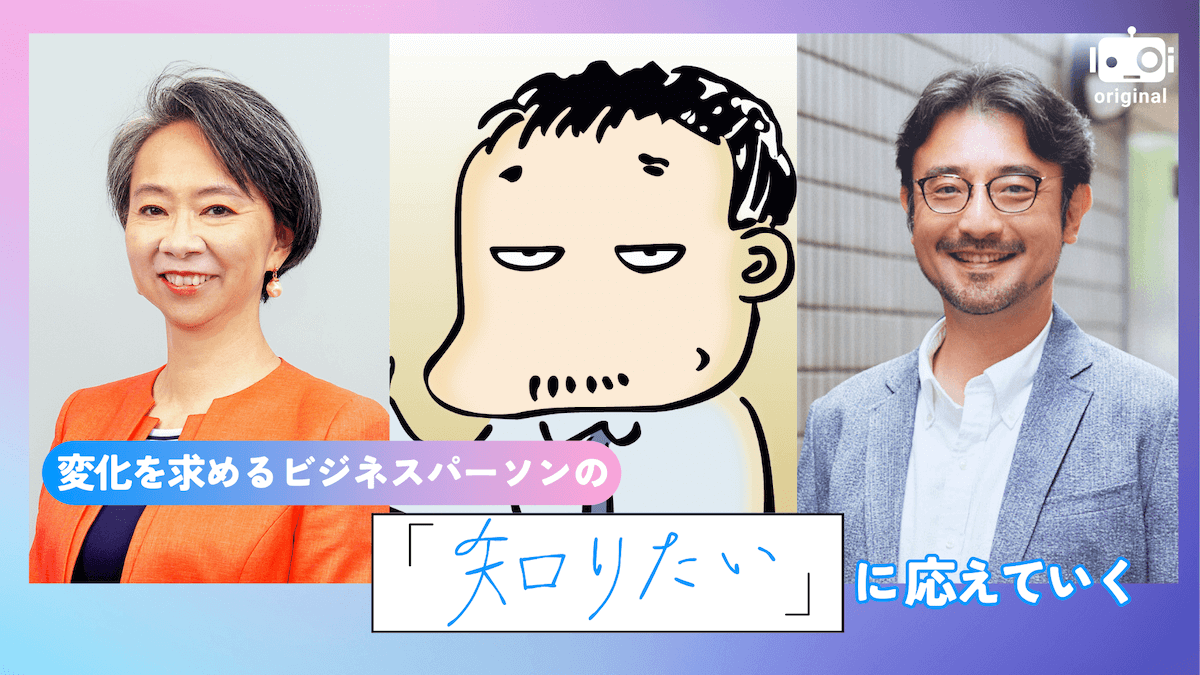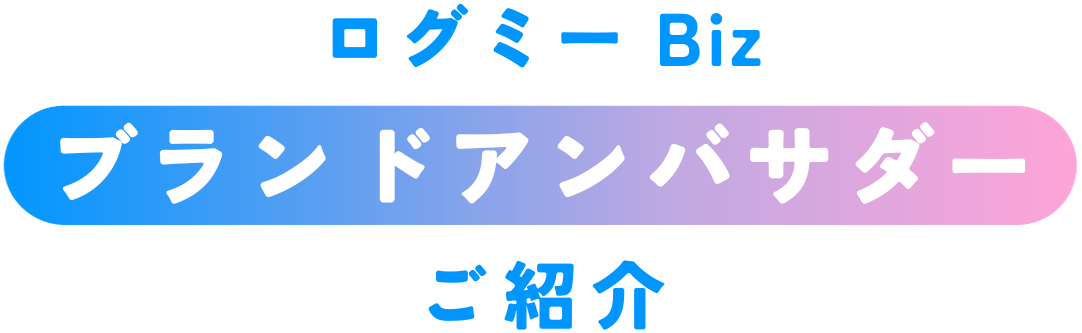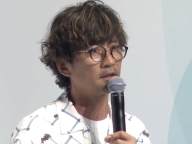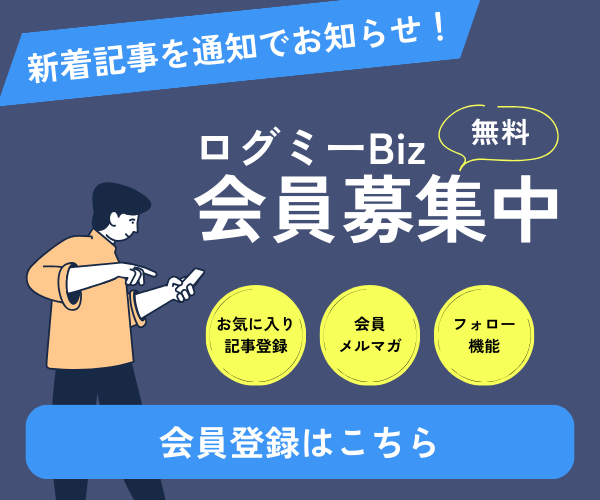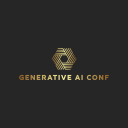銀行員に戻らず、現地のVCへ行った理由
佐俣アンリ氏(以下、佐俣):お話を戻すと、そういう課題を抱えて、スタンフォード行かれたあとにDCMに行かれた。
伊佐山:そうですね。スタンフォード行ったあと、本当は戻らなきゃいけないんですけど、よくありがちな、行ってる間に洗脳されて、「新しい日本の経営のスタイルというのを知りたい」と。
それが(日本に)戻って銀行員でできることならいいんですけど、それをやるためには、ここに残るしかないということになったので、何らかの形で残る術を見つけて。それは別にベンチャーへの丁稚奉公でもいいし、何でもいいと思ったんです。
幸い僕は「卒業して何もないと困る」ということで卒業生にいろいろ相談してたときに、たまたま「1年ぐらい丁稚奉公してみる?」って。それで、IVSじゃないですけど「何でもやります」と。
提案してくれたのはそのDCMという、当時はまだアメリカのファンドで、これからどうなるんだろうなぐらいの、大手でもないところに入ったんですけど。
そのあと、DCMはアジアという戦略を打ち出すことによって、中国ではナンバーワンファンドに近いようなポジションを取って、ものすごく伸びて、私も1年いるはずが結果的に10年いたということです。
佐俣:もうそこで10年。
伊佐山:はい。
佐俣:日本人で、シリコンバレーのトップファームでパートナーというのは初めてですよね。
伊佐山:そう言うと格好いいんですけど、実態的にいなかっただけなので(笑)。
佐俣:なるほど(笑)。
DCMにいた10年で得た成長
伊佐山:僕がすごかったわけではないですけど、すごくレアな経験ができたのはありがたかった。今の僕の、ひとつの付加価値になっていると思います。
サンドヒルロードという、非常に閉鎖的な、白人でユダヤ系の人ばかりが牛耳ってる世界の中で、僕みたいな人間が10年間も生活できた。毎日その人たちと同じ空気を吸いながら、仕事も一緒にする機会をもらえたのは、極めてユニークな経験であることは確かです。
パートナーになるとか云々というのは、DCM自体がもともと小さいファームで、大きくなって、僕はたまたまその小さいときにいた。タイミングが良かっただけです。
佐俣:まさにスタートアップで、一緒に成長していったという感じですね?
伊佐山:一緒に成長していったということ、そのパートナーになれたということで、何となく世間体がいいというのはありがたい話ではあるんですけれども。
日本人がいなかった分野に飛び込めたということが非常にラッキーだったし、そういう機会をくださったDCMの創業メンバーがいたというのが、今の僕のベースになっているという意味では、人の出会いとかタイミングってすごい大事だと思います。
VC時代に経験した通信バブル
佐俣:それで10年やられて、WiLを立ち上げられるんですけど、やっぱりその「日本をもう1回上げる」みたいなところが大きかったんですか?
伊佐山:そうですね。もとの話で言うと、何でベンチャーキャピタルという業界に行ったかというと、1つはベンチャー企業、経営者に興味があったわけですよね。だけどキャピタルって、立場としては経営者とは同じではないじゃないですか。
ただ、経営者を支援する立場。しかもそれをお金という強い立場でベンチャーを支援できる。そこはおもしろいし、もともと銀行にいたぐらいだから、そんなに違和感がない世界だったんですね。
そこに入って目の当たりにした現場というのは、90年から2000年をピークに通信でのベンチャーがすごい増えて、2000年以降はインターネットという新しい産業が生まれて、そこにいろんな投資がされて、今度はソフトウェアが全盛の時代。
半導体とか通信みたいなハードの時代から、ソフトの時代に入っていった中で、DCMでいろいろアメリカのベンチャーへの投資をしたりしてたんですけど。
先ほど申し上げてた中国に投資して、中国ははじめほどんど半導体の会社とネットの会社だったんですね。半導体の投資はそんなにうまくいかなかったんですけど、ネットの投資は当たりまくって。
佐俣:そうですよね。もう伝説的な。
WiLを創業したきっかけ
伊佐山:すごい案件ばかりで、とにかく目の前をサバイブすることがすべてだったので、必死になって目の前の仕事をやってただけなんですけど、ある日突然「なんで日本ってここに入ってこないんだっけ?」と。
いろんな外国人が頑張ってやってるのは支援したんだけど、何で日本人ってこの中に全然出てこないんだろうっていうのが素朴な疑問としてあって。
佐俣:なるほど。
伊佐山:その思ったポイントというのはいくつかあって。事業をやってる人とか、応援してる人のプロファイルとかを見ても学歴がいい人もいっぱいいるんですけど。でも事業をやってる人も、雇っている人も、普通の人だったりするわけじゃないですか。
そういう人たちが、気づいたら大企業になって、上場企業の経営者やったりしてるのを見たときに、「何でそれが日本ではできないんだろう」というのが、ますます疑問に思えたんですね。
日本に出張して行っていろんな人に会うと、みんなセンスもあるし、頭もいいし、「世の中たぶんこうなるから、こういうの流行るんじゃない」って言ってることはすごいまともなわけですよ。
だけど世界的に見たときに、ベンチャーの中でそういう目立った経営者が日本人で出てきたかというと、ほとんどいない。
今日に至っても実際少ない。何でだろうという問題意識がすごいあって、わからなかったんですよね。日本には金がないからなのか、単純に終身雇用が強すぎるからなのか、学校がいけないのか、いろんな理由があるわけですけれども、何をすれば変えられるかってなかなかわからなくて。
僕がベンチャーキャピタルの仕事を、そこそこ理解できる、ワンサイクルをやるのにやっぱり10年かかったと思っていて、かつ日本の問題が何かというのをある程度見極めるまでに、10年必要だったと思うんですけど。結論は、やっぱり日本人ってすごい考えるのうまいんだけど、動けてないと。
つまり、動きやすい環境がないというのが、最大の問題じゃないかなと思って。じゃあ何をすると、冴えたアイデアを持ってる人とか、キャリアと頭の良さを持ってる人が動きやすい環境をつくれるのかなと思って始めたのがWiLの構想なんですね。
WiLはベンチャーキャピタルじゃない
佐俣:ここでWiLについてもっと深く伺っていきたいんですけど、すごい印象的なキーワードがあって「WiLはベンチャーキャピタルじゃない」と。これはすごいびっくりしたんですね。
僕はベンチャーキャピタリストで、ファンドがありきで、ファンドをいかに運用するかみたいなイメージがどうしても強くなるんですけど、伊佐山さんの中では、あまりベンチャーキャピタルと思ってないと。
伊佐山:はい。
佐俣:WiLは自分たちで何だと定義してるんですか?
伊佐山:WiLの創業メンバーは、西條と松本、私を入れて3人いるんですけど、基本的にやりたかったのは、何かをトライさせるべき人が、実際にトライできるような実験場をつくりたいというのが、そもそもの根底にあるんですね。
実験場というとちょっと語弊があるので、我々としては研究所(Lab)をつくろうと。研究所というと、サイエンティストが集まって、小難しいことを研究してて、こんなの商売になるのかなというイメージがあるんですけど。
佐俣:50年後、100年後の技術を黙々とやっているイメージですね。
伊佐山:もしくは何か技を自慢するためだけ、学会で発表するためだけに、大学の延長線上で博士が集まって会社の研究所でやってるというイメージが強いと思うんですけど。我々はそうじゃなくて、商用化・ビジネス化をもっと前面に出した研究所をつくりたいというのが、そもそもの発想なんですね。
佐俣:研究所をつくろうと。
伊佐山:研究所をつくろう。ラボって言葉が一番初めに僕の頭の中にはあったんですね。
佐俣:ファンドじゃなくて、ラボをつくると。
日本人が新しい事業にトライできる環境をつくりたい
伊佐山:ラボをつくったときに、どういうアプローチがあるのかなというのが、次のステップで、WiLを始めるときも、初めからファンドをパッとやる構想があったわけじゃなくて。
やっぱり人が何か新しい事業をやってみたいとか、世の中がこう変わってるから、自分の技術を使って、こういうことを実験してみたい、トライしてみたいと言ったときに、そういうトライができる環境をつくりたいというのがあったんですね。
ひとつのやり方としては、そういうやり方を教えてあげる学校をやるというアプローチがあると思ったんです。
佐俣:なるほど。
伊佐山:僕は学校が初めのアイデアだったんですよ。要するに、アントレプレナーの育成とか、イノベーションを仕掛ける人が、どうやったら仕掛けられるかということを教える学校をつくろうと。
佐俣:それは、日本人がそういうのをできるための学校。
伊佐山:MBAとか、グロービスさんがやっているような学校ではなくて、もうちょっと事業を立ち上げることだけに特化した学校で、うまくできたら、そこに投資して支援できたらいいなぐらいはあったんですけど。
佐俣:なるほど。それを聞くと、全然ベンチャーキャピタルじゃないですね。
事業化を支援するためには資金が必要
伊佐山:もともとは、そういう学校をやりたいというので。僕は自分自身がそうだったように、ある環境をつくってあげれば人は変われるはずだと。
佐俣:なるほど。
伊佐山:自分を見てみると、一介の銀行員がシリコンバレーに行って感化されて、これぐらいのことができるようになったわけだから、それなりのセンスがある人はできるはずだと。そのためには環境をつくらなきゃいけない。
そのためにはシリコンバレーに学校をつくろうということで、WiLのもともとの発想があるんですね。学校だけだと、やっぱり教育して終りで、本当にその人が事業を仕掛けるところまで、面倒を見きれないじゃないですか。受講してそのあと結局サラリーマンに戻っちゃう人もいるし。
佐俣:そうですね。いい勉強したって言って、会社に戻っていくみたいな。そうすると、やりたいことが違うわけですよね。
伊佐山:結局よくありがちな、MBA行ったのに何もやってない人と同じになっちゃうから、それはまずいなということで。次に考えたのは、やっぱりそういう人たちの事業化を支援できる具体的なインフラを持とうということで、そうするとお金を持たなきゃいけないんですよね。
佐俣:確かに。
伊佐山:「自分がお金を持って、やってみたら」というふうにできる構造をつくりたかったので、そこで初めて、僕が10年間やったファンドのビジネスモデルを使おうということで、お金を集めることにしたんですね。
佐俣:なるほど。
伊佐山:初めはお金集めも、金融ファンドとして集めてるというよりは、研究開発費を集めましょうというアプローチでやっていて。研究開発費っていろんな大企業が持ってるわけじゃないですか。
佐俣:はい。
伊佐山:それを1ヵ所にプールして、単純に研究開発だけに使うんではなくて、ビジネス化するということに使えたらおもしろいんじゃないかなと。
佐俣:なるほど。
伊佐山:そうするとさっき言った、人を教育して、その人たちがトライするときに、僕が初めの資金を提供するという、資本家として支援できる。それがうまくいったときには、出したお金はちゃんと回収されて、WiLの活動をどんどん大きくできるという、いい循環ができるなと。