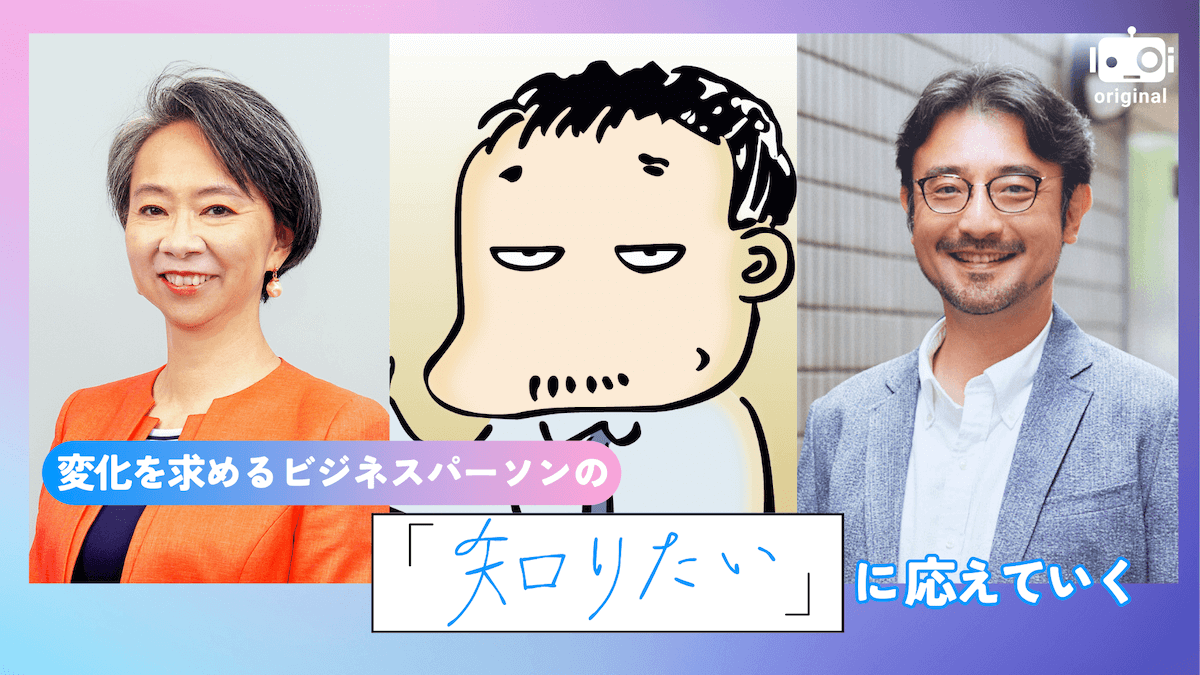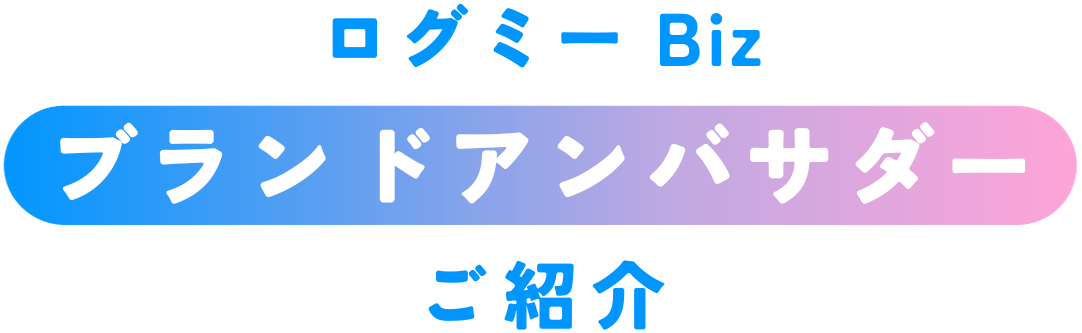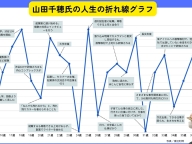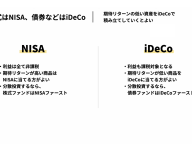1年かけて書いた想いを聞いてもらいたい
はあちゅう氏(以下、はあちゅう):はあちゅうです。よろしくお願いします。
(会場拍手)
今日はみなさまにもお伝えしたとおり、SHOWROOMの方と交互に行き来しながら始めていこうと思うので、よろしくお願いします。ちなみにSHOWROOM、今日初めてダウンロードされる方はどれぐらいいらっしゃいますか?
(会場挙手)
けっこういますね。たぶん、わかりづらいと思いますが、ぜんぜんわからなくても大丈夫です。ただ、今日会場にいらっしゃらない方のために、こちらでも配信していこうと思います。
今日はみなさんに、最初にお知らせしたいことがあります。いつもはすぐに言っちゃうんですけど、黙っていたことで。みなさんのおかげで本日重版が決まりました!
(会場拍手)
ちょうど発売から1週間が経ったところで。こんなことを言ったらあれですけど、どんどん重版をかけてくださる出版社もあるんですね。やっぱり重版をかけたってこと自体がニュースになるので。
最初、ちょっと少なめに刷っておいて「重版決まりました!」「また決まりました!」って言って、売れているふうに見せているところもある中、講談社さんは、けっこう初版の部数もがんばってくださったうえで、慎重に重版を重ねていくので。そんな講談社さんで、1週間で重版が決まったのは、みなさんの後押しのおかげです。
Twitterのコメントでも、Amazonでも「もしよかったら載せてくださいね」って今日呼びかけたら、すぐに書いてくださった方もいたので、それでまた買ってくれた人も増えたかなと思います。そういうことも伝えていただけると、すごくありがたいです。
今日はオンラインサロンのせっかくのイベントだから、いろんなかたちを考えたんです。ワークショップみたいにした方がいいかなとか、ちょっと授業チックにした方がいいかなとか、いろいろ考えたんですけど、中身のことに言及されずに勢いだけで広まっていったら嫌だなと思ったので。
今回この作品も1年かけて大切に1作ずつ書いて来たので、その想いなんかを、今日みなさんに聞いてもらう会にしたいなと思っています。まず私の方でお話しさせていただいて、そのあとに質疑応答をSHOWROOMと、リアルな会場の両方から質問を受け付けながらやっていきたいと思います。
「文章を書いているのに、小説から逃げている」
よく私、「なんで小説を書いたんですか?」と聞かれるんですね。ただ、私の中ではどちらかというと、「なんで」というより「やっと小説が書けたんだ」という気持ちが強くて。
私はずーっと小説を書く作家さんに憧れていたんです。小さい頃、2歳から「作家になりたい」と言っていたんですけど、やっぱりそのときにパッと思い浮かぶのは、お話を書く人、物語を作る人だったんですね。私もこういう小説を書きたいなって思って、中高生のときは自分でいろんな身近なものからヒントを得て小説風のものを書いていたんです。
それをいろんなネットだったり、文学賞だったり、そういうところに応募してたんです。でも、他の才能ある方と違ってなかなか引っかからず。
どこかの雑誌の編集長とかが私の書いたものを見て、いきなり「君は天才だ!」と言って連載を持たせてくれるみたいな、そういう夢のストーリーを自分で妄想しながら、いろんな編集部にメールを出してみたり、作品を送ったり、そんなこともしていたんです。でも、ぜんぜん当たらず。私には本を書く才能がないんだなって、ずっと思ってたんです。
そういったときに、同世代の作家さんがと若くして文学賞を受賞されている人を見て、「私はたぶん作家に向いてないんだ、諦めよう」「小説っていうのはたぶん、私の人生では、もう出てこないんだ」と思って、1回諦めたんです。
でも、そうやって諦めていたら、ブログというものに出会った。そのブログが意外とメディアの人に見てもらえて、書籍化することになって。そこから自分の人生を企画化して、本にしていくっていうことを大学1年生のときからずっとしていました。
1年に1冊ずつぐらい出しているんですね。だから、夢だった本をコンスタントに出せるようになって、すごくうれしいなっていう気持ちがあったんです。でもどこかで「小説から逃げてるな」という、うしろめたさもあったんです。
「作家になりたい」っていうのを小さいころから言っていたのも、やっぱり「小説を書きたい」という気持ちだったのに、「他の本を出して逃げてる自分がいるな」「文章から逃げているな」「文章を書いてるのに、文章から逃げているなっ」ていう気持ちがあった。
今年、フリーランスの3年目になって、いろんなことが夢みたいに叶いました。海の見えるお家に住むとか、自分でちゃんと稼いでいく、男の人に頼らなくても大丈夫なぐらいの収入を稼ぐとか、親を自分の家に住まわせてあげるとか、そういう夢見てた小さな暮らしの夢は叶っているんですけど。
でも、どこかで気持ちが晴れないなと思っていたときに「私は文章を書いているのに、小説から逃げてるな」と思って。どこかでやらなくちゃ、書きたいなっていう気持ちはあって、でもどうしていいかわからない。
逃げ続けてきた先で開かれた、小説への門
そんなときに、とあるお友達のイベントに行ったら、講談社の編集者さんが私に、「はあちゅうさんの小説を僕は読んでみたいです」って言ってくれました。ここらへんはいろんなインタビューでも書いているので、もしかしたらかぶっているとか、聞いたことあるという方もいらっしゃるかもしれないんですけど。
『FRIDAY』のグラビア担当の方が、「僕はグラビア担当マンだからなにもしてあげることはできないけど、同期に僕の知っている編集者さんがいるからそこに繋ぎます」って言ってくれて。ただ、繋いでくれたというか、メールを書いてくれたみたいなんですけど。そんなに『群像』の本の門は放たれているわけではなくて「サンプル原稿を書いてください」と言われたんですね。
私は今まで、どこにあるかわからなかったドアがちょっとでも見えて、そして開いたから、もうそこに飛び込むしかないと思ってすぐにサンプル原稿を書いて送ったんです。
でも、送ってもなかなかレスポンスが返ってこなくて、「今ちょっと担当編集者が忙しいみたいで」ということで1ヶ月待ったんですね。1ヶ月経ったら、そこで「読ませていただきました。これだったら掲載させていただいて大丈夫です」ということで、お返事をいただきました。
打ち合わせに行って、それで「あと2作品書いたら、載せられるボリュームになりますよ」ということで、3作品書いてようやく載ることができたんですよね。それが今年1月です。3作品で、純文学というずっと逃げていたものからやっとデビューできて、そこから「本にしましょう」と群像さんが言ってくださって何作も書きました。
ここに載ったのが7作品なんですけど、本当はあと2つ書いたものがありました。それはボツになっています。まだぜんぜん書く力が足りなくて、今回書いた7作品とも、自分の中で小説になっているかどうかが一番わからなくて。「小説を書く時に一番大変だったことってなんですか?」ってよく聞かれるんですけど、私は小説がなにかわからなくて、すごく困りました。
こんなに人生で何冊も何冊も誰より本を読んできたと思っていたのに、自分で小説を書く時ってこんなに難しいんだということに、すごく戸惑いを感じて。
今回の7作品は、すべて自分の実体験だったり、出会ってきた人がベースになっていたりするんですけど、それを書くことははたして小説なのか、それとも自分のあったことをただ書いているだけなのかが、よくわからなくなってしまって。
小説というものは一体なんなんだろう。と書いている間ずっと毎日、考えていました。
もしよかったらみなさんも、今日ここで手を挙げて教えてくださいみたいなことはしないんですけど、「小説ってなんだと思いますか?」ということを、持ち帰って考えてみてもらいたいなと思います。これは、ただ私が聞きたいだけなんですけど。
小説とは「ラストで主人公に少しでも前へ進んでいるもの」
私、燃え殻さんっていう、今、彼の著書である『ボクたちはみんな大人になれなかった』が売れに売れている作家さんと1回ご飯を2人で食べに行ったことがありました。そこでまさに私が書いていたときに、燃え殻さんも小説が出るちょっと前だったので「小説ってなんだろうね」っていう話をしたんですね。
そうしたら、「最初と終わりで主人公が少しでも前に動いていること、感情が少し変わっていること、それは良い方向に変わっていても、悪い方向に変わっていてもよいけど、なんらかの動きがあったことが小説じゃないか」ということを燃え殻さんと一緒にしゃべって、その言葉をずっと頼りに書いていた気がします。
どの作品も、すごく大きな変化がドーンとあったりとかするわけではないと思うんですけど、主人公がちょっとだけ前に進んだっていうのを自分なりに考えながら書きました。
今から1作ずつ、どんなことをモデルにしたかみたいなことを話していきたいなと思うんですが、『世界が終わる前に』っていう1作目の作品。これは講談社の特設サイトにも書いたことなんですけど、これが一番最初にサンプル原稿として群像さんに送った作品なんです。これは私が香港大学に留学している時の話と、その時あった話をだいぶ美化して書いています。
実際にあったことは、私は実際に台湾系アメリカ人の人と出会って、恋をして、3年間お付き合いをしたんです。しかし、彼が本当にあちら側の世界に行ってしまって、ただ私はずっと付き合っているときからそれに気づかなかったんです。
彼はすごく威勢のいいことを言うんです。「世界を変える」「自分はこうやって生きていきたい」ということを熱を込めて語るので、すごくパワフルな人だなって、こういう人の近くにいたら元気をもらえるなと思っていました。
そこが好きだったんですけど、彼は卒業後の進路に失敗してしまって、自分を追い詰めてしまって、コミュニケーションがとれない人になってしまって……っていう、ちょっと湿っぽい話になってしまうんですけど。
ただ、私はその彼が向こうに行っちゃってからも何度か会っているんですけど、会っていると普通なんです。「この人は本当に精神科の治療を受けているのかな」「深刻な精神の病気って本当かな」っていうことがよくわからなくて。「この人が狂っているというのなら、私もたぶん狂っているんだろうな」と思っていました。
すごく今って、心の病んだ人は向こう側に行っちゃった人、私たちはまだ正常な方にいる人みたいな感じで、境界線があるような感覚にとらわれることがあると思うんですけど。でも、実際は自分だって一歩踏み入れていたり、踏み入れていても気づかなかったりします。あまりそこの境界線ってないんだろうなって思ったので、そのことを表現したくて書きました。
思い入れのある悲しさ、思い入れのない悲しさ
3つ目の『妖精がいた夜』に関しては、これを好きだと言ってくれる方が取材者の方とかネットの方とかで多いんですけど、実は私の中で一番自信のなかった作品です。なので、これが好きだって言ってくれる人が多いのが不思議な感じがします。これは原稿としてまとまっているのかよくわからなくて、見切り発車で編集者さんに投げたらOKをもらえて「あ、よかった、ラッキー」って思ったぐらいの感覚だったんですけど。
元になっているのは、高校生の時に同じクラスの男の子がいたんです。彼はすごくカッコよくて、女の子の憧れで、私からは遠い人だと思っていたんですけど、あるときクラスの席替えで前後になったんです。
その前後になった時に、私は彼の下の名前を知らなかったんですけど、向こうは私の上の名前も下の名前も覚えてくれていて、それがすごくうれしくて「この人とすごく仲良くなれそう」って思ったんですね。
仲良くなれそうって思ったんですけど、やっぱり向こうはクラスの人気者で、こちらはどっちかというと控えめなキャラだから、私がガツガツと話しかけて「周りの人にみじめだって思われるの嫌だな」「気があるって思われるのもすごく恥ずかしい」って思って、すごい遠慮して話しかけずにいて。
そのまま何事もなく私たちは高校で次の学年にいき、クラスもバラバラになって、別々の大学の学部でお互いに別の大学生活を過ごしていて、なんの接点もなかったんです。だけどある時、彼がもう就職も決まっていたのに交通事故で死んでしまうっていうことがあって、私、その時に高校のあの席替えの前に話したことがあるだけなのにすっごく悲しかったんです。
もう死んでからだいぶ経ってからそのニュースを聞いたにもかかわらず、2日間ぐらい「彼と会いたいな」「彼の魂はここらへんにウロウロしてたりとかしないかな」と、すごく不思議な感覚になっていました。その話がこうなりました。
……って言っても、どうしてこの小説ができたのかわからない人もいると思うんですけど。思い入れがあるからこその悲しさというのもあるし、思い入れがないけど悲しいというのもあると思うんです。