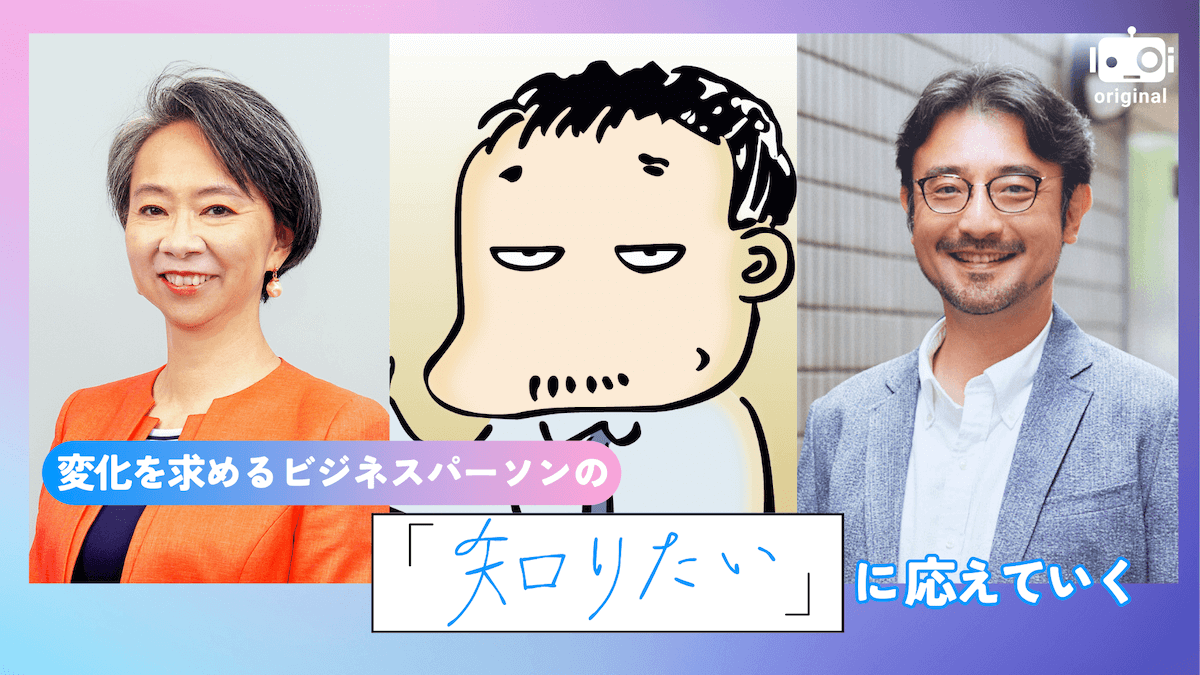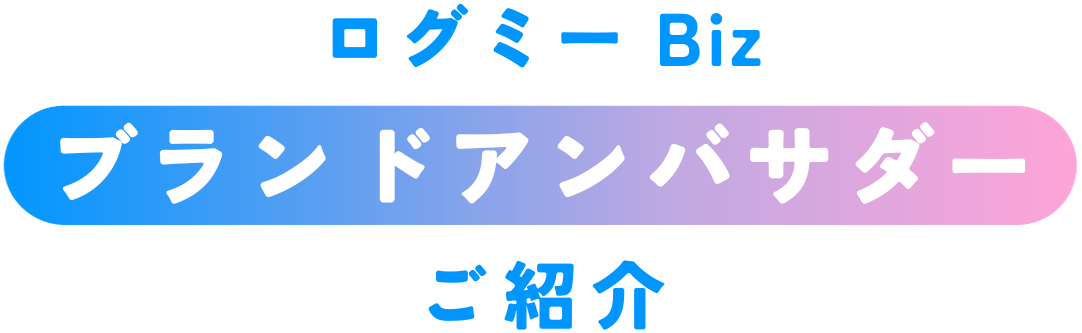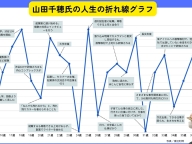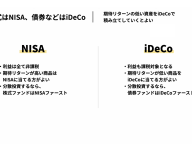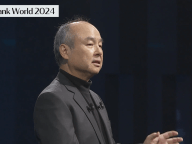なぜ灘では「幾何」に1年かけるのか?
――本日はよろしくお願いいたします! お2人は「灘中→灘高→東大法学部」という典型的なエリートコースを歩んでこられた先輩・後輩とのこと。
文部科学大臣補佐官である鈴木さんは「制度面」から、企業研修講師としてもご活躍の津田さんは「ビジネス面」からという違いはありますが、まずは「教育」に対する問題意識をお聞かせください。
津田久資氏(以下、津田):鈴木さんとは灘中・灘高の先輩・後輩関係なのですが、こうしてじっくりお話しさせていただくのは今日が初めてなんですよね。本日はよろしくお願いします。
鈴木寛氏(以下、鈴木):はい、よろしくお願いします!
津田:せっかくなのでまずは「灘高」の話から。今回書いた『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか』という本を、灘時代の同級生に送ったんですが、そのときに「僕らが灘で受けた教育というのは、大学入試という視点だけから見ると、おそらくかなりオーバースペックだったんじゃないか」というメッセージを添えたんですよ。
鈴木:ええ、オーバースペック。それはそのとおりだと思いますね。
津田:その友人というのも、鈴木さんと同じくいま大学教授をやっていて、普段はいわゆるビジネス書をほとんど読まないんですが、彼も「その通り。灘の教育はオーバースペックだった!」と言っていました。
本書では、「考える能力が欠けていて、学ぶ能力だけに偏っている人材」を「東大卒」とシンボリックに表現したわけですが、これはもちろん東京大学という特定の大学だけを批判する意図はありません。
一方で、変な言い方ですが「灘高型エリート」というものがあるとすれば、それは「東大卒」的なイメージからはかなりかけ離れていると思いませんか?
鈴木:おっしゃるとおりですね。灘のロールモデルというのは、津田さんの言葉を借りれば、まさに「思考する野蛮人」ですよ。もちろん、「大学入試なんて戦略的にやれば簡単だ」とか「数学は暗記だ」と主張している灘の出身者もいますが、実際に行われている教育はまさにオーバースペックで、「受験に最適化されている」とはおよそ言いがたいですよね。
たとえば私が灘にいたころ、中2の数学では「幾何」しか習いませんでした。1年かけてずーっとひたすら幾何を学ぶんです。幾何なんてたいして入試に出ないんですが、あれがよかったと思いますね。灘高生の「思考力」を鍛え上げているのは、あの幾何を重視する伝統だと思います。
津田:僕が受けた授業もまったく同じでした。しかも当時使われていた幾何の教科書って、えらく古めかしいガリ版刷りじゃなかったですか? 市販の教科書ではなかったと記憶しています。
鈴木:そうそう、きっと旧制高校時代の教科書をそのまま使っていたんじゃないですかね。私のころにはまだ東京高等師範学校(現在の筑波大学の前身)とか帝国大学(現在の東京大学の前身)を卒業された先生方がかなりいました。彼らがやっていたのは、まさに旧制高校時代の教育なんだと思いますね。
津田:日本でかつて最も優れた「考える」教育がなされていたのは、じつは旧制高校だったんじゃないかと僕は思っています。
灘は数学の時間でも、徹底的に「証明」をやりますよね。証明ができるかできないかというのは、まさに論理的思考力の有無に直結しますから。
今でも覚えていますが、いきなり定理の証明をやるのではなく、ユークリッドの『原論』みたいに、公理から見ていくんですよ。「1つの直線とその直線上にない1点が与えられたとき、その点を通りかつその直線と平行な直線は1つ存在する」というようなところからやりましたから。
鈴木:期末試験も定理の証明問題がメインで出題されていましたね。そうやって「考える」土台をつくる教育が構築されていたと思います。
定理をつくり出す人が勝者になる
津田:僕はふだん企業研修なんかをやっているんですが、ビジネスの世界というのは数学とは違って「定理」みたいなものがないですよね。数学みたいに普遍性がある理論はまず存在しない。
鈴木:なるほど。
津田:ですから、実務においては自分なりの定理とかフレームワークをつくれないといけないんです。でも、なかなかできる人がいなくて、他人がつくった理論とかフレームワークを鵜呑みにしている。だからケーススタディをやらせても、そういう枠組みに当てはめて、なにかを考えた「気分」になって終わってしまっている人がほとんどです。
鈴木:まったくそのとおりですね。それは霞が関のエリート官僚たちを見ていても感じるところです。
他人のフレームを使うにしても、結局のところ、その根本にある原理原則・基礎基本が「なぜそうなっているのか」がわかっていないと、いざというときにプロダクトイノベーションができないんです。
今は「先行者利益」の時代ですから、後追いでは勝てない。工業化社会のときには、すでにある製品の生産性を上げるとか、不良品率を下げるとかいったプロセスイノベーションでもよかったんですが、今は違います。新しいプロダクトをいち早く生み出した人間が総取りする、“winner-takes-all”の時代なんですよね。
津田:おっしゃるとおりです。プロセスイノベーションって、言ってみれば改善ですから、本来のイノベーションとは呼べないと思います。
鈴木:日本のイノベーションのほとんどはプロセスイノベーション、つまり改善で終わっているから、なかなか競争力が保てなくなってきていますよね。
灘高のエリート教育はなぜ「言葉」にこだわるのか?
津田:じゃあ、表面的な改善で終わらせずに、原理原則までどうやって立ち戻るのかという話になると、やはり「言葉」の力が必要になるというのが持論です。
鈴木:それはまったく同感ですね。
津田:企業研修に出てくる社会人たちと話していると、本当に言葉がいい加減なんです。
鈴木:そうですか。
津田:「グローバル」とか「ソリューション」とか、外来語がいっぱい出てくるんですけど、「それってなんなの? ソリューションと解決ってなにがちがうの?」と聞くと、モゴモゴ言っていてはっきり答えられない。
鈴木:「言葉の意味」という話でいえば、灘高には国語の森本先生という方がいました。森本先生は本当に「言葉」にうるさかったですよね。言葉の意味がしっかり言えるまで、30分も40分も立たされている生徒がたくさんいたのを覚えています。
津田:僕も森本先生には個人的にご自宅で「古文」を習っていました。古文を日本語に訳していくんですが、わからない部分を勝手に想像して訳したりすると、ものすごく叱られた。
「国語というのは、いい加減に想像してものを言うことと違うんや。君らはまず言葉の意味がはっきりわかってへん。勝手に想像するな!」って。
鈴木:どやされましたよね(笑)。だから先生に指された生徒は、本当にひと言ひと言、言葉を選びながら答えていました。必死で頭をフル回転させてね。
あの授業というのは「どれだけ正確な言葉・表現を使うか」という点でものすごく鍛えられましたし、いま私が政治家や官僚と仕事をするなかでは本当に役に立っています。
津田:そうでしょうね。
鈴木:似て非なる言葉の違いを、境界線をきっちり引いてちゃんと言い分けられないといけない。まさにdefinition(定義。語源は「境界線をはっきりさせること」の意)ですよ。
仕事というのはやはり「言葉」の力がすべてのベースなんです。高校時代、先生はよくこうおっしゃっていました。
「君らはこれから東大に入って、将来は弁護士とか国家公務員になろうと思ってるんやろ? 言葉遣いがいい加減な連中が、人を弁護したり判決・法律を書いたりしたら、人の命に関わる。無罪の人が有罪になるかもしれん。言葉をおろそかにしたらあかん!」
私大文系より旧帝大の試験のほうが優れている!?
――ひと口に教育と言ってもいろいろありますが、なかでも知育の部分では「“学ぶ”から“考える”へのシフト」がカギになってくるというのが津田さん『東大卒』本のご主張だと思います。
鈴木さんは文科相補佐官というお立場にあって、そのあたりはどうお考えなんでしょうか?
鈴木:国のレベルでも問題意識はまったく同じですよ。かなり前から「学習指導要領」でも思考・判断・表現の重要性を謳っています。謳ってはいるのですが、国が言うだけではなかなか変わりませんね。
学校の現場でも「思考力・判断力・表現力を養おう」という意識を持って熱心に指導している教員というのは、全体の5~10パーセントじゃないでしょうか。依然として「考える」はメインストリームとはならず、まだ「学ぶ・覚える」偏重なのが現状です。
津田:なにがボトルネックになっているんでしょうか?
鈴木:それはもうはっきりしていて、なによりもまず「大学入試」です。いまの入試がある限り、どれだけ細かい部分を改革しても難しいでしょうね。
だからこそ「本腰を入れて入試改革をやろう」ということになり、下村前文部科学大臣が、私を今年(2015年)2月から文部科学大臣補佐官に任命されたというわけです。
津田:大学入試がダメというのは具体的には?
鈴木:もちろん全部が全部ダメというわけではないですよ。たとえば東大の「国語」とか「世界史」「日本史」「政経」、あと京大の「数学」、このあたりの入試問題はすばらしいですよ。これは世界に出しても恥ずかしくない水準で、海外の入試問題にまったく引けを取りません。
津田:なるほど。ただ、いくら問題がすばらしくても、受験生側が本当に「考えて」解いているのか、それとも傾向と対策を「学んで」いるだけなのかは、かなりあやしいと僕は思っていますが。
鈴木:そういう側面はあると思います。でも、もっと問題なのは……「私大文系」なんです。
もちろんここで言う「私大文系」というのは、津田さんの本で言う「東大卒」と同じでシンボリックな表現でしかありませんが、とにかくマニアックな知識を問う難問・奇問を出す大学がかなり多い傾向にあるのは事実です。しかも、そういう大学ほど受験者数が多かったりするから、影響力が大きいんですよ。
「世界史」とか「日本史」の試験を見ても、山川の『用語集』の脚注にしか書いていないようなことが出題されている。こういう試験のためにの勉強をしようとすると、どうしても単なる知識の詰め込みになるし、膨大な時間を奪われてしまうんです。
津田:どうしてそんなことになってしまうんですか?
鈴木:それはシンプルで「落とすための試験」だからですよ。つまり、みんなが満点をとってしまうと困るから、「差」をつけないといけない。だから一部の学生しか答えられないような難問・奇問を入れざるを得なくなる、と。
津田:そうなってしまうそもそもの元凶は、マークシートの選択方式ですよね。論述式にすれば、変な問題を出さなくてもちゃんと差はつくはずですから。
鈴木:そのとおりです。ただ、論述式というのは学生に敬遠されるんですよね……。
津田:なるほど。それだと大学が儲からない、と(笑)。
鈴木:ええ。たとえば、近畿大学、明治大学、早稲田大学は11万人以上の受験生が受けるんです。一方、慶應大学の経済学部なんかだと小論文があったり、数学があったりする。
もちろんこのほうがいいんですけど、慶應の受験生が一挙に減ってしまう。4万人くらいなんです。つまり、7万人に敬遠されるということは、ざっと見積もっても20億円の受験料収入を失うってことなんですよね。
津田:なるほど。大学経営とも結びついた根深い問題ですね。
鈴木:ただ、その犠牲になっているのは、学生たちですよ。そういう試験を出す大学を受けるかどうかで、受験生時代の勉強法が決定的に違ってくるんです。ここで詰め込み式の勉強に時間を奪われるのは本当にもったいない。覚えることが多すぎて歴史が嫌いになる人って、かなりいるんじゃないかな。
僕が灘高時代に「世界史」を習った誉田先生は「年号なんて覚えなくていい。東大は論述なので年号を忘れたら『18世紀半ば』とかかいておけばいい」とよく言っていました。「ただ、歴史というのは『Aという事件がBを引き起こして、Cという事件が起きる』というつながりなので、順番とか流れはつかんでないとあかん」と言われていましたね。
だから私はいまでも世界史が大好きなんですよ。歴史そのものを暗記ものだと思っていないですから。
「暗記型」人材の問題はビジネスの現場にも連なっている
津田:当たり前のことかもしれませんが、ビジネス教育の現場にいても、「暗記型」人材の問題はずっと続いていると感じますね。フレームワークを覚えて満足している人だとか、そこに当てはめて答えを出している人だとか。
たとえば、プロダクトポートフォリオマネジメント(PPM)っていうビジネスフレームワークがあります。これはボストン コンサルティング グループ(BCG)がつくったものなんですけど、僕がBCGにいたときはそんなもの使ったことなかったし、同僚の誰かが使っているのも見たことがなかった。
なぜかというと、いまの環境に合わないので使えないんですよ。でも、PPMそのものは長らく「一人歩き」の状態が続いていて、なぜかいろんなところで「学び」の対象として言及されているわけです。
鈴木:「考える」力がない人が、自分をカモフラージュするために、そういうもので武装した気分になっているという側面もありそうですね。
津田:ええ(笑)。ところが、同じビジネススクールでも、ハーバードビジネススクールというのは逆で、「学ぶ」ためのレクチャーをやらないわけです。ケーススタディをとにかくやる。「考えろ、とにかく考えろ」というわけです。
これがなぜか日本に持ってくると、同じビジネススクールでも似て非なるもの、「お勉強」になってしまう。
鈴木:ビジネススクールというのは「考えるための場」のはずなのに、「学ぶための場」にすり替えられてしまうわけですね。そこにはまさに大学入試の呪縛があるように思います。
津田:そうなんですよ。前回、藤原和博さんと対談させていただいたとき、僕の本(『あの人はなぜ、東大卒に勝てるのか』)を読んでくださって、「この本が3万部以上売れるんなら、日本も捨てたもんじゃないと思った」と言ってもらえたんです(笑)。
藤原さんなんかもやはり「暗記型人間」「マニュアル人間」が圧倒的に多いということを非常に危惧されているんですよね。
鈴木:それはすばらしい! そういう人のなによりもの問題点は、既存のルールを破壊できないことですよね。破壊的イノベーションを起こせない。霞が関の役人たちを見ていても、もどかしく感じることは多々ありますよ。
「間違いだらけ」でも司法試験をトップ通過できた理由
津田:政治でも「憲法によって規定された権力」と「憲法をつくる権力」は違います。イノベーションというのは結局、憲法をつくる権力のようなものですよね。
たとえば弁護士でも、「判例をつくる弁護士」と「判例に当てはめて結論を出す弁護士」という2つのタイプがいると思います。この2つというのはまったく違う。
鈴木:ぜんぜん違いますね。「判例をつくる」というのは、ものすごくクリエイティブであることが求められます。もう10年以上も前ですが、大学時代の恩師が東大法学部長時代に憂いていました。
「本来、裁判官というのは『これまでにない問題』に対してきわめて洗練された答えを出す仕事であり、それが判決というものなんだ。だから昔の裁判官は、本当に考えて考えて考え抜いて判決文を書いていた。
しかし、昨今の裁判官は、過去の判例からパターン的に判決を導いているような風潮がある。これをなんとか変えないとまずいことになる。法科大学院では『徹底的に考える法曹』を育てたい」と。
津田:今の話で思い出したんですが、東大法学部の先輩で、昭和50年代に大蔵省にトップで入ったものすごい秀才がいました。
彼は司法試験もトップの成績で通ったんですが、試験のあとにどんな答案だったのかを、みんなの前で再現してみせてくれたんですよ。
それを見せてもらった同級生たちは、あっと驚いてしまった。なぜかというと、彼が答案中で引き合いに出している判例にはけっこう間違いがあったんです。
鈴木:つまり、暗記に関してはかなりあやふやだったと(笑)。
津田:そうなんです。しかし、答案そのものはとにかく徹底的に考えて書かれているので、論理性が非常に高い。だから知識が間違っていても、司法試験でトップになれたというわけなんですね。
当時の東大では、司法試験をいかに効率的にクリアするかという風潮があったんですが、彼の答案を見たことで「そうか、日本の法曹界が望んでいるのはこういう頭脳なんだ」とみんなの認識がガラッと変わりました。だから、その再現答案を見せてもらった人たちは、みんな翌年の司法試験に受かったそうです。
鈴木:それはいい話ですね。
津田:そういう意味では、現状の司法試験だとか東大入試でも、結果が同じ「合格」なのだとしても、本当は2通りいるはずなんですよ。覚えたことをアウトプットしているだけの人と、思考力を働かせながら問題を解いた人。試験の段階では同じ結果でも、社会に出てくるとその差が一気に目立ってくるように思いますね。