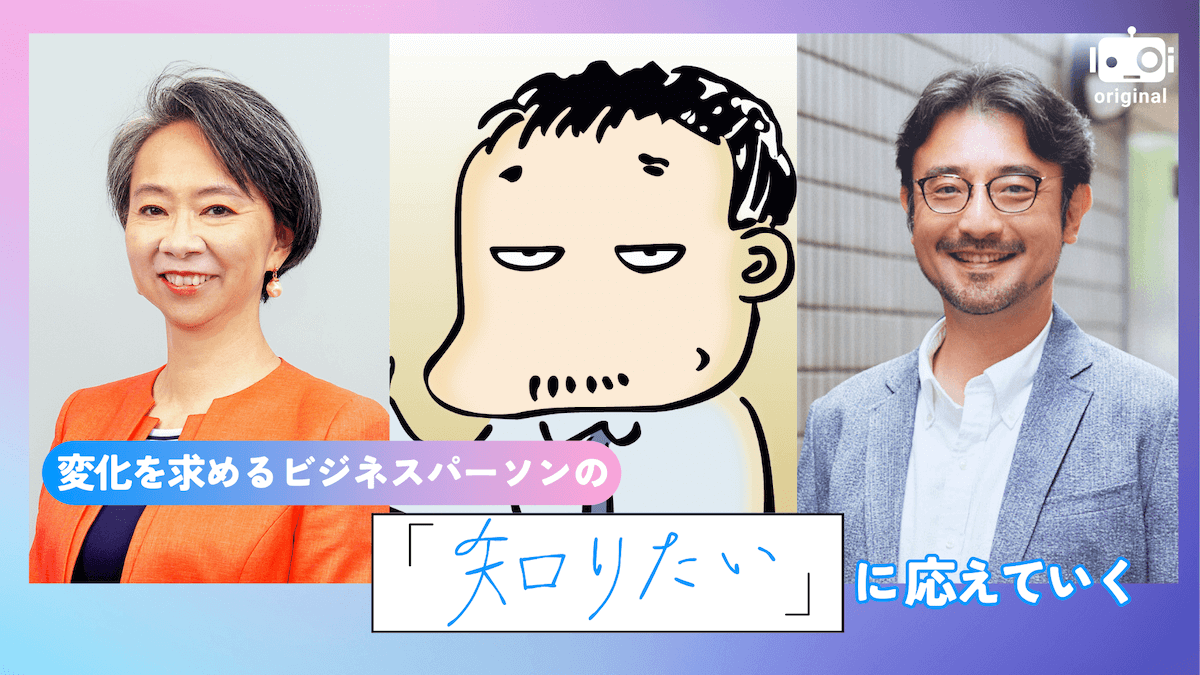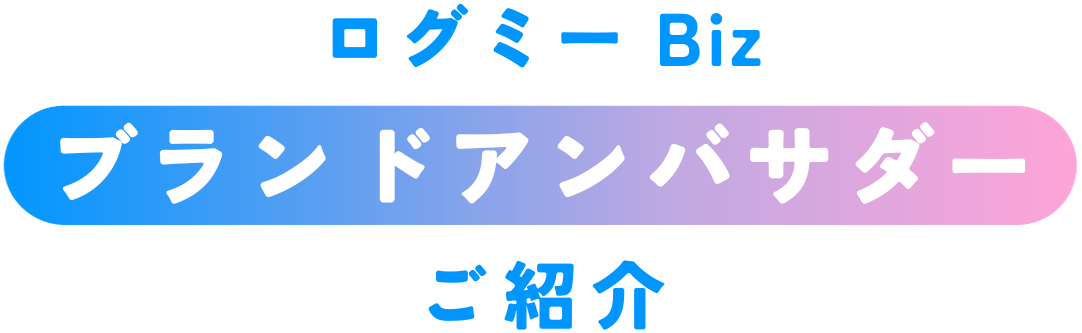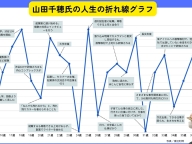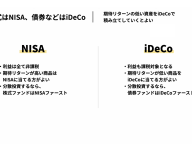新しい日本人の文化をことごとく押さえる謎の企業
宇野常寛(以下、宇野):グッドスマイルカンパニーって、フィギュアを中心にアニメやゲームといったコンテンツビジネスに進出している会社といったイメージが一般的だと思うんですね。でも、僕の見立てでは、安藝さんはもっと広い意味での「文化」を作ろうとしているように思えて仕方がないんです。
例えば、いま僕が20代、30代に向けた若い「BRUTUS」のような雑誌を作ろうとしたら、単にグッスマがやっていることを全ジャンルフォローして行くと思うんですね。アニメ、ゲーム、ホビー、自転車、アウトドアグッズにガジェット系、それにアイドル……これって、実は20代~30代の若い文化系男性の必修科目で、それをグッスマが片っ端から押さえていっている印象があるんです。
安藝貴範(以下、安藝):そう言って下さると、嬉しいですよ。自分でも何をやってるのか分かってないんで(笑)、自信がつきますね。
宇野:たぶん、安藝さんが好きなものは、みんな好きなんですよ。僕が思うに、そうやってグッスマが押さえているものって、実は戦後の中流家庭の人たちが考えてきた「文化」とは違う、新しい文化のスタンダードに近いものという気がするんです。 去年出した『日本文化の論点』という新書で、僕は「新しいホワイトカラーが都市部を中心に登場してきた」という話を書いたんです。彼らはテレビを見ないし、百貨店でモノを買わない。情報の収集は基本的にネットで、ECサイトでの購入が多い。服装もアウトドア系がなぜか好きで、自転車やスニーカー集めが趣味で、ガジェットが大好き。
安藝:僕の生活スタイルですね(笑)。でも、僕が知ってる外国の一線級のアーティストの連中も、ほとんど一緒ですよ。
宇野:たぶんこの10年くらいで、IT業界を中心に米国の西海岸的な文化を日本的に受容する動きがあるんだと思います。おそらく、昭和のサラリーマンが米国式のライフスタイルを受容する中で、東京を西に延長しながら戦後的中流文化にローカライズしていったのと同じように、これから西海岸文化のローカライズがはじまっていくのだと思います。そしてそのポスト戦後中流文化になっていきそうなジャンルをことごとく押さえている謎の企業が、グッスマです(笑)。
安藝:はっはっは(笑)。僕らのやっていることは、そういう文化の表層でしかないですが、きっと掘り下げていくと色んなものが出てくるんじゃないですか。深いところで繋がっていますよ。
"オーバースペック"という新しい美学
宇野:例えば、アウトドアの服にしても、普通に東京でデスクワークをしている人間には、本当は「異常に丈夫な服」とか絶対に必要ないはずなんですよ。
安藝:「これを着てると、全然寒くないんだぜ」みたいな服もあるよね(笑)。
宇野:これは過剰なスペックへの「萌え」みたいなもので、一つの新しい文化と見てよいと思うんです。ああいう20代~30代のカジュアルなオタクセンスって、僕の周囲のホワイトカラーに凄く広がっているんですが、何か昔の銀座の「ゴルフ文化圏」的ものの次になり得る予感も僕にはあるんです。
安藝:確かに衒いなくオーバースペックを求めるのはありますね。実は今度、変形するヘッドフォンを作ってるんです。
宇野:へええ。ヘッドフォンですか。
安藝:いま、ヘッドフォンが面白いんですよ。iPhoneのお陰でみんなが音楽を持ち歩くようになって、ヘッドフォンへの需要がファッションアイテムの一面もあって高まってるんです。その人気の先駆けになったのが「Beats」で、いま世界中の若い子たちにとって、あの「かっこいい」ヘッドフォン持っているのが、ある種のステータスなんです。
Beats by Dr.Dre beats studio ノイズキャンセリングヘッドフォン ブラックカラー BT OV STUDIO V2 BLK(amazonへ)
安藝:商売としても大きくなっていて、一個3万円するものもあるのに一ヶ月に10万の桁で売れることもあるらしいです。一ヶ月に3万円×20万個だと仮定すると、60億ですよ。
実はいま、日本のFostexさんっていう凄腕の音響メーカーさんが、自分たちのブランドでヘッドフォンを作ろうとして、グッドスマイルカンパニーに声かけて下さったんです。それで考えたのが、「トランスフォーミング・ヘッドフォン」というもので、さっきも言ったように変形するヘッドフォンですよ(笑)。
もうね、これを作るのに下町の技術からなにから寄せ集めてます。昔のガラケーに、SONYのわけわからない変形をするヤツがあったじゃないですか。その辺の職人さんたちなんかも呼んできて、複雑でもスムーズネスがあって、しかも強度も両立させるようなヒンジ設計をしてもらっています。音についても、一般的なものでは10万円クラスであろうと言われるドライバーが入っていて、チューニングも最高です。4万円前後くらいで販売するつもりなんですが、これにGizmodeさんがが凄く良いタイトルをつけて紹介してくれたんです。
GEEK JAPANを代表するプロダクツになるかも?グッスマ×フォステクスの可変ヘッドフォン : ギズモード・ジャパン
宇野:なるほど、「ギークジャパンを代表するプロダクト」。
安藝:いや、良いタイトルでしょう(笑)?
これを今度、Linkin Parkのジョー・ハーンと一緒に展開します。今、そのチューニングセッションのために、スタッフがロサンゼルスに行ってます。更にこのプロジェクトには、グラミーアーティストなんかも興味持ってくれてます。Skrillexって知ってます? ダブステップで今一番人気があるアーティストなんです。
安藝:カップスタックという遊びで米国の女の子が新記録を出した瞬間の声をYouTubeからサンプリングして曲の冒頭に使っちゃったりして、話題づくりも上手い。グラミー賞ホルダーです。
宇野:あ、ニコ動的な感じなんですね。
安藝:そうそう、「キーボードクラッシャー」みたいな。YouTubeを上手く使うアーティストで、全米を席巻してます。その彼が『ブラック★ロックシューター』のhukeくんのアートを凄く気に入って、彼らがとっても仲良しなんです。Skrillexのキャラクターをhuke君がデザインしてみたり。彼らの協業もこれから実現したいと思っています。
skrillexのPVは爆発的な再生数です。1億5000万再生とかされてるわけです。そうすると、hukeくんとのコラボPVとかあったら凄い認知が広がるなぁと……夢が広がりますよ! こうやって、だんだん色んなものが繋がっていくんですよ。
「日本のスーパーアニメーターはワンカット8000円」
宇野:いまのお話は西海岸的なギークカルチャーのグローバル化に対して、日本のオタクカルチャーがどう応答していくかという話でもありますね。
安藝:いやもう、その二つは混ざります。日本のローカルなオタクカルチャーが、外国人は大好きなんですよ。最大の発信源である西海岸の人たちが、特に大好き。Skrillexもそうですが、みんな東京で何かやりたがるんです。日本に来ても、京都に行かないですからね。ひたすら秋葉原や中野、浅草なんかを回ってますよ(笑)。
宇野:社会学者の知人が香港にいるのですが、彼がこの間、「東京の人たちは、東京の西側に文化があると思っている。それは外国からみたら大きな間違いで、外国人にとっての東京は、やはり浅草と秋葉原と銀座とビックサイトである」と言っていたんですね(笑)。つまり、昔ながらのスキヤキ・フジヤマの日本と、クールジャパンのサブカルチャー・ジャパンの二つにしか彼らは興味がなくて、それは東京の東側の文化なんだ、と。
いま西海岸的なギークカルチャーがインテリ層へと世界的に広がっている中で、それを一番ホットに打ち返せる場所の一つが東京の、それも東側なのだと思うんです。僕は21世紀前半の日本が新しい文化を発信できるのは、この文脈しかないとさえ思うんですよ。
安藝:そういう意味では、ロサンゼルスとのマッチングがまだうまく行ってないかもしれませんね。ハリウッドがあるので、どうしてもエンターテイメントはそこで完結してしまうんです。でも、アパレルやアートの人たちは、非常に東京に注目していますね。
実は僕らもロスに数百坪くらいの大きなウェアハウスを借りていて、そこに一流どころの絵描きやミュージシャンなんかが集まっているんです。でも、彼らと遊んでいると、なんかこうちょっと"嫌な気分"になるんですよ。
というのも、基本的には普通のヤツラなんです。会話の節々や人柄、そして作品にカリスマや天才性は大いに感じられるんですけどね。でも、日本に帰ってくると、彼らのような、いやもしかしたら彼ら以上に凄い連中が、普通にフィギュアの原型を作っていたり、アニメの世界でLAの絵描きとは段違いのギャラで絵を描いていたりするんです。かたや絵を一枚何千万円で売ってる連中がいるのに、相変わらず日本のスーパーアニメーターはワンカット8000円ですよ。
これ、僕にもどうしたらいいか答えがないですね。一時期、もう少しアート寄りに作品の価値をつけた方がいいのかと悩んだりしたけど、それも違っていて……。
宇野:例えば、そこに竹谷隆之さんのフィギュアがありますよね。彼は一部の日本人にしか知られていないけど、現代日本における最大のアーティストですよ。将来的には絶対に名前が残る人だと思うんです。
安藝:いや、本当に大天才ですよ。他に匹敵する人はいるのかな……。
宇野:S.I.Cの初期に、竹谷隆之の造形が3500円とか売られていたでしょう。当時、こんなことが許されるのかとびっくりしましたね(笑)。この3500円のフィギュアが、もし世界中のトイザラスで売れたらと思うんです。そのとき、きっと彼の制作環境は今の10倍どころではなく良くなる。
安藝:彼のような作家に、しっかりしたギャラリーがつけば……ただ、竹谷さんの場合は、そもそも値段をつけることに興味がなさそうですね。「その値段で!」とびっくりするような額を聞いたことがあります。
宇野:いや、竹谷さんの一点物が買えるんなら、僕はいくらでも出しますよ。僕は生まれ変われたら、ホビージャパンの撮影スタッフになりたいと思ってますからね。そうしたら毎回、竹谷さんの造形を撮影できるじゃないですか。
安藝:別に今からでも竹谷さんのところにちょいちょい遊びに行かせてもらえば、全然中に入れてくれるようになりますよ(笑)。宇野さん詳しいし!
話を戻すと、フィギュアをアートとして売ることは何回も考えたんです。だけど、やっぱり「こっちはオリジナルのコピーです。こっちはマスプロダクトです」というふうに分けるのは難しい。
それに、アートとある種のキャラクターグッズとしてのフィギュアをどう折衷させるかも悩ましい。やっぱり中途半端なところに価値を置いておきたくて……(笑)。アートと呼ぶには、元の作品を愛しすぎていて、おこがましいわけです。
宇野:日本のアートの文脈って、巻き込まれて幸せになるのか微妙ですしね。あそこに巻き込まれると、むしろ作家は死んでいくとよく言われている。だから、村上隆さんはあんなに苦労しているわけでしょう。
安藝:竹谷さんも、アートに行ってないから幸せという気がするんです。人からオファーがあって、作りたい人なんですよね。
宇野:しかも竹谷さんは、日本においてホビーと映画美術とアートの間に区別がないことの象徴ですからね。いや、本当はホビーが美術よりレベルが高いことをみんな知っているわけですからね。
彼らはあまりにも過小評価されているし、コンテンツ産業の末端にいる人も多い。でも、アートの世界に行ったら行ったで、その才能がうまく花開かない可能性が高い。そういう状況の中で、安藝さんは例えば質の高い商品化でお金を回したり、企画そのものにスポンサーとして入ることで、彼らの創作環境を整えていくことを考えているわけでしょう。
安藝:上手い着地点を探しています。でも、探しても、探しても、難しい。結局、エンターテイメントもアートも、成功するケースって稀なんですよ。だからこそ、そのときにはもっとお金がしっかり入るようにしたい。フィギュアやアニメがそこそこ売れた程度では、日本のクリエーターやユーザーが求める品質感やエンターテイメント性は実現できない。成功したときの最大値が日本では低いんですよ。
宇野:この日本のサブカルチャーのまま、グローバルに支持されるしかないと思うんですよね。
安藝:まったく、その通りです。ただ、それに気付いてもらうために、アメリカの音楽を使ったりするのはアリだと思っていますね。日本のサブカルチャーに憧れや敬意を持っている外国人たちとパートナーシップを組んでね。そろそろできるような気がするんです。
「僕らにスターウォーズさえあれば」
安藝:そういう意味で、いま考えてるのは『スターウォーズ』ですよ。何十年、ヘタしたら百年持つような、バカみたいに稼げる状態を、今の日本の作家たちが生きていくために作りたいんです。
宇野:そこで必要なのは「作品」である、と考えるんですね。
安藝:それさえあれば、僕らに『スターウォーズ』さえあれば、と思います。たぶん、海外では200億円かかるものでも、日本でなら3分の1の予算でできるはずなんです。
宇野:でも、3分の1のお金を集めるのも大変でしょう。それに、日本中のクリエーターを総動員体制にしないといけないですし。
安藝:確かにお金はかかるけど、お陰様でグッスマは今なら多少キャッシュがあるんです。だからこそ、いまのうちにある種の博打を打ちたいんです。ここから、あと何年かでこのキャッシュを使い切って制作して、そのときに僕らはヒットを手にできているか……という。まあ、もし手にしていなかったら、また一から貯めなきゃいけないですね(笑)。
そういう作品を制作できたとき、僕が手を広げてきた全てがつながる気がするんです。ヘッドフォンも格好よくなるし、自転車ももっと格好いいものが出せるかもしれない。F1にもフィギュアにも使えるかもしれない。そういう、会社のすべてを振り返るような作品になると思う。
ただ、どういう人たちと組めばいいのかと、考えることは多いですよ。宇野さん、なんかいいアイディアないですか(笑)?
宇野:そうですね……。ちょっと抽象的な言い方になりますが、ひと言でいうと「ネットをやっていない人」がいいと思いますね。
たぶん、現在の日本ではVOCALOIDが典型ですけど、消費者が勝手に歌を歌わせたり、勝手に衣装を作ったりという、ネットのファンたちの力を取り込む手法が圧倒的に強いんです。 ただ、こと映画に関して言えば、実はグローバルな趨勢は真逆に向かっています。むしろ、徹底的に作り込まれたものを提示するのが、映画のようなメディアの役目になりつつあるんですよ。ハリウッドがヒーローモノしか当たらなくなっていて、『ゼロ・グラビティ』が話題になって、あと売れてるのはディズニーやPixarでしょう。国内でも当たっているのは、『風立ちぬ』の東宝とライダーとプリキュアの東映で、松竹は厳しい。要は、売れているのは、純度100%の虚構なんです。 その背景にあるのは、ネットの台頭でしょうね。90年代に流行っていたようなナチュラル系の演技でドキュメントタッチで撮る映像なんて「だったら、お前YouTubeで現実そのものを見ろよ」って感じじゃないですか。
安藝:そっちの方がドキュメンタリー性は強いですからね。
宇野:20世紀の映画が自然主義リアリズムを目指したとすれば、21世紀のアフターハリウッドの映像はアニメを目指すことになるんです。少なくとも映画館にわざわざ出かけて観るような映画について言えば、「全ての映画がアニメと特撮になる」というのが僕の考えです。
安藝:アトラクションですもんね。日常から離れたいわけだから。じゃあ、アニメ監督が有利じゃないですか。
宇野:そう思いますよ。どれだけいまの映画評論家が北野武や山田洋次を褒めようと、50年後に書かれる文化史の教科書には「20世紀後半、日本ではアニメや特撮が発展した」と書かれて、代表的なクリエイターには円谷英二と宮﨑駿の名前が載るに決まっている。僕は21世紀の映画産業では、日本はアニメと特撮で勝てるはずだと思っていますね。これをグローバルにどう打ち出していくのかが、いま問われていると思います。
安藝:素晴らしいですね。最近の日本のアニメーションはもう毎クールあって、それがまるで勝ち馬予想みたいに見られているでしょう。作家たちも、さすがに「それはちょっと」となってるんです。
宇野:そんなことよりも、グローバルな映像産業がいま徹底的に作りこまれたものに傾きつつある意味だとかを、もっとちゃんと考えるべきだと思いますね。もちろん、一方でボカロみたいなものの楽しみ方を海外のギークに教えていくのも大事でしょう。日本はそのどちらも得意なのですが、これだけハッキリと楽しみ方が二分されている中で、中途半端にやるのだけは良くないと思いますね。
安藝:そうですね。僕らはユーザーさんと仲良くやっていくスタイルだったので、フルフィクションのコンテンツ制作に舵を振りきれてないんです。
宇野:両面戦略は十分ありだと思いますよ。一番良くないのは、例えば、深夜アニメをCM代わりに流してソフトで小さくマネタイズしていくような中途半端なことじゃないですかね。
安藝:いやあ、あれは厳しいモデルです、中で見ている人間としても、今のまま続いていくかが非常に不安です。周辺ビジネスを巻き込んで、まだまだ作品を生み出す原動力として機能すると思いますが。
「長いモラトリアムが終わり始めているのかもしれませんね」
宇野:今日は面白い話をありがとうございました。本当に期待以上のことを聞かせていただいて……。
安藝:ひとつ聞きたいんですが、宇野さんって何でそんなに元気なんですか。羨ましいですよ。出力が多い人って、常に何か鬱憤が溜まっていますよね。そうなんですか?
宇野:もちろん、相当に溜まってるタイプですけど……でも安藝さんも、相当にエネルギッシュじゃないですか(笑)。
安藝:いや、僕は違うんです。根っこがないヤツなんです。オタクにもなりきれないから、自分で「これをやりたい!」というのが出てこない。だから、いつもモチベーションがない状態から始まるんです。で、誰かがやりたいと言い出したら、「よし、じゃあモノにしちゃおうかなぁ」となる。それだけのことであって、自分ひとりでは何も出来ない人間なんです。特にグッスマが始まってからのこの10年くらいは特に顕著で、人からモチベーションを借りて生きていますよ。
宇野:でも今日、僕は安藝さんと話していて、パトロンとしての意識を強く感じました。小黒さんの「アニメスタイル」への支援なんかもそうでしょう。凄い特殊な作画オタクのためのメディアだけど、でも、50年後、100年後にアニメが学術的研究の対象になったとき、きっと大きな意味を持ってくる。
安藝:そのときまでは一般には知られないかもしれないんですけどね(笑)。ユーフォーテーブルの近藤社長と一緒に支援しているのですが、彼も僕も「小黒さんの仕事を奪っちゃいかん」という思いでした。短期的なリターンは求めてないです。僕は、あれを英語化したいと考えてますよ。外国人にはまだわからないかもしれないけど、いつか「うんうん」と分かる日が来る。何より、きっとアカデミックに振り返る日が来たとき、彼の考察は世界中で必ず役立つわけだから。
たぶん、僕はモノを作れないコンプレックスが凄く強い。一緒にみんなでモノを作るのは大好きだけど、作る人たちに近づけば近づくほど、彼らのアイディアや情熱と、それにかけてきた時間が僕の比じゃないことに気づいてね……もう何も言えなくなってしまうんです。
宇野:だからこそ、安藝さんは若い消費者と同じ目線が保てているんだと思いますよ。
安藝:ある種のファン目線です。でも、彼らは違うんですよ。小林可夢偉と初めて会ったのは、彼が24歳くらいのときだったかな。そのときから彼は、世界を相手に戦うことになんの恐れも抱いていなかったです。「俺の方が速い」と言えてしまうんです。そして、フィギュアやアニメの人たちに至っては、世界と戦おうとは思っていない。「俺が一番作りたい映像はこれだ」というのが頭の中。
安藝:現実には、彼らがモノづくりをするためには、予算を取れる企画の建て付けや、評価を受けさせるための準備が必要なんです。でも、そんなことを彼らはきっと好きじゃない。だから、それは僕のような人間たちがやるべきことなんです。
最近、何とかして彼らを外に出すために戦いたい、と本気で思うんです。そういう意味では、もしかしたら僕の長いモラトリアムがやっと終わり始めているのかもしれませんね(笑)。 (構成・稲葉ほたて)