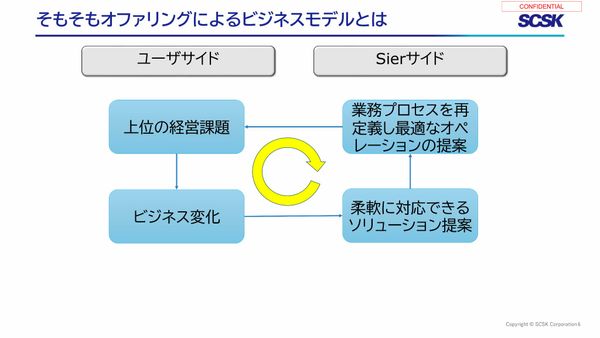 PR
PR2024.12.24
ビジネスが急速に変化する現代は「OODAサイクル」と親和性が高い 流通卸売業界を取り巻く5つの課題と打開策
リンクをコピー
記事をブックマーク
堀雅彦氏(以下、堀):ここまでは担当者の話だったので、意思決定者に話を移します。意思決定者の情報量は当然担当者がぐっと考え、浴びてきた情報量とぜんぜん違います。なので意思決定突破のための必要要件は、担当者が作り上げた確証、ロジックに対して、頭ではわかるという理解と、一方で担当者が持っている絶対いけるんだという感覚的な確信に対して「あ、確かにわかる」という共感をどう意思決定者のなかで作っていくかだと思います。

文章でまとめると、確信に対して「いいね、それ」という「共感」をどう作っていくか。一方で確証というロジックに対して、頭でその数字が魅力的であるという「理解」をどう得ていくかが、事業開発において意思決定を突破する上で必要な条件になります。
ただ頭ではわかったとしても、そんな簡単じゃないよという話はどうしてもあります。大きく分けて2つ問題が存在します。そもそも確信と確証が事業開発の過程の中で作れないというプロセスに起因する問題と、あとは絶対いけると思うんだけど伝わらないんですというコミュニケーションの問題。

この2つが、事業開発の現場では大きな課題になっています。今回は、こっち側(プロセス側)です。コミュニケーション側の問題も当然多くあるんですけれども。事業開発において、確信・確証をどうやって作っていくかに軸を寄せて、この後お話をしていきます。
ちょっとプロセスの話になっていきますね。お話をばっと進めてしまうので、抜けていってしまう情報もあるかもしれないですけれども、アンケート答えていただいたら資料を丸ごとお渡しをしようと思っているので、その前提で何個かキーワードだけでも持っていただけるといいなと思います。
お話を戻します。プロセスですね。確信・確証をどう作っていくかというお話です。これはおさらいですね。確信・確証がゴールである上で、それぞれ分解するとそれぞれ3つに分かれます。

お客さんが絶対いて、絶対困っているということへの確信と、提供しようとしている価値。これは渇望されているんだという確信ですね。あとは仕組み。できそうだ、これいけそうということへの確信。この3つで確信っていうのが作られていくと思います。
一方で確証は市場が大きくて、勝てる。かつ儲かりそうという3つですね。計6つの問い、感覚を、ミクロとマクロという視座を行き来しながら作っていく。これが事業構想におけるゴールだと思います。
これを作るには、仮説を作り、検証し、定義する、このサイクルを回し続ける中で不確実性を下げながら、確信と確証を高めていくことが必要です。

ただ、現場を見た上での話で言うと、そんな簡単じゃないよという話がどうしてもあります。なぜならば、お話ししたとおりビジネスモデルは持続的に成立する構造だからです。

それを作る上で整合性が大事だと思っていて。この整合性と構造を、冒頭話したところより少しぐっと解像度を高めてお伝えすると、お客さんがいて課題があって、価値があって、それを体験する手法がある。
お客さんと課題があるということは、マーケットがあるということ。価値なり手法が決まっているということは代替品、競合が存在する。なので、選ばれる理由の戦略が必要です。
この戦略とか価値手法をどうやって作っていくかという位置づけで仕組みがある。その上で、仕組みを通じてコストの構造、あるいは料金のモデルが決まってきます。その結果として収入・支出が現れ、ここはバランスしないといけない。これが事業が成立するという状態の構造ですね。
ここに時間軸を足すと、事業を続けていければ当然たまっていくものがある。それで何が強化されるのか、結果何に還元されるのかというサイクルが持続的に回っていくことが必要です。
この外のサイクルは、例えばAmazonをシンプルに本を売るマーケットプレイスと考えると、当然Amazonでユーザーが本を買うとAmazon側にはどのお客さんがどの本を買ったかという購買のデータが溜まっていきます。
購買のデータが溜まっていくと、レコメンドの精度が強化されて、それは結果的に来訪者にとってAmazonでの購入体験の進化という形で還元されていく。すごくシンプルに話していますけど、これがAmazonの場合の持続的な成長を創り出すサイクルの一つだと思います。
ビジネスモデルを描くとは、こういう構造、整合性を作っていくことだと思います。ここに意思決定の話を乗せると、(スライドを示して)ここは課題で需要で、実現性で、ここはミクロで見ないといけない。このへんは市場性や、優位性で、収益性で、こっちはマクロで見ないといけない。どんどん複雑になってきます。

つまり、確信・確証を作るためにビジネスモデルに向き合うことは、視座とか要素を行ったり来たりしながらも、全体の整合性は意識し続けないといけない。さらに言えば領域ごとに求められる人とかスキルセットも変わってきます。結果、やっぱり迷子になるんです。
これが現場に近い観点から見た時の確信・確証を作っていく難しさです。なので、ステップとしては単純に仮説を書いて検証して定義するという、このサイクルだけでは不十分なんです。仮説を書く前に1回全体像を眺めて、どこが今足りていないんだとか、まずどこを検証しないといけないのかというチェックが必要になります。

チェックがあるからこそ、規定した弱点に対して仮説を描き、検証して定義する。どれかの要素を定義したら、また全体像に戻って何が足りないのかもう1度チェックをして、さらに仮説検証を回していく。
このチェックを起点にしたサイクルが、確信・確証をちょっとずつ高めて不確実性を下げていくプロセスの目指す姿だと思います。
このチェックの機能について、僕たちNEWhははこれまでの事業開発支援の経験からフレームワークを開発し、活用しています。ここからの話は、このフレームワークを土台に確信・確証とは何かについてお話をしていければと思っています。

バリューデザイン・シンタックスと申します。全体の構造は後ほどお話しするんですけれども、見ていただいてわかるとおり文章で書くことがアプローチの特徴です。
文章で言語化をすると、無意識に、視点と視座の移動が起きやすく、整合性も意識しやすいんです。
実際にこれを現場で使っている機会はあります。書いてみると思考の濃淡がかなり顕著に浮かび上がります。書ける、書けないとかぜんぜん考えられていないということがかなり如実に出てくるので、担当者の事業構想の中での弱点を特定しやすいんです。

構造としては、先ほどお話したビジネスモデルの構造が文章に落とし込まれています。少しだけご説明をすると、n1のお客さんたちの課題をどういう手法でどういう価値にするのかというミクロのコンセプト。一方で、その結果としてどういうセグメントに対してどういう課題と価値を提供するのかというマクロのコンセプト。そして、マクロのコンセプトに対して、どこが戦う相手でどう戦っていくのかという戦略があります。
さらに、戦略は言葉にしただけでは意味がないので、それをどうやって作っていくのかという仕組みが文章として規定されていく。そして、仕組み、事業活動を通じて何が溜まっていくのかを言語化し、その結果として、持続的な競争優位性を作り上げるサイクルを回していくという文書の構造になっています。
そして、最終的に何が収益の源泉で、どこがコストで、儲かりそうな算段がついているのかということを規定していきます。このように構造で捉えると少し複雑に見えちゃうんですけれども、シンプルに文章でビジネスモデルと向き合うというフレームワークになっています。
話を少し戻すと、各ブロックごとに、冒頭お話しした確信と確証を作っていくための各問いに答えていくような構造になっています。

なので、事業開発を進め、仮説検証のチェックを回していった結果として、全体の文章が自信を持って書けている状態が確信と確証ができあがっている状態です。そういう位置づけで使っていけるフレームワークだと思います。

ちょっと複雑な話をしてしまったんですけど、シンプルに、まずは書いてみましょう。という話です。書いてみると弱いところが見えてきます。書いてみると、書けないというパターンが起こってきます。要素が書けない場合は視点として抜けているので、まず仮説を作っていくことが必要になります。

チームでやっている場合、書いてみると、人によって内容がぜんぜん違うという状態も出てきます。この場合は共通認識を作らないといけません。書けはするしチームで方向性も合っているんだけど、本当にそうなの? と自信がない状態も出てきます。これは検証しないといけない。つまりこういった状況を把握できるということがチェックだと思います。
「バリューデザイン・シンタックス」という名前なんですけど、文章を埋めていってどこが弱いのか、どういう状態なのかをきちんと可視化して、そこにフォーカスを絞って仮説を書いて検証して定義をしていく。1つ決まったらまた全体像に戻って、次にどこを決めるのかを考えて、またさらに回していく。このサイクルを作っていくことが、不確実性を下げて確信・確証を上げていくためのあるべきプロセスです。

構造としてはコンセプトというエリアと、戦略と仕組みというエリアと、収益デザインという3つに分かれた1つの長文になっています。各ブロックごとにどういうことを書くのか。どういう考え方が背景にあるのかをこの後お伝えできればと思います。

2025.01.16
社内プレゼンは時間のムダ パワポ資料のプロが重視する、「ペライチ資料」で意見を通すこと

2025.01.15
若手がごろごろ辞める会社で「給料を5万円アップ」するも効果なし… 従業員のモチベーションを上げるために必要なことは何か

2025.01.20
組織で評価されない「自分でやったほうが早い病」の人 マネジメント層に求められる「部下を動かす力」の鍛え方

2025.01.14
目標がなく悩む若手、育成を放棄する管理職… 社員をやる気にさせる「等級制度」を作るための第一歩

2025.01.09
マッキンゼーのマネージャーが「資料を作る前」に準備する すべてのアウトプットを支える論理的なフレームワーク

2025.01.14
コンサルが「理由は3つあります」と前置きする理由 マッキンゼー流、プレゼンの質を向上させる具体的Tips

2025.01.07
1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.21
言われたことしかやらないタイプの6つの言動 やらされ感が強く他人任せなメンバーを見極めるチェックリスト

2017.03.05
地面からつららが伸びる? 氷がもたらす不思議な現象

2015.11.24
人は食事をしないとどうなるか 餓死に至る3つのステップ
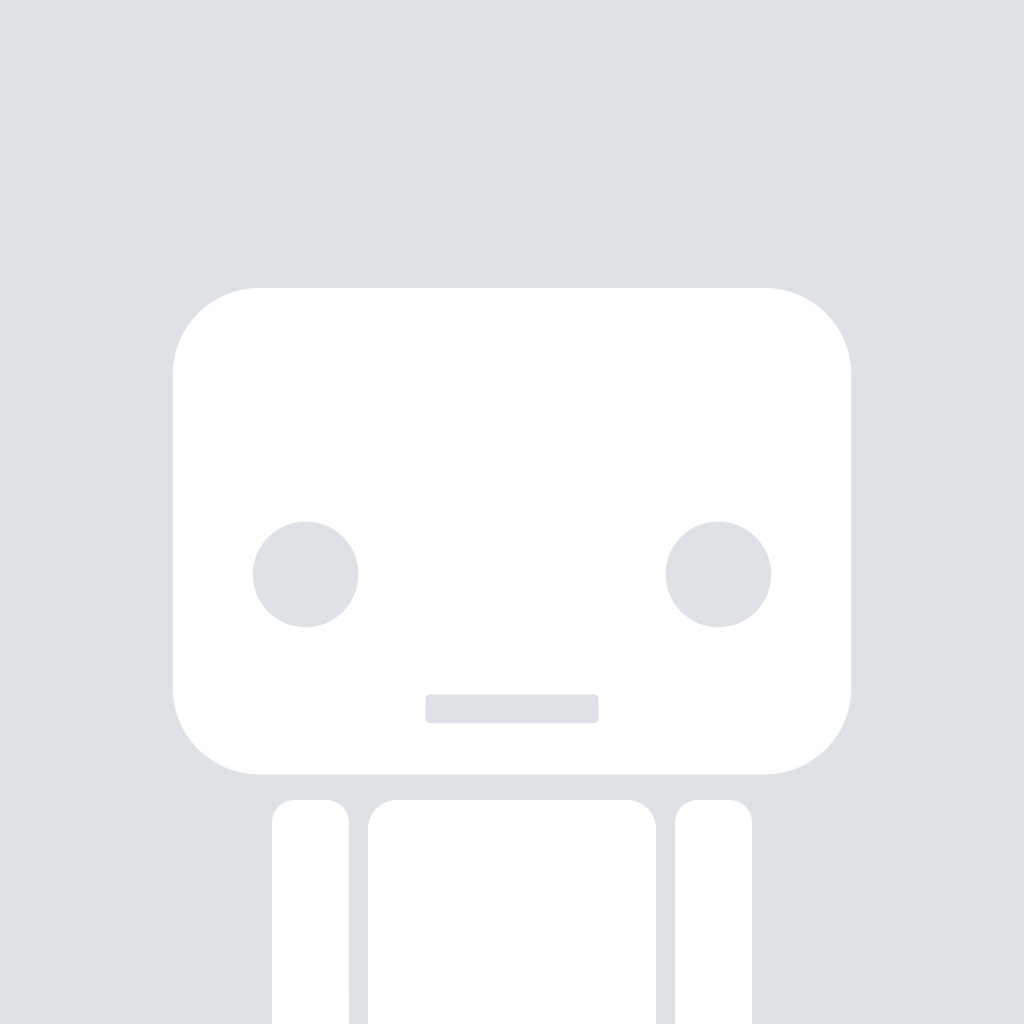
チームの生産性を上げるマネジメント術
2024.12.11 - 2024.12.11
特別対談「伝える×伝える」 ~1on1で伝えること、伝わること~
2024.12.16 - 2024.12.16
安野たかひろ氏・AIプロジェクト「デジタル民主主義2030」立ち上げ会見
2025.01.16 - 2025.01.16
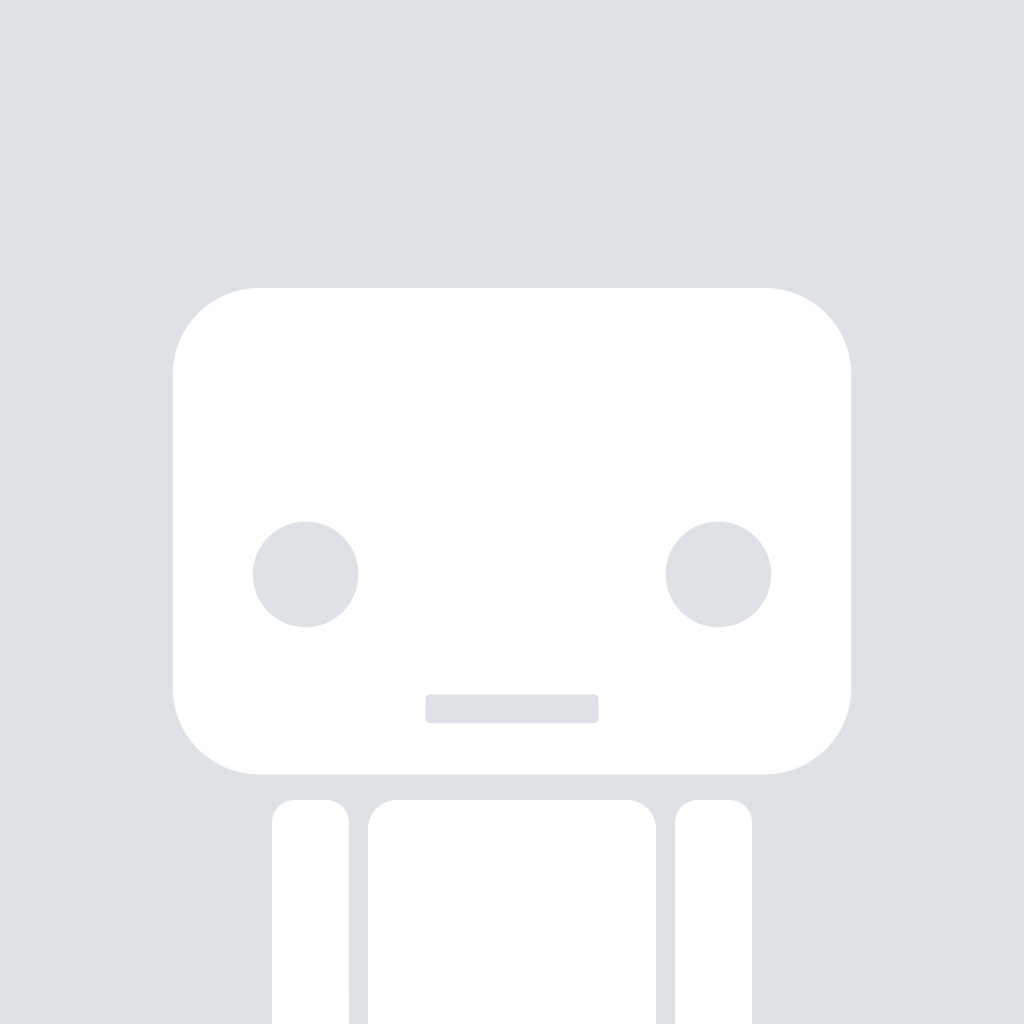
国際コーチング連盟認定のプロフェッショナルコーチ”あべき光司”先生新刊『リーダーのためのコーチングがイチからわかる本』発売記念【オンラインイベント】
2024.12.09 - 2024.12.09
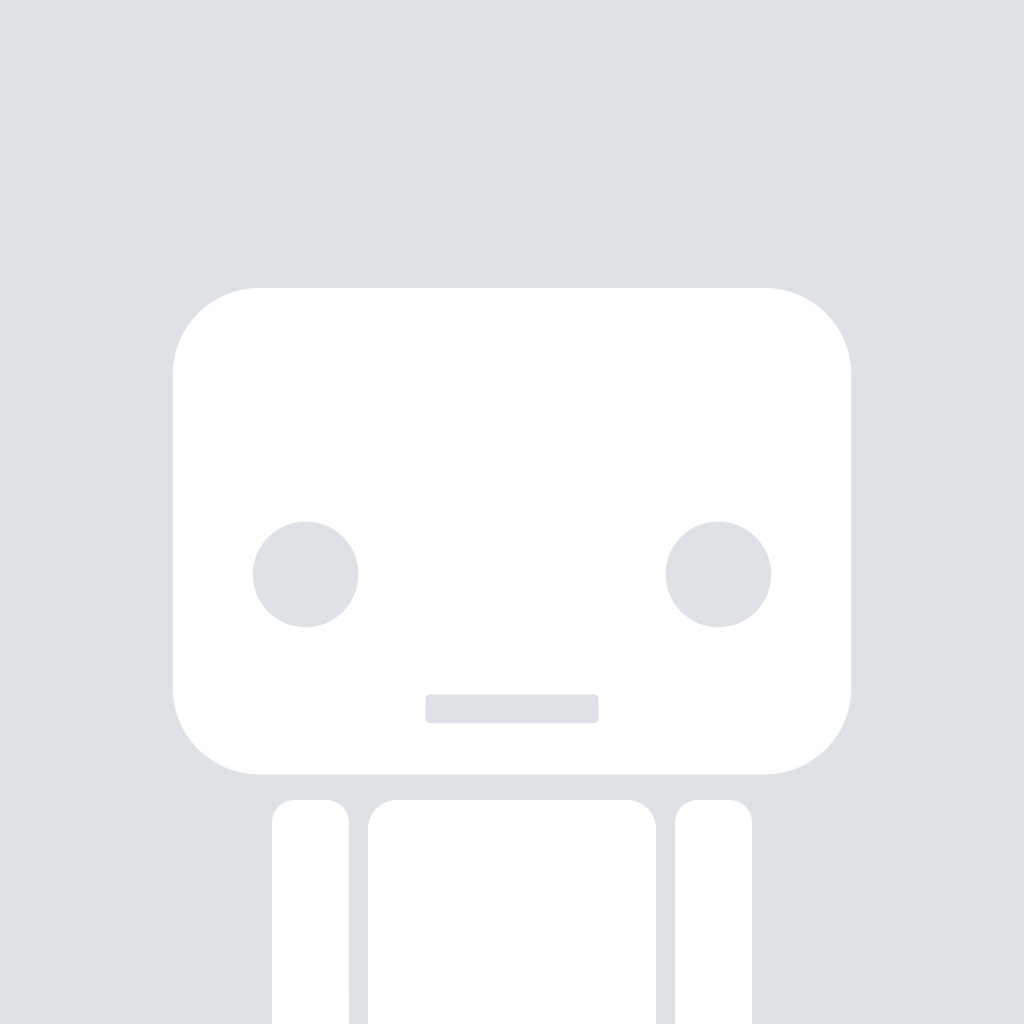
NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn特別提供コンテンツ
2024.12.24 - 2024.12.24