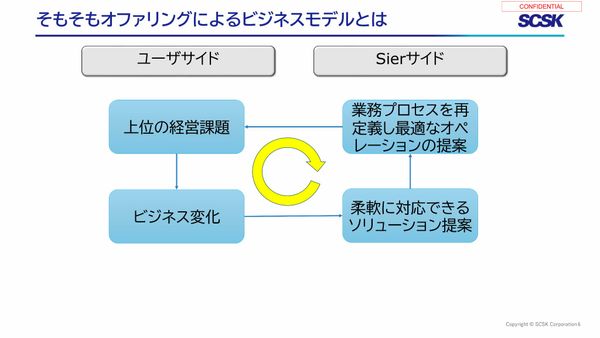 PR
PR2024.12.24
ビジネスが急速に変化する現代は「OODAサイクル」と親和性が高い 流通卸売業界を取り巻く5つの課題と打開策
『情報生産者になってみた』(筑摩書房)刊行記念トークイベント 大滝世津子×開沼博×竹内慶至 ゲスト:上野千鶴子 「社会を変える/人を育てる」(全5記事)
リンクをコピー
記事をブックマーク
竹内慶至氏(以下、竹内):みなさま、お集まりいただきありがとうございます。今回は『情報生産者になってみた』の刊行記念イベントで、「社会を変える/人を育てる」というタイトルで、私を含めて4人でトークをしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
最初の1時間はトークをして、そのあと質疑応答の時間にします。さっそく大滝さんから自己紹介をお願いできますか。
大滝世津子氏(以下、大滝):大滝世津子です。私は、なんだかんだと10年ぐらい上野ゼミでお世話になりました。それから鎌倉女子大学で専任講師として働きました。今は地元で学童保育施設や保育園を作って、活動しております。よろしくお願いいたします。
開沼博氏(以下、開沼):開沼と申します。僕は2004年から2010年まで上野ゼミに出ていました。学部ゼミから始まって大学院ゼミに至るまで、考えてみればすごく学ぶ時間が長かったなと思っております。今は東京大学の情報学環というところに所属して、准教授として教育研究をやっております。よろしくお願いします。
竹内:ありがとうございます。それでは上野さん……ご紹介というか(笑)、みなさんご存知かと思いますが。
上野千鶴子氏(以下、上野):高齢者で(新型コロナワクチンの)ブースター接種はまだやっておりませんが、オンラインでは感染しませんので(マスクを)外します。手術の後で、目ん玉が今ちょっと調子がよくないので、この状態で失礼いたします。片目の女でございます。今日は、教育の話をするんですかね。
竹内:はい、そうですね。
上野:みなさんの教歴を後でお聞きしたいんだけど、私はたぶん教育者としての経験の幅は一番大きいんじゃないかな。塾講師から始めて、みなさんも大学時代にやったかもしれない、家庭教師もやりました。それから専門学校、女子短大、4年制大学、旧帝大から大学院。それと海外の大学と大学院でも教えました。それにフリースクールでも教えました。ということで、教師でもありました上野です。
竹内:ありがとうございます。今日の司会進行を務めます、竹内と申します。私自身は今、教え始めて13年になります。初めは金沢大学で研究員をやり、助教をやりました。その後、兼任ですが、大阪大学大学院で教えていました。
金沢大学では「子どものこころの発達研究センター」という、研究者にとってはパラダイス……つまり、教育のオブリゲーションがほとんどなく、(受け持ちが)年間1コマではなくて年間3回みたいな、仕事がほぼ研究という所にいました。理化学研究所が研究者にとってのパラダイスだと言われるのと同じですね。今は名古屋外国語大学の現代国際学部国際教養学科という所で教えています。
この『情報生産者になってみた』の著者が6名いるんですが、そのうちの半数と上野さんとで、今回は教育に焦点を当ててお話をしていきます。
 『情報生産者になってみた ――上野千鶴子に極意を学ぶ 』(ちくま新書)
『情報生産者になってみた ――上野千鶴子に極意を学ぶ 』(ちくま新書)
さっそくですがこの『情報生産者になってみた』という本は、今日ご覧になっているみなさんもお買い求めになった方も多いかと思うんですが、もともとは上野さんの『情報生産者になる』という本の、子どもみたいな本ということで作りました。
上野さん関連の本を並べてみると『上野千鶴子に挑む』(千田有紀著)とか『上野先生、勝手に死なれちゃ困ります』(古市憲寿著)とか、いろんなことを「こうしてください、ああしてください」と言われていますが(笑)。今度は「なってみた」。『上野千鶴子になってみた』ではなく『情報生産者になってみた』ということで、『上野千鶴子に極意を学ぶ』というサブタイトルがついています。
まず上野さんにどういう極意を学んできたのか。私も含め大滝さん・開沼さんも大学の現場で働いてきたり、いろいろ社会実践に携わってきたりしていると思いますので。上野メソッドの極意がどこにあって、自分たちがそれをどう応用してきたのかというところから、話を進めていけたらと思うんですが。
竹内:大滝さん、今は大学ではない所で教育に携わっているということですが、いかがですかね。
大滝:大学で教えていた時は、私もゼミを持っていたので、そこでは上野先生の教えてくださった方法をベースにしてやっていました。内容は『情報生産者になる』に書いてあった、ほぼそのままなんですけれど。
最初に私がゼミ生を募集した時、集まったのは3名でしたね。どんな教員が来るのかもわからない状態で応募してくれたのがその3名で、2年目からは定員の10名を超える応募がくるようにはなったんです。
ですがだんだん評判として「せっちゃんゼミは厳しい」「怖い」「英語論文を読むらしい」という、尾びれがどんどんついていって(笑)。英語論文は読んでいなかったんですけど、そういう噂が広がっていたと、あとから聞きました。
それでもやっぱり論文を批判的に多読することと、実際に問いを立てて論文を書いていくという実践は、すごく大切にしていました。上野先生がなさっていたように、自分が指定した文献に加えて、指定した学会誌の中から学生自身が興味を持てる論本を1本ずつ持ってきてもらって、ゼミで精読するということもしていました。
論文を書く時は、学生たちに「何もない状態だと書き始められない」みたいなところがちょっと見られたので、すごくかわいい文字のワークシートを作りました(笑)。そのワークシートに自分の問題意識に沿って書き込んでいくと、なんとなく論文の骨子ができあがる、みたいなものです。それがあることで「何から手をつけたらいいかわからない」という状況の子が減って、ずいぶん心理的に書きやすくなったように思います。
大滝:一度だけゼミ中に、机に突っ伏して泣き出した学生がいて……(笑)。普通の発表の時だったんですけれど、「自分が思っている水準に仕上げられなかった」と感じていたみたいです。自分のレジュメを「本当にダメなので、もうこれは見なくていいです。メモにしてもらっていいので」とか言いながら出してきたことがあって、その時はちょっとびっくりしました。
私のゼミはそこまで追い詰めるような雰囲気は出していなくて、わりと和やかだったので「なんでこうなったんだろう」と困っちゃったんですけれど。すごく真面目な子が多い学校でもあったので、「締め切りがある」とか「ほかの人がすごくできているように見える」と感じる中で「真剣に向き合わなきゃいけないのに、できていない」みたいな感じで、そんな表出になったんだろうな……と思ったのが思い出です。
本の中でも書いているんですけれど、私の大学では研究室まで学生が入ってくることはできない制度だったんです。でも結局、ラウンジに呼び出されてしていた相談の内容は、上野研究室、通称「上野保健室」で繰り広げられていたようなものに近くて。私の本業って人生相談なのかなぁと錯覚しそうになるほどの時期もけっこうありましたね(笑)。
あとは上野メソッドに関係することとして、自分の中で大事にしていたのは授業です。自分がおもしろいと思ったことしか教えていなかったということです。やっぱり(上野)先生も自分がおもしろいと思うことを教えてくださったから、授業がおもしろかったという話がよく話題に上がりますが、それは私もすごく大事にしていました。
竹内:ありがとうございます。開沼さんもやっぱり厳しいゼミをやっているんですか?(笑)。
開沼:そうですね、けっこう厳しいと思います。福島関係の研究をやっていると、高校生の指導をすることもあります。福島の高校が文部科学省からスーパーサイエンスハイスクールに指定されて、「大学と一緒に研究しろ」とか、かなりハードルが高いこともやっているので。
そこのゼミ的なところでは、プレゼンを見てもらいたいと言われたら、子ども扱いはせずに厳しいことは言います。こちらも真剣にやればそれで十分についてきますし。その前提で呼んでくれる高校の先生たちと、ずっと付き合いをしてきました。
今年度からは東大で、研究者・学者になりたいという学生の割合が高い、ある面では特殊な環境になったのでまた違いますけど。
たぶん上野メソッドが何なのかと聞きたい方も今日は多く来ていると思うんですけれども、『情報生産者になる』を読んでいただければ、上野メソッドの相当部分は学べると思っています。『なってみた』を見ていただいても、実際に上野メソッドをどうする(活かす)のか、というのは書いてあると思います。
開沼:この中から私なりに2点ポイントを絞ると、1つはやっぱり「概念を大事にする」ということかなと思っています。それは僕の今のゼミでも、あるいは論文の審査とか入試とかで研究計画を見たりする時も同じです。何も特殊なことはやっていないつもりだけども、でも一般社会では特殊かもしれない。僕は上野先生のように「英語にしたら何なんだ」という言い方はあまりしないけれども、「それの定義は何ですか」とか、同じようなことを言っています。
例えば「復興」と言っているけど、それは誰のレベルの復興なんだと。行政がやる復興もあれば、住民がやる復興も、産業でいろんな仕事で関わっている人にとっての復興もある。「あなたがやっている復興(というテーマ)が、誰の復興なのかわからないから曖昧なんじゃないの」みたいなことを言う。だからまず概念を大事にする。定義とか位置づけとかをしっかりさせろ、と言うのは厳しくしているところだと思います。
もう1点が、「先行研究を読む」。情報収集ですね。上野ゼミでは先行文献の読み方みたいなことをやります。これはほかのどのゼミでも教えているんだろうけれども、ちゃんと身につく人とつかない人がいる、形式的に教えられているだけなのか、しっかりトレーニングされてきたのかが分かれるというのは、大学院の学生と接していても思います。
それはやっぱり上野ゼミの厳しい雰囲気のおかげで、ふわっとした「こういうところが良かったです」みたいな書評ではなくて、ちゃんと「批判的に見る」とは何か、どう切り込むのが美しいのかを、お互い学び合える環境の中で鍛えられたのかなと思います。
先行研究を見るというのは、すでに世の中にある情報を見た上で、単なる情報消費者から生産者になるためにジャンプするポイントなのかなと思います。その点も厳しく教育してきたなと思っています。
高校生にも躊躇なく(文献を)読ませるんですけど、意外と高校生でも読めるなと思っていて。そういう観点でも上野メソッドは相当普遍的な、どんな人にでも役に立つものかなと思っています。
竹内:ありがとうございました。今、開沼さんから「概念」と「先行研究」というポイントをお話しいただきました。僕も実は、最近は高校への出前授業みたいなかたちで(の依頼が)けっこう増えてきています。そこで、この『学びの技法』という本を2年ぐらい前に作ったんです。
ここでもちょっと書いたんですが、大切なのはターゲットとポジショナリティ(立場性)だと考えています。つまり、まず何か発言があった時に、それを言っているのは誰なのか。どういう立場から見て、どう切り取られて、その発言につながっているのか。それがポジショナリティということ。
そして、もう一つ重要なのがターゲット。自分が情報生産者として何かを届ける時に、それは誰に向けて届けようとしているのか、そのターゲットを明確にする。そこはかなり僕も、上野メソッドの中では、印象に残っています。
何かを書く時に、形式も重要ですが、1つ「これだけは絶対に忘れてはいけないポイント」を教える時は、ターゲットだと言っています。
上野さん、こういう教え方は合っているんでしょうか(笑)。これではまた上野ゼミになってしまいますが、いかがですか。
上野:それで終わり?(笑)
竹内:(笑)。
上野:三者三様、言うポイントが違うのね。
上野:大滝さんが言った「学生さんが突っ伏して泣いた」のは、あなたが追い詰めたんじゃなくて、自分の設定した期待水準のハードルが高くて達成することができなかったということで、悔し泣きをしているわけでしょ。
大滝:たぶん。
上野:それは、成長痛みたいなもんでしょう。その子にとってはその環境は、伸びることのできる環境だからよ。「和やかにやっている」と「ぬるくやっている」は一緒じゃないんだから、その子がそうやって泣くほどの環境を、あなたが作ったってことなんじゃないの。
大滝:なるほど。
上野:それから開沼さんは今、大学院生を教えているんだよね。大学院生と年齢はそんなに変わらないでしょう?
開沼:変わるといえば変わりますけど(笑)、まぁそうですね。
上野:まだ親子とまではいかないよね。
開沼:そういうことですね。
上野:そうなると、ライバルを育てているようなものなのよ。あなた自身も学ぶし、向こうからもあなたの隙や限界を衝かれる。大学院ってそういう所だからね。そういう意味では真剣勝負だよね。でもその真剣勝負は高校生だってみんな同じだよということは、まぁそりゃそうだ。
上野:そして、竹内さん。おもしろいね。「ターゲット」に当たる、私の使った言葉は「宛先」だよね。
竹内:「宛先」ですね。
上野:誰に読ませたいのかをはっきりさせるって、大事。どうしてかと言ったら、みんな論文を書くと、やっぱり審査員がどう反応するかを気にするでしょう。それで、その審査員があれこれ言うことに右往左往して、振り回される。
だけど、「あなたがこの論文を本当に届けたい相手は、大学みたいな狭い所にいると思うなよ」と(笑)、ずっと言ってきたのよね。だから本当に届けたい相手をちゃんと想定して、その人が納得できるような、その人に届くような論文を書きなさいと言ったところを、竹内さんはちゃんとストライクゾーンで受け止めてくれたんだね。
竹内:それはもう毎回毎回「あなた、これは誰に言いたいの?」って(笑)。
上野:(笑)。そうだね。

2025.01.09
マッキンゼーのマネージャーが「資料を作る前」に準備する すべてのアウトプットを支える論理的なフレームワーク

2025.01.15
若手がごろごろ辞める会社で「給料を5万円アップ」するも効果なし… 従業員のモチベーションを上げるために必要なことは何か

2025.01.16
社内プレゼンは時間のムダ パワポ資料のプロが重視する、「ペライチ資料」で意見を通すこと

2025.01.07
資料は3日前に完成 「伝え方」で差がつく、マッキンゼー流プレゼン準備術

2025.01.10
プレゼンで突っ込まれそうなポイントの事前準備術 マッキンゼー流、顧客や上司の「意思決定」を加速させる工夫

2025.01.14
コンサルが「理由は3つあります」と前置きする理由 マッキンゼー流、プレゼンの質を向上させる具体的Tips

2025.01.07
1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.08
職場にいる「嫌われた上司」がたどる末路 よくあるダメな嫌われ方・良い嫌われ方の違いとは

2025.01.10
職場にいる「できる上司」と「できない上司」の違いとは 優秀な人が辞めることも…マネジメントのNGパターン

2024.06.03
「Willハラスメント」にならず、部下のやりたいことを聞き出すコツ 個人の成長と組織のパフォーマンス向上を両立するには

安野たかひろ氏・AIプロジェクト「デジタル民主主義2030」立ち上げ会見
2025.01.16 - 2025.01.16

国際コーチング連盟認定のプロフェッショナルコーチ”あべき光司”先生新刊『リーダーのためのコーチングがイチからわかる本』発売記念【オンラインイベント】
2024.12.09 - 2024.12.09

NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn特別提供コンテンツ
2024.12.24 - 2024.12.24

プレゼンが上手くなる!5つのポイント|話し方のプロ・資料のプロが解説【カエカ 千葉様】
2024.08.31 - 2024.08.31

育て方改革第2弾!若手をつぶす等級制度、若手を育てる等級制度~等級設定のポイントから育成計画策定まで~
2024.12.18 - 2024.12.18