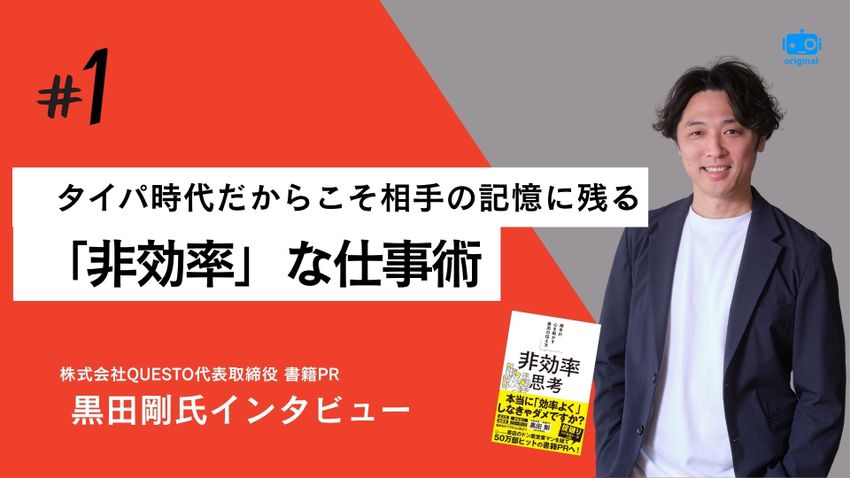【3行要約】
・タイパ・コスパが重視される時代だが、効率性を重視した仕事で成果が出ないという悩みを持つビジネスパーソンは多い。
・『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』の黒田剛氏は「相手に徹底的に合わせる非効率な方法こそが、実は最も効果的」と語る。
・営業パーソンは顧客の困りごとを聞き出し、自社のやり方に固執せず柔軟に対応することが重要。
相手の心を動かす「非効率」な仕事術
——黒田さんは今年の4月に『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』を上梓されましたが、書籍のPRとはどんな仕事なのか教えてください。
黒田剛氏(以下、黒田):テレビや雑誌、ラジオとかのメディアに本を売り込んで紹介してもらう仕事です。例えば『徹子の部屋』の制作の方に、「こんな著者が本を出したのでゲストでご検討してもらえませんか?」と提案します。出版社さんからPR費用をいただいて、メディアのキャスティングする人や企画を考える人に「ネタ」として「こんな本がありますよ」と提案するかたちです。
例えば最近だと、水族館の飼育員の方が書いたエッセイ本があります。これから夏休みの時期になると水族館に行く方が増えるので、情報番組のネタとして「飼育員しか知らない水族館の裏話」みたいに提案します。「これを読んでから水族館に行くと楽しいですよ」と言うと、「あっ、それ企画になるかも」みたいな感じですね。
——出版社とテレビ局などのメディアをつなぐ役割をされているんですね。黒田さんは一般的なタイパ、コスパを重視した効率の良い仕事のやり方ではなく、あえて非効率な仕事の仕方をされているとうかがいましたが、これはどういったものなのでしょうか?
黒田:僕が非効率だと思っているというよりは、みんなから非効率だと言われるんですね。一言で言うと、相手のことを思って動くことを「非効率思考」と本(『非効率思考 相手の心を動かす最高の伝え方』)の中では言っています。
僕がメディアの人に何かプレゼンする時に、例えば「今日は1日ロケです」と言われたら、多くの人は「プレゼンする時間がなくなるから」とロケに行かないところを、僕は1日同行して、いろんな話(プレゼン)をする。
よく「黒田さんは足で稼ぐんですよね?」みたいな言い方をされるのですが、そうではなくて、徹底的に相手に合わせるということです。例えば、自分がSlackをやっていたら「Slackで連絡をさせてほしいんですけど」とか言う人が多いんですが、僕は相手が対面が良いなら対面で、メールが良いならメール、「LINE」が良いならLINEでと、いかに相手に合わせられるかを重視しています。
“雑談きっかけ”で提案が通る
——相手に合わせて自分のやり方を変えるということですね。
黒田:はい。相手に合わせず自分のやり方でやっていても、結果は出ません。そもそも、1時間のアポイントを取って説明して決まることもあるんですけど、あらかじめ時間をとってもらって、「そんなに大した話じゃなかったね」となったら、向こうにご迷惑をかけてしまいます。
そんな中、取材の帰り道に「最近こんな本があって」と1分以内ぐらいで言ったような小ばなしがきっかけで、後日に「黒田さん、この間の本の話がおもしろかったから取材したいんだけど、できる?」って言われて、「あれ?あの話で取材が決まっちゃうの?」と。雑談で提案するやり方のほうが決まると気づいて、途中からそのやり方に切り替えました。

ダメダメ営業が一気に新規契約を獲得
——黒田さんはもともと芳林堂書店外商部で営業をされていたとうかがいました。当初はなかなか売れず成果を出せずにいたとのことですが、どんなきっかけで売れるようになったのでしょうか?
黒田:当時は、営業って、学校のテストみたいに正解が1つしかないものだと思っていたんですよね。会社から渡された資料の説明をすれば契約が決まると思っていたけど一向に決まらない。「大きい書店みたいにこれぐらいの割引率でできるの?」とか「こういうサービスはできるの?」と言われて、「いや、できません」と言うしかなかった。「こんなのどうやっても決まるわけないじゃん」と思っていたのが、僕のダメダメ時代です。
僕がそこで気づいたのは、「ビジネスには答えがあるわけではなく、みんな答えをずっと探しているんだ」ということです。たとえ答えがわかったとしても、時代が変わればまたその方程式が変わってしまう。だから常にやり方をアップデートし続けないといけないという、ビジネスのおもしろさに気づいたわけです。
僕が勤めていた芳林堂書店はそこまで大きい書店ではなかったんですけど、大きい書店に勝つにはどうしたらいいかを考えて、「今、契約していらっしゃる書店のサービスで、改善してほしい点があったら教えていただけませんか?」と相手のお困り事を聞いて解決していく方法に辿り着きました。これがお客さんを満足させる一番の方法なんだと気づいたんです。
——商品を売り込むのではなく、まず相手のお悩みを聞いたんですね。
黒田:そうです。書店外商時代の顧客はおもに学校図書館だったんですが、図書館の「お困り事」のひとつは、「新刊図書パンフレットが発売から3ヶ月経たないと届かない」だと分かった。そこで、自前でリストを作って持っていくようにしたら喜ばれて、一気に新規契約を取れたんです。
それと同様に、メディアの人は視聴率を取りたいという目的があるので、「この本をネタにしてどうやったら視聴率が取れるか」を提案する。視聴率が取れるものは時代によって変わるので、まずは「今はどんなネタが視聴率を取れるのか」を聞き出す。
そうすると、「最近はもうお米ネタですね」とか言ってくれるんですね。JAさんのお米の美味しい食べ方の本を紹介して、企画にならないか提案したりします。
要するに、ビジネスにおいて教科書はあるようでない。その現場現場で、その人たちの言葉を聞きながら考えて提案して、どんどんアップグレードしていく。これに気づいたのが、ダメダメな営業時代からうまくいくようになったきっかけです。
新たな需要を生み出していく新規営業の難しさ
——なるほど。そのあとは書店の外商部から、講談社で本のPRをされるようになったんですね。
黒田:はい。テレビ局とかに本のPRをするようになって、最初は勝手がぜんぜん違うのでうまくいかなかったんですよね。
書店の外商部にいた時は私立の高校に営業していたんですが、そこは一応営業に行けば会ってもらえるんです。スーパーにお酒のメーカーの人が営業するみたいなものですから、「そりゃ、ビールの営業も来ますよね」と受け入れてもらえるんですけど。
今、僕がやっている本のPRはそうではない。テレビの人たちは基本的に、番組で何の本を扱うかも自分たちで決めていて、人に提案されて決めることはあんまりないんです。だから「なんで来たの?」という感じで、無視されることもあります。
——これまで、黒田さんがされているような本のPRの仕事は業界では一般的ではなかったんですね。
黒田:そう。だから僕のPRの営業って、いわゆるルート営業ではなく新規営業の仕事です。ルート営業って、すでにお客さんとのコネクションはあって、保険の営業は「保険の新商品が出たので」とか、車の営業なら「新しい車が出たので」と提案しますよね。
メディアPRの場合はそうじゃなくて、例えば僕がウォーターサーバーの営業だとしたら、車の販売にウォーターサーバーを入れるみたいな感じです。「ウォーターサーバーを入れると、お客さんが待ち時間に利用できて良くないですか?」とか言いながら、まだ競合他社はどこも導入していない場所に提案するイメージですな。だから「なぜ車の販売店にウォーターサーバーが必要か?」ということを提案するところから始めないといけないんです。
「いや、実はIKEAみたいな大型の家具店で買い物をしてる家族がいて、子どもがすごく疲れてぐずってしまったと。でもそこにあったウォーターサーバーで冷たい水を飲んだだけで、子どもがまたその家具屋さんに行きたい、と言うようになったんですよ」とかの事例を言ってあげる。
それで「あぁ、確かにウォーターサーバーがあってもいいかも」となったら、「1ヶ月だけお試しできるので、それでダメだったらぜんぜん無理してやらなくていいですよ」と言って契約に結び付けていく。そういうふうに需要のないところに需要を生み出していくのが、僕の仕事の大変なところですね。
 PR
PR