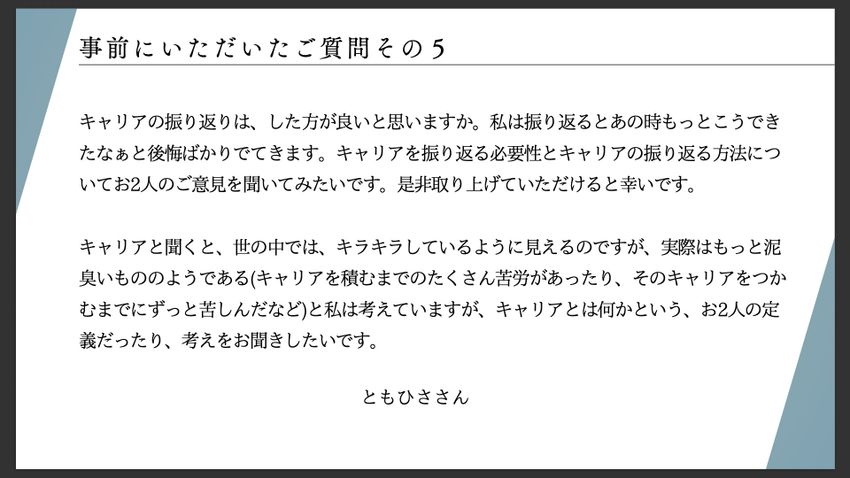なぜキャリアを問い直すのに、哲学と物語が必要なのか 〜ポジティブでない自分との付き合い方〜(全8記事)
仕事に悩んだ時、ヒントは“無意識の行動パターン”にある 自分のキャリアの欲求を振り返る方法 [2/2]
コピーリンクをコピー
ブックマーク記事をブックマーク ブックマークブックマーク解除
物語を読むことが気分に与える効果
谷川:もう少し物語との付き合い方について聞いてみたいんですけど、そういう時って、何を反芻しているんでしょう? ストーリーなのか、シチュエーションなのか、キャラクターや感情の流れなのか……。どういう部分に引っかかることが多いですか?
三宅:私は、作家の価値観やテンションみたいなものを自分にインストールしている感覚があるんです。最近だと、高殿円さんの『上流階級(富久丸百貨店外商部)』というシリーズがあって、デパートの外商さんの話なんですが、全体的にエネルギーが高い作品なんですよね。
仕事に向かう人の姿が描かれていて、その「エネルギーの高さ」みたいなものを取り入れたいと思って再読することが多い気がします。キャラクターやシチュエーションというより、テンション全体を浴びている。
谷川:つまり、作者が設計した気分のリズムみたいなものを、自分に入れているんですね。
三宅:そうそう。村上春樹を読む時は、「ひとりでいる感覚」を取り込みたい時だったり、山本文緒ならうだうだと考えを巡らせるような感じに浸りたい時だったりしますね。
谷川:なるほど。それって多くの人にとっては、音楽を聴く感覚に近いかもしれませんね。
三宅:ああ、そうかもしれない。
谷川:気分のトーンを調整している、みたいな?
三宅:そうです、そうです。元気になりたい時にアッパーな音楽を聴く、みたいな感じに近いですね。
谷川:なるほどなぁ。
人はなぜゴシップを追い求めるのか
谷川:あまり意識してこなかったけど、物語でそれをやっている人って、けっこう多そうですね。
三宅:無意識にやってますよね。例えば、少年漫画を読む時って、バトルモードに入っているような感覚ありますし。
谷川:わかります、わかります。だから『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』があれだけ読まれている時期って、「みんな、ちょっと殺伐としすぎてない?」って思っていました。もしあれを読んで、気分をチューニングしているんだとしたら……それ、けっこう大変な社会だなって。
三宅:確かに。この間、ちょっと『ヤンマガ(週刊ヤングマガジン)』の漫画だけを、20冊くらい一気にバーッと読んだんですよ。ヤンマガって、本当にバイオレンスとエロしかないみたいな感じなんですよね。
谷川:そうですよね。
三宅:それで読んでいるうちにだんだん不思議な気持ちになってきて、「やっぱりテストステロンだな…」みたいな(笑)。つまり、「世の中ってバイオレンスを抑圧してるけど、やっぱりそういう欲求はあるんだよな。まあ当たり前か」と。
SNSばかり見ていると、つい「今の世の中はクリーンになって、ポリコレも大事にされて…」みたいなことを言いたくなっちゃうんですけど、「いや、そう簡単な話じゃないな」と思ったりして。物語ってキャラクターや展開のおもしろさだけじゃなくて、気分を受け取る側面もあるんですよね。
谷川:確かに。自分の中では発散できないテンションを、物語が代わりに発散してくれてるのかもしれないですね。
三宅:単に楽しむというより、「その世界に浸りたい」みたいな。
谷川:それ、ほんとにそうだなと思います。今ってすごくクリーンな社会になってきてるけど、それでもみんな必死にゴシップを追いかけたり、悪口を言いたがったりするのって、もしかするとその延長かもしれないですね。
最近の午後は過去ドラマの再放送が多いですけど、昔だったら昼ドラが多かったじゃないですか。ベタな不倫ドラマが昼間によく流れていて。ああいう“どろどろした世界”を通じて、何かを発散してたのかもしれませんね。
「給料を上げたい」は表面的な欲求…本質的な欲求は「あの上司が嫌」
三宅:でも、しゃべりながら思ったんですけど、谷川さんがさっき言っていた「ある種の気分のクリシェが生まれる」みたいな話って、おもしろいですよね。
自分の悩みにしても、表面的な欲求……例えば「給料を上げたいから転職したほうがいいんじゃないか?」というものがある。でも実はその下に、「とにかくあの上司が嫌だ」みたいな、もっと本質的な欲求があるかもしれない。その場合、もしかしたら転職しなくても、その上司から離れられる環境に移るだけで問題は解決するかもしれない。
あるいは「今の人間関係がどうしても合わない」と感じているのだとしたら、業界を変えることが有効かもしれない。つまり、選択肢としてはもっといろいろあるはずなのに、表面的な欲望だけを見てしまうと、「給料アップのための転職をすべき」しか目が向かなくて、結果的に本当の自分の欲望とはズレたキャリア選びになってしまうこともある気がするんです。
物語でも、クリーンなものが流行っているように見えて、実はその奥にもっとドロドロした欲望がある、そういうことが人間にはよくあると思うんですよね。
そういう意味で、谷川さんは、「奥のほうにある気分」とか「もっと深い欲望」みたいなものを、ちゃんとつかんだほうがいい、と言う話をずっとされてますよね。
谷川:そうですね。
三宅:しかし表層の欲望をいったん脇に置いて、もっと深いところにある欲望を見つけるには、どうしたらいいのかなあ。
谷川:やり方としては、三宅さんが本を選ぶ時みたいに、「意味」じゃなくて「パターン」を見ることなのかなと。
意味っていうのは、「この本を読んで何か学びがある」とか、そういう“意図された読み”のこと。一方でパターンっていうのは、「無意識に同じような本ばかり選んでいる」とか、「気づけば同じテーマの物語に惹かれている」とか。つまり、あとから振り返ると見えてくる“規則性”みたいなものですね。
人の“潜在欲求を可視化”する方法
谷川:手短に言語化するのが難しいんですけど……精神分析みたいなイメージですね。精神分析というのは、20世紀初めにジークムント・フロイトという人物が提唱したもので、心との付き合い方に関するコンセプトなんです。
「自由連想法」っていう手法があって。普段、私たちは基本的に“意識”でしゃべっている。例えば、インタビューで「こうなんですか?」って聞いても、返ってくるのは意識レベルの話だけだったりするんですよね。
なので、「最初の入力だけして、あとは思いついたことをどんどん言ってみてください」とか、「単語を1つ言うので、それから連想したことを話してください」みたいな方法を取るんです。いかにも意味がなさそうに見える応答の連鎖の中から、その人の心の中にある“無意識のドラマ”を描き出していこうとするわけです。
フロイトはそのドラマの原型が「家族関係にあるんじゃないか」と言っていますけど、それはいったん脇に置くとして……。私が「パターン」や「規則性」って言っているのは、まさにそういう、自分では気づいていないけれどつい繰り返してしまう行動や思考の流れのことなんです。
三宅:なるほど。じゃあ、さっきの話で言えば、「なんか上司のことをつい考えちゃうな」とか、「こういう場面でイライラしてしまう」とか。「こういうのを手に取りがちだな」とか、そういうものを手がかりにしていく感じですかね?
谷川:そうですね。そういうところから探っていくのがいいと思います。あとは、すごく具体的なレコメンデーションとしては……千葉雅也さんの『勉強の哲学(―来たるべきバカのために)』にも、そういう話が書かれていて。
三宅:いい本ですよね。
谷川:あの本に出てくる「欲望年表」っていう考え方が、まさにそれに近いんです。あれって、キャリアの本として読むのもアリだと思います。
三宅:『勉強の哲学』は、すごく実践的なかたちで哲学を提示してくれている本ですよね。
谷川:そうですね。 続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。
無料会員登録
すでに会員の方はこちらからログイン
または
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!
スマホで読み込んで
ログインまたは登録作業をスキップ
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
ボタンをタップするだけで
すぐに記事が読めます!
 PR
PR