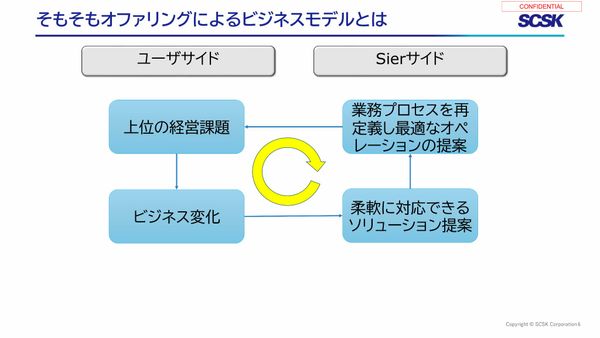 PR
PR2024.12.24
ビジネスが急速に変化する現代は「OODAサイクル」と親和性が高い 流通卸売業界を取り巻く5つの課題と打開策
【投資のプロが語る】2040年、おいしいニッポンの時代がやってくる?(全1記事)
リンクをコピー
記事をブックマーク
藤野英人氏(以下、藤野):『おいしいニッポン』というタイトルの本を、2021年の11月に出すことになりました。(本記事は2022年1月にYouTubeチャンネル『お金のまなびば!』で公開された動画の書き起こしです)
最初、このタイトルだと、「グルメ本じゃないか?」と言われまして(笑)。何がおいしいかというと、「これから僕らが生きていく上で、ニッポンという舞台は最高だ」という本になります。
でも、多くの人はそう思っていないと思うんです。これは悪いことだとは思っていないんですが、2年くらい前から若い人の間でアメリカ株投資がすごくブームで、アメリカ株の投資信託も今は絶好調ですよね。
一方で日本株はあまり人気がない。なぜかと言うと、「日本は成長してないじゃん」「規制がありすぎるよね。古臭いよね」と。
実はもう1つ、「昭和96年の会社」が多すぎるというのがあります。今(2021年)は昭和にすると昭和96年なんです。元号が変わって平成から令和になっても、あまりにもオジサン文化すぎるよね、という意味です。例えば、日本の経団連の会長・副会長は19名くらいいますけど、DeNAの南場智子さんが副会長になるまで、全員男だったんです。
全員60歳以上、全員日本人、かつ全員転職を経験したことがない人たちです。みんな新卒で、そのままその会社の社長・会長になった人たちばかりなんですよ。だから日本に足りないのは、ダイバーシティ(多様性)なんですよね。
でも裏を返せば、令和3年型の会社であれば、大きく伸びる余地がある。なぜならば、消費者が変わっているからです。世界の消費者も変わっている。
ナレーター:そんな中、藤野さんは「おいしいニッポン」の兆しを見つけたといいます。それは、未来を担う大学生たちです。
藤野:私が教えている大学生たちに、「どういう会社に就職したらいいですか?」と聞かれることがあります。そう聞かれたとき、まず言うのが、「好きなところに行きなさい」「自分の好きなことをしなさい」「ベンチャー企業で伸びているところか、外資系の会社に行きなさい」と。「日本の大企業の古い会社に行かないほうがいい。たぶん、ロクなことが起きないから」と言っています。
ナレーター:受験戦争を勝ち抜き、大企業に就職するのが当たり前と思われてきた一流大学の学生たち。しかしここ数年、ベンチャー企業の話をした時の彼らの反応が変わってきたと、藤野さんは言います。
藤野:一番すごいのが、東大ですね。日本で一番ベンチャー企業を作って、ベンチャー企業に就職しているのが東京大学出身の人たちです。
20年前は、40パーセントくらいが何もしない子でした。「何があっても何もしない」みたいな人が、40パーセントくらいでした。逆に「どんなことがあっても挑戦しつづける人」が、0.5パーセントくらいでした。
今は「何があっても何もしない」子が、40〜60パーセントくらいになった感じですね。全体で見るとすごく保守化して、何もしない子が増えた。でも、「何があっても、どういう困難があっても挑戦する」という人が、0.5パーセントから2パーセント、もしくは3パーセントくらいに増えた感じなんです。4~5倍になった感じですね。
私は、後者の変化をとても大事にしています。この子たちが雇用を作り、この人たちが新しい産業を作ってくれる。今のベンチャー起業家って、みんな魅力的なんですよ。人格や雰囲気が大人なんです。
例えば将棋の藤井聡太さんとか、野球の大谷翔平さんとか、あの人たちはすごく素敵ですよね。性格もいいし、圧倒的な力を持っている。ああいう感じの起業家とか経営者候補みたいな人が、今けっこう出ているんです。
僕はそれを見ているから、「そういう子たちを中心に、日本はよくなる」という確信を持っています。でも、「誰もがよくなるわけじゃない」ということは、強調したいなと思いますね。
ナレーター:「日本の未来を変えてくれる」と藤野さんが期待を寄せる、若い起業家たち。例えば、ドローンで畑の写真を撮ることで、野菜の収穫量や状態が一目でわかるシステムを開発した起業家がいます。そのシステムは農業だけでなく、測量や巨大プラントの安全管理など、さまざまな場面で活躍しています。
また、「同じ家に住み、毎日通勤する」という常識を変えようとする若者がいます。全国の空き家を改装し、いつでもどこでも住めるサブスクを展開する、豊かな人生と地方活性化を両立させる画期的なビジネスです。
そんな「おいしいニッポン」を作り出す令和3年型の企業には、共通の特徴があるそうです。
藤野:例えば、「昭和96年型と令和3年型の会社の違いは何だろう?」というと、3つあると思います。

1番目は「お客さま第一主義」です。2番目は「長期目線」。3番目は「科学的な考え方」もしくは「データオリエンテッド(データ主義)」です。
昭和96年型の会社は、この3つが全部ない。例えば、「お客さま第一主義」じゃなくて「会社都合主義」です。自分たちの経営陣だったり、自分たちのやり方が大事だというのがある。
2番目も、「長期主義」ではなく「短期主義」なんです。「日本は欧米型資本主義とは違うんだよ」と。「あいつらは、非常に短期で物事を考えている。そして、株主利益だけ追及しているんだよ」みたいなことを、古臭い考えを持つ経営者が言っているわけですよ。
「僕らはね、人材の材は材料の材じゃなくて、財産の財と言っているんですよ」と言うので、「いい会社なのかな」と思うと、だいたいそういう会社のホームページや有価証券報告書、アニュアルレポートを見ると、社員がぜんぜん載っていないんです。だから、人を「財産ではなくて材料」だと思っている可能性があるのではないかと思います。
かつ、データオリエンテッドではなく、経営者の勘や過去の慣習が意思決定に大きく影響することが多いです。
こういう昭和96年型の会社が、日本の主要産業にたくさんあります。ということは、裏を返せば、そうではないかたちで会社を経営したら、成功する可能性が高いのです。
藤野:2040年には時価総額上位100社のうちのたぶん半分以上が、直近20年間で伸びた会社になるのではないかと、大きな期待を寄せています。
なぜか? これと同じ現象が、過去にアメリカで起きたからですね。2000年頃、アメリカの優秀な子たちがみんなベンチャー企業を興したり、そこに就職したりしたんですよ。そういう人たちがGAFAのようなベンチャー企業を作り、その会社が巨大企業になり、アメリカの時価総額上位の会社になってアメリカの株式市場を支えた。
今の日本もだいぶ変わりました。最優秀の子が、今言ったような日本の昭和96年型の会社に入ることを良しとしなくなった。むしろ自分たちで会社を作ったり、ベンチャー企業に就職したり、外資系に入るようになっています。
要は2000年のアメリカで起きていたことが、今日本で起き始めているんです。ということは、2040年になったら社会が激変するんですね。
これから僕らはどういう選択をするのか? 未来に向けて、この20年で起きるだろう変化を確信し準備することの大事さが、この『おいしいニッポン』で書かれていることです。

2025.01.09
マッキンゼーのマネージャーが「資料を作る前」に準備する すべてのアウトプットを支える論理的なフレームワーク

2025.01.16
社内プレゼンは時間のムダ パワポ資料のプロが重視する、「ペライチ資料」で意見を通すこと

2025.01.15
若手がごろごろ辞める会社で「給料を5万円アップ」するも効果なし… 従業員のモチベーションを上げるために必要なことは何か

2025.01.14
コンサルが「理由は3つあります」と前置きする理由 マッキンゼー流、プレゼンの質を向上させる具体的Tips

2025.01.07
資料は3日前に完成 「伝え方」で差がつく、マッキンゼー流プレゼン準備術

2025.01.07
1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.10
プレゼンで突っ込まれそうなポイントの事前準備術 マッキンゼー流、顧客や上司の「意思決定」を加速させる工夫

2025.01.08
職場にいる「嫌われた上司」がたどる末路 よくあるダメな嫌われ方・良い嫌われ方の違いとは

2024.06.03
「Willハラスメント」にならず、部下のやりたいことを聞き出すコツ 個人の成長と組織のパフォーマンス向上を両立するには

2025.01.14
目標がなく悩む若手、育成を放棄する管理職… 社員をやる気にさせる「等級制度」を作るための第一歩

安野たかひろ氏・AIプロジェクト「デジタル民主主義2030」立ち上げ会見
2025.01.16 - 2025.01.16

国際コーチング連盟認定のプロフェッショナルコーチ”あべき光司”先生新刊『リーダーのためのコーチングがイチからわかる本』発売記念【オンラインイベント】
2024.12.09 - 2024.12.09

NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn特別提供コンテンツ
2024.12.24 - 2024.12.24

プレゼンが上手くなる!5つのポイント|話し方のプロ・資料のプロが解説【カエカ 千葉様】
2024.08.31 - 2024.08.31

育て方改革第2弾!若手をつぶす等級制度、若手を育てる等級制度~等級設定のポイントから育成計画策定まで~
2024.12.18 - 2024.12.18