 PR
PR2026.01.19
業務フローを変えずに、メール1通3分を削減 自動でAIにナレッジが貯まる問い合わせシステム「楽楽自動応対」
コピーリンクをコピー
ブックマーク記事をブックマーク
漆原茂氏(以下、漆原):では、みなさんのようなヤバい尖った人材はもちろんですが、そういう人たちのような若い人たち、どんな人たちに未踏に応募してほしいかとか、どんな人たちだったら成長するのかとか。「むしろこういう人たちは止めたほうがいいんじゃないの?」みたいなものも含めて、ありましたらザッとトークできればなと思います。安野さん、いかがですかね?
安野貴博氏(以下、安野):やはり自分でやりたいことが明確で、「これがやりたいんだ」ということがある人は、一見、未踏の力を借りなくてもいいかなと思っちゃいがちな気がするんです。
けれども、そういう人こそ応募してもらえるといいのかなと思っています。やはり、締め切りを勝手に設定されるとか、まとまったものを作るまでの活性化エネルギーを得られるとか、そういう意味で、プロジェクトを持っている人は応募するだけでアドしかないので、そういう人がやるのはすごくいいと思います。おすすめだと思います。
漆原:ネタがあって、もうやるしかない状況に追い込まれたい人。
安野:そう。追い込まれたい人にはすごくいいですよね。
漆原:はい。かつPM、ビジネスアドバイザーを含めてちゃんと技術もわかっているので、半端な行動は許さないというのもけっこう大事ですよね。
稲見昌彦氏(以下、稲見):そうですね。しっかりと中身がある提案じゃないとすぐに見透かされます。
漆原:そうですね。提案はそれなり以上にハードルは高いと思います。しっかり、すべて内容を見ているので、かたちだけの提案をしても通らないということは事前に伝えておいたほうがいいかなと思いますね。

漆原:中村さんはどうですか?
中村裕美氏(以下、中村):そうですね。先日亡くなられた鳥山明先生の言葉を借りてしまうのですが、「オラ、ワクワクすっぞ」メンタルがある人は、けっこう未踏に向いているんじゃないかなと思っています。
漆原:確かにそうですね。
中村:知的好奇心的な意味でもそうなのですが、未踏にいる人たちは戦闘力が高い。スーパーサイヤ人とサイヤ人の卵がいっぱいいるみたいな感じで、そこで武者震いを起こして奮起できるようなタイプの人は、未踏の中でどんどん強くなっていけるんじゃないかな、未踏を通して強くなることができそうだなとは思っています。
漆原:確かに、そもそも最初からスーパーサイヤ人の人はいませんからね。でも本当にプロジェクト期間中、たった8ヶ月なのですが、化ける人は化けますもんね。

漆原:稲見先生もプロジェクトを見ていてどうでした? ビックリするほど、超すごいですよね。
稲見:物理世界には奇跡はないはずなんですけど、人間には奇跡が起きますよね。
漆原:えぇ。急に大人びて、起業家として、社長としてすごくしっかりやったりとか。「ここまでグダグダになったら普通は折れて止めちゃうかな」と思っていても、絶対に止めないで、もっといいものを作りきってやってくるみたいな。
稲見:そう。途中で「どうなることかなぁ」とか、ずっとヒヤヒヤしていたものが、最後にドカンといいものが出てきたりして、「あ、奇跡だ!」という感じです。そこに立ち会えるのはいいですよね。
漆原:たった8ヶ月でも濃い期間で、非常に強い期待とプレッシャーを浴びることで人は成長するんだなということは体験できますよね。
安野:そういう意味では、「未踏は俺にはまだ早いんじゃないか」みたいな、自信のない人に応募してほしいですね。
漆原:そうですよね。
安野:別に自信がない人ばかりだと思うし、結局、人間は追い込まれれば何とかなるので、そういう方はすごくおすすめですね。
漆原:なるほどね。安野さんの場合は、締め切りに追い込まれるのも慣れてきた感じですかね。
安野:いや、締め切り前はやはり頭がすごく活性化しますよね(笑)。なので締め切りは僕は欲しいなと思っています。
稲見:やはり締め切りホルモンってありますよね?
安野:ありますよね。
稲見:はい。締め切りの前にバーッと。でもそこをうまく乗りこなして使い切るというのが(大事)。やはり人類は締め切りが大切なので。
安野:締め切りドリブンで生きている感じがしますもんね。
稲見:はい。

漆原:登さんからはいかがですか? この未踏事業の意義も含めて、どんな人に挑戦してほしいとか。
登大遊氏(以下、登):国のお金を使っていますが、普通、国のお金でやる時は大変計画主義で、バーッとすごいお金を、大変な金額を一気に博打みたいにやります。これは例えばIT以外の、石油化学コンビナートを作るとか、製鉄所を作るみたいな時にはやり方がわかっていますので、たくさん投資したほうがいいです。
ですがITの場合、やり方がわからない問題をやるわけで、UNIXの発明を考えても……。1969年に、アメリカの電話会社の社員のケン・トンプソンさん、デニス・リッチーさんの2人がゲームをやりながら遊びで作ったのが、UNIXとC言語でした。その前に大計画主義をやって作ったMulticsは、大変なお金を使ったけど、あまり普及しなかったんです。
また、こんなことはUNIX以外にもいろいろとあって、GoogleもAmazonもそうなんですよ。Googleは大学院生が大学のサーバールームで検索エンジンを作って、OSなんかもどんどん自分で拡張して作っていったのがきっかけです。Amazonもそうなのですが、そういうふうに考えると、我々ITはスロースタートの原則を貫かなければならないのです。
未踏はスロースタートの原則をやっていて、一人ひとりに予算はありますけれども、それほど高額ではないです。非常に少額です。この小さい予算で、できるだけたくさんの方々が挑戦することで、宝くじの番号を全部買うみたいな感じですね。石油化学コンビナートは立てて失敗すればダメですが、ITは1万人が宝くじを買って、その中の1個でも当たれば、それを複製・再現できるという大変大きな特徴があります。
だから未踏は、たくさんの人を選択と集中(するの)ではなくて、分散型でやっているということです。
それとやはり未踏に向いている人材というのは、次の人材やと思います。人材育成というものは、例えば何でもいいんです。クラウド人材でも、AI人材でもいいのですが、〇〇人材を育成するということです。〇〇人材を育成するということは、〇〇という技術、製品、サービスを作り、それを提供する側の人材(を育成するということ)です。
それを考えると、例えば鉄道人材は電車の予約をうまくやって席に座って、全国をてっちゃんとして回るのは鉄道人材とは言わなくて、普通は鉄道の運行をする側が鉄道人材です。
漆原:そうですね。提供側ですね。
登:そうです。行政人材といったら行政の福祉をもらうユーザー側ではなくて、福祉を提供する側です。教育人材といったら教育を受ける側でなく、教育を提供する側です。ところが最近の国の政策は、例えばクラウド人材、AI人材と言っていて、クラウドを使う側の人材、電車に乗る側を(育成している)。
漆原:ユーザー側のね。
登:これは話がおかしい。人材育成までは正しいんですが、やり方が逆になっているように思います。未踏はちゃんとしたAI、クラウド、コンピューターシステムの人材を育成する場所で、正当なやり方だと思います。この正当なやり方に参加したい方には大変おすすめなんじゃないかなと思います。
漆原:なるほど。まさにそういうところが、登さん自身にも未踏がピッタリ合致していたということですかね。
登:自分は大変しょうもないものしか作っていないんですけれども。
漆原:いえいえ、すばらしい。
登:みんな集まっている方は、まったくの人材、作る側の人材です。そればかりやっています。
漆原:登さんから見て、他にもいろいろあるじゃないですか。応募しようと思えば(応募をするような先は)それほど数が多くなかったかもしれませんが、(他にも)あったと思うのですが、その中で未踏を選ばれたのはどうしてですか?
登:2000年ぐらいに新聞に書いてありましたね。中学3年生の頃でしたが、経産省がこういうものをやるらしいということが書いてあったのを……。覚えていて。
漆原:新聞広告!?
登:広告といいますか、記事ですね。社会記事です。
漆原:なるほど。IPAさん、ぜひちょっと新聞にも記事を出しましょう。
(会場笑)
登:記事はIPAが書いたんじゃなくて、記者さんが経産省を取材したやつです。それを読みました。
漆原:今日メディアの方もたくさんいますので、書いてもらうことが未来の日本の発展に非常に寄与するということをぜひ肝に銘じてもらって、記事に書いてもらえればと思います。
登:よろしくお願いします。

(次回につづく)
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。
すでに会員の方はこちらからログイン
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!
スマホで読み込んで
ログインまたは登録作業をスキップ

安野貴博
エンジニア/小説家
プレゼンター
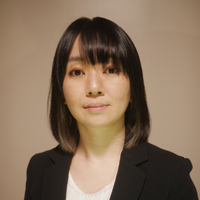
中村裕美
東京大学大学院情報学環 特任准教授(現:東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 准教授)
プレゼンター

登大遊
ソフトイーサ株式会社 代表取締役/独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)産業サイバーセキュリティセンター サイバー技術研究室 室長/NTT東日本 特殊局員
プレゼンター

稲見昌彦
東京大学 総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授/未踏IT人材発掘・育成事業プロジェクトマネージャー
プレゼンター

漆原茂
ウルシステムズ株式会社 代表取締役会長/ULSグループ株式会社 代表取締役社長/株式会社アークウェイ 代表取締役社長/未踏アドバンスト事業プロジェクトマネージャー
プレゼンター
この記事をブックマークすると、同じログの新着記事をマイページでお知らせします