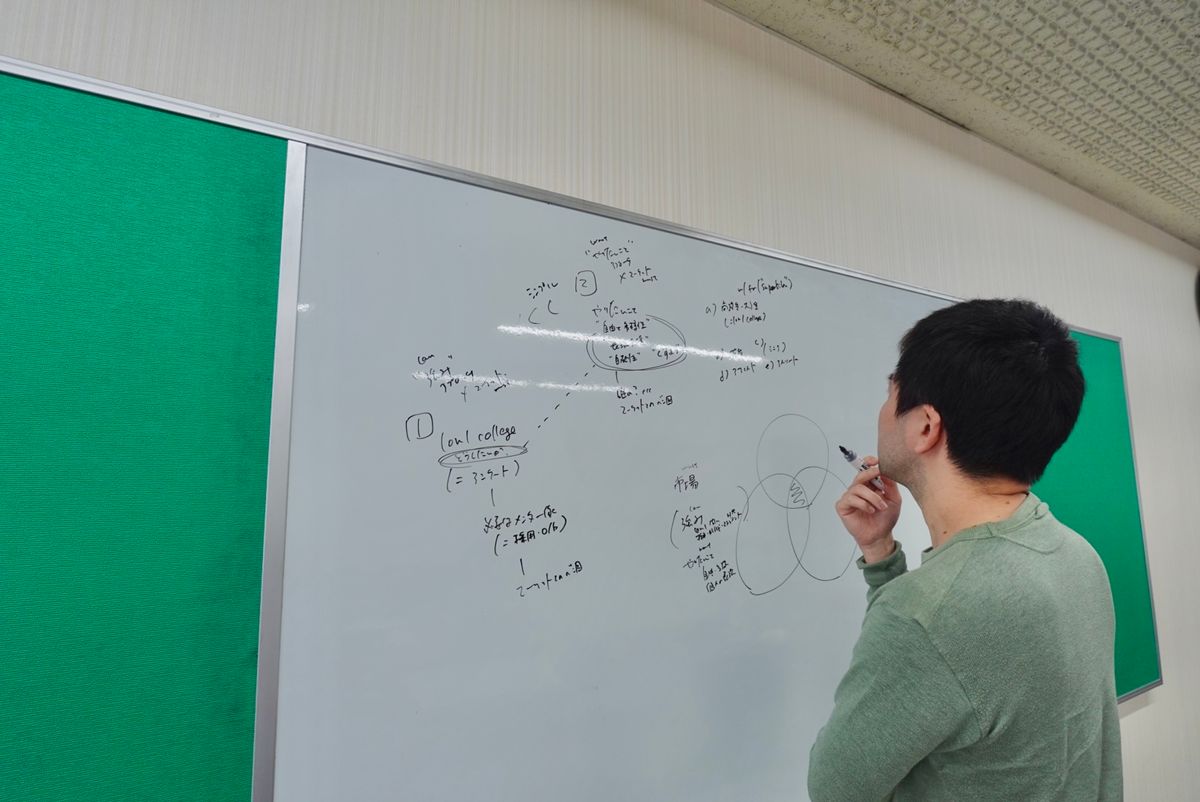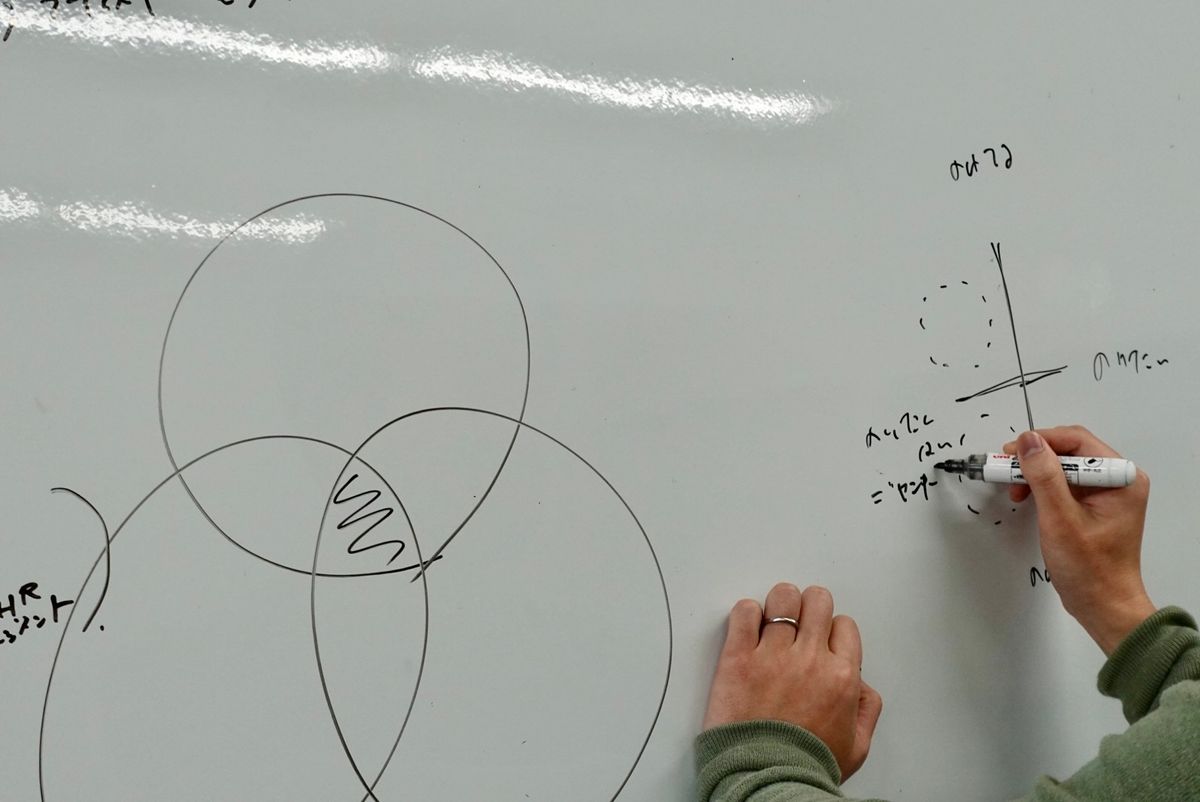人事・組織領域で企業を支援しているオトナタチ合同会社代表の長谷川亮祐氏が、スタートアップや中小企業における初期の採用活動のポイントについて解説します。企業文化の言語化をトピックに、採用におけるメリットや、組織の成長に与える影響について紹介します。
創業時の数名が企業のカラーを作る
三鈷捺稀氏(以下、三鈷):さっき、公募をするタイミングはあらためて組織について言語化する必要があるという話があったじゃないですか? すでに一定の人数の社員がいる場合の難しさってあるんですか?
長谷川亮祐氏(以下、長谷川):文化は形成されていると思う。1人だと文化を作るのはなかなか難しい。自分が採用のサポートに携わるタイミングは、1人というより、最初の何人かはいる状態。5人から10人ぐらいいるタイミングで首を突っ込ませてもらうことが多いけど、その最初の何人かで文化が作られている気がする。
もしかしたら複数人の中で、文化に強く影響を及ぼしている特定の1人がいるケースはあると思うけど、やはり何人かいることによってコミュニケーションが生まれるし、色が出てくる。だから、たくさんいるから難しいというより、何人かいることでより色濃く見えるという感覚かもしれない。
やはり、修正したほうがいいことは、本人たちも気づくこともたくさんあるから、悪い風習として修正すればいいと思うんだけれども。そうじゃなくて残っていく、残していく文化や価値観は、本来はバリューやミッションなどから紡がれるべきだと思う。採用も、スキル的な基準も重要だけど、こういう働き方、文化、美徳の中で働くことが一致しないと難しい。
その企業文化だからできること
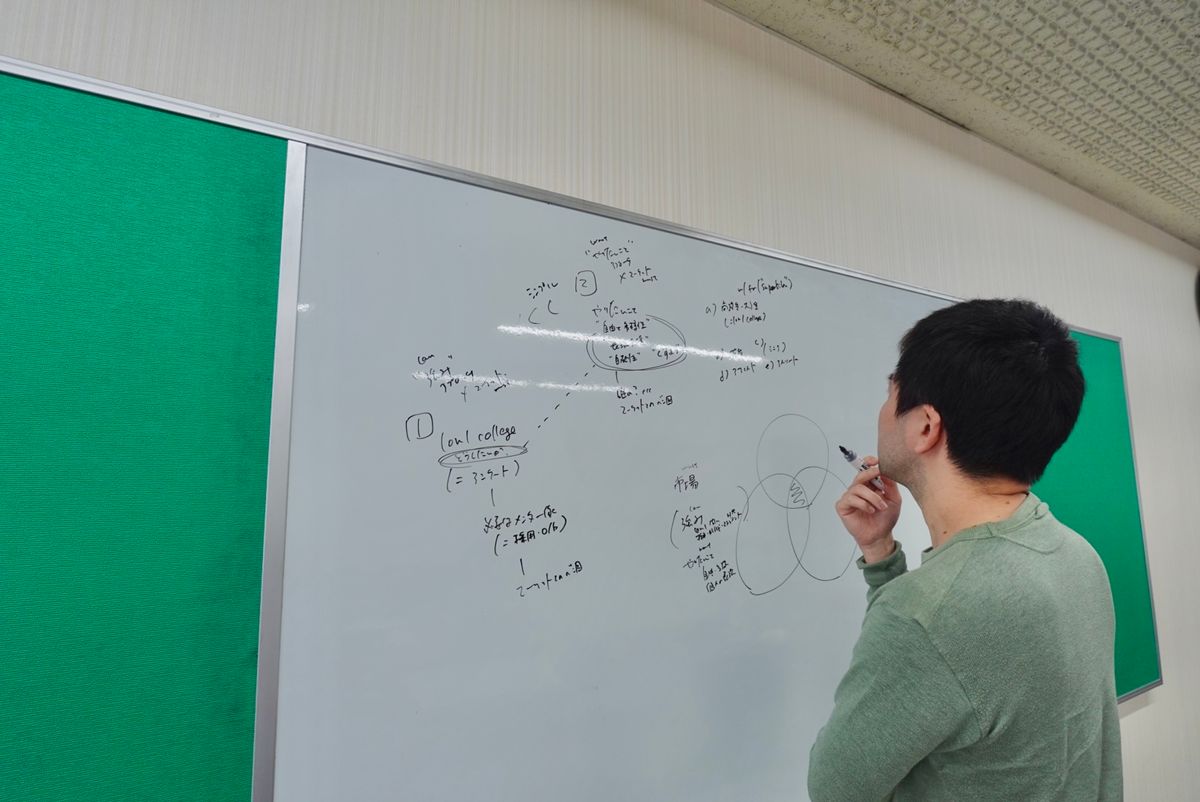
長谷川:その文化だからできることがたくさんあるのがおもしろいんだよね。できないこともあるんだけど、そこに会社の色をすごく感じるから。もちろんその事業や業界で、シェアがどうとか、ユーザーが何人いるという話だって重要なんだけど、個人的に、単純に企業ごとの色がおもしろすぎる(笑)。
ふだん1on1で1人に向かっているからというのもあるだろうけど、そういう自分の興味関心として色濃いから気づけるものもあると思うし、すごくおもしろいですね。
わざわざ創業しているぐらいの人たちなので、「何か」はいろいろあるけど、やはり強いこだわりや思い入れがあって、問題意識とか、どうしても成し遂げたいことに向かっていく強さがあるからすごくリスペクトするし、自分の刺激になる。
そういうものに触れて形にしていって、それこそ、その人がルフィになっていくことを手伝えるのは、単純にやりがいがあっておもしろい。それがちゃんと表現できると、面接フェーズで求職者と価値観がマッチした時のWin-Win感とか、ハッピーな感じはたまらないよね(笑)。
もちろん業種や職種やスキルの話はある。キャリアプランもあれば勤務地もあるかもしれない。それは別にお金ならお金でいいんだよ。何でもいいんだけど、大事にしていることが相思相愛になった時の、出会えた時の感じはやはりいい。
やはり初期の、社員数が1桁、あるいは30人未満の時には、そういう存在が会社にとって超重要。背中を預けられるとか、きつくても一緒にがんばろうと思えるとか。だって、何人かしかいない会社って、前途多難だし、行く末が見えないし。
三鈷:はい(笑)。
長谷川:プランどおりに行くこともあるだろうけど「じゃあ、どうやったらうまくいくんだっけ?」みたいな時には、何があっても踏ん張れるかとか、試行錯誤できるかとか、それをご一緒できるかとか。10人〜20人の時の1人の影響力って半端ないので(笑)。それはお互いにとっても、社長にとってもその人の影響力の大きさを痛感するし。
小規模な組織ならではのやりがい
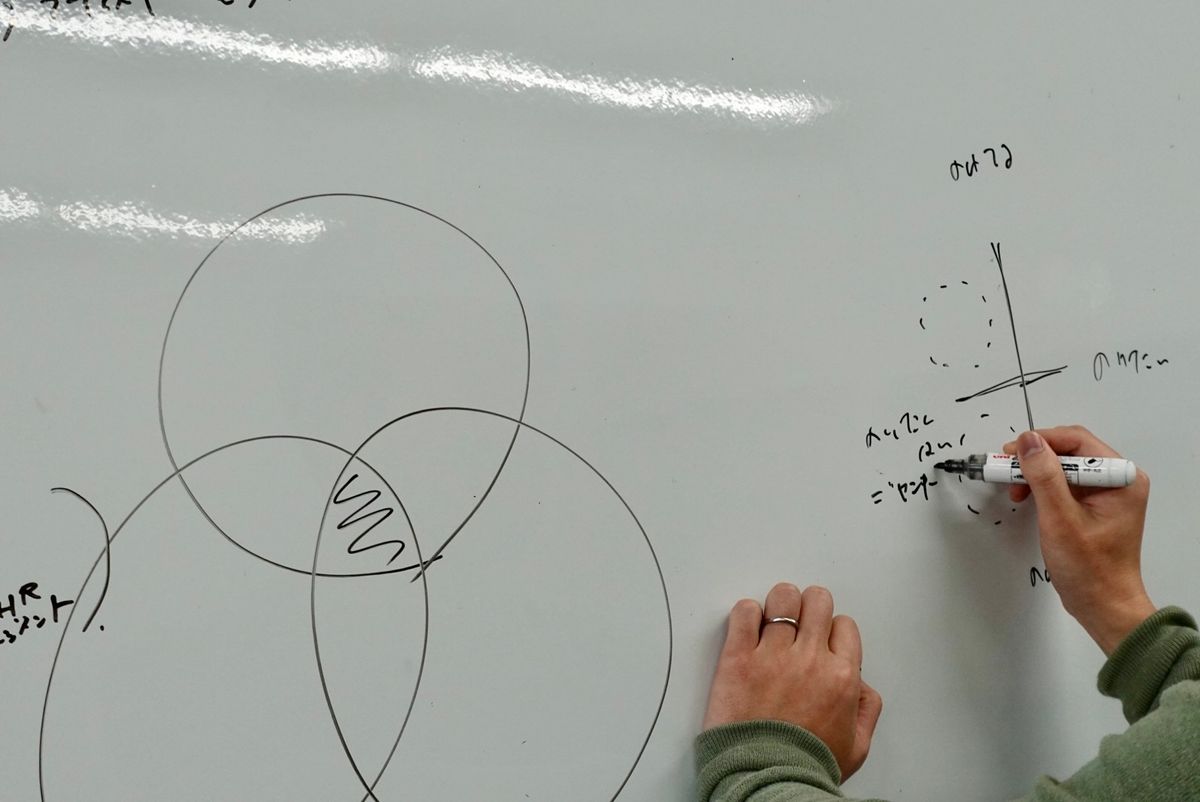
長谷川:逆もしかりで、個人の側に立ったとしても、やはり10人〜20人の時の、自分の組織に対する影響力が大きいフェーズは、責任もあるけどおもしろいと思える人にとってはめちゃくちゃおもしろいはずで、これが一致した時はやはりいいですよね。
もちろん「出会いあれば……」みたいな話で、人生のフェーズとともに大切にしたいものが変わることもある。それは別にしょうがないというか。見越すことはすごく難しくて。
この初期の段階で、例えば3年だけだとしても、それだけ大切なことを共有できる人に出会えるというのは、単純にうれしいと思うし、組織や事業の発展にめちゃくちゃ大きなことだと思うね。
三鈷:長谷川さん自身も採用している側じゃないですか。
長谷川:自社のね。はいはい(笑)。
三鈷:クライアントの採用を担っていらっしゃる方々と、ある種、同じ規模じゃないですか。
長谷川:同じ。我が社は今、4人だからね。
三鈷:そういう点で何か思うことってあるんですか?
長谷川:考えたことなかったけど、思うことか。お互い大事な時期ですよね(笑)。
(一同笑)
採用担当が経営者意識を持つ
長谷川:いや、いつまでも大事なんだけど。わからない。これはもともと単純に中にいて採用をやっていた経験が大きい気がするけど、その時も、ふだんは細かいことを言わないボスから「本当にお前が経営者だとして、採用するかどうか決めるつもりでやれよ」と言われていたんですね。
入社1ヶ月〜2ヶ月目から採用を始めて、求人を書いたりするだけじゃなくて実際に面接もする中で、「俺に判断をゆだねるなよ」みたいな。実際、途中からは内定権も持っていたんだけど。
当然、それは判断が変わることはあったから、そのたびにすり合わせをして採用基準を修正したりとか、コミュニケーションは本当にたくさん取った。
当時も経営者のつもりでやっていたから、会社で採用をやらせてもらう時は、今もこれまでも、そのつもりでやっている。それを忘れないようにしているのが大きい気がする。
三鈷:その時ってどういう心境だったんですか?
長谷川:「やったるわ」という(笑)。
三鈷:(笑)。
長谷川:その前も経営者の近くにいる仕事だったから、経営者の感じていることを自分なりに考えるのはそんなに苦じゃない。前職の時は財務面を含め経営にまつわる情報が全部見える立場だったので、それを見てこれからの事業をどうしていくか、自分で判断する。
もちろんボスとも本当に毎日話す距離感だったから、来年と言わずとも本当に今期の後半、来期、どういうプロジェクトがあって、どういう必要や不足があってみたいなことを、日々感じたり話したりしていたから。
自分事として会社のビジョンも話せるし、プロジェクトについても早く首を突っ込んでいるから話せるし、何が足りないとか何が必要だとか、そこから判断できた。だから苦しさとか難しさはなかったかな。
「仲間を増やしていく喜びを楽しんでもらいたい」
長谷川:採用に関するテクニカルな部分はもちろんある。採用媒体をどこにするとか、予算をこのぐらいかけないとこの職種をこのスケジュールで採るのは難しいとか、今の採用マーケットの潮流とか、計画を立てて基準を落とし込んでいく作業とか。
求人票やスカウトの文章をいかに魅力的にするかの能力とか、採用ページをどう作るかとか、知見を伴うことはたくさんあるから、やったことがない人がやるのはとっても大変。事業を進めながらイチからキャッチアップするのは本当に難しい。そっち側は「プロとやったほうがいい」という気持ちはすごくある。今日話していて思ったけど、経営者の方々は、喜びにあふれたフェーズにおいては希望を忘れずに(笑)。
(一同笑)
長谷川:もちろんそれに伴う苦難もあるけど、仲間を増やしていく喜びを楽しんでもらいたい。社会にとっても「麦わら海賊団」がいっぱいできるのはいいことだから。そこにしかない色でできている海賊団が生まれるといいなと思いますね(笑)。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スピーカー略歴:長谷川 亮祐氏
Otonatachi創業者。高校生から社会人までの個人と、人事・組織領域でスタートアップ・中小企業を支援している。これまで、チームラボ採用・事業開発、ポピンズ社長室・経営企画、衆議院議員秘書、インテリジェンスなど。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 PR
PR