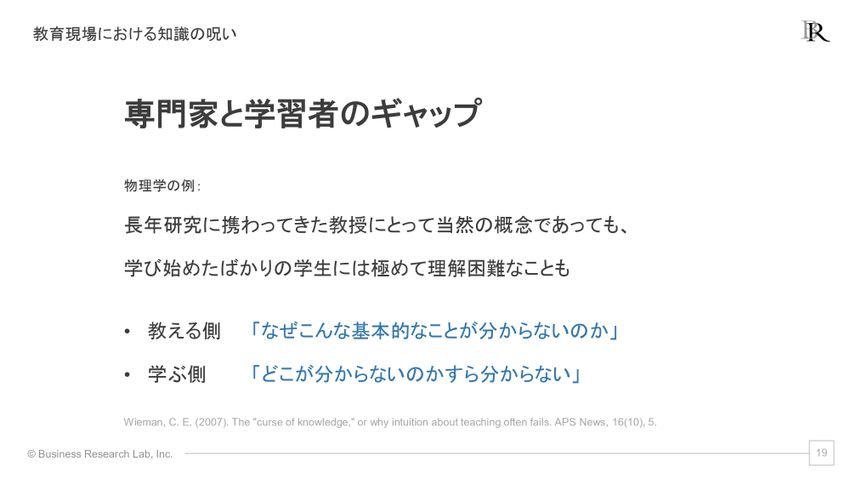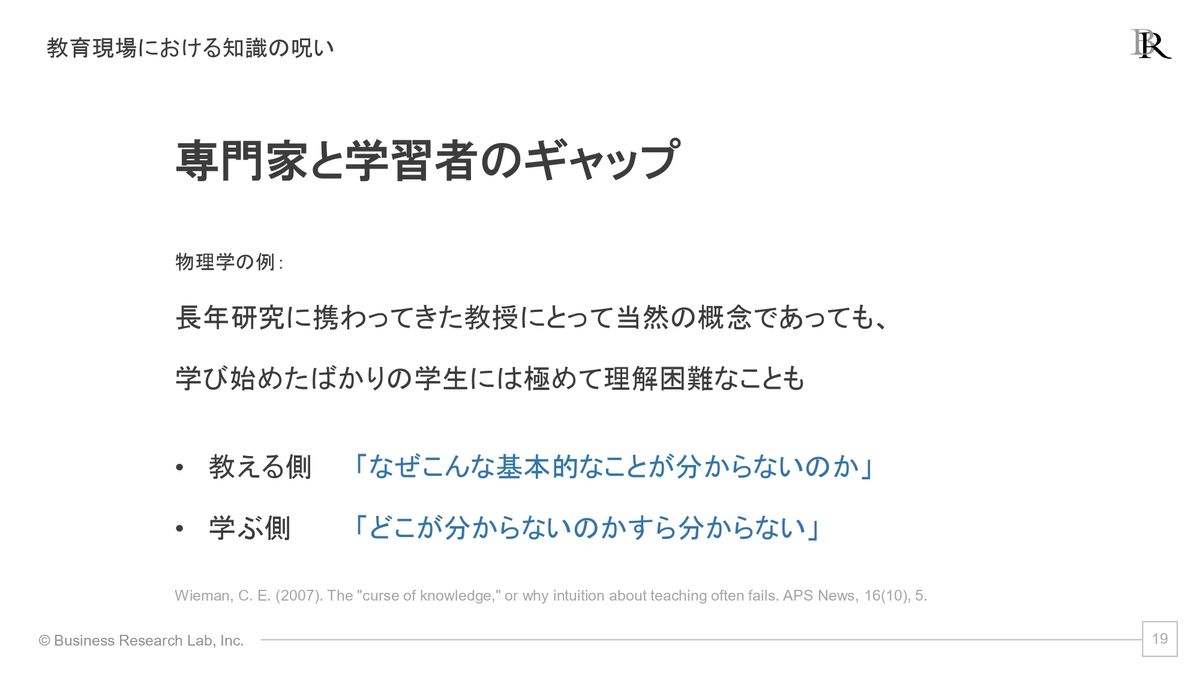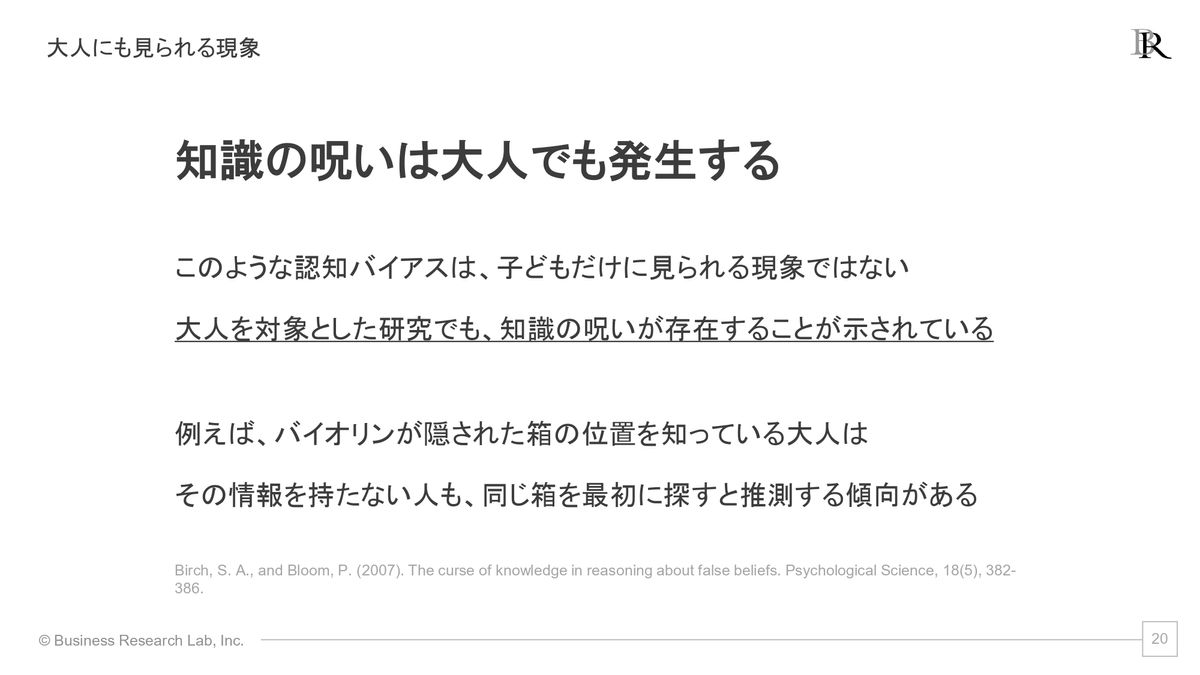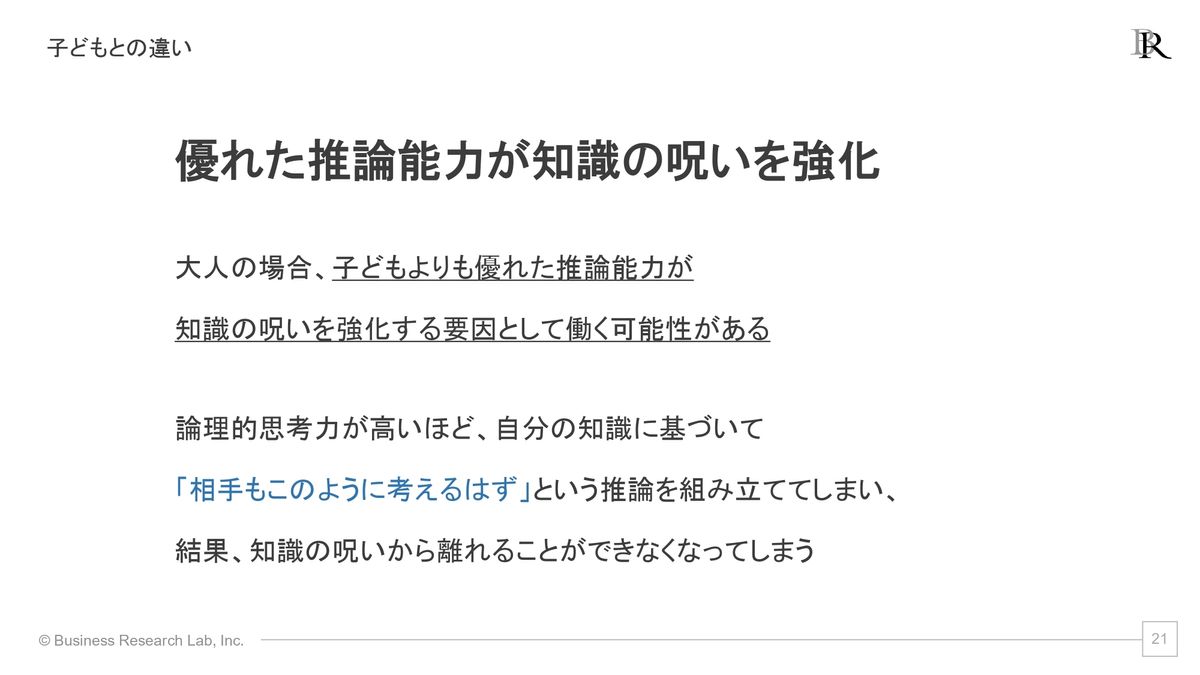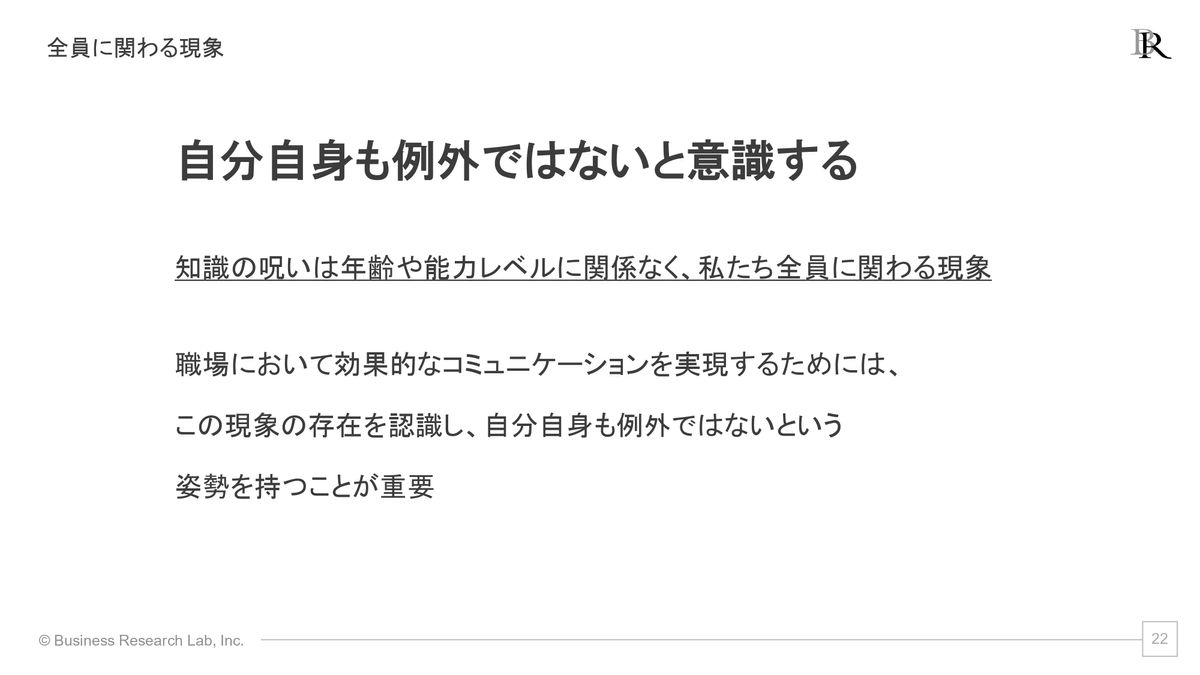教育現場における「知識の呪い」
他の文脈での「知識の呪い」の例も挙げてみたいと思います。こういう経験があるかもしれないんですが、教育現場における「知識の呪い」ですね。ここも専門家と学習者の間の、知識のギャップがやはりあるわけです。
専門家、つまり教授側というのは、たくさんの知識を持っているわけです。長年研究に携わってきているので、ある概念について教えていこうとした時に、それがすごく慣れ親しんだ概念なんですよね。ところが、学び始めたばかりの学生にとっては、なかなか難しくて理解することが困難であったりする。こうしたケースは珍しくありません。
教える側からすると、「なんでこんな基本的なことがわからないんだろうか?」と思ってしまって、学ぶ側としても「いったい自分がどこがわからないのかさえわからない」といった状況に陥ってしまう。このような「知識の呪い」と呼ばれる現象は、教育、企業の中だと人材育成の文脈で認められる可能性があるわけです。
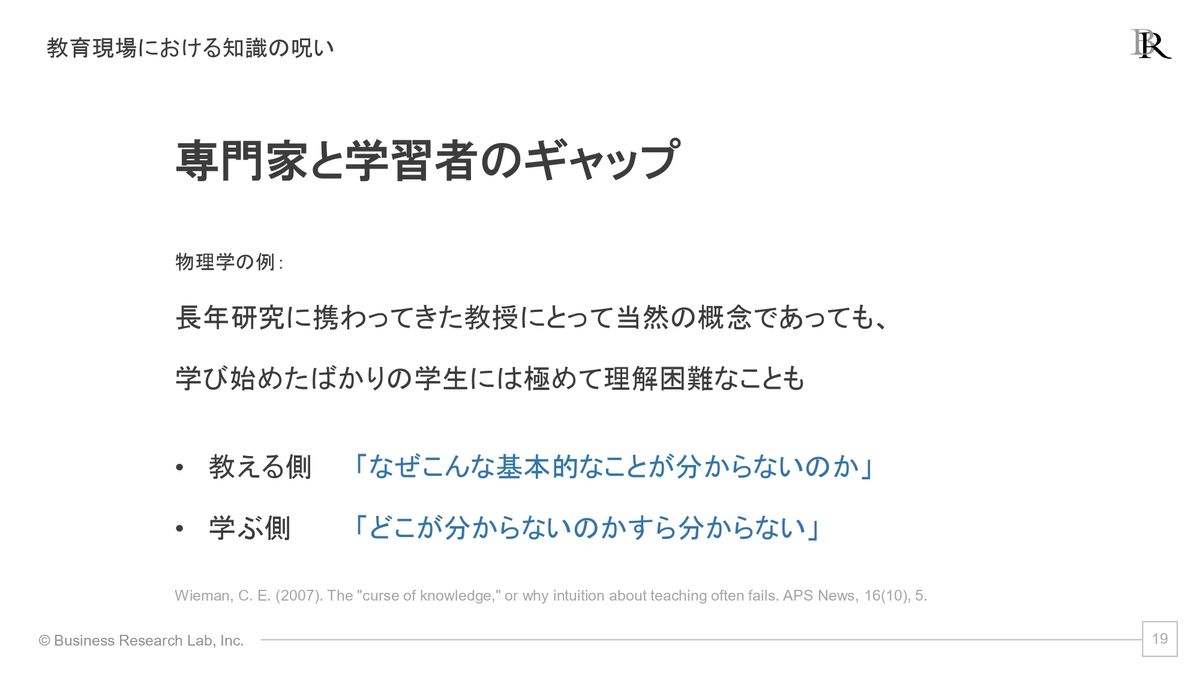
推論能力・論理的な思考力の高さが「知識の呪い」を生む
「知識の呪い」は、子どもだけではないんですよね。大人を対象にした研究の中でも、「知識の呪い」という現象が存在することが示されています。
例えば、子どもと同じような課題を課した実験研究があるんですが、バイオリンを部屋の中に隠すんですね。それをどこに隠したかを知っている人と知らない人を用意します。知っている人は知識を持っている人ですね。
どこにバイオリンを隠したかがわかっていると、新しくやってきた人が「どこにバイオリンが隠されているんだろうか?」と探す時に、「きっと隠された場所から最初に探すんじゃないのか?」と思ってしまうんですね。
実際には知らないので、そんなわけないですよね。探している相手はバイオリンの場所を知らないので、自分だけが知っていて、「きっと隠された場所から探すんじゃないのか?」と過剰に推測してしまう傾向があって、こちらも「知識の呪い」の一種と捉えることができます。
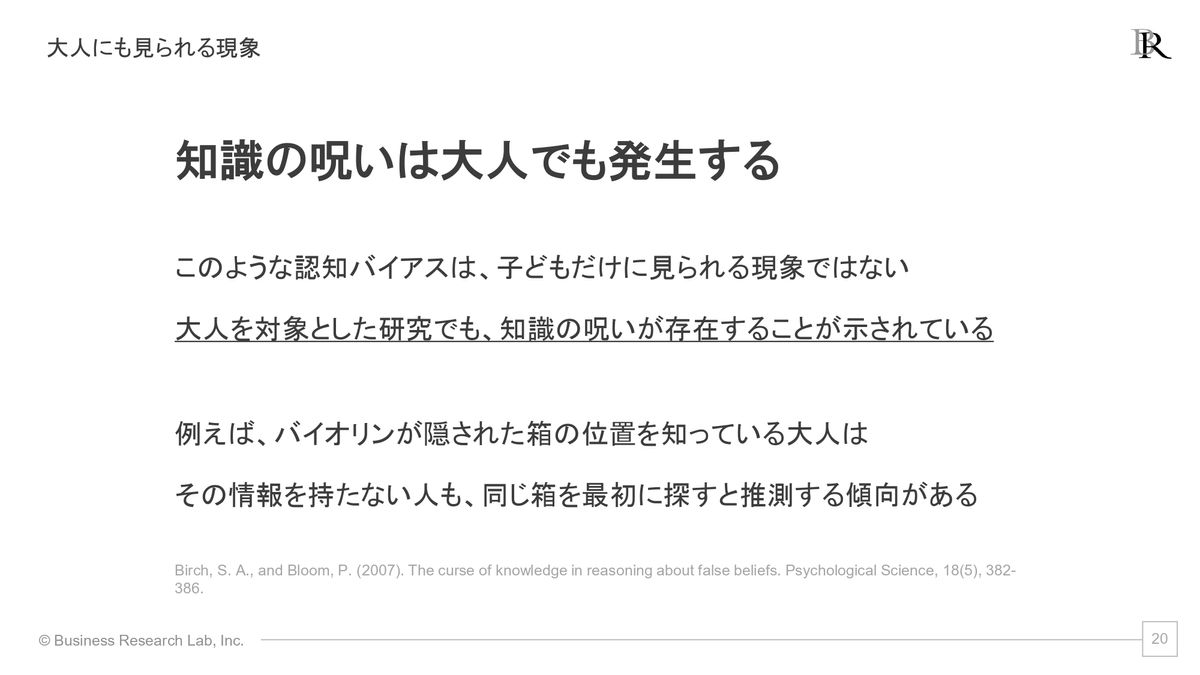
大人の場合、いろいろなことを考える能力、推論能力が子どもより強くなってくるわけです。なので、あれこれ考えられるものだから、「相手もきっと自分と同じように考えるはずだ」と思ってしまう。
例えば大きな箱の中に入っていたとすれば、「バイオリンを入れるには、それなりの大きさがなければならないとすると、最初に探すのはこの箱ではないのか?」といったかたちで論理的な思考力が働いてしまって、「相手もきっとこういうふうに考えるはずだ」と過剰に推論を組み立ててしまい、結果的に「知識の呪い」が発生してしまうことがわかっています。
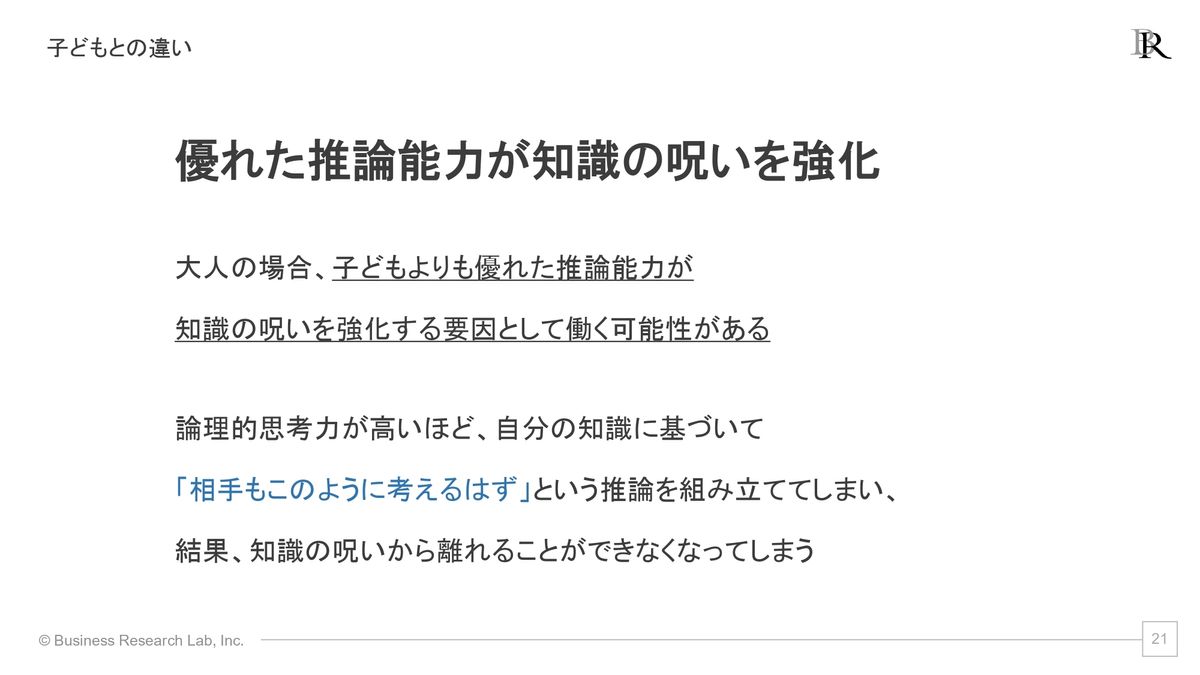
「知識の呪い」は年齢や能力のレベルにかかわらず発生する
したがって、本日紹介している「知識の呪い」は、年齢や能力のレベルにかかわらず発生してくるものなんですね。むしろ能力のレベルが高いほど、「知識の呪い」は発生してくる可能性が高まります。そして、年齢も関係ありません。
ですので、「私たちみんなに関わりのある現象だ」と言えると思います。当然ながら、職場の中でもそういった「知識の呪い」という現象が起こってきても、何ら不思議ではないわけです。
次は、「知識の呪い」をきちんと理解していくことが、どれほど重要なのかをご理解いただくために、「『知識の呪い』がいろいろな場面で顔を出していきますよ」ということを説明させていただきます。
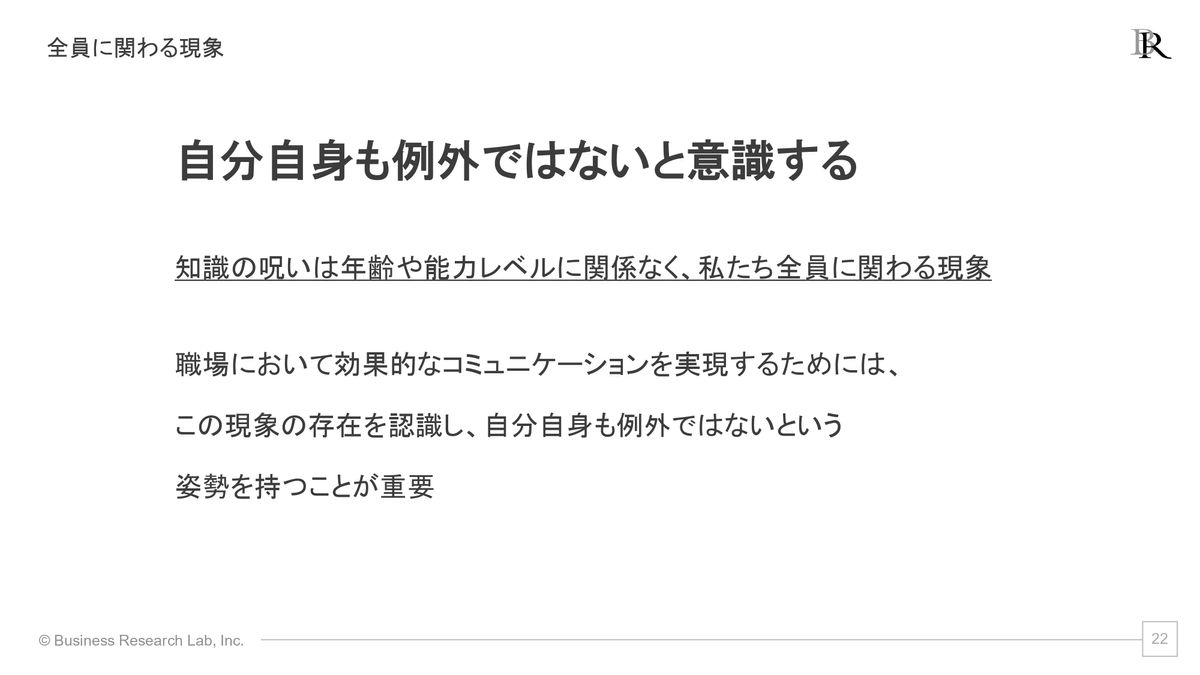
 PR
PR