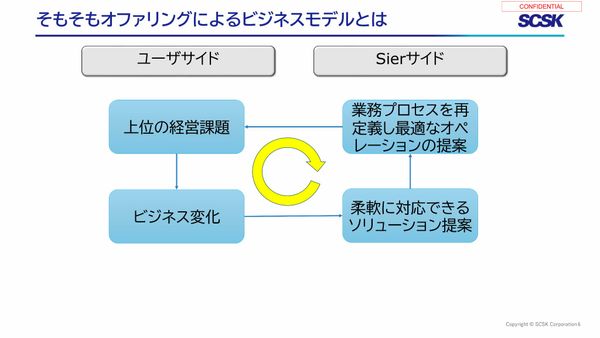 PR
PR2024.12.24
ビジネスが急速に変化する現代は「OODAサイクル」と親和性が高い 流通卸売業界を取り巻く5つの課題と打開策
リンクをコピー
記事をブックマーク

猪瀬直樹氏(以下、猪瀬):今日のゲストは為末大さんです。
為末大氏(以下、為末):よろしくお願いします。
猪瀬:為末さんとは、色んなところでチョコチョコお会いしているんだけど、話したことはないんだよね。為末さんが陸上選手でありながら、言葉でそれを説明しているということが、とても興味深いと思って。Twitterで為末さんが書いているのに気づいていて、運動の選手ってあんまり自分で自分のことを説明しないのに、為末さんが言葉で自分のことを一生懸命説明していて、それがわかりやすいと思っていて。
為末:ありがとうございます。
猪瀬:僕が前に、『言葉の力』という本を出していて、それと同じ中公新書ラクレから、為末さんが『遊ぶが勝ち』という本を出している。このタイトルはどういうことかをおうかがいする前に、皆さんもうご存知だと思いますが、為末さんがどんな人かを説明しようかと。

猪瀬:年表を先にするのではなく、写真をお見せしましょう。2001年の世界陸上で、400メートルハードルで銅メダルをとったことがあります。その時の写真ですね。
その後の2004年のアテネオリンピックです。400メートルハードルってどういうものか知らないかもしれないから説明すると、ハードルがあって400メートルを走るものですね。これが、2004年のアテネオリンピックの時はメダルがとれなかったんですね。
為末:はい、ダメでしたね。

猪瀬:これはもう1つ世界陸上の写真。ハードルっていうのはこんなに足を上げないといけないんですね。2005年の世界陸上でも、再び銅メダルをとっている。世界陸上で2回メダルをとっている人って他にはいない。
為末:トラックでは僕だけです。
猪瀬:短距離選手ではね。そういう為末さんのことを、まずは紹介したいです。
為末:ありがとうございます。持ち上げていただいて(笑)。

猪瀬:こんなにいっぱいあるけれど全部読めないと思うんで、省略していくつか紹介しますと、世界陸上ではじめて銅メダルをとったのが2001年ということで。1978年生まれですから23歳の時ですね。23歳に銅メダルをとった。それで、もう引退したんですよね。
為末:去年の6月ですね。ロンドンオリンピックを目指していたんですけど、予選で敗退したので、引退しました。
猪瀬:その時の年齢は?
為末:34歳ですね。
猪瀬:23歳で世界陸上で銅メダルとって、34歳でも頑張っていたということですね(笑)。日本人はマラソンで優勝することもあるけど、陸上の短距離ではなかなか勝てない。
でも為末さんは、世界陸上で銅メダルを2回もとっている。どうしてそれができたかということと、この本で、「遊ぶが勝ち」という言葉が出てきたが、その2つがどういうふうにつながっているのかを、お聞きしたいですね。

為末:ハードルでメダルがとれたんですけど、はじめて世界大会に出たのが18歳のときで。その時に僕は、実は短距離の選手ではじめて走ってみて400メートルで4番に入ったんです。1番の選手は、はるかかなたを走っていて。100メートルにもすごい選手が一緒にいたんですけど、彼らでも予選で全然歯が立たないと。
猪瀬:他の選手も全然歯が立たないと。
為末:短距離の世界は相当厳しいなというのがあって、その時にたまたま見ていたのがハードルのレースでした。トップの選手でもハードルの前でチョコチョコっとしていたり、高く跳びすぎてフワッとしたり。
それを見ていてこの種目なら工夫したらいけるんじゃないかなと思って、それからハードルに移ったんです。短距離じゃなくてハードルをやりたかったのは、技術の持ち込みようがある競技なので、その点が良かったなと思います。
猪瀬:確かに、100メートルのボルト選手、すごいよね。体はでっかいし。
為末:198センチくらいで。
猪瀬:体格だけの問題じゃないけど、日本人の体格だと、色んなところで勝ちにくいというのはありますよね。それから基本的にアジア人は、長距離は強いけど、短距離は割と弱いと思われてしまいますよね。でも、そこに技術力が入ってくると、中国の……。
為末:劉翔という選手がいて。
猪瀬:2004年に金メダルをとっていますね。110メートルハードルですよね。金メダルとれるじゃないかと、とっている人がいたと。技術的なところを含めると、全体の総合力でこれはとれるという判断をしたのは、すごく自覚的ですね。
為末:ハードルって、どうしても複雑なんです。どちらもハードルが10台あるんですけど、その間を走っていって跳ぶんです。400メートルハードルは間隔が35メートルですけど、その間を13歩という歩数で走る人もいれば、14歩で走る人も、15歩で走る人もいるんです。
猪瀬:400メートルで13個あるの?
為末:いえ、ハードルが10個で、その間を13歩で走るんです。なんですけど、疲れてくると、歩幅が縮まるんで、最初の5台までは13歩で、あとは14歩とか15歩とか、歩数のマネージメントができるんです。
これが、日本はかなり前にハードルで活躍された方たちがいて、データの蓄積があって、このぐらいの身長でこういう体質だとこれくらいの戦略が良いんじゃないかというのが、すでに日本では溜まっていて。
当時はこんなにクリアに考えてはいないんですけど、日本でやるならハードルが1番有利なんじゃないかなって、ハードルを選んだのが1番大きかったですね。単純に足が速い選手でも、ハードルの前でスピードをロスしていて。
僕よりも圧倒的に速くて、400メートルだと2秒ぐらい早くても、一周ぐるっと回ってくると、ちょっとずつロスした0.2秒くらいが蓄積されていって、最後には同時にゴールみたいなこともあったんで、戦いようがあったっていう感じですね。
猪瀬:為末さんは、高校時代から100メートルに出る、抜きんでている人ですけど、抜きんでていても世界との競争の中では、より考えなくてはいけなかったと。そうすると、そこから考えはじめているんですよね。
為末:もともとは100メートルの選手だったんですけど、そのあたりに2つあって、1つはこのまま100メートルでいっても勝てないというのと、もう1つは世界で勝負したいというのがあって。
その頃から、他の選手よりもちょっと早く自分のポジショニングとか、何をやったら勝てるんだろうと考えだしたということですね。
猪瀬:当たり前ですけど、スポーツというのは単純な体力の問題ではない、どうやって自分をマネージメントするか、そういうことだと思うんですね。そこで、為末さんはなぜそもそもスポーツをやるのかと、根本的な問題も考えるようになった。競技生命も長かったし。
為末:時間がありましたから(笑)。
猪瀬:その中でこの本を書いた時に、何を1番言いたかったのかなと。ホイジンガという有名な学者の引用がありますね。
「われわれ人間は常により高いものを追い求める存在であり、それが現世の名誉や優越であろうと、または地上的なものを超越した勝利であろうと、とにかくわれわれは、そういうものを探求する本性を備えている……。そしてそういう努力を実現するために、人間に先天的に与えられている機能、それが遊びなのだ」
『ホモ・ルーデンス』の著者ですね。ここから何を考えたのか?

為末:僕自身は当然スポーツばっかりの人生だったので、スポーツが人生の中では結構大きなファクターだったんですけど、海外をうろうろするようになって、特に南米とかアジアとか回っていくと、オリンピックをあまり知らない国もあったりするんです。
その時に「オリンピックってこんなにすごいんだ」と説明してもわかってもらえなくて、もちろんスポーツなんてやっていないんです。オリンピックってすごく生真面目な祭典だと思っていたんだけど、大きくいうと遊びの祭典で。
人類が自分の体を使って遊んできたものが、高いレベルにはなってきているんですけど、こうやってオリンピックの祭典になったんだとその時に思って。ある意味でオリンピックに対して力が抜けた部分もあって、ある意味でオリンピックに対して新しい勝負だけでない魅力を感じたという。
猪瀬:簡単に言えば、この『ホモ・ルーデンス』のホイジンガは「人生というのは、食うためだけに生きているんじゃないよね」と言っている。動物は餌を探して、あとは自分のDNAを残して生き残ってということ。
そうではなくて、高みを目指すのは人間だけが与えられたものだから、あえて仕事に対しても遊びという。仕事というのは食うためだけど、仕事の中にも遊びがある。向上心みたいなものは動物とは違うよね、ということですよね。
為末:24歳くらいからブログを書いていて、当然珍しかったんですね、当時書くということが。走る時に自分の体がどんな感覚なのかを一生懸命書こうとして、当然書きたい自分がいたりして。
『ホモ・ルーデンス』を読んでいくと、「体で表現することと、言葉で表現するという欲求は同じだ」というところがあって、すごく面白かったんです。
そもそもなんで自分が表現したいんだろうかということが、この辺からピンと来たんですね。それが文化というか、人間が食う寝るだけじゃない、もう一歩先のものを求めているからなのかわからないですけど、そういうことを感じたんです。
猪瀬:走ることって、ある意味苦しいことのように見えるよね、それははじめ感じたところはあったんでしょ? しかし、「待てよ」と思った。そのあたりの気持ちはどういうふうに……。
為末:最初は苦しいことだけど、勝つと賞賛が得られるわけです。それに向かってまた走って賞賛を得て、ということをやってきて、だんだん簡単には得にくい世界に入っていくんです。目的が達成しにくいレベルになっていくんですよね。
猪瀬:世界との競争だからね。すごい奴がいっぱいいるからね(笑)。
為末:そうなんです(笑)。そのくらいから色々と思うようになってきて、シンプルじゃない世界になってきて。勝てるかどうかもわからない、伸びるかどうかもわからないのに、何で自分は走るんだと、走りたいし、自分の力を出し切りたいという欲求を、自分で眺めてみるあたりですかね。
それが自分にとってはものすごく興味深かったんですね。だんだん、アーティストはなんでアートをするのかとか、作家の方はなんで言葉を扱うのということの、そもそものところに興味を持つようになってきて。
猪瀬:そもそも、余分なものなんだよね。
為末:そうなんですよ!(笑)
猪瀬:余分なものなんだけど、その余分なものがあって、はじめて全体だからね。
為末:だから余分なものに夢中になっている自分がいて、でも余分なものがあって人間社会っぽいところがあるじゃないですか。
多くのこういう職業を持っている方は、同じようなことにぶつかると思うんです。食っていくのには必要ないけれど、社会の方がそのエッセンスを必要としていて、それに自分は人生をかけているという。その構図自体がすごく面白いなと。
猪瀬:はじめは無意識にやっているけれど、そのうち「これって自覚してやっていいことなんだよね」と思っていくようになったんだよね。
スポーツを楽しむのは当たり前だけど、日本人は苦しむみたいなイメージを持っちゃっているところがあるから、できなかったらダメじゃないかと叩いちゃったり、そういうことがちょっと起きがちだったね。
為末:本当におっしゃる通りで、この本を書きはじめた時は、体罰の問題とかなかったんですけど、年末になってそういう話が出てきた時も、日本のスポーツがどこか生真面目で、勝負のためだけにあるみたいなのが気になっていたんです。
最初のうちは体をなんとなく動かしたいから動かす、そのうち競争になったから競争するやつもいれば、その中でもそうじゃなくて淡々と遊ぶやつもいる。それくらい豊かで、はじめてスポーツなんじゃないかなと。日本は、すこし、勝ち負けと若い人たちが鍛錬と自分の身をこう……。
猪瀬:修行みたいな感じに思われちゃったんだな。
為末:反対サイドのものが、そろそろ次の時代で出てきてもいいんじゃないかなと。
猪瀬:僕なんかは中学の運動会以来走ったことなんかないんですよ(笑)。走ると、息がハアハア言ってくたびれると思っちゃっているから。
為末:でも走られたんですよね?
猪瀬:週末にテニスぐらいはやっていましたけど(笑)。作家だから原稿を夜中書くし、ふと2年半くらい前に、家の周りを300メートル走ってみたんです。ゆっくりゆっくり。300メートルいけるから、500メートルくらいできるかなと。
それからだんだん走るようになってきて、1年後に去年の2月の東京マラソンに出たんだけど、時間内に走らなくてはならないから、最後まで走れるかなと。5キロごとに関門があって、タイムオーバーになっちゃったら縄引っ張られて終わりだから。
僕みたいに全く素人でも、最初は家の周り300メートルでハアハアとなって、苦しいと思ったんだけど、そのうち、だんだんやっていくと、「あれ、気分転換になるな」とか、「頭整理できるな」とか、走ること自体も風景も面白いし、そうなってくる。それまでは僕、大変なものだと思っていたから。
為末:農耕の時代ではなかった昔、人間が猟をしてきた時代に、運動しながら相手がどう動いてくるかを考えられる種だけが生き残っていたという研究があるんですけど。ある一定数の脈拍の中で、人のクリエイティビティが発揮されるということを研究している方がいるんです。そういうものが、もしあったりすると面白いなと。
猪瀬:そうかもしれないよね。農耕生活より前の段階で、動物に追いかけられたり、追いかけたり、木の実が落っこちそうになってとろうとしたり、色んなことがあったはずだよね。動きと思考が一緒になっていたわけですよね。
確かに、僕なんかも机に座って原稿を書くのは1つの仕事ではあったけど、体のバランスとか全体を考えると、スポーツという分野が改めてあるんだなと。前からテニスとか色々やってはいるけど、ひたすら続けていると僕も良い面が分かってきて、スポーツは楽しいものなんだと。
走るっていうのは苦しいだけでなく、楽しいことなんだと、だんだん考えができていく。東京オリンピック・パラリンピックを目指して、スポーツって楽しいぞと言えるようになって。

為末:色々なパターンのスポーツがあっていいと思うんです。さっきの『ホモ・ルーデンス』の本の中でも、ものを書くということが、活字で表現していたんですけど。アメリカでトレーニングをしていたことがあって、短距離選手って足を上げ下げして前に進んでいくんですけど、彼らは「push」と「pull」という言い方をするんですね。
猪瀬:「push」は押すで、「pull」は引っ張るだよね。
為末:「pull」で足を引っ張ると、「push」が地面を押すと。そう言われたんでそのままやっていたんですけど、そうすると、その場で足上げみたいになるんです。でも進んでいくんです、アメリカ人は。「push」と「pull」を繰り返して、進んでいく。
猪瀬:為末さんは、その場で静止して「push」、「pull」をやると受け取った。
為末:はい。でも彼らからすると「push」、「pull」で徐々に進んでいくんです。それでコーチに怒られて。だって、「push」、「pull」ってその場でやることじゃないかと思いながらやっていたんです。
猪瀬:自然に出ちゃった方が良いってこと? だってトレーニングでしょ? トレーニングでも自然に出ないとだめだということ?
為末:それで、日本人に同じ動きしようと思うと、押す、引くじゃなくて、「乗り込む」とか「挟む」という表現になると同じ動きになるんです。「乗り込む」というのは足の上に体がグーッと乗りこむということで、「挟む」というのは後ろ足で挟むという動きになるんですね。
為末:骨格上、日本人の骨盤の形って引き擦り易くなっているんです。擦り足みたいに。そうすると、「pull」という動きが剣道でも柔道でもなくて、引き上げるという動作はないんですね。
猪瀬:擦り足っぽい感覚だったということですね。
為末:乗り込んで、足を擦って前に出すということをやると、彼らと同じ「push」、「pull」の動きになって。
猪瀬:乗り込んで擦るようにすると、彼らと同じ動きになるということですね。そうじゃない場合だと、日本人は?
為末:「push」と「pull」だとその場で足踏みする形になるんです。乗り込んで、この足を挟むという動きにすると、アメリカ人の「push」と「pull」と同じ動きになるんです。だから、言葉と身体的な動きの違いに、その時気づいて。そのまま訳しても違うという。
猪瀬:そうか。英語を翻訳して指導を受けたら、違う概念になっちゃったということだよね。
為末:スポーツ通訳というか。
猪瀬:言葉1つで違うことになっちゃうからね、外国人に指導してもらう場合も。そういうところから他の人に伝えるときも、自分自身に伝えるときも表現を考えた言葉を選ぶようになったということだよね。
為末:その時から、動きに関する言葉のセンスというか、考えはじめた気がします。
猪瀬:それは何歳くらいの時?
為末:24歳の時ですね。
猪瀬:世界陸上でハードルで3位になって、さらに次に飛躍しようとしていた時期ですね。
為末:海外へ出て行こうと思って、やっていた時期ですね。それより前は、なんとなく自分とハードルだけの世界だったんですね。これを超えていくぞという。
そのくらいから、走っている自分を客観視して、それで説明できるところもあって。自分の姿を見る自分はそのくらいからです。ハードルを跳ぶとき、抜けるように跳ぶんですけど、普通に跳ぶんじゃなくて、1歩深くグッと入ってから跳ばなくちゃいけないんです。
その時に、ハードルの上にものがあって、それを自分の体で重いものを蹴っ飛ばすように跳ぶという表現をすると、何となくその動きに近くなったりするんです。
猪瀬:ハードルの上になんかがあって、それを膝で、グッとやるような感じだと。
為末:そうすると最後の1歩がグッとなるんです。
猪瀬:わかりますね。左の踏み込みが入って、右の足がまっすぐに伸びるというイメージができるんですね。
為末:あと、サーカスの輪っかをくぐるように、1回小さくなってと。
猪瀬:輪の中をこういう風に小さくなって通るという。そういうふうに表現していると。
為末:だから「滑りぬける」ほうが「すり抜ける」よりハードルでは的確だなと。地面も走るというより、弾むみたいな感覚が良いとか。自分が「弾んで」いって最後ハードルの上を「滑りぬける」みたいな。
猪瀬:弾んでいって。最後小さなサーカスみたいな輪にスッと入って、なんかありそうなところにピュッと指す。
為末:昔はバンと飛ぶんだよ、みたいなひと言だったのが。
猪瀬:コーチがそういう言葉を使ってくれたらよかったね。当たり前だけど、今度はあなたがコーチになれるよね、今の表現で説明できるから。
為末:そういうものと日本の指導者の話って似ているのかなと。言語をうまく扱えないとどうしても体罰的になりますよね。
猪瀬:確かに、うまく表現できなくてイライラして「何やってんだ、バカ」というタイプの指導者がいるとすると、もうちょっと表現を考えればいいかもしれないですね。
関連タグ:

2025.01.16
社内プレゼンは時間のムダ パワポ資料のプロが重視する、「ペライチ資料」で意見を通すこと

2025.01.15
若手がごろごろ辞める会社で「給料を5万円アップ」するも効果なし… 従業員のモチベーションを上げるために必要なことは何か

2025.01.20
組織で評価されない「自分でやったほうが早い病」の人 マネジメント層に求められる「部下を動かす力」の鍛え方

2025.01.14
目標がなく悩む若手、育成を放棄する管理職… 社員をやる気にさせる「等級制度」を作るための第一歩

2025.01.09
マッキンゼーのマネージャーが「資料を作る前」に準備する すべてのアウトプットを支える論理的なフレームワーク

2025.01.14
コンサルが「理由は3つあります」と前置きする理由 マッキンゼー流、プレゼンの質を向上させる具体的Tips

2025.01.07
1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.21
言われたことしかやらないタイプの6つの言動 やらされ感が強く他人任せなメンバーを見極めるチェックリスト

2017.03.05
地面からつららが伸びる? 氷がもたらす不思議な現象

2015.11.24
人は食事をしないとどうなるか 餓死に至る3つのステップ
特別対談「伝える×伝える」 ~1on1で伝えること、伝わること~
2024.12.16 - 2024.12.16
安野たかひろ氏・AIプロジェクト「デジタル民主主義2030」立ち上げ会見
2025.01.16 - 2025.01.16
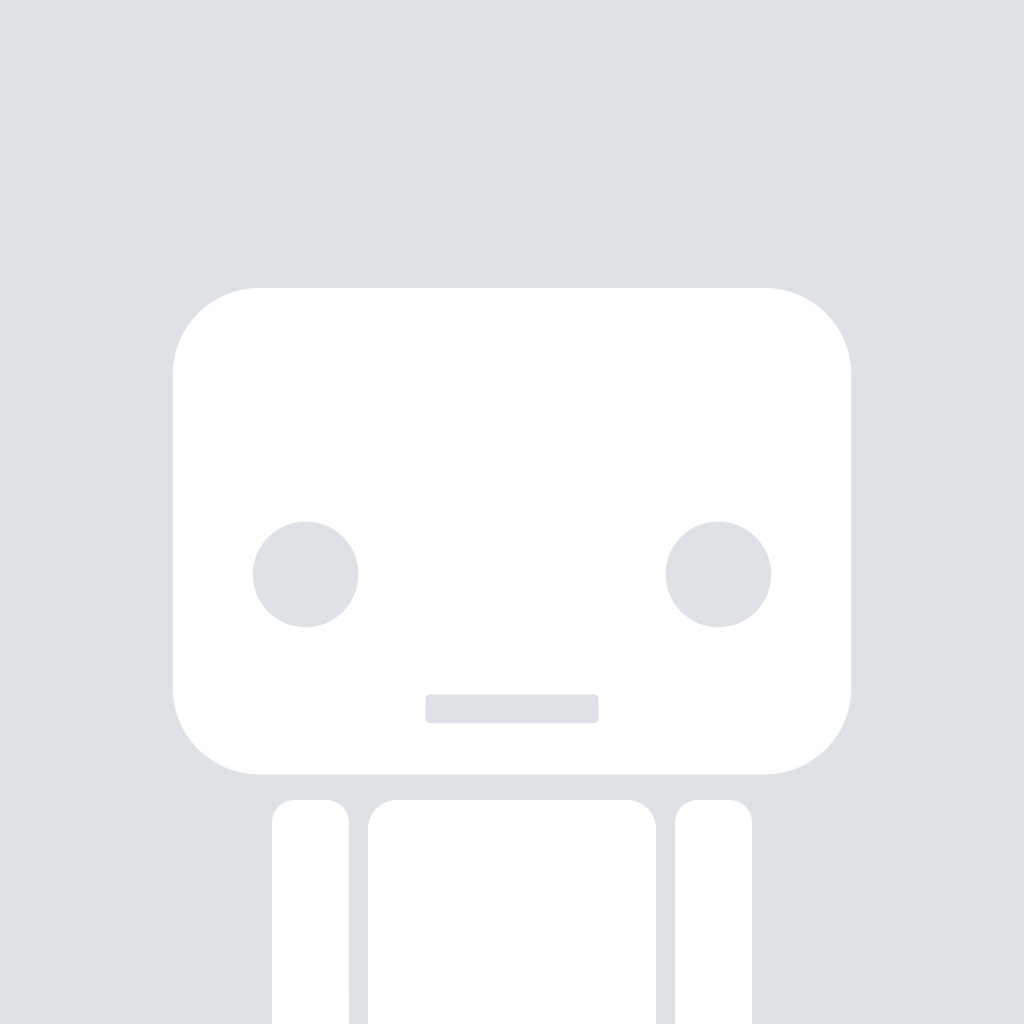
国際コーチング連盟認定のプロフェッショナルコーチ”あべき光司”先生新刊『リーダーのためのコーチングがイチからわかる本』発売記念【オンラインイベント】
2024.12.09 - 2024.12.09
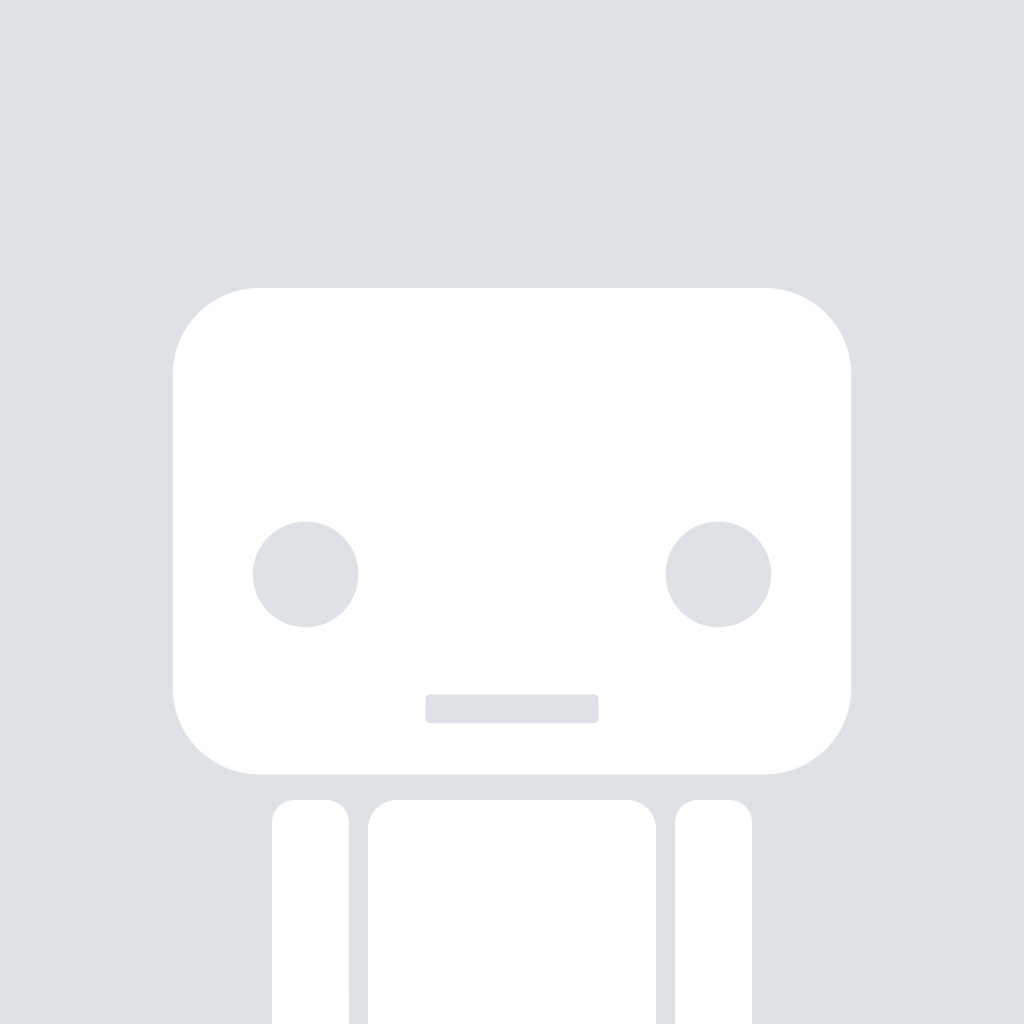
NEXT Innovation Summit 2024 in Autumn特別提供コンテンツ
2024.12.24 - 2024.12.24
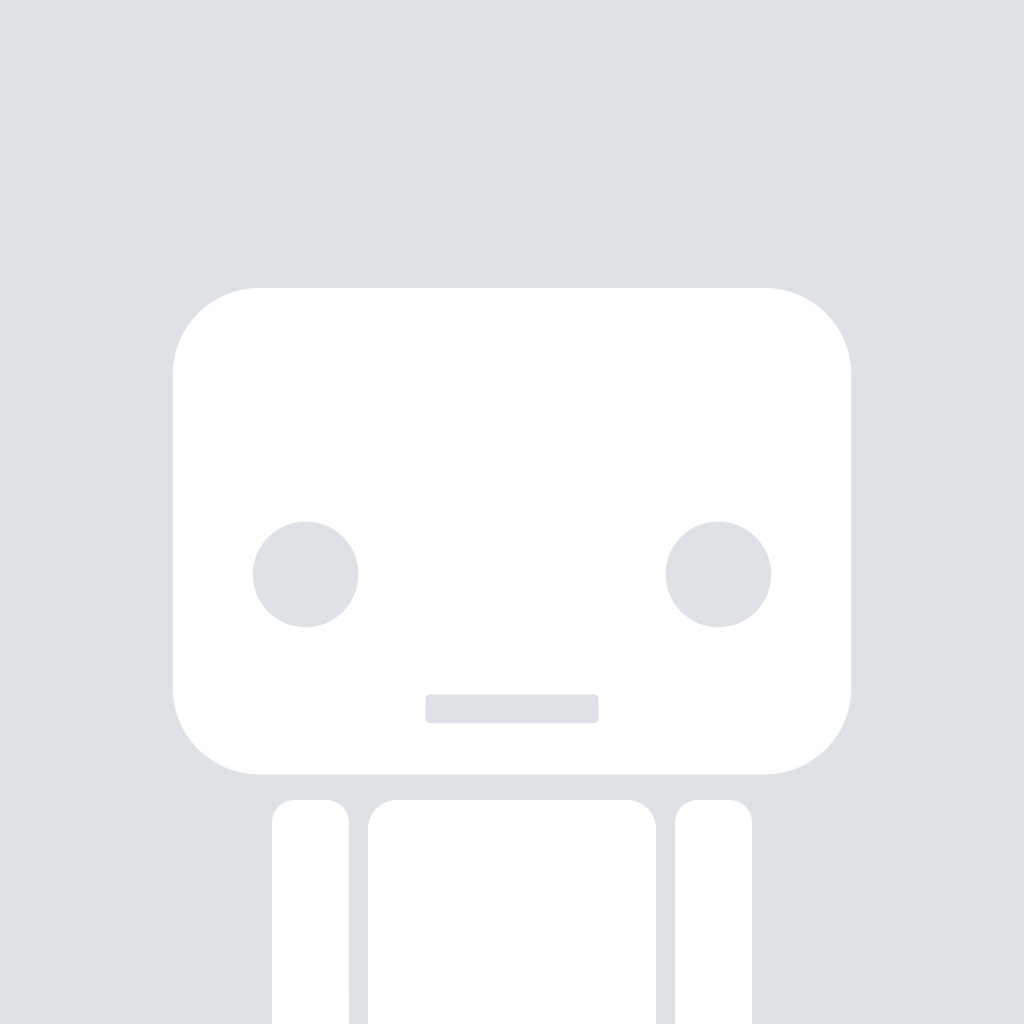
プレゼンが上手くなる!5つのポイント|話し方のプロ・資料のプロが解説【カエカ 千葉様】
2024.08.31 - 2024.08.31