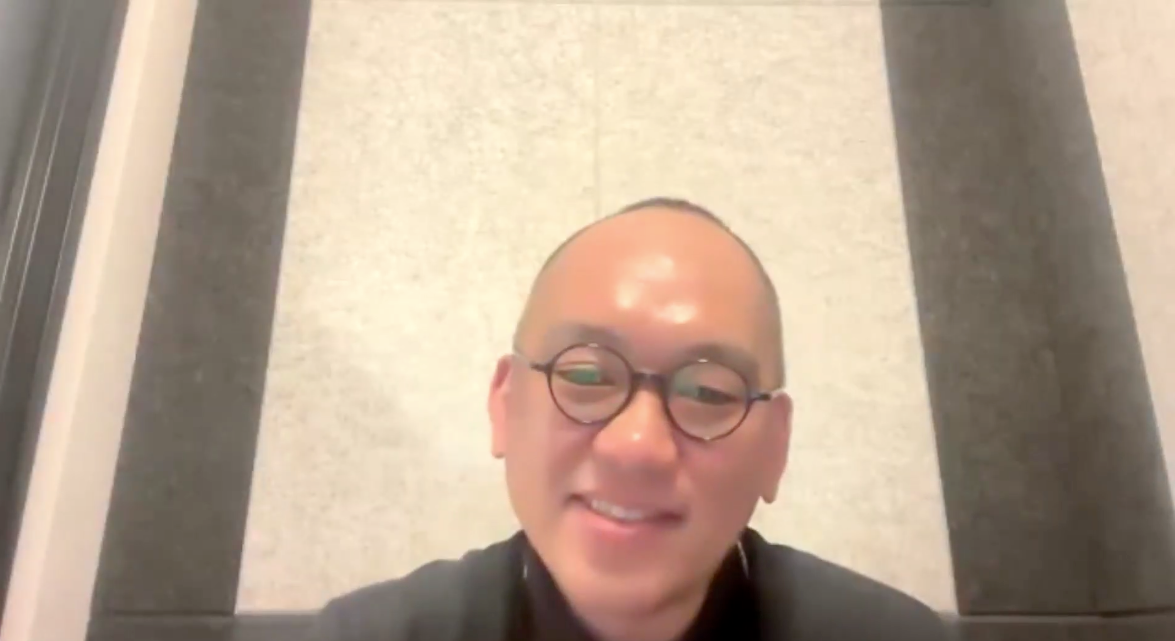【3行要約】・新規事業における「賢い失敗」とは何か。多くの企業が失敗を奨励する中、チャレンジとギャンブルの違いが重要な論点となっています。
・ミズノ出身の清水氏は「失敗から何を学び、どんな意思決定ができるかを意識する」ことが成功への鍵だと語ります。
・ 企業文化として失敗から学ぶ姿勢を根付かせるには、真に自分事として痛みを伴う意思決定ができる環境づくりが必要です。
前回の記事はこちら チャレンジ = ギャンブルではない
大長伸行氏(以下、大長):じゃあ、次にいきましょう。「『賢く失敗する』について、とても賛同します。企業の多くは失敗を奨励するようにしています。間違ってはいけないのは、チャレンジとギャンブルの違いかなと思って聞いていました。チャレンジ = リスクを取ってでも得られるものがある。これが賢く失敗するという意味です。ギャンブル = 偶然や運に依存。準備に計画がないという意味です」。
ありがとうございます。ここについて思うことはありますか? チャレンジなのかギャンブルなのか。三冨さんにも、プロトタイピングの専門家としての意見もちょっと聞きたいなと思うんですが。
清水雄一氏(以下、清水):私からしゃべってもいいですか?
大長:どうぞ。
清水:ありがとうございます。さっき、守屋さんからのご質問の時に「1個しゃべりたいことがあったのに忘れた」と言っていた話がまさにこの話だったなと思っていました。

「失敗がちょっとずつうまくなってきた」の中で、「何をもってうまい失敗だったと思えるようになったのか?」の話で言うと、「1つのチャレンジで得られることが何なのか?」をきちんと意識するようになったところです。
それと、「どこまでいったらこれを失敗認定できるのか?」というラインをきちんと意識しながらやるようになったことだと思っています。
「成功するのか失敗するのかはやってみないと本当の意味ではわからない」となった時に、「これが失敗したらどんな意思決定ができるんやったっけ?」とかもきちんとセットで考えるのが必要になってくるんだろうなと。それがない状態の中で「失敗しました」は、さっきのギャンブルみたいなお話かなと思うので。
さっき三冨さんからご質問いただいた、「今の検証って何をやろうとしているんですか?」って、撤退の意思決定ができるから今チャレンジしているみたいなお話だと思っています。
「『ここが、はまらん』となったら別の方法を探さないといけない」の中で、「今はまったら勝ちにいけるところで一番強いところはどこなのか?」を探しながら、そこの挑戦にリソースを振りましょうという話がようやくちょっとずつでき始めてくる。
今までたくさん失敗して得た教訓じゃないですけど、「その失敗や成功をもって、何の意思決定ができるの」かを意識しながら活動するのがポイントなのかなと思いました。
うまくいっても運用面が課題になるケース
大長:ありがとうございます。じゃあ、次にいきましょう。これはおもしろいなと思うんですが、「トライして、最初は状態が良くて成功かと思ったんだけど、徐々に失敗だなと思った事例はありますか?」という(笑)。
初めはいい状態だけど、だんだん「思ってたんと違う!」みたいなので、徐々に目減りしていくような失敗。これはどうですか?
清水:どうでしょうね。事例が今パッと浮かばないですけど、あるかな?
大長:初めは使ってくれるんだけど、すぐ解約されるとかリピートが起こらないみたいなのはどうでしょう?
清水:はいはい。確かにそういうのがあるのか。足型の計測チャネルとか、さっきの「小売店でのなんちゃらかんちゃらですごく良かったな」みたいなことをご紹介したかと思うんです。けれども「あれを継続的に、システマチックにやっていきましょう」となった時に、一定の難しさが出てくるシーンがあります。
1つ目の取り組みでやった時って、「本当に現場の形に寄り添うかたち」ではないですけど、「運用しやすいようにやりながら、かなりアナログにデータを溜めた」みたいな話をしました。その段階においては「かなり前に進んだな」という手応えがあったと。
ただ「これを効率化していこう」と考えた時に、ちょっとだけオペレーションが変わってしまうようなことをお願いした時に、「いけるやろと思っていたところがぜんぜん前に進まん」みたいな話はあったりしましたね。
なので、連携しながら足型を採らせてもらうというコアの部分に関しては確認が取れて成功だったんですけれども、その後の実装していく部分において、「あっ、この方法じゃ無理なんか? どうなんや?」みたいなところもあったかなと思います。今思い至ったのはそれですかね。
ピボットする領域の選び方
大長:ありがとうございます。じゃあ、せっかく質問をくれているので、残り3つを5分ぐらいでいき切っちゃいましょう。
「初期ローンチモデルでうまくいった時に、ピボットする先として次にどのような領域を選ぶのがよいと思いますか?」ということです。例えば清水さんは、今の事業はサッカーシューズでローンチしましたけど、「次に広げていく時にどんな領域を選ぶと思いますか?」という質問はどうですか?。
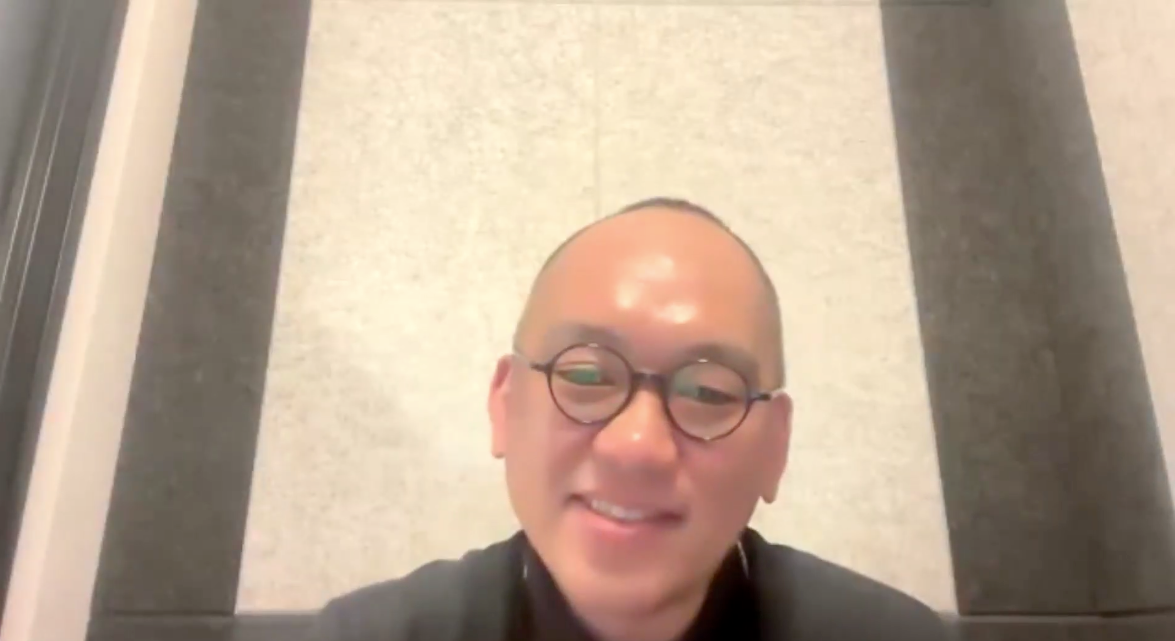 清水
清水:具体の話でいいんですかね?
大長:これは質問を書いてくださった方から声でフォローがもしできたらお願いします。
質問者3:よろしくお願いします。ちょっと質問とは違って、うまくいかなかった時のパターンをお聞きしたいんですね。「やはり初期ローンチモデルがうまくいかないパターンって多いよね」という話を聞きました。僕も今、新規事業をやりながら、ちょっとうまくいっていないんです。
その時に、「ピボット先としてどっちに振っていくのがいいのかな?」とすごく思うんですよね。お客さんを取るために要望に寄っていくのがいいのか、それとも軸をぶらさないほうがいいのか。ちょっとご経験の中から、「そのへんって、こうやるのはどうだろう?」というのがあれば。
最初のローンチで見える結果があるか
清水:ありがとうございます。私もさっき初期ローンチモデルがこけたという話をしました。けれど、その中でも顧客との関係性など得られるものがあったなと思っています。
初期モデルを作った時に比べたら、持っている情報量は増えたなと思っています。その中において最善の選択をするしかないかな、というのがお話を聞いて思った話でした。
本当に対象とするユーザーさんや課題そのものを変える必要があるのかが、ファーストローンチされたプロダクトの中で何かしら見えてきていらっしゃるんじゃないかなと推察します。
となった時に、課題や顧客とかを大きくピボットする必要があった場合には、今つながりがある方や採れてきた情報が、「もしかしたら活用しづらいのかもしれないな」となった時に分岐しそうな気がすると思いました。
なので、今持っている情報や採れてきた情報が使えそうだとしたら、近い領域でやるのがいいんじゃないかなと思います。そこの採れた情報から「もう狙っていた課題感がまったく機能しなさそうだ」という話なのであれば遠いところに行く必要があります。
質問者3:そうですね。やはり初期ローンチモデルの中でいろいろ情報は集まったかなと思っているので、それを活かせるのかをポイントとして考えていきたいと思います。ありがとうございます。
清水:ありがとうございます。
靴の片足売りと言えば………
大長:じゃあ、あと2ついきましょう。次はちょっと感想というかいいコメントをくれています。「靴の流通センターで左右別々のサイズの靴を売っていて、それを買った人がいて笑っちゃったんだけれど、自分のバイアスだと気づきました」という。
清水:いいですね(笑)。
大長:靴の流通センターがすでに察知していたという。
清水:ありがとうございます。別々のサイズを買って……そういうことですね。そうですね。なんか片足売りって、けっこう……。
大長:(笑)。
清水:わかる人はわかるかと思うんですけど、けっこう治安の悪いとされている街で、露天商の人が片方だけ靴を売っているみたいな笑い話があるんですけど、「(足が左右別サイズの人がいるという課題に対する)本質的なアプローチやな」みたいな話になったらいいなと思いますね。
なのでこれが笑い話じゃなくて、「あっ、そのほうが素敵だよね」となっていったら、世間的なバイアスを含めて、我々はいろいろと変えていけたのかなと思えます。なので十数年先にはそんな世界になっていたらうれしいなと思いながら事業を進めていきたいなと思いました。
大長:ありがとうございます。じゃあ、ちょっと最後。「自分の足に合った靴を見つけることは確かに難しいと思います。各自の足に合った靴を1足ずつ作るのは1つの解決方法だと思いますが、逆に各自の足に合うように変形する靴を作る方法を検討されたことはありますか?」。要は靴のほうが変形していくということです。
「素人質問で恐縮ですが、スキーブーツの加熱成形のインナーや低反発マットレスのようなものを想像しています」ということです。
 PR
PR