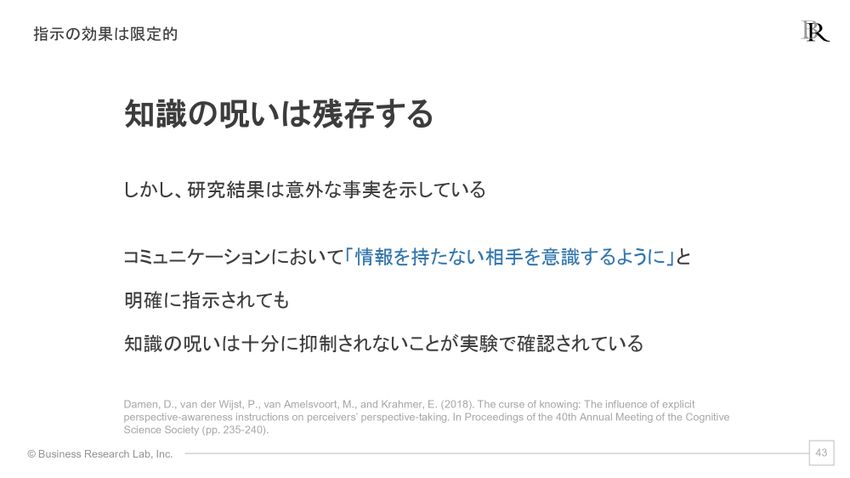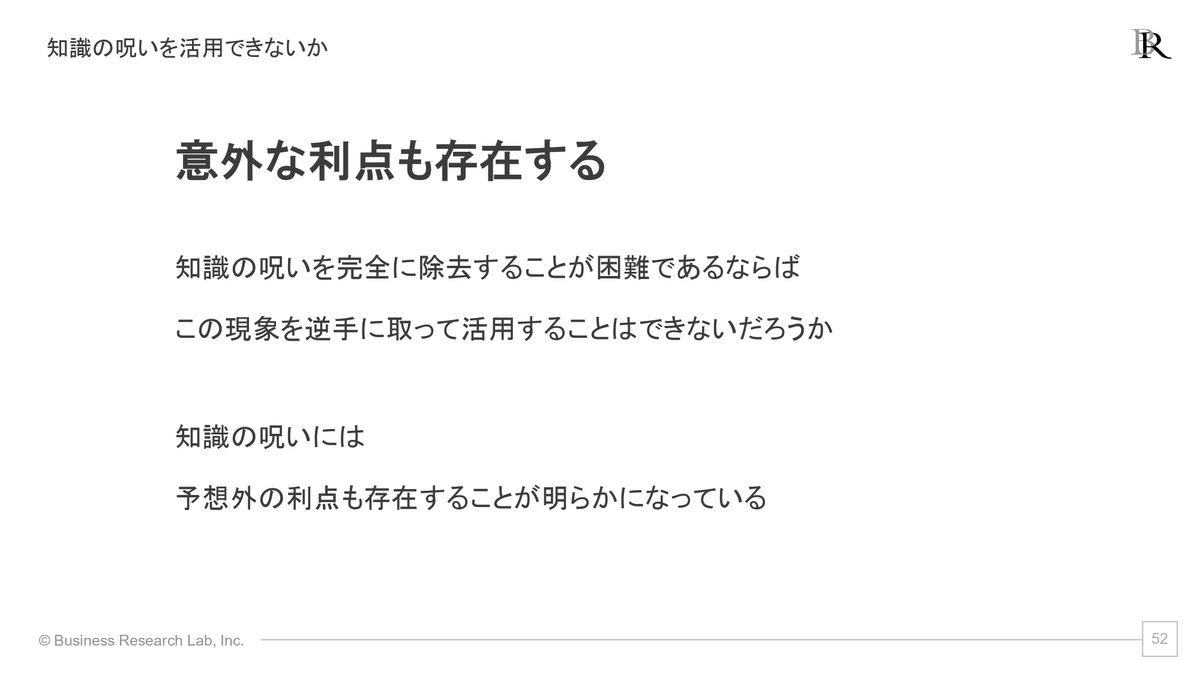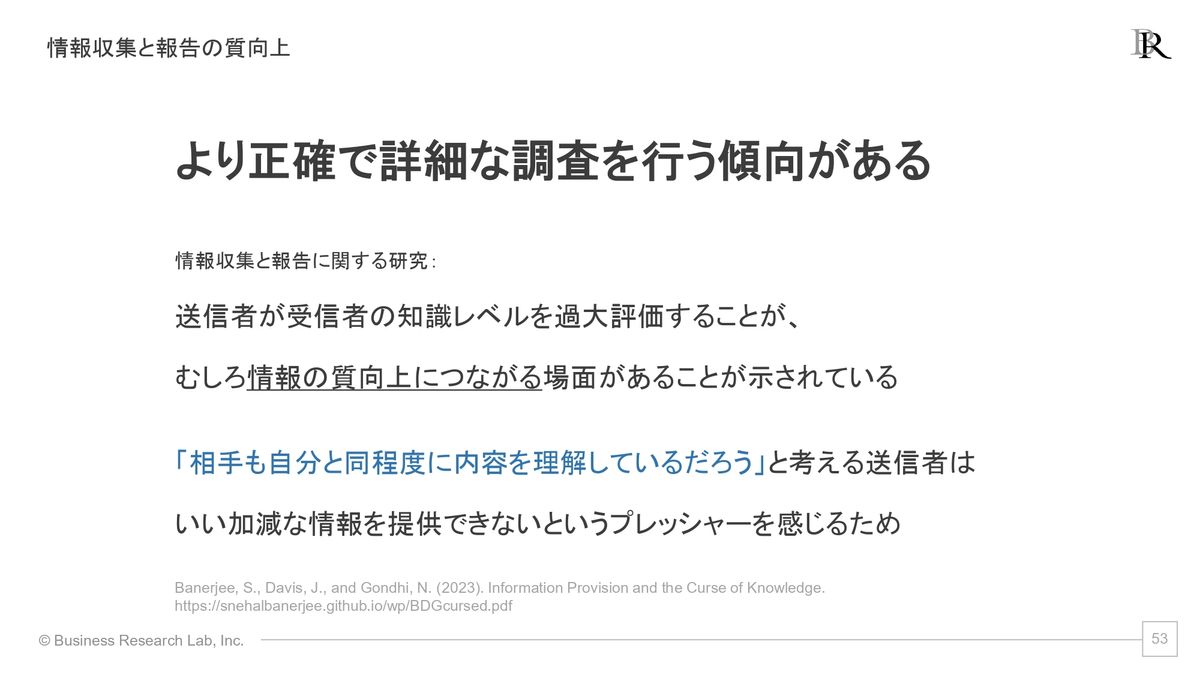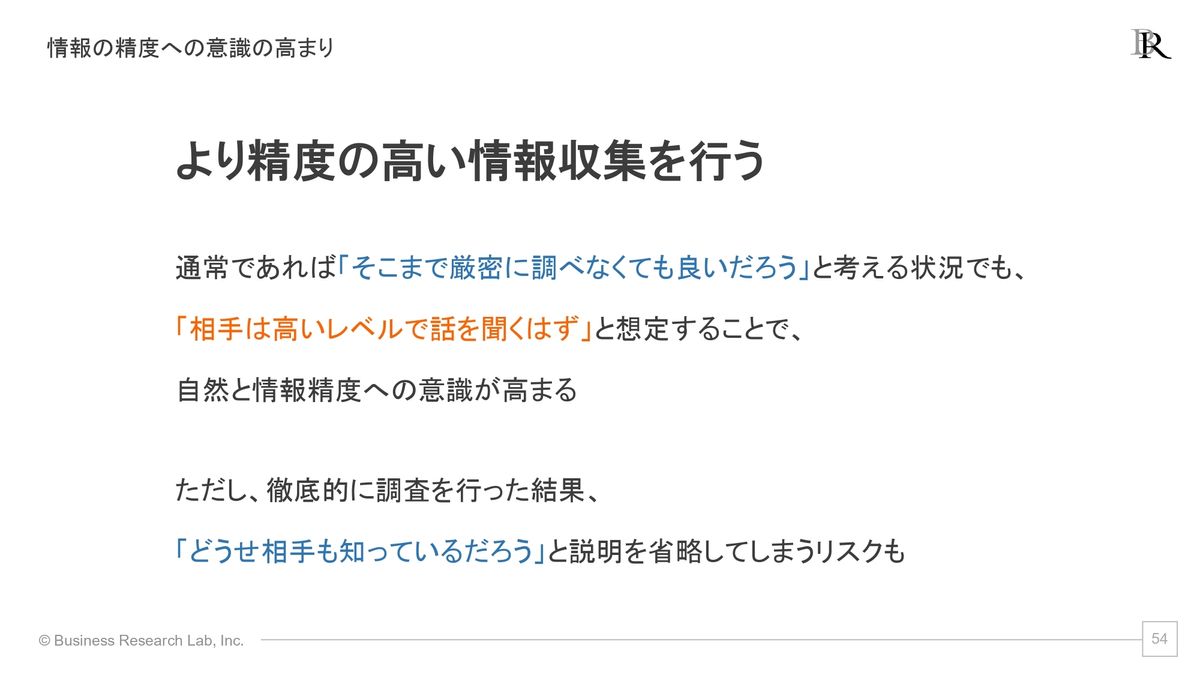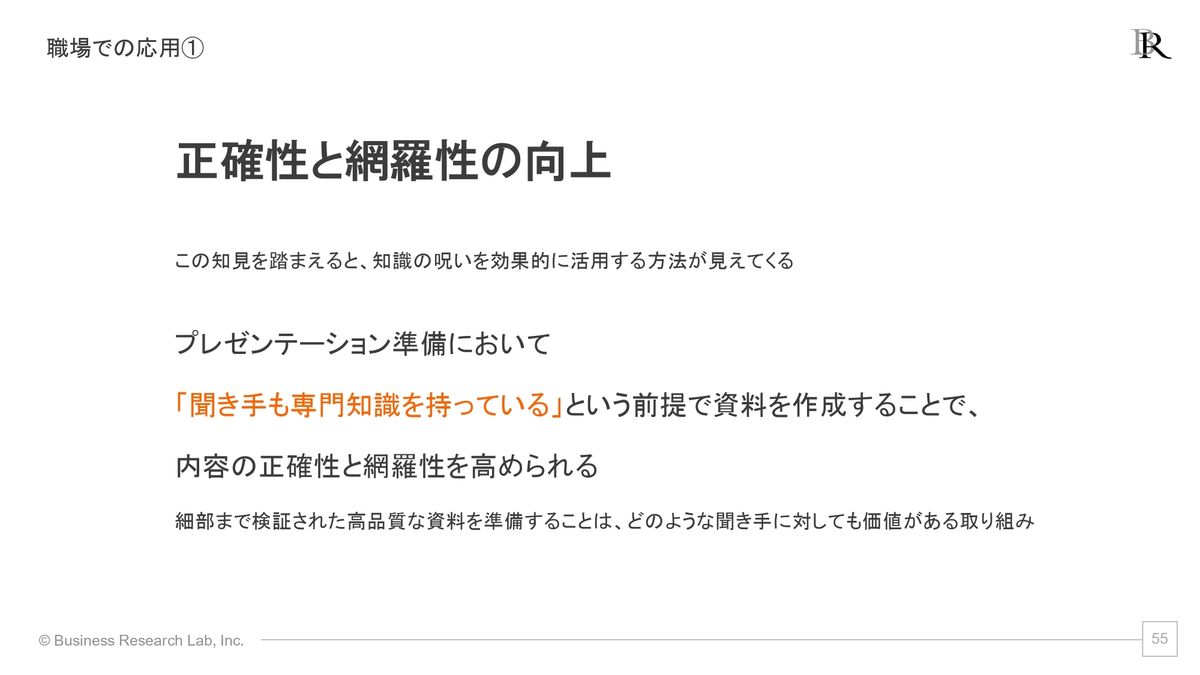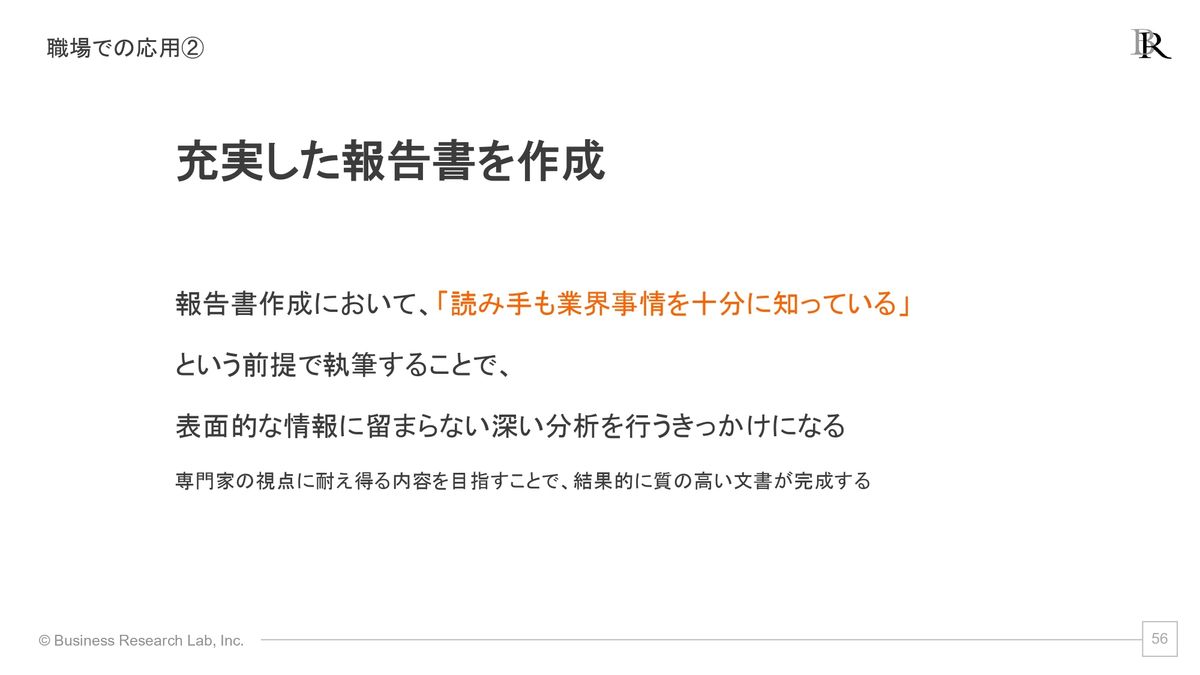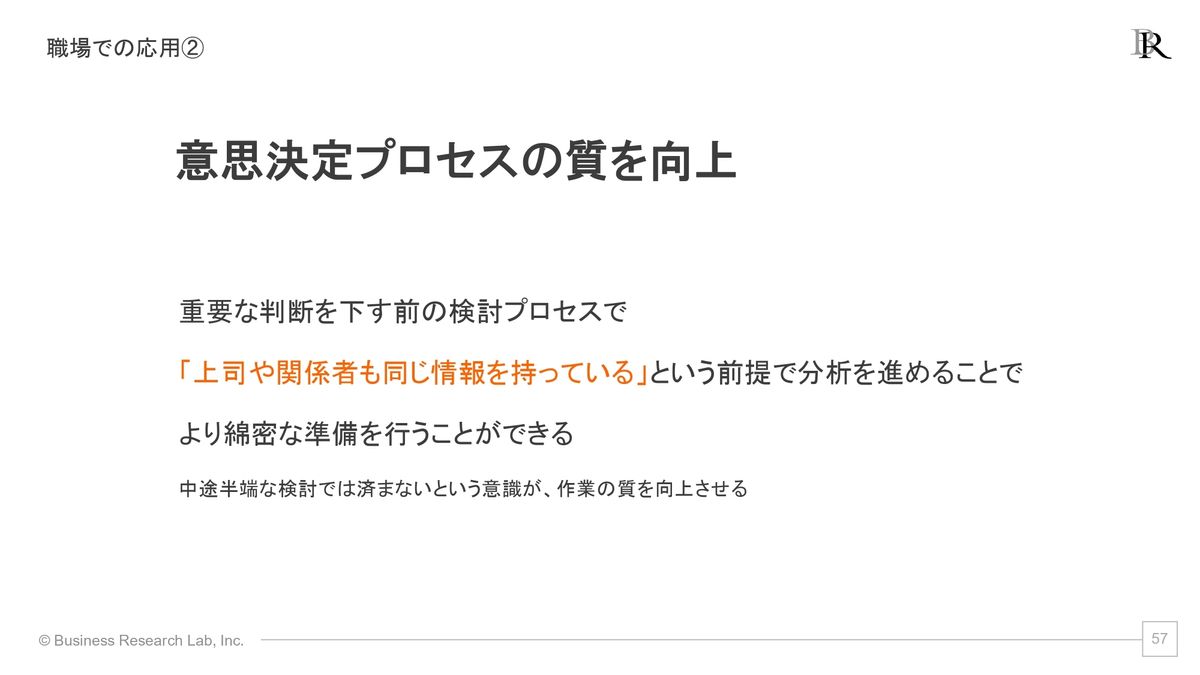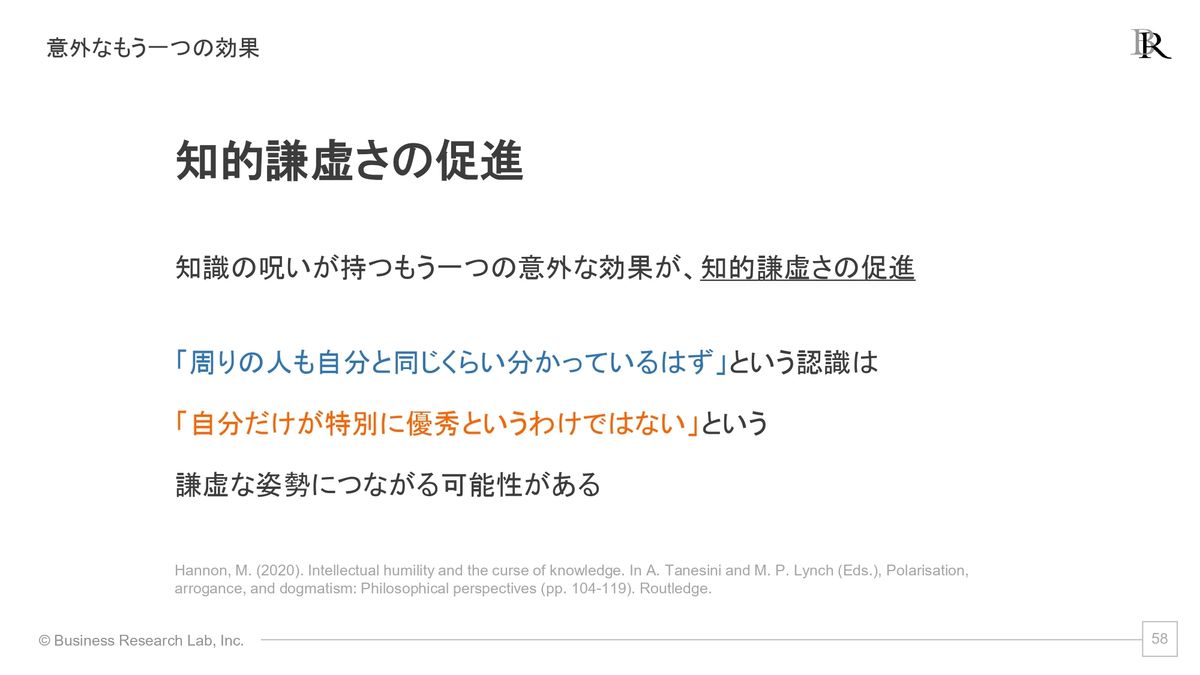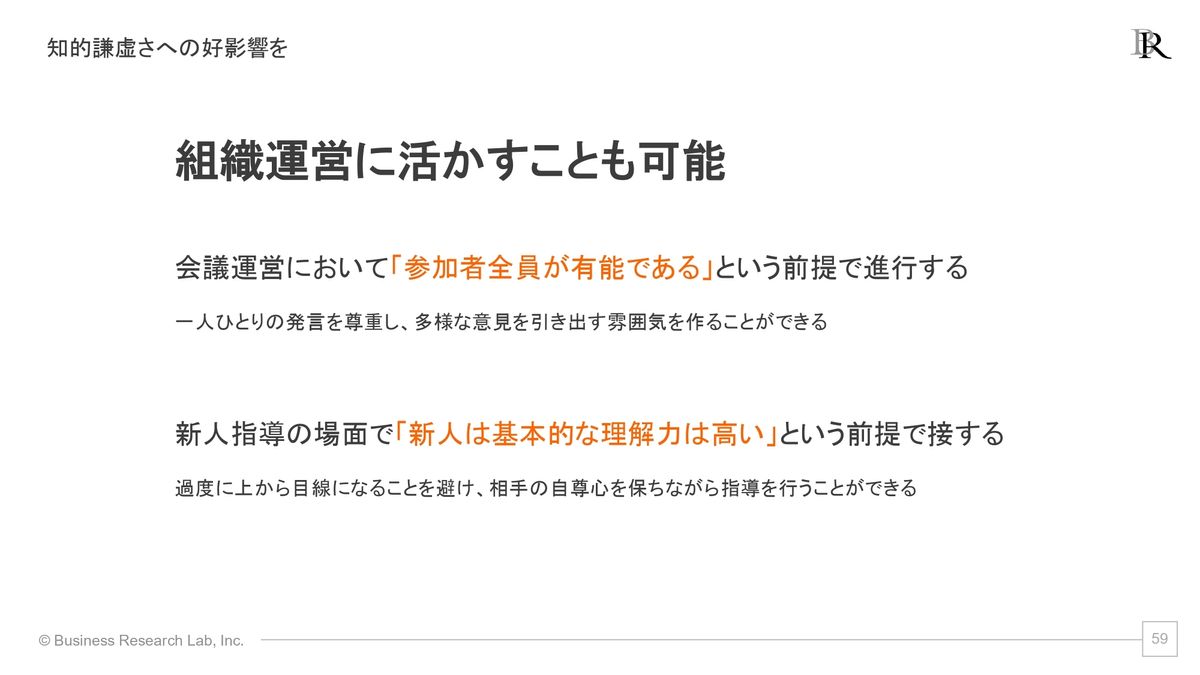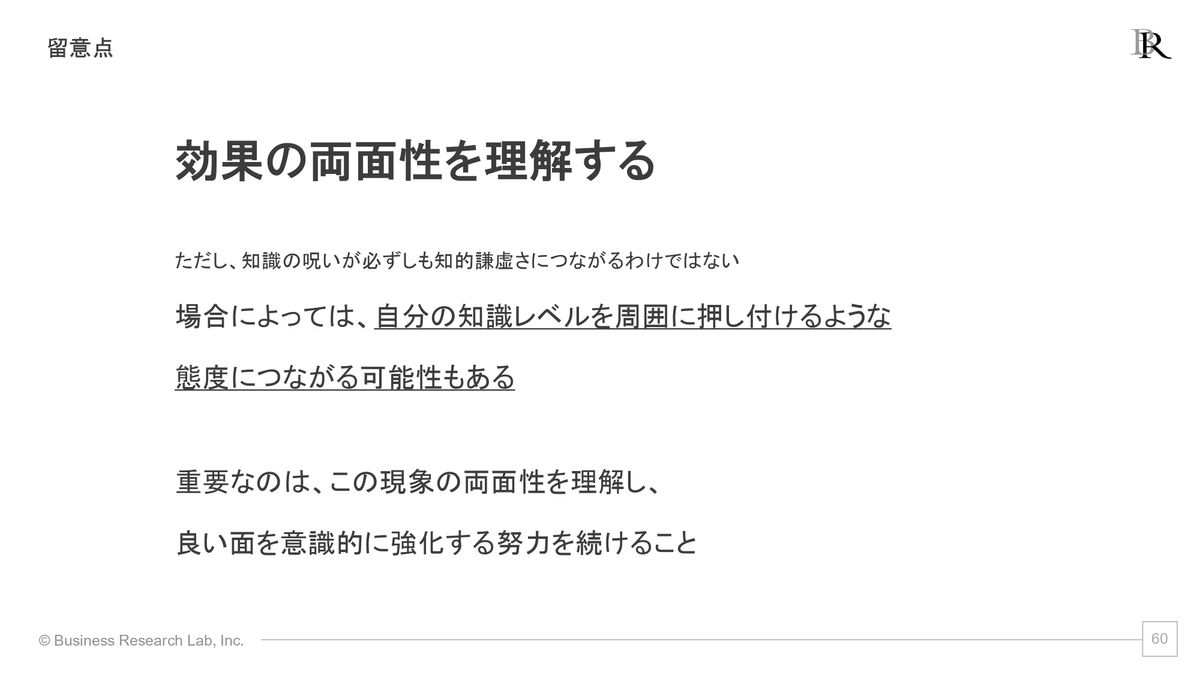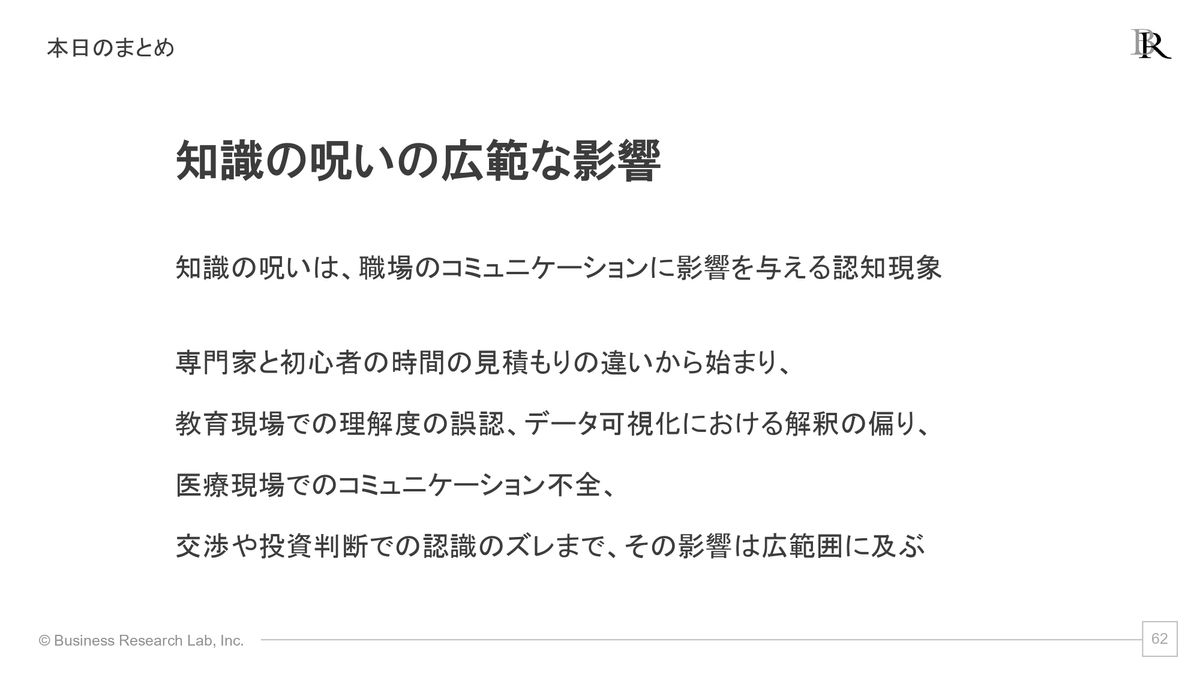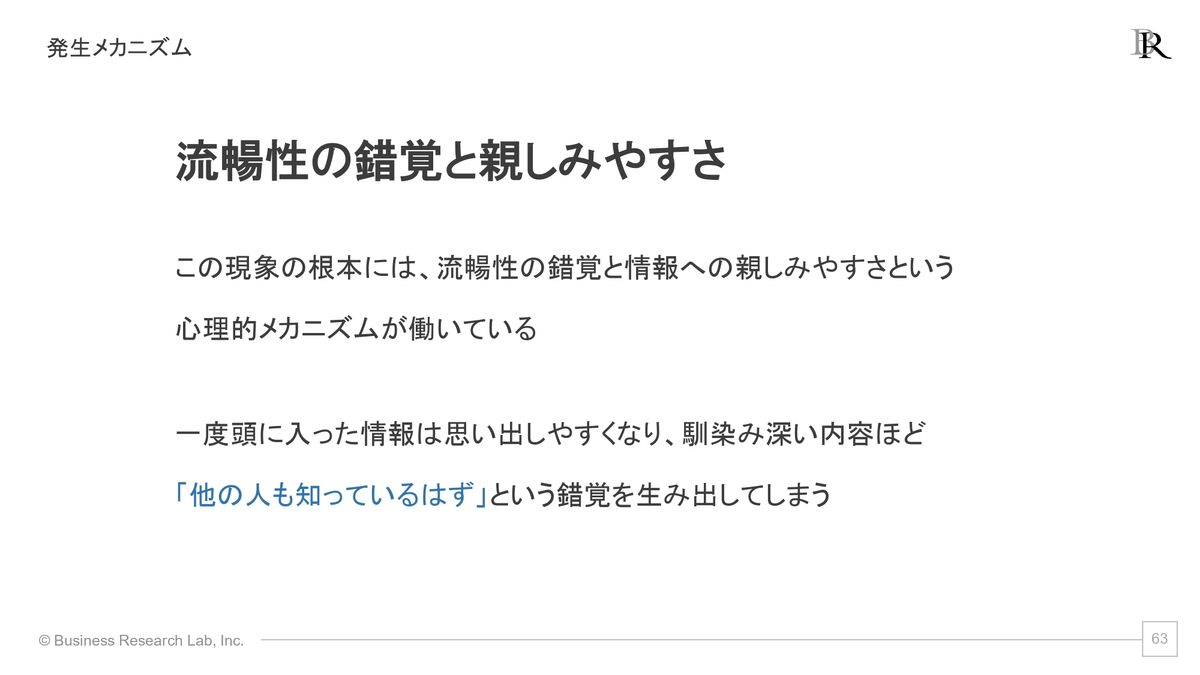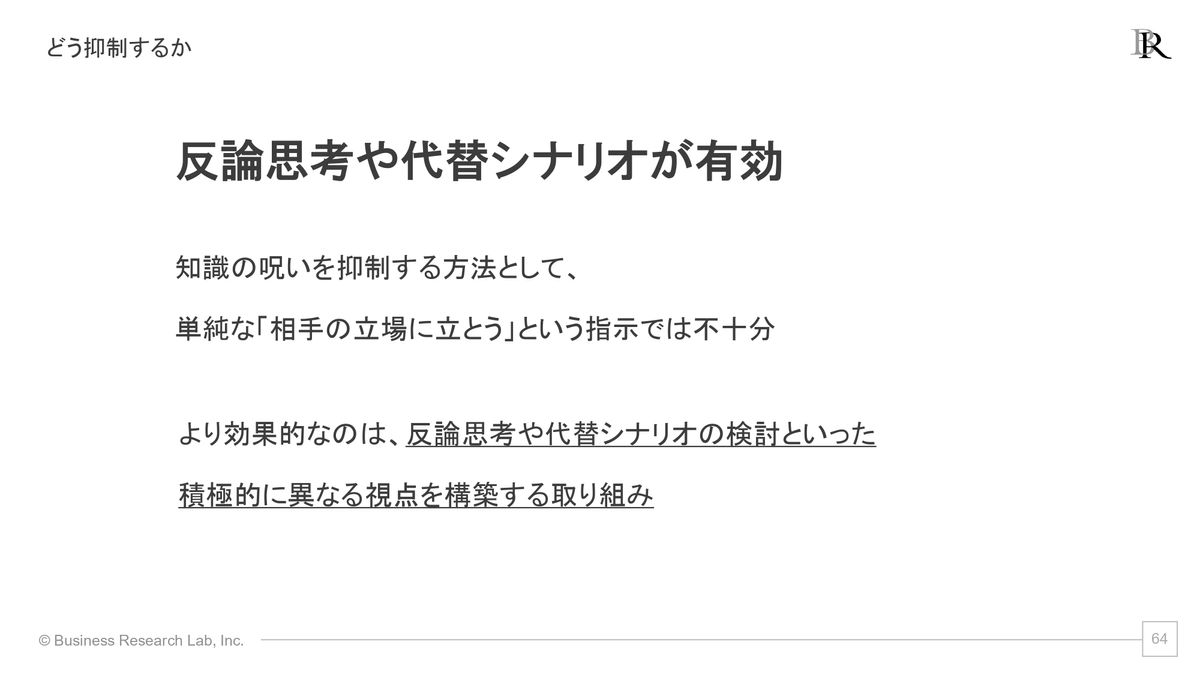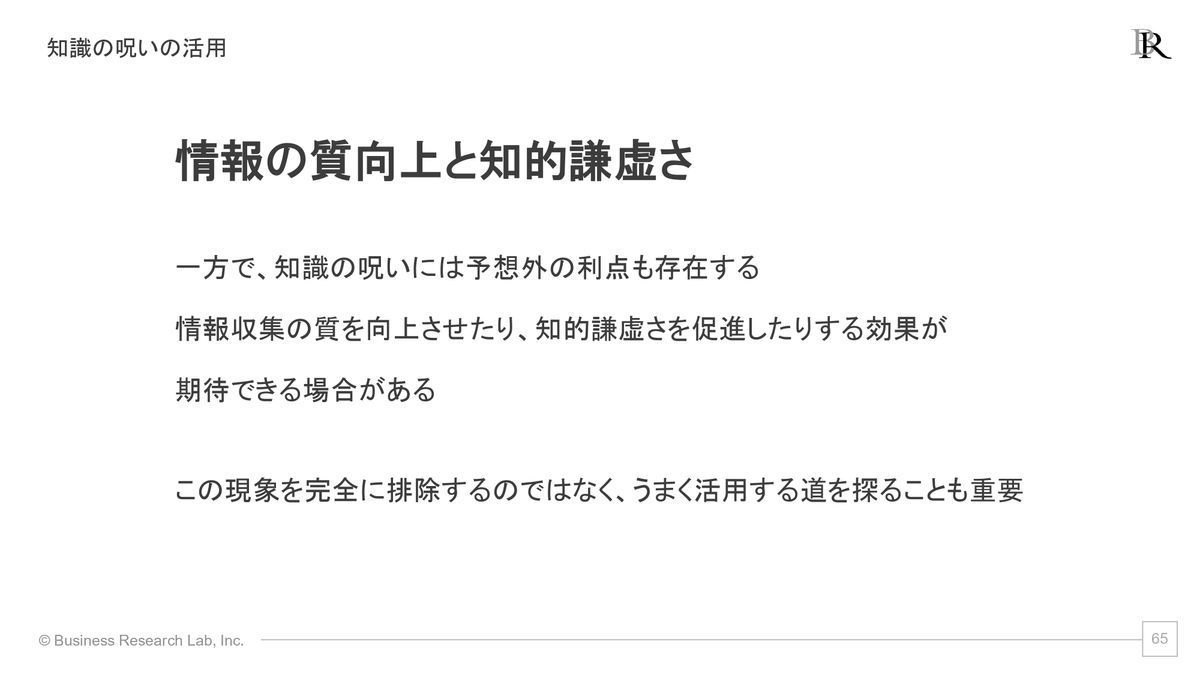「知識の呪い」を逆手に取って活用できないか?
だとすれば、「『知識の呪い』を何かプラスに変えられないだろうか?」「何か利点はないだろうか?」と考えていく。「逆手に取って活用していけないだろうか?」と少し考えてみたいと思います。
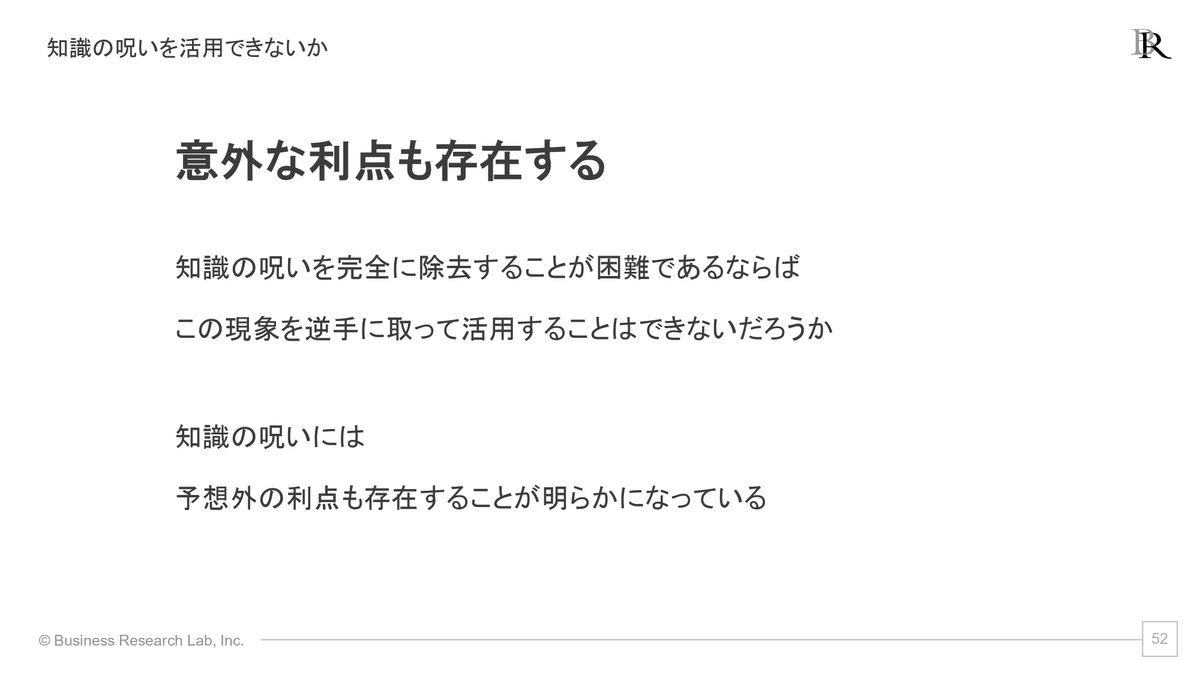
そこでちょっと興味深い研究があるんですが、情報を送る人というのは、情報を受け取る人に対して、知識のレベルを過大評価するわけですね。これが「知識の呪い」につながっていくわけです。ただ、そういうふうに「知識の呪い」が生じると、情報の質が高まる可能性があると実証されています。
情報を送る人は「相手もきっと自分と同じぐらい、この内容について理解しているだろう」と考えるんですよ。だから、「いいかげんな情報を提供できない」と思うわけですね。本当は相手は知らないわけです。
みなさんもプレゼンの準備の時などに、そういう心理になることはないですか? 「プレゼンを聞く人は、この問題についてとても詳しいだろうな。自分と同じくらい詳しいから、ちょっとでも矛盾があったりしたらきっと気づいてくるだろうな」というふうに、いろいろなことを考えるわけです。実際は初めて聞くので、気づかないんですけどね。
ただ、これはいいところもあって、「きっと聞き手のレベルは高いだろう」と思うと、準備をきちんとやるんですね。
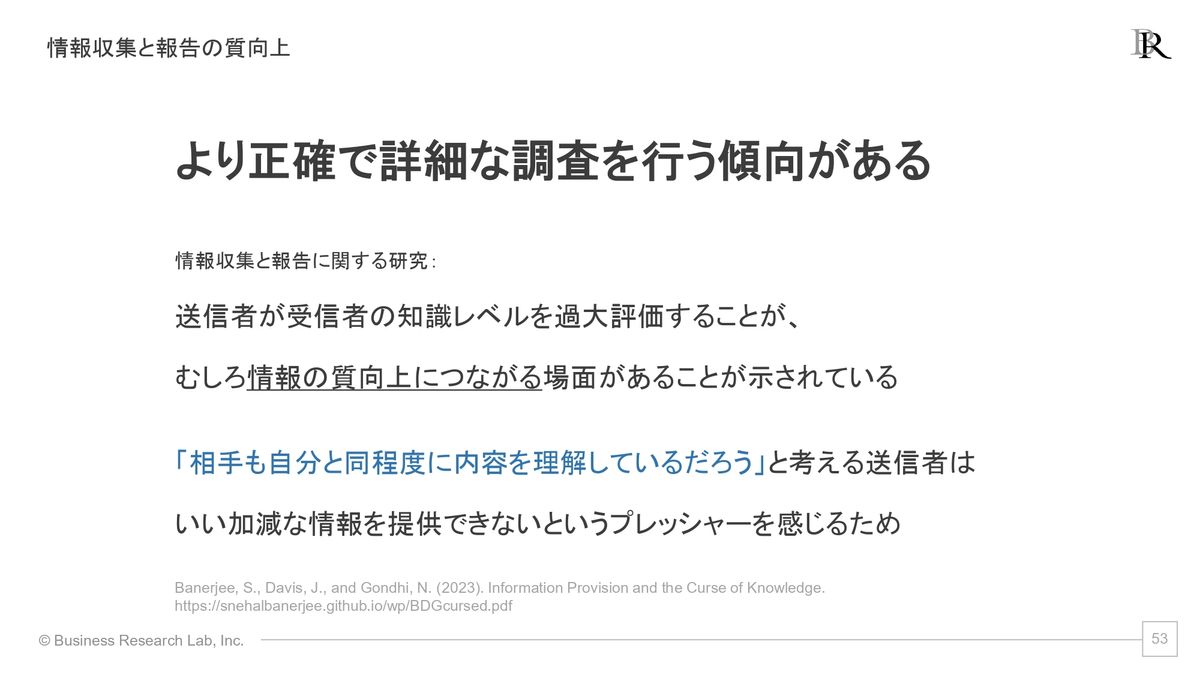
「そこまで厳密に調べなくてもいいだろう」みたいなことでも、「相手はきっと高いレベルで話を聞いていくはずなんだ」と想定することになるので。そうすると、情報の精度が高まるわけです。
準備の質を高める点において「知識の呪い」は有用
つまり、実際よりも相手を大きく見積もるので、「知識の呪い」は準備にはすごくいいんですよ。例えばマネージャーとか経営層であれば、すごくわかっていただけると思うんですが、自分はこの問題に対して、そこまで深い知識を持っているわけでもなければ、ふだんから考えているわけでもない。でも、部下からはすごく考えているみたいな感じのモードで来られると。
これは「知識の呪い」なわけなんですが、部下側の立場に立ってみると、その心理があるからこそ「きちんと調べる」と。つまり、準備の質を高めていくところに「知識の呪い」は使える可能性があるわけですね。
ただ、準備をめちゃくちゃやったとしても、「どうせわかっているだろうから、説明は省略しますね」みたいな感じになると意味がなくなってしまうので。準備の質は高めることができるんですが、実際に情報を伝えていくシーンでは、先ほどのような反論思考とか代替パターンとかを考えて、ちゃんと「知識の呪い」を解きながら説明していくことが必要になってくるかと思います。
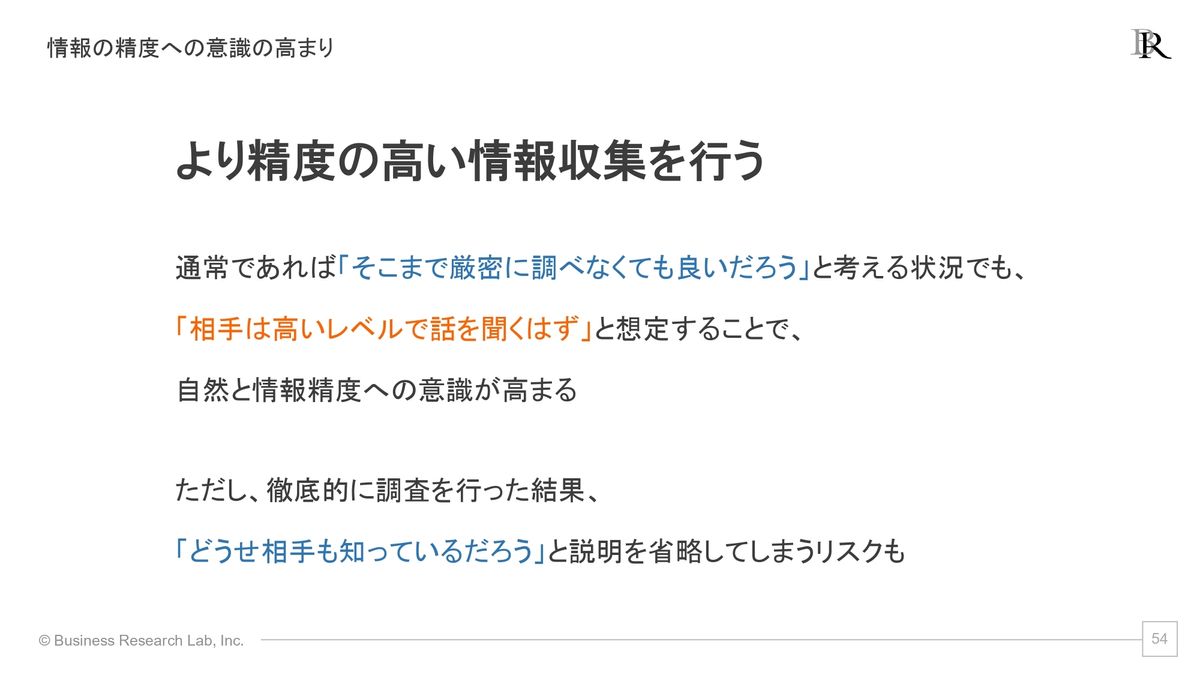
「知識の呪い」をうまく活用するイメージ
ただし今の原理というのは、活用できる可能性がたくさんあるわけですね。先ほどからのプレゼンテーションを準備する例が挙げられるかと思います。聞き手が専門知識を持っていなくても、「きっと専門知識を持っているだろう」と思って資料を作っていくわけですね。
そういう前提で資料を作っていけると、内容がやはり正確になるし、網羅性も高めることができるんですね。つまり、敵を非常に大きく見積もると。
格闘技でもそういうことを言ったりしますよね。敵をものすごく強いとシミュレーションしていくと、当日、「あれ? そんなこともないな」と思えて、うまく振る舞えるみたいな話とかが言われたりします。
その準備の質を高めていくために、むしろ「知識の呪い」をうまく使っていくことができるんじゃないのかと。もちろん、細部まできちんと考えて、高品質な思考に基づいた資料は大事なわけです。そういった、準備の質を高めていくところでは、やはり使えるだろうということです。
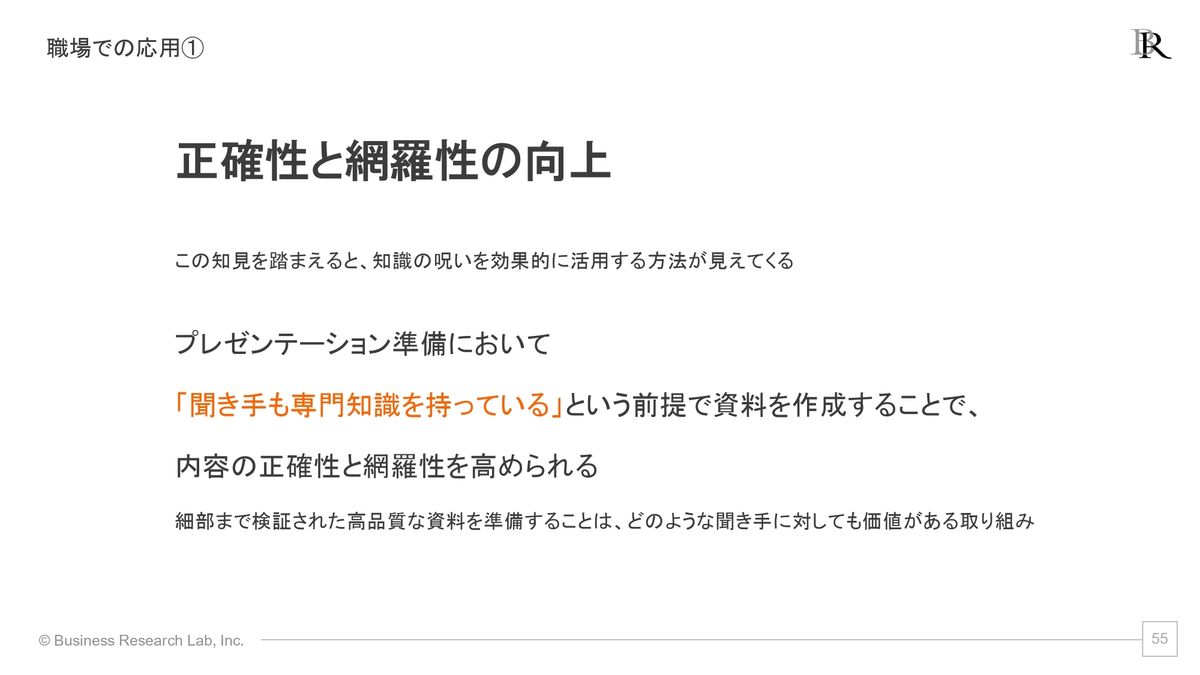
報告書を作成していく時にもまったく同じことが言えますね。「読み手もきっと、業界の事情について十分知っているだろう」と思うと、「表面的な情報を出すだけでは駄目だろう」と思うわけですね。
そうなると、「深い分析を行っていこう」とモチベーション、意欲を高めていくことができる。「きっと聞く人も専門家だろう」と思って、専門家の視点に耐えられるような内容をきちんと目指していこうと思うと、結果的にいい報告書ができるということが言えるかと思います。
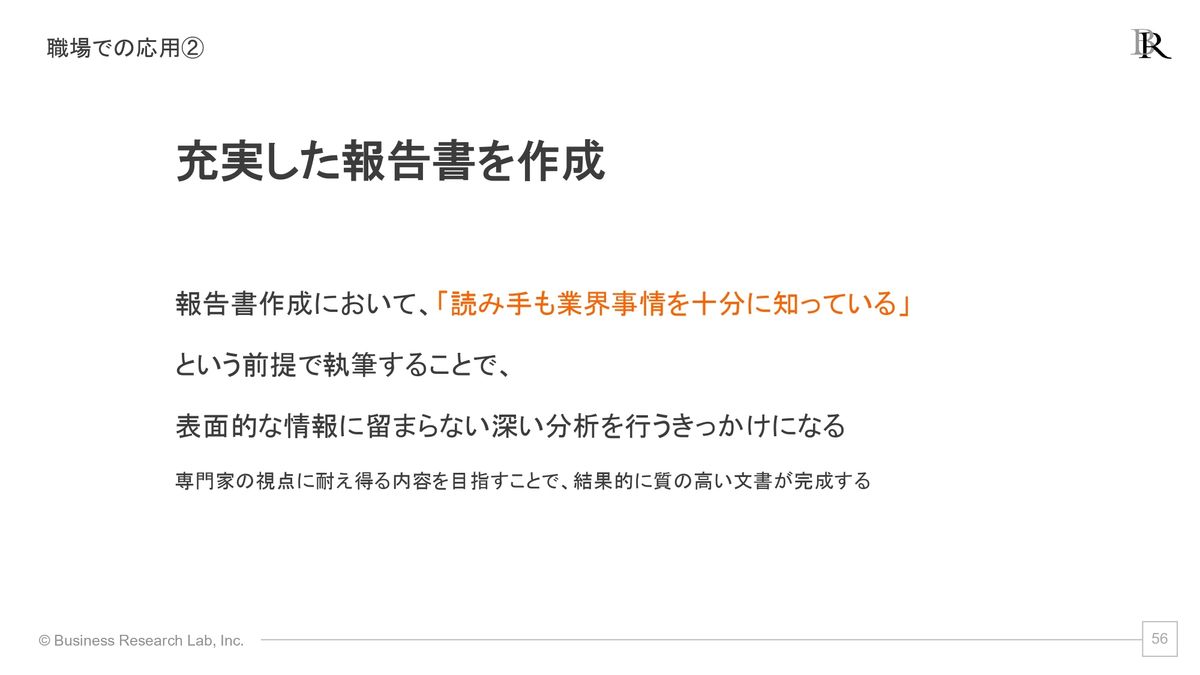
さらには意思決定を下していくような状況においても、情報を提供していく時に、「上司や関係者もきっと同じ情報を持っているはずだ。みんなこれを知っているはずだ」というふうに考えると、「より深いインサイトを出していかないと駄目だ」と綿密に準備を進めていくことになるので、「中途半端な検討では済まされない」と思うわけですね。
その結果、作業の質が高まって、提供できる情報の価値を高めていくことができます。「準備の質を高められる」というのが、「知識の呪い」をうまく活用するイメージの1つです。
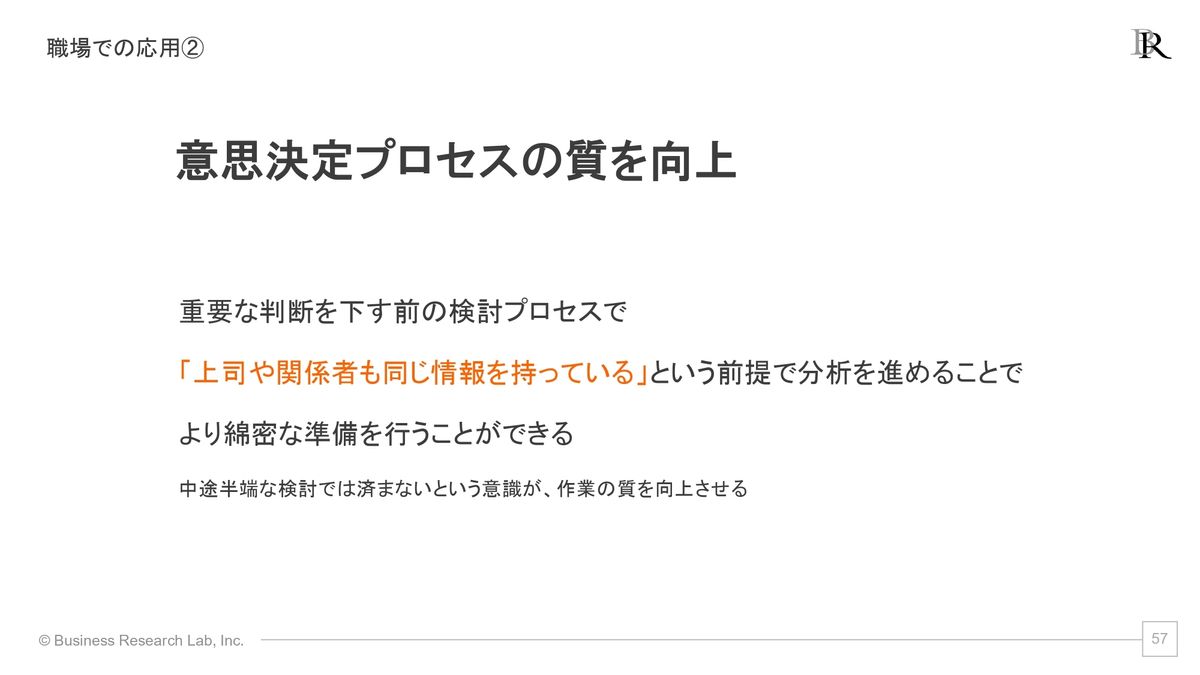
謙虚な姿勢を促せる点も「知識の呪い」のメリット
もう1つ「知識の呪い」が持っている良い側面が、「知的謙虚さを促すことができる」ということです。「周りの人も自分くらいわかっているはず」と思うのが、「知識の呪い」の1つの性質なわけですね。そうすると、「知識の呪い」を適切に持っていることで、「自分だけが別に優秀というわけじゃありませんよ」というように、謙虚な姿勢になるんですね。
「自分ができることって、周りの人もできるよね」と思うと、「自分って別に特別な存在ではなくて、がんばっていかないとな」と謙虚になれるわけです。
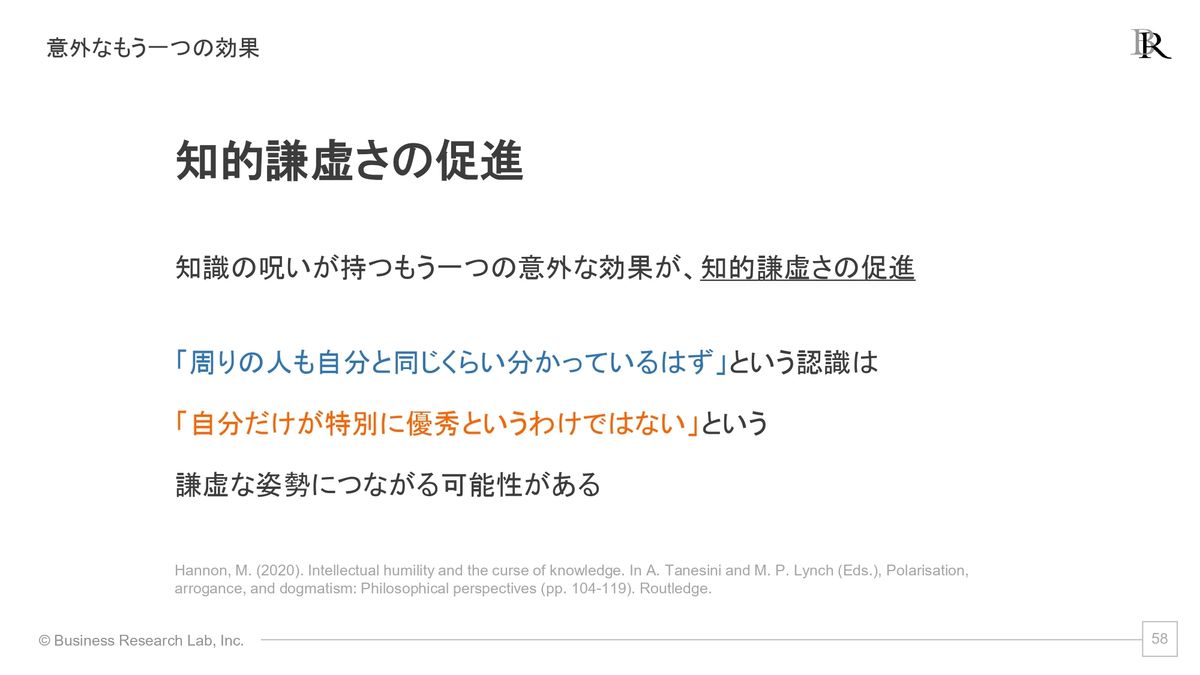
「謙虚になれる」ということ自体は、努力を促していくことにもつながっていきますし、悪くないことなんじゃないのかなと思います。
例えば、会議を運営していく時にも、「自分はぜんぜん特別じゃなくて、ここに参加する人たちはみんな有能なんだ」という前提で進行することができれば、一人ひとりの発言を大切にすることができますよね。また、いろいろな意見を引き出していくこともできるかと思います。
あるいは、新人を指導していく場面でも、「新人とはいえ、きっと基本的な能力、理解力は高いんだ」という前提で接していく。謙虚に接していくことができれば、上から目線にならずに済みますし、新人に対して過剰に叱ったりも防ぐことができる。新人の自己肯定感を潰さずに、指導を行っていくこともできるんじゃないのかなと思います。
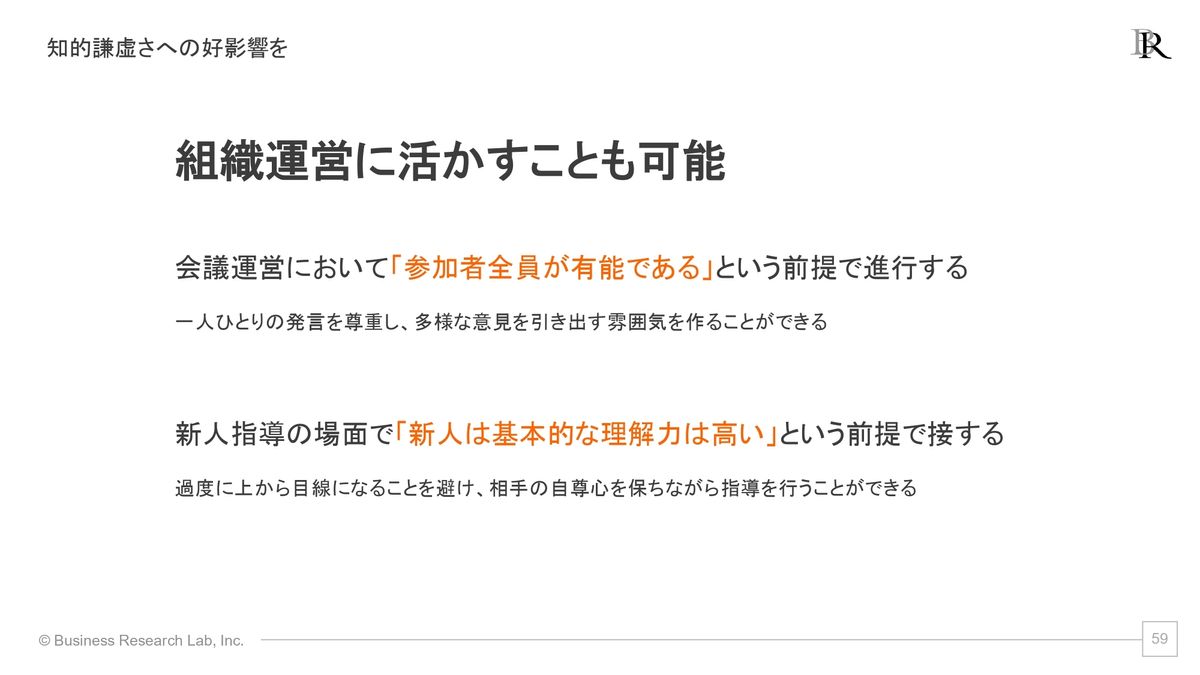
ただしメリットはすべての人にあるわけではない
ただもちろん、「知識の呪い」が発生することで、すべての人の知的謙虚さにつながるわけではないので、「自分が知っているんだから、他の人も絶対知っているでしょ」と傲慢になってしまうケースもないわけではないのかなと。ただ、実証されているところだと、謙虚になる傾向はあるわけです。
いずれにせよ重要なのは、例えば「準備の質を高めることができる」とか「謙虚さを促すことができる」とかのプラスの側面もあるんだということですね。「知識の呪い」を100パーセント消しにかかるだけではなくて、「知識の呪い」をうまく活用していくことも、1つの手ではないかというのがここでのお話でした。
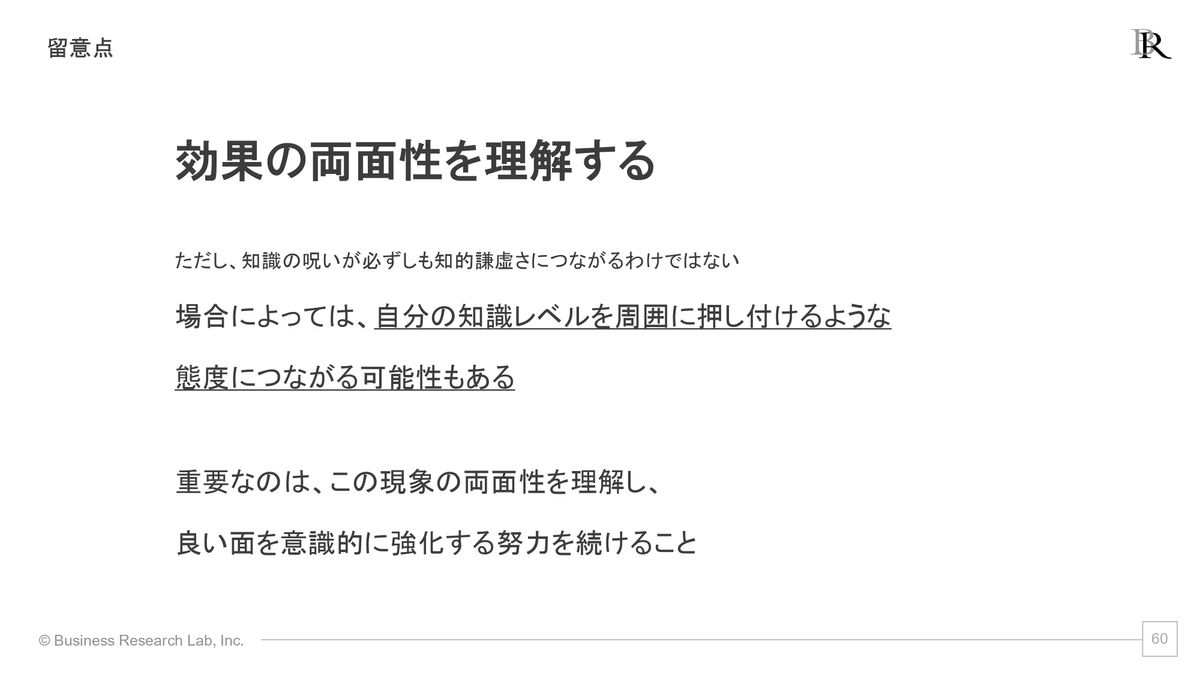
「知識の呪い」の発生メカニズムから対策まとめ
では最後に、私が本日お話しした内容を振り返っていきたいと思います。本日取り上げたのは、「知識の呪い」と呼ばれる現象でした。「知識の呪い」というのは、専門家が初心者のことを過大評価してしまうこと。その結果、いろいろなところに影響が出てくるんですね。
例えば時間の見積もりが、実際よりも想定が短くなってしまう。実験の結果とされていますが、仕事の中ではけっこうあるあるですよね。あるいは教育現場、育成の現場で、相手の理解度を誤認してしまったり。あるいはデータを可視化する時に、「ここは当然見るでしょ」と思ってしまって、解釈が偏ってしまったり。
あるいは医療現場の中でも、コミュニケーション不全が起こってしまったり。ネゴシエーションとか意思決定を行っていく時に、情報を十分に伝えず、認識がずれてしまってうまくいかなくなってしまったり。このように、「知識の呪い」はいろんなかたちで表れてくるということを説明させていただきました。
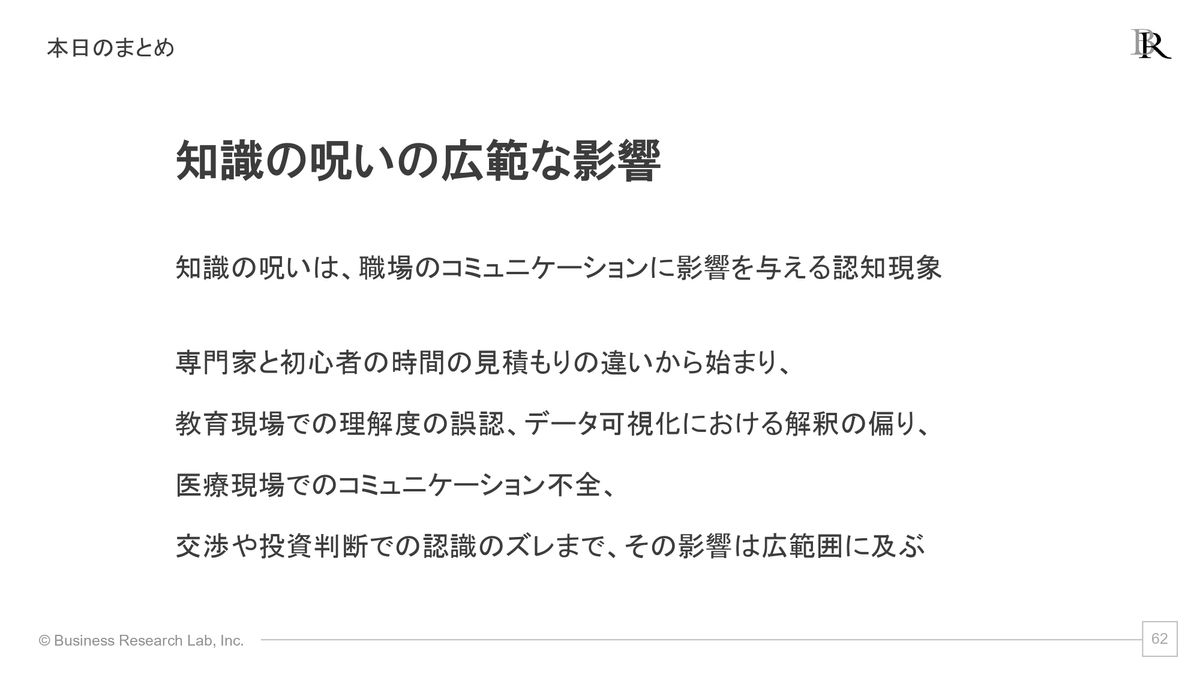
「知識の呪い」が発生してくるメカニズムですが、2つあります。1つは流暢性、アクセスしやすさですね。それが錯覚を生み出していくこと。さらに、情報が親しみやすいと、「みんなわかっているよね」となってしまう。
こうした心理的なメカニズムについても紹介しました。要するに、一度頭に入った情報とか、馴染み深い内容になってくると、「他の人も知っているはず」と思ってしまうということなんですね。
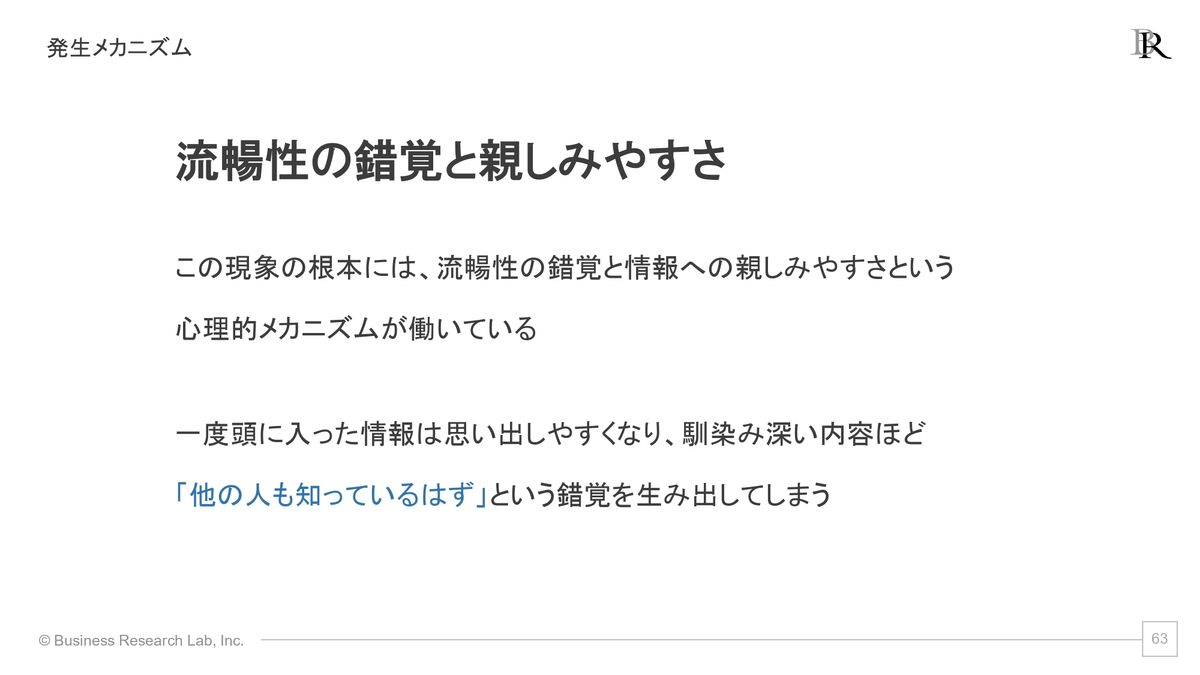
では、「『知識の呪い』をどうやって抑制していくのか?」ということですが、「相手の立場に立って考えてくださいね」と言うだけでは、なかなか難しいというお話をしました。より効果的なのは、逆のことを考えたり、別のシナリオを考えたり、異なる視点を積極的に取ってみようとすることが有効なんだというお話をさせていただきました。
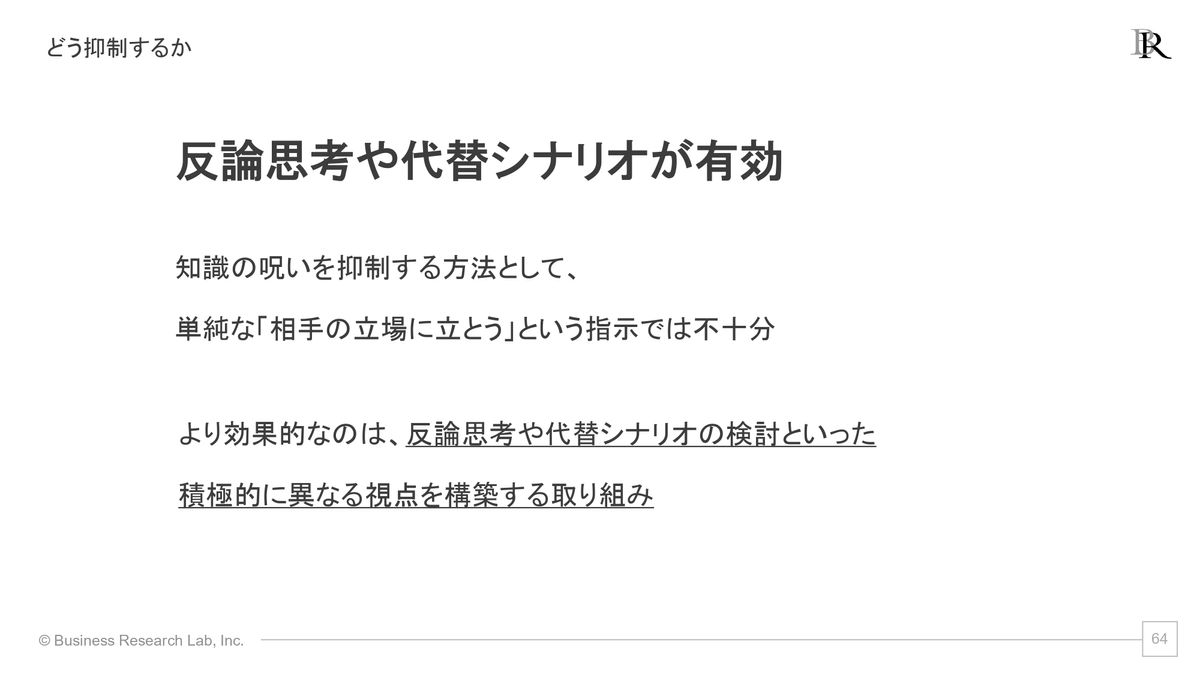
他方で、「知識の呪い」というのは、認知的なバイアスの1つで根深いものなので、それをうまく利用していく発想も必要ではないかということで、具体的には情報収集の質を向上させるということにつなげたり、知的謙虚さを促進したりする効果があることも説明させていただきました。
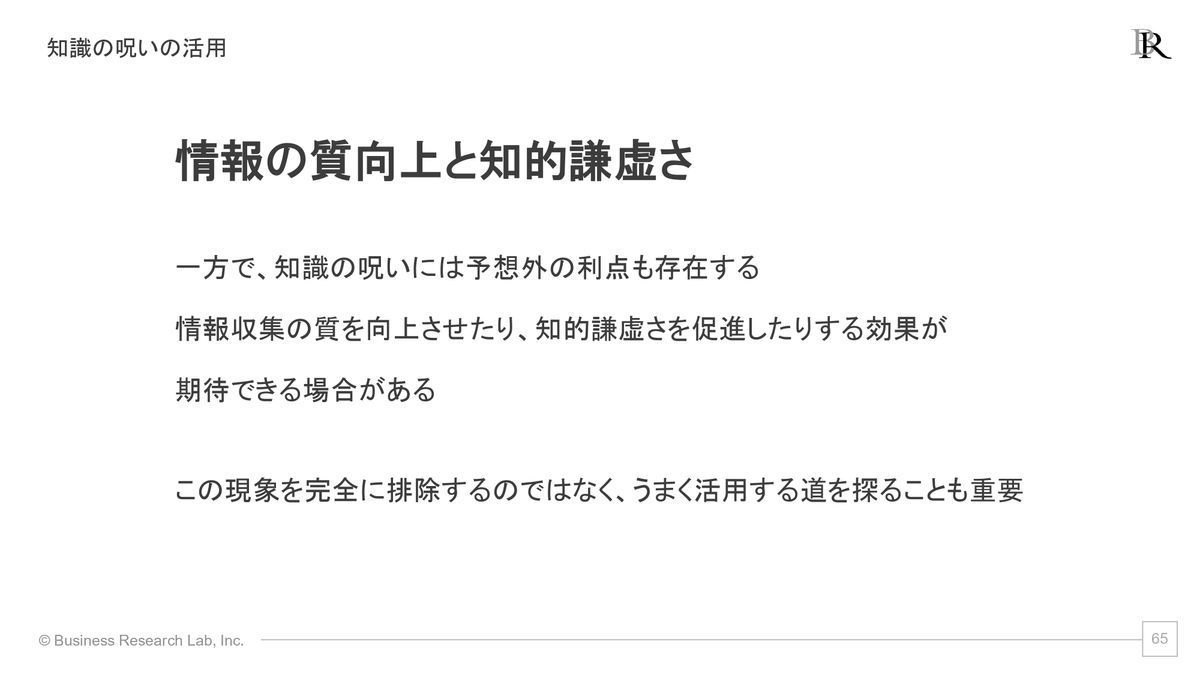
以上、私のほうから、「知識の呪い」ということを巡って、いろいろな観点からこの現象について説明をさせていただきました。
 PR
PR