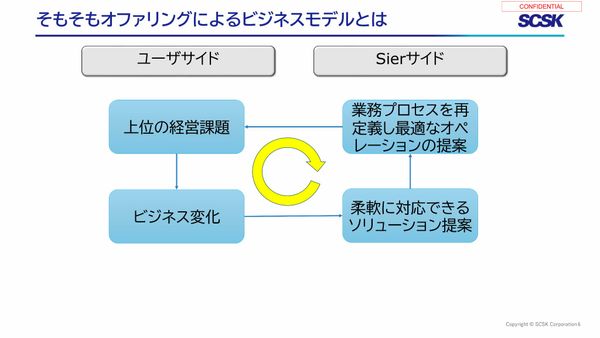 PR
PR2024.12.24
ビジネスが急速に変化する現代は「OODAサイクル」と親和性が高い 流通卸売業界を取り巻く5つの課題と打開策
リンクをコピー
記事をブックマーク
松村圭一郎氏(以下、松村):次に、今日は『ブルシット・ジョブ』の話をごく簡単にかいつまんで話します。
 『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)
『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』(岩波書店)
『ブルシット・ジョブ』はグレーバーの本ですが、翻訳された酒井隆史さんが去年、講談社現代新書で日本の文脈とかも含めて書かれたわかりやすい本を出されているので、興味がある方は読まれたらと思います。まさに、『ブルシット・ジョブの謎 クソどうでもいい仕事はなぜ増えるのか』というタイトルです。
この本のエッセンスで、今日ちょうど関わるかなと思うところをお話ししようと思います。「ブルシット・ジョブ」とは、「自分のやっていることが無意味で、不必要で、有害ですらあると考えるような仕事のこと」とグレーバーは定義しています。
イギリスやオランダでグレーバーが短いエッセイを発表したあとに、反響がけっこう大きくて、実際にイギリスやオランダで働いている人にアンケート調査がされました。「自分の仕事が『ブルシット・ジョブ』だと思う」という人が35パーセントから40パーセントいたことが明らかになっています。それによって、グレーバーは新たに1冊の本をまとめるんです。

前提として、1930年に有名な経済学者のケインズが、「どんどんテクノロジーが進歩して、生産性が上がって機械化も進んで、20世紀末までには先進国では週15時間労働が達成されるはずだ」と予測している。でも、20世紀末を通り越して21世紀に入ってもう20年以上経ちましたが、週15時間しか働かなくていい人がどれだけいるか、ですよね。
週5日勤務だったら1日3時間労働ですが、なぜか私たちはいまだに働きすぎて人が亡くなってしまう社会を生きている。機械化も進んで、インターネットができて、Eメールができて、携帯電話とか常にどこでも効率的に仕事ができるツールが出て、「こうやって仕事を効率化していくと、ちゃんと時間に余裕ができるはずだ」と言われてきたはずなんですけどね。
松村:1930年は知らないかもしれないけど、実感としてここ20年くらい、インターネットが仕事の中に普及する過程を知っている人にとっても、「言われていることと違うじゃん」とか、今回もそうですが「メール1本で仕事がどんどん入ってくるじゃないか」とか。「これは何なんだ」と。
グレーバーは、「なんで無意味で不必要な仕事が増殖しているのか?」と問いかけて、「実際にケインズが予想したように、生産性は一貫して戦後上昇している。でも1970年代以降、その生産性の上昇が賃金の増加に結びつかなくなっている」ことを指摘しています。

これ(スライド参照)が『ブルシット・ジョブ』の中に出てくるグラフです。生産性はずっと右肩上がりで、1970年代くらいまでは生産性とともに平均時間あたりの賃金や報酬も上がっていますが、そこから上がらなくなるんです。でも生産性は上がっていく。
じゃあその利益はどこにいったのかというと、「1パーセントの富裕層にいくようになった」「投資家や企業幹部とか、上位層の専門的管理職の諸階級にいった」とグレーバーは言っている。
実際に想像できると思うんですが、1960年代、1970年代の大企業の社長であっても、何十億ドルの報酬とかありえなかったはずですが、いつのまにかそれがあたりまえになって、「それくらいのお金を出さないと優秀な経営者は雇えないんだ」という話になっています。
松村:もう1つは酒井さんも引用していて、大学に関係のある仕事をしている人だったら「本当にそのとおり!」と思う図です。たぶん、いろんな企業の中でも似たり寄ったりのことがあると思います。

(スライドの)左側は、シラバスを作る作業がどうなっているか。下はかつての図なんですが、大学職員から「シラバスを書いてください」と依頼が来て教員が書いて、終わり。
今はすごいですよね。大学職員も管理者もいて、まず作成依頼があります。「アップロードしました」「フォーマットが今年から変わったので、ここを変更してください」「はい、わかりました」。これを管理者に確認を取って、また承認を受ける。
これは今年2月、3月に実際にあったことですが、「シラバスに空欄があります」「授業時に指示する、じゃ駄目です。修正してください」と私も言われたんです。「いやいや、授業時に指示しますから」と言っても、「具体的に書いてください」と言われるんです。「1年後の授業時に何と指示するかわかりませんよ」と言いたいんですが、「書いてください」と。
私はそういうのはだいたい無視します。無視したらもう1回チェックはしないかなと思っていたんですが、またチェックするんですよ。事務の人がかわいそうになってきて、そんなの「修正指示を出しました」で終わらせればいいのに、確認して、「まだ修正されていないから、書いてください」というやり取りが増えるわけです。しょうがないから書き直しましたけど(笑)。
松村:私の仕事はシラバスを作ることじゃなくて学生の前で話すことですが、半年前や1年前に、そこで何を話すかのメニューをここまで精緻に固めることに、お互いどんな意味があるのかよくわからないですよね。こういうのが「ブルシット・ジョブ」の典型です。
(スライドの)右の試験問題作成も、問題の出題ミスがあると、1人が確認作業をして、もう1回別の人が確認するとか、当日の朝も早く行って「最終確認します」ということがいっぱいあるんですよ。かつてはそんなことせずにうまくいっていたんですが、いつの間にかうまくいかなくなった。こういう余計な仕事が増えていっている。
資本主義は本来、効率的に無駄を削減して、コストに対してベネフィットを最大化するように働くはずなのに、こんなにコストがかかる。これには当然、チェックする人や確認する人が必要になってくるわけです。
そのやり取りをしていることが仕事のように見えるけど、実際は大学で学生の前で何を話して何を伝えるかが重要であって、事務の人と延々と書類をやり取りしていることには社会的意義が1ミリもないわけです。
でも、そこで無駄な仕事を生み、雇用を生み、ストレスを生み、労働時間を長時間化させ、疲弊させ、教員のやる気も失わせる負のスパイラル(が起こる)。こういうことは、たぶんいろんな企業の中でもあると思うんです。
松村:『ブルシット・ジョブ』を全部読むといろんなことが書かれていて、すっきり読むのは難しいですが、主に「労働はモラリティとして働かなきゃいけない」ということが歴史的にずっと形成されてきたと書かれています。

1行でまとめると、「労働は富を作り出したり他者に対するケアというよりも、むしろ苦行として喜びや快楽を犠牲にするものとイメージされるようになってきた。惨めで絶望的なほど、それはあなたにとっていいんだ」というモラリティです。
平たく言うと、「あなたは若いんだから苦労しなきゃ駄目よ」ということです。「今の仕事はつまらないかもしれないけど、がんばって努力することによって、あなたは人間として成長しますよ」「だから、好きなことを好きなようにやるのは駄目なんですよ」「苦労しなきゃ駄目。苦しまなきゃ駄目。むしろ苦しむ仕事ほどいいんです」という価値観が広がってきた。
20世紀の仕事に関する調査研究でも、多くの人が自分の仕事を嫌っていると同時に、働いていることが自分の尊厳や自尊心につながっていることが明らかになった。これをグレーバーは「近代的仕事の逆説だ」と言っています。
「肉体的につらくて退屈で疲れるし屈辱的なんだけど、働いていることが私にとって心の安定になる」「人間としてちゃんとしている証になる」「つらいがゆえに、むしろ仕事をすることを望む」ということです。
松村:仕事は何かをしたくてお金が必要だから稼ぐ手段ではなくて、仕事そのものが目的化してしまう。「働いていないと駄目人間に思われてしまう」「ごろごろ寝そべっている人たちは仕事していない!」となっていった。
だからそれは、「なぜ私たちは働き続けるのか?」につながるわけです。「苦しい仕事をがんばってやり続けることが『人としての道』である」という労働のモラルが私たちを働くことに駆り立てているし、労働から逃れられなくしている。「働いていないと一人前の人間じゃない」という言い方ですね。
そこまでストレートじゃなくても、例えば「社会人」という言葉1つとっても、社会人は「すでに働いている人」で、学生は毎日アルバイトをやっていても「学生」として捉えられる。就職して働いている人が「社会人」で、「ちょっと休職して旅に出ている人は、社会の人じゃないんですか?」ということです。
例えば学生で1人だけいたんですけど、「就活も就職もしたくないです。これから旅に出ます」と言われて、私も「うーん、でも1回社会に出たほうがいいんじゃない?」と普通のアドバイスをしたりしているわけですから、矛盾しています(笑)。
でも、ちょっと不安ですよね。「働きたくないので世界を旅しに行きたいです」と学生に言われると、「仕事もちょっと経験したほうがいいんじゃない?」と私も言ってしまう。そこには「旅でふらふらしているよりは、働いたほうが彼女のためになるのではないか」「人間として一人前になる道なのではないか」という考えがあるんです。

つまり、働いていることが「よきこと」として、私たちを駆り立てる。本当にしんどくて嫌なことで駄目なことで社会的にも悪いことだったら、そこから逃れる理由を見つけるのは簡単ですが、社会的によきことで、そうしていないと駄目な人間だと思われるという「よきこと」が、私たちをすごく強力に縛っている。
松村:サモアの人たちの例に戻りますが、宣教師がなんでサモア人に働くよう求めたのか。これはまさに、キリスト教的なモラルの体現者として宣教師でなければいけなかったんです。
ここでの話のネタは「(将来)ごろごろできる」から働くように求めているかたちになっていますが、実はそうではない。宣教師は、「ごろごろしているような怠け者はモラルに反する」と言っているんです。

だから「いったいなにをしているのかね! そうやってごろごろして、人生をムダにしちゃだめじゃないか」と言う。つまり、働いていることは有意義な人生の過ごし方で、そうじゃない時間の使い方をしていると、人生を無駄にしていることになる。
シンプルに考えて労働がお金を稼ぐことだとしたら、「この本を買いたい」「服を買いたい」「いい家に住みたい」「だからお金が必要」と目的が別にあるわけですよね。だから手段のはずなんですけど、「人生を無駄にしない」「働いていること自体が有意義な時間の過ごし方」というのは、まさに労働が目的そのものになっているということです。
「お金がたくさん手に入って、そのお金でもっと手早く干し椰子の実が作れると、もっと儲かってお金持ちになれるではないか」というロジックは、まさに資本の論理ですよね。(労働が)どんどん終わりなき資本の循環の一部になっている。お金はいくらでも増やしていけるわけですから。
私たちはどんなにおいしいものが好きで、食べることが好きでも、1日20キロのお米は食べられません。限界があります。でも、お金は100万円より200万円。1,000万円や1億円あっても困らない。資本はそのように際限ない無限の増殖と蓄積に駆り立てられるのです。
松村:宣教師が言っているのはまさに、「お金を稼ぐとより多く儲かる」「お金のためにお金を儲ける」ということです。お金はそこでも手段ではなく、目的そのものになっています。
お金とは、単に何かを手に入れるためのクーポン券でしかないですよね。(お金)そのものは使えないじゃないですか。それを何かと交換することによって何かを手に入れるものなのに、そのクーポン券を集めることが目的化してしまう。結局、いつまで経ってもごろごろできないわけです。その資本の論理に巻き込まれる。
『負債論』の最後のほうにグレーバーが書いている言葉を引用して、この話題を締めようと思います。彼は『ブルシット・ジョブ』の中で「働くことの本質はケアにある」と言っているんです。
「だからこそ、わたしは勤勉ではない貧者を言祝いで(祝福して)、本書を終えたい。少なくとも彼らはだれも傷つけていない。彼らが、余暇の時間を、友人たちや家族とすごすこと、愛する者たちと楽しみ、配慮をむけあうことについやしている以上、彼らは考えられている以上に世界をよくしているのだ。おそらく、わたしたちは、彼らを、わたしたちの現在の経済秩序がはらんでいる自己破壊衝動を共有しようとしない、新しい経済秩序の先駆者とみなすべきだろう」と。
松村:ここで言う「勤勉ではない貧者」というのは、まさにごろごろしている、「ちょっと働いたほうがいいんじゃない?」と周りから言われてしまう人なわけです。これは、サモア人が浜辺で寝そべっていることに象徴されているわけですけれども、彼らは何をしていたのか。
もしかしたら寝そべりながら、実は友人の人生相談を受けていたかもしれない。恋愛に悩んでいて、それを聞いてあげていたかもしれない。これはたぶん、確実にこの世界をよくすることの一端なわけですよね。お金にはならないけれども。
労働の本質がケアだとしたら、仕事に見えないことの中に、働くとか仕事ということがあるかもしれない。これは、Podcastの『働くことの人類学』の中では、エチオピアのダサネッチという牧畜民が、「30歳くらいを過ぎたら、だいたい男たちは木陰で一日中、政治の話をしている」という話とつながっています。
一見だらだらしているように見えるんだけれども、政治は自分たちの暮らしをどうやっていくかをああだこうだ話し合うという、まさに重要な、社会をケアしていくことそのものですよね。そういうことも重要な仕事なわけです。私たちが仕事と生活で忙しくて政治に無関心になっているのと対照的です。
関連タグ:

2025.01.09
マッキンゼーのマネージャーが「資料を作る前」に準備する すべてのアウトプットを支える論理的なフレームワーク

2025.01.08
職場にいる「嫌われた上司」がたどる末路 よくあるダメな嫌われ方・良い嫌われ方の違いとは

2025.01.10
プレゼンで突っ込まれそうなポイントの事前準備術 マッキンゼー流、顧客や上司の「意思決定」を加速させる工夫

2025.01.07
資料は3日前に完成 「伝え方」で差がつく、マッキンゼー流プレゼン準備術

2025.01.08
どんなに説明しても話が伝わらない“マトリョーシカ現象”とは? マッキンゼー流、メッセージが明確になる構造的アプローチ

2025.01.07
1月から始めたい「日記」を書く習慣 ビジネスパーソンにおすすめな3つの理由

2025.01.09
記憶力に自信がない人におすすめな「メモ」の取り方 無理に覚えようとせず、精神的にも楽になる仕事術

2025.01.10
職場にいる「できる上司」と「できない上司」の違いとは 優秀な人が辞めることも…マネジメントのNGパターン

2025.01.09
職場に必要なのは「仲良し集団」ではなく「対立」 メンバーのやる気を引き出すチームビルディング理論

2025.01.14
コンサルが「理由は3つあります」と前置きする理由 マッキンゼー流、プレゼンの質を向上させる具体的Tips