『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』の出版を記念して開催された本イベントでは、著者であり編集工学研究所の安藤昭子氏と株式会社コルク代表の佐渡島庸平氏が登壇。本記事では、佐渡島庸平氏が持つ「問う力」の鋭さについてお伝えします。
松岡正剛氏が興味を持つ人とは
佐渡島庸平氏(以下、佐渡島):松岡正剛さんが興味を持つ人と持たない人の差って、何なのでしょう?
安藤昭子氏(以下、安藤):もしかしたら佐渡島さんが作家さんを発見する時に、「この人のおもしろさは俺にしかわからない」という瞬間ってあるんじゃないかと思うんですけど。松岡も、例えばさっきの尺八の中村明一さんのお話もそうですけれども、「絶対にあなたはすごい」という目利きがあるわけなんですよね。
「絶対にあなたはすごい」という時のジャンルは、それこそ音楽から、踊りから、大工さんから、1人の主婦に至るまでとても幅広いですが、そうした目利きをすることも、生涯をかけて、自分の仕事としてものすごく大切にしていたところだったんだろうと思います。
それが、どういう人がいいと思っていて、どういう人は引っ掛からないのかというのは、永遠の私たちの課題というか(笑)。そこに方程式はないんだけれども、やはり目利きって、たぶん佐渡島さんもそうだと思うけど、分解し切れない何かがあるじゃないですか。
やはり松岡さんの目利き力は、一番方法として私たちが取りきれていないものじゃないかと思います。
佐渡島:そうですね。僕も中村さんは尺八を聴いていいと思ったのではなく、呼吸法の本を読んで「この人は並々ならぬ音を出すだろう」と思って、「音楽を聴かせてください」となった感じです。
安藤:そうですね。何かシンパシーを感じるのは、さっきの「述語的」とちょっと近いかもしれないんですけども。ビジョンや主題で何かをしようとしているというよりも、技術をものすごく鍛錬している人に対しては「俺、本当に弱いんだよね」と言っていたことがありました。例えば職人さんもすごく好きですし。
冒頭にお話しした「世界たち」というところですね。すごく微細だったり、壊れやすかったりするんだけれども、ものすごい集中力や鍛錬によって、いろんな文化を生み出そうとしている人たちは無条件にリスペクトしているところはありました。
「コンセプト主義に陥るな」
佐渡島:問いの編集というモノの思考法として紹介されているものは、かなりクライアントと一緒にやるためのツールにもなっているじゃないですか。
それをやっていくと、コンセプトみたいなものとか、ある種会社のビジョン・ミッション・バリューみたいなのが明確になっていくのを手伝うツールのようにも、技術のようにも感じるんですけど。その中で、コンセプトが明確な人には興味がないっておもしろくないですか?
安藤:(笑)。クライアントさんとお仕事をする時も、ここはなかなか難しくて。松岡からよく叱られた時は、「コンセプト主義に陥るな」とよく言われていました。
佐渡島:それ、詳しく聞きたい。
安藤:それはやはり、徹頭徹尾、方法から見ていくというところです。最初からそれっぽいコンセプトを置いてしまうと、それこそフィルターが外しにくくなるんですね。例えば、クライアントさんの様子をまっさらに見るとか。佐渡島さんであれば、作家さんの「この人の何がすごいのか」を細かく言葉にできるところまで自分でかみ砕くとか。
そっちの方法が先であって、後から出てくるコンセプトは、こんなことを言ったら怒られるけれども、便宜上置くみたいなところはけっこうあるわけです。なので、一緒にやっていく過程の中で、クライアントさんが「あっ!」と思うことのほうが大事。
耳障りの良いコンセプトに自分を寄せていくのは違う
佐渡島:だから、先に耳障りの良いコンセプトを作って、そっちに自分を合わせにいくのは違うよということですね。
安藤:そうそう。
佐渡島:ある種、目利きである松岡さんが見つけた多くの人たちは、もうすごいから、そのままでいい人たちじゃないですか。それを松岡さんが代わりに言語化してあげる場合もあれば、しない場合もあるけれども。
クライアントの場合は、相手が認知できるように言語化していくのを手伝うために、こういう編集的なテクニックを使っていたということなんですかね。
安藤:そうですね。よく私たちの仕事の仕方でやるのは、コンセプトを「X」として空欄を置いちゃうんですね。
ある程度のところまでXを埋めないまま、クライアントさんといろんなことを一緒にやっていく。でもある時にぽっと置くXは、誰も聞いたことがない、でもそれによって一気に世界が広がるようなものを置く。そういう仕事の仕方は、松岡さんとのやり方であり、編集のプロセスなんですね。
佐渡島:それはソクラテスの問いの産婆術みたいなものに感じますよね。ソクラテスは、街中で出会った人とただしゃべっているだけで、ソクラテスも相手も知らなかったことが対話で出てきて、それが気づきになる。そういう感じの話し方をするのかもしれないですね。
安藤:実は『知の編集工学』で、今日冒頭でちょっとお話しした松岡の7つの問いの部分の手前に、「編集的創発性」という言葉があるんですよ。やはり世界の創発、相転移に当たるものがとてもおもしろいと。そこに非常に可能性を感じていると言うと簡単な言葉になりすぎますけれども、創発をすごく大事にしていた。

今のソクラテスの話もそうですけれども、最初から何かが用意してある、もしくは最初から何かを用意してあげるのではなくて、ある出会い頭でしか生まれてこない。これを松岡はよく「コンティンジェンシー(contingency)」という言い方もしましたが、「別様の可能性」というものです。
それまで伏せられていて何かがいつ出てきてもおかしくない状態、そうした創発的な状態をいかに作るかが、文章を書いていても、クライアントさんの仕事をしていても、ずっとやってきたことなんですよね。
なので、『問いの編集力』で読者のみなさんと共有したいなと思いながら書いていたことのひとつに、私の裏テーマとしても創発があります。
佐渡島:問いによって、創発を生み出せますからね。
安藤:そうなんですよね。「これはわかった」と思う状態が一番止まっている状態なんです。知れば知るほどわからないことが増えていく状態を作っていく中で、自分でも思いもかけないようなことが生まれてきたりするのは、たぶん編集的創発性だと思いますね。
佐渡島:今の会話の流れで、僕がちょっと前にChatGPTに相談していた問いを急に思い出したので。
安藤:そうそう、そんな感じ(笑)。
興味を持って質問したのに「尋問だ」と言われてしまう
佐渡島:僕、いろんな人からよく「圧がある」とか言われるんですね。昔、為末大さんと出会った時に、バスで横の席に座っていて、僕としてはすごく楽しく終わったんですよ。でも数ヶ月後に会った時に、「刑事に尋問されている感じでした」と言われて、変に警戒されていたんですね。
安藤:(笑)。
佐渡島:こちらは好奇心を持って聞いただけだったのに、「尋問だ」と言われることが、けっこう定期的に発生するんですよ。
こっちとしては、相手に「興味を持った」という時点で何らかの好意の発露だから、褒めるよりも問いのほうが気色悪くないコミュニケーションだと思って問うんだけど、圧と捉える人もいる。
でも、編集者としては対話は創発的でありたくて、問いが最もそれの近道だとも思っています。だから、ChatGPTに「問いは、相手に『答えないといけない』という圧力を生むから、一切問いを使わずに対話をしていきながら創発する方法は何ですか?」という質問をしたんですよ。
安藤:(笑)。本当に高度な相談をしていますね。
佐渡島:そう。それはけっこうしっくりくる答えは来なくて、どうすりゃいいんだろうなとここ数ヶ月ずっと考えていたんだけど。「あ、自分は問いを使わない対話がうまくなりたいんだ」と気づいたのは、2ヶ月から3ヶ月くらい前です。
その時はChatGPTにそういう質問の仕方をして。ChatGPTも「すぐに答えを教えてくれ」という感じの問いのかけ方だといい感じのが来ないから、「今の問いをもっと小分けにして聞くと、ChatGPTも教えてくれる時があるかな?」と今は思っているんですよ。
安藤:随分仲が良いじゃないですか(笑)。
佐渡島:そうなんですよ(笑)。
佐渡島庸平氏の「問う力」
安藤:この本も『問いの編集力』というタイトルですけれども、まさに今佐渡島さんがおっしゃられたような、ど真ん中の何かを聞いても、編集って案外動かなかったりするんですよね。
私は佐渡島さんといつもお話しして「やはりすごいな」と思うのは、佐渡島さんの問いが普通よりもちょっと奥なんですよ。だから、たぶん聞かれているほうは疲れるんですよね。「そこを尋ねるのか」みたいな(笑)。
やはり、人の才能を引き出す仕事をしている人ならではの問い力だなと思います。普通の人は、それはなかなかできないんだけれども、それを編集力だと考えると、例えば何かを言い換えたり、見立てたり、ずらしたりということで、何かをズバッと質問するのと案外同じくらい、相手のイメージを動かす効果があるんですよね。

会話をしている時に、ちょっとずつ相手の言っていることを言い換えてずらしていくみたいなのは、おそらくみなさんも自然にされることがあると思うんですけども。まあ、為末さんの気持ちもよくわかります(笑)。
でもね、佐渡島さん、この(『問の編集力』の)帯を書いてくださったじゃないですか。メッセンジャーでもお伝えしましたけれども、これがいいんですね。佐渡島さんが私の本文の中から一行抜いてくださっているんですよ。
「『問う』ということはつまり、『いつもの私』の中にはないものに出会うこと、その未知との遭遇の驚きを自分に向けて表明することだと言っていい」と。
「この本文中にあった一文に、編集の真髄を感じた」というメッセージを寄せてくださったんですけど、この一文を抜くセンスがすごいなと思ったんです。
本を1冊書くと、佐渡島さんもそうかもしれないですけど、「このセンテンス、めちゃ気に入っている」というのがありますよね。私もこれだけ文字数を書いた中で(気に入った)3つくらいの中の1つなんですよ。「お、これを見つけられた」と思って、やはり『観察力の鍛え方』という本を書かれているだけあるなぁと。
井上雄彦氏に会って褒めたら、不機嫌にさせてしまった
佐渡島:そう言ってもらえると、本当に編集者冥利に尽きます。僕は講談社にいた時に、先輩に「この前、井上(雄彦)さんに(会った時に)すごく褒めたのに、めっちゃ不機嫌になられたんですよ」と先輩に相談したことがあります。
そうしたら「お前、当たり前だろ。井上雄彦のこと、何百万人が褒めているんだよ」と言われました(笑)。
安藤:(笑)。
佐渡島:それで、「追加でお前に褒められてうれしいか? そんなの別に聞きたいわけないだろう」と言われて。「確かに。僕が話すことって、井上雄彦を褒めることじゃないし、僕に褒められても1ミリもうれしくないわな」とめっちゃ思ったんですよ。
だから「あ、僕がやることって、井上さんがどこを工夫したかに気づくことなのかな」と。毎回原稿の中で、最も工夫しているところとか、苦戦したところとかがあるはずだから。おもしろいページの中から、「ここに苦戦したんじゃないか?」「ここは苦戦を乗り越えたんじゃないか?」と気づくこと。
もしくは、乗り越えられていないところが見つけられると、「そこについて話しましょう」と言う。だから、(作家とは)最も時間をかけたところとか、練ったところはどこなのかは話していますね。
僕は月に1回読書会をやっているんですけど、そこでは「立派な感想は持たなくてよくて、本の中から一文だけ抜いてきて」と。それをみんなの前で話すだけでもいいと言っています。読書会に参加する人は別に編集者じゃないから、その1文を抜いてきたら、「作家がなんでそれを書いたか」とか、「これが物語の中でどういう意味を持つだろう?」という問いに変えて、みんなで話し合う。
安藤:それ、とてもいいですね。
佐渡島:これをやっていくだけで、読書会として十分成立するんですけどね。
安藤:そうですよね。おそらく著者の人も、そこに居合わせたらめちゃくちゃうれしい読書会だと思います。
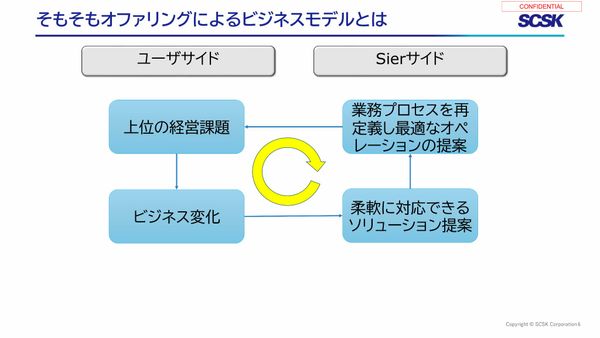 PR
PR











