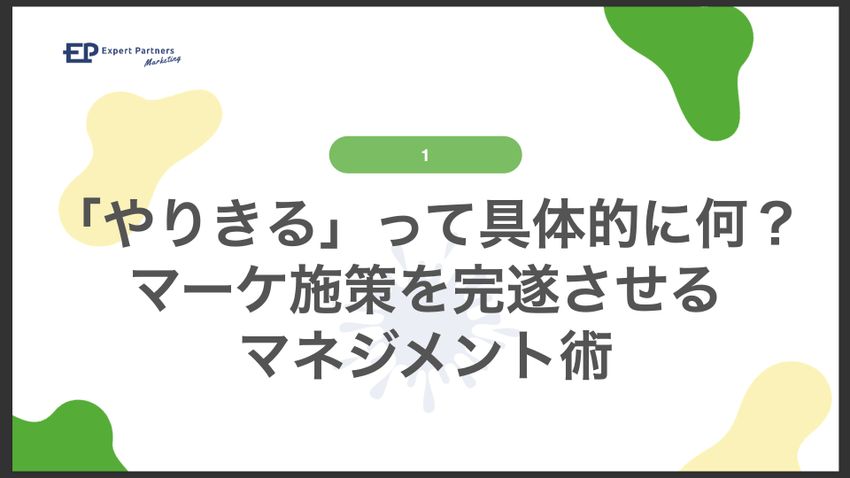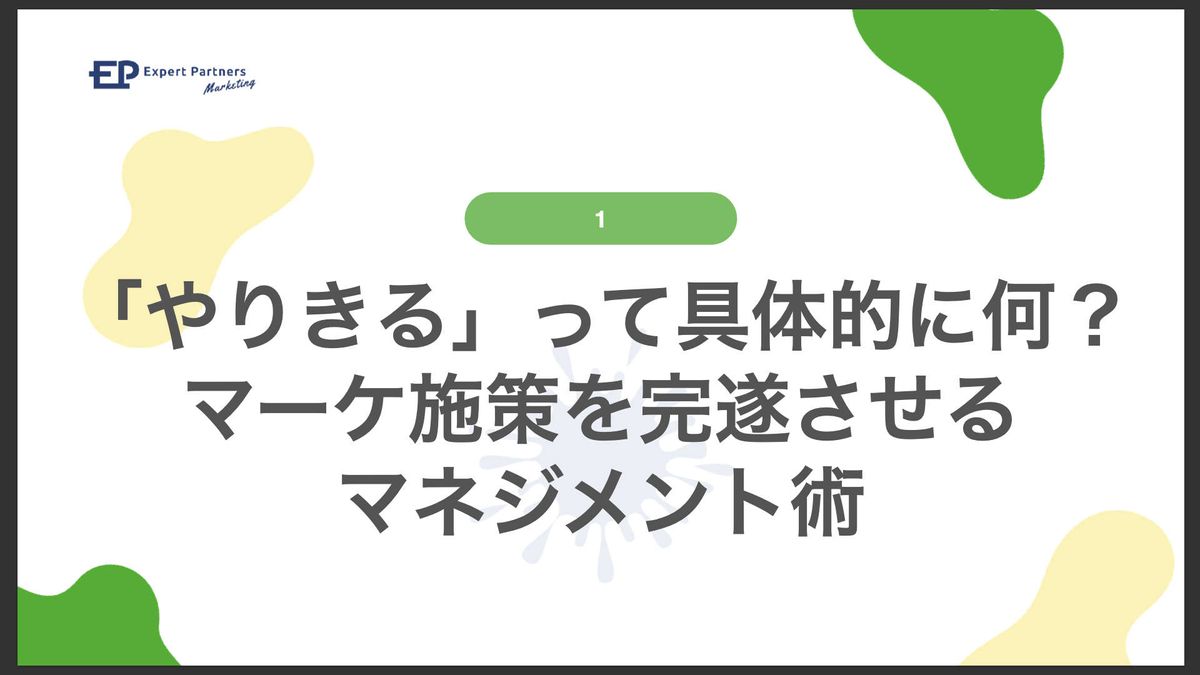企業のマーケティング支援を行う株式会社Digital Arrow Partnersと株式会社SAKIYOMIの共催セミナー。今回はSAKIYOMI社の執行役員CMOで『マーケティングの全施策60』の著者・田中龍之介氏と、Digital Arrow Partnersの小畑匡平氏によるパネルディスカッションの模様をお伝えします。1人マーケ統括の田中氏が実践した50超のマーケ施策と効果的な打ち手について語られました。
マーケ施策をやりきるためのマネジメント術
小畑匡平氏(以下、小畑):それではここから、パネルディスカッションとQ&Aの時間に移らせていただきます。
田中龍之介氏(以下、田中):はい、お願いします。
小畑:このパートでは、事前に用意したテーマをもとに田中さんと対話形式でお話しできればと思います。最初のテーマは、「『やりきる』って具体的に何か? マーケ施策を完遂させるマネジメント術」についてです。
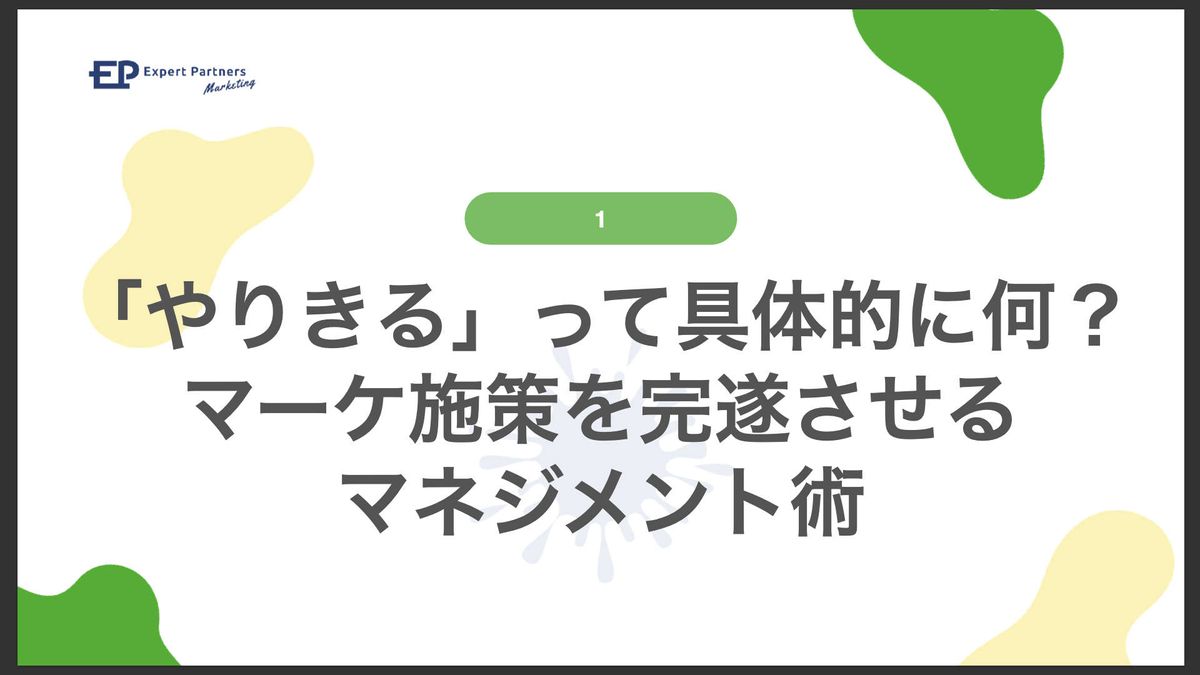
田中さん、BtoBマーケの現場で実際にマネジメントをしていく中で、「これはうまくいったな」と感じた施策や、「これは難しかった」というような経験はありますか?
田中:そうですね、大きなインパクトがあったのは、やはりコンテンツマーケティングですね。Instagram、YouTube、SEOといったところはすべてうまく機能したと思っています。
これはSAKIYOMIとしてももともと得意な分野だったというのもありますし、僕自身を含めたマーケチームのコアな強みでもあります。それに加えて、参入した当初の市場状況として、競合他社があまりコンテンツマーケに力を入れていなかったこともあって、比較的スムーズに成果を出すことができました。
小畑:なるほど。その上で、マネジメントの観点から見て、施策をうまく回す上で意識されていた点はありますか?
田中:これはマネジメント論というよりも実行上の要点かもしれませんが、「経営陣や責任者がどれだけ本気でコミットできるか」がかなり重要だと思っています。
例えばコンテンツを作るとなった時に、それを完全に外注任せにするのは正直かなり難易度が高い。クオリティやスピード感、ブランドの一貫性を保つ上でも、やはり中の人が深く関与しないと難しいんですよね。
その点、SAKIYOMIでは、僕自身がマーケ責任者としてしっかりコミットして、チームを組みながら推進してきました。現在、正社員のマーケメンバーは僕を含めて2人ほどですが、それ以外はすべて業務委託のプロフェッショナルの方々と組んで、同時に10件から20件程度のマーケプロジェクトを並行して動かしています。
そういった体制がうまく機能しているのは、責任者が現場に深く関わっているからこそだと思います。
初期アウトプットの成否を分ける、責任者の関わり方
小畑:責任者や経営層が、BtoBマーケの施策レベルにまでしっかりコミットしていくということですね?
田中:そうですね。特に最初の1本目は、責任者自身が深く関わるべきだと思います。もちろん、その後は徐々に任せられる範囲が広がっていきますし、今の僕自身も、具体的な施策に関わる部分はかなり減っています。中には定点観測だけしているプロジェクトもありますが、最初のアウトプットをつくる段階では、やはりかなりのコミットが必要だと感じています。
小畑:最初のフェーズでは、たとえ責任者であっても実際に手を動かして進めていくということですね。
田中:そうですね。そのほうが結果的に最短距離で成果につながりますし、自分自身が早く手を離せるようにもなると思います。
小畑:わかります、めちゃくちゃありますよね。それに、責任者自身がまったく経験のない施策について、ディレクションやクオリティ担保をしようとするのは、現実的には難しい部分があると思います。
田中:本当にそうで、例えば業務委託のメンバーとチームを組んで、「ここをもう少し良くしたい」と思った時に、どうリクエストすればいいかがわからないと、結果として60点の施策にしかならず、成果にも結びつかないということが起きがちなんですよね。
小畑:それは本当に「あるある」ですよね。ありがとうございます。ですので、みなさんへのメッセージとしては、まずは自分で手を動かして施策の解像度を上げていきましょう、ということに尽きるのかなと思います。
田中:そうですね。ちなみに御社の場合、マーケチームはどういう体制で動かされているんですか?
小畑:うちの場合は、正社員の倍以上が業務委託のメンバーという構成になっています。正社員は基本的にディレクターが中心で、施策の実行部分はフリーランスの方にお願いしているかたちですね。
さっきお見せしたホワイトペーパーもそうですが、「これをつくるのはこの人」「TikTokを運用するのはこの人」「LPを作るのはこの人」といったように、領域ごとにスペシャリストをアサインしています。
また、例えば今日お話ししたセミナーの構成なども、実際には別のフリーランスの方が企画を考えてくれていたりするんです。そうした専門性のある人たちをうまく組み合わせていく。正社員のディレクターは、そうした力を単なる足し算ではなく、掛け算に変えていく役割を担う。その体制が非常にうまくいっています。
マーケ施策の進行スピードを2倍に速めるメンバーとは?
田中:少し話がそれてしまうかもしれませんが、SAKIYOMIで業務委託メンバーをマーケチームに採用してきた中で、特にインパクトが大きかったのは、「図解を最速かつ高クオリティで量産できる人」が1人いるだけで、施策全体の進行スピードが体感で2倍くらいになる、という実感がありますね。
小畑:それ、めちゃくちゃわかります。
田中:図解があると、そこから記事にしたり、YouTube動画に展開したり、セミナー資料に落とし込んだりと、さまざまな形で再利用がしやすくなるんですよね。だから軌道修正も早くなるし、とはいえ責任者がすべてのスライドを自分で作るのは手が回らなくなる。
なので、図解が得意な人材は、僕にとってはマーケチームをゼロから組成する時に、最初に確保したいポジションかもしれません。
小畑:それ、めっちゃありますね。一番最初のアウトプットとしても、図解ってすごくつくりやすいですし。
田中:そうなんです。図解って情報整理のハブになるんですよね。
小畑:結局、動画で話す時も、ウェビナーでプレゼンする時も、図解をベースにして話すことが多いじゃないですか。
田中:そうそう。
小畑:だからこそ重要なんですよね。しかもポイントなのが、構成をあらかじめ考えて、それをきれいにデザインしてくれる人というよりは、口頭で説明した内容をその場でキャッチアップして、自然なかたちで図解に落とし込める人がいてくれると、すごく助かるというか。
田中:めちゃくちゃ大事ですね。極端な話、10分話すだけで翌日にスライドが上がってくるような動きができると、全体の施策が倍速で進んでいくイメージです。
小畑:そうそう、それなんですよ。まさにうちの資料も、そういうスタイルで作ってくれているフリーランスの方が担当していて、かなり助かっています。
田中:それはいいですね。
小畑:ですよね。じゃないと、ここまでのクオリティに作り込むのは、社内だけではなかなか難しいですから。
中小・スタートアップのマーケチームが最初に採用すべき人材
田中:確かに、これは意外と盲点かもしれませんね。マーケをやると聞いた時、多くの人はまず広告運用に強い人とか、戦略に長けた人を採用したくなると思うんです。でも実際には、それよりも図解を作れる人、最初のアウトプットを担える人を優先してチームに入れることで、全体の施策の質もスピードも底上げされる気がしています。
小畑:コンテンツであれば、自分たちで企画や設計ができるので、そこまで大きなコストをかけずに始められるじゃないですか。
田中:間違いないですね。
小畑:なので、明確に言うと、すでに予算が潤沢にあるような大企業であれば、優秀な広告運用者を複数集めて、「どの媒体でどんな広告を出すのか」という戦略設計に注力していくべきだとは思うんですよ。
ただ、今日ご参加いただいているみなさんの中には、スタートアップや中小企業の方も多くいらっしゃると思っています。そういった場合には、派手な広告展開よりも、地道な積み上げ型で、コンテンツを量産していくような草の根的な戦い方が有効になることが多いですよね。
そう考えると、やはり社内に「コンテンツを自ら生み出せる人」が1人いると、マーケティング施策の推進力がぐっと上がる。1人目のマーケ人材として、そういうスキルを持った人がいるのは非常に強いなと思います。
田中:いやぁ、まさにその通りだと思います。みなさん、本当にお勧めです。「コンテンツの図解をよしなに作れる人材」は、BtoBマーケチームの初期においてはかなりのキーパーソンになりますよ。
小畑:本当にそうですよね。僕もまったく同感です。ありがとうございます。ここは田中さんとすごく意見が一致しましたね。
田中:ですね(笑)。
▼主催
株式会社Digital Arrow Partners  PR
PR