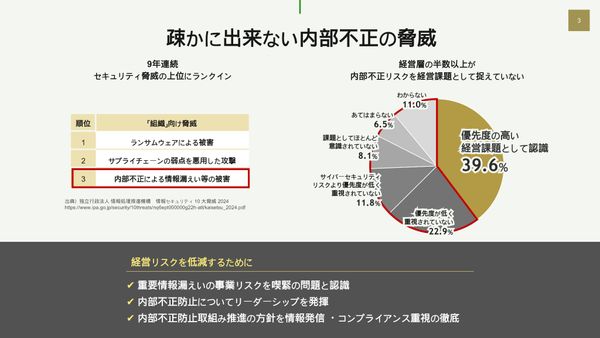 PR
PR2025.09.16
退職者の営業秘密の持ち出しや巨額損失事例も… 内部不正が起こる要因とログ監視の抑止策
リンクをコピー
記事をブックマーク
岩佐十良氏(以下、岩佐):僕は箱根本箱が3件目です。里山十帖をやって、2件目が山形の(山形座)瀧波という宿で、ここが3件目なんです。正確に言えば滋賀県大津市でも7棟の町家を再生したホテルを同時並行で作っていたので、3.5件目と言うか。僕のやり方は、まず壊してみるところから始まって、壊しながら「ここ使えるね」「ここ使えないね」とか考えます。
最初に「ここの抜け感はこうしたいよね」とか全部決めているので、そこはもうばーっと全部壊しちゃって。頭には完成した時の絵がもう浮かんでいて、部屋の抜け感もこうしたいねとか、けっこう抜け感がいいから、この抜け感をやっぱり重要視したいということで、壁はこの位置まで全部壊すぞとか。
ベランダにも壁があったんですけど、それも全部壊そうというのは決めて、とにかく壊していく。破壊していくというかね。
海法圭氏(以下、海法):まあ階段だけじゃなくて、最初から「本当に全部壊したいね」と岩佐さんと話していたんですけど(笑)。
(会場笑)
既存の状態を剥ぎ取ってみて、どこまでその既存を尊重するかは、やっぱり壊してみないとわからないことがたくさんあります。「あ、なんかいいものが出てきたね。これでこういうふうにデザインできない?」というところからスタートしていくのも、リノベーションのおもしろさだと思います。
染谷拓郎氏(以下、染谷):リノベーションも本当に剥がしたり壊してみないと、設計が進まないようなポイントがいくつかあるということですよね。
岩佐:そうです。結局、壊さずに設計すると安全牌でしか設計ができないんですよ。壊して全部を見てから設計をしないと、使える部分と使えない部分がわからないんです。でもこれは、実はすごく危険なやり方でもあります。
壊したということは、作り直さないと施設として再生ができないんですね。この状態で、もしもあとから予算が足りないことが判明した場合、廃墟と化すかもしれない。
岩佐:あしかりの場合も、まだあの状態なら売却できるんですよ。だれかが買うじゃないですか。ザ・保養所でもちゃんと不動産価値がある。でも、この状態(壊したあと)は、建物の価値ゼロですよね。
ゼロというより、「これだったら、むしろきれいさっぱり更地にしておいてくれよ」くらいの状態です。むしろ手に負えない状態にするということなので、実はすごくリスキーなやり方ではあるんです。
しかも、投資総額がいくらになるかは読めないです。まぁ、もちろんそこは経験値である程度はわかるけれど、分解してみないとわからないので読めないし。でも、投資額を最初から把握したいとなると、つまらない設計しかできないんですよね。大胆な設計ができないので。そこは僕流に言うと「全部壊しましょう」となる。海法くんからすると、そこは怖いんだよね。
設計者としてはあとでなにを言われるかわからないし、どうなるかもわからない。予算に収められるかどうかもわからないので怖い。日販さんにとってみれば、それこそ「事業予算がどうなるかも見えない中で壊すって、大丈夫なの?」という話です。
そんな中で、それをみんなでやりました。日販さんの決断もすごいし、海法くんも「それでやろうよ」ということになったのはすごいよね。
海法:作り手側の視点で話しますと、建築家は模型を作るじゃないですか。あれは実物大のものを小さい縮尺で再現して、その空間に入り込むことで、自分の想像力では思いつかないような発見をしていきたいから作っているんですよ。
そういう意味では、内装や階段などの余計なものを壊し切って、既存の素の状態を設計の早めの段階で見られたのはよいことだったと思います。それこそ、既存の状態は実物大の模型みたいなもので、自分が新築でゼロから作り上げるのとはまた違うような設計の、発想の源にしている感覚があります。
染谷:事業主側の感覚としては、この(建物が壊されていく)状態が長く続いて、もう雨ざらし状態になっていて、謎の動物の糞とかが落ちていて……。「なんか来てるな」という感じだったでしょうね。
(会場笑)
お二人が毎週くらいの感じで現場に行っていたんですけど、本当にどんどん変わっていく姿がすごく印象的だったんですよね。(「写真を指して)これは先ほどの、吹き抜けの2階のところなんですけど、階段を全部取っちゃったんですね。
娯楽室だったところは打ち合わせスペースになっていました。もう本当に、この打ち合わせスペースを見るだけでちょっと吐き気がするくらいです(笑)。
(会場笑)
いろいろな思いがあります。
岩佐:吐き気(笑)。
染谷:吐き気がします(笑)。(写真を指して)こんな感じで現場に入っていました。右にいらっしゃる方は、今、箱根本箱の支配人をやられている窪田さんという女性で『自遊人』の社員さんですね。
僕がお二人を見ていて、すごくびっくりしたのは、本当に視線をとても大切にされているというか。目線とか、視線ですね。
海法:見えるもの。
染谷:見えるもの。「主観的に、ここからどういうビューが見えるか」という話がほとんどみたいな感じで、それがすごくおもしろかった。(写真を指して)おもしろいのはこの辺りから。
岩佐:ジャングルだった場所に露天風呂を作ろうってね。日販のみなさんはもうほとんど敷地とは認識していなくて、「ここに露天風呂は作れないんじゃないのか」という話も出ましたが、そんなことはない。
つまり「その空間を上手に使えば露天風呂を作れるよ」という話をしました。そこに入ったときの目線でやっているんですよね。
染谷:いつも「ここからどう見えるか」をすごく考えてられていましたよね。部屋からのビューとか、「ここに露天風呂を置いたときに山がこう見えるから、こっち向きにしよう」という話をずっとされていた印象があります。
(写真を指して)こういう感じですね。ここからどう見えるのか、みたいな。岩佐さんは、もともと建築出身ではないところから、こういう施設を作るようになったんですよね。その岩佐流に至った背景は、どういうところから来ているんでしょうか。
岩佐:(僕は)建築出身じゃないんですけど、大学は美術大学のインテリアデザイン専攻で、建築に近いところにいました。僕は在学中にグラフィックデザインの仕事と空間構成の仕事をやっていたので、建築じゃないけれども、空間はけっこう重要視するタイプです。
ただその後、23年~24年間は建築関係に一切関わっていませんでした。それでいきなり里山十帖を作って、「やっぱり空間はおもしろいな」という状態の中で、瀧波やここ(箱根本箱)をやったんです。
僕がすごく重要視するのは、今おっしゃった人間の快適性、本質的な快適性とか。目に見えるもの・耳から入ってくるものみたいな、五感で感じるものはすごく大切にしたいタイプなんです。
とくに箱根本箱の景色はけっこうこだわりました。この箱根本箱は、実は敷地の面積があまり広くはないんですが、上手く切り取っていけば、その敷地が何十倍にも広がるように見えるはずと考えていました。要は都内の狭小住宅のような感じです。
広いスペースを無駄に使うと、ただ広いだけになってしまうけれど、狭小住宅と同じような考え方でいけば、スペースは何十倍も有効活用できると僕はいつも考えていました。
海法くんに言っていた、「おこもり空間」。それもあとで出てきますが、まさにそんな空間スペースをいかに使うかについて、よく話をしていました。
染谷:海法さんは、そのあたりの目線の使い方とか、岩佐さんの手法を見られていて、例えば「建築畑の方とはぜんぜん違う手法だ」という感じはあるんですか? それとも、アプローチは違えど、感覚的には理解できるようなところもあるんでしょうか。
海法:そうですね。先ほど岩佐さんが「五感」とおっしゃったように、視線もそうなんですが、温かさなどの熱環境やエネルギーの消費量、構造検討による地震等に対する安心感、周辺環境とのつながり方など、そういうあらゆるものをインテグレートさせて答えを見つけることは、やっぱり建築家にジェネラリストとして求められる職能なんです。
岩佐さんは里山十帖などを経て、見えるものや聞こえるものに対して、ものすごい嗅覚で実践している感じですよね。里山十帖のときの岩佐さんも、なんだかもうおかしな感じになっていたんですよ。
(会場笑)
もう本当に普通じゃない現場になっていました。大工集団を二組取り入れて動かす時点で、もう少々掟破りなんですよ。
染谷:なるほど。
海法:大工集団が喧嘩したり、床を開けたら水が大量に溜まっていたりとか。普通の現場であれば、役割分担しているはずの事業者・設計監理者・現場監督という三役を、岩佐さんが一人でこなしていて。普通は役割分担して、緊張感を高めてクオリティを上げるわけです。岩佐さんはそれを全部一人でやっていました。
岩佐:海法くんには、僕が里山十帖を作るときに一部屋デザインしてもらって、後半のぐちゃぐちゃな現場を見に来て、ビビったんだよね。
海法:ぐちゃぐちゃでしたよ。なかなか見たことない、すさまじい現場でしたね。
染谷:すごい。それをまとめたんですね。じゃあ箱根は里山十帖に比べると……。もちろん比較できない部分はあるんでしょうけど。
岩佐:僕にとってこの箱根本箱の現場は、ぜんぜん怖くないというか。今日、箱根本箱の建設に関わった方は来ていないですよね。
染谷:はい、大丈夫です。
岩佐:僕がここで思ったのは、やっぱりゼネコンなので、安全牌を踏まないと作業が進んでいかないんですよ。「四の五の言わないで、さっさと工事進めろよ」というところがあって。なにかと「修正の見積もりとご承認を」とか言われて、「承認の前にさっさと仕事しろよ」という話はありましたね。
染谷:(写真を指して)これもレストランのスペースですよね。海法さんは事務所でのスタディも含めて、最後のほうは現場にも1週間に1回のペースで来られていましたし、岩佐さんはほぼ毎週くらい来ていましたよね。
毎週現場のゼネコンさんと進捗会議をやるんですけど、8月1日オープンという話をしているのに、例えば3月や4月で「マイナス14日の進捗です」と出してくるような状況が続いていました。しかも、そのマイナスがだんだん増えていく(笑)。
(会場笑)
「やってください」「やれません」「やってください」という押し問答も含めて、ぐりぐりにやっていたのがこの時期ですね。(スライドを指して)こういうのがだんだんできていって、ここぐらいまでくるとすごく感動します。
(写真を指して)ここが箱根本箱のメインラウンジになるのですが、海法さんはここの設計にあたって考えられたことはありますか?
海法:今回、メインラウンジに大きな本箱と、館内全体に散りばめられた小さな本箱を作っているんですけど、(スライドを指して)これは大きな本箱の方です。大きな本箱は岩佐さんからも「象徴的な場所として作りたいので、そこに人が入れるようにしてほしい」とオーダーを受けたんですよ。最初は「マジか」と思ったんですけれど。
(会場笑)
「本棚に人が入っちゃうのか」と思って。どうしようかなと思いましたが、よくよく考えてみると、ここでの設計は、人と本がどのように出会うか、その出会い方の風景を作り出しているなと思ったんです。
最近、街中や図書館などで見る本と人の出会いの風景って、だいたい想像がついちゃうと思うんです。テーブルで本を読みますよとか、電車の中で本を読んでいますよとか。
もう出尽くしているんですよね。本の大きさや種類も大きくは変わらないし、特に日本においては、読書まわりに出てくる家具もだいたい同じになっちゃっているのが要因の一つです。そこに含まれないような人と本の触れ合い方を実現できたら、すごく価値のある空間になるなと考え直して、おもしろいオーダーだなと思って設計しました。
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。
すでに会員の方はこちらからログイン
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!
スマホで読み込んで
ログインまたは登録作業をスキップ
価値観が多様化する現代における“新しいフォロワーシップ”
2025.10.09 - 2025.10.09
【自民党総裁選】新総裁記者会見
2025.10.04 - 2025.10.04
【Re-Communication Challenge】学ぶ楽しさで地域とキャリアを変える
2025.08.19 - 2025.08.19
まだリーダーになりたくない人向け ラジオ風ウェビナー『リーダーが育たないのは“心理的安全性”の副作用?』 ~「安心感」を「挑戦力」に変えるリーダー育成の実践ロジック~
2025.09.10 - 2025.09.10
【19分で人生変わる】東証上場社長が実践する目標達成術
2024.08.03 - 2024.08.03