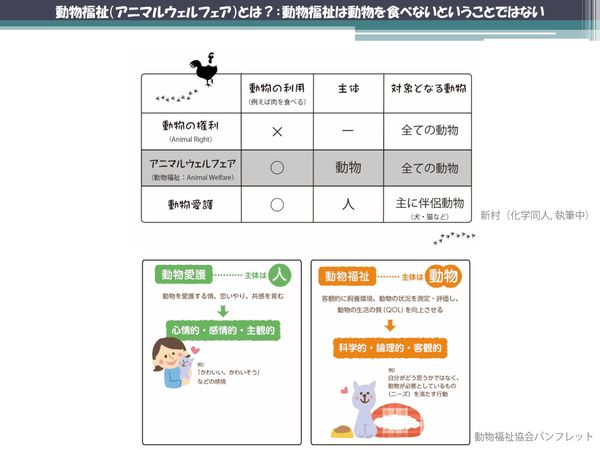 PR
PR2024.10.10
将来は卵1パックの価格が2倍に? 多くの日本人が知らない世界の新潮流、「動物福祉」とは
リンクをコピー
記事をブックマーク
広木大地氏:今日は『エンジニアリング組織論への招待』という、僕が書いた本に関しての概観というか、いったいどういうコンセプトで書かれた本なのかという話を通じて、仕事をすることや、この書籍のサブタイトルでもある「不確実性に向き合う」ことについて、みなさんと一緒に考えていけたらなと思っています。よろしくお願いします。
まず簡単に自己紹介です。あらためまして、広木大地と申します。2008年に新卒第1期生としてMIXIという会社に入りました。基本的にはいろいろな広告商材を作ったり、機械学習の走りのようなことをしてコミュニティ分析をして商品にしてみたり、あるいはフロントエンドのライブラリを作ったり、フロントエンド、バックエンド、インフラなど、そういう言葉があまりなかった時代に、ソフトウェアエンジニアとしてなんでもやっていました。
いろいろなプロジェクトでさまざまな体験をしながら、ある時、事業自体の盛り返しをしていこうと、ビジネスのマネジメントも含めてやっていくことになりました。
もともとはスペシャリストとしてのキャリアを歩んでいたのですが、事業を中心に見ていくようになり、組織改革でさまざまなイノベーションが生まれるような仕掛けを作りました。『モンスト』をはじめ、たくさんの新ヒット事業が出る会社となった時に、退社することになりました。
新卒で入った会社に7年いたら「十分いただろう」と自分の中でも思ったのもありますし、技術と経営の間にさまざまな問題があるなぁというところで、このノウハウを世の中に還元しないと日本社会自体にとってもいいことがないんじゃないかと考えて、2016年にレクターという会社を創業しました。
技術組織のお手伝いをさせていただく中で得たさまざまなノウハウを、1冊の本にまとめていきました。それがこの『エンジニアリング組織論への招待』という本です。
この本はちょっと変わったことになっていて、「ブクログ」において、その年のビジネス書の大賞をいただきました。また、翔泳社さんからは、ITエンジニアに読んでもらいたい技術書の大賞をいただきました。技術書とビジネス書の両方の分野で大賞を取った本は、僕の知る限りこの本だけで、ビジネスと技術が近いところにあるぞ、ということが出てきているんじゃないかなと思いました。
最近では朝日新聞社の社外CTOとして、経営陣含め現場の技術陣と共に、より新しい新聞、ジャーナリズムのかたちを見つけていったり、グッドパッチというUXの会社の社外取締役も務めています。いろいろやっているんだな、とご理解いただければと思います。

お話をする前に、「みなさんは仕事に対してどんなイメージを持っていますか?」ということを問いかけたいです。

1つのイメージとしては、決められたタスクをひたすら進めていくようなイメージ。もう1つの捉え方としては、なにかをみんなで決めたり、仮説を立てて具体化していくというイメージ。

「仕事をする」と言った時に、具体化していくことと、タスクを減らしていく・こなしていくという2つのイメージがあるんじゃないかなと思っていて、その中で私たちがどういう活動をしているのかを、ちょっと考えてみたいなと思います。

近年、たくさんの人が関わるような、特にソフトウェアビジネスに関わる人がやっている仕事について考えてみると、同じ作業を繰り返して最終的に物事を実現していくというより、はじめは曖昧な状態で何も決まっておらずモヤモヤとしているものが、だんだんと方針が定まってきて、最終的にはマニュアルや契約、ソフトウェアといった具体的で明確な表現物になって実現されていく。こういう過程を通っていくことが多いんじゃないでしょうか。
この過程の中で私たちが仕事をしているとした場合、モヤモヤとしている状態のものから、具体的で明確なものにしていく過程が仕事なんじゃないかと考えられると思います。

本書『エンジニアリング組織論への招待』では、この過程、つまり曖昧で不確実性の高い状態であるものから、徐々に不確実性の低い確実な状態・明確な状態にしていく過程をエンジニアリングだと定義しています。これは物事を実現する工学的な定義からも外れていない、1つのエンジニアリングの定義と捉えることができます。

では、この仕事を行っていく過程で、実際に進めていくと減っていくものは何かということを考えれば、仕事を進めるということの正体に近づけるんじゃないかと考えました。

それが先ほどもチラッとお出しした「不確実性」という言葉です。これがみなさんがやられている仕事を理解する上でのキーワードになっていくと考えています。

エンジニアリングを「不確実性を減らす試み」だと考えると、さまざまなことが理解できます。プロジェクトをこなしていく過程でも不確実性が減っている。この図は「不確実性コーン」と呼ばれる図です。
あるプロジェクトに取り掛かり始めた時、プロジェクト前半はその納期には大きな不確実性があります。状況によっては最初の読みから4倍であったり、あるいは4分の1で終わるかもしれない大きな幅を持っています。
この状態から仕事を効率よく進めれば進めるほど、この見込みの幅がどんどん狭まっていき、後半になると不確実性が減っていって、いつぐらいにできるのかという確度が上がっていく状態になると思います。
これは理想的なケースです。うまくこの不確実性に注目しないと、プロジェクトの後半になってから「実はこんな不確実なことがあった」というものが見つかって、思ったより時間がかかるかもしれませんが、理想的にはだんだんと確度が定まっていくのがプロジェクトのあり姿だと思います。
同時に、組織という観点でもこの不確実性という補助線を入れてみると、同じものだということに気づくことができます。社長自身が具体的に1個1個のアクションをすることは難しいから、大きな会社の組織では曖昧な構想をまずはブチ上げる。
その構想は、ツッコミどころなどいろいろ細かく考えるとキリがないところはあるのですが、こっちでいこうと話を決めて、次に部長陣がそれを「曖昧ながらもこういう方向の方策をしていくべきなんだよなぁ」と定義づける。
さらには次のマネジメントラインの人が、具体的な方策へと解きほぐしていき、最終的に社員が分解された具体的な策を実行していく・行動していくということを繰り返すと、組織は「仕事をした」という状態になります。
これも、私だけが言っているわけではなくて、経営学の中ではよく知られた定義です。このような不確実性を減らす試みを補助線として仕事を捉えていくと、何がわかるのでしょうか。

よくあるマイクロマネジメント型の組織、あるいはエンパワーメント型の、権限を渡している型のチームを考えた時に、不確実性という補助線を入れるとより詳しく理解することができます。多くの不確実性に耐えられる・応えられる、つまり不確実な状態からでも実現していけるチームほど、生産的だと言い換えることができるからです。
この抽象的で曖昧な要求がやってきた場合に、ある上司が細かく具体的に指示しなければ実施できないチームは、上長の処理能力がボトルネックとなってしまって、高度に生産的なチームにはなかなかなりにくいです。
リーダーとメンバーの格差が大きすぎて、リーダー自身が分解してあげないとなかなかできない組織はこうなりやすく、この場合、組織の出せるアウトプットには限界が出てきてしまうわけです。
それに対してエンパワーメント型と言われるチーム、つまり不確実な要求をそのまま受け取って具体的なアクションに展開できるような組織は、そういった観点では生産的になります。これはチームとリーダーの格差が減ってきて権限が委譲されていたり、チーム内のコミュニケーションが進んでいるとなりやすい状態です。これはアジャイルの文脈で「自己組織化」と呼ばれるものです。
つまり、「自分から見て上長やその周りの指示が具体的じゃないから仕事が難しいよ」とか「仕事ができないよ」という状態は、まだ自分がエンパワーメントされた不確実な要求に応えられる状態ではないんだなという状況でもあるかもしれない。
逆にそういうことを考えることができるのに、細かく指示しすぎるマネージャーがいると、マイクロマネジメントでモチベーションの湧きにくい職場になってしまうかもしれません。こういったことも、不確実性に応えられるチームのほうが生産的だという補助線を入れると、理解することができます。

僕は「夏休みの宿題」という話をよく例に出すので、ここでちょっとお話しします。中学・高校時代ぐらいに夏休みの宿題が出ていました。僕は最初、ドリルとか日記とか、いつまでにやったらどのぐらい終わるのかが比較的読みやすく、やれば終わるものから手をつけて素早くこなしていたんですね。
夏休みの後半になってくると、自由研究とか苦手な教科の宿題とか、創作活動が入ってくるような、ちょっと曖昧で不確実性の高い宿題が残っていて、それをどうしようと思いながら遊んでいるとか。「宿題が残っているのにな」とずっと不安を抱えたままこなしている。そういった気分になってしまいました。

そのことに気づいた次の年からは、不確実性の低い宿題に先に手をつけるのではなくて、不確実性の高い、どのぐらいで終わるかわからないところから手をつけて、それが一段落してきたら確実な宿題をこなしていこうと考えるようになりました。
そうすると、「あとどれぐらいこれをやらなきゃいけないのか」とか「いつまでに終わるのか」ということに怯えながら夏休みの後半を過ごすことはなくなり、非常に遊びやすいし精神的に健やかな日々を過ごせたという教訓がありました。これもプロジェクトの中で同じことが言えるなと思っています。
プロの仕事の仕方と「パーキンソンの法則」を紹介したいです。パーキンソンの法則は、「仕事の量は完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する」という経験則です。つまり余裕があればあるほど、その部分に無駄な仕事を詰めてしまうという考え方でもあります。

プロがなにか物事をこなしていく時に、自分がわかる確実なものから進めていくと、どんどん進んでいってタスクの量は減っていくのですが、最後の最後にクオリティに関わるところ、不確実性の高い部分に相対した時に、なかなかスケジュールどおりにいかなかったり、あるいは揺り戻し、あるいは差し戻しといった外的な要因で変化するものに出くわしてしまって、後半バタバタとしてしまう。これが仕事に慣れていないうちはよくあるのではないでしょうか? 僕もそうでした。
そうではなくて、むしろ最初の短い時間、最初の3割ぐらいの時間で7割ぐらいのクオリティに持っていく方法はないかと考える。そこの間にできる限り試行錯誤して、あるいはお客さんやユーザー、ステークホルダーの人たちのフィードバックを受けながら、確かなものにしていく。残り7割の時間を使って、クオリティを7割から100パーセントに揃えていくことにエネルギーを費やせたらうまくいくな、ということがわかってきました。
プロはそういうふうに不確実性の高い部分から手をつけていき、低い部分に関しては後回しにする。対して、まだ仕事に慣れていない人は確実なものから進めていってしまうという特性があります。
では、この仕事の進む・進まないの源泉でもある不確実性の究極の発生源とは何なのか、というところについて考えてみたいと思います。それがわかれば、生産的な組織や仕事の仕方が見えてくるはずです。

突き詰めて考えると、人間が本質的にわからない、つまり不確実性を発生させるものは、たった2種類だと言うことができます。1つは「未来」です。私たちは未来を知ることができないため、未来で起こることはわかりません。もう1つは「他人」です。他人というものは、何を考えているか究極のところわからないため、自分の想像とは外側の動きをするものです。

「未来」と「他人」というこの2つを別の用語で置き換えると、環境の不確実性、あるいはマーケットの不確実性、通信不確実性、コミュニケーションの不確実性と言われるものがそれに当たります。
じゃあ、こういった仕事における不確実なものに取り組もう、そこからやっていけばいいんだな、そうすれば仕事は効率よく進むのだな、と考えた時に、なかなかうまくいかないのが難しいところです。なぜ難しいのかというと、人が不確実性に向き合う時に生まれる感情があるからです。

人は、わからないものに対して、あるコマンドを求められます。闘う、あるいは逃げる。これは心理学の分野で言えば、「Fight or Flight」という言い方をします。肉食動物がなにか恐怖を感じた時に大きく吠えて襲いかかって来たり、あるいは草食動物がなにか怖い気配を感じた時にサッと物陰に隠れてしまう。未知のものに対して攻撃または回避をするということは、人間も含めた動物の本能として組み込まれているものなのです。


こういったものに対して、わからないもの・不確実性なものに出くわした時に、私たちはある種の怒りを感じたり、あるいは恐怖を感じたりします。異分子だと感じているわからないものに、自分の立場を危うくされるようなことをいきなりされると、やはり怒り出す人が多かったりします。
怒っている時はいろいろな理屈を述べているのですが、怒りというのは自分の大切なものを攻撃されたと感じる時に発生します。見た目や威圧的な態度に反して、変化に弱い人は実はマウンティングや威圧、冷笑などを使って異分子を攻撃しようとします。こういった本能は、組織が新しいことを始めることを恐れる、そういった結果をもたらします。

もう1つの防御的行動や回避的行動も組織の中でよく見られます。目標に対する有形無形の圧力が大きい時、つまり納期やスケジュール、成果といったものに対する圧力が強い場合、その不確実性への恐怖が問題を隠蔽する方向に機能します。
例えば納期の圧力が高い状態では、マネジメントから真実の情報はどんどん隠蔽されてしまいます。プロジェクト終盤で問題が頻発するのは、わかっていなかったわけではなく、問題が自然と隠れていってしまう文化が醸成されたことによります。
こういった場合、「じゃあマネジメントがしっかり監視しておけば、そういったことが見つけられるんじゃないか」と考えるのですが、それをすればするほど無駄が生じます。これを「エージェンシー・スラック」と言います。これは経済学の用語なのですが、無意識の恐怖。そういったものが実際に会社の中のコストとなって現れて、リスクとなって発現するということが起きています。
「不確実なもの・わからないものをいきなりバッと押しつけられたぞ」と感じた時、「やらなければならないぞ、向き合わなければならないぞ」と感じた時に、怒りを感じる人がいます。これは攻撃的な本能に近いと言いましたが、実は怒りは二次的な感情に過ぎないということがわかっています。二次的な感情というのは生物として本能的にもともと備わっている感情ではないということです。
なにか自分が脅かされると感じる時、人間の脳は、本当は最初に恐怖が扁桃体に対して発火します。扁桃体は理性の脳に近い位置についているため、理屈で怒りという情報に変換しようとします。
怒っている人ってメチャクチャ理屈をワーッとしゃべって、「自分って間違ってる?」みたいなことを言ったりすることがあると思います。怒っている人ほど自分のことを「論理的に考えている」と捉えがちなのは、実はその怒りという感情は、本当は扁桃体が感じている悲しみや危機という感情を受け取って、その外側にある知的な能力を司る脳が防御・回避を起こそうとする時に怒りが生まれているからです。
なので、自分がすごく怒っているかもなと思う時に、人に対して怒っている感情をぶつけるんじゃなくて、まずは「自分はちょっとそれで悲しかったよ」とか、「ちょっと悲しいと感じたよ」と言うだけで、怒りの連鎖は防げたりするので、なんらかのテクニックとして覚えておいてもらえるといいかもしれないです。
(次回へつづく)
関連タグ:

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
マネーゲームの「手駒」にされる起業家たち 経営学者が指摘するエコシステムの落とし穴

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.08
仕事の成果につながる「自分の才能」を言語化するヒント 今は「自分らしさ」を求められるけど、誰からも教わっていない…

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
マネーゲームの「手駒」にされる起業家たち 経営学者が指摘するエコシステムの落とし穴

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.08
仕事の成果につながる「自分の才能」を言語化するヒント 今は「自分らしさ」を求められるけど、誰からも教わっていない…