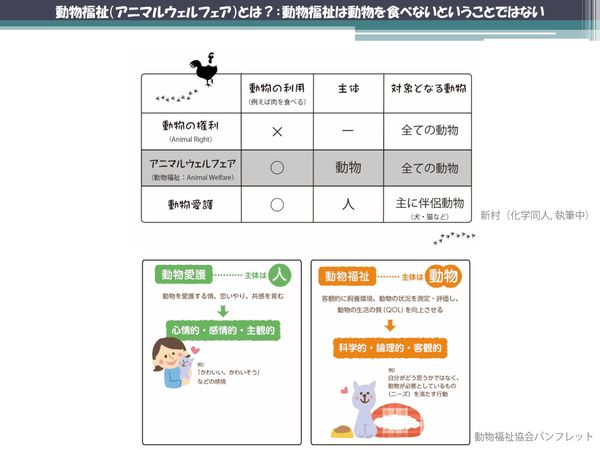 PR
PR2024.10.10
将来は卵1パックの価格が2倍に? 多くの日本人が知らない世界の新潮流、「動物福祉」とは
リンクをコピー
記事をブックマーク
川口真沙美氏(以下、川口):次の福光委員からいただいたのが、一番身近にあるデザインということで。
福光松太郎氏(以下、福光):まあ愛用といえば愛用で、仕事そのものの話になりますが、一升瓶に入った日本酒って書いてあるのは要するに一升瓶のことです。瓶のことですね。

気を惹かれるプロダクトにはやっぱり、いいデザインの中に新しさが必ずある。そうでないと人はそれを買ってみようと思わないので。いかにロングライフに新しさっていうものを発揮できるかはとても重要なことだと思うんです。
実は、一升瓶っていうのは戦前、昭和10年代くらいにこの格好で登場しております。少し前は同じような格好だけどちょっと違った格好で、上の栓がバネのついた陶器のバチっと止める、機械栓っていうんですけど、それになってまして。その前はいわゆる徳利。2升くらい入るいわゆる貧乏徳利です。その前は酒樽になるんですね。
それで、酒樽そのものから少し話しますと、あれは吉野の杉と京都の竹でできているんです。これは灘の人たちがデザインしたのです。
東京、江戸に幕府ができて、急に都市が作られていくので、最初は独身者と単身赴任者の人が集められて町が作られていったわけですが、急にマーケットができてね。それもごく変わった、独身者と単身赴任者だけの町がまずできまして、それで非常に気性が荒くて酒が飲みたいというマーケットができて。
今の灘はお酒の主産地で大きいメーカーはみんなあそこにあるんですが、もう少し内陸に酒蔵があったんですね。それを東京・江戸ができたんで、わざわざ酒蔵が海岸線まで出てきました。
何をしたかというと、物流に海を使おうと。いわゆるシャトルシップというか、廻船というのを作って、酒を載せる樽廻船を作った。
そのときに、江戸の人たちに格好良く受け入れてほしいので、吉野の杉と京都の竹で四斗樽という、すかーっとした当時本当に新しいグッドデザインを作って。それが船に乗って、日本橋の新川の運河に到着するのを心待ちにしたわけでね。
だからすごいかっこいいもの、かつ、酒がやってくるというところから、酒の容器が始まってるんです。
貧乏徳利は、普通のうちでは四斗樽を買えないので、小分けしてもらうっていうんでニックネームがついた。お金持ちは樽で買うけど、そうでない人は徳利で買ったっていうんで。今は洒落になりませんけど、かつてはそういう洒落だったんですね。
それはけっこう長く、明治ぐらいまでずっとあって。それからガラスっていうものが入ってきて、それで瓶になっていくんですね。
このかたちの一升瓶っていうのは、だいたいこの格好でみんながこの型で行くようになったのは、たぶんもう第二次大戦直前からだと思います。
福光:私は、自分の会社に戻ったのが28歳くらいだったと思いますが、その当時はもう一升瓶は日本酒の主たる容器でした。当時私の30歳前後のころ、たぶん出荷量の8割が一升瓶(でした)。
だけど若い私には「なんかこれいい格好じゃないんじゃない?」って思って、要するに古めかしいように見えたか、「新しい感じがしない」と思ってね。
「こんなのに入れて売ってたら、そのうち若い人が買わなくなるんじゃないか」と思った。それで30歳を超えてしばらくした頃だったと思いますが、あえて榮久庵憲司先生のとこに一升瓶を持って行きまして「新しいかっこいい容器を作ってください」「期間は3年くらい待ってもいい」と。「ぜひやってほしい」ってことを、いくらかかるか考えずに言ったんですね。
私にとっては、それぐらい重要な、つまり跡を継ぐことを思っていたからすごく重要なことだった。それで、3年ぐらいって言わなきゃ良かったってくらい、何の反応もなくて(笑)。
(会場笑)
それで(笑)。しょうがないから1年くらい経ったとき「あれはどうですかね?」って、お酒持って世間話しに来たような感じで言いましたら「ああ福光君ね、できない」って。
「できない」と言うのは忙しいからだと思うじゃないですか。そうではなく「1.8リッターという容量を一番大きく一番美しく見せるフォルムはこれしかない」と。だから「これに自信をもって、これを使いたまえ」って言われて。
「はあー、そうなんですかー」ということになって、デザイン料は払ってないんだけど、お土産は2~3回持ってったと思う(笑)。
だから私にとっては、一升瓶と生涯付き合うっていう覚悟が、この榮久庵先生の発言でできたっていうかね。なんか「嫌な古い容器をずっと使わなきゃいけないのか」と思ってたのは、私の浅学菲才だった。
そのものの見方を変えられたということであって、実際今もこれ今のうちのプロダクトですけど、実に多彩ですね。色もいろいろできたりパッケージデザインもすいぶん進みましたので、まあ堂々たる商品として業界が一升瓶を使っております。
福光:しかし業界的に言っても、うちの場合はとくにかもしれませんが、一升瓶はもう出荷量の2割です。全部4合瓶という720ミリリッターが主流でして。それからもっと小さいもの。
日本酒業界の販売量というのは、消費量はなかなか伸びないんですが、販売本数は私のところなんかではこの20年で6倍か7倍になっています。要するに、小分けになっている。
みなさんの生活が一升瓶ではなく4合瓶を中心にして小さくなっていってる。多品種が出ておりますので、いろんなものを楽しみたいっていうのもあってですが、一升瓶のミニチュアみたいなものが一般型になってまして、必ず(デザインの)バランスを崩してるわけですね。そこはすごく残念です。
それで、私が35歳くらいで社長を受け継いだ頃でしたけど、「小瓶については自分がデザインをしよう」と思い、いろんなデザイナーの人と組んで瓶を作った。
瓶っていうのはご承知のように、型を起こして生産するとものすごくたくさんできます。そんなにたくさん私のところでは使えないので、瓶を作る人と組んで、各県1社ずつ私が優秀だと思われる酒蔵に「買ってもらえ」ってことで。
そういうことをしてまで、パッケージと瓶に取り組んだという歴史があります。ですから一升瓶というのは大変思い入れの深いものでございました。
福光:それからもう1つ。ご覧になったことがあるかと思いますが、清酒グラスというものです。これは私の会社ではなくて、酒造組合中央会という酒造組合の日本全体の組合が作った酒器です。これは柳宗理先生にお願いをしたものです。

私の父が業界の担当委員長だったんで父から聞いた話ですが、冷酒が増えている方向にあったときに、お燗も冷酒も飲めて、それから乾杯もできるし、ステムもあるように見える。そういう和洋折衷的な「日本酒のグラスを作ってください」と、柳先生のところへお願いしてこれができてきた。
当時、業界にはそんなにお金もないので、「一発でデザイン料が払えませんので、売れたら1個当たり何銭」という「ロイヤリティー契約をしてくれ」と言って。
当時非常に珍しかったらしいです。デザイン料を1個当たりのロイヤリティーで払ったっていうのは。でも柳先生のところはそれを受け入れてくださいました。
一升瓶よりは短いですが、歴史は長い。30年はあると思いますね。ひと型で1,500万個だったかな。なんせ食器のロットとしては「なぜこれをギネスに登録しないのか」と私が思ったぐらいのロングベストセラーです。
でも、10年くらい前にロイヤリティーを「もういらん」って言われてやめました(笑)。だから述べ払ったお金は、けっこうたくさん(笑)。そんなことで2つご紹介をいたしました。ちょっと長くなりまして。
川口:いえいえ、ありがとうございます。

関連タグ:

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.18
20名の会社でGoogleの採用を真似するのはもったいない 人手不足の時代における「脱能力主義」のヒント

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.14
よってたかってハイリスクのビジネスモデルに仕立て上げるステークホルダー 「社会的理由」が求められる時代の起業戦略

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.18
20名の会社でGoogleの採用を真似するのはもったいない 人手不足の時代における「脱能力主義」のヒント

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.14
よってたかってハイリスクのビジネスモデルに仕立て上げるステークホルダー 「社会的理由」が求められる時代の起業戦略