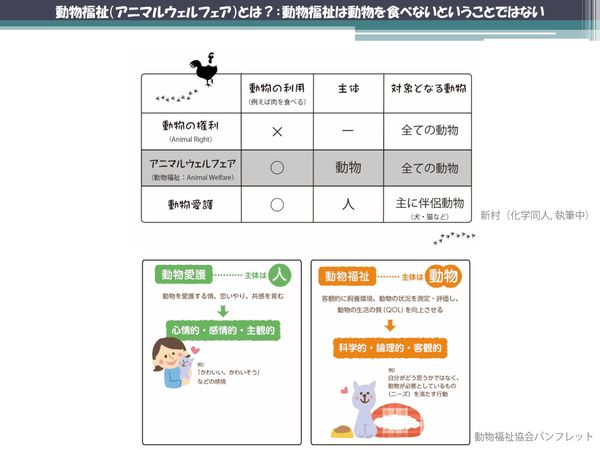 PR
PR2024.10.10
将来は卵1パックの価格が2倍に? 多くの日本人が知らない世界の新潮流、「動物福祉」とは
リンクをコピー
記事をブックマーク
石山友美氏(以下、石山):こんにちは。石山友美と申します。

『だれも知らない建築のはなし』という映画を監督しました。
この映画は、2年前に渋谷のシアター・イメージフォーラムという映画館で公開していたんですけれども、同じくらいのときに、大分の映画祭でもこの映画を上映したことがありまして。
ゆふいん文化・記録映画祭という映画祭で、私はその映画祭にうかがうことはできなかったんですけれども。ちょうど坂さんが、大分県立美術館のお仕事をなさって、オープンぐらいのときだったんですかね? ご縁があって坂さんに、その映画祭で映画を観ていただいたという経緯がありました。
これが公開時の映画のポスターなんですけれども、建築家や建築関係者にインタビューして、それをまとめた映画です。この映画のDVDが発売されるにあたって、こちらの書店でなにかイベントをしたいということになりました。
それで、坂さんがこの映画に登場するさまざまな方と交流があることはおうかがいしておりましたので、私のほうから、ぜひ坂さんにトークをお願いしたいとお頼みして、快く引き受けてくださったんです。今日はよろしくお願いします。
ちなみに、この映画をご覧になってくださった方はいらっしゃいますか?
(会場挙手)
石山:あ、どうもありがとうございます(笑)。でももちろん、映画をご覧になってない方もいらっしゃると思うので、まず少し、私のほうから映画の説明をさせていただいて、そのあと、この映画にまつわる話を坂さんとトークさせていただきます。
この映画はもともと、イタリアの「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」という大きな建築の展覧会で、2014年に展示上映されていたものです。その展示の様子が、この写真です。
この年の「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」全体のコミッショナーを務めたのが、映画の登場人物でもある、レム・コールハースです。彼が「近代建築というものがいったい何だったのか」ということを、反省もふまえて、テーマとして取り上げたいということで。そのテーマのもとに、世界中からの参加国がそれぞれリサーチプロジェクトを立ち上げ、最終的な成果を展示するというものでした。
そのとき日本のチームは、70年代の建築を主に取り上げたんですね。70年代にあらわれてきた「日本の近代の挫折」のようなものを、建築家たちがどうやって克服していこうとしたのか、その試みを展示したいということで、そのようになりました。
それで、「展示の補足的に、映像をつくってくれないか」と言われて、私が映像をつくることになったんです。はじめから、建築家にインタビューをするということは決まっていました。登場人物はほぼ最初から決まっていた状態で、私のところに話がきたわけです。
実ははじめは、「10分程度にまとめてくれ」と言われていたんです。けれども、実際にインタビューに行ってみると、1人2時間も3時間も貴重なお話をしてくださった。10分にまとめてしまうのはもったいないということで、私のほうで、だいたい1時間ぐらいのものをつくったわけですね。
(スライドを指して)撮影の様子です。左側にいるのが、チャールズ・ジェンクスさんという建築理論家で、右下が安藤忠雄さんです。

それで、イタリアで展示上映を半年間くらいしていたんですけれども、そのあと、縁があって「日本の映画館で公開しないか」というお話をいただきまして、劇場公開することになりました。
建築の専門的なところまで踏み込んでいたものだったので、「一般の方が来てくれるのかな?」という不安もあったんですけれども。ふたを開けてみると、けっこう来てくださったんですね。
これが公開時の様子です。

満員になった日もあって自分が思っていたよりも反響は大きかったです。というのは、ちょうど、新国立競技場の問題が世間を騒がせていたときだったので。そういった社会的な関心と、この映画の公開のタイミングが重なって、「建築家っていうのは何を考えているんだろう?」ということを探りに、観客の方が来てくださったという感覚がしております。
映画の原題は『Inside Architecture-A Challenge to Japanese Society』というタイトルをつけていました。これを日本語でどういったタイトルにしようかと、配給の方やいろんな方が考えてくださって、『だれも知らない建築のはなし』というタイトルになりました。
先ほど、もともと「10分間ぐらいの映像をつくってほしい」と言われていたのに、60分ぐらいになってしまったという話をしたんですけれども。なぜ10分間なのかというと、展示を立って見てくださっているお客様に対して、60分はあまりにも長いと。
それで苦肉の策で、チャプターごとに分けて、1個のチャプターを見ただけでも立ち去れるようにしました。1個のチャプターがだいたい10分から15分くらいと言い訳をして、最終的なものにつくりあげていったんです。
4つの章立てをしまして、第1章では70年代の話を建築家の方にうかがっています。それに続いて、第2章では日本のポストモダン建築。70年代を発端として、80年代、消費社会がだんだん進行していくときに、建築家たちが何を考え、どんな建築が生まれていたのか、ということをフューチャーしました。
第3章では、消費社会のピークといいますか、バブル景気が日本全体を覆っていたとき。そのとき、主に、磯崎新さんが日本の熊本や富山など、いろんな場所でやっていたコミッショナープロジェクトに焦点を当てて描きました。最後、第4章は、バブルがはじけたあとから、現代にいたるまでの流れをインタビューしました。
これは第1章、70年代です。70年代の一番大きな建築界の出来事として、2度のオイルショックがあって非常に不景気だった。それで、今と同じように若い建築家の方たちに全然仕事がなかった、という時代でした。そのときに、若い建築家たちが、住宅の設計を非常に積極的にはじめて、そこで彼らは作家性を爆発させるような、本当にすばらしい住宅を生み出していくんです。
それは前の時代とだいぶ変わっていた。その前の時代では、建築家というのは大きな公共建築を手がけるイメージなんですけれども、この時代から、住宅が建築家の作家性があらわれるものとして非常に多く出始めました。このスライドは、伊東豊雄さんの「中野本町の家」という住宅で、たいへん素晴らしい建築です。
同じように、何個かの住宅を取り上げました。これは毛綱毅曠(もづなきこう)さんという建築家の、お母様のお家です。こういった優れた小住宅がたくさん出てきたときに、世界中から注目をされるようになってきます。
そのときに、映画の出演者でもある磯崎新さんが中心となって、日本の小住宅をやっている若手の建築家を、積極的に世界で紹介していきます。磯崎さんは当時から、独自の海外との関係、人脈がすごくたくさんおありになったので。
そんななか、80年代の初頭にあった「P3会議」という、当時のスター建築家たちが集まる建築家会議に、まだ無名だった伊東豊雄さんと安藤忠雄さんを磯崎さんが連れて行ったというエピソードがありました。そこで彼らは、ある種の挫折感のようなものを味わうことになるんですけれども。そういったことも、映画のなかで紹介しています。
これは、その「P3会議」の様子です。右側にいるのが、レム・コールハースさんで、彼にもインタビューをしに行っています。真ん中にいるのはハンス・ホラインさんなんですけれども、この方にはインタビューしていません。左側がピーター・アイゼンマンさんで、彼にもインタビューしに行きました。これは、安藤さんと伊東さんです。
本当にそうそうたる面々が集まっています。私も「P3会議」の記録の本を読んでみて、本当に熱い議論を交わされていて、すごくおもしろいものだったんですけれども。やはり、伊東さんと安藤さんは、発言自体もすごく少ないし、肩身の狭い思いをしたんじゃないかというのがひしひしと伝わります。
伊東さんは、映画の中でもこのことを語っているんですけれども、すごく挫折感もあったというお話をしています。やはり、欧米中心の建築業界のスターたちのなかで、日本人としてそこにいるということが、たいへんにプレッシャーだったのではないでしょうか。
こういった国際的な会議のほかに、70年代の大きなことと言えば、日本において「a+u」や「GA」という建築の専門誌が出始めたことです。そして、これらの雑誌が世界的にも非常に大きな影響を与えていくことになります。これらの雑誌に引っ張られるようなかたちで、日本の建築家が世界に紹介される、という流れがあったのではないかと思います。
そういう流れで、第2章の日本のポストモダン建築につながっていきます。映画の登場人物でもあるイギリス人のチャールズ・ジェンクスさんがまとめた、『POST-MODERN ARCHITECTURE』という、大ベストセラーになった本があります。

このなかで、第1章で描いていた日本の小住宅などを手がけた多くの日本人建築家が取り上げられました。この表紙の写真は、建築家の竹山実さんの「二番館」という、新宿にある建築です。これが「二番館」の今ある姿です。

これらのほかに、ポストモダン建築として非常に有名な、磯崎新さんの「つくばセンタービル」。

こういったものを紹介しています。
これは、秋田市にある「秋田市立体育館」で、渡辺豊和さんという建築家がデザインしています。

これは「ヤマトインターナショナル」で、原広司さんによる建築です。

これは隈研吾さんです。

高松伸さん。

長谷川逸子さん。

このように、日本人のポストモダン建築も紹介されているのですが、やはりバブル景気と相まって、そのころピークを迎え、本当に多くのポストモダン建築が生み出されてきました。それと同時に、バブル景気が外国人の建築家をたくさん呼び込んだという事実があります。
これは、イタリア人のアルド・ロッシさんの建築で、福岡にある「ホテル・イル・パラッツォ」です。

これは、フランク・オーウェン・ゲーリーさんの「フィッシュ・ダンス」というオブジェで、神戸にあります。

これはみなさんご存知だと思いますが、スタルクさんによる、浅草にあるアサヒビールの建物です。

これは、マイケル・グレイヴスさんというアメリカ人の建築家が建てた、福岡にある高層マンション。

これもやはり、バブル景気のころに建てられたものです。これは、ダニエル・リベスキンドさんという建築家が富山県にある公園のなかに建てた、オブジェです。

今では非常に有名な建築家ですけれども、当時はほとんど無名に近かった彼を、磯崎新さんが呼んで、日本のバブル期にこのような建築をつくらせていました。
これは、ザハ・ハディッドさんによるフォリーです。大阪の花博が90年にあったときの、仮設のオブジェのようなもので、現存はしていません。

これも、同じ博覧会のときのコープ・ヒンメルブラウという建築設計事務所のもの。

関連タグ:
1970年代、建築家には仕事がなかった––住宅建築をきっかけに才能を羽ばたかせた、日本人たちの記録
「シュガーベア」とバカにされて… 時代の変化とともに振り返る、建築家・坂 茂の新人時代
日本人のプレゼン能力は劣っている? 建築家・坂 茂氏が説く、世界で戦うために必要なこと
「その建物が仮設かどうかは、人からの愛で決まる」“紙の筒”で建てた教会が、街のシンボルになるまで
コンテナで作った仮設住宅から紙の教会まで 建築家・坂茂氏が問う、被災地支援のあり方
新国立競技場の再コンペは「出来レースだった」 建築家・坂茂氏が指摘する、日本の建設業界の問題点
日本の木造建築は遅れている? 坂茂が語る、建築業界の意外な事実

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.18
20名の会社でGoogleの採用を真似するのはもったいない 人手不足の時代における「脱能力主義」のヒント

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.14
よってたかってハイリスクのビジネスモデルに仕立て上げるステークホルダー 「社会的理由」が求められる時代の起業戦略

2024.11.13
週3日働いて年収2,000万稼ぐ元印刷屋のおじさん 好きなことだけして楽に稼ぐ3つのパターン

2024.11.11
自分の「本質的な才能」が見つかる一番簡単な質問 他者から「すごい」と思われても意外と気づかないのが才能

2024.11.13
“退職者が出た時の会社の対応”を従業員は見ている 離職防止策の前に見つめ直したい、部下との向き合い方

2024.11.12
自分の人生にプラスに働く「イライラ」は才能 自分の強みや才能につながる“良いイライラ”を見分けるポイント

2023.03.21
民間宇宙開発で高まる「飛行機とロケットの衝突」の危機...どうやって回避する?

2024.11.11
気づいたら借金、倒産して身ぐるみを剥がされる経営者 起業に「立派な動機」を求められる恐ろしさ

2024.11.11
「退職代行」を使われた管理職の本音と葛藤 メディアで話題、利用者が右肩上がり…企業が置かれている現状とは

2024.11.18
20名の会社でGoogleの採用を真似するのはもったいない 人手不足の時代における「脱能力主義」のヒント

2024.11.12
先週まで元気だったのに、突然辞める「びっくり退職」 退職代行サービスの影響も?上司と部下の“すれ違い”が起きる原因

2024.11.14
よってたかってハイリスクのビジネスモデルに仕立て上げるステークホルダー 「社会的理由」が求められる時代の起業戦略