 PR
PR2026.01.19
業務フローを変えずに、メール1通3分を削減 自動でAIにナレッジが貯まる問い合わせシステム「楽楽自動応対」
コピーリンクをコピー
ブックマーク記事をブックマーク
漆原茂氏(以下、漆原):だいぶ前になると思うのですが、みなさん修了生なので、あらためてちょっと振り返ってもらって。今と同じテーマをやっている方、違うテーマをやっている方がいると思いますが、未踏時代にどんな思い出があって、どうだったかを話してもらえればと思います。安野さんからいかがですかね?
安野貴博氏(以下、安野):はい。私が未踏をやっていたのが10年前ぐらいですかね?
漆原:10年前!?
安野:2015年度の未踏本体みたいな。
漆原:その時は小説は書いていなかったですよね?
安野:その時は書いていなかったですね。その時にやっていたのは、ユーザーの、Windowsの操作履歴みたいなものを取った上で、ユーザーが次にどのボタンをクリックするのかを予想するようなことをやっていました。
漆原:なるほど。
安野:デモの時にはパワポを作るデモをして、「パワポ上で何か線を引いて、次にテキストを入れて」みたいなことを覚えさせてあるので、ある程度自動でツールバーにある「次にこれが必要だよね」みたいなものがポンポンと表示されて、そこをクリックして、それで作ったスライドでそのまま発表するようなことをやっていました。ですが、10年経って、AIエージェントとかでけっこう似たようなことが……。
漆原:そうですよね。かなり先取りした感じはありますね。
安野:よりできるようになってきて、うれしいなと思っています。

漆原:そこから今の執筆活動にはだいぶ距離があるようにも感じるんですが(笑)。
安野:そうですね。まぁ、距離はありますね(笑)。
漆原:なるほど。AI屋さんもやっていたりしますよね。
安野:そうですね。小説家になる前にはAIスタートアップを何社か。
漆原:起業されていますもんね。
安野:そうですね。でもすごく大きく言うと、基本的に共通したことをやっていると思っていて。技術が進歩していく中で「将来的にこれはできるようになりそうだぞ。そうするとこういううれしさがありそうだぞ」みたいなことを考えた上で、それを何らかのかたちでアウトプットをしているという意味では同じかなと思います。なので、そういう意味での共通性はあるかなと思っています。
漆原:なるほど。結局は未来社会に向かって技術もやるし、執筆活動もしているという、そんなかたちですかね?
安野:そうですね。小説は会社登記をしなくてもプロダクトが出せる、自動運転とかについて書けるというところで、すごくコスパのいいアウトプットだと思います。
漆原:ただ、ソフトウェアを書ける人は文章が苦手というイメージがすごくあるんですが。
安野:いや、僕も苦手ですね。
漆原:苦手なんですか(笑)!?
安野:文章がぜんぜんうまくならないので、すごく難しいです。
漆原:そうですか。
安野:ソフトウェアと真逆ですね。ソフトウェアは疎結合、密凝集でやる設計が良いとされているのですが、小説だとぜんぜん逆で、密結合にすべての文章が絡まり合ってスパゲッティになっているほうが美しい文章だったりするので、頭の使い方は実は真逆だなと思いながらやっています。
漆原:なるほど。難しい。きれいにし過ぎちゃいけないみたいな。リファクタリングするとダメみたいな。
安野:そうなんですよね。モジュールになっていて交換可能になっている文章は良くないみたいな、そんな感じです。
漆原:でもそういう二刀流人材は非常に稀有なので、おもしろいと思いますね。
安野:両方できるようになりたいなと思いながらやっている感じです。
漆原:じゃあ、未来を見据えているところは未踏時代から変わっていないという理解でいいですね?
安野:そうですね。
漆原:ありがとうございます。

漆原:では続いて中村さん、いかがですか? ぜひイグ・ノーベルのお話もお願いします。
中村裕美氏(以下、中村):はい(笑)。私は2010年の未踏で当時あったユースで採択してもらって、その頃からずっと電気を食べ続けて。
漆原:「電気を食べる」? 知らない方もいると思うんですが。どうやったら電気を食べられるのかをぜひ。
中村:そうですね。いろいろな食べ方があるのですが、舌に電気刺激が来たら、何らかの味が感じられるんですね。私自身は食器の形にして、食器、食べ物、舌となるように回路を設計して、食べた時に味が変わるような食器を未踏の頃に作っていました。
当時は面接の際にもプロトタイプを持ち込んで、PMの方々に「これを飲んでください!」ってやりに行きました(笑)。
漆原:スプーンで電気刺激を変えて味覚を変えるというやつですよね。
中村:私が作っていたのはフォークのほうです。
漆原:フォークのほうなんですね。
中村:今は共著者の先生のほうで社会応用されていますね。
漆原:しょっぱくなったり、いろいろと味が変わるんですよね。
中村:はい。味を濃くしたり薄くしたりできて、塩分を足さずにしょっぱさだけを得られるというところだと、いろいろな方の健康に役立てられるんじゃないかなと思っています。
漆原:なるほど。この未踏というプロジェクトを使って、持っている自身のアイデアをプロトタイプからしっかり仕上げて、その先に続けたという感じなんですかね。
中村:そうですね。未踏に出した頃は本当にその研究を始めたばかりで、そこで深めると同時に幅を広げることを未踏の期間でさせてもらえたなと思っていますね。
漆原:なるほど。要は「やりたいことがあったらやってみろよ」というかたちで。「やりたいのよ!」と持ち込んだらPMの人たちが「どうぞ!」(となった)というかたちですかね?
中村:そうですね(笑)。それを受け入れてくれる懐の深い方々ばかりなので。漆原:なるほど。わかりました。ありがとうございます。
稲見昌彦氏(以下、稲見):純粋なソフトウェアじゃないのもおもしろいですよね? どうしても「未踏」というとプログラミングだけというイメージがありがちなんですが、まさにこの「食」というある意味めちゃくちゃハードな業界のところに、ソフトウェア的な観点でうまくハックしたところがすごくユニークだなと、私も傍から見て思いましたね。
漆原:そうですね。ソフトウェアエンジニア以外にも、ハードウェアもあればおもしろくビジネスインキュベーション(できる)ようなものもあるので、どんどん幅が広がっているイメージはありますね。

漆原:登さんは未踏時代を振り返っていかがですか? もうだいぶ前ですよね? 10年、20年?
登大遊氏(以下、登):20年前の2003年ですね。
漆原:20年前。
登:大学に入学して、1年生の時に未踏に応募しました。
漆原:1年生で!? すごい。
登:はい。そこに座っていらっしゃる竹内先生(竹内郁雄氏)がPMでした。
漆原:すごいですね。直々に。
登:そうです。当時の未踏ユースは300万円の予算で、自分は大変ありがたいことに、200万円ぐらい使わせてもらいました。こういうシステムやネットワークの開発をするには、ハードウェアと言いますか、LANを自分で構築したりインターネットに直接つながったりする変な環境が必要です。
普通の家にはそんなものはありません。お金もかかります。サーバーも4台ぐらい買わないといけません。全部未踏の予算を使わせていただいて、自宅のアパートの部屋にラックを立てて、データセンターみたいな感じものを作りました。(それでやっていたこととしては)ソフトウェアをがんばって半年ぐらい書いたという、そういうふうな感じでやっていました。
漆原:なるほどね。それは1人のプロジェクトだったのですが。
登:未踏では1人のプロジェクトですけど、そのソフトは公開前に大学の仲間にたくさん使ってもらったんですよ。
漆原:SoftEtherを?
登:SoftEtherですね。もっと言えば、いきなり未踏で出したわけじゃなくて、大学の中の強権的な管理者、学術情報センターが、ファイアウォールでフィルタリングをするんです。
学生の同意なく、勝手にパケットのポリシーを決めるんですね。それをうまいことトンネリングという技術で全部通信できるようにしてしまおうということで。大学の連中はみんなそれが欲しかったので、自分が未踏で作ったという感じであります。
漆原:なるほどね。そこからずっと、脈々と20年間、ひたすらそういう開発に没頭されて、特にコロナ禍ではものすごく大活躍されたわけですよね。
登:コロナ禍はそうですね。20年前がSoftEtherの最初のバージョンで、10年ぐらい前にそれを使った検閲回避システムを作って、外国のファイアウォールをやっつける。コロナ禍は2020年がテレワーク、2021年が行政向けのテレワークで、それ全部SoftEtherの未踏で作ったやつをベースに作っています。
漆原:なるほど。何かのブロックをとにかく回避したい人ですかね(笑)。
登:ブロックというか、例えば子どもや勉強したい人で、通信が規制されていると「Wikipedia」やニュースサイトも見れないという方々がたくさんいます。
漆原:そうですね。
登:通信の自由、表現の自由がある日本でそういうソフトウェアを作り、世界中の若い方々が勉強できる機会があり、それを使っていろいろなホームページなどを見られたら非常に良いことだと思っています。
漆原:おっしゃるとおりですね。

漆原:ちなみに、採択された時に、PMや他の未踏の方を見てて、どう感じましたか?
登:みなさんすごくレベルが高いので、「自分はこれは付いていけない」と思ってですね。
漆原:登さんがそう思う!?
登:会議の時でも「すごいなぁ」と思いましたね。ブースト会議というものがあって、2日間合宿をやりました。PMに混じってOBみたいな人も聞きに来るんですけど、すごい。オペレーティングシステムを全部わかっている方とかが出てきましたね。
漆原:コアエンジニアみたいな人たちがやってくる。
登:「自分は勉強しないといけないな」という気分になりまして。有益な機会でございました。
漆原:なるほど。やはり先輩やPMの方々が寄ってたかってかわいがるというのは本当なんですね。
登:はい。そのとおりです。
漆原:ありがとうございます。
漆原:稲見先生はいかがですか? 未踏のPMもされていて、過去も何件も採択されていると思うんですけど。
稲見:いや、まずね。みなさんが羨ましくて。実は私もすごく未踏に出したかったんですよ。ちょうど2003年に、竹内先生もいらっしゃった電気通信大学に新米の講師として行った時に、まさに未踏の事務局の方が「説明会をしたいので、ぜひ協力してください」と言ってきたんですよ。「いや、私が出したい!」と言ったら、「稲見先生、未踏は発掘事業であって、発掘された人はダメです」と。
(一同笑)
そう言われてしまって(笑)。「えー!! 出せない!?」と思いました。でもそれは確かに大切で、大学教員という立場になっているならば、むしろ未来に活躍する人たちをどういうふうに支援していくかに自分は回ったほうがいいなということで。そういう意味では今はPMを楽しくやっています。
印象深いプロジェクトとしてはこういうものがあります。これは菅野さん(菅野龍太氏)という「未踏クリエータ」の方のものですが、その人はもともと少年時代からずっと野球をやっていました。アマチュア野球はだいぶ審判の誤審が多いらしいのですが、それがあまりにも悔しくて、その球審の選球眼をVRでトレーニングするシステムを作っていたんですよね。
なぜこれがおもしろいかというと、たぶんサッカーとかの判定と同じで、「だったら野球はもう全部3Dで計測してしまって、審判をなくしてもいいんじゃないか」という議論にもなったんですよね。
それでいろいろと調べてみると、どうやらキャッチャーがボールをキャッチした時に、ちょっとミットを動かすんです。フレーミングというテクニックで、それによって(ストライクゾーンを外れている)ボールの球を(体の動きなどを工夫することで)ストライクゾーンに入れて、しかもそれが周りの人もそういうふうに感じるというテクニックがあって。それも含めてトレーニングするには3Dで解析しただけじゃダメだと。つまり、(野球のプレイヤーにとっても、審判にとっても、観客にとっても)ボールの軌跡は物理量ではなくて、どうやら心理量だったとわかったのです。
人の心理をうまくハックするところをやっていくというのは、私のスポーツの見方さえも変わるような。ソフトでもあるんだけれども、新しい視点のプロジェクトで非常に興味深かったなというのはありましたね。
漆原:なるほどね。新しい視点でも、若い方々が素直に思っている未来や今までないものに関して、未踏は最適な場所なんじゃないかなという感じですかね。
稲見:本当におもしろいプロジェクトは、世の中の見え方が変わりますね。
漆原:僕も未踏のアドバンストのPMをしていますが、むしろこっちのほうが勉強になるぐらい、なかなかエモい、おもしろいネタがたくさん来ますからね。これからも期待したいと思います。

(次回につづく)
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。
すでに会員の方はこちらからログイン
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!
スマホで読み込んで
ログインまたは登録作業をスキップ

安野貴博
エンジニア/小説家
プレゼンター
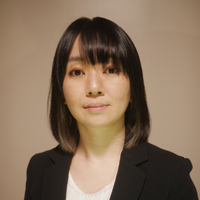
中村裕美
東京大学大学院情報学環 特任准教授(現:東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科 准教授)
プレゼンター

登大遊
ソフトイーサ株式会社 代表取締役/独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)産業サイバーセキュリティセンター サイバー技術研究室 室長/NTT東日本 特殊局員
プレゼンター

稲見昌彦
東京大学 総長特任補佐 先端科学技術研究センター 副所長・教授/未踏IT人材発掘・育成事業プロジェクトマネージャー
プレゼンター

漆原茂
ウルシステムズ株式会社 代表取締役会長/ULSグループ株式会社 代表取締役社長/株式会社アークウェイ 代表取締役社長/未踏アドバンスト事業プロジェクトマネージャー
プレゼンター
この記事をブックマークすると、同じログの新着記事をマイページでお知らせします