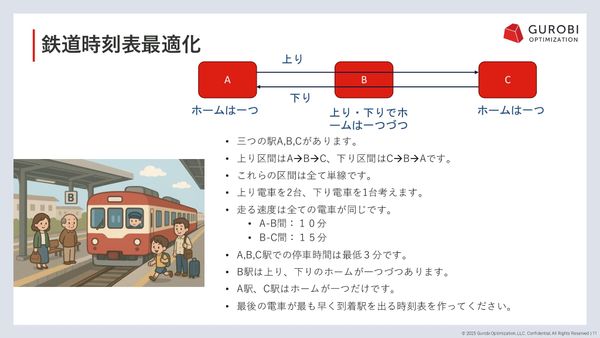 PR
PR2025.12.24
鉄道ダイヤの最適化に学ぶ、生成AI活用 複雑なビジネス課題をチャットボットで前に進めるポイント
コピーリンクをコピー
ブックマーク記事をブックマーク
曽根原春樹氏(以下、曽根原):じゃあこのプロダクトビジョンですが、正しくプロダクトビジョンを作るためにはどんなポイントがあるかを本書では説明しています。
インパクトあるプロダクトビジョンを作るために必要な要素はなにかというと、全部で5個あります。
まずはwhoです。どのユーザーの世界を変えたいのかということです。先ほど総花的なプロダクトという話から戦略肥大の話をしましたが、ラディカさんが説明されていたように、たくさんのペルソナをサポートするプロダクトの話がありました。
やはり「誰に向けて作ったものなのか」がユーザーさんに伝わらないと、ユーザーさんも「これ、自分のためなの?」という感じで疑問に思っちゃうんですよね。なので、我々がしっかり「どのユーザーさんの世界を変えたいのか」に関してクリアに見ておく必要があります。
2つ目はwhatです。現在そのユーザーの世界はどのように見えるのか、そしてどんな制約があるのかです。これはユーザーの視点でもかまいません。もしくはユーザーの世界を外から見た視点でもかまいません。我々の目から見て、「このユーザーさんって、なぜこんな制約がある中で、タスクなりをこなさなきゃいけないんだ」という、そういった疑問です。
もしくは、例えばBtoBのプロダクトもそうですが、1つのビジネスプロセスでずーっと仕事を続けていると、制約があったとしてもそれが当たり前過ぎちゃって、問題に感じなかったりするんですね。むしろそれが生産性を大きく阻害したりするわけです。
なので、現状みなさんのプロダクトが存在する前に、ユーザーの世界が今どのように見えるのかと。なにが当たり前になっていて、「でもその当たり前って、我々から見た時にすごくおかしいよね」という部分です。こういった部分で、例えばどんな制約があるのかとかをぜひ導き出してほしいなって思います。
3点目はwhyです。なぜそのユーザーの世界を変革する必要があるのかということです。ターゲットユーザーさん、もしくはターゲットユーザーさんが存在する世界が、どんなにおかしく見えたとしても、そのユーザーさんの世界を変えなきゃいけない理由が強くないと、そのプロダクトとしてのインパクトはどうしても弱くなってしまうわけです。
これはプロダクトを手にするユーザーさんの立場になって考えると、特に重要になってきます。「なぜ僕はこのプロダクト、私はこのプロダクトを使わなきゃいけないんだ」と。こういった疑問を持たれてしまうと、プロダクトを使い続けてもらうためのその次の1歩がもう出てきません。
だからこそこのwhyです。なぜそのユーザーの世界を変革する必要があるのか。これはその問題を解決しないと、例えばその企業の生産性がまったく上がらないとか、自分の生活が不便なままとか、いろいろな問題があるとは思いますが、いわゆるこのpainにつながる部分ですよね。ぜひwhyについても深掘りしてもらえるといいかなと思います。
4点目、whenです。その世界に辿り着いたことをどんな時に知ることができるかという話です。最近僕は「現代プロダクトというのは、アウトカム・オーバー・アウトプットで作られているんですよ」という話をしています。
つまり、そのプロダクトをとおして、ユーザーさんの行動がどれだけ変わったのかという話です。プロダクトが存在する前と存在した後でなにが変わってくるかといえば、ユーザーさんの行動なんですよ。
そのプロダクトを使うことによってユーザーさんの行動が変わるから、そのユーザーさんの抱えている問題や今まで感じていなかった問題がすごくpainに感じてベネフィットを得ようとするのか、とか。面倒くさいプロセスを例えばクリック1発で解決できるようになるとか、そういう話ですよね。
ユーザーさんが行動を変えてくれたということを、どうやって・いつ知ることができますかという話です。これはある種、プロダクトを使っている状況を、どうやってデータとして収集するのかということにつながってきます。もしくはKPIとか、ノーススターメトリックの話にもつながってきますよね。
最後、howです。どのようにその変革を起こしていくのか。これはインパクトあるプロダクトビジョンを作る時に気をつけてほしいことですが、who、what、why、whenを見た上で必ずhowに進んでください。いきなりhowからやるのはやめてください。
いきなりhowからやってしまうと、先ほどのプロダクト病に引っかかっちゃいます。なので、4点がそろった上で、じゃあその変革をどうやって起こしていこうかという議論がようやくできるようになるわけです。
ここで初めて「これはやはりブロックチェーンを使ったほうがいい」という話になるのか、「いや、AIを使ったほうがいい」という話になるのか。もしくはDXというイニシアチブのもとに、いろいろな人を巻き込んでやったほうがいいという話になるのかという議論につながっていくんです。
ということで、インパクトあるプロダクトビジョンを作るために、この5点をぜひみなさんの中で議論してほしいと思います。
「みなさんの中で」と言っている意味は、別にプロダクトマネージャーだけで議論する必要はないんですよ。例えば営業のみなさん、カスタマーサクセスの人、マーケティングの人も含め(て話す)。プロダクトにいろいろなかたちで関わる人がいますが、そういった人たちとぜひ1回議論をしてみてください。
なぜここを強調しているかというと、プロダクト作りってプロダクトマネージャーだけじゃなくて、さっき言ったとおり、いろいろな人が関わっています。「このビジョンを作るのに自分は貢献しているぞ」という気持ちがあるのとないのとでは、でき上がったビジョンに対するコミットメントのレベルがまったく違うんです。
僕のおすすめは、この議論をぜひいろいろなステークホルダーとやってください。最終的に決めるのはプロダクトマネージャーだとしても、議論そのものは広くやったほうが僕はいいと思っています。

こうした変革に関わるプロダクトビジョンですが、本書では具体的な例を使ってビジョンの作り方や活かし方についていろいろ説明しています。
プロダクトビジョンというものは、当然作って終わりではありません。作った後にもたくさんのやらなきゃいけないことがあります。大きく分けてこの5つ、プロダクトビジョンを作ることを抜かせば4つですね。
ビジョンができたら次になにをするかといったら、戦略です。ビジョンで我々が辿り着きたい世界観を定義します。定義をしたら、じゃあそこに辿り着くためになにをしてなにをしないかということ決めなきゃいけない。いわゆる完全にリソース配分の話です。
これはいわゆるプロダクト戦略ですよね。戦略があったとしても、実行する時に全部やろうとすると、例によって総花的になったり全部が中途半端になってしまったりするわけなので、ここで大事なのが優先度です。なにを優先的に行うかという話です。
この優先度が決まったら次になにをするかというと、実行と計測ですよね。実際にそのプロダクトを作るなり、ユーザーインタビューをするなりして、本当に我々の仮説が正しいのかを検証していかなきゃいけないわけです。
大事なのは検証して終わりではなくて、そこで得られた知見をどうやって次のアクションに回していくかという、フィードバックループです。ここが実行と計測ではすごく重要になってきます。
(スライドを示して)最後に「文化」と書いてあります。このプロダクトのビジョンから戦略、優先度決め、実行と計測というこの流れは、別にプロダクトマネージャー組織だけで実行する話でもないんです。本当のプロダクト思考組織を目指すのであれば、全社的にぜひ理解していただきたいプロセスです。
どんな組織文化をアクティビティとして埋め込むべきかも議論されるのが一番いいなと思っていて、この本には文化に落とす時のトラップとか(を)、いろいろな事例を含めながら説明しています。
それぞれの要素はありますが、ただプロダクトチームで実行するだけではなくて、それぞれの要素をぜひチームとか社内全体に伝えていってください。
プロダクトマネージャーの1つの重要な仕事はコミュニケーションなわけで、こういった良いプロダクトを作るための考え方というのは、自分のところだけで留めてはだめです。ちゃんと広めていきましょう。こうした考え方を伝えることで浸透していきます。
(ダット氏 話す)
曽根原:今ラディカさんがお話されていたことは非常に重要で、ビジョンと聞くと、中にはトップダウンで降ってくるものだと考えられている方がいます。でもこれからのプロダクトということで考えると、実はこれでは時代遅れです。
今ラディカさんがお話されていた中に、「インターナライズ」という言葉が出てきました。インターナライズというのは、そのビジョンを作る時に自分が、自分というのは別にプロダクトマネージャーだけではなく、マーケティングのチーム、他のチームを含めて関わっていくことによって、そのビジョンが自分の仕事の中に内面化していく、血肉化していくということです。これがビジョンの本当の力だということになります。
(ダット氏 話す)
曽根原:(ラディカさんが)今お話されていたのは、よくビジョンを考える時に、「短くあるべし」みたいなことを書いている本があったりします。「それを覚えなさい」みたいな話があります。
別にそれ自体は悪いことではありませんが、実はそれ以上に大事なのは、先ほど言ったwho、what、why、when、howという話がありましたね。
こうしたそれぞれの要素を、ビジョンを実行する人たちが個人のそれぞれの立場で理解することによって、プロダクトを作るアクションもそうだし、プロダクトを広めるマーケティングアクションもそうだし、プロダクトをサポートするサポートアクション、それから売る立場のセールスのポジションも、ビジョンに向かって1つのアクティビティが同じ方向に向くわけです。
これが少し前のスライドで説明した、矢印の中にそれぞれのイニシアチブがそろっている状態です。みんなが同じ方向を向いて、勢いを増していくという。まさにこの理想的な状況を作るという話です。
だからこそ巷で言っている、例えばトップダウンとか、「短くてパンチ力があるビジョンを作りましょう」みたいな話がありますが、実はプロダクトビジョンの肝は単純にそういうところじゃなくて、先ほどお見せしたビジョンに必要な5つの要素を全員でしっかり議論して、それぞれの立場でビジョンを噛み砕く部分が肝になっています。
(ダット氏 話す)
曽根原:今ラディカさんがお話されていましたが、最近、経産省が出したレポート、日本のこれからの労働力について警鐘を鳴らしたものがありました。そのレポートで、日本人の企業に対するやる気のなさみたいなことが話題になりました。今ラディカさんがお話されていたのは、まさにそこなんですね。
つまり我々は、仕事をする時になにか意味を感じたいわけなんです。例えばプロダクトを作るのでもいいし、サービスを実行するのでもいいです。それぞれの仕事の中に意味があるから、人は働く時にやる気になるわけです。
やはり強いビジョンとか、目指す方向がはっきりしているとか、自分だけではなくて他の人も同じビジョンを向いている状況がないばかりに、こういった非常に悲しい状況が起きてしまうという現状があるわけです。
だからこそ『ラディカル・プロダクト・シンキング』を通じて、我々がプロダクトをとおしてなにを作りたいのか、どんな世界にしたいのかという部分が組織の中でしっかり統一される状況ができるだけでも、企業の中の環境は大きく変わってくると思います。
恐らく、そのビジョンを作る作業、作業も恐らく時間がかかると思いますが、そういった“議論をとおす”というアクティビティをとおすことで、各事業部、各立場の人が、例えばビジネスに対して、プロダクトに対して、ユーザーさんに対してどんなことを考えているのか。
実は自分が知らないほど大きなギャップがあったと思います。いろいろなことに気づくと思います。でもそれはいいんです。それは正しいビジョンを作る過程で起こることです。こうした作業をとおして全員が同じ方向に向くことができたら、これは本当に強い企業の推進力になるということです。

曽根原:ということで今回は、真にインパクトあるプロダクトを作るためのメソッドということで『ラディカル・プロダクト・シンキング』をご紹介しました。例えばスタートアップであろうと大企業であろうと、各組織に、すぐ使っていただけるようなステップごとの実践的なアプローチを紹介しています。なので、今回のプレゼンテーションを聞いて興味を持ったという方は、ぜひ手に取っていただければなと思います。
「もうすでに読んだよ」という方がいたら本当にありがたい話ですが、今日の話を聞いて「もう1度ちょっとあそこを読んでおこう」みたいに活用していただく、もしくは他のチームのメンバーに読んでもらえるようなことをすると、よりこのビジョンドリブンでプロダクトを作る姿勢が浸透していくのではないかなと思います。
(ダット氏 話す)
曽根原:(ラディカさんによると)よく世界を変えるプロダクトという話をすると、「カリスマのCEOがいないといけないんじゃないか」「いわゆるスティーブ・ジョブズみたいな人がいないと無理なんじゃないか」とみなさんどうしても考えがちです。
しかし実はそんなふうに考える必要はなくて、今回の『ラディカル・プロダクト・シンキング』で書いたメソッドに従って順にビジョンを作っていけば、決して誰か人に依存したかたちでインパクトあるプロダクトを作るということにはなりません。ちゃんとみなさんでもできます。
その先に我々が目指しているものは、ちゃんとプロダクトを通じて世界が良い方向に変わっていくという部分です。こういった部分をぜひみなさんと一緒に実現していきたいということで、(私は)今回日本語に訳すかたちで関わりました。

ということで、プレゼンテーションは以上になります。
(次回に続く)
続きを読むには会員登録
(無料)が必要です。
会員登録していただくと、すべての記事が制限なく閲覧でき、
スピーカーフォローや記事のブックマークなど、便利な機能がご利用いただけます。
すでに会員の方はこちらからログイン
名刺アプリ「Eight」をご利用中の方は
こちらを読み込むだけで、すぐに記事が読めます!
スマホで読み込んで
ログインまたは登録作業をスキップ
この記事をブックマークすると、同じログの新着記事をマイページでお知らせします