『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』の出版を記念して開催された本イベントでは、著者であり編集工学研究所の安藤昭子氏と株式会社コルク代表の佐渡島庸平氏が登壇。本記事では、佐渡島氏が「基本的にゼロイチはない」と語る理由をお伝えします。
作家であっても「ゼロイチ」はない
佐渡島庸平氏(以下、佐渡島):ずっと
松岡(正剛)さんの話をしていたけど、主語と述語のところから本の中身にもつながっていくので、詳しく聞いてもいいですか。安藤さんが持っている編集についての技術は、松岡さんが型化して、それをかなり自分のものにしたから、ここまでわかりやすい文章になっているんだと思うんですよね。
よく作家の人が「ゼロイチを生み出してすばらしい」という言われ方をするんだけれども、僕はあんまりそうは考えていないんです。創作物自体はすばらしいとは思っているんだけれども、基本的に「ゼロイチはない」。
安藤昭子氏(以下、安藤):そうですよね。
佐渡島:作家が過去に読んだものが作家の中で編集されて、物語として紡がれていっている。作家の中から急に生まれることはなく、「世の中のすべての物事は編集されている」と言えてしまう。それくらい編集っていう言葉や概念が、何にでも使えてしまうくらい広いものだと思います。
編集を、本を出す作業として具体的に捉えるのか、思考の仕方として捉えるのかによって、ぜんぜん変わってきてしまうものだと捉えています。作家の人たちは、創作という面において編集しているんです。
それを世の中のどこに置くのか、人と人をどう結び合わせるのか、人とテーマをどう結び合わせるのかとか、作家の人よりも抽象度が高い編集をしていると「編集者」と呼ばれる。できる限りそれを物語とキャラクターに寄せていくと「作家」と呼ばれる。
みんな同じ行為をしているんだけど、抽象度が違うと僕は捉えているんですよね。その中で、さっきの主語と述語のところはすごく重要な考え方だけれども、すっと自分の思考にしていくのは難しいじゃないですか。もう1回そこを話してもらって、広げていきたいなぁと思います。
情報を扱う営みは全部「編集」である
安藤:そうですね。まずみなさんが、編集という言葉にどんなイメージを持っていらっしゃるかをお聞きしてみたいところですけど。普通に考えれば、書籍の編集者とか雑誌の編集者という職業だと捉えられる言葉だと思うんですけれども。
今、佐渡島さんがお話しされたように、少なくとも私たち編集工学研究所はものすごく広い意味で編集という言葉を使っています。今日、冒頭で情報という言葉を出していただいたと思うんですが、「情報を扱う営みは全部編集だ」としているわけなんですね。作家さんであれば、物語を作っていくところも1つの情報を編集していくことです。
情報を編集する行為においては、すべてを主体的にやっていることって、たぶんほとんどないと思うんですよ。例えば、「なんか喉が乾いたな」と思ってペットボトルを持って水を飲もうと思った時、このペットボトルの位置を計算して、手の形を決めてと、私の主体性だけでこれを持っているわけではないですよね。

前に佐渡島さんとも1回お話ししたことがありますけど、「アフォーダンス」という考え方があります。(ペットボトルを指して)こっちの情報の側が相当な意味を持っていて、私に対して「これを持つ時には手の形はこう」ということを、これ(ペットボトル)が誘っているわけです。
こういうふうにして私たちが何かの情報に出会って、それを「自分なりにもっとおもしろくしたいな」とか、「もっと自由に考えたい」と思っている時は、情報の側から相当いろんなものをもらったうえで、編集という営みが起こっているんですよね。
連綿と続いている文脈の中で「新しいもの」が生まれているように見える
安藤:なので、さっきの主語と述語の話にちょっと戻ると、あまりにも主語を大事にして、「ペットボトルとはこういうものである」から始めると、ペットボトルをおもしろくするアイデアが動きにくくなるはずなんですよね。
ペットボトルは、例えば重しにもなるとか、枕にもなるとか。これが持っている可能性のほうをいじるのが、編集者が述語を大事にしているところに通じるんだと思います。
そういう意味もあって、新しく作られているものがすべてゼロイチで始まっているのではなくて、今まで連綿と続いている文脈の中でそういうものをもらいながら、あたかも新しいものが出来上がったかのように見えていると。
その文脈を使いながら述語的に手伝いをしているのが、編集という営みなんだろうなって思いますね。
佐渡島:述語部分についてのアイデアがどんどん出てきて、「これってこうなんじゃないかなぁ」と思いついていく。それで違う可能性でモノを見てみると、驚きになる。違う可能性を見ずに「これは水だ」と思って決めつけていると、絶対に驚きはない。
けれども、これに対して「ペットボトルの中に入っているのは水だ」じゃなくて、違う述語が思いついた瞬間に、急にこれに対して笑いが起きたり、驚きが起きたりしていく。今回の安藤さんの本の前半部分は、述語的に考えることを違うかたちで説明しようとしているのかなぁとも思っています。
安藤:そうかもしれないですね。驚きを『問いの編集力』に寄せてお話しすると、驚く能力って間違いなく人間こそが持ちうる力です。今AIが相当なところまで来ていますけれども、AIはやはり驚けないんですよね。「わっ!」と言われて「あぁ、びっくりした」という驚きじゃなく、ここで言う驚きは「あれ?」と思うことです。
いつも見ている景色なんだけれども、「そういえばなんでこんなかたちなんだっけ」と思うところが、『問いの編集力』の中でも非常にキーになっているところなんです。
佐渡島さんも、(2021年に)『観察力の鍛え方 一流のクリエイターは世界をどう見ているのか』という本を出されましたね。その中にも「どうすると観察力は研ぎ澄まされていくのか」といういろいろな方法論が語られていました。
その中に、今、ペットボトルの例でお話しいただいたように、「フィルターを外す」というものがありました。私たちは、水を水と簡易的に理解するようなテンプレートがあるわけです。そうじゃないと、毎回頭を使わなきゃいけなくて大変なので。
テンプレートやフィルターになっているものを1回あえて外すのは、たぶんめちゃくちゃ難しいことだと思うんですけれども。私たちの言葉で言えば、それも1つの編集力なんですよ。自分自身のフィルターに自覚的になって、いったん外してモノを見てみる。
そうすると「あれ」というような、「これ、ずっと見ていたけどなんでこんなかたちをしているんだろう」という問いが生まれるんじゃないかなと思いますね。
佐渡島庸平氏のChatGPTの使い方
佐渡島:まさに今の「AIを驚かすことができない」という時に、僕らが「これは未知だ」と思ってAIに聞いた時の、返ってくる答えのすごさ。
安藤:本当にすごいです。
佐渡島:『問いの編集力』がまさにこの時代に必要だなというふうに思うのが、僕、ずーっとAIに質問できるんです(笑)。
(一同笑)
それで、他の人と比べてAIへの質問がめっちゃうまいと自分で思うんですよ。
安藤:ずっと作家さんと編集者として仕事をしているからですか?
佐渡島:そうかもしれないです。今朝も知り合いのトレーニングジムの経営者と話していて、自分の毎日の睡眠スコアとボディバッテリーと、体重と飲んだお酒とかを細かくExcelで記録をつけていたんですよ。
データを取っているから、「今からChatGPTにこのデータを読ませましょう」と言って、「このデータのExcelの表だけで、自分がどんな人間だと思うかを聞いてみてください」って。
「その次に『会社での役職は何だと思いますか』と推測してもらってください」と言いました。そしたら、チームリーダーとか社長とか、AIがしっかり推測してくれたんです。
それで、「じゃあこのデータからわかる自分に足りないところと、もっと伸ばしたほうがいいところを聞いてみてください」とか。「部下と接する時、何に気をつけたらいいかを聞いてみてください」とかやっていくと、AIがかなりその人のことをわかっている感じで答えるんですよね。
Excelの表の縦と横にどんな項目をつけて、どんな言葉で何日間入力していったかということだけなんだけれども、相当AIが読み取ってくれる。しっかり問いを立てていくと、むちゃくちゃサポートしてくれて、やはりAIの時代は、どういうふうにAIに問うていくのか(が大事)なんだなぁと思いますね。
人間が自分の尊厳を見失わないように生きるために大事なこと
安藤:そうですね。私もそのことはよく考えています。ある時、ChatGPTに今お話ししたように、「AIは問うことができない」という前提で、「今、あなたが一番関心のある問いは何ですか」って、聞いてみたんですよ。
ちょっと前のChatGPTだったら「私はAIですから、問いなどは持ちません」という答えが返ってくるかなと思ったら、「あなたといかに楽しく話せるかということが、もっぱらの私の今の問いです」ということを書いてきて。
逆に私に「あなたはどうすると快適ですか」とかを聞いてきて、学習しようとするんですね。
佐渡島:(過去のやり取りを)記憶してくれますからね。
安藤:そう。もうどんどん日進月歩で進化していて、ずるいなと思いました。ただ、人間の特殊性は、問いがすごく非線形ということ。人間は、それまでの経験値と自分自身の個性や関心事の中で、「意味はわかんないけど突然これが気になる」とか、「A」という情報を聞いた時に、突然関係のない「X」について連想する、といったことが起こります。
それはこの本の中にもちょっと書きましたけど、暗黙知がずっと動いているからだと思うんです。それも早晩、AIも似たようなことをするかもしれないんですね。AIに対して問いを与えていっておもしろい活動をしていくのはとても大事なことだと思うんですが。
そういうことをAIができちゃうような世の中で、人間が人間たる尊厳を手放さずに生きていく時に、自分の中から湧き上がってくる非線形な、説明のつかないような問いが湧いていき続ける状態に自分を置いておく。
これはたぶん自分の尊厳を見失わないように生きるという意味でも、すごく大事なんじゃないかなと思っています。どちらかというと、『問いの編集力』を書こうと思ったきっかけは、そこだったんですね。
松岡正剛氏が情熱を持っていたもの
佐渡島:また話が松岡さんに戻っちゃうんですけど、AIにできなくて人間にできることといった時に、さっきの「話が飛ぶ」も含めてなんですけれども、やはりそこには「したいこと」がある。そのしたいことを軸に「こうじゃないかな?」という問いが発生してくる感じ。
例えば僕が松岡正剛さんを知りたいと思うのも、大本としてはやはり編集というものをよく知って理解して、自分の仕事に使いたいという思いがある。(だから)正剛さんに関する質問がずっと出てくるわけじゃないですか。
そう考えると、松岡さんはいろいろなことに好奇心を持たれていたと聞きましたが、「やはりそうは言っても軸があるんじゃないか」って気持ちになっていますね。
安藤:(笑)。聞きたいですね。
佐渡島:象の全体像がアリにはわからないという感じで。例えばさっき言っていた7つの問いを発生させる中心となる、正剛さんにとってもブラインドになっている問いみたいなものがあるんじゃないかと、正剛さんの本とかを読んだりしていると思ってしまいます。
 安藤:
安藤:(笑)。つかみにくいし、不思議だし、どこかマジックがあるしね。気持ちはとてもよくわかる。でもやはり、これは私の仮説ですけど、どこまでいっても「この世界はなんでこうであるんだろうか?」ということだと思います。
そこに目的はないんだけれども、そこへの好奇心がたぶん子どもの頃からあって、ずーっと考えていたから、たぶん20代で「ああ、だいたいわかった」となったんだと思うんです。つまり、さっき出た「フィルターを外せない」ということで言うと、松岡さんにとっては最初からフィルターが外れた状態でモノを見る目を鍛えてきていて、常に何重かのモードを重ねて見ているんだと思います。
今クライアントと仕事をしている目で見ているけれども、その奥にはフィルターが一切かかっていない目もあるという、複眼だったんだと思うんです。その中で活動する時に、「ああ、そうか。世界ってこうなのか」と編集の構造が更新されていくところ、またその風景を人と共有するところに、松岡さんの情熱があったように思います。
世界を「つながり合うパターン」として見る
安藤:『遊』の中で有名な特集で、「相似律」というのがあるんですけど。ただただひたすら似ている写真を集めてくるんですよ。例えば、象の皮膚のシワとガラスのひび割れと蜘蛛の巣など、「ほら、並べると似てるでしょ」みたいな。ひたすらそれで特集を組んでいくという相似律というのがあるんです。
この本の中にもちょっと出てくる(アメリカの人類学者の)グレゴリー・ベイトソンは、「世界をつながり合うパターンとして見る」と言ったんですけども。松岡さんもベイトソンには非常に影響を受けています。
世界の中にあるパターンを見つけてきて、それを発見した時に喜ぶとか。人間が後から一生懸命にも適当にも作り上げた、世界のもっと奥にある美しさみたいなもの。宇宙物理学者や数学者などはそういう目で探究している人が多いんじゃないかなと思いますが。
その一番奥のフィルターがかかっていない目をいかに持ち続けるかということに、本当に信じられないくらいの鍛錬や訓練をしてきた人だなという、私もそれくらいしかわからない(笑)。
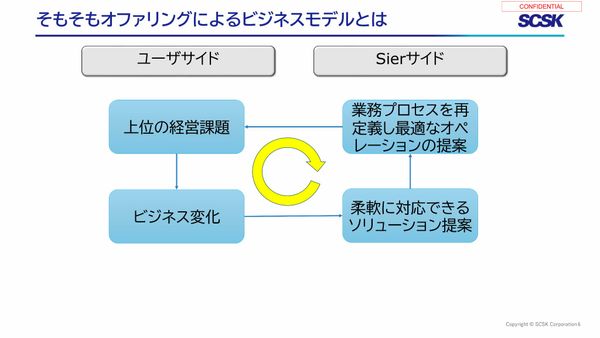 PR
PR











