『問いの編集力 思考の「はじまり」を探究する』の出版を記念して開催された本イベントでは、著者であり編集工学研究所の安藤昭子氏と株式会社コルク代表の佐渡島庸平氏が登壇。本記事では、知の巨人・松岡正剛氏が持ち続けていた「問い」について語りました。
コルク佐渡島庸平氏と編集工学研究所の安藤昭子氏が対談
司会者:それでは時間になりましたので、今日のイベントを始めさせていただきたいと思います。今日は、安藤さんの新刊『問いの編集力』を出版したディスカヴァー・トゥエンティワンと、コルクの佐渡島さんが主催するコミュニティ「コルクラボ」さんとの協賛というかたちで出版記念イベントをさせていただきます。
僕もお二人の話を聞くのをすごく楽しみにして来ました。さっそくお二人にバトンを渡してイベントを開始したいと思います。よろしくお願いします。
佐渡島庸平氏(以下、佐渡島):はい。よろしくお願いします。
安藤昭子氏(以下、安藤):よろしくお願いします。
佐渡島:(司会者である伊東佑真氏を指して)「いひがし」と呼んでいるんですけど、いひがしはコルクラボのメンバーでありながら、安藤さんの今回の本を編集したので、「じゃあ一緒にイベントをやっちゃおう」ということで実現しました。
僕自身も(安藤さんの師である)松岡正剛さんの塾に通わせていただいていました。実は僕は、松岡さんの事務所の向かいにあるマンションに長年住んでいたので、いつも会社に行く時に目の前を通って、「ここに松岡さんがいるんだよなぁ」と思っていました。
今日は本の中身を聞いても意味がないので、僕が安藤さんにいっぱい質問をして、本から派生した深掘りをしていこうかなと思います。
安藤:よろしくお願いします。
佐渡島:この本のゲラのやり取りをさせていただいている途中に、松岡さんが亡くなられたというニュースがありました。松岡さんの塾に行き出した理由は、本だけじゃなくて生の声を聞いて「編集とは何か」を考えたいというふうに思ったんですが。
実は僕が松岡さんとお会いさせていただいたり、本を読ませていただいたりする中でずっと思っていたことがあって、松岡さんは情報を編集しているんだけれども、情報を編集した結果、どんな社会にしたいのか。松岡さん自体がどんな問いをもって自分の人生に取り組んでいるのかがわからなくて。
すごくおもしろいのが、実はこのコルクラボには、数ヶ月前に尺八奏者の中村明一さんに来ていただいているんですが、その1ヶ月くらい前に、松岡さんのところで演奏会をやっていて。
「趣味が被るな」と、中村さんに「松岡正剛さんが好きで」という話をしたら、「もうデビューの時から、30年間ぐらい松岡さんには支えてもらっている」とおっしゃっていました。35歳くらいになってから、何かに興味を持って調べると松岡さんのつながりだったりします。
松岡正剛氏はどんな「問い」を持っていたのか
佐渡島:そうした格調高いところに松岡さんがいるのはまだわかるにしても、俗っぽいところにも松岡さんがいて。「僕は松岡正剛とみうらじゅんの手のひらの上にいるのか」と思わされます(笑)。
安藤:その組み合わせはちょっとわかるかもしれない。
佐渡島:松岡正剛は何をしたかったのか。例えば「社会を変えたい」だ思ったら、僕が編集者としてそれを勝手に引き継ぐことだって起こり得ますが、どこまでいっても松岡さんの問いが見えてこない感じがあって。でも『問いの編集力』で、問いを持つことの大切さを、安藤さんは松岡さんからたくさん教えられていたのですよね。
「そこに関してはどんなふうに見ていたんですか」とか「松岡正剛さんはどんな人間なんですか」というところから、今日のお話を始めたいなと思います。
安藤:一番難しいところからですね(笑)。おそらく松岡正剛という人の問いが見えにくいのは、もともと社会的なビジョンが先じゃないんですよね。
よく日本って中空構造(特定の中心が存在せず、相反する要素がバランスを保つという構造)と言われますけれども、松岡さん自体がすごく日本的なんですね。神社とかも真ん中は空っぽで、そこに神様がどこかからいらっしゃる。日本はそういう特徴を持っていますよね。

松岡さんも、真ん中は空洞な感じがするんです。なんだけれども、じゃあ何に関心を持っていたかというと、「この世界はどうなっているんだろうか」ということに対する好奇心。
なので、松岡正剛は当然ながら常にふつふつと問いが湧いている人ではあると思うんです。ただビジョンが先にあって「そこに向かうために僕はどうしたらいいだろうか」という類の問いではないんです。
「世界とはそもそもどうやってできているんだろうか」とか「そこにある石は、いつからあの形であるんだろうか」。「じゃあ人間の生命は、石とどう関係があるんだろうか」という、何らかの社会的な目的を持つわけではないような問いが生まれては消え、生まれては消えしていた。
佐渡島:その時に多くの人は、文化人類学者や哲学者になっていきますが、例えば落合陽一さんが会社をやってみたりしているように、幅広く好奇心を持たれている。でも、学者っていうのともなんか違うじゃないですか。
安藤:違いますね。
「ここまでつかみきれない人は本当に珍しい」
佐渡島:所長ではあるけど経営者っていうのもなんか違う。それって例えば、周りを刺激して社会を変えるような、吉田松陰みたいな感じだと思うんです。
いろいろな知識について並列で語っている感じというか、何でも知ってるんだけど、そこには松岡さんならではの意思や趣味があるし、知りたいと思っても、近づききれない感じが(ある)。
僕の場合は本当に接した時間もすごく短いながら、ここまでつかみきれない人は本当に珍しいと感じました。
安藤:そうですね。ちょっと1つ手がかりになるかもしれないなと思うのが、『知の編集工学』という本の中には、松岡さんが相当若い頃にいったん設定した7つくらいの問いがあるんですよ。
それはもう大きな問いなんですけど、例えば「なぜ自然は階層性を持つのか」とか、「なぜ人間は自己を持ち得たのか」とか。「なぜ生命は相互作用が入っているのか」というのが7つくらいあるんですね。
以前松岡さんが言っていたことがあるんですけれども、20代後半くらいの時に、ほぼほぼ「あぁ、世界ってそうなっているのか」ということがわかったらしいんですよね。それ以降は『遊』を作って、雑誌を作ってそうして見えてきた世界の様子を発信していくことになったんですけれども。
おそらく最初の頃にそういったいくつかの大きな問いを自分の中に持っていた。でもそれは目的があるわけではなくて、ただ好奇心として世界の謎が知りたかった。
『知の編集工学』は1990年代に書かれたもので、そこまで(問いを)持ち続けていたということは、そういう大きな問いをずっと更新し続けているんですね。その時に「そうか、この世界は情報でできていて我々はそれらを編集していると見れば、ほとんどのことが解けるんじゃないか」と感じたんだと思うんですよ。
世の中の「編集を覚えようとする」流れに抵抗し続けた
安藤:おそらく松岡さんの中で最初に設定した大きな問いは、それこそ世界の始まりや根源に触れるようなことなので、今お話に出ていたような、例えば会社をやるとか社会を変えるとか、というスコープではないんですよね。人間がある時期以降、人間の力で作ってきたものの手前に(問いが)あったんだと思うんです。
なので松岡さんの興味関心が、今の私たちが生きている人間が作った社会構造の中には、非常にマッピングしにくい。その分類の手前にある感じなので誰も名づけられないし、本人も「編集者」という以外名乗っていないのが、まず松岡正剛のあり方の基本だったと思うんですね。
1つ、はっきりとしたメッセージがあるとすれば、松岡さんは「今の世の中は、ほぼほぼみんな編集を覚えようとしている。それに僕は抵抗しているんだ」と言っていました。
松岡さんは当然ながらいろんな強い意志があった人だと思いますけれども。その強い意志がどう表れているかというと、人々や社会が「もうこれは作り終えたよね。これでいいよね」と済ませていくものに対して、「本来の生命はもっとこんなふうに生き生きとしているじゃないか」とか、「歴史はもっとこんな素敵な複雑さを持っていたじゃないか」ということを、自分の持ちうる限りの編集力で差し戻して抵抗し続けたのが、半世紀やり続けたことだったんじゃないかなぁと思います。
佐渡島:僕がすごく思うのが、(『西遊記』で)悟空がお釈迦さまの手の上から出られなかったように、モノを見る時の見方の眼鏡が僕と松岡さんだとスケールが違っている。同じスケールで見ないと松岡さんのしたいことが感じ取れなかったり。
僕が聞いた「松岡さんがしたいことってなんですか」というのは具体的すぎた。もう少し抽象的なしたいことを一貫してやられている可能性はあるのに、それに気づけていないんだとしたら、その抽象度を手に入れたいとすごく思いました。
俗世間から離れているように見えるが、現場仕事のプロフェッショナルだった
安藤:でも、それはたぶん松岡さんからしたらすごくうれしいことだと思います。次の世代の人たちが、松岡正剛の方法論をもってして「じゃあ自分はここを解いていこう」とか、「自分はその方法論で社会の中でこうしていくよ」というのは、それこそ仏教があんなふうにいろんな形になっていったように、「このあたりを継ごうかな」と思う人たちが自分の解釈でやっていくのがいいんじゃないかなと思っていますね。
佐渡島:松岡さんの問いのサイズは、世間と大きく乖離しているじゃないですか。でもお金を扱って生活しているところでは、世間とつながっている。
だから、自分の普段の他人との距離感や行動やお金、家族との関係とか。社会から期待されている行動と、自分の好奇心の自由さというか興味のあり方に相当なギャップがあるだろうから、そこにどうやって折り合いをつけたのか。

別に、松岡さんは山の中にこもって座禅を組みながらそういう問いをずっと考えたわけじゃなく、しっかりとした事務所を構えて、すごく現代人っぽい生活をしながら考えていた。そういうバランスをどうやって取っていたんだろうと、すごく考えていたんです。
安藤:おそらく佐渡島さんみたいな活躍されている方たちが、すごく興味があるところだと思うんですね。1つは、松岡正剛という人は、そういう俗世間からは遠そうな深遠な問いを抱えていた人ではありますが、一方でめちゃくちゃ現場仕事のプロフェッショナルなんです。
どなたかから相談をきっかけにいざ仕事が始まると、それを仕上げていく時の相手との関係の取り方とか、「これを渡してあげたことで、この人はどれくらいの社会的価値を手に入れることができるだろうか」というようなことまで含めて、徹底的に相手を納得させる仕事を仕上げるんです。だから仕事人として、本当に大工の棟梁みたいに、ものすごくプロフェッショナルなんですね。
もう1つ、おそらくこっちのほうが大事かもしれないんですけれども、さっき「何か調べていると、サブカルとかも全部松岡正剛とつながる」とおっしゃっていました。
コンビニの新商品やドン・キホーテのつけまつげの種類の多さにも関心を持っていた
安藤:松岡さんって、かすみを食べているような人に見えるかもしれないけど、現実社会で起こっていること、特に「コンビニでこういう新商品が出た」とか、「ドン・キホーテにはなんでこんなにつけまつげの種類がいっぱいあるのか」とか、そういうことにものすごく関心があったんですよね。
晩年はよく「世界」と「世界たち」という言い方をしていたんですけれども。「世界」というのは、さっきお話ししたように、深淵なる7つの問いに代表されるような「世界とはなんだろうか」というある種普遍性を持った世界があると。
一方で、ものすごくささやかだったり、小さかったり、もしくはいろんな姿をしている、普遍的ではない「世界たち」というのがある。松岡正剛はずっとイシス編集学校をやってきましたけれども、たぶん自分が作った作品の中で、イシス編集学校が一番好きなんですね。
なぜかというと、イシス編集学校ですごくがんばっている人たちは、その人たちなりのいろんな世界を持っているんです。その人が今どこに差し掛かっていて、何ができるようになっていて、何に関心を持っているのかに、松岡さん自身がものすごく関心を持つんですね。
それは、松岡さんにとってみたらすごく貴重な世界たちなんです。「そういうところからしか文化は生まれない」と思っていて。それが、サブカルの世界やコンビニの新商品やドン・キホーテのつけまつげにすごく現れていると見ています。
佐渡島さんはコルクラボをやられて、おそらくコルクラボのみなさんにもすごく関心がおありだと思うんですよ。その感覚とちょっと近いんじゃないかなと思います。
だから、今この世界を生きている人たちの感性にもすごく関心がある。たぶん本人はバランスを取っているつもりは一切ないと思うんだけど、そういう深淵さと今刻々と更新されている文化の両方で生きている人だったんだなと思います。
編集者が持つ「憑依力」
佐渡島:ちょっと話が戻るんですけど、中空構造の日本と言われる中で、「松岡さん自体も中空的だった」とおっしゃっていました。
それは編集という仕事自体が、聖も俗も併せて、全部1回並べてから整理していくものだからだと思います。先に自分の意思とかしたいことがあると全部は並べられなくなるじゃないですか。
安藤:そうですね。
佐渡島:僕がしたいこととかがすごく気になるのは、僕も作家がいると、「この作家はどうありたいんだろう」と、何をしたいかと(考える)。ある種、憑依するみたいな感じでなりきって、作家には漫画を描く、小説を書くだけに特化してもらって、それ以外のところをやっています。そこの憑依力みたいなのを強くしようと思うと、自分が中空的で(あるほうがいい)。
昔、先輩から「本当にいい編集は、右翼からも左翼からも『あいつを最も信頼している』と言われる」と言われました。なんで右翼の本を出した編集者に対して、左翼の人が「あんなに信頼できるやつはいない」となるのか。その感じって、中空感というか、ブラックホール感があって。
松岡さんがクライアントと対峙しているところはあんまり見たことがないんですが。僕の場合は自分で漫画家のエージェントの会社を作る時に、今までは「漫画家一人ひとりにとって何がいいだろう」と考えていたのが、「漫画業界にとって、新しい新人漫画家が生まれる仕組みができるためには何がいいだろうか」と考えるようになりました。それでいろんなことを会社の社長として振る舞おうという調整をしているわけです。
自分の主張が先にあるのではなく、周りとの関わりで主題が生まれる
安藤:今お話しされた「右翼からも左翼からも」というのは、本当に松岡さんもそういう人だと思います。というのは、「方法こそがコンテンツだ」という考え方なんですよね。なので、右翼的なことや左翼的なことっていう思想やコンテンツが先にあるんじゃなくて。
むしろそういう人たちの方法はどういうものか、どうするとそれがおもしろく見えるかっていうほうに興味がある。トピックやテーマや思想にはそれを動かしている方法があって、編集工学っていうのはそうしたものを読み解く視点なんです。
なので、今言われたような「中空である」というのは、真ん中に先に自分の主張やテーマがある状態ではなくて、いろんなものとの関わりの中でいかようにも主題が生じてくるということだと思います。
この話をもう少しだけ言い方を変えると、よく「(編集は)主語よりも述語的である」(と言っていました)。私は佐渡島さんの本を拝見していてもすごく感じるんですが、編集者の仕事って、とかく述語的だと思うんですよね。
主語がどこかにあって、自分自身は述語でどうとでも包んであげられるというような。それをしていくと、本当に扱うものは何でも大丈夫なんです。その分、自分自身が変幻自在なので、おそらく周りとしてはつかみにくい。
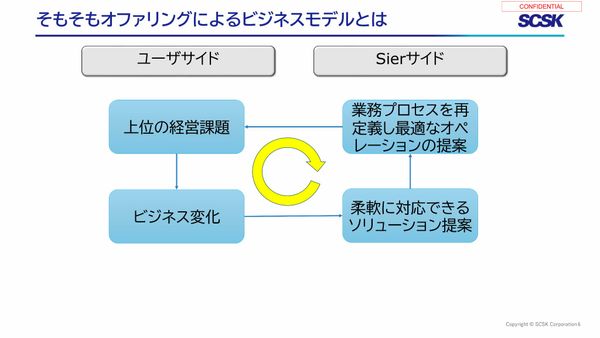 PR
PR





















