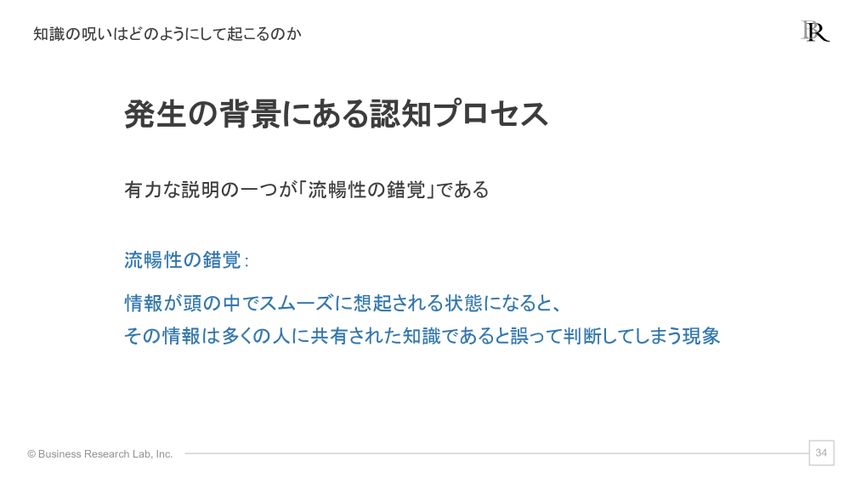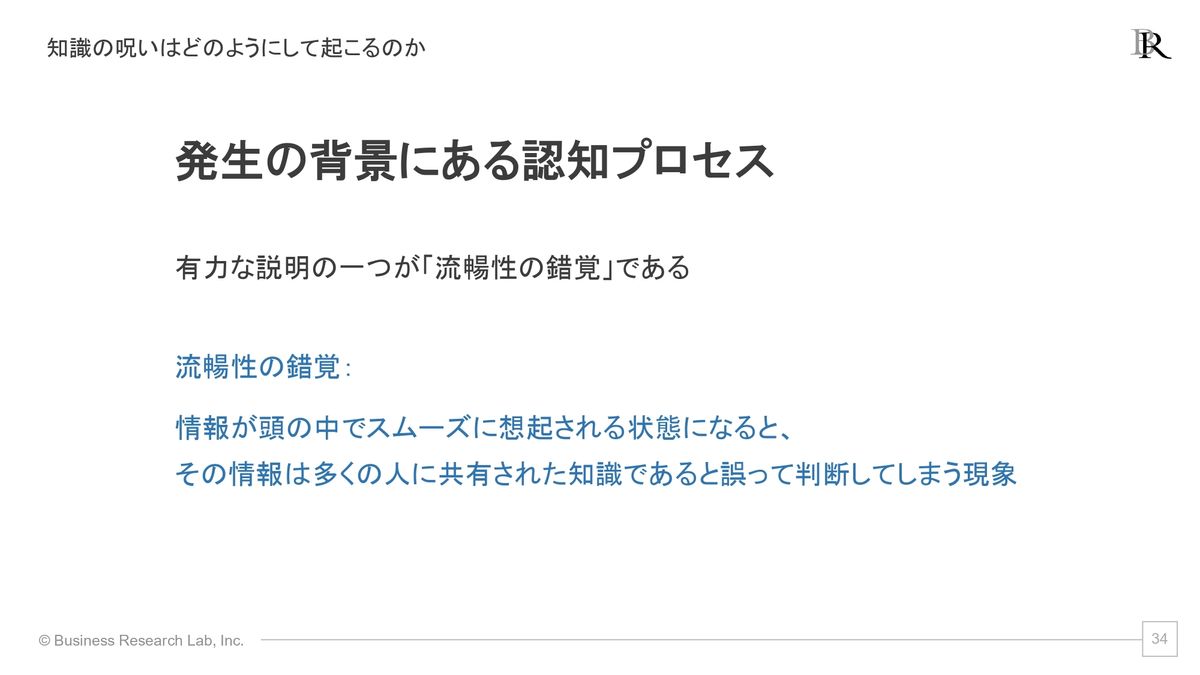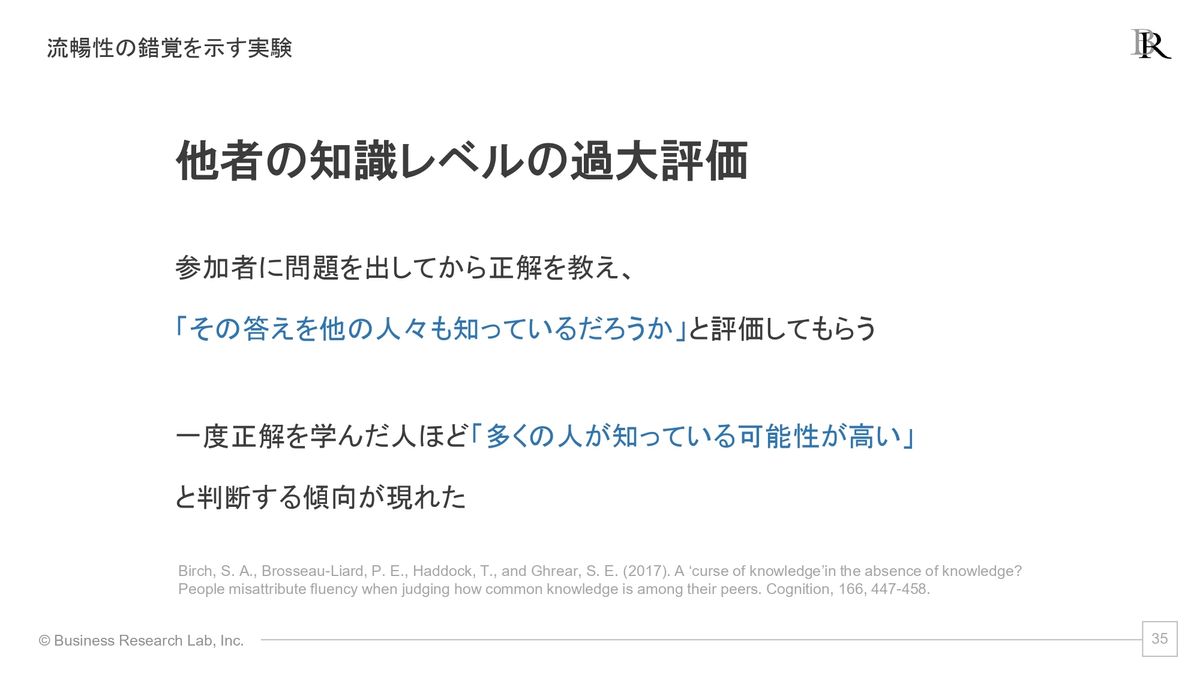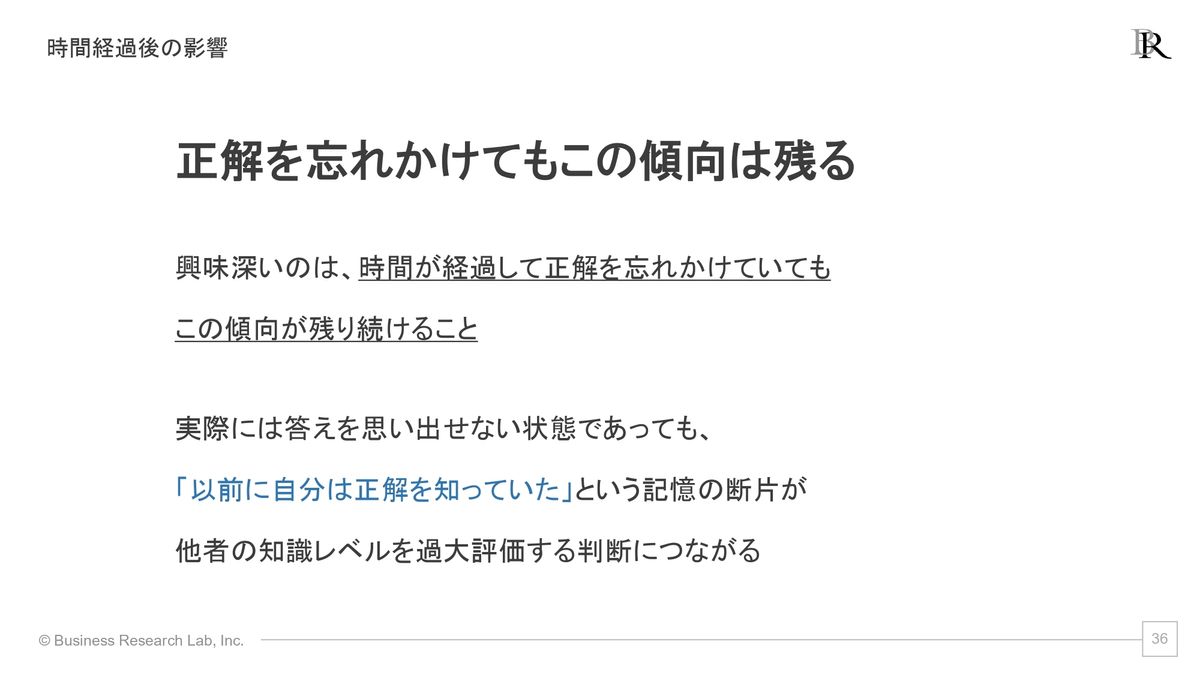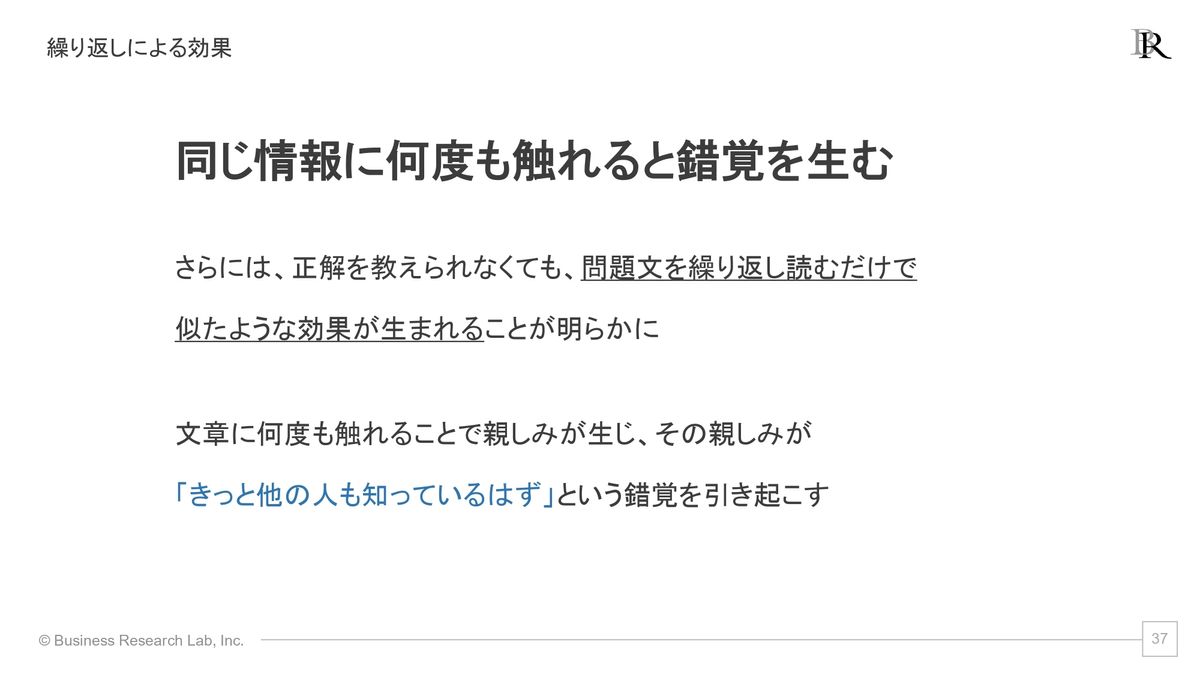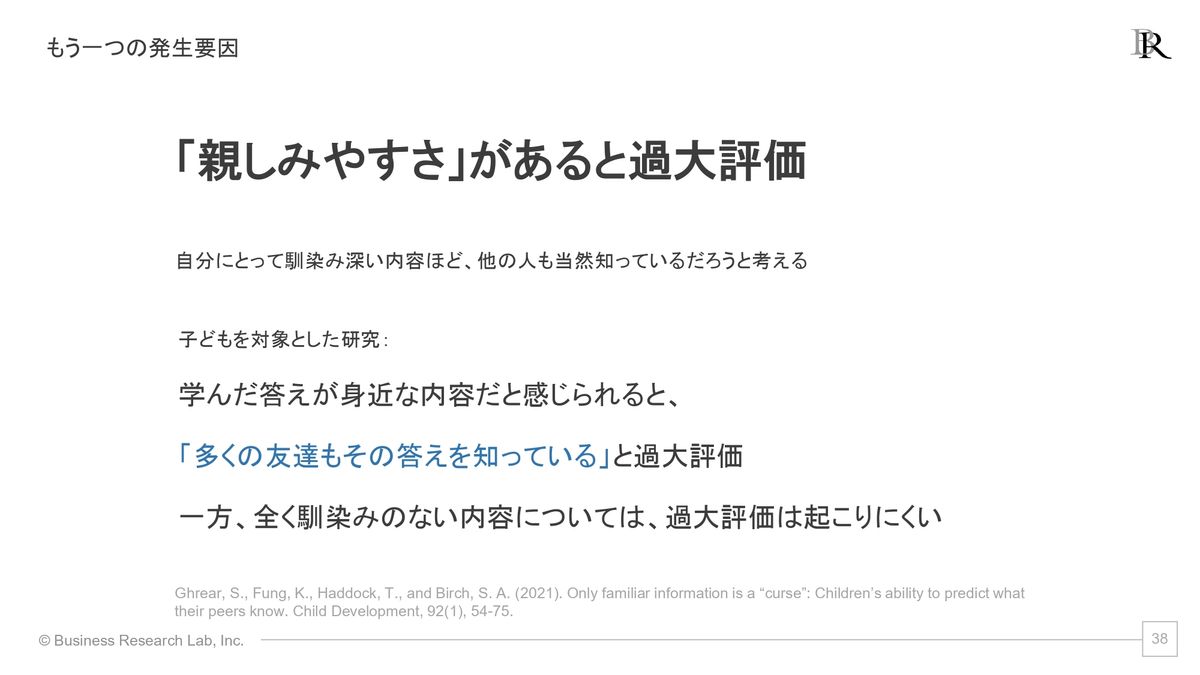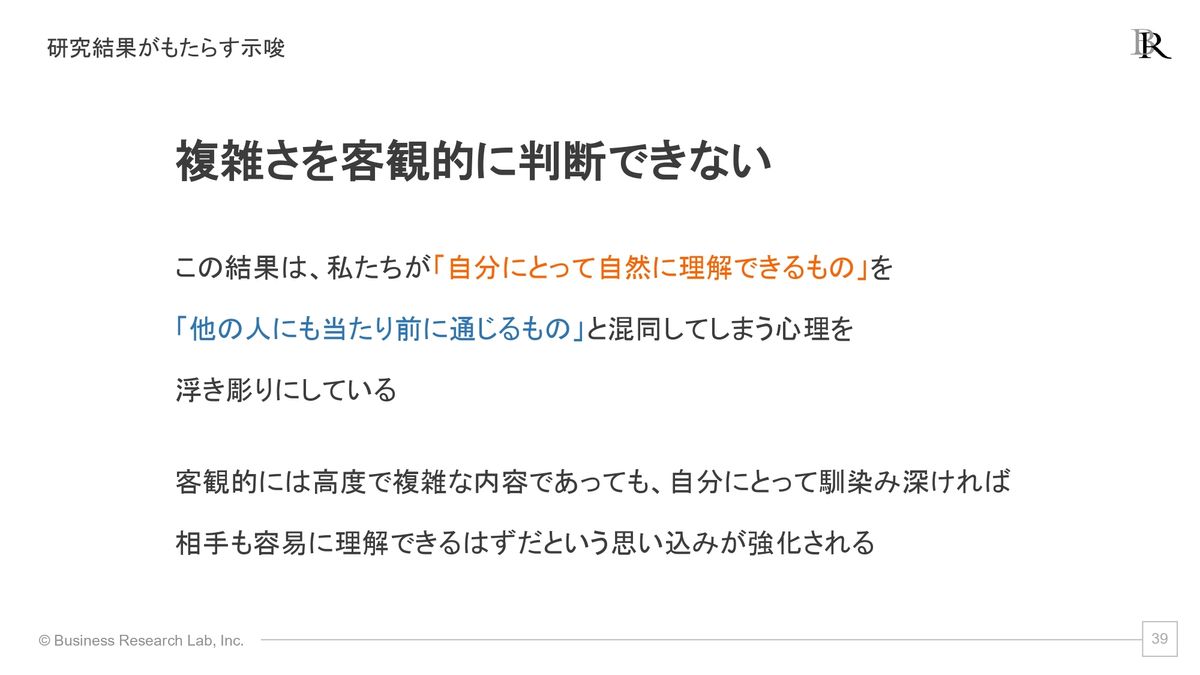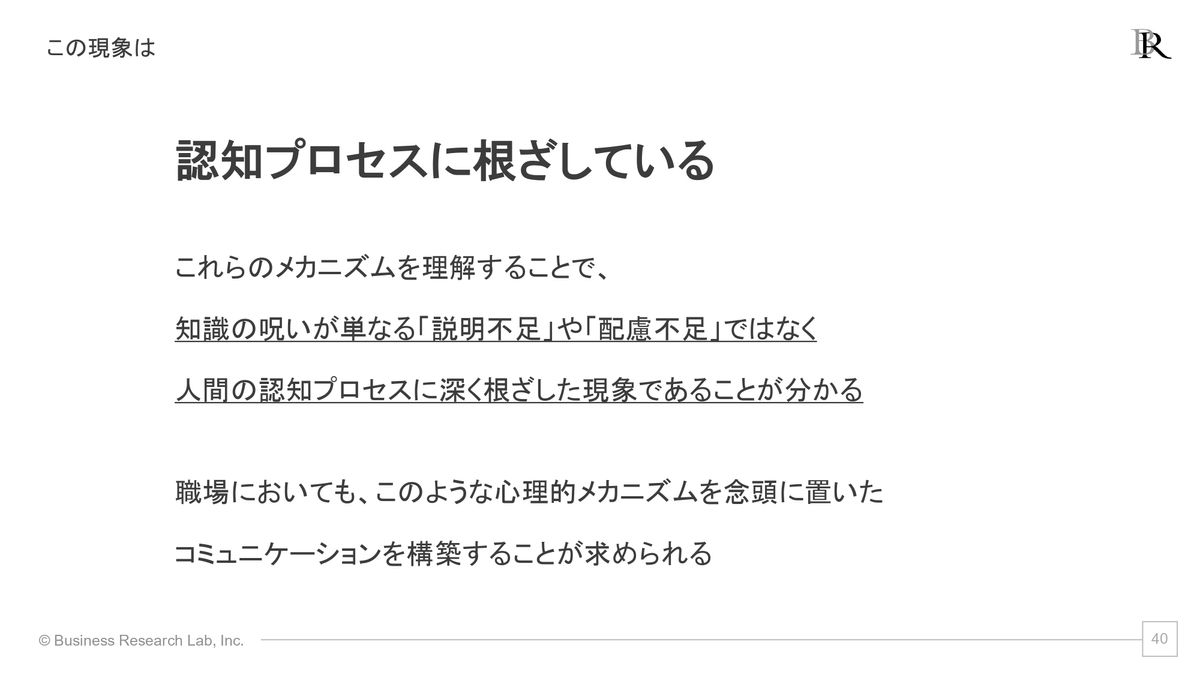「知識の呪い」が起こるメカニズム
では、その対策を考えていくために、まずそもそも「『知識の呪い』という身近な現象がなぜ生じてしまうのか?」というメカニズムについて考えてみたいと思います。「『知識の呪い』ってどういうふうに起こってくるんだろうか?」ということです。
さまざまな説明が試みられているんですが、その中でも有力な説明の1つが、「流暢性の錯覚」と呼ばれるものです。「流暢性の錯覚」というのは、ある種の認知バイアスなんですが、人は情報が頭の中でスムーズに想起されるような状態になると、「きっとその情報は、多くの人に共有されていはず」と思ってしまう。
要するに、思い出しやすい、想起されやすい知識というのは、「他の人も持っているだろう」と誤って判断してしまう傾向がある。「本人にとって」というのがポイントなんですが、本人にとってアクセスしやすい情報というのは、「他の人もきっと共有されているはずなんだ」と思ってしまうということを、「流暢性の錯覚」と呼びます。
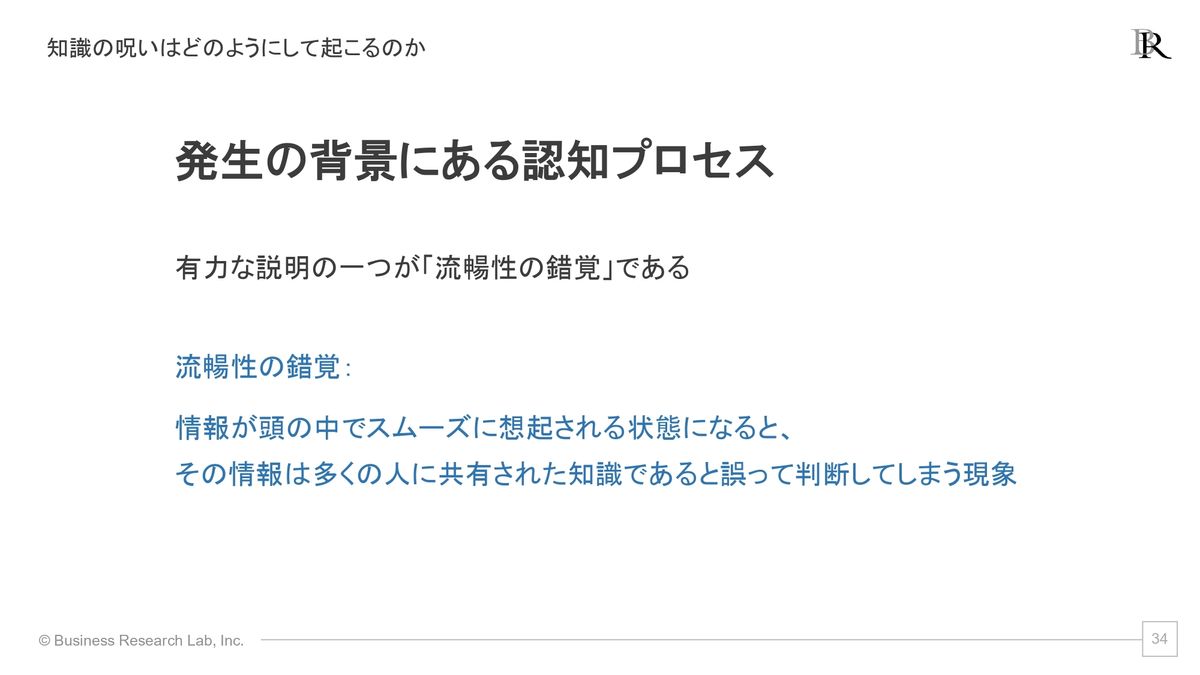
流暢性の錯覚が「知識の呪い」を発生させる
興味深い研究があるので、紹介させていただきます。実験の参加者に対して問題を出します。そして、正解を教えます。その上で、「その答えって、他の人は知っていると思いますか?」と評価してもらうんですね。
そうすると、正解を学んでいるグループ、正解を教えてもらったグループのほうが、「多くの人が知っている可能性が高いよね」と思うわけです。これは「知識の呪い」で、(この回答を)引き出しやすくなっているので、そうだろうと思われるんですが。
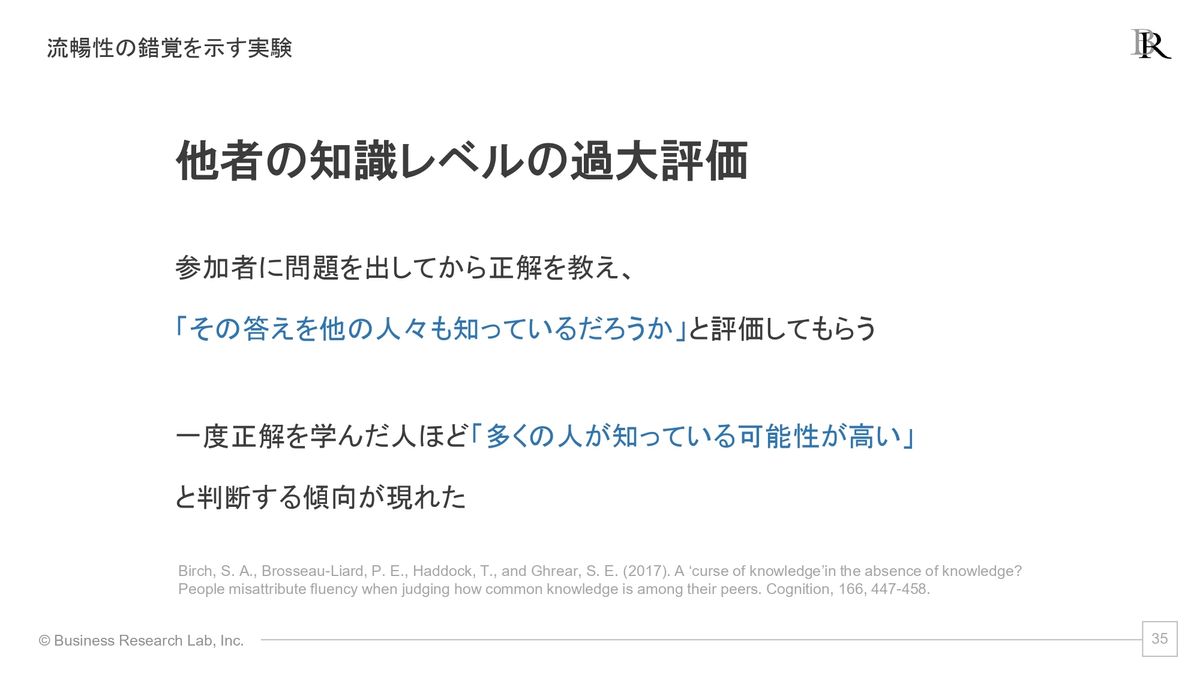
ここからがなかなかおもしろくて、時間が経つと、人は忘却するわけですね。その正解を忘れてしまうわけです。ところが、本人は正解を忘れている、答えを思い出せないという状態にもかかわらず、「以前、自分は正解を知っていたな」と思ってしまう。
これはまさに「流暢性が高い」状態です。「なんかアクセスできそう」といった状態になっていると、結局「知識の呪い」が起こるんですよね。つまり、答えを知らなくても、「答えを知っていた」という記憶だけで、「知識の呪い」が発生してきてしまうわけです。
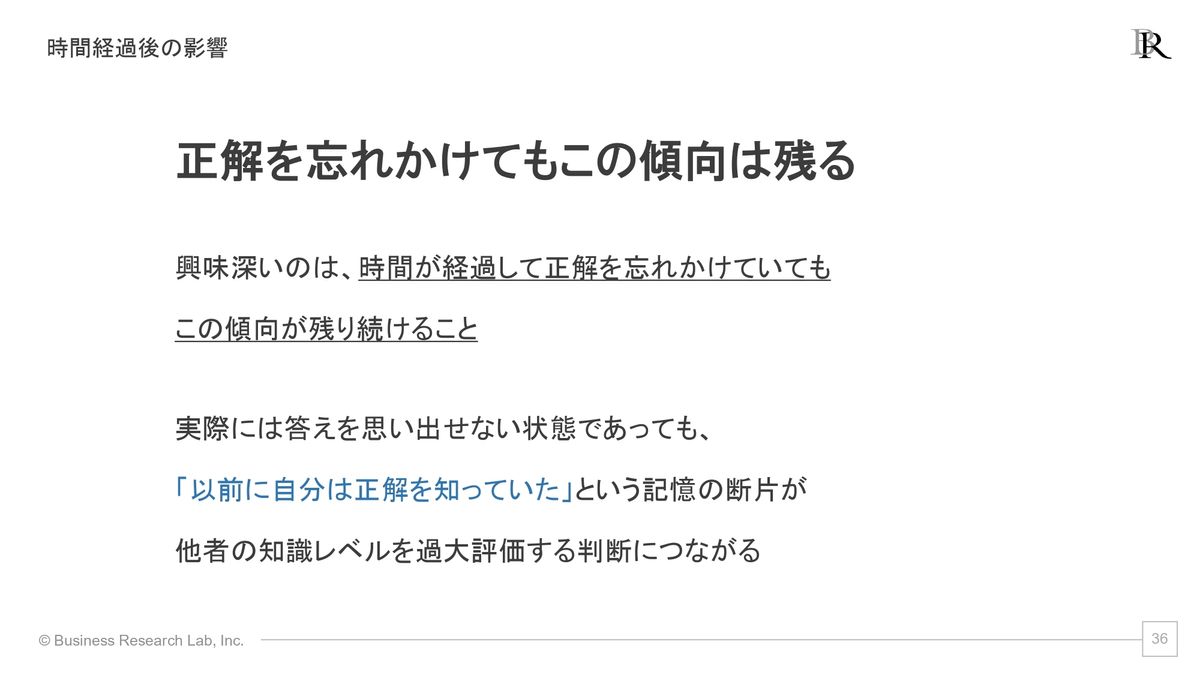
さらに、答えだけではなくて、問題文を繰り返し読むだけでも、同じように「知識の呪い」が発生してきてしまうことも明らかになっています。まさに「流暢性の錯覚」だと思うんですが、何度も何度も見ていると、答えを知らないのにアクセスしやすくなるわけですね。
その文章、問題文に何度も触れていくと、アクセスしやすくなって、流暢性が高まるわけです。そうなると、「他の人もこのことを知っているんじゃないの?」と思ってしまって、「知識の呪い」が発生してくる。過大評価が行われるようになってしまう傾向があります。
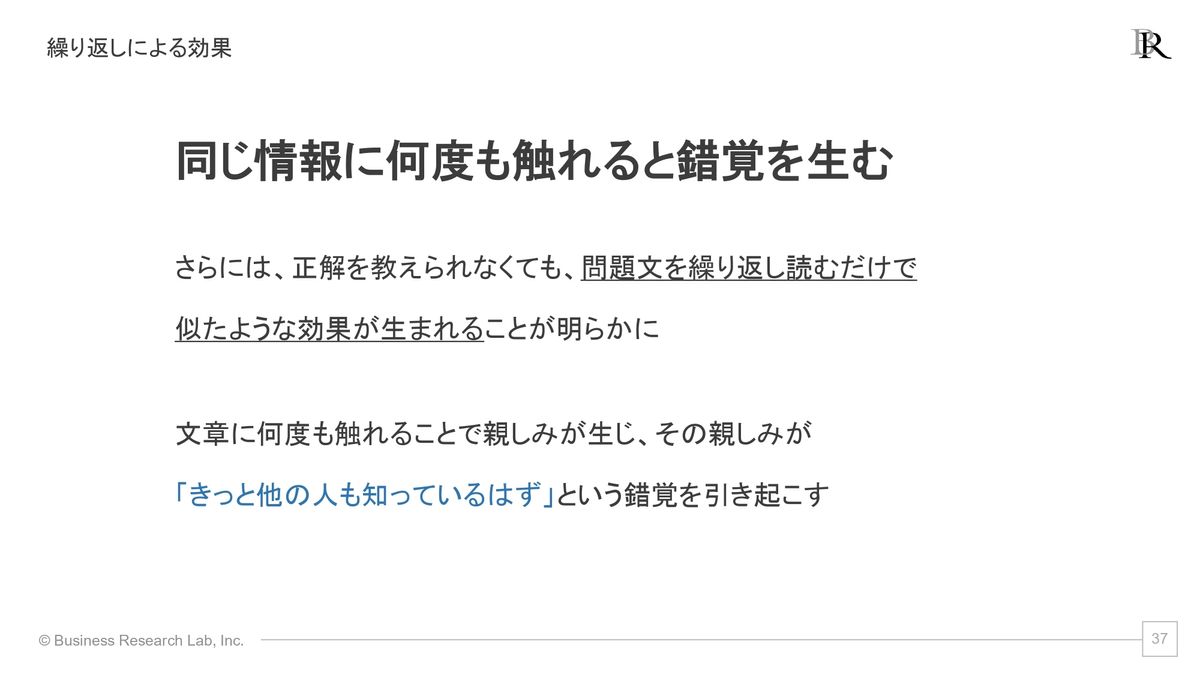
親しみやすさも「知識の呪い」を生む
もう1つの類似する説明原理として持ち出されているのが「親しみやすさ」なんですね。比較的類似しているとは思うんですが、これは子どもを対象にした研究を紹介させていただきます。
いろいろなことを学ぶ中で、その学んだことが自分にとって身近な場合もあれば、そうでない場合もあると思うんですね。その学んだ答えが「自分にとって身近なことなんだ」となると、「友だちもきっとこの答えを知っているよね」というふうに過大評価してしまう傾向があるわけです。
逆に、自分にとってあまり馴染みがないような内容については、「多くの友だちはその答えを知っているわけじゃない」と過大評価が起こりにくい傾向があります。自分にとって馴染み深い内容ほど、「他の人も知っているはずなんだ」と思って、知識の呪いが生じてきてしまうということです。
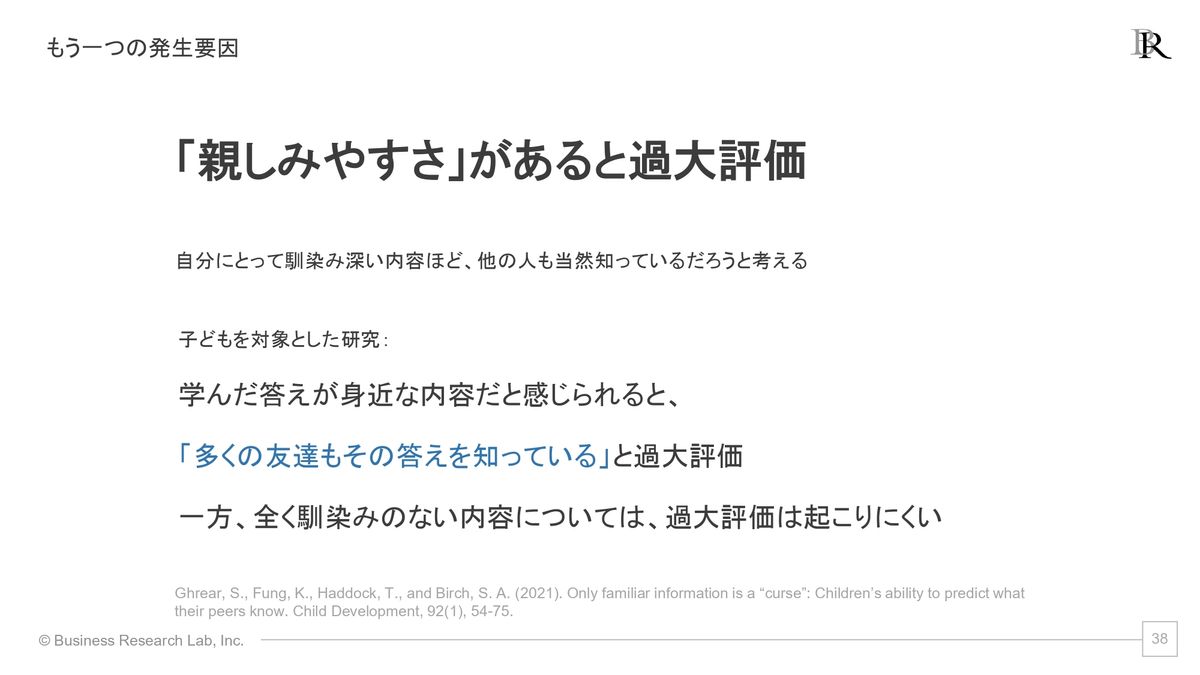
「自分にとって自然に理解できること」は、「他の人にも当たり前にわかっているよね」と思ってしまう。ぜんぜん違うんですけどね。自分が自然に理解できることと、他の人が知っていることは別の現象ですよね。そう言われたら「そのとおりだ」という感じなんですが。
ただ、人間心理というのはここをあまり区別できなくて、混同してしまうわけです。「自分が知っているなら他の人も知っているだろう」とか、「自分にとって馴染みがある。他の人も知っているだろう」と思ってしまう傾向があります。
客観的に見た時に、特に専門家になってくると、高度で複雑な内容でも自分にとって馴染みがあったりとかアクセスしやすくなっている状態って、決して珍しくないと思うんですね。そういう場合には、「きっと相手も理解できるんじゃないのかな?」と思い込みが強化されてしまう。「知識の呪い」が強まってしまうということがわかると思います。
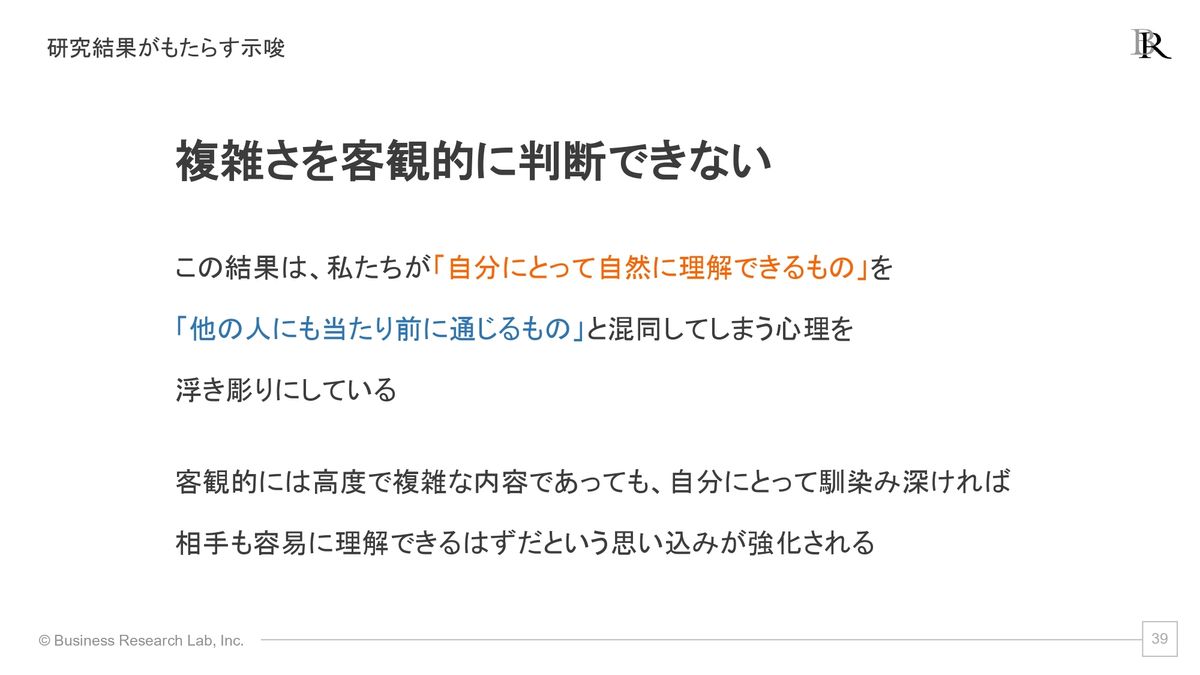
「知識の呪い」は人間の認知プロセスの中に深く刻み込まれた現象
今の説明からおわかりいただけたと思うんですが、「知識の呪い」という現象は身近であると。相手にとっては「なんでこの人、こんなに専門用語を使うんだろうか?」「なんでこんなに難しく言うんだろうか?」「なんでこんなに説明を省略するんだろうか?」と感じるわけですね。
それって単純な説明不足とか、配慮していないということではないんですね。人間の認知プロセスの中に深く刻み込まれた現象であることが、おわかりいただけるかなと思います。
ということは、「知識の呪い」は本人の努力不足とか、そういうことではないんです。きちんと「『知識の呪い』というのが発生するものなんだ」と考えた上で、どのようにコミュニケーションを設計していくのかが重要になってくるわけですね。
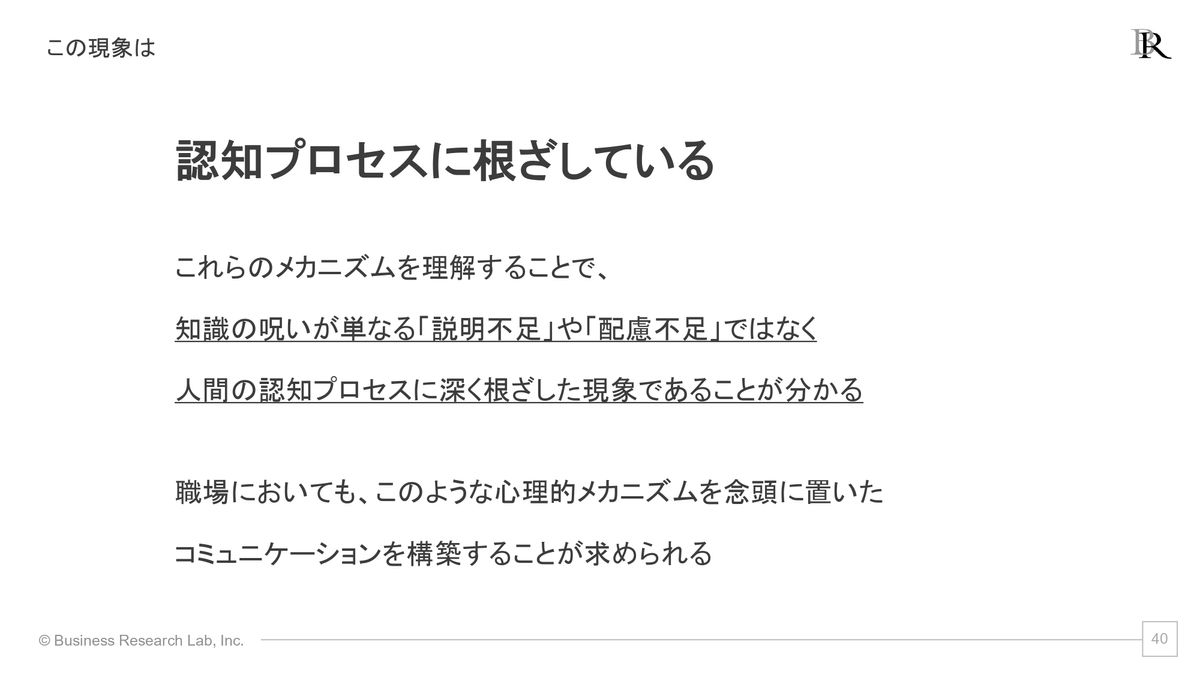
 PR
PR