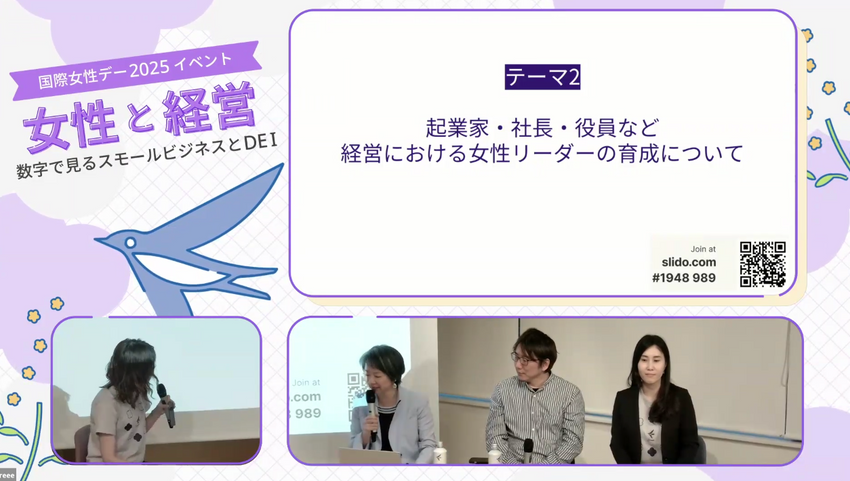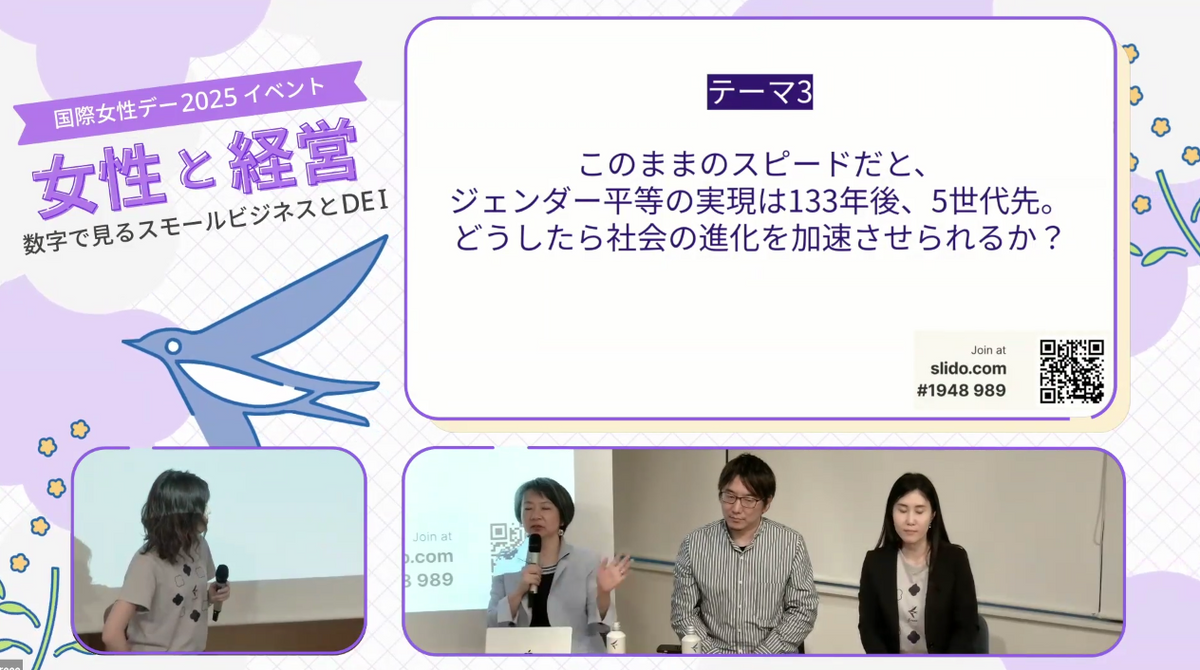管理職が実力のある部下に気づいているか
吉村:テーマ3、「このままのスピードだと、ジェンダー平等の実現は133年後」。これ、別に私が勝手に言っている話じゃないですよ。ジェンダーギャップ指数を出している、世界的な機関が出している示唆なんです。
今のままだと5世代先だと。「5世代って……」みたいなところがありますけれど(笑)、そうなんですよ。どうしたら社会の進化を加速できるかを、じゃあ、みかりんに実体験としてどうですかというところをおうかがいできたらと思います。
小泉:私はこの話で強烈に思い浮かぶエピソードがあって、2年前にfreeeの社内で出会ったシーンなんですけど、男性のマネージャーの何気ない発言。彼は「こういう重要なプロジェクトにアサインされるのも実力だからね」って言ったんですね。
私ともう1人女性のメンバーがいて、2人で顔を見合わせちゃって。「この人、アンコンシャス・バイアスに気づいてないんだ」と思って。
何かっていうと、重要なプロジェクトをアサインされるには確かに実力もあると思うんですけど、その候補者の中にどれだけマイノリティがいるんだろう。アサインを考えている人は、その人たちにどれだけアクセスしているか。
さっきの役職の定義に近いんですけど、本当に必要なスキルを定義して、そこへフィットする人材を探しているか。そこってまさにエクイティ(EqualityではなくEquity、平等でなく公正)の観点で、管理職が実力のある人にアクセスする努力ができていないために、そこにいけないんじゃないかと。
この変化を加速するには、やはりアサインする側、組織側はマイノリティ……例えば女性で管理職に挑戦したいとなんとなく思っているんだけど、まだ踏み込めていない人にチャンスを与えるように、声をちゃんと聞く。
やってみたいなって思う人、あるいはそこまで思わないんだけど「どうかな」って思っている人も、自分がどうしたいか。マイノリティ側もどうしたいかを考えて、私も、考えて主張するのが苦手だったんですけど、訓練をして主張していく。
日本の教育だとなかなか難しいことかもしれないですけど、スピークアップ(主張)していくことが大事だなと思います。
「無意識バイアス」はすべてが悪いわけじゃない
吉村:ありがとうございます。今、みかりんの話の中で「アンコンシャス・バイアス」という単語が出ましたけれども、この単語は「無意識バイアス」と言われたりするんですが、本人が無意識下で思い込んでいる偏見や思い込みを指します。
この話は自分で認知が難しいので、周りから指摘されたりとか、何か意識的な行動をしないと修正が難しいと言われているんですが。
このアンコンシャス・バイアスの文脈だと、篠田さんが過去にもいろいろ記事を書いてらっしゃって、そのあたりのお話もうかがってよろしいでしょうか。
篠田:ありがとうございます。無意識バイアスそのものは人間にとって大事な能力なんですね。例えば、今、私たちがいるのは19階ですけど、そこの窓がパーンって開いていても、赤ちゃんや2歳ぐらいの子って別に怖くないんですよ。ひゅーって覗いたりして、場合によっては痛ましい事故が起きる。
大人は近づいた瞬間にもう「うわ、怖い」って反応をさせてくれるのが無意識バイアスなんです。つまり経験を積んで「あれは危ない」と知ったら、いちいち思考を通さなくても、ある意味反射的に身を守るための反応なんですね。
なので基本的に、「無意識バイアスをなくそう」というのはおかしいんです。それは人間として生きていけなくなるから。ここで問題なのは、自分が育つ過程で身につけた無意識バイアスと、目の前の状況が齟齬をきたした時には、別のやり方で修正しないといかんよねという話です。
制度は充実しつつあるのに、活用できない日本
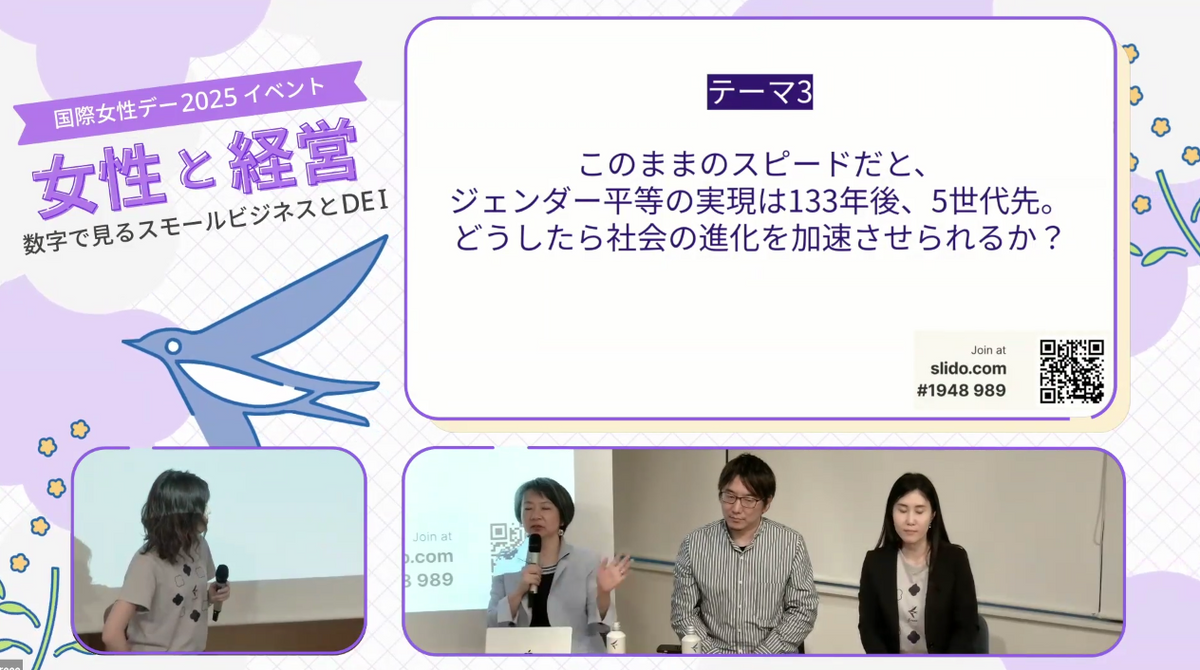
篠田:今日のテーマに即して言うと、主なものが「男性は仕事、女性は家庭」という役割分担の意識なんですよね。先ほどのお話(トークセッション前のプレゼン)でも「日本ってジェンダーギャップ指数がぜんぜん改善してないよね」というものがありました。
私が社会人になってから現在までの間に、本当にさまざまな制度が整って、保育園も一時期はまったくない状況からかなりの改善をしている。私はもうだいぶ年上になったので「いやぁ、良い世の中になったな」ぐらいにのんびり思っていたのですが。
20代とか30歳前後の女性の方たちとお話をすると、例えば「こうやって今、仕事が大好きでやっているけれども、自分が結婚したらどうなるんだろう。子どもを産んでも仕事を続けられるんだろうか」とか。
例えば、今お付き合いしているパートナーと結婚を考えていて、自分としては姓を変えたくないので事実婚を選びたいんだけれども、ご実家のご両親がそれにとても反対をしていて結婚に暗雲が……みたいな。
吉村:ああ、つらい……。
石倉:それは 高市(早苗)さんではない?
篠田:ではない(笑)。
(一同笑)
篠田:そういうことをたくさん耳にしまして。この30年はいったいどこにいったのかと考えると、やはり無意識バイアスに対して、私たちがあまりにもなんの手も打ってこなかった。
制度でいくと日本って本当に、先ほどの指数が改善していた国よりも良い、充実した制度もたくさんあるぐらいなんです。なんですけど、それを自分たちのシーンにちゃんと使えていない。まさに、これからの伸び代のポイントかなと思いますね。
「自分が構造を作ってきた側にいたんだな」
吉村:ありがとうございます。このあたり、石倉さんからもぜひマジョリティとしての意見をうかがいたいなと思っているんですが。
石倉:マジョリティというか、本来は女性と男性半々いるはずなのでアレなんですけど。でも、今の仕事をやり始めて登壇に呼んでいただくと、基本的には女性3:男性1みたいなパターンがほとんどなんですよね。そのくらい、男性でこの領域の仕事をしている人とか、お話しする人がいないんだろうと思っています。
僕も男3兄弟だし、キャスターをやる前まではどちらかというと非常にマッチョな会社にずっといたので、今思うと、バイアスはものすごく見られていたと思うんですよ。
で、なんで今みたいなことに急になったのかというと、キャスターの経験がすごく大きくて。今まで自分が信じていたこととか思っていたことって、自分が構造を作ってきた側にいたんだなと気づいたんですよね。「これは自分が当事者だな。変えなきゃな」って思ったのが一番大きいんですよ。
幸いにも最近、男性の中でも「やっぱりおかしくね?」って思っていたりとか、例えばエンジニアとかでも「なんでこんなに男しかいないの?」みたいに思っている人が、むしろけっこういる感覚があって。
男性がマイノリティの立場を経験することが大事
石倉:でも、この人たちが声を上げるのが、けっこう怖い領域になっちゃっているのも、ちょっとあると思うんですよ。よく知らないのにしゃべると何か言われることもあるじゃないですか。
なので、いかにおかしくないと思っている男性をちゃんと巻き込んで、チームとして解決するかは、非常に重要だろうと思います。男性として思うのは、自分がマイノリティの側に立つ経験をするのが重要だなと思っていて。
小泉:おもしろいですね、それ。
石倉:例えば僕、子どもが小学生なんですけど、保育園に送って行った時に、送りは3割ぐらいお父さんなんですけど、迎えに行くとほぼいないんですよ。僕ぐらいしかいないんです。僕はリモートワークだったので、行けるから行っていたんですよね。
土曜日に保護者会みたいなものがあって、先生たちを囲んで話す時に、僕しかお父さんがいなくて、あとは全員お母さんたちだったんですよね。女性はこれで20年間とか30年間も働いていると思うと、そりゃパワー出ねえわ、みたいに思うわけです。
なので自分が環境に身を置くとわかることもあるから、男性はもっとマイノリティになる所に行くとか、逆に女性の方はもし男性のパートナーがいたら連れ出すとか。女子会の中に身を置くみたいなのは(笑)、けっこう重要なんじゃないかなと思っているのが1個。
もう1個はD&Iとかもう周回遅れだとか言っている、うるさいおじさんたちがTwitter(X)をやめるのが、すごく大事かなって。
(一同笑)
 PR
PR