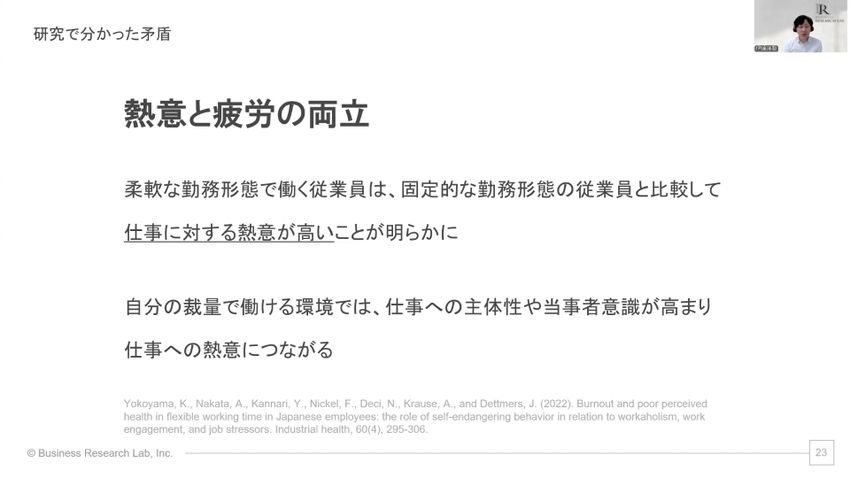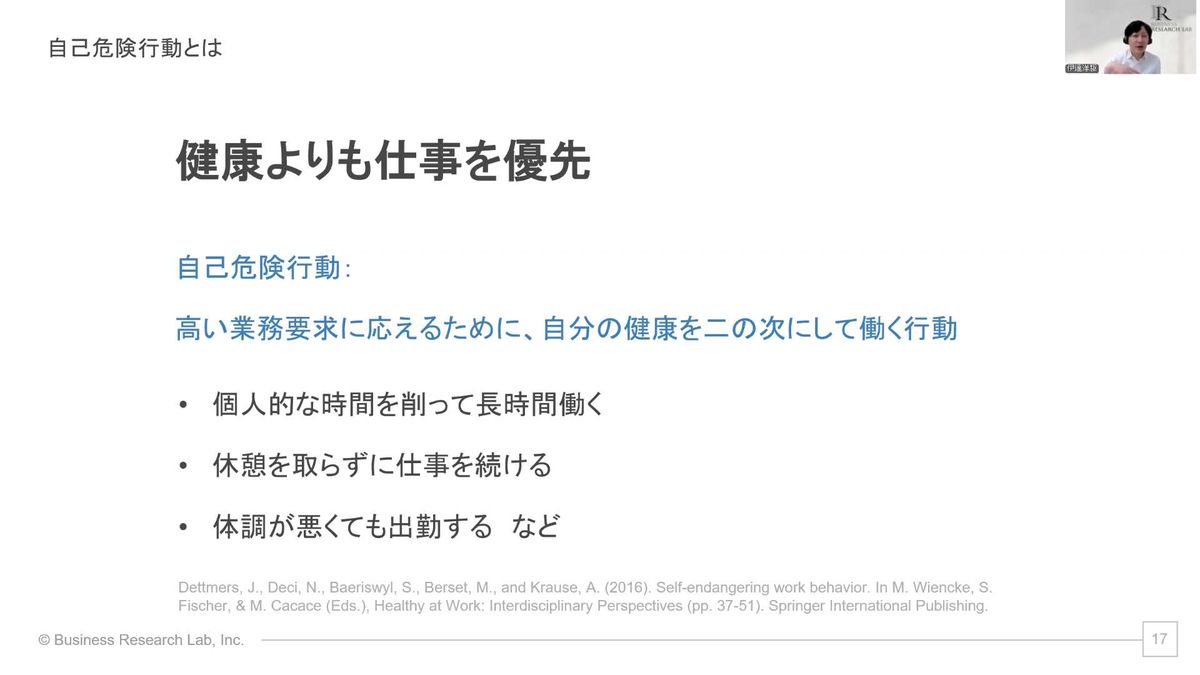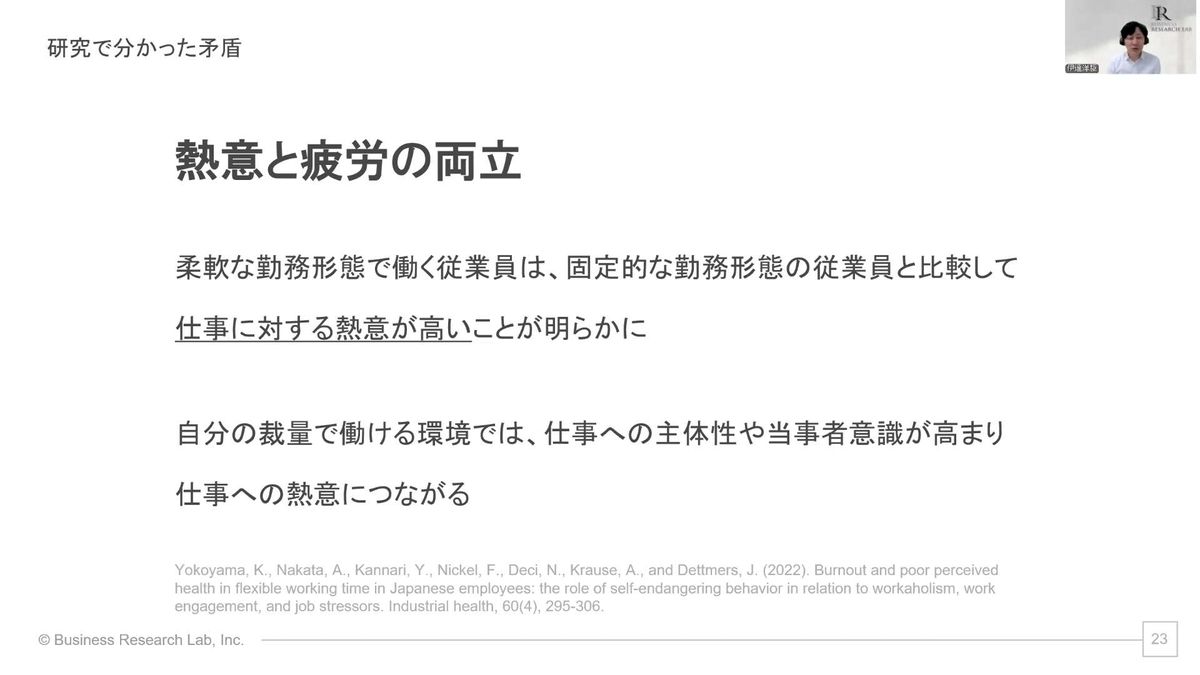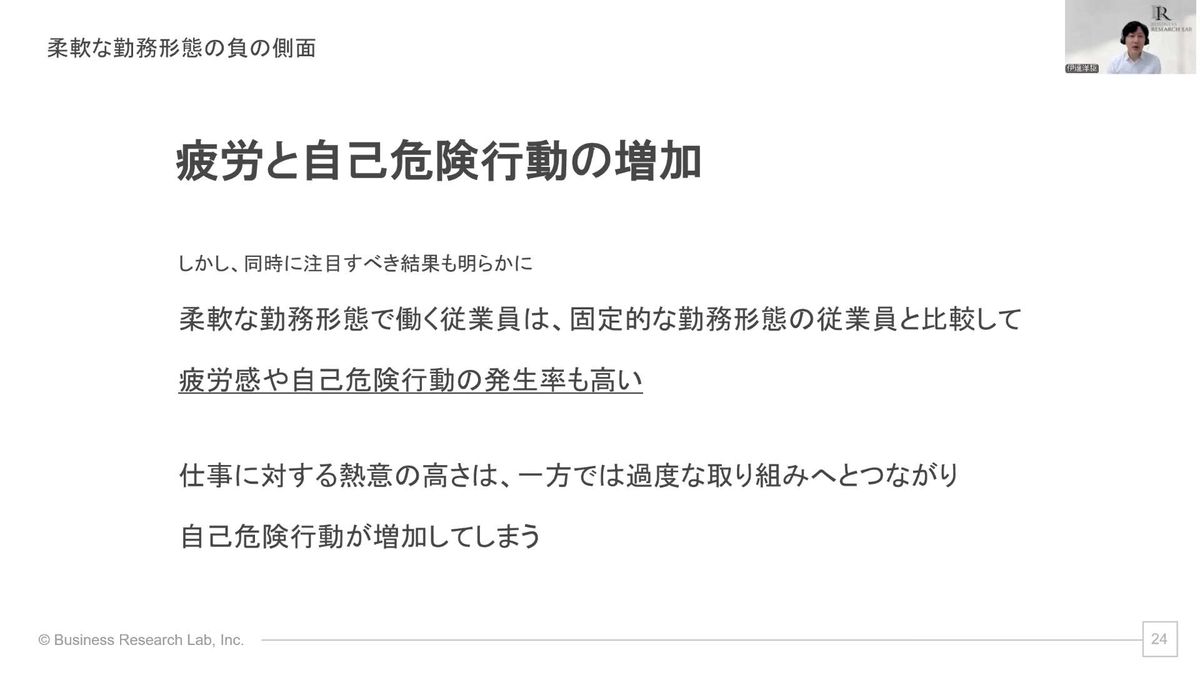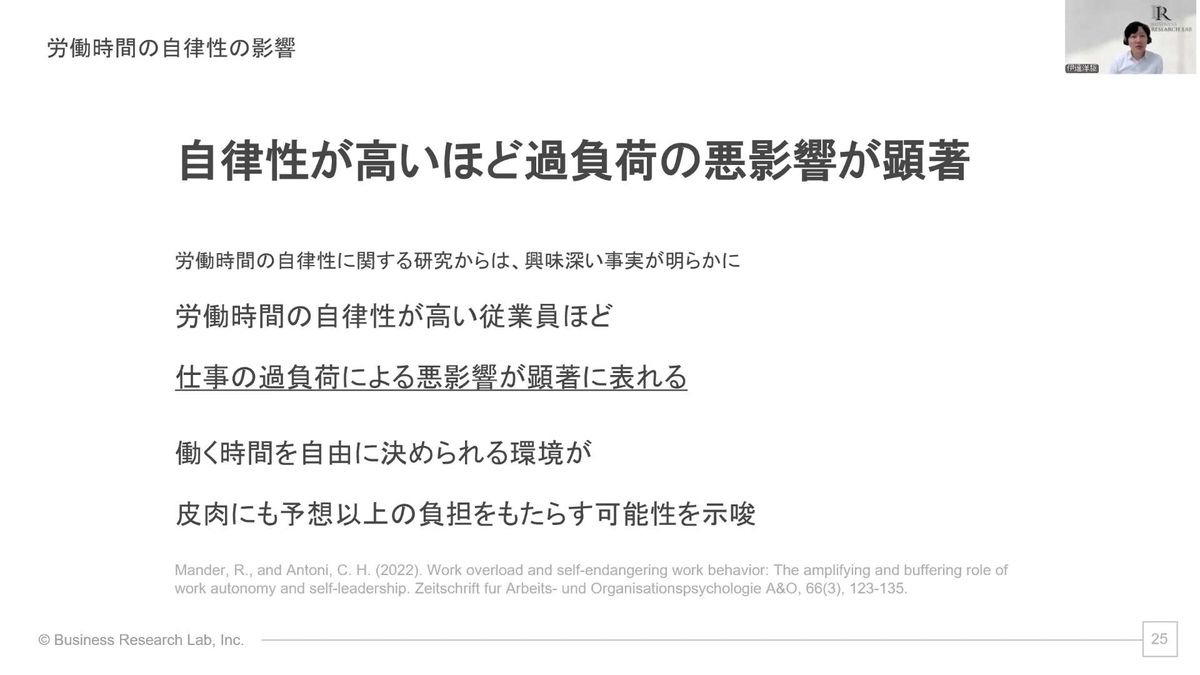組織課題を丹念に読み解く調査&コンサルティング会社「ビジネスリサーチラボ」が開催するセミナー。今回は「柔軟な働き方の落とし穴」をテーマとしたセッションの模様をお届けします。働きやすくなったはずなのに、なぜ以前よりも疲れるのか。その背景にある「自己危険行動」について解説しました。
昼食の時間を削ってのメール対応、体調が悪くても無理して出勤…
伊達洋駆氏:では、柔軟な勤務形態の副作用という1つ目のパートに入っていきます。
自己危険行動というのが本日のテーマですが、定義をしておきたいと思います。自己危険行動とは、学術的には、「高い業務要求に応えるために、自分の健康を二の次にして働く行動」と定義されます。要求があった時、自分の健康は横に置いて、とにかくその要求に応えるということですね。
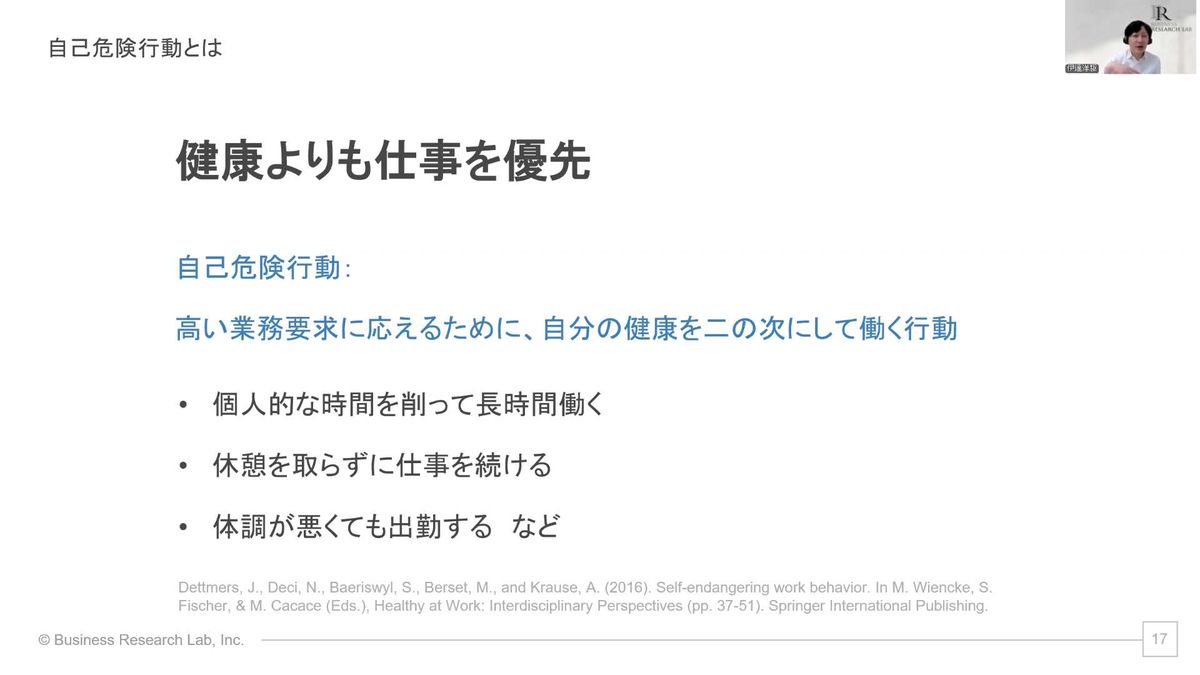
例えば、個人的な時間を削って長時間働く、休憩を取らずに仕事を続ける、体調が多少悪くても出勤する。このような行動を、自己危険行動と言います。
みなさん自身、あるいは周囲に、こうした自己危険行動を取っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。もう少し掘り下げて、自己危険行動が日常の中でどのように表れるのか、具体的なパターンを考えてみましょう。
例えば、夜遅くまで仕事を続けて、家族との時間や趣味の時間を犠牲にしてしまう。あるいは、昼食の時間を削ってメール対応を続けたり、ご飯を食べながら仕事をしたりする、といった行動です。
また、熱がある・体調が悪いといった状況でも、「仕事が溜まってしまうから」「同僚に迷惑をかけたくないから」と考えて、無理をして出勤する。こうしたケースも含まれます。さらに、疲れている中で過度にカフェインを摂取して、なんとか自分を奮い立たせてがんばるといった行動も見られます。適量のカフェインであれば問題ありませんが、明らかに無理をしているケースですね。
あるいは、睡眠時間を削ってでも仕事を優先する。これも、自己危険行動の一例として挙げることができます。自己危険行動のイメージが少し湧いてきたのではないでしょうか。
この自己危険行動の研究が注目されている背景には、柔軟な働き方、柔軟な勤務形態がもたらす副作用の1つとして位置づけられているという点があります。
柔軟な勤務形態は、基本的には良いことだと思います。ただ、それが実は、予期せぬかたちでマイナスの効果、特に「健康リスクを高めてしまう」という結果を引き起こすケースがあります。そうした事態への警鐘を鳴らすために、この「自己危険行動」という概念が注目されているわけです。働きやすさを促す施策が、皮肉にも健康リスクを高めてしまうということですね。
仕事をする場所や時間を自分で選べる「柔軟な勤務形態」の増加
柔軟な勤務形態といっても、いろいろなかたちがありますが、基本的には、従業員が「仕事をする場所」や「時間」を自分で選べるような働き方や制度を指します。
例えば在宅勤務は、その代表的な例です。自宅でもオフィスでも働くことができる。自宅であれば、慣れ親しんだ環境で仕事ができますし、通勤をしなくて済むという利点もあります。通勤は、特にラッシュアワーの時間帯になると、かなりのストレスになりますよね。また、通勤には時間的な制約もある。
その意味では、こうした制約を取り払って、自分のペースで仕事ができるという点で、在宅勤務は柔軟な働き方の1つといえます。
もう1つは、フレックスタイムをはじめとした、労働時間に関わる柔軟な制度です。フレックスタイム制では、コアタイムがある場合とない場合がありますが、コアタイムを除いた時間帯は、出退勤の時刻をある程度自由に決めることができます。
そうすると、自分のライフスタイルやライフイベントに合わせて、働く時間を調整できるようになります。例えば朝型の人であれば、早めに出勤して、早めに業務を終えるといった働き方もできるかもしれません。
このように労働時間の自由度が広がってくると、子育てや介護といった個々の事情があっても、それに合わせて勤務時間を調整しながら、うまく働くことが可能になります。
その意味では、柔軟な働き方を支援する制度というのは、基本的には非常に意義があるものです。多様な人々の「働く場」を広げ、活躍の可能性を広げていく、重要な制度だといえるでしょう。
他にも、例えばワーケーションも柔軟な働き方の1つとして挙げられるかもしれません。ワーケーションというのは、リゾート地などで、仕事と休暇を組み合わせて働くスタイルのことを指します。リゾート地で働いたり、オンライン会議を行ったりするような働き方ですね。
ワーケーションもフレックスタイム制や在宅勤務も、いずれも従業員にとって働きやすい環境を提供するものです。ワークライフバランスを向上させるきっかけにもなり得る、非常に重要な制度だと考えられます。
柔軟な働き方の人のほうが仕事に対する熱意が高い
実際に、柔軟な勤務形態で働いている従業員と、それ以外の従業員を比較すると、柔軟な勤務形態で働く人のほうが、仕事に対する熱意が高いことが明らかになっています。つまり、エンゲージメントが高くなる傾向があるということです。
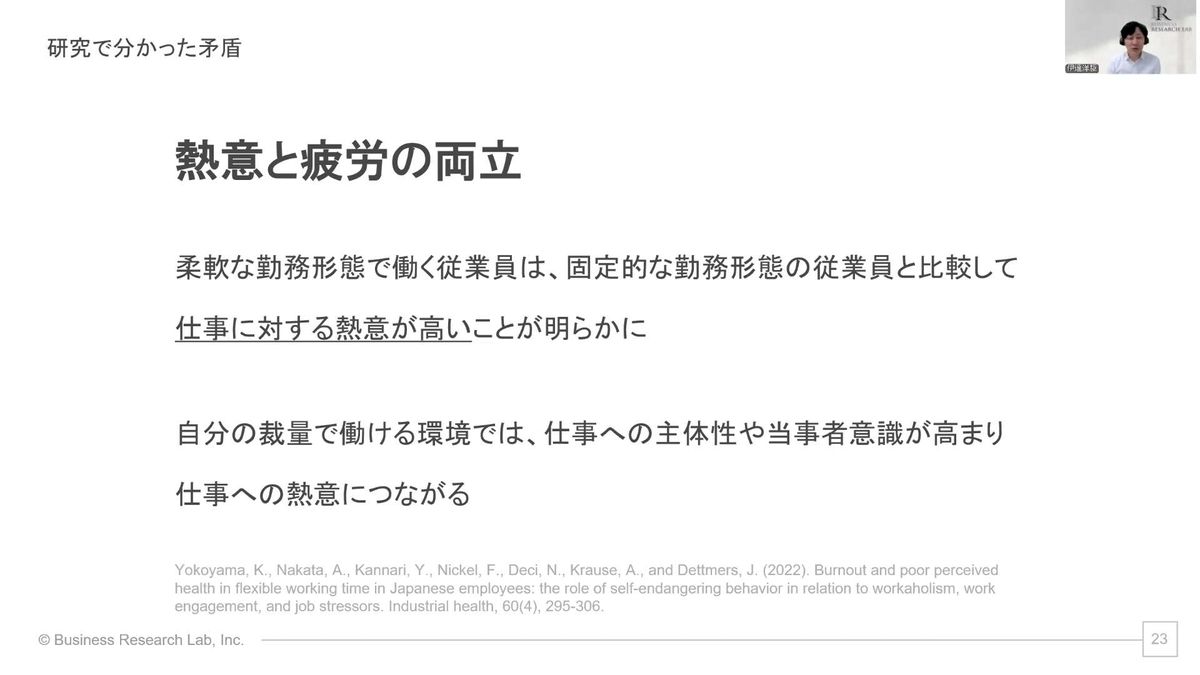
なぜかというと、自分の裁量で働けるからです。自律性の高い環境にあると、人は仕事に対して主体性を持ちやすくなりますし、当事者意識も生まれます。その結果、仕事に熱意を持って、没頭して取り組むことができるようになるわけです。そういった意味でも、柔軟な勤務環境は熱意を高める要因になり得ます。
ただその一方で、少し考えさせられる結果もあります。柔軟な働き方をしている従業員は、それ以外の従業員と比べて、疲労感が高い傾向があるんですね。また、自己危険行動の発生率も高いということが明らかになっています。
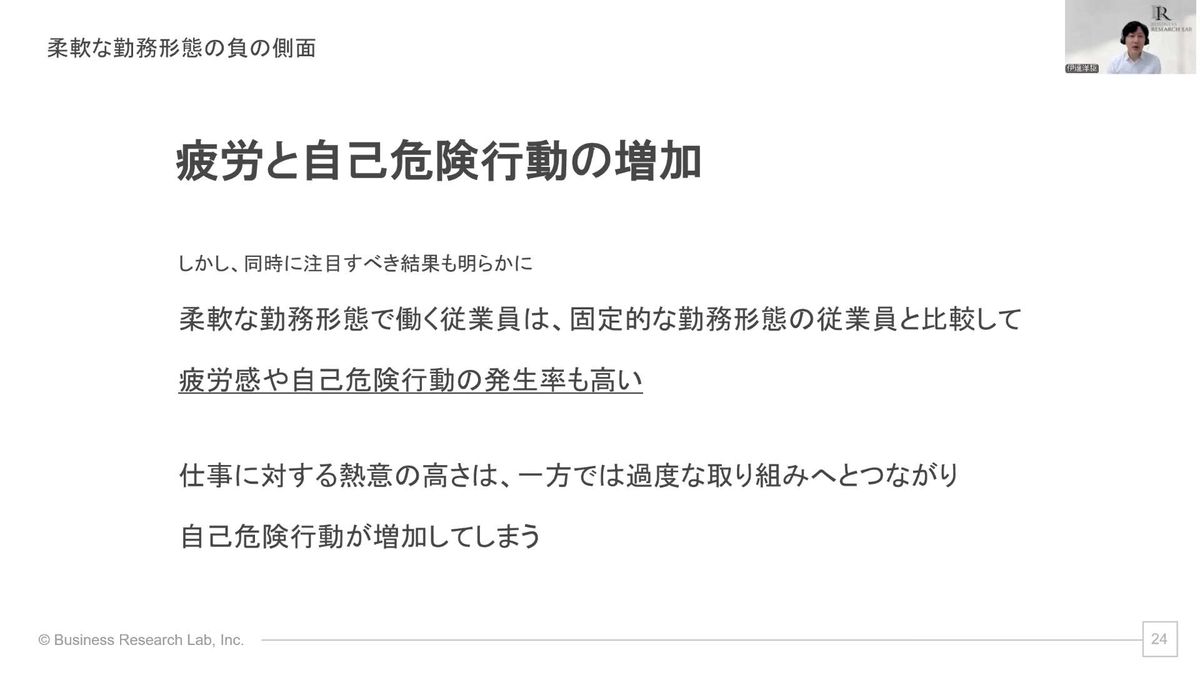
ここは先ほどの話ともつながってくる部分ですが、仕事に対する熱意が高いからこそ、過剰にがんばりすぎてしまい、結果的に疲れてしまう。柔軟性があるからこそ、裁量を持って働けるわけですが、その裁量のもとで働きすぎてしまう傾向が出てくる。
つまり、仕事への熱意が生まれる一方で、過剰に責任を抱えてしまい、健康リスクを伴うような働き方につながってしまう。そして結果として、疲労感を覚えることも多くなるといった実態が明らかになっているのです。
自律性の良い側面と難しい側面
そして、もう1つ考えさせられる研究があります。労働時間の自律性に関する研究です。さきほど触れたフレックスタイム制などは、まさに労働時間の自律性を確保する取り組みですが、この自律性が高い従業員ほど、仕事の過負荷による悪影響が顕著に表れることがわかっているんですね。
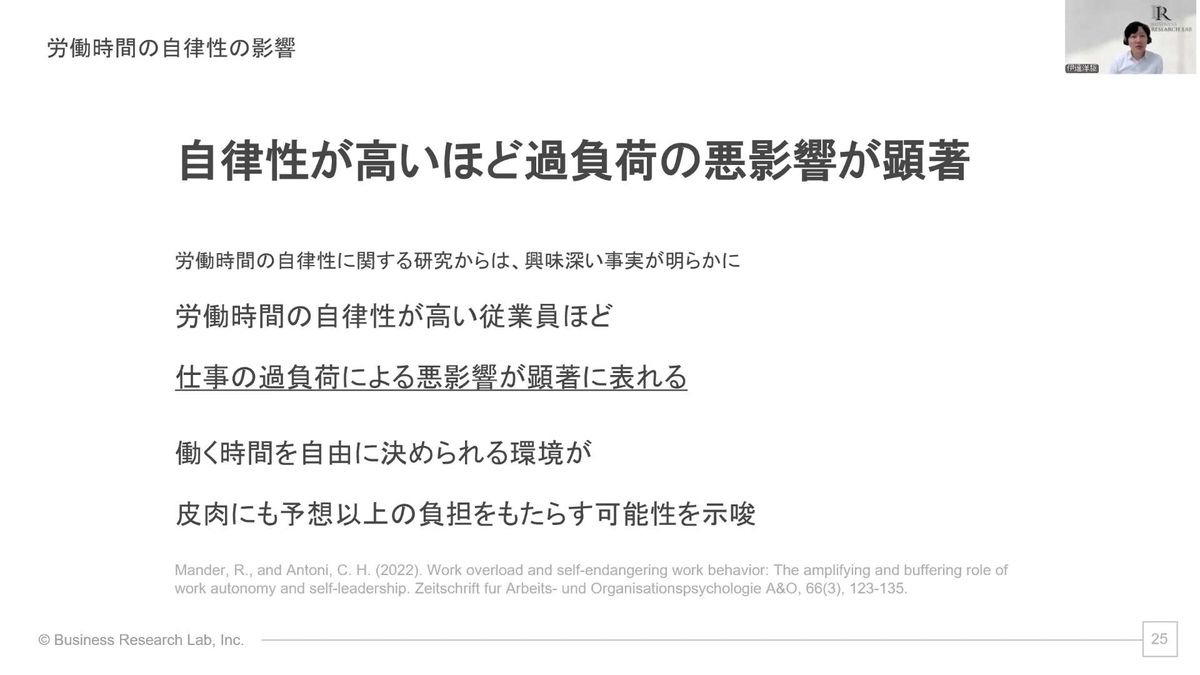
これはどういうことかというと、仕事が多いと人は当然疲れますし、大変になりますよね。この「仕事が多いことによる疲れやすさ、大変さ」といった悪影響が、労働時間の自律性が高い人ほど強く出てしまう、ということなんです。なぜかというと、がんばりすぎてしまうからです。一言で言えば、そういうことになります。
例えば、ある程度決まった時間で働くような環境であれば、仕事が多くても「今日はここまで」と区切りをつけて終えることができますよね。18時に終わると決まっていれば、どこかで割り切って仕事を終えることができます。
でも、自分で時間をコントロールできるような働き方だと、「もう少しやっておこう」とか、「ここで終えるのは無責任なんじゃないか」といった気持ちが生まれて、想定以上に働いてしまう。その結果、負担が大きくなるという傾向があることが明らかになっています。
自律性というのは、良い側面と難しい側面の両方があります。主体的に仕事に取り組める、熱意が高まるといった良い面がある一方で、仕事が多い時には、自分で抱え込みすぎてしまう可能性もある。そして、疲労につながり、自己危険行動を引き起こすリスクにもなってしまうわけです。
柔軟な勤務環境が無理を生む背景にある“心理的圧力”
柔軟な働き方というのは、まとめると、従業員に「自由度」を与える制度です。仕事の進め方、働く場所、働く時間に対して自由がある。
ただし、その自由は「がんばれる環境」をつくる一方で、「責任感を強く意識させる要因」にもなり得ます。例えば、「自分で時間を決められるのだから、ちゃんと結果を出さなければいけない」という心理が働いてしまう。
その結果、必要以上に仕事を抱え込み、余裕がなくなってしまう。いわゆる「あっぷあっぷ」になって、心身の限界を迎えるようなリスクにもつながりかねないのです。これは、なかなか考えさせられる結果だと思います。
例えば、柔軟な働き方によって無理をしてしまうケースをいくつか挙げてみましょう。まず、在宅勤務で通勤が不要になったことで、本来ならその時間を休息にあてられるはずが、逆に「その分も仕事にあててしまう」といった、がんばりすぎのケースがあります。
また、フレックスタイム制で好きな時間に働けるはずなのに、なぜか残業が増えてしまうというケースもあります。夜遅くまで仕事を続けてしまい、結果として勤務時間が長くなっている。フレックスタイム制であっても残業は発生しますから、「自由に働けるはずなのに、なぜか負担が増えている」という状況です。
さらに、「自分の裁量で働けるんだから、成果を出さなければ」とプレッシャーを感じて、周囲の期待に応えようとして、ますます無理をしてしまうといったケースもあります。
このように、柔軟な働き方は、ワークライフバランスの向上や、裁量の広がりによって主体性を引き出す一方で、無理をさせてしまうリスクもあるということが、さまざまな研究から明らかになってきています。
 PR
PR