株式会社ニジボックス主催の『UI UX Camp! 2025』に、ユーザビリティの先駆者であり、UX分野で41年の経験を持つ専門家であるヤコブ・ニールセン氏が登壇。「UXのこれまで、現在、そしてこれから」というテーマで、IT分野に携わるビジネスパーソン向けに講演を行いました。講演の最後には参加者からの質問に答え、エールを贈りました。パイオニア的存在が提唱する「10のユーザビリティの理論」と、UI UXの未来展望とは?
ユーザビリティの原則、認識は記憶よりも頼れる
ヤコブ・ニールセン氏(以下、ニールセン):それでは「ユーザビリティの原則」について少しお話ししたいので、動画をお見せしたいと思います。2分しかない短い映像ですが、私の10のユーザビリティの理論の1つを紹介します。再生してください。
(動画開始)
動画音声:ヤコブ・ニールセンの10のルール。Webを使いやすくするツール!

大声で言おう。「認識」は記憶よりも頼れるぞ! 覚えさせるのはやめにして、見える選択肢を示そうね。記憶はすぐに消えていく。ヒントをくれたら助かるよ!

メニューとアイコン、明るくハッキリ。選ぶのが楽しくなるように、難解コマンドいらないよ。クリックひとつで動けばOK!
オートコンプリート、君の味方。少し打てば、導いてくれる。もう迷わない、苦労しない。認識こそが成功のカギ!
Amazonは賢い、わかってる。「一緒に購入」ヒントになる。何も見えない検索じゃなく、認識あれば買い物楽々!
必要なヒントをちゃんと配置。ユーザーの声を無視しない。知識は頭じゃなく世界に。UI広がり、進化する。
だからシンプル、わかりやすく。ユーザー助けるデザインに! もう迷わない、足止めなし。認識こそ最強だ!
(動画終了)
ニールセン:このビデオをお見せしたい理由は2つあります。1つ目は、メディアタイプをある形式から別の形式に変換することを可能にするという、AIの興味深い点の1つを示すことです。
もちろん私はこれらの原則について書いてきましたが、曲は作っていません(笑)。しかしAIに原則についての曲を作るように指示したり、ホッキョクグマのアニメーションを作るように指示したり、作らせたりすることができます。
将来的にマルチメディア・エクスペリエンスは、はるかに興味深いマルチモーダルになることについて考えることが重要です。なぜならこれらすべての異なるモダリティ、異なるメディアタイプは、AIによって相互に変換できるからです。
AIは読解力のレベルに関係なく理解できるように変換する
ニールセン:私たちが実行できる非常に実用的なことの1つは、さまざまな難易度で情報を提示できることです。非常に高い読解力を持つ人、読み書きが堪能な人、高度な教育を受けた人、とても賢い人など、かなり難しい情報でも理解できる人がいます。
ユーザビリティに関する問題が発生する理由として多く挙げられるのは、デザインプロジェクトを行う人が難しい情報を理解できる傾向にあることです。大企業のプログラマーや上位管理職には、高度な教育を受けて複雑な情報を扱うことが得意でないとなれません。彼らは情報を見て「十分簡単だ」と思うでしょう。
多くの人は読むのが得意でなく、高度な教育を受けておらず、複雑な情報を扱うのに慣れていません。AIは自動的に情報の難易度を異なるレベルに変換し、その人に適したレベルで提示することができます。
これは特に医療分野、ヘルスケアにおいて重要です。医師や医療専門家が患者と話す時、彼らは高度な教育を受け複雑な医学文献を多く読みかなり難しい情報でも理解できますが、必ずしもその診断内容や患者が何をすべきかをわかりやすく説明するのが得意とは限らないからです。
しかしAIは、これらの指示を読解力のレベルに関係なく理解できるものに変換することができます。つまり、AIによる情報の変換は非常に重要な用途の一つなのです。
これが私が「高度なAIの利用」と呼ぶものです。シンプルなAIの使い方は、「質問をして、答えを得る」ことですが、高度な使い方とは、情報を異なるメディア形式や説明レベルに変換することなどを考慮することです。
ユーザビリティの原則、認識は想起よりも優れている
ニールセン:さて、私がシロクマの歌をお見せした2つ目の理由ですが、これは私が30年以上前に書いた「ユーザビリティの原則」の一例を示すものであり、今でもその原則が有効だからです。
なぜ今日でも当てはまるのかというと、シロクマが言っていたように「私の記憶は短いし、すぐに消えてしまう」からです。記憶力が悪いのはクマだけではありません(笑)。人間全体に当てはまることであり、実は人間のほうが深刻です。

実際に、人間は多くの情報を覚えておくのが苦手です。ワークフローを進める中で、前の画面で見た情報を忘れてしまうことがよくあります。だからこそ、「認識(Recognition)は想起(Recall)よりも優れている」のです。情報を思い出させるのではなく、見て認識できるようにするべきです。
これは私の「ユーザビリティの10原則」の1つとして30年以上前から存在し、UXを向上させるために今日でも有効なアドバイスです。なぜなら人間は賢くなることはなく、10年後も50年後も記憶力は悪いままだからです(笑)。脳は今後も同じタイプのままですし、30年前でも将来でも記憶力は同じでしょう。
時々、「10の理論を現代版にアップデートしたいか?」と聞かれることがありますが、私の答えは「いいえ」です。なぜなら、これらの原則は人間に関するものだからです。
つまり、コンピューターと人間がうまく連携できるようにする方法についての原則ですが、実際には「コンピューターをどのように変えて、人間に適応させるか」が問題なのです。
人間を変えることはできず、人類は同じ人類のままです。人間に合わせてデザインしなければならないというのが、私の基本的な考え方の1つです。人々に変化を求めてはいけないということです。
何かを議論する時に、あるものが難しすぎるというと「もっと良いトレーニングや研修が必要だ」「もっと良いマニュアルと説明が必要だ」と言うことがあります。
しかし経験上、人はマニュアルを読みたがりませんし、トレーニングを受けるのは費用がかかります。そもそも人間がコンピューターに適応して変化するのではなく、コンピューターが人間に適応して変化すべきなのです。
だからこそ「ユーザビリティの原則」は、コンピューターを人間にとって使いやすくする方法を示しているのです。これらの原則は今も30年前も同じで、30年後も変わらないでしょう。
ですので、ユーザビリティの原則を学ぶことは、非常に高い費用対効果があります。人間に関するものであり、人間の脳が変わらない以上、不変であり続けると見込まれるからです。
AIによって「パンケーキ現象」が起きる
ニールセン:一方、多くのテクノロジーは非常に急速に変化します。特にAIのような分野では進化のスピードが速すぎて、今日「この製品がおすすめだよ」とすら言えません。もっと良い新製品が現れて、来週には間違ったアドバイスになっているかもしれませんから(笑)。しかし人間と、人間との関わり方に関する原則は変わりません。
人工知能によって変化していることの1つは、すでに述べたとおり「生産性の向上」です。多くの研究が示しているとおり、AIは人々の作業効率を高め、同じ人間がより多くの仕事をこなせるようになります。
つまり以前はもっと大きなチームが必要でしたが、より小さなチームで作業できるようになります。10人のチームで20人分の仕事をこなせるようになるということです。結果として、話し合いをして混乱する人数も少なくて済むし、全員が正しく調整されているかを確認するために、多くのレベルの管理職を置く必要もありません。
私はこれを「パンケーキ」と呼んでいます。大きなケーキではなく平らなケーキなので、管理職の階層が減り、より効率的なチーム、より小さなチームになります。この変化はUXにおいても非常に重要だと考えます。
少数の非常に優れたUX専門家が、大規模で混乱しがちなチームよりも多くの成果を生み出せるようになるからです。かつては残念ながら常にリソースや予算不足に悩まされてきましたが、将来的には少人数でより多くのことができるようになり、はるかに良くなるでしょう。
ただし、1つ懸念していることがあります。それは、これまでのAIの経験から、AIが特に「プログラマーや開発者の生産性を向上させることに優れている」という点です。現在のAIが最も得意とするのは、プログラマーや開発者の支援です。

もちろんこれはすばらしいことです。彼らがより多くの仕事をこなせるようになれば、より多くのソフトウェアが生まれ、UXに優れた人々がそれらをより良くしていく仕事も増えるでしょう。開発者の仕事がより効率的になるのは良いことです。
「超スーパーギーク」と働く覚悟はあるか
ニールセン:しかし1つ心配なのは、すでにソフトウェア開発において、技術面と人間側……つまり私たちUXやデザインの側との間に、少しミスマッチが生じていることです。
もし開発者が今よりもはるかに優秀になり、私たちがわずかしか成長できなかったとしたら、彼らの支配力が今よりもさらに強くなってしまうかもしれません。それが私の懸念です。
私たちにできる唯一のことは、この状況を認識することです。つまり、私たちはこれから「スーパー開発者」、つまりかつてないほど優秀になる「超スーパーギーク」と一緒に働くことになるのです。それは、私たち自身も過去よりはるかに優れた存在にならなければならないということを意味します。
そうすれば、両者は間違いなく協力しあうことができる。これが唯一の解決策です。私たちが何かを成し遂げるには、異なる分野の人々と協力するしかありませんが、私たちが置き去りにされるような状況にはしてはいけません。
これまでのところ、AIは大きな革命をもたらし、多くのすばらしいことを実現してきました。しかし、それは技術に支配されすぎていて、デザインの影響力があまりにも小さかったのです。
これは、AIが研究、科学、工学の分野から生まれたためでもあります。AIを発明した天才たちには大いに敬意を表しますが、彼らはユーザビリティの専門家ではなく、人間の視点を十分に理解していませんでした。
そして、これは私たちの責任でもあります。デザインコミュニティは眠っていて、AI製品をより人間に適したものにするために積極的に関与してこなかったのです。
私の考えでは、今後AIがますます普及していくことは確実ですが、それはAIが使いやすく、人間のニーズをより良く満たし、組織の中で適切に機能する場合に限られます。こうした課題はすべて人間に関係する問題であり、ユーザビリティの課題であり、私たちがより良くデザインしなければならない領域なのです。
「AIを学び、使いこなし、改善する」挑戦をしよう
ニールセン:ですから、これはみなさんへの挑戦です。AIを真に受け入れてください。そうでなければ、エンジニアたちは私たちを圧倒してしまうでしょう。彼らは私たちよりもはるかに効率的ですから。これがまず1つ。

第2に、私たちはAIをより良いものにしなければなりません。そうでなければ、AIはその潜在能力を十分に発揮できないでしょう。AIにはすばらしい可能性がありますが、それが実現されるのは、人間のことを忘れず、人の要素を考慮し、ユーザビリティやユーザーエクスペリエンスを重視する場合に限られます。
そして、それをうまくできるのは私たちだけです。我々にはそれを実行するだけの特別な専門知識があるからです。だからこそ、私がみなさんに課す挑戦は「AIを学び、使いこなし、改善すること」です。ありがとうございました。
西村真里子氏(以下、西村):本当にありがとうございました、ヤコブさん! すばらしかったです。私もたくさんのメモを取りました。では、ここからは質問の時間にしたいと思います。
それではとても刺激的なお話がありましたけれども、ここからは会場から質問を受けたいと思います。これは直接聞きたいという方、挙手いただけますでしょうか。
(会場挙手)
ではヤコブさん、今1人の女性が手を挙げたので、彼女が質問をしますね。
AIによって企業はUXデザイナーの数を減らすのでは?
質問者1:ニールセン先生、非常に有益な講演をありがとうございました。あなたのスピーチを聞けることを大変光栄に思います。私の質問は、デザイナーの効率性についてです。プレゼンテーションの中で「小規模なチームでも、これまでより多くのことを生み出せる」とおっしゃっていましたよね。
それを聞いて少し心配になったのですが、つまり、企業はUXデザイナーの数を減らすようになるのではないでしょうか。もっと効率的になるためにはどうすればいいでしょう。AI技術を活用することが重要なのか、それともほかに効率を上げる方法があるのか、お聞きしたいです。
ニールセン:とても良い質問ですね。もし狭い視点で、または具体的に考えれば、将来的に同じものをデザインするのに必要な人数は、AIの助けを借りることで半分になるかもしれません。
しかし、それは残り半分の人が不要になるという意味ではありません。私は実際には、将来的に今の倍以上のデザイン作業をすることになると考えています。
先ほども言いましたが、AIが最も有用なのは実はソフトウェア開発者です。彼らはもっともっとたくさんのソフトウェアを生み出すことができます。
私はこれまでのキャリアの中でずっと「プログラマーやソフトウェア開発者が少なすぎる」という話を聞いてきました。「大学は十分な数のソフトウェアエンジニアを育成していない」と、新聞でも40年以上の間、毎年同じ見出しが載っています。
しかし、今は違います。AIの支援を受けることで、開発者は以前よりもはるかに多くのソフトウェアを作ることができます。ソフトウェアのコストは下がり、それがより多くの用途で使われるようになります。
つまり、ソフトウェア製品がもっとたくさん出てくるでしょう。それはモバイルアプリやWebサイト、あるいは今はまだ存在しない、まったく新しいものかもしれません。しかしソフトウェアの数が増えれば、それに伴いデザインの必要性も増えるのです。
UXデザインの必要性はAI革命時代にさらに増していく
ニールセン:仮にソフトウェアの数が2倍になったとしましょう。それでデザインの仕事が2倍になるとは限りません。現在のUXの品質はまだ十分ではなく、人間のニーズを満たすレベルに達していません。私は、むしろ5倍以上のUXデザインが必要になると思います。
10年後にソフトウェアの量が2倍になったとして、それをより高品質にするために5倍のUXデザインが必要になるなら、10倍のUX作業が必要だという計算になります。
つまり、たとえ1人のUXデザイナーが2倍、3倍の生産性を発揮できるようになったとしても、UXの人材はもっと必要になると思います。10年後には4倍、5倍の作業ができるかもしれませんが、それでも少なくとも今の2倍、実際にはそれ以上のUXデザイナーが必要になると思います。
とにかくこの質問に対する私の答えは、エンジニアの同僚がより効率的に働けるようになることで、さらに多くのUX人材が必要になるということです。
またUXの高品質化も求められます。なぜなら、世界はますます知識志向にシフトしていき、人々は扱いにくいものや難しいものに苦労することを、ますます受け入れなくなっていくでしょう。
難しすぎるものに対応しなくてはならないがゆえに、高品質のソフトウェアと高品質のデザイン、そしてそれを実現できる人材、つまり効率性に対する需要は増え続けるでしょう。生産性の向上で、より少ないスタッフで済むようになるとはまったく思いません。私たちは全員、将来やるべきことがたくさんあると思いますよ。
質問者1:ありがとうございます。明るい未来が見えました。私も学び続けようと思います。
西村:ありがとうございます。
グローバル展開におけるユーザー調査の重要性
西村:では、次の質問を受け付けます。
(会場挙手)
質問者2:講演ありがとうございました。私はプロダクトマネージャーをしています。質問ですが、日本から海外市場へビジネスを拡大することを考えた場合、文化の違いを考慮する必要があると思います。
先ほどのお話の中で「認識は想起よりも優れている」という原則についても触れられていましたが、グローバル展開を成功させるために、特に注意すべき点について、もう少し詳しく教えていただけますか?
ニールセン:これもまたすばらしい質問ですね。考慮すべきことは3つあります。1つ目は、先ほどお話しした「認識は想起に勝る」のようなユーザビリティの原則です。
これは、基本的にどの国でも同じです。人体の構造は生物学的にほとんど同じで、脳もまた然り。どの国の人も記憶力には大差ないということです。したがって、ある国で使いやすいものはどこでも使いやすいのです。
しかし、ほかに重要な問題が2つあります。1つはもちろん言語で、翻訳の支援があるのでこれは比較的解決しやすいでしょう。例えば、過去には多くの国でユーザーテストを実施するには非常に高額な費用がかかりましたが、今ではAIの助けを借りることで大幅に安く済むので、利用すべきです。
3つ目の問題は、おっしゃるとおり絶対的な文化の違いがあるということです。あらゆる地域で人々の価値観やビジネスのやり方の好みが異なり、1つのガイドラインを示すことは不可能です。唯一の手掛かりは、それを真実として受け入れ研究することです。
ユーザー調査についての質問に戻ると、単語の純粋な翻訳では文化を翻訳していることにはなりません。それは最初のステップでする必要はありますが、それだけでは完全ではなく、不十分です。
そのため、各国の顧客またはユーザーの調査も行う必要があります。幸い、現在ではインターネットのおかげで、リモートでの調査が容易になりました。私はシリコンバレーから東京のみなさんに向けて話していますが、問題なく機能していますよね。
同じようにユーザー調査をオンラインで行い、必要に応じて翻訳を活用すれば、どこにも移動することなく、かつてのような高いコストを払わずともうまくいく可能性があります。
国際的なユーザー調査がより大事だというのが私からの唯一のアドバイスです。文化的な違いは認識できますが、調査を行わない限り、それが実際に何であるか知ることはできません。
質問者2:ユーザー調査がカギということですね。よくわかりました、ありがとうございます。
日本人は美しさなどの文化的価値を維持してほしい
西村:それでは、まだまだ質問を受けたいんですけれども、お時間になりましたのでここらへんで終了とさせていただきたいと思います。ヤコブさん、本当にありがとうございました。最後に、日本の聴衆に向けて、一言メッセージをお願いします。
ニールセン:日本は多くの点で世界的に有名だと思いますが、中でも注目すべきは品質と細部へのこだわり、そしてすばらしいデザインを生み出すことです。もちろんこれは千年もの間、常に重要であり続けましたが、これからの時代はますます重要になるでしょう。
エンジニアや開発者が扱うAIの美点は、生産性を向上させ、より多くの製品を生み出せるようにしてくれるところにあります。これはすばらしいことですが、品質や洗練度合い、美しさといった要素が取り残されています。
みなさんが特別な技術を持っているのはこの部分だと思いますが、だからこそ日本の伝統である品質と細部へのこだわりを守り続けるという、人類全体にとっての特別な義務も負っているのです。
細部を大切にすることはUXにとって非常に重要であり、ほんの少しでも間違えると全体が不快なものになってしまいます。
ですから私からみなさんへのメッセージは、その文化的価値を維持してほしいということです。これから先の未来には、それがますます重要になってくるでしょうから。
西村:ヤコブさん、どうもありがとうございました。みなさん、ぜひ拍手を送っていただけますでしょうか。
(会場拍手)
ニールセン:ありがとうございました。
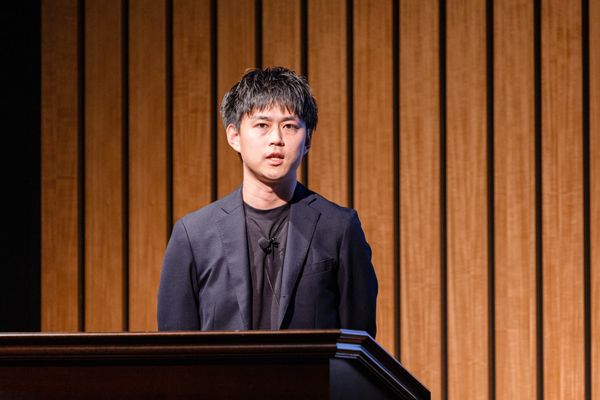 PR
PR
























