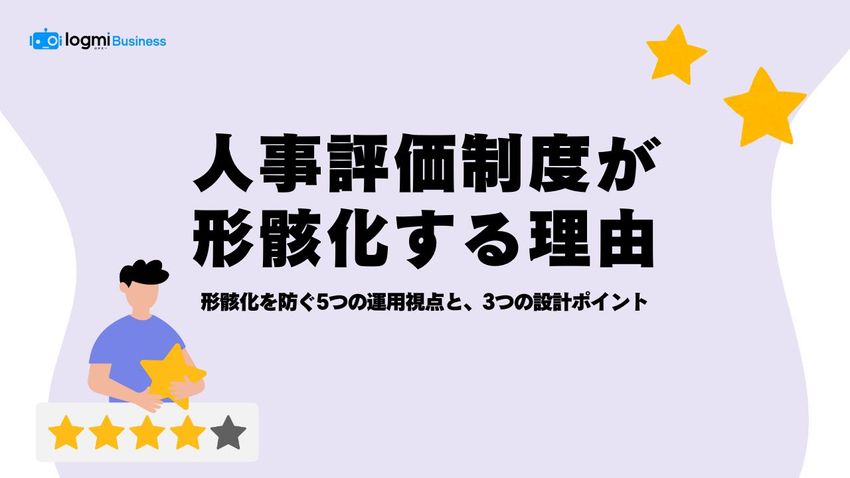【3行要約】
・ 人事評価制度は時間とコストをかけて構築しても形骸化しやすく、多くの企業が運用面での課題を抱えています。
・株式会社PDCAの宮地氏や白潟総合研究所株式会社の白潟氏らは、制度の複雑化より評価者の信頼性と面談の質が重要であり、納得感を高める必要があると指摘します。
・ 効果的な人事評価制度には「ポリシーの明確化」「わかりやすさ」「浸透へのコミュニケーション」が必須で、経営戦略と連動させることが組織成長のカギです。
なぜ人事評価制度は形骸化してしまうのか?
時間とコストをかけて構築した人事評価制度が、いつの間にか形骸化してしまうという問題に直面する企業は少なくありません。この形骸化の根本的な原因は、制度そのものの設計にある場合もありますが、それ以上に「運用」の側面に潜んでいることもあります。
株式会社PDCAの学校の宮地尚貴氏は、どんなに優れた仕組みを導入しても、それを運用する評価者、特に管理職層が制度の意図や目的を深く理解していなければ、良い仕組みも機能しないと指摘しています。例えば、評価基準が曖昧なままでは、評価は評価者の主観や直近の印象に左右されがちです。「なんとなく」の評価は、部下の納得感を得られず、「上司の好き嫌いで評価されている」といった不信感を生む温床となります。
また、多くの企業では、評価面談の頻度が年1〜2回に留まっています。これでは上司が部下の1年間の働きぶりを正確に把握し、納得感のあるフィードバックを行うことは極めて困難です。結果として、面談は直近の成果や失敗に偏った「印象評価」になりやすく、部下が1年を通じて行ってきたプロセスや地道な努力が見過ごされがちになります。
「数値で成果が判断できる目標以外の取り組みや成果は評価されない」といった不満は、まさにこうした運用上の課題から生じているのです。
人事評価制度の形骸化を防ぐためには、制度の見直しも重要ですが、まずは評価者の意識とスキルに焦点を当て、運用を改善していくことが第一歩となります。
約7割が不満を抱える人事評価面談の実態
人事評価制度の運用において、中心的な役割を果たすのが評価面談です。しかしその実態は、多くの従業員にとって満足のいくものではないようです。
株式会社PDCAの学校の宮地尚貴氏が紹介した、jinjer株式会社の調査によれば、自社の人事評価面談に対して「とても満足している」と回答したのはわずか6パーセント、「やや満足している」が26パーセントであるのに対し、「とても不満がある」と「やや不満がある」を合わせると、実に67.4パーセントもの従業員が何らかの不満を抱えているという結果が出ています。
これは、企業の9割が年1〜2回しか評価面談を実施していないという状況下でのデータであり、コミュニケーションの頻度と満足度の間には深い関係があることが伺えます。
では、従業員は具体的にどのような点に不満を感じているのでしょうか。その声を集約すると、「何をどう頑張れば、どう評価されるのかが不透明」という1点に集約されます。具体的には、以下のような不満が挙げられています。
- 何を評価されているのかわからない
- 上司の好き嫌いで評価され、客観的な能力評価がない
- 毎回同じ評価しかされず、何が良いのか悪いのかもわからない
- 数値で判断できる目標以外のプロセスや過程がまったく見られない
- 定量的な基準もない中で、面談もなく一方的に評点が通知される
これらの不満の根底にあるのは、評価基準の不明確さと、評価プロセスにおける対話の欠如です。従業員は、一方的な評価結果だけを求めているわけではありません。彼らが本当に求めているのは、自身の働きぶりに対する公正で納得感のある評価と、未来の成長につながる具体的なフィードバックです。
部下が評価面談に求めることを具体的に見ていくと、「納得感のある評価、公正な評価」が筆頭に挙げられると宮地氏は指摘します。それに加えて、「目標達成に向けたアドバイスと、行動改善につながるフィードバック」や「成長実感の確認と承認」といった、自身の成長に直接関わる要素が強く求められています。特に20代の若手社員においては、承認欲求を満たすことも重要な要素とされています。
さらに、キャリアについての対話も極めて重要です。今の業務が自身の将来にどうつながっていくのか、その道筋を上司と共に確認し、意図や意義を理解することで、日々の業務に対するモチベーションは大きく変わってきます。
これらの要素が満たされて初めて、評価面談は単なる査定の場から、部下の成長を支援し、人事評価制度自体も、未来を共に描くための有意義な対話のシステムへと昇華するのです。
評価を無力化させないための5つの視点
人事評価制度の納得感を高めようとする際、多くの企業が評価項目を精緻に作り込むことに注力しがちです。しかし、評価項目を増やして複雑にすればするほど、運用が困難になり、かえって社員からの不満を招くという落とし穴があります。
項目が増えれば評価誤差は大きくなり、公平感が損なわれ、「これとこれ、おかしくないですか?」といった指摘を受けるリスクも高まってしまうのです。
白潟総合研究所株式会社の白潟敏朗氏は、人事評価はあくまで「社員の給与と賞与を決めるための道具」と割り切り、完璧な正確さよりも最低限の納得感と公平感を重視すべきだと提唱しています。では、真に納得感を高めるためには、どこに時間と費用をかけるべきなのでしょうか。その答えは「評価者と評価面談」にあります。どれほど精緻な評価項目を用意しても、部下から信頼されていない評価者が運用すれば、その価値は失われてしまいます。
みなさん、このセリフをご覧いただいていいですか? 部下から「○○マネージャーには評価されたくない」「○○リーダーには評価されたくない」「○○課長には評価されたくない」というセリフが出た瞬間に、1,000万円、500万円をかけた人事評価シートが完全に無力になってしまうんですね。
なので、まずは各評価者が部下から信頼を得ているかどうか。これは、先ほどモチベーションが下がるところでもご紹介しました。あと、部下から尊敬されているかどうか。尊敬されていない人が評価すると、「あの人に評価されたくない」とやはり言われてしまいます。
引用:「部下から信頼されていない評価者」は人事評価シートを無力化させる 社員の納得感を高める「評価者の評価」5項目(ログミーBusiness)
この言葉が示すように、評価の納得度の根幹をなすのは、評価者自身の信頼性です。部下が「この人に評価されるなら納得できる」と感じられるかどうかが、制度全体の成否を分けることになります。
そこで、評価者に評価権を与える前に、その適性を評価する仕組みを導入することが極めて重要になります。白潟氏によると、具体的には以下の5つの項目について、評価者自身が「YES」と答えられるかどうかをアセスメントすることが推奨されます。
- 全員の部下から信頼されていますか?
- 全員の部下から尊敬されていますか?
- 個人で成果を出す力がありますか?
- 全員のメンバーの日頃の仕事ぶりをしっかり見て記録していますか?
- 人事評価シートをつける時に適切に評価していますか?(評価誤差がないか)
これらの項目をクリアした人物にのみ評価権を与えることで、部下の納得感は劇的に高まります。極論すれば、これらの条件を満たした上司であれば、精緻な評価項目がなくても、部下は評価を受け入れるでしょう。評価者自身が部下から信頼され、尊敬される存在であるかを見つめ直すことも、人事評価制度を機能させるためには重要な事項です。
 PR
PR