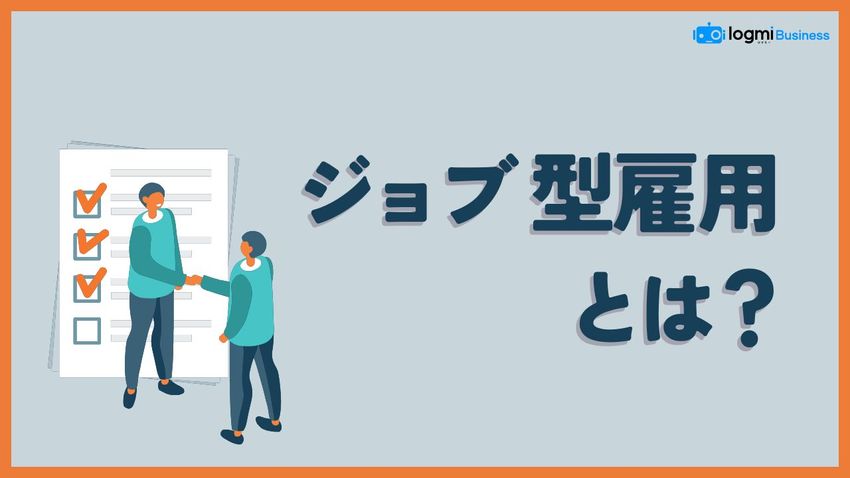ジョブ型雇用への移行で変化する管理職の役割
ジョブ型人事制度への移行は、従業員一人ひとりの働き方だけでなく、管理職であるマネージャーの役割にも大きな変革を迫ります。従来のメンバーシップ型雇用では、マネージャーの役割は、経験や勘に頼った我流のマネジメントが許容される側面がありましたが、ジョブ型ではより専門的で体系的な「ピープルマネジメント」のスキルが不可欠となります。
パナソニック コネクトではこの変革に対応するため、約1,400人のマネージャーに対して30時間にも及ぶ研修を実施したと言います。これは、ジョブ型への移行が単なる制度変更ではなく、マネジメント層の意識と行動の変革を伴う大がかりなプロジェクトであることを示唆しています。
西洋諸国では、ピープルマネジメントはラインマネージャーが担うべき中核的な業務として明確に位置づけられています。
青山学院大学教授の須田敏子氏は、その具体的な役割をいくつか挙げています。まず、採用や配置の権限です。欠員が出た際や新しいポジションが生まれた際に、どのような人材が必要かを定義し、採用プロセスを主導するのはラインマネージャーの仕事です。そして、ジョブ型人事の根幹をなすジョブディスクリプション(JD)の作成と更新も、マネージャーの重要な責務となります。
須田氏はこの点について、次のように具体的に解説しています。
ビジネス戦略が大きく変わったり、組織構造が大きく変わって、グレード構造が変わるという時には、人事と一緒になってJDを作ったりするんですけれども。日々のJDの書き直しは常にラインマネージャーが行っていきます。
例えば、目標設定。目標面談をして新しい目標が設定されると、JDの書き直しとなります。例えば、営業で年間の売上目標が3,000万円だった人が4,000万円になったとすると、JD書き直しとなります。あるいは、育児休業を取っている人がいて、ほかの職場の同僚3人が、その人の仕事を分担してあげたとしたら、当然JD書き直しですね。
引用:「なんとなく」の採用や人事が通用しなくなる ジョブ型で変わる管理職の役割(ログミーBusiness)
このように、JDは一度作ったら終わりではなく、目標の変化や業務分担の変更といった日々の業務実態に合わせて、常に最新の状態に保たれる必要があります。そしてJDが更新されれば、それに応じて報酬も見直されます。これにより、従業員は自身の貢献が正当に評価・処遇されているという納得感を得ることができます。
これまでのように「なんとなく採用し、年功序列で人事を決める」といった曖昧なマネジメントは通用しなくなります。一人ひとりの部下と向き合い、その役割と貢献を明確に定義し、公正に評価する。ジョブ型社会の管理職には、人事のプロフェッショナルとして、より戦略的で高度なスキルが求められるようになるのです。
ジョブ型雇用の導入において重要になる「のりしろ」概念
ジョブ型雇用の導入にあたって、多くの企業が懸念するのが、従業員の意識が「自分の仕事だけやっていればいい」という方向に傾いてしまうことです。
職務記述書によって仕事の範囲が明確に定義されることは、責任の所在を明らかにする一方で、役割間の連携を阻害し、組織全体のパフォーマンスを低下させるリスクをはらんでいます。いわゆる「サイロ化」やセクショナリズムを助長し、誰も拾わない「グレーゾーン」の業務が発生しやすくなるのです。
この課題に対し、立教大学 経営学部 助教の田中聡氏は、役割間にあえて重なり部分を作る「のりしろ」という概念の重要性を提唱しています。「のりしろ」とは、自分の役割と他者の役割が接する境界領域を指します。この部分を意図的に設けることで、従業員は自分の仕事だけでなく、隣接する他者の仕事にも関心を持つようになります。これは、単なる業務の重複を意味するのではなく、チーム全体の目標達成に向けて、互いの仕事がどのように連携しているのかを俯瞰的に捉える「メタ認知」を促すための仕掛けです。
立教大学のビジネス・リーダーシップ・プログラム(BLP)での学生たちのチームワーキングの例を見ても、最初に役割分担を厳密にしすぎたチームは、かえって成果を出せない傾向があったと言います。これは各々が自分のタスクをこなすことに終始し、最終的なアウトプットを統合する段階で齟齬が生じてしまうためです。
逆に、分担はしつつも互いの進捗に関心を持ち、助け合う「のりしろ」をうまく機能させたチームが高い成果を上げていました。
この「のりしろ」を効果的に機能させるためには、チーム全体で「自分たちが今どこに向かっているのか」という目的・目標を常に共有し続けることが不可欠です。
多くの職場の定例会議が単なる個々の進捗報告の場に終始してしまいがちなのは、この共有が欠けているからです。目的が共有されていれば、「自分の仕事」と「あなたの仕事」が、より大きな目標の中でどのように結びついているのかを意識することができます。
ジョブ型雇用は、個々の専門性を高め、自律性を促す有効な仕組みですが、それが行き過ぎると組織はバラバラになってしまいます。だからこそ、田中氏が指摘するように「どこまでのりしろを残しながらジョブ型にするか」という議論が不可欠なのです。個の専門性とチームとしての協調性を両立させるカギは、この「のりしろ」の設計にあると言えるでしょう。
ジョブ型雇用における企業と個人の関係性
ジョブ型雇用制度への移行は、企業と個人の関係性を根本から変えるものです。その核心は、「キャリアは会社から与えられるものではなく、自ら選び取る時代」への転換にあります。
従来のメンバーシップ型雇用では、企業が従業員のキャリアパスを設計し、定期的な人事異動によってさまざまな経験を積ませるのが一般的でした。しかし、ジョブ型社会では、キャリア形成の主導権は個人に移ります。自分がどのような専門性を身につけ、どのようなポジションを目指すのかを主体的に考え、行動することが求められるのです。
この変化に伴い、企業の役割も大きく変わります。キャリアパスを一方的に「与える」存在から、従業員一人ひとりの自律的なキャリア形成を「サポートする」存在へとシフトしなければなりません。
カゴメ株式会社では、従業員が希望するキャリアをタレントマネジメントシステムに入力し、人事担当者と対話しながらキャリアプランを実現していく仕組みを構築していると、常務執行役員の有沢正人氏は言います。これは会社が旧来的な中央集権型の人事権を手放し、個人の選択を尊重するという姿勢の表れです。企業は社内のさまざまなポジション(ジョブ)に求められるスキルや経験を明示し、従業員がそこに至るための学習機会や挑戦の場を提供することが重要な責務となります。
一方で、ジョブ型への移行が、会社と個人の関係をドライで希薄なものにするわけではありません。むしろ、エンゲージメントの重要性はこれまで以上に高まります。LinikedIn 日本代表の村上臣氏は、ジョブ型と会社へのロイヤリティは両立すると強調します。
まず会社に対してのロイヤリティは、メンバーシップ型でもジョブ型でも変わらないと思います。特にアメリカは、ジョブ型が行き過ぎちゃったがために、むしろ会社と個人の関係をより良くしようとしている。最近では日本のやり方を参考にしていたりするんですよ。会社にいる時は会社を好きになってほしいし、会社もその人のことをすごく考えるのが、今のグローバル企業の標準的なやり方になっている。
だから、ジョブ型になったからといって会社より自分を重視するということでもないですよね。
引用:「昭和型雇用」「進まないキャリア教育」「遅れる社会保障」 日本で“ジョブ型”の働き方が浸透しない3つの理由(ログミーBusiness)
ジョブ型社会では人材の流動性が高まるため、企業は従業員に「選ばれ続ける」努力が求められます。そのためには、公正な評価や報酬制度はもちろんのこと、働きがいや成長実感といった非金銭的な魅力も高めていく必要があります。
また、カゴメ株式会社の事例のように、一度ジョブのミスマッチが起きても、再チャレンジできる「敗者復活」の機会を制度として保障することも、従業員のモチベーションを維持し、安心して挑戦できる文化を醸成する上で不可欠です。ジョブ型雇用を採用することで、企業は自律的なキャリアを目指す個人を全力で支援し、共に成長していくパートナーとしての役割を担っていくことになるのです。
ジョブ型雇用に移行することによる報酬体系の変化
ジョブ型人事制度への移行は、企業の報酬体系に構造的な変化をもたらします。従来のメンバーシップ型雇用における報酬は、年齢や勤続年数といった属人的な要素が大きく影響する「職能給」が中心でした。しかしジョブ型雇用では、その人が就いている「職務(ジョブ)」の価値に基づいて報酬が決定される「職務給」が基本となります。
この職務の価値は社内的な基準だけでなく、社外の労働市場における相場によって大きく左右されます。つまり自社の報酬水準が市場価格に見合っていなければ、優秀な人材はより高い報酬を提示する他社へ流出してしまうリスクが高まるのです。
この変化は、エンジニアのような専門職の給与動向に顕著に表れています。給与の源泉は企業の利益であり、マーケットサイズが大きく利益率の高い事業を展開している企業ほど、高い給与を支払う余力があります。そのため、ジョブ型が浸透すれば、成長産業や高収益企業に人材が集中しやすくなります。
また、報酬のあり方そのものも多様化していきます。月々の給与だけでなく、将来の企業価値向上に連動するストックオプションやRSU(譲渡制限付株式ユニット)といった株式報酬(ストック)の重要性が増していきます。
株式会社レクター 代表取締役の広木大地氏は、ジョブ型社会では「会社と一体となってコミットするための仕組み」が不可欠であり、将来的な企業価値を上げるインセンティブとして株式報酬が有効だと指摘します。従業員が自社の株主となることで、会社の成長が自身の利益に直結するため、日々の業務に対する当事者意識が高まります。これは、短期的な雇用関係になりがちなジョブ型において、従業員のエンゲージメントを維持し、フリーライダーを防ぐための重要なメカニズムとなります。
アメリカの巨大IT企業が報酬の一部として自社株を付与することで、従業員のモチベーションを高め、好循環を生み出しているのはその好例です。日本の報酬体系も、単なる労働対価としての給与から、企業の成長に貢献したことへのリターンという側面を強め、より戦略的で多面的なものへと進化していくことが求められています。
 PR
PR