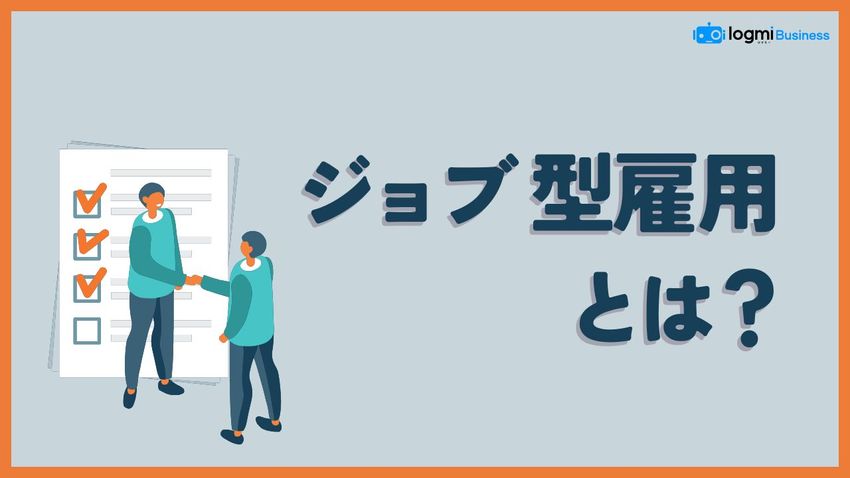【3行要約】
・ジョブ型雇用は単なる職務限定ではなく、人的要件の具体化と共有化を意味します。
・日本でジョブ型が浸透しない三大要因として、 LinkedInやGoogleで採用を見てきた村上氏は「昭和型雇用」「進まないキャリア教育」「遅れる社会保障」の3つを指摘。
・ ジョブ型雇用を導入する際は、カゴメのように自社に合った「日本的ジョブ型」を模索し、役割間の「のりしろ」を設けることで、専門性と協調性の両立を図りましょう。
ジョブ型雇用とは
近年、多くの企業で導入が検討されている「ジョブ型雇用」ですが、この言葉はしばしば表面的な理解にとどまりがちです。一般的には、職務記述書(ジョブディスクリプション)によって仕事の範囲を明確に限定する雇用形態と捉えられていますが、その本質はより深く、人事システム全体の変革を意味します。
青山学院大学教授の須田敏子氏は、これを「ジョブ型人事」という言葉で表現し、その本質を「ジョブを遂行するための知識・スキル・経験・行動など、人的要件が非常に具体化され、見える化して、それが組織内外で共有化されること」だと説明しています。これは単に仕事を区切るのではなく、各ポジションで求められる能力や経験を徹底的に言語化し、透明性を確保する取り組みです。
これまで日本の人事制度は「ヒト型・職人基準」とされ、個人の潜在能力や総合的な経験を重視してきました。これに対し、世界標準のジョブ型は「ジョブ型・職務基準」と対比されますが、須田氏はこの見方を「間違い」だと指摘します。むしろジョブ型人事こそが、人の基準を具体的に突き詰めた「究極のヒト型」であると言うのです。
例えば、テルモ株式会社のジョブディスクリプションを見ると、「職責」といった仕事内容だけでなく、「人的要件」として、そのジョブを担うために必要な職歴や経験、専門知識・スキル、さらには具体的な行動特性(コンピテンシー)までが詳細に定義されています。これは、従来の人事評価で用いられてきた曖昧な「能力」という基準よりも、はるかに具体的で「人」に焦点を当てた基準と言えるでしょう。
ジョブ型人事の導入は、採用活動にも大きな変化をもたらします。ジョブディスクリプションに勤務地や賃金、福利厚生といった条件を明記し、そのポジションに最適な人材を社内外から探すことが標準となります。
重要なのは、このシステムが持つ柔軟性です。日本でよく懸念される「ジョブディスクリプションに書いていないことはやらない」という問題について、須田氏は「やったことを書き直すのが、ライン管理者の主要な仕事になる」と述べています。つまり、ジョブディスクリプションは固定的なものではなく、ビジネスの変化や個人の成長に応じて更新されていく動的なツールなのです。
このように、ジョブ型雇用の本質は、仕事と人の関係を再定義し、透明性と具体性をもって組織全体のパフォーマンスを向上させることにあるのです。
日本でジョブ型雇用が浸透しない理由
日本でジョブ型雇用の導入が叫ばれて久しいですが、その浸透が欧米諸国に比べて遅々として進まないのには、根深い構造的な理由が存在します。
LinikedIn 日本代表の村上臣氏は、その原因を「まだ昭和を引きずっていること」と表現し、3つの主要な要因を挙げています。1つ目が歴史的な背景です。戦後の高度経済成長期において、日本の産業は製造業が中心でした。この時代には、新卒者を一括で大量に採用し、社内のさまざまな部署を経験させながら長期的に育成していく「メンバーシップ型雇用」が非常に効率的に機能しました。この成功体験が今なお多くの企業、特に歴史のある大企業において強固な慣習として残っており、働き方の変革を阻む一因となっています。
2つ目に教育の問題が挙げられます。日本の教育システムでは、学生時代に自身のキャリアについて深く考える「キャリア教育」が十分に行われていないのが現状です。その結果、学生にとって最も身近なキャリアのロールモデルは親世代となります。その親世代の多くはメンバーシップ型雇用が主流だった時代を生きてきたため、その価値観が子ども世代にも無意識のうちに受け継がれてしまいます。
村上氏は、世代を超えて変化していくには20年、30年という時間が必要な過渡期にあると指摘しています。個々人が自律的にキャリアを設計するという意識が社会全体に根づいていないことが、ジョブを基軸とする働き方の浸透を難しくしているのです。
3つ目の理由は、日本の社会保障制度のあり方です。日本では、多くの会社員が年末調整によって納税を完了させるように、本来国が担うべき社会保障の一部を企業が肩代わりしてきました。給与からの天引きというかたちで年金や健康保険料を徴収する仕組みは、効率的なシステムとして機能してきた一方で、個人と国の直接的な結びつきを弱め、企業への依存度を高める結果となりました。
この「企業が個人を保護する」という構造がメンバーシップ型雇用の温床となり、個人が自立してキャリアを選択するジョブ型の考え方とは相容れない側面を持っています。
これら「働き方」「教育」「社会制度」という3つの要素が複雑に絡み合い、相互に影響し合っているため、どれか1つだけを変えようとしても、社会全体のシステムが動かないというジレンマに陥っているのが、日本の現状なのです。
欧米式のジョブ型雇用をそのまま導入するリスク
日本でジョブ型雇用が浸透しない理由として、導入時のリスクがあることも挙げられます。ジョブ型雇用への移行を検討する日本企業が直面する最大の課題の1つは、欧米で主流となっているモデルをそのまま導入することの危険性です。
カゴメ株式会社 常務執行役員の有沢正人氏は、欧米型のジョアプローチを「ジョブディスクリプション至上主義」と呼び、その弊害を警告しています。欧米型のジョブ型は「職務記述書により明確に定義される」「専門性の高い業務を限定的に行う」という特徴を持ちますが、これが機能するのは、労働市場の流動性が極めて高いという前提があるからです。個人が自身の専門性を武器に、より良い条件を求めて企業間を自由に移動できる社会だからこそ、仕事に人を割り当てるという考え方が成り立つのです。
しかし、日本の現状は大きく異なります。まず、教育システムが欧米型ジョブ雇用と合致していません。大学で専門的なスキルを身につけるというよりは、前述したとおり新卒一括採用でポテンシャルのある人材を採用し、入社後にOJTを通じて育成していくのが一般的です。
スキルを持たない新卒者に対して特定のジョブを割り当て、そのジョブがなくなればキャリアが閉ざされるというシステムは、日本の採用・育成慣行とは相容れません。
欧米みたいに労働市場の流通性が極めて高いところであれば、これでもいいわけです。自分の持っているスペシャリティとマーケットアビリティを持って転職できますから。(中略)
ジョブ型雇用はあくまでも欧米型であって、日本の場合はあまり向いていないんじゃないかなと思います。
引用:日本企業が欧米式のジョブ型雇用を採用するリスク カゴメが採り入れた、日本の採用方式にもマッチするジョブ型(ログミーBusiness)
さらに解雇規制の問題も深刻です。アメリカでは比較的自由に解雇が行え、欧州の多くの国でも金銭解決制度が整備されています。つまり、ジョブと個人のスキルがミスマッチを起こした場合、「解雇」という選択肢が現実に存在します。
しかし、日本では労働者保護の観点から解雇規制が厳しく、一度採用した従業員を簡単に解雇することはできません。このような法制度の中で、職務内容を厳格に限定する欧米型のジョブ型を導入し、人事異動の柔軟性まで失ってしまうと、企業は事業環境の変化に対応できなくなってしまいます。
したがって、日本企業がジョブ型雇用を導入する際には、自国の労働市場、採用慣行、法制度といった特殊な環境を十分に考慮した、独自のモデルを構築することが不可欠となります。
日本企業が目指すべき「日本的ジョブ型雇用」の姿
欧米式のジョブ型雇用が日本の風土に馴染まない以上、企業は自社の実態に即した「日本的ジョブ型」を模索する必要があります。
その先進的な事例として、カゴメ株式会社の取り組みが挙げられます。同社の有沢正人氏は、日本企業が目指すべき方向性を「ジェネラリストを志向したジョブ型」と表現しています。これは、キャリアの初期段階において、従業員が幅広い知識や経験を積むことを重視する考え方です。特に、新卒で入社した若手社員がさまざまな業務を経験し、自身の適性や専門性を見出していく過程では、職務範囲を厳格に定めるジョブディスクリプションはむしろ成長の妨げになると指摘します。
カゴメでは、管理職になるまでは年功的な要素も加味した役割等級制度を運用しており、厳密なジョブ型は適用していないと言います。その代わり、個々人の詳細なジョブディスクリプションを作成するのではなく、「ポジション」ごとに求められるミッションやアカウンタビリティ(説明責任)を明確にしているそうです。
そして、全社員の期初の目標設定シートを役員から新入社員まで全員が閲覧できるように公開することで、組織全体の透明性を確保しています。これにより、「誰が、どのような目標に向かって、何をしているのか」が一目瞭然となり、欧米式なジョブディスクリプションがなくても、各々の役割と責任が明確になるのです。
このアプローチの根底にあるのは、ジョブ型雇用の導入目的を正しく設定することの重要性です。もし「働かない中高年の給与を下げたい」といった短期的なコスト削減が目的であれば、制度は形骸化し、従業員の不満を招くだけに終わるでしょう。
カゴメが目指したのは、真のグローバル企業へと脱皮することであり、そのために上級職から制度改革に着手しました。降格や降職も役員から実行することで、変革に対する本気度を示し、全社の納得感を得ることに成功したのです。
重要なのは、一度失敗しても再チャレンジできる「敗者復活」の仕組みを設けることです。これにより、従業員は変化を恐れずに挑戦し続けることができます。
有沢氏が「各社別のジョブ型でいい」と語るように、他社の成功事例を単に模倣するのではなく、自社の理念や事業戦略、組織文化に根ざしたオーダーメイドの「日本的ジョブ型」を構築することこそが、成功へのカギとなるのです。  PR
PR