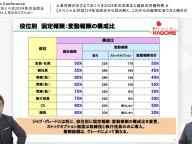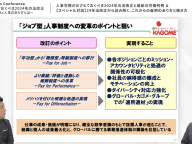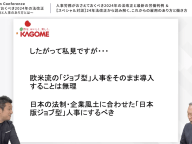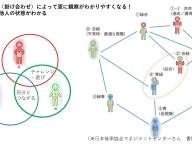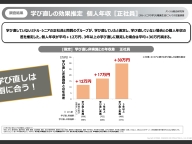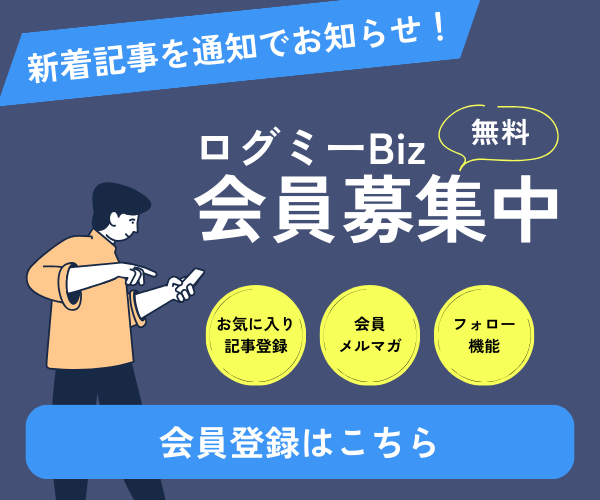誰もが知るあの作品を手掛けた、メディアクリエイターが紫綬褒章を受賞
佐藤雅彦氏(以下、佐藤):東京藝術大学の佐藤雅彦です。
――このたび紫綬褒章を受章されましたが、御感想を一言お願いします。
佐藤:最初聞いたときはすごく意外な感じがしました。驚いたというよりも意外で。「なんで自分が?」とまず感じたんですけど、その後に「どこかで見てくれている人がいるんだなぁ」と感じました。それがすごく感激しました。
――クリエイティブディレクターとして、これまで様々な作品を作っていらっしゃいますが、特に思い入れの強い作品はありますか?
佐藤:広告から始まって、テレビ番組とかいろんなことをやってますけども、まあ1つと言われたらもう絶対これだなと思うのがあって、それはプレイステーションのゲームソフトで「I.Q」というものですね。
佐藤:広告とかテレビ番組はどうしても見る人、対象があって、その人たちに届かなくちゃいけないという表現を目指してるんですけれども、ゲームソフトのI.Qっていうのは自分の好きな世界を思いっきりやったんですね。なので、I.Qがいちばん自分らしいなと思っていて、思い入れもあります。
――これまでの作品を通して一番伝えたいメッセージは何ですか?
佐藤:とても難しい質問だと思います。なぜ難しいかというと、僕はテーマとかメッセージを作るということはやってなくて、どちらかと言うと、どうやったらそれが伝わるかという「表現方法」、どうやったらこれを学んでくれるかっていう「教育方法」をやっていたんですよね。
届けるメッセージは、広告だったらクライアントが「この商品のこういう特長を伝えてほしい」ということもあるし、テレビ番組だったら例えば「中学生に理科の新しい考え方を伝えたい」っていうメッセージがまずあるわけですよね。
僕はどちらかと言うと、「どうやったらそれがその人たちに届くか」ということをやっていたので、特にいつもテーマとかメッセージというのはなかったんですね。ただ、どの表現でも、単純にわかりやすいとかそういうことじゃなくて、その人が主体的にそれを理解する、解釈するというのを目標に作っていました。
閃きを得るコツは「うまく待つこと」「ものすごく追求すること」
――見た人が考えさせられるような作品をたくさん作られていますが、アイデアはどのようなところから思いつかれるのでしょうか?
佐藤:表現を解釈する人、例えばテレビだったらリビングやお茶の間にいる人々、視聴者ですよね。書籍なら読者だったりするんですけど、非常に鑑賞者として、僕はプロだと思っているんですよね。ですから同じような表現をとると、やっぱりどこか「つまらないな」って思うんだろうなと思っていて。
やっぱりその人たちが「あっ、これは新しいわかり方だ」「自分はわかってしまうんだけど新しい」ということがないと、その表現を認めてもらえないんですよね。ですから、いつもそこで何らかの「ジャンプ」が行われなくちゃいけないんですよ。
過去やった表現を流用したりとかすると、それはもう軽く見抜かれてしまうんですよね。ですからこっちも毎回ジャンプしなくちゃいけません。やったことがなくて、やられたことがなくて、まだ言語化されてないけれどこれはおもしろいんじゃないか? っていうのをジャンプして見つける。ジャンプしたあかつきには言語化できるんですけど、もう毎回ジャンプを入れようとしているんですね。
でもジャンプっていうのは非常に難しくて、どこで見つけるかっていう質問だったんですけど、それはすごく難しくて、いろんなところに隠れているんですよ。
僕は「うまく待つ」って言っているんですけど、そういうものを見出す自分でいるように、うまく待っている。見過ごさないように。当たり前だと思っていることが実は当たり前じゃない、ということがとってもあるんですよね。
それと、これは鍛錬なのかもしれないですけど、いろんな場合の数、無数の場合の数を頭の中でやる訓練というか。全部「この場合、この場合、この場合……」全部「つまんない、つまんない、つまんない……」って頭の中でガシガシやっているうちに、セレンディピティというんですかね、たまたま何かのものが見えたりしたときに、それがガーンと来るジャンプの映像だったりしますね。
だからやっぱり「うまく待つ」ということと、「ものすごく追求する」ということだと思いますね。
佐藤氏が重視する"たたずまい"の価値
――作品を作るときに一番大事にしていることは何ですか?
佐藤:先ほど言ったように、本当の答えっていうのは、そこまで行く道がない、橋がないんですよ。頭のいい人は「こうだからこう、こうだからこうで済むじゃないか」という風に、通り一遍の解決っていうのは、今の世の中にいくつかあると思うんですね。
ところがそれはそんなに解決になっていない場合が多くて、表現の場合はそれは一言で「つまらない」とか言われてしまって、おしまいになることがあるんですね、一生懸命作っても。
佐藤:教育の場合はやっぱり、その人が興味を持ってあることを学んで獲得しなければいけないので、教育表現っていうのが……なんて言うんですかね? とある「たたずまい」って言うんですかね? 「この数学的な考え方、物理の考え方はおもしろそうな雰囲気がある」というたたずまいを出していないと、中学生とか高校生とかは挑んでくれないんですよね。
そういうたたずまい、別の言い方で言うと表現なんですけど、そういったものを作るときに「こうだからこう、こうだからこう」と通り一遍のことをやると、それはやっぱりそういうたたずまいを持たなくて、そんな本格的にその問題と格闘する価値があるのかどうか、っていうことを見透かされてしまうんですね。「これはきっと普通にやれば解ける」と。
そうじゃなくて、さっき言ったように、何らかの発見やジャンプをそこに入れたときにそういうたたずまいが出るので、どんなものでも必ずそういうものを入れようとしていますね。
それは広告で「ポリンキー」作るときも「バザールでござーる」を作るときも、ゲームの「I.Q」を作るときも、「ピタゴラスイッチ」を作るときも、全部やっぱりそういった自分の発見を絶対に入れないと、鑑賞してくれる人、読者とか視聴者はそれに対して自分が持っている時間を使って付き合うわけですからね。
本だったら何時間、番組だったら短い番組でも何分かは付き合ってくれるんですけど、そういうものに値するような雰囲気やたたずまいが、なかなか持てないんですね。
どうやったら伝わるか、を極めていきたい
――今後はどんな活動をしたいとお考えですか?
佐藤:実は自分が作った表現って、さっきも言ったようにコマーシャル、ゲーム、本、あるいは展示、テレビの番組とか、すごくいろんな風に見えるかもしれないんですけど、僕としてはやっていることは1つなんですね。それは「どうやったらあることが他の人に伝わるか」ということなんです。
例えば「ポリンキー」だったら、ポリンキーの名前とか存在とか商品特長が、どうやったら15秒で伝わるだろうか、とか。あるいは「I.Q」というゲームだったら、I.Qの持っているものすごい世界観、その中であるゲーム性が展開していく、これはどうやったら伝わるだろうか、と。
あるいは「考えるカラス」だったら、科学の考え方を頭ごなしに教科書的に伝えるんじゃなくて、みんながびっくりするような実験をし、あるいはアニメーションを作る。そしたら伝わるんじゃないか、ということをずっとやってきたんですね。
佐藤:今回の賞では、単発で1つ1つ見てくれる人というより、全体を見てくれている人がいるんだなぁ、ということにすごく感激したんですね。今後も僕はやっぱりやることは1つだと思います。「どうやったらそれが伝わるか」「どうやったらそれがわかってもらえるか」っていうことを極めていきたいですね。
作り方を、作る
――クリエイターから大学での教育者になられた経緯を教えてください。
佐藤:実は僕が大学のときって、「表現方法」とか「教育方法」という言葉はなかったし、例えば卒論で「数学を教えるのにアニメーションとかマンガを使う」っていうことを指導教官に言ったときには、ものすごく怒られたんですよね。「マンガかよ」って言われちゃったんですよね。すごく身分の低いものだったんです。
僕が使っていた数学の参考書で、寺田先生っていうすごく有名な数学の先生がいるんですけど、その方の書いていた数学(の参考書)は、そのとき唯一と言ってもいいくらいなんですけど、マンガの挿絵でポイントが書いてあるんですよ。それがすごくわかりやすいんですよね。「なんだ、このコミュニケーションは」と思ったんです。
そのときはまだ高校生ですから「コミュニケーション」とかは思わなかったんですけど、すごくそれでポンポンわかっていって、大学で教育学部に行ったときに「そういう新しい教育方法はないのかな?」と思ったんですね。
まだビデオもないし、アニメーションも……、サザエさんもなかった頃ですからね。ウォルトディズニーのアニメーションがあるぐらいで、動画なんか見ることも、作ることなんかとてもできないし。
そんな時代に新しい教育方法として、例えば科学の番組あるいは数学の番組をアニメーションでやる、っていう研究をやりたいと言ったときに、正直言って理解されなかったんですね。それで居場所がなくて、自分はサラリーマンになろうかなと思って、普通にサラリーマンになったんですね。
それで、表現の世界に入ったのはすごく遅くて30歳を過ぎてからなんですよ。なぜかテレビコマーシャルも好きだったので、そういうものを作るところに行き着くことができて、夢中になって作ったんですね。コマーシャルを作っていた時期ってすごく短くて、ものすごい量を作っていたんですけど、それがすごく変で、「作り方を作る」ということをやっていました。
要するに僕自身の表現方法論を作っては、それを具体的に(当てはめていく)。例えばトヨタ自動車から「カローラⅡ」がきたらこうするとか。これは「映像は音から作る」っていう方法論があるので、「カローラⅡに乗って」と小沢健二が歌っていたら、すごくカローラⅡのブランドが上がるな、とか。
濁音のチカラ
佐藤:例えばNECから店頭フェア(のCM)をやりたいという話が来たとき。いいネーミングがないというときに、僕には「濁音時代」っていう方法論があったんですね。
「ダースベーダー」とか「午後の紅茶」とか、濁音はやけに強いっていう方法論なんですけど、そのときに「バザールでござーる」っていうのを作った。「だんご3兄弟」も濁音時代で作ったんですけど、表現方法論を作っては試していたんですね。
佐藤:それが非常に効果があって、商品の知名度とか売上を伸ばしていって。それでどんどん表現方法論を作っていたんですけど、そのうちに「自分はなんでこんな作り方を作っているんだろう?」と思ったときに、広告やコマーシャルを作りたいんじゃないっていうことがやっとわかるんですね。
何百本作った後に。「自分は表現方法を作りたかったんだ」ということがわかったんです。表現方法や教育方法を作りたい、そっちなんだと思って、新しい分野に行くんですね。別にコマーシャルじゃなくてもいいなと思って。
それで新しい表現方法、自分の言葉なんですけど「トーン」という表現方法を見つけたときに、その先にゲームのアイデアや世界が生まれて、先ほど言った「I.Q」という世界観を、その新しい方法論で作るんです。それでそういう「表現方法を作りたいんだ」っていうことがだんだんわかってくるんです。
頭でわかってくるんじゃなくて、どんどん作りたいものを作っていくと、それが言語化されて、最後に抽出されたのが教育方法、表現方法だったんです。それをやっていた頃に慶応大学に呼ばれて「そういうものを教育・研究してくれ」ということで大学の研究室を作って、それからどんどん言語化して、新しい表現方法を何個も見つけた、というのが今までの流れですね。
作り方が新しければ、出来たものも新しい
――どんなクリエイターを育てたいですか?
佐藤:今話したように、僕は表現だけじゃなくても新しいものを作るときに、「その作り方が新しければ、自ずとできたものは新しい」ということを教えているんですよね。ですから、みんなに言っているのは「作り方を作る」ということ。「マニュアルを教わって作る」っていうやり方も1つあるんだけど、そうじゃなくて「作り方を作る」。
僕はテレビコマーシャルの作り方を、例えば「音から作る」とか、それまでの作り方からちょっと変えたんですね。そうするとやっぱりO.Aで流れたときに、みんな「なんか違うぞ」と思うわけですよね。だから、「作り方を作ると、自ずとできたものは新しくなる」ということを言っています。
表現を目指している人たちだけじゃなくて、新しい製品を作る人とか、新しい事業を作る人とかにもそういうことを言って、大学では教えているんですね。自分の作り方っていうのは、すごく自分のオリジナルがそこに入るんですよね。そこを今いちばん教えています。今というかずっとですね。
夢中になることで、集中の仕方が身につく
――将来、佐藤さんのようになりたいと思っている若者や子どもたちへの、メッセージをお願いします。
佐藤:僕は実は、30歳を過ぎてから表現の世界に入ってきたわけなんですけど、今なんでこんなにものを作ることに集中して夢中になれるかというと、小さいとき、僕は静岡県の伊豆で育ったんです。
毎日海に行って、アメフラシとかヒトデとか、そういった海の生物に夢中になっていたんですね。それとか、近所の子どもたちに新しい遊びを提供することに夢中になったりしていて。海もありますし、山もあるし川もあって、もう夢中になれる素材が周りに溢れていたんです。虫も魚もものすごくいっぱいいたし、遊びも自分で作ってものすごく夢中になっていたんですね。
その時には表現の"ひょ"の字もないですよね。デザインの"デ"の字もないんですよ。
何がおもしろいのか。僕は夢中になることを「studious」っていうラテン語で表していて、「study」は「勉強」と訳しますけど、本当はそのstudyの語源はstudiousといって、夢中になる・熱中する、という状態なんです。ですから「studio」なんかでは、みんなが熱中して物事を作ったり撮影したりしているわけですけど。
「studious」になることを覚えた子どもだったら、将来は表現をやろうと、例えば研究をやろうと、あるいは物を作る人になろうと、やっぱり1つのものへの集中の仕方がわかっているので、自分のやりたいことに到達できるんですね。
一番いけないのは、体裁だけを整えて「こっちの方がなんか見栄えがいい」とか、表面だけのことを覚えて、取り繕うことだけは巧みになる、というのが、僕がすごく恐れていることなんですね。
この映像ってたぶん子どもが直接見るというより、お母さんとか大学生とか、これから若い人を育てる立場の人だと思うので言いたいんですけれど、もう小さいときはそれが釣りだろうと音楽だろうと、特にスポーツ、野球、サッカー、そういうものに夢中になることを周りで勧めたいなぁと思っているんですよね、そういう環境を作りたい。
熱中した体験が、真価を見極める目を養う
佐藤:例えば僕は結構体育会の子が好きなんですけど、例えば野球をやっていた子っていうのは、中途半端なおもしろさ、シュールなおもしろさみたいなものには「つまんないんじゃないの、それ」って一言で看破できる力を持っているんですね。
なにかに夢中とか熱中した経験のある子だったら、何が本当におもしろいのか、何が本当に美味しいのかとかというのがわかる。
世の中マスコミがすごくうるさいから、「これが美味しいですよ」とか「これがおもしろいですよ」とか、いっぱい情報がありますよね。そのときに大事なのはやっぱり自分の考え、自分の案、意見ですよね。
「なんだ、つまんないじゃないか」「世の中間違ってるな」と思ってもいい。とにかく自分が一度夢中になった、熱中した体験があると、本当のものを見つける力があるなぁと思うんです。
表現の世界に入ったのは30歳過ぎてからですごく遅いんですけど、それまでにやっぱり夢中になったものが今思うとたくさんあって。
たまたま故郷が伊豆で、海とか山とか自然がとてもきれいなところで、それは今すごく感謝していますね。本当におもしろいもの、きれいなもの、美味しいものっていうのを、そこで身を持って知ったと思うんです。
ですから、子どもたちにはそこを体験させたいですね。間違ってもうわべだけ、あるいは人との関係だけで成立するような人間にはなってほしくなくて。だからズバッと、本当におもしろい番組とか表現をやりたいな、と思っているんです。