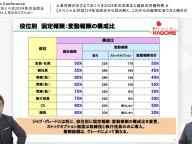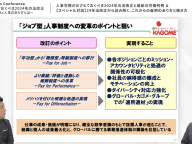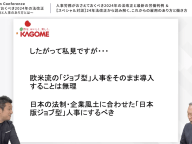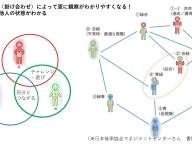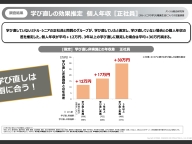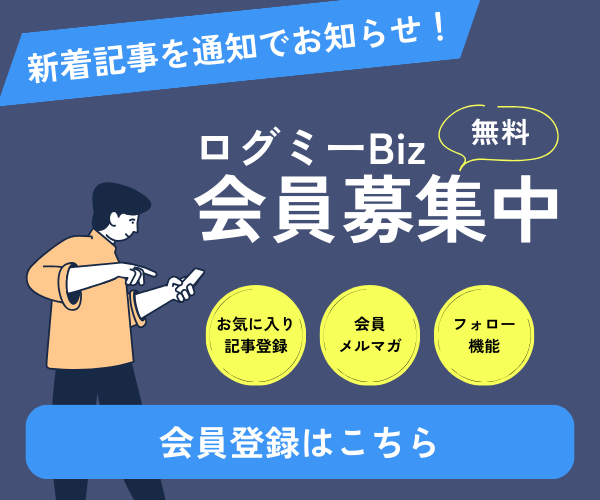「無駄な中庭」と「花が刺さらない花瓶」
川原崎晋裕氏(以下、川原崎):最初に簡単に自己紹介も兼ねて、アートに関心を持たれるようになったきっかけを教えていただけますか?
福武英明氏(以下、福武):私の祖父も父もアートは好きで、コレクターでした。それから岡山には大原美術館があって、クラレの大原さんがやっているんですよね。要は経済と文化両方やっているという土壌があるので、小さい頃からアートには触れているんです。
よく覚えているのは、小学校4年か5年くらいのときに、初めてうちが一戸建ての家を作ったとき。大した大きさではないんですけれども、そこに中庭があって。1畳ぐらいしかないんですけど。
川原崎:1畳!?
福武:せまーい中庭で。意味がわからないんですけれども(笑)。それがあるがゆえに間取りに相当制限があって、家の中を移動するのに迂回もしなければいけないし、ドアの制限などがいろいろあって。なんのためにあるのかがぜんぜんわからないし、それがなければ大きい広い部屋なのにな、と思いながらも、思い出としてはそこがずっと残っていて。
初めての家で1番覚えているところがその中庭なので、次に自分が家を作るならそういうのを作りたいな、と思っている。ということは、相当無駄なものがゆえになにか価値を感じたのかな、というのがアートに興味を持ったきっかけとしてはあるのかなと。
川原崎:「無駄な中庭」が強烈な記憶として残ってるんですね。
福武:あとは、初めて買った”結果的に”アートだったものがあって。結婚した24〜5歳くらいのときに、うちの奥さんが新しい家に花を飾ろうというので、サイズが違う3つの花瓶を買ってきたんですよ。それが家に持って帰ったら、花がささらない花瓶で……(笑)。
中野信子氏(以下、中野):おもしろい(笑)。
福武:「これなんなんだ!?」と。意味がわからないですよね。花瓶は花をさすものだろうと思ったら、花がささらない花瓶で。「これなんの意味があるんだろう?」と思いながらも、なんとなく気になって。15年くらい経っていまだにたぶん家にあると思うんですが。
川原崎:花がささらないままですか?
福武:ささらないまま(笑)。でもやっぱり気になる。意味があるものだとリプレイスされていくので。つまり花瓶を買うと、より良い花瓶、より素敵な花瓶があったら買い替えてしまうけれども、あまりにも意味がないものなので、買い替える対象もなくて(笑)。
中野:汎用性と有用性が逆比例しているという話ですね。
福武:そうそう。
川原崎:福武さんは、「余白」の話などもよくされていますよね。さっきの中庭ではないですけれども、解釈の余地を与えるための「余白」。
福武:最終的にはそういうのが、アートに関して強く求めているところだろうと思います。僕の家の1番良い場所にその花瓶を3つ置いたんですけど、来客がみんな「これはきっとすごいものだろう」と思うみたいで。
中野:思う、思う(笑)。
福武:「これ何?」と言うんですけれども(笑)。一応話のきっかけとして置いているだけで、大したものではないんです。でもそう思うというのは、そこからストーリーも出てくるし。人がつながったり、そこからまた話が広がったりもするのでおもしろいなと。そのへんが最初のきっかけですかね。
脳にとって「美」とはなにか?
川原崎:ありがとうございます。中野さんは……最近『不倫』(文春新書)が飛ぶ鳥を落とす勢いで売れているみたいですね。
中野:おかげさまで忙しくて、体力も飛ぶ鳥を落とされる勢いで……。
(一同笑)
川原崎:そもそも脳科学者という肩書は、なんとなくアートといった類のものとは正反対のイメージがありますね。
中野:アートは、もちろん自分が快の気持ちを感じて楽しいな、というのもありますが、価値を生み出す活動であるというところがおもしろいなと思っていて。
例えば私のアートコレクターの先輩のような人がいて。その人が20年くらい前に、こんな小さいカボチャを20万円で買ったんです。
川原崎:まさか、草間彌生さんの?
中野:そう。それが今1,500万円で売れるんですよ(笑)。
福武:すごい。
中野:それはなかなかすごいことではないですか。例えばふつうの人がカボチャに点々を描いて「これ1,500万円ね」と言ったら、「ふざけんな」と言われると思うんです(笑)。
でもそう思われない人がいるわけですよね。その価値の作り方というのに興味があって。そういう美しさの価値、お金を払うだけの価値を感じているというのを、脳のどこがどういうふうにやってるんだろうというのに、すごく興味を持ったんですよ。
福武:へぇー。
中野:そういうのは目に見えないじゃないですか。人間しか感知できないし。この分野の草分け的な人としてセミール・ゼキという研究者がいて。彼によれば、眼窩前頭皮質の内側がやっているという。そこの部分が、「美しい」「これは自分にとって良いものだ」と感じると、だいたい平均で35パーセントくらい活動がアップするんですよね。
おもしろいことに、そこは美人に反応する領域でもあるんですよ。しかも美しい顔だけではなく、「魅力度がそんなに高くないよ」と判定された人の顔でも、笑った顔になると反応したり。
必ずしも外形的な美醜というだけではなく、それ以上の意味を持って認知しているんだろうな、ということが推測されるわけですよね。なんでそんなものがあるのか、私はすごく不思議に思っていて。
福武:なるほどね。
中野:生きる上でぜんぜん関係ないじゃないですか。そんなものがなくても生きていけるし、食べて子孫を残すだけだったらそんなところは必要ないと言うか、むしろ邪魔なわけで。「なんでだろう?」というのがきっかけで。
川原崎:「脳にとって美とは何か」みたいなことですね。
中野:そうそう。
川原崎:人間の生存にとって必要かという点でいうと、優秀なDNAを持つ人が美人・イケメンに見える、というわけではないのですか?
中野:「美しさ」と「生殖能力」の関係ですよね。あれも今まで言われていたんですが、実は関係ないのではないかということが……(笑)。
福武:関係ないんですか?
中野:何年か前までそう言われていたんですが、それを覆す研究が出てきて。(美人の基準である)顔などの対称性の高さと生殖能力、健康な度合いとは関係がない。顔が対称だと脳が認知にかかる負荷が半分で済むので、それで好ましいと思うだけではないかと。
ビジネスの文脈でアートは説明可能か?
川原崎:そもそも「アート」と「ビジネス」というのは、過去から現在にかけてどういう関わりがあったのでしょうか? 例えば時の権力者や企業がアーティストのパトロンになるといったものは、ずっとありますよね。
福武さんが今ベネッセなどでやっていらっしゃる活動も、そういう活動のひとつに見えます。お金を持っている企業が文化活動を支えていく、というような。それは遠回りかもしれないけれど、ビジネスの点でメリットがあるからなのでしょうか。
福武:もともとは今おっしゃったように、大金持ちの家や国家などがパトロンとしてアーティストを支援して、それを宗教学的なメディアとして使ったりというのも、もちろんあったと思うんです。今ももちろん一部そういうのはあると思いますね。
ただ、どうなんですかね……アートの役割としてはたぶん、けっこういろんなものがあるので。ビジネスとアートを直接結びつけようとすると、けっこう無理があるのではないのかなと、個人的には。
川原崎:直接的には結びつかない?
福武:個人的にはそう思います。ただいずれにしろ、今まではアートで経済的な活動はなかなかしづらかった。だから、経済的な活動で生み出した富によって、時間軸は長いけれども文化活動を支援する、という流れだったと思うんです。今まではそれしかなかったですよね。
アートの役割はけっこう広がっていて。例えば地域を活性化するためにアートを使ったりというケースもあれば、(川原崎さんに取材前にご紹介いただいた)『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(山口周・著/光文社)にも書いてあったように、新しい未知のものに対する事業メイキングやビジョンを作っていくときに、過去の分析から作るのではなくてアーティスティックな思考で次の行き先を導くというのは、アートの使い方としてはもちろんあるのかもしれません。今はかなり多様化しているイメージがありますね。
いずれにしろ、アートとビジネスは近いようで……なんて言うんですかね。なんとなくビジネス側からすると、アートは「なんでもできる」というようなイメージがあるじゃないですか(笑)。
川原崎:なんでもできる?
福武:「アート」と言っておけばなんとなく良いよね、という(笑)。
中野:(笑)。
福武:いろんなアーティストがいるので。徹底的に今の体制を批判するアートがあったり、すごく新しいものを作ったりするアーティストもいます。アートとビジネスの関係で言うと、敢えて今まではその2つを結びつけようとしていないので。
直島を中心とした瀬戸内の活動は、結果としてベネッセが企業活動としてやっているようなイメージを持たれている方もいらっしゃいますが、無理やり結びつけようとすると整合性が取れなくなってしまうので、実際にはそのような発信はほとんどやっていない。あまりにも活動とそれに対する反応のタイミングが違うという問題があるため、例えばビジネス側がそれを強引につなげようとしても、アート・文化側は短期的には許容できなかったりするので。
例えば直島の活動が、今30年やってこんな状態です、というものに対して、上場企業の場合は四半期決算というのがあって。そこの整合性は時間軸で絶対に取れない。
川原崎:それはたしかにそうですね。
福武:ビジネスとこれを一緒にしようとすると……今のところ、説明しようと思えば説明できるんですけれども、基本的には見ている時間軸もだいぶ違うし、目指している部分もそれぞれ違うという状態ですね。
株主からは「言われますよ(笑)」
川原崎:株主からはなにも言われないですか?
福武:すごく言われますよ。取締役会でもすごく言われます(笑)。
川原崎:なんと(笑)。社内からも言われるんですね。
福武:でもそれは仕方がなくて。アート・文化活動というのは、数年単位どころか50年、100年単位の話になりがちで。今の京都があるというのもそうです。何百年前の遺産をがんばって保存しながら活用しているというのがあると思います。何百年も前にそれを始めていなければ今の京都はなかったということを考えると、かなり腰を据えて長く活動しなければいけないんです。
もし人の寿命が500年くらいになれば、経済活動と文化活動が両立し、整合性が取れた説明ができるようになるかもしれませんが、今の段階では100年未満なので。100年未満できれいに説明するのは難しいかなと。人の寿命と企業の寿命と文化の寿命の差がそれぞれ大きいので難しいですね。
川原崎:株主も100年経ったら死んでしまいますが、「100年、200年続けたら、これはベネッセになにかしらの利益を生みますよ」という説明の仕方は存在するということですか。
福武:そういう立て付けで説明はしていて、基本的には僕らもそういうふうに強く思っています。ただ、ベネッセのためにやっているという感覚はぜんぜんありません。ベネッセはベネッセで、「よく生きる」というものを事業を通して達成しようとしていますし、直島や瀬戸内の活動は、「よく生きる」というのを文化活動を通して達成しようとしています。
最終的には同じ目標なので、絶対にどこかで交わると思います。文化活動と経済活動は両輪のはずですが、ただ単にスピードが違えば燃料も違うので。文化活動のほうは必要不可欠なファウンデーションのようなイメージですね。
川原崎:なるほど。
福武:事業は変わるじゃないですか。iPhoneも、新しいiPhoneが出たら古いiPhoneは捨てられちゃうじゃないですか。事業は性質上、新しいモノが出ると、同じ役割の古いモノはなくなっていく。でも、最初にお話しした僕の花瓶じゃないですが、文化やアートは残されて、保存されて、蓄積されていくので、やっぱり性質が違うのかなと思います。
アートは”言い訳”に使える?
中野:花瓶の話で思い出すのは、岡本太郎の「坐ることを拒否する椅子」という作品があって。すごく座りにくいんですよ。真ん中が高くなっていたりして。カンチョーみたいな(笑)。
(一同笑)
ご存命だったころ、岡本太郎さんのところに知人が訪ねていくと、その椅子をみんな褒めるわけですよ。「すばらしい」「座りやすい」などと言うわけです。岡本太郎さんはそれを聞いて、すごく不機嫌になる。
福武:へぇー。
中野:1人だけ、「なんですかこの椅子は?」と言った人がいたらしくて。「君はすばらしい」と言われたという(笑)。そういう逸話があるんですよね。つまり、そもそも座りにくい椅子を作ったのに、みんなが褒めそやすのがすごく気に入らなかったと。
福武:面倒くさいですよね(笑)。
(一同笑)
中野:面倒くさいですが、汎用性と有用性の高いものがアートではないよ、ということを彼は言いたかったんでしょうね。私の勝手な解釈ですが。むしろ使われなくて無駄なもののほうが残るというのは、すごく印象的で。汎用性が高くて有用なものなら、私たちは例えばパートナーですら捨てますよね。
福武:うーん(笑)。
中野:物理的に捨てることはしないにしても、メンタルでは捨ててしまう。それで、もっと目新しい、自分の思い通りにならないかわいい女がいたら、そちらにずっと心が奪われてしまうでしょう。人間はそういうものです。刺激としては、そちらのほうがドーパミンが出るから仕方がない。アートは汎用性を追求してはいけない、ということになります。
もう1つおもしろいと私が思っているポイントが、福武さんの話の中にあって。アートとビジネスが直接は結びつかないというのは、確かにおもしろい点なんですよね。ビジネスというと、自分で企業を立ち上げたり、執行役員として中核にいる人以外には、ちょっと遠い話であって。どちらかといえばお金の世界、言葉を選びますが、多くの人は「あまりきれいな領域ではない」と思っているんですよね。
川原崎:ビジネスのことをですか?
中野:お金が絡んでいるダークな領域、というような無意識的なイメージ(笑)を持っている人がけっこういるわけですよね。そのダークな感覚はおもしろくて、多くの人はお金のことをあまり良いものと思っていないことが多い。もちろんあったほうがいいことは知っているけど、きれいなものとは思っていない。
これはさっきの「美しさを感じる(脳の)領域」と同じ領域が判断していて、お金をいわばネガティブな価値として見ているわけですね。むしろ個人にとっては役に立たないものを、美しいと……個人としては犠牲を払うけれど公共の利益に資するものがきれいなものだと感じている。それが美でありアートであるという感覚が多くの人にはあるわけですよね。たぶんこれは、ユニバーサルに人間に備わっているものです。
福武:企業がすごくお金を儲けていて、でも例えば株主還元が少なくて、「なんだあいつらは」となっていく。「でもなんか良い感じの芸術活動をしているしなあ」ということで、ちょっとその嫉妬心のようなものが相殺される(笑)。
中野:そうそう。だからベネッセさんはすごく良いバランスのとり方をしているのかな、と私は思います。
福武:アートは否定されにくい領域ですよね。「アート」と言えば許してもらえる、という(笑)。
(一同笑)
中野:やっぱり長期的に見て、公共の利益に資することをしているんだ、という言い訳ができる。言い訳というか、そこで多くの人が納得するロジックができるんですよね。
多くの人が納得するというのは、世間一般の人が納得するという以上に、そこで働いている人も納得するんですよ。「俺たちはヤツらのエゴのために働いているんじゃない」と。それは間接的に生産性を高めたり、仕事のモチベーションを高めたりするきっかけになり得る。
福武:確かに。直接混じり合ってはいなくて、それぞれ独立しているんだけれども、一応メリットはあるというか。
中野:あると思いますね。必ずしも人間は経済合理性だけで動くわけではない。従来のエコノミクスでは、経済合理性だけで動くというモデルが立てられていましたけれども、現実はそうではないですよね。「自分が損をしてでも誰かのために働きたい」と思ったり、ちょっとズルをしている人を見ると「自分がコストを払ってでも罰を与えたい」と思ったり。
そういうことを加味した経済モデルを作らなければ、実際の世の中が読み解けない。これまでの経済理論でない理論にアートも組み込まなければいけないわけですが、今はまだできていないですね。でも、みんながうっすらと可能性を感じて、「アートをやらなければ」という気持ちに同時多発的になっているというところが、おもしろいなと。