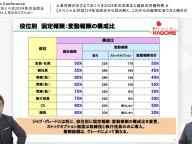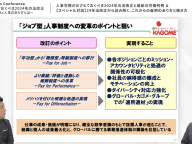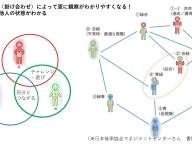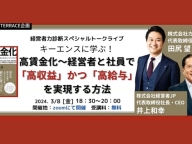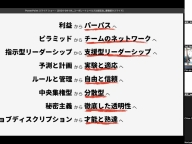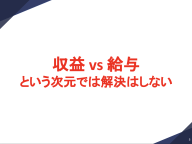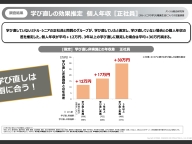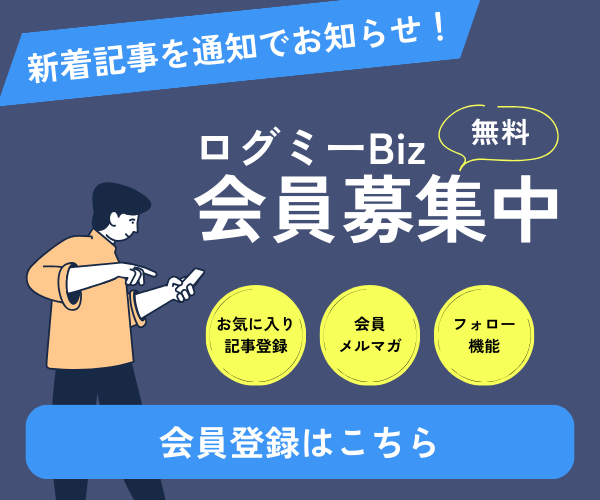AirbnbもPinterestも建築家が生み出した
各務太郎氏:おはようございます。各務太郎と申します。本日はご足労いただきまして誠にありがとうございました。ハーバード大学のデザインプログラムの話をさせていただくんですけれども、デザインデザインした話を今からするわけではありません。みなさんご存知かと思うんですけれども、例えば Airbnbの創業メンバーはみんな建築学科の方です。
Pinterestもコロンビアの建築の方が起業されました。ちょっと古い例になっちゃいますけども、スターバックスももともとの企業理念は「サードプレイス」ということで、コーヒーは一切関係なく建築の不動産事業なんです。
という点で、事業開発をする上でデザインや建築の考え方が意外と重要な時代になってきていると思いますので、人材開発という視点でデザインの話をさせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。
日米のデザイン教育の違いは「選択の余地」があるか
一番最初に、まず日本とアメリカのデザイン教育を比べたいなと思います。これは変な例になっちゃうかもしれないんですが、僕は幼少期に2年ほどアメリカにいたことがありまして。ランチタイムにランチボックスを開いてみんなでご飯を食べるんですけど、ここからもう根本的に、デザインであったり教育や人材開発の観点が日本とアメリカで違うなと思うのは、アメリカってみんなと違うお弁当を持ってきているので、「今日みんな違うお弁当だよね」というのを比べながら話すんですね。
なるべく被らないように被らないように、明日どんなものを食べようというのをみんなで話すんですけど、日本って給食じゃないですか。それで、みんな同じものを食べると思っているんですね。
これは極端な例なんですけれど、「選択の余地がもともとある」っていうことを知っている国民性と、とりあえず向こうから与えられたものをこなしていくというような考え方、「選択の余地がない」というのでは、けっこう大きな差別化があるんじゃないかなと思っておりまして、そこを起点にお話しさせていただければと思っております。
先ほどお話もあったんですけれども、私は早稲田で建築を学んだ後に電通でコピーライターを3年半ほどやりまして、辞めてからハーバード大学で都市デザインの修士課程を経て、日本に戻って旅館業で起業しました。
これから自分も実業をやっていくなかで、事業開発の部分に関してはまだ卵ではあるんですけれども、もしかしたらみなさんと共有できる話があるのではないかと思っております。
デザインの意味は、「設計」から「見た目のデザイン」に変化した
私が行っていた大学は、Graduate School of Designというデザインスクールと呼ばれるところです。ハーバードやスタンフォードのロースクール、またはビジネススクール出身の方はみなさんのお知り合いにもたくさんおられると思うんですけど、建築やデザインスクール出身の方はなかなか周りにいないんじゃないかなと思っております。(スライドを指して)これがキャンパスなんですけど、右側がちょっと変な三角形の建物になっておりまして、中に入ると広大な階段教室が広がっているんですね。1人1つずつ机が与えられまして、もう1年中そこに住んでいるような感じになるんです。みなさん徹夜で1日中建築をつくっていくような2年間がずっと続いていきます。
デザインスクールと言っているんですけれども、「デザイン」っていう言葉は日本で2回輸入されたと言われています。最初は明治時代に「設計」という言葉で和訳されて輸入されました。このときは都市開発とか組織の設計みたいな意味で、広い意味でデザインという言葉が輸入されました。
戦後に輸入されたデザインという言葉は、今みなさんが思っているグラフィックデザインであるとかプロダクトデザイン、要するに仕上げの部分ですね。見た目の部分のデザインという言葉は戦後輸入されました。
この学校自体は100年前から続いている学科なので、もともと組織の設計や社会構造の設計という意味で、建築しかないデザインスクールです。
大きく分けて3つありまして、建築と都市のデザインを意味するアーバンデザイン、そしてランドスケープデザインです。ランドスケープデザインとはセントラルパークとか日比谷公園みたいなことですね。あるいはミッドタウンの21_21あたりのエリアであったり。この3つの学科から構成されています。
セミナー形式×デザインスタジオによる2年間の授業
卒業生は、フランク・ゲーリーさんやパリのルーブル美術館のI.M.ペイ、日本からも槇文彦さんや谷口吉生さんなどいろんな卒業生がいらっしゃいます。授業は2年間の修士課程なんですけれども、大きく分けて2つの構成になっています。
1つは、いわゆる座学というとあれなんですけれども、セミナーやレクチャー形式のものですね。いろんな書物を読んだりして、それをディスカッションしていきながら議論をして論文を書いていくという構成の授業。
もう1つはデザインスタジオといいまして、ある建築家の教授が1人ついて、その下に13人ぐらい学生がわらわらとついてですね。この14人から15人くらいのグループで4ヶ月にわたって1つの建物を設計していくというようなもの。これがいわゆる建築学科生がよくやっているようなものなんですけれども。
この2つを合わせていって2年間の教育を行っていくということになっております。本日は、とくにこのセミナーとレクチャーの方から、ハーバードのデザインスクールを形づくっている名物授業を2つと、後半のデザインスタジオがどういう理念でやられているかというところを、人材開発の視点でお話しさせていただければと思います。
自分で「建築とは何か」を定義させる名物授業
まずは1個目ですね。これはプレストン・スコット・コーエンという教授によるティーチングテクニックスというすごく有名な授業で、建築大学のカリキュラムをつくります。建築を学びに大学院に来てるのに、この授業では「今から2年間で良い建築家を育てるためのカリキュラムをあなた方がデザインしてください」というところから始まります。これがけっこう重要かなと思っています。
例えば、企業に新入社員が入ってくると数ヶ月の研修期間があると思うんですけれども、そこでいろんな方々がレクチャーするのではなくて、どういう社員像になりたいか、どういうカリキュラムをつくれば一人前の新入社員になれるかっていう、そもそもの研修プログラムを1年目の方に作ってくださいと課題を出すようなものですね。
これが名物授業で、どういう順番で学んでいくかっていうのを、2年間に渡ってほぼ素人の建築学生がゼロから考えることになります。その過程で、それぞれが建築っていうものはどういうことかを自分で定義していくことになるんですね。
与えられた「建築の歴史はこうなんだ」ということではなくて、歴史というものはそもそもどういうことかを学生が認識して、今の設計や今後未来をつくる上でどういうフローになっていくのかを自分で考えていく。
あるいは、いわゆる設計課題がどういう役割を持っているのか、どのくらいの配分でそれを入れるべきなのかを自分で考えるという授業です。これがすごく売りの名物授業になっています。
100年後に「建築」と呼ばれそうなものを掘り起こす
もう1つはカルロス・ムロというスペインの建築家がやっているポテンシャルアーキテクチャっていう授業です。これはちょっとポエムみたいな話になっちゃうんですけど、「建築になり得るような、建築とは呼べないもの」の授業です。
建築にはビルや家具、都市計画などあると思うんですけど、この授業では音楽とか小説、数式の話しかしません。「これって建築的だよね」「これって100年後は建築って呼ばれるんじゃない?」っていうものをひたすらにみんなが挙げていく授業になっています。
例えば、僕は最後の課題で俳句を建築的なものとして挙げました。「五七五」という構造体、フレームワークは、実は建築で使われているフレームワークとなっていまして、こういうビルとかも全部その考え方は数値によってできていると。
俳句みたいなものは建築と呼べるようになってくるんじゃないかってことを考えていく授業になります。
(スライドを指して)昔ドイツにバウハウスっていうデザインスクールがあったんですけれども、ナチスドイツのためにみんなが亡命しなくてはいけなくなったときに、ドイツのデザイナーがまるごと全員ハーバードに来てつくったのが建築学科だったんですね。
当時ヨーロッパで行われていた活動がボストンにけっこう輸入されたんですけれども、当時「ウリポ」という知的サロンみたいなものがフランスのほうにはありました。イタロ・カルヴィーノっていうすごくエッジの効いた小説家であるとか、建築家、数学者、あるいはチェスのプレイヤーとかが集まって日々、さっきのポテンシャルアーキテクチャについて話したと言われています。
例えば、「チェスの動きみたいなものを建物の正面でやるとどういうことになるかな?」とか、「この数式って音楽になるからこの音楽は建物になるかな?」みたいなことをずっと話していくような、ちょっと難しそうな人たちなんですけれども。
こういうようなインターディシプリナリーと言いますか、分野を越えて話すことによって、まだ建築と呼ばれてないけれども今後建築になりそうな部分をみんなで掘っていくようなことが、今のハーバードの教育の基点になっています。
僕は広告会社にいたんですけれども、広告と呼べないものってたくさんあると思うんですよ。
もちろん4マス広告やインターネット広告みたいなものもあるんですけれども、例えば歩いてるだけですごく目立つ人がいたら「その人の後頭部はメディアになるんじゃないか?」とか、今メディアと呼べないものをメディアと呼んでみようかというようなことが、このハーバードの教育ともしかして通底するのかなと考える。
自社が業務だけを1年目の人に教えるんじゃなくて、今後自社としてやるべきこと・やり得るべきことを、1年目の社員や人材開発を教える側の方々に提案していただくというのが、1つの人材開発プログラムとしてありうるかなと思っています。
日本のデザイン教育では、新規事業をつくれる建築家が育たない
2つの名物授業を紹介させていただいたんですが、簡単にまとめると「自分が学びたいデザインを自分で選ばせる」っていうことなんですね。これは日本だと全くありません。東大、早稲田、京大などの建築学科のいろんなプログラムを見ましたけど、基本的には先生が敷地を指定して「ここに美術館を建ててください」と言って、みんなが徹夜してつくっていく。
「そもそも美術館ってなんだっけ?」を考えるの余地は与えられません。「そもそも美術館が必要なんだっけ?」とか「アートって呼ぶものは僕たちにどういう影響を与えるのか?」っていうそもそもの部分を考えずに、とりあえずみんなが格好いい模型をつくって、「ここにモネを置こう」みたいになるんです。
「それって何の問題を解決してるんだろう?」ということを僕たちは考えないまま建築を進めていくんですね。そうすると、卒業した後に自分で問いを立てられなくなってしまうので、結局与えられたものしか答えられないデザイナーが多くなってしまう。イラストレーターとかのソフトが使えるだけのスキルの人になってしまう。
根本的に世の中を変えるような、新規事業をつくれるような建築家にはならないんじゃないかという問題意識を、僕は日本に持っています。
問題解決ではなく、問題提起のためにデザインを使う
先ほど、ハーバードの授業ではセミナー・レクチャーとデザインスタジオというものがあるとお話ししたんですけど、その設計課題の特徴をもう1つご共有させていただければと思います。ヨーロッパ発なんですけれども、今アメリカのMITメディアラボやハーバードのデザインスクールで主流になりはじめているのが、スペキュラティブ・デザインという考え方です。日本でも田川欣哉さんやスプツニ子!さんなど一部の方が提唱しはじめているんですけども、今この考え方がとくにロンドンとアメリカ東海岸のほうでは主流になってきています。
アンソニー・ダンとフィオナ・レイビーという、ロンドンの王立芸大ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの教授2人が書いた『SPECULATIVE EVERYTHING』(邦題は『スペキュラティヴ・デザイン 問題解決から、問題提起へ。—未来を思索するためにデザインができること』)という本が4年前に出版されました。
この本で彼らは……(スライドを指して)ごめんなさい、英語なんですけれども。
もともとデザインって問題解決という印象で、例えば雨に濡れるのを避けたいから傘をつくるとか、なにか問題があって解決するものがデザインっていうデフィニションだったと思うんです。でも彼らは「将来こういう世の中になる、という未来を提示するためにデザインが使えるんじゃないか」と言ったんですね。
スペキュレーションって、ファイナンスの用語で「投機する」とか「推測する」という意味です。どういうことかというと、問題解決じゃなくて問題提起としてのデザインということです。
つくりたい未来のためにデザイナーは動く
(スライドを指して)これは彼らが書いた有名なダイアグラムで「フューチャーコーン」、未来の三角錐と言われているものです。一番左のプレゼントというのが現在ですね。右に行くほど未来になってきます。一番真ん中の濃い三角形「Probable Future」、ほぼ確実に起こる未来。
次の水色の三角形が「Plausible Future」で、最もらしい起こりえるかなっていう未来。一番外側が「Possible Future」で、理論上あり得るけどまぁこないかもねっていう未来です。
未来って、可能性においてはスペクトラムに分かれていきます。未来のことを話すときに、私たちよく「未来ってどうなるんだろう?」と、とくに日本人の方は言いがちなんです。でも「どうなる?」というのは、もう未来が決まっていてそれを受け身として受けるときの言葉だと思うんです。「どうなっていくんだろう?」って勝手に自然に決まっていくようなものです。
彼らは(スライドを指して)この茶色い部分、「Preferable Future」っていうんですけれども、「自分がそうしたい未来をつくりましょう」と言っているんですね。「未来はどうなるんだろう?」ではなくて、「こういう未来にしよう」ということのためにデザイナーは動くべきなんじゃないか、というのがスペキュラティブ・デザインの基本的な考え方です。
問題提起というアクションを起こさせるデザインの力
3つほど例をご説明させていただければと思います。1つは、先ほどお話しさせていただきました東京とロンドンで活躍されているtakramという会社のプロジェクトです。「100年後の水筒をデザインしてください」というアートプロジェクトのお題があったときに、彼らは何をしたか。100年後って、もしかしたら砂漠化であったり酸性雨の影響で飲み水が少なくなってるかもしれないと。そうすると摂取した水を大切に体内で処理しなきゃいけない。だから、そもそも喉が乾かなくなくなるような膀胱と喉のデザインをしたんですね。
これって、「水筒をつくってください」と言われてからかなりのジャンプがあると思うんです。これは問題解決じゃないですけど、このアートを観た人は「あ、将来水がなくなっていくんだ。じゃあ今からどういうアクションを起こしたらいいのかな?」というふうに、これを観たことによって問題提起されて、それによってアクションが生まれるということです。
要するに、「デザインというものはアクションを促すために使えるんじゃないか?」っていう1つの例です。
もう1つは、MITメディアラボの学生の方がつくったプロジェクトです。
イギリスで女性の皮膚の細胞を採ってiPS細胞にし、そこから精子をつくることができるようになったという生物学の論文が出たんですね。そうすると何が起こるかというと、女性同士で子供を産めるようになるんです。
(スライドを指して)両側にいるのは実際にレズビアンのカップルの方なんですけど、彼らの遺伝子を採って、将来産まれうる娘たち2人の姿を「こういう子どもが産まれるだろう」ということを遺伝子解析でビジュアライズしたアートです。
これも問題解決は何もしてないんですけれども、これを観た人の間で「じゃあ女性同士で子どもも産めるようになったときに法律ってどうなるんだっけ?」「そのときの倫理ってどうなるんだったけ?」「男性の役割ってどうなるんだっけ?」という議論が巻き起こりますよね。
要するに、これは問題提起なんです。これを観たことによって問題提起が行われて、「法律を変えなきゃいけない」「結婚の意味を変えなきゃいけない」とか、それによって例えば「社会保険を変えなきゃいけないんじゃないか?」というような、いろんな社会の構造自体を変える必要があるということをみんなが認識して動き始める。そういうことにデザイン使えるんじゃないかっていうことの例ですね。
食事をデザインし直したソイレントの成功事例
アートのプロジェクトを2つご紹介したんですが、もう1つは、実際にある起業アイデアです。アメリカの西海岸にあるソイレントという会社のプロダクトで、1日に必要な栄養素が全部粉末状になっているプロテインみたいなものです。
もともとは4人の若者が起業したIT企業だったんですけれども、、家賃も日々の食事代も払えなくなってにっちもさっちもいかなくなたときに、彼ら4人で医学書を読みふけって1日に必要な栄養素を全部数字で書きだしたんですね。ちょっとでも食費を浮かすために。
必要なサプリメントを全部最安値で取り寄せて、ミキサーに入れて粉にしたものに水をかけて飲んでたんですよ。そしたらみんなめちゃくちゃ肌が綺麗になってくるっていうことが起こりまして。「これで起業できるんじゃない?」っていうことで起業したら数十億円の資金調達に成功したんですね。
今すごく成功している会社です。ちょっとこないだ食中毒みたいなのがあったっていう話を聞いたんですけれども。
(会場笑)
最初はそういう思いつきから始まったんですけれども、起業した後に自身のホームページの中で「未来の食事は日々の栄養を摂るために必要な食事、要するに粉末みたいな食事と、お寿司やステーキみたいに味を楽しむレジャーの食事に分かれていくだろう」というステートメントを書いています。
ちょっと不思議なSF小説のような、星新一みたいなイメージを持っちゃうかもしれないんですけど、スペキュラティブ・デザインで「未来はこうなりたい」「こうしたいんだ」という未来の小説のシナリオを先に描いて、その逆算としてこういうプロダクトをつくって現代に売っているんですね。
SF小説の逆算でブルーオーシャンのパイオニアに
今ってマーケティングがと盛んに言われていて、「今のニーズはどこにあるんだろう?」というものを見つけてそれに対して商品を置こうとするんですけど、今ある問題を解決するのは参入障壁が低さからレッドオーシャンになりがちなんですよ。でも、「こういう未来にしたいんだ」という、みんながまだ賛成しきれてないぐらいの未来を提示して、それに対してみんなが驚くような商品を出すと、当たったときにブルーオーシャンでパイオニアになる可能性がある。アメリカにすごく伸びる企業が多いのは、SF小説を逆算して起業するところが多いから。要するに自分で問いを立てる企業が多いからかなと思います。
日本の場合は、もちろんアントレプレナーはいっぱいいるんですけれども、問いを外部からアウトソースする方が多いのかなと思います。「今の社会問題ってこれだよね。だから解決しようか」という方がいて、それはもちろんすごく重要なんですけれども、「こういう未来にしたいんだ」「解きたい問いが僕にはあるんだ」と考える人があまり日本にはないのかなっていう意識が少しありました。最初にお話したランチボックスと給食の違いような印象を僕は持っています。
NASAに建築を提案するハーバード大での卒業設計
実際にハーバードで行われていた建築科での課題をここでご説明させてください。アメリカの建築課題っていうのは、スポンサーがつくんですね。僕の卒業設計のときは、NASAがついたんです。日本では絶対スポンサーがつかなくてですね。先ほど申し上げましたとおり、教授が課題を出してそれをつくっていくだけなんですけど、アメリカの教育では実際に会社がついて、彼らから200〜300万もらって、彼らに対して建築を提案する。なので、かなり実践的でリアルな教育になってるんですね。
僕たちも実際にロサンゼルスにあるNASAに招待されて、1週間研究所に行きました。そこでいろんな研究者の方をインタビューしていって、本当に必要なオフィスとはなんだろうか、ということを話し合ってきました。
そのときに出た課題が「50年後のNASAの働き方をデザインしてください」っていうもので、これが僕たちの最後の卒業設計の課題だったんですね。このときに「この建築をつくってください」とは言われませんでした。「働き方をつくってください」としか言われないんです。だから僕たちが必要な建築のプログラムというか機能は僕たちが決めないといけないんですね。
日本ではただ「美術館をつくってください」と言われます。僕がやったリサーチは、NASAって国家予算がついているんですけど、アポロ以降どんどん下がってきているなかで、どうやったら国からのアテンションをもっと引けるかなということを問題提起しました。
50年後のNASAを自分自身で提起できるか
NASAは宇宙事業をやっていますけど、それ以上に地球に起こっている問題が大きいんですよね。温暖化とか砂漠化、あとは地震とか台風もある。なので僕は、そもそもNASAはもう宇宙をやるべきじゃなくて、その宇宙で得られた知見みたいなものを地球に還元する時代になるんじゃないかという問題・仮説を立てました。本当に起こるかどうかではなく、あくまでも「こういう未来にしたいんだ」ということが前提です。宇宙ってやっぱり極限状態の場所だと思うんですね。要するに私は、スペースはエクストリーム・シチュエーションの場所だと定義しました。
例えば、火星に住むために彼らが研究開発してきた技術を砂漠に住むための技術に適用したり、月に住むためにやってきたことを南極に住むために使ったり、あるいは無重力で住むためのものを水中に住めるような事業開発に使っていくような機関になると。
トランプ自身は、もう地球すらもやらなくていいって言ってるんですけども。実際にNASAの予算を見ると宇宙よりもアースサイエンスに力を入れ始めていたので、僕はそれが誇張されると予測しました。
「もしかして地球の事業をもっとやっていくとバジェットのアテンションが上がるんじゃないの?」みたいな仮説設計で進めました。
私がつくった機能は、ちょっと長いんですけども「エクストリーム・シチュエーション・エクスペリメンタル・ラボ」っていう、極限状態を実験するための施設をNASAは50年後につくるんじゃないかっていうことを、1つの仮説において建築の設計をはじめたんですね。(略して)「XSXL」といいます。
僕がNASAに行ったとき、ここにはめちゃくちゃ狭い空間とめちゃくちゃ広い空間が必要であることが分かったんですね。研究者って狭いところと大きい施設を往復していたので、これを密接にしたような建築設計を行いました。実際はこういうXSとXLのところがある箱を、さらに大きい箱に陥入させていくような建築をつくっていきました。たまたまダジャレみたいになってるんですけど。
これが重要なのは、この建築自体ももちろんなんですけど、最初の仮説の部分ですね。NASAのバジェットを読んで、「50年後はこういうふうになるんじゃないか?」、もしくは「NASAをこうしたい」と私たちが意思をもって決めるということがすごく重要で、これは日本の教育にはないところです。
アメリカのデザイン教育はコピーライティングと似ている
まとめさせていただくと、日本ってやっぱり問いに答える文化だなと思うんですね。問いがあって、その問いを見つけてきて、その問いに答えようとする。あるいは、今潜在的なニーズは何かをマーケティングして見つけてくるのが、多くの日本の教育のベースにあるんではないかと私は思いました。
アメリカの教育、とくに今回のハーバードのデザインスクールでは、問いをつくることが1つの課題でした。あるいはニーズすらもつくるということですね。それはちょっとコピーライティングの話にも近づくなとも思ったんです。
ちょっと前に「ちょいワルオヤジ」っていう言葉があったと思うんですけど、の前から年配で格好いい服を着られている方っていっぱいいらっしゃったとと思うんです。それが「ちょいワルオヤジ」というカテゴリーをつくることによって、一気に市場規模が50億円が顕在化してくることがある。
要するに、ニーズっていうものを自分からつくりだすことに対して時間を割くのがアメリカのデザイン教育なんじゃないかと私は感じております。
文化はゼロイチからキュレーションに
最後に、今回はみなさんに早稲田大学キャンパスの5階にあるWASEDA NEOというところに来ていただいたんですけれども、問いをつくる、ニーズをつくるということを新規事業開発の事業創造プログラムにできないかということで、私は今プログラムをつくっています。ここは「みらいブレンディピティ」という組織、というか事業になっております。ブレンディピティというのはこの早稲田大学がつくった造語で、場所をブレンドさせるっていう意味と、そこで偶発的に起こる出会いみたいなセレンディピティを合わせた言葉です。
私たちが今やろうとしているのは、新規事業開発をする事業プロデューサーの育成プログラムです。ゼロイチの話をさせていただいたんですけども、今ってやっぱりキュレーションの文化になってきてると思うんですね。今すでにあるものを掛け算したりして新規事業をつくっていくと。
例えばこの中川政七商店さんも、すでにある日本のいいものを日用品にしていますし、Factelier (ファクトリエ) さんも工場の人たちと直接商品開発することによって安くいいものを提供する会社です。すごくいいブランドを卸しているけど、間にマージンを取られて給料も安く、最後のアウトプットのブランドは高くなってしまう下町の工場の「間」を全部取っ払ってしまったんですね。
knotさんはそれを時計でやるっていうことですね。aeruさんはいろんな地域にある伝統工芸品で赤ちゃん用品をつくっている会社です。そうすると2代のジェネレーションギャップを超えて子供たちが使うので、彼らが大人になっても伝統工芸品が使われ続けるだろうということなんですね。
彼らがやっているのは、既存のすでにいいものを掛け算するということであったり、ターゲットを変えることによってキュレーションすることによって、新規事業をつくるということです。
アクションまで起こせるプログラムにしたい
彼らを1つの目標にしながら私たちがやろうとしてるのは、ミライシュハンさんという日本酒のベンチャー企業の方が1つの協賛企業について、432年続いている酒蔵さんの1つのお酒をリブランディングするという課題で事業開発をするプログラムです。先ほどのスペキュラティブ・デザイン的な考え方を適用すると、単純にパッケージとかネーミングを変えてリブランディングするんじゃなくて、「そもそも50年後って日本酒の役割ってどうなってるんでしたっけ?」「そもそも飲み物のままなのか?」「そもそもお酒市場ってどうなってるんでしょう?」っていうところをしっかりと予測する。
あるいは、こうしたいっていう未来を最初に作って、その逆算として今どういうプロダクトが必要なんだろうっていうことをやっていく事業開発プログラムにしたいと思っております。
4日間しかないプログラムなんですけれども、間がそれぞれ2週間ずつぐらい空いていて、グループワークでプロダクトをつくっていきます。実際にはプレゼンテーションから始まるプログラムになっていて、アントレプレナーが投資家の方にピッチするようなイメージの授業になっています。
普通のビジネスコンテストやアクセラレータープログラムは、課題が出てそれに対してビジネスアイデアを設けて発表し、順位づけて終わるんです。要するに、プラン・ドゥまでで終わってしまうんですね。ただ今回、私たちの売りは3日目までにプロトタイプをつくってしまって、ミライシュハンさんの店舗に実際に置かせていただくことです。
そこから1ヶ月ぐらいにわたって市場調査をしていって、PDC(プラン・ドゥ・チェック)までやろうと思ってるんですね。その調査結果をもう1回プレゼンテーションしてもらって、どう改善していくと新しいプログラム、新規事業になるかというところまでやって、本当に意識がある方はそのまま新規事業を立ち上げたり起業してもらうのを、1つの目標にしているプログラムになっております。
先ほども申し上げたんですけれども、ビジネスコンテストやハッカソンはプラン・ドゥで終わってしまうものも多いんですね、なので、しっかりと未来のシナリオから逆算していって、100年続くような日本酒の会社はどういうものだろうっていうことを考えていきながら、チェック・アクションまで起こしていけるようなプログラムにしたいと思っております。
理想なのは新入社員がピボット案を考えられる会社
すみません、最後は宣伝で終わってしまったんですけれども、今回のまとめとしては、先ほどの「問いをつくる、ニーズをつくる」ということが1つのポイントかなと思っております。これは今、日本に決定的に足りていません。もしかしたら企業の人材開発のなかで、こういう人材にしたいといったときの1つのスローガンになるかなと私は思ってるんですね。
例えば、GEなんかは何度もピボットしてすごく大きな会社になっていますけど、新入社員が自分の入った会社のピボット案まで考えられるような、そのくらいの問いをつくれるような人をつくっていけるような人材開発ができるのが僕は理想なんじゃないかなと思っております。ありがとうございました。