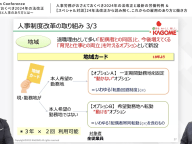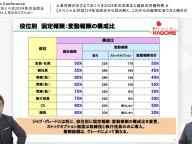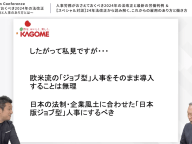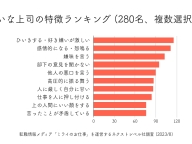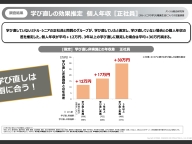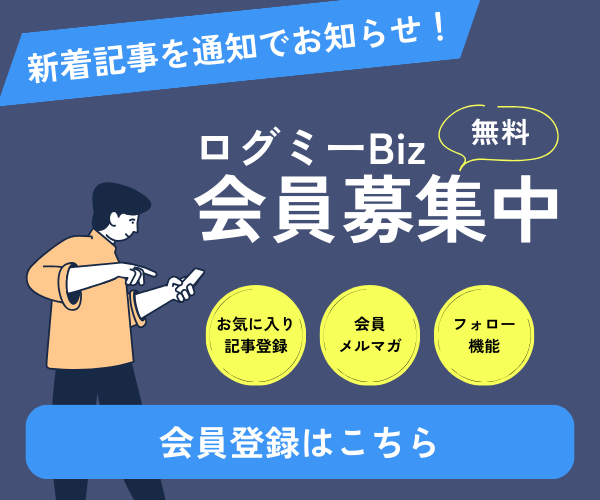トップレベルの環境での切磋琢磨を目指し東京大学に進学し、大腸がんのエキスパートを志し外科に
アマテラス藤岡清高氏(以下、藤岡):さっそくですが、自己紹介及び、現在携わっていらっしゃる役割を教えて下さい。
多田智裕氏(以下、多田):AIメディカルサービス株式会社のCEOの多田と申します。山内や青山と一緒に、この9月に創業しました。
山内善行氏(以下、山内):COOの山内です。多田とは私が以前に創業したQLife(医療情報サービス会社)時代からの付き合いで、多田がAIにチャレンジしていると聞いたのがきっかけで参画することになりました。
青山和玄氏(以下、青山):CTOの青山です。以前の会社で多田から仕事を請け負った縁が発展して、一緒に世のためになるビジネスをしたいと参画しました。
藤岡:まずはCEO多田さんにおうかがいします。医師を志した背景や、その後の進路についてのお話をお聞かせ下さい。
多田:東京大学に入学したのはトップレベルの環境で自身を研鑽したかったからです。大学では遺伝子の研究に取り組んでいました。
卒業後の専門分野は外科を選択しました。公益財団法人がん研有明病院の名誉院長でもある武藤徹一郎先生から、今後大腸がんが増えることや、それを専門でできる人がいないという話をうかがい、ぜひ取り組みたいと考えたのが理由です。
その後勤務した辻仲病院は、当時肛門外科で国内トップの症例数を誇っていた病院です。辻仲康伸先生には1年間マンツーマンで指導を受け、開業の際も支援をいただきました。
日本最大級の医療モールで胃腸・肛門科を開業
藤岡:「ただともひろ胃腸科肛門科」開業の経緯についても教えて下さい。
多田:さいたま市で日本最大の医療モールを作る計画があり、胃腸科の医師を探しているということだったので、そちらで胃腸・肛門科を開業しました。ちょうど私の側も開業地を探していた時でした。
藤岡:ご自身の病院でいまも現役の医師業をしながらAIメディカルサービス社の経営をしているということですね。
多田:はい、開業してから約11年です。その現場体験で困ったことがあったからこそ、当社を創業することになりました。
困りごとは大きく2つあり、1つは内視鏡医としてがんを見落とす怖さと常に隣り合わせで過ごしているということ、2つめは胃のバリウム検査が内視鏡による検診に切り替わることに伴いチェックする画像の枚数が大幅に増え、業務負担が増大したことです。 藤岡:臨床現場に問題意識の根源があったのですね。
多田:はい。さいたま市のがん検診ではバリウムが胃カメラに置き換わり、以前はバリウム:胃カメラが9:1だったのが今では2:8にまでなってきました。
撮影された画像の枚数も人間では処理しきれないほどに増えてきました。私が所属する浦和医師会だけでダブルチェック業務で診る画像は年間200万枚以上におよびます。多い時には担当医師が1時間で3000枚以上も目を通すことがあります。
この作業を1時間以上続けるのは正直無理。人間はそれ以上集中力が続きません。まして、専門医の少ない地域の先生方は健診現場で本当に苦慮しています。
その悩みを感じていた時に、AI研究における権威である、東京大学の松尾豊先生の講演を聞く機会がありました。「動物が目を持つように、人工知能が目を持った。人工知能の画像認識能力が人間を上回りはじめた。」という話でしたが、私の中でピンと来ました。
「これで現場の苦しみを解決できる!医療現場で人がさばききれない画像は人工知能にやってもらうべきではないか?」と。
ビジネスは何かと何かの組み合わせかと思いますが、AIと内視鏡の話が結びついたのです。
医師の技術格差で24%がガン見逃しの実態
多田:がんの早期発見、早期治療を阻む「壁」の一つは、医師による病変の「見逃し」の問題です。
大腸ポリープ、大腸がんの海外の研究報告例でいうと、「前がん状態」と言われる腺腫性ポリープの見逃し率は24%に上るそうです。これは、肉眼で見分けにくい病変や発生部位があるため、および医師に技術格差があるためです。
また、別の研究では、大腸内視鏡検査をうけていたにもかかわらず、後に大腸がんにいたるケースが6%もあり、その原因の58%が「内視鏡検査時の見逃し」だと報告されています。
AIを活用した「リアルタイム内視鏡診断サポートシステム」が実現すれば、大腸がんの見逃し防止の有望な選択肢となるかもしれません。
多田:AIが瞬時に病変を検出し、「ガンがここにあります」と場所まで特定してくれます。 「顔認証技術」や「病理画像解析」の技術を応用して、深層学習(ディープラーニング)により病変かそうでないかの見分けがつくようになりつつあります。
藤岡:先にAIありきではなかったのですね。
多田:もし誰かがやっていたなら私がやる必要はなかったのですが、調べてみたら誰もやっていません。内視鏡自体が日本で開発された医療機器ということもあり、海外でも研究は遅れているようでした。
「それなら自分でやってみよう」とエンジニアの青山と一緒に取り組みを開始しました。試行錯誤するうち比較的短期間で充分な精度が出てきましたので、「よし、本格的にビジネス化していこう」と、山内に声を掛けた次第です。
参画の動機は世の役に立ちたいと考えたこと、世界のマーケットに直結するビジネスであること、そして魅力ある起業メンバーであったこと
藤岡:では、青山さんと山内さんにうかがいます。AIメディカルサービス社に参画したきっかけや動機についてお聞かせいただけますか。
青山:知人経由で多田からの仕事を請け負ったのがきっかけで知り合い、そのときに作ったプロトタイプで内視鏡画像をピロリ菌陰性陽性のAI判定したところ、とても良好な結果が出ました。医師平均を上回るものでした。
自分のスキルが人の命を救うことに役立つと感じましたし、やるならすぐに取り組む必要があると考えたので、創業に至りました。
山内:QLife時代から多田とは共通の友人を介して付き合いがあり、すでに信頼関係はありました。その人がAIにチャレンジしていると聞いて、興味を持ちました。
最終的にビジネスとして参画するに至った理由は2つあります。
1つは世界のマーケットに直結する高速道路が見えていたことです。医療は国内市場でさえ日本企業のプレゼンスが年々狭まっています。
そんな中、内視鏡は出自がそもそも日本発であり、世界シェアも日本メーカーが7割を占めています。加えて、内視鏡を使っているドクターが海外より多いぶん、臨床の知見の厚みも世界で群を抜いています。
日本で実用化すれば、世界がすぐさま受けいれてくれる素地があるのです。
2つめは、多田と青山という2人の人間をみて、2人とも人を呼び寄せる人格があるなと思ったことです。ベンチャーは人が全てです。「この人のためだったら」と集まってくる、そういう人がコアにいるかが大変重要です。
彼らと実際に会って何度か話すうち、人を惹きつける力があると確信しました。
藤岡:山内さんにとくにおうかがいしたいのは、ご自身が創業されたQLife社をエムスリー社に売却されて余裕のある生活を送れるはずなのに、敢えてスタートアップのハードな環境に再び身を置かれたのはなぜですか?
山内:内視鏡の第二世代、「内視鏡2.0」を自分たちが作れるかもしれない、これはすごいことだという直感です。
内視鏡自体がそもそも大発明です。昔から医師はカラダの中を目で確認したくて仕方なかったのですが、古くはX線が発見されて、これは第1回ノーベル物理学賞になりました。内視鏡も、消化管という私たちのカラダのなかを通っている管の内側を、メスを使わずに見れるようにした画期的な技術です。
そして今、内視鏡の「眼」が精巧にデジタル化されつつあります。あるいはカプセル内視鏡といって、ゴクンと患者が飲み込めば、普通に生活をしていても勝手に大量の画像を撮影してくれるものが実用化されています。
デジタル解析する対象のデータが爆発的に増えており、これはAIの得意分野と合致しますから、まさに内視鏡の第2世代として革命的なことが起きるのです。世界中でコスト10分の1で内視鏡が大々的に利用されるようになり、病気をスクリーニングできるようになるでしょう。
1.0から2.0への不連続の階段を上ることに直接関わることができるなんて、千載一遇の大チャンスじゃありませんか。「リタイアなんてしている場合じゃない!」と焦りましたね、むしろ。
起業の壁は、資金よりも、技術面で世界初の一歩を踏み出せるかの見極めだった
藤岡:多田さんにおうかがいします。医療ベンチャーの立ち上げにあたってはいろいろな壁があったと思います。どのように乗り越えたのか教えて下さい。
多田:まず資金面ですが、クリニックを10年以上経営しており多少の蓄えができていたので、初期段階の研究は自己資金で工面しました。
当然ビジネス化の段階となると億単位の資金が必要になりますが、こちらも、ベンチャーキャピタルのみなさんから非常に高い評価をいただいており、すでに10社以上から大きな金額でラブコールをもらっているため、あまり心配はしていません。
むしろ技術的な壁の方が、起業にあたっては大きかったと思います。ピロリ菌や胃がんの検出をプロトタイプでどの精度まで出せるか、です。運もあったと思いますが、その壁を青山と研究チームのみなさんがよく乗り越えてくれました。
藤岡:技術的な手ごたえがあったために、起業に踏み切れたということですね。
多田:はい、2017年1月に青山がプロトタイプ作成に着手しました。最初はビジネス開発ではなく、あくまで普通の研究活動として、頑張って世界で初めてのことを実現しようぜという感覚でした。
進めるうち、幸いにも精度の高い検出率が出たものですから、全世界に通用する技術に育てられるぞという手応えを感じるようになりました。これなら臨床現場で使える、ビジネスにもできる、と。