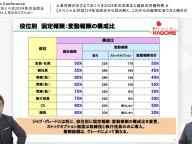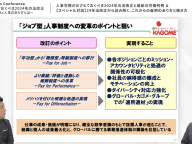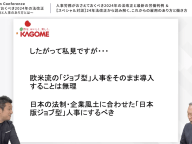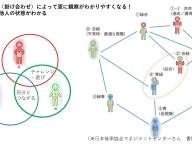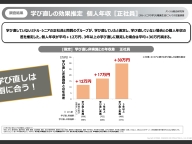ベテランには思いつかない表現技法がある
浜田敬子氏(以下、浜田):(BuzzFeedの)古田さんのところも、男女も半々だし、意識的に国籍もいろんな国の方がいらっしゃるということなんですけど。
それが実際の編集やコンテンツをつくるうえで、どんなふうにおもしろくなるのか。さっきも国会の議論の話をされていましたが、もう少しそのへん、新しい価値としてどんなことが生み出されているか、お話いただいてもいいですか?
古田大輔氏(以下、古田):例えば、BuzzFeedで書いた、iPhoneXやiPhone8の記事を読んでいただいたらわかるんですけれども。
めちゃめちゃビジュアルはわかりやすいんですよ。GIFってわかりますか? ちょっとカクカク動く、動画っぽくつくった写真の短いスライドショーみたいなやつですね。
あれをうまく配置することで、文字だけではぜったいに表現できない、めちゃくちゃわかりやすいiPhoneXの記事があるんですよね。見たらぜったい買いたくなると思うんですけど。その記事を書いたライターも20代の女性なんですけれども。
彼女は、どんなにiPhoneXのスペックに詳しいベテランライターでも書けないものが書けるんです。使い手目線だから。使い手目線から見たら、このiPhoneXの機能をどうやって見せるのが一番効率的かを、突き詰めてちゃんと考えてるんですよね。その結果彼女が選んだのがGIFで。
そういことも、文章を書くことを生業にして、当たり前に10年20年キャリアを積んできた人たちだけで書いていたら、ぜったいできない記事なんですよね。
今、BuzzFeedは、テキストだけではなくて動画やライブ配信にどんどんウイングを広げていっています。別に、「今の時代は動画だから」ということで発信しているわけではなくて。ただ単に自分たちが今から表現しようとしてるものが、どう表現をしたらオーディエンスは最高に受け取ってくれるか、最高に刺さるか、ということを考えてるんです。それで新たな表現技法に踏み出していく。
でも、新たな表現技法に踏み出していくときに大切なのは、その表現技法を普段から使っている人たちが、チームのメンバーのなかにいないといけないんですよね。その人たちに自由にやってもらう。
自分にはよくわからなくても、誠実なコンテンツなら取り入れる
古田:それをもし、40代の「私は経験積んできたから」みたいな、例えば僕みたいな人間が、「いや、お前こんなのよくわかんないよ」みたいな言い方をしたらダメなんですよね。
僕は編集長をやってて、うちのコンテンツ見ながら3割ぐらいのコンテンツは、あんまり理解できないんですよ。「何なんだろう、これ?」って思うんですけど。でも、それが間違っていなくて、人を傷付けるようなものではなくて、嘘をついていない誠実なコンテンツだったら通すんです。
そうすると、それが例えば10代の女性にうけたりするんですよね。当たり前の話で、10代の女性が喜ぶものが僕にわかるはずないんですよ。そういうことからも、さっき言ったようなバックグラウンドや考え方の柔軟性を、どれだけ取り入れるのかということが、そのコンテンツのおもしろさに繋がると思います。
僕ら、新しいプラットフォームが生まれたら、「InstagramのStoriesをどうやって使おうか」とか、そういうことをよくみんなで話すんです。そういうときも、普段からInstagramのStoriesを使っている人間がチーム内にいないと、話がはじまらないんですよね。
アラフォーのおっさんがInstagram Storiesの使い方をみんなで議論しても、まあ、ろくでもないものしか出てきません。そういうところが本当に、いろんな人が集う強さかなって思います。
社外といっしょにやるって本当に素晴らしいことで、今の時代、必然だと思うんです。僕らだったら、例えばアメリカではテレビ局といっしょにやったりしてるんですけど。日本はまだそこまでいってなくて、早くはじめたいと思っています。
今だったら、ソーシャルメディアのハッシュタグを使えば、既存のハッシュタグでオーディエンスといっしょにコンテンツをつくり上げていくこともできるし。もしくは自分たちから新しいハッシュタグを仕掛けて、1本目は僕らが書く。そうすると自然と、いろんな話が持ち上がってくる。それをもとに今度は、それを取り入れたものを書くとか。そうやって、どんどん多様性を取り込むようにしてますね。
そのときに「できること」が「やりたいこと」になってくる
浜田:私も、紙のメディアからネットメディアにいったら、ネットメディアのほうがやっぱり読者との壁打ちの速度が早いので取り込みやすいですよね。紙だと立ち読みで(笑)。中村さんはすごく、それをストックされているということもありますが。なかなか、そこの打ち返しがなかったものが、ネットだと時間も早くなって、多様性を取り入れやすいなって、すごく思います。
そういう意味で時代ってすごく変わってきていて。とくにBuzzFeedは、ネットメディアのテクノロジーを駆使していらっしゃると思うんですけれども。いろんな時代の変化があるなかで、例えば今一番大きな変化はテクノロジーだと思います。
中村さんはずっと「ミーハー」ということで、ご自身の価値観とかやり方は変わっていないかもしれないですが、ビジネスとしては少しずつ変えていかないと、時代に合わなくなってしまうと思います。「少しこういうこと変えてみようかな」とか、その辺は、なにか意識していらっしゃることありますか? とくにグローバルという視点は先ほどもおっしゃっていましたけれども。
中村貞裕氏(以下、中村):そうですね、あんまり変えなきゃいけないという意識はないんですけど。おのずと変わっていっています。
「変わっていって」というか、増えていっているだけで。僕が起業したときは30代で、30歳のときにやりたかったことは、今、うちの30代のスタッフがやってくれてて。
なんか、やりたいことって、「できること」が「やりたいこと」になってくるんですよ。やりたいことが早く見つかっちゃう人はプロフェッショナルとしてずっとやっていく人で。僕みたいな人って、できることがやりたいことになるんです。会社にホテルのスタッフが増えればホテルをやれるからホテルやりたいな、と思うし。
「bills」や「MAX BRENNER」を運営して海外ライセンスのノウハウが溜り、海外ライセンスの仕事ができるのでそれがやりたいことになってきたんですね。会社の成長や、優秀なスタッフが揃えば揃うほど、僕自身はできないんですけど、会社としてできることが増えていくので。
会社としてできることが増えて、代表としての僕のやりたいこともどんどん増えてきちゃってて。でもそれって、時代のタイミングがあって、やり残しちゃうことがたくさんあるんですよ。
自分がやり残したことは、次の世代の社員がやってくれる
中村:例えば、3年後にやりたいことがある。3年後にはもっとできることが増えているので、やりたいことも増えてしまうと思うんです。それに、自分でやったことが追いつかなくなっちゃうことがあって。
そうするといろんなことをやってるように見えても、やれなかったことがどんどん増えてきちゃうので。会社も大きくなってやれることが増えれば増えるほど、やり残したことが増えてきちゃって、僕のストレスが溜まるんです。
時代の流れと、残りの仕事をこなせる数とか。規模も大きくなれば1個1個のプロジェクトが長くなるし。
ちょっと質問忘れちゃったんですけど(笑)。
浜田:(笑)。でも、そのストレスはどうしてるんですか? 「やれないことが多い!」っていうストレスが溜まるんですよね。
中村:僕自身はやれないんですけど、会社としてやれるんですよ。そうすると、僕が40歳でやり残したことを、40歳の社員にやってもらってるんで。だから会社的にはやっているので満足してるし、(やり残したことを)切り捨てることもありますし。
浜田:いろんな年代がいることで、中村さんが40代でできなかったことは次の世代がやってくれる、と。そういうことで、会社としては、中村さんの胸を晴らすじゃないですけど(笑)。
中村:そうですね(笑)。最終的には、それが会社のなりたいところだと思うんです。僕がやり残したことを残りのメンバーがやりこなしてくれるというイメージで。なので、僕は代表として、ひたすら僕がやりたいことをやり続けてるだけです。
会社はそれだけだと成り立たないので、僕がやり残したことだったり、僕が今やりたくないけど会社ができることをやっています。何か1つでも減らすということはあんまりなくて、どんどん領域が広がってるだけなんです。
浜田:なるほど。
中村:世の中的には僕が代表なので、僕がやってることが目立ってるかもしれないんですけど。僕がひたすらやってるだけで、会社はチャンスを1個でも減らすことなく、やり残したこともコツコツとやっていってるんですよ。
時代に乗る、乗らないはあまり意識していない
浜田:なるほど。今日来ていただいた3人の共通点は、「世の中に新しい価値をつくる」。普通、起業のことをゼロイチと言いますけど、ただ起業するだけじゃなくって、中村さんだったらカフェの文化とか新しいレストラン文化を日本につくる。古田さんは新しいメディアをつくる。後藤さんは、新しく地域などの環境をデザインする、みたいな今までにないような仕事自体をまさにつくっていらっしゃると思うんですけども。
そういった新しい仕事をつくるなかで、時代との共生と言ったら変ですけど。時代が変わっていくなかで意識していらっしゃることはありますか? 「多様性が大事だよね」と言われてきたのも今の時代だと思いますし。「スピードが大事だよね」と言われているなかで、むしろ「自分たちはそこには与(くみ)しない」とか。
時代に乗っかるところと、時代には巻き込まれないようにするところって、意識していらっしゃいますか? ちょっと抽象的な質問なんですけれども。
後藤太一氏(以下、後藤):たぶん、あんまり意識してないです。
浜田:そうなんですね。直感的に。
後藤:わりと自然にまかせてる。僕は、後付けでぜんぶ肯定しちゃう性格なので。「俺がやってきたことは正しかったんだ、よかった、時代が追いついてきた」みたいに思っちゃうタイプなんですよ。
浜田:なるほどね(笑)。
後藤:なので、例えば僕、20年前にポートランドの行政に飛び込んで働いて、24人の部署のうちアジア人1人、黒人1人、あとぜんぶ白人という時代だったんですよね。行政で、英語はネイティブじゃなくて、でも生き残ったんですけど。それを思い出したときに、さっき中村さんがおっしゃったようにやっぱりもう「地域の時代だ」と思ったんですよ。もう、国家じゃない、と。
最近になって、アメリカでも「国家じゃない」とか言い出して、世の中みんな「そりゃそうだよね」って思ってるわけですよね。でも、じゃあ(自分が)考えてやったかというと、そうでもなくて。そのときの24歳の私は「その経験が一番いいはずだ!」と思って行っただけなので、あまり戦略的じゃないんですよね。
今やっていることも、例えば、妙に食に関する仕事が多い。あとは、自治体とも仕事してるんですが、日本的なよさでみると、自治体よりもいっぱい資産を持っている鉄道会社のやっている街づくりって世界にいけるな、と思ってるんです。これも、前から思ってたんですけど、最近みんなそんなことを言っているので、「そうだね」と思ってるだけで。あまり意識していないです。
意識しているのは縁を大事にすること
浜田:その直観力みたいなものって、どうやって養われたんですか? これも後付けかもしれないですけど。
後藤:後付け力でしょうね、どちらかというと。先月ヨーロッパに行ったときに、衝撃というか「そうだな」と思ったのは、「アメリカ人は別にポートランドがいけてるとか思ってないよ」とか。
浜田:でも、日本で大騒ぎしてますよね。
後藤:「ドイツ人は別に、ベルリンがイノベイティブだと思ってないよ」と。「そりゃ悪い都市じゃないけど、あんなんいっぱいあるよね」みたいなことを言われて。「そうなんだ、日本ではすごく話題だよ」って言って。「それは日本で本が出てるからだ」とか言われて。「そりゃそうかもね」と。
ただ、そんないやらしい言い方をしなくても、確かにどこの街にも魅力はあるし、おもしろい人はいるので。素直に、オープンに、好奇心を持って付き合っていれば、いろいろできるんじゃないかな、と思っています。
例えば、神山も、渋谷も、福岡の事務局長を降りた日に電話がきたから付き合ってるんです。
浜田:なるほど。すごいですね、スピードが。
後藤:「君が福岡以外のこともできるようになったから」って言われました。そういうのも単なる縁だと思うので、縁があるところを大事にするというくらいにしか、たぶん考えてないです。すみません、こんな社長です。
都市マネジャーという職能をもった人が働いている状態をつくりたい
浜田:中村さんも後藤さんも、好奇心があって、おもしろいと思ったら自ら動くとか、自ら見に行くとか。我慢しないで「好き」「おもしろい」と言う感覚はすごく大事にしているということですね。
後藤:ちょっとだけ足すと「宇宙から見てるみたいな自分がいる」と言ったんですが、世界中の都市に、都市マネジャーという職能をもった人が働いている状態をつくりたい、と20年前から言ってるんですよ。
浜田:なんでそんなこと思ったんですか?
後藤:アメリカで目の当たりにしたから。
浜田:へえー。ポートランドで?
後藤:やっぱり、政治や経済のサイクルを乗り越えて、地域が発展していくためには、プロとしてそこに関わる人間が要る、と。
浜田:おもしろい。
後藤:それは副市長かもしれないし、デベロッパーかもしれないし、商店街の会長かもしれない。ただその職能が日本はなくて、「シティマネージャー=市長」なんですよ。
浜田:はい。
後藤:そこに傭兵部隊で入る人間がいたり、民間がそれをやるという状態ができたらいいと思うし。もっと言うと、アジアって、20年前は首都以外はみんな今ひとつで、ぜんぶ首都が独占してた。それを変えたい。だから福岡に行ったんです、実は(笑)。
そういうことは妄想してました。それとは別に、今、云々というのはかけ離れているかもしれないですが。
浜田:でも、妄想がある程度、本当に実現していますよね。
後藤:後付けです。
浜田:妄想するってけっこう大事なんですよ。
後藤:妄想しないものはできないので。
浜田:できないですよね。
後藤:それはそうかもしれないですね。
メディアはテクノロジーの最先端の波に乗っていかないと生き残れない
浜田:古田さんはどうですか? 今、新しいメディアをつくっていらっしゃるんですけども。逆に時代がBuzzFeedに乗っていて、時代の波のなかでおもしろい価値観をつくってきてると思うんですけども。時代というものを、どのように捉えていらっしゃいますか?
古田:僕は、すごく考えます。メディアの場合は、本当にそうしないと簡単に死んじゃうんですよね。10年生き残るメディアって、本当にこれから先少ないと思うんですよ。3年、4年ならなんとかなると思うんですけど。でも10年生き残るって、本当にこれから大変だろうなって思っていて。
僕、BuzzFeedに入るときに誘ってもらって、CEOのジョナ・ペレッティとニューヨークとの間でテレカンしたんですよね。最終面談みたいな感じで、1回しか面談なかったんですけど(笑)。
それでお互いにいろいろ質問して。僕も不安だからいろいろ聞きたいし。僕が最後に聞いたのが「今、BuzzFeedはグローバルなメディアになってるけど、5年後にどういうメディアにしたいと思ってるの?」というふうに質問したんですよ。
BuzzFeedってこの5年ぐらいで本当にドーンと大きくなって、グローバルなメディアになったんです。それまではニューヨークのちっちゃなメディアだったんですよ。それを5年でこれだけ大きくしたんだから、「じゃあ、5年後どうしたいと思ってるの?」って聞いたら、ジョナ・ペレッティが言ったのが、「わからん」と。
なぜなら、「5年後のインターネットなんてもう凄まじい勢いで成長してるだろうから、今から5年後のプランを完璧に立てるなんて無理だ」と。「そのときどきに合わせて、生き延びて成長していくしかないよね」と言っていて。「軸の哲学はぶらさないけれども、どうやって生きていくのかというハウトゥーのところは柔軟にやっていくしかない」と。
僕もその通りだな、と思うんです。そのなかで、今のメディア環境がどう変わっていくのか。今のテクノロジーがどう変わっていくのかを、しっかりと勉強しながら最先端の波に乗っていかないといけない。
いまだにテキストのニュースが人気なのは日本だけ
古田:もう1つ勉強しないといけないのが、決して、世界の最先端の波と日本の最先端のメディア環境が、いっしょではないということ。
浜田:そうですね。
古田:すごくおもしろかったのが、つい先月ロイターが1年に1回出しているニュースメディアレポートみたいなものがあるんですけど。そのアジア代表版が出たんです。
それを読んでいたら、1行目にドーンと大見出しで「日本だけ! いまだにテキストのニュースが人気」って(笑)。ほかの国はぜんぶ動画に変わったのに、日本だけめっちゃテキストが人気というのを指摘するところから入ってるんですよね。
そういうなかで、僕もそれは気付いてたし、テキストが大好きなんですけど。でも、「それだけだとおもしろくないよね」と。テキストでは伝わらない世界もあって、動画でしか伝わらない世界もある。それこそコンテンツの多様性ですよね。そういたものを日本に持ってきたいと思ったし、それも僕がBuzzFeedに移った理由の1つなんです。
時代をちゃんと捉えながら、今自分たちがいる場所を見て、足りないものってなんだろう、と。自分が好きだけどまだここにないもの。そういったものを日本に持ってきたいな、と思っています。
むしろ日本から、さらに生み出す。GIFでバンバン説明をするという記事を、海外のBuzzFeedのメンバーが「この記事いいね」って言ってくれるんですよね。だからそういうふうに、逆に日本から新しい表現技法を生み出していったりしたいな、と思ってますね。
人生100年時代、どんな「働く×人生」を歩んでいきたいか
浜田:ありがとうございます。みなさんにぜひ聞きたいのは、みなさん年代がちょっとずつ違うんですけれども。実は、この前のセッションが、「働き方で新しい価値観をつくる」というセッションだったんです。
これからご自身は、今のビジネスをやるかもしれないし、やらないかもしれないけど。今、人生100年時代と言われる長い時代で仕事やキャリアを積んでいくなかで、どんな「働く×人生」を歩んでいきたいな、と思っていらっしゃいますか?
ちょっと違う質問なんですけども、ぜひみなさんに聞いてみたいと思います。後藤さんからお願いします。
後藤:たぶん死ぬまで働いてるとは思います。別に、働くこと嫌いじゃないので。……旅行はしたいんですよね。
浜田:へえ。
後藤:自分が行きたい街を増やしたいという動機が、かなり根底にあって。そのためにいろんなシティマネージャーが世界中にいてくれて、各街を磨いてくれたらもっと楽しいのに、と思ってるんです。
浜田:なるほど。
後藤:今、飛び回ってるように見えるかもしれないけど、ライフステージ上はあんまり動けていないので(笑)。もうちょっと……体力は落ちてると思いますけど、時間が経っていったらもっとグルグル動きたい気持ちはすごくあります、実は。
そのときの関わり方はわからないけれども。今の歳でも思うのは、最先端のことをわかってるふりはもはやできないおじさんになってしまったな、と思うときが正直あって。
浜田:はい。私もです。
いい仕事をしている人との縁を大事にする
後藤:おもてに出たくないな、と。あんまり性に合ってないのはあるんです。どちらかと言うと、「風車の弥七」とか「次元」が大好き、みたいな。中村さんみたいな人がガーッと前にいってるときに、うしろにいるほうが居心地はいいんですよ。
だから、いっしょにやれる人とどれだけ知り合えるかというのが、すごく大事だと思っています。やっぱりおもしろいこと、いい仕事をしてる人との縁を大事にして繋いでいくと、人生100年、残りの期間も楽しくやれるかなと思ってます。
浜田:先ほどのセッションで、若い人にも伝えたい話で。60年、70年キャリアを続けるのは難しいので、自分が何がやりたいかみたいなことを見つけろと言われると、逆に「やりたいこと迷子」みたいになる。「好きなこと迷子」が、今すごく増えてきているんですけど。
後藤さんは、どうやって、自分がこうありたいとか、やりたい、を見つけられたんですか?
後藤:あまりそこは難しく考えてないですよ。基本的に人が、喋るのが好きです。あまり人のこと嫌いにならないんですよね。ほかには食べることが好きです。だらっとする、外を歩くとかも好きなので。そうすると飽きることはたぶんないんですよね。
浜田:なるほど。
後藤:一生かかっても、世界中すべての国に飛ぶことはできないので。だから自分についてはぜんぜん心配していなくて、むしろ、今関わってる人。会社のスタッフもそうだしクライアントもそうだけど、その人たちが次のステージに進むときに、「よかったな、いっしょにやれて」と。「でも、今はまた自分のやりたいこと見つけられた」みたいになっていくようなチームを、あちこちで関わるところ毎にできればいいな、とは思っています。
35歳で「折り返せてねえな」と思ったことが転機
浜田:ありがとうございます。古田さんは、40歳という若い年齢で編集長になられて。私なんか、あとはどうするだろう? って思うんですけど(笑)。余計なお世話かもしれないんですけど。私はもう50歳でネットメディアで疲れ果てています(笑)。どうですか? このスピードの世界で。
古田:僕は38歳で編集長になったんですよね。先月で40歳になったんですけど、編集長になって2年間。
村上春樹の『プールサイド』という短編があって。読んだことありますか?
そのなかで、主人公の男性が35歳になったときに自分の人生の折り返し地点に達したことに気付いたっていう一遍があるんですよ。僕、大学生のころにそれを読んで、「35歳って折り返し地点なんだ」って思ってたんです。
それで、35歳になったときに、当時シンガポール支局長で、マレーシアのすごい田舎町に取材に行っていて。そこのホテルで1人で誕生日を迎えて。「折り返せてねえな」って思ったんですよね。「何もしてないな」と。何も自分のなかに積み上げているものはないし、何の専門性もないし。本当に、「俺はこれを成し遂げた」というものがとくにない。
折り返せてないから、40歳までに折り返そうって思ったんですよね。そのときに、じゃあ40歳までに何を折り返せるかな? って思って。思ったのがインターネットの世界に行こうと思ったんですよ。もともとインターネット大好きだったし、やっぱりそのとき紙の新聞記者をやってて紙の凋落、限界にも気付いてたし。今、日本で足りないのはそっちだな、と思って。それもあってデジタルの部門に移ったんですよね。
「世の中ってあんまり捨てたもんじゃないよ」ということを伝え続けたい
古田:今はそこから、自分が持っている個性。ストレングスファインダーでいうストレングスを、自分のなかで考えて。ポートフォリオを組んで、キャリアパスを考えていって。インターネットの世界で自分の記者としての経験と力を活かしつつ、同時にインターネットをずっと追いかけてきたから、その知見を足し合わせたことをやって。
そうするとBuzzFeedから声がかかって、今はBuzzFeedの編集長になって。より世界と密接に繋がって、世界の動きを日本に持ってくることができるようになって。
今の僕がやりたいことは、編集長という責任ある立場になったので、まずはBuzzFeedが永続的にちゃんとまわるモデルにすること。たとえ僕がいなくなったとしても、きちんとその組織が日本に根付いて、ずっと発展を続ける体制にすることが、まず僕の第一にやることだと思うんですよね。
それが終わったあとは、まあ……そうですね。自分で何かまた別のことをはじめるんじゃないかな、と思うんですけど。
ただ、根本的に僕がずっと思ってるのは、僕は20歳のときにこの業界に行こうって決めたんですけど。そのときに決めたのは、当時、インドでボランティアをしていて、格差とか貧困の現場をずっと見ていて。そのなかで、僕はこれに対して何かをしたいと思ったんですよね。
でも格差とか貧困の現場って、日本にもいっぱいあるし、世界中にあるじゃないですか。どれかを選びきれなかったんですよ。僕、当時、いろんなところでボランティアやってたんですけど。
どれか1つ選べないな、と思って。でも、そういう問題が世界中とか日本の全国にある一方で、そういう問題に対して一生懸命がんばってる人たちもいるから。「世の中ってあんま捨てたもんじゃないよ」ということを伝えることが一番、自分にとっていいことじゃないかなと思って。
それで記者という職業を選んだんですよね。なのでそこは、もうおそらく死ぬまで変わらず何かを伝える、ネガティブな問題もあればポジティブないいところもあるよ、ということを伝える仕事をやりたいな、と思ってます。
人への好奇心が仕事のモチベーション
浜田:ありがとうございます。中村さんは、ずっとミーハーでい続けられる自信がありますか?
中村:そうですね。僕の仕事のモチベーションは、人との出会い。実際に出会った人もいるし、あの人と仕事したいなということもあってそのために仕事をつくったり。あとは自分よりいろんなことができる人との出会い。ある特化した部分でもいいんですけど、そういうできる人に出会うと、さっき言ったように、その人といっしょにやれば自分が「できる自分」になるわけじゃないですか。
そういう人との出会いとか、人への好奇心が僕の仕事のモチベーションだし、それをポジティブなワーカホリックって言ってるんですけど。僕の今の仕事をしていると、どんどん人に会うじゃないですか。なので、僕の性格上、おのずと仕事をしたくなっちゃう環境にあって。なにかをきっかけに、本当に人嫌いになっちゃったりすれば、僕の仕事がとまると思うんですけど(笑)。
浜田:そうですね(笑)。あるときないんですか? 会いたくないとか。
中村:いや、なんにもなくて。とりあえずこう……そこがミーハーのゆえんだと思うんですけど。なんか能力を持ってる人にものすごく好奇心があるんですよ。
浜田:(笑)。会わずにいられないみたいな。
中村:そうですね。もう話しかけますし、会うんだったらちょっと調べて、このような仕事ができるんじゃないかなって考えたり。さっき言った妄想じゃないですけど、この人と組めば何かできる、みたいなことを常に考えています。
そういう人への興味や知識がなくなったら……、まあ、性格上、なくなることはたぶんないと思うんですよ。なのでずっとモチベーション上がって、ずっと続けてるんじゃないかな、と。
文化をつくり街を変えていく仕事にふさわしい肩書とは?
中村:じゃあ、僕なりに会社をどういうふうにしていきたいか、ということですけど。僕の肩書きって17年前にはじめてカフェをつくったときは「カフェオーナー」みたいな感じで紹介されていたんです。その次に「クラスカ」や「THE SOHO」などを手掛け、空間のいろんな仕事をしはじめて「空間プロデューサー」みたいに言われて。
それが「ちょっと違うな」と。なんか、昔のバブルのはじけちゃった職業なんじゃないかな、と思って。あえてそれを言われないようにしていて、どうしても雑誌の取材をやると、「なんて書きますか?」って聞かれて……それで「空間プロデューサー」になっちゃったりして。そうこうしているうちに、「パンケーキの人」になっちゃって。
浜田:ははは(笑)。
中村:なんか最近は「かき氷の人」みたいになって、ちょっと迷走したんですけども。僕の肩書きって「TRANSIT GENERAL OFFICE 代表」とかはあるんですけど。3年ぐらい前に海外に行ったときに、海外では会社名とか関係なく、何をやっている人かという感じになるので。
そのときに、「プロデューサーじゃないんだよね、中村くん」って海外の人に言われたんです。プロデューサーというと、映画プロデューサー、音楽プロデューサーで。ブロードウェイとかつくって、チームをつくって終わりで、さあ次みたいな。
「中村くんみたいにカルチャーを作り、運営もオペレーションもする人って、カルチュラルエンジニアと言う」って言われたんですよ。
浜田:おもしろいですね。
中村:僕、Ace Hotel(エースホテル)を6年ぐらい前につくった代表の人に会って。そのとき、名刺がCEOって書いてあったんです。だから、代表だなと思って見たら、「Cultural Engineering Officer」って書いてあって。
その人がつくった言葉かな? と思ってたんですよ。でもカルチュラル・エンジニアリング・オフィサーはたぶんその人がつくったんですけど、カルチュラル・エンジニアというのは海外でけっこう通じる言葉で、イメージが湧くらしくて。
それ以来、僕の会社はカルチュラル・エンジニアリング・カンパニーになろう、と。僕らがやったことがそこで文化をつくって、街を変えていくような、なにかのきっかけになるようなことをカルチュラル・エンジニアとしてやっていきたいな、と思ったんですよ。
「どうやってグルーピングして大きな波をつくるかが僕らの仕事」
中村:プロジェクトがカフェ2個ぐらいだと(波は)できないんですけど、同時多発にいろんなことをやっていると、それがアメーバのようにくっついて、はじめて大きな波にできるんですね。
もちろん僕らのコンペティターともくっついて。それは、僕のプロモーションのやり方の1つなんですけど。例えば、GAPとZARAとH&Mとか、1個1個のときはパワーはない……もちろんあるんですけど、ライフスタイルに影響を与えるトレンドになるかというと、それがぜんぶ揃ってファストファッションとしてアメーバのようにくっついて、大きな波になるじゃないですか。
なので、僕らは常にどのグルーピングができるかなってことは考えてるんですよ。僕らのなかのプロジェクトでもグルーピングしますし、コンペティターがやっていることもグルーピングとして飲み込んで。同じグループだったのに、急に敵のグループになったりもするんです。
そうやって、どうやってグルーピングして大きな波をつくるかが僕らの仕事です。僕の会社も、だいぶいろんな実績が出てきたので、やっとそういうグルーピングができる手持ちと、コンペティターの人たちが見えてきました。なので、そういう人たちと組んで、ライフスタイルに影響を与えるカルチャーをつくるような会社にしていきたいな、と思っています。
僕のなかでは、さっきの都市それぞれのキーパーソンがいて、マーケティングするとき常に(意識しています)。シンガポールにもカルチュラル・エンジニアがいるし、カルチュラル・エンジニアリング・カンパニーもあるし、ニューヨークはもちろん、ブルックリンにも、ロンドンにも、パリにも、台北にも、韓国にも。
「カルチュラル・エンジニアリング・カンパニー」であり続けたい
中村:いろんな業態やジャンルはあるんですけど。僕がイメージしているカルチュラル・エンジニアリング・カンパニーって、だいたい2、3社あるんですよ。その人たちのやっている仕事って、すごく影響力があることをやっているのが見えてくるんです。
僕は海外に行ってマーケティングするときには、まずその国、その地域のカルチュラル・エンジニアだったり、カルチュラル・エンジニアリング・カンパニーを調べます。そして、最終的にはその人と仲良くなるルートをつくって、仲良くなるといろんな情報が入ってくるんです。
シドニー、台湾、シンガポール、ニューヨークなど、僕が思うカルチュラル・エンジニアとかカルチュラル・エンジニアリング・カンパニーとは、すごくみんな仲がいいんですよ。なので、それが僕のすごい財産で。日本とか東京でもそういう会社はたくさんあるんですけど、うちの会社もそういう会社でい続けて、そういう会社になりたいな、と思っています。
で、最近、カルチュラル・エンジニアリング・カンパニーと言い続けてるんですよ。いまいちカルチュラル・エンジニアカンパニーって言葉が馴染まなくて浸透してないんですけど(笑)。とりあえず、こういうところで言い続けて浸透させようかな、と思っています。
浜田:ありがとうございます。みなさん、打ち合わせ0分のセッションだったんですよ(笑)。何を聞くか質問も決めてなくて。みなさん、無茶振りにも答えていただきましてありがとうございました。
お時間になりましたので、お三方に大きな拍手をよろしくお願いいたします。
(会場拍手)