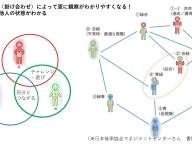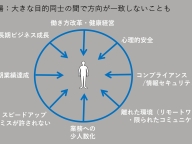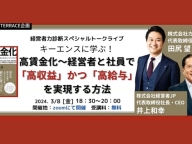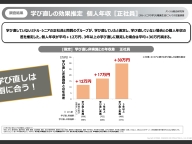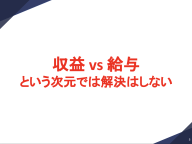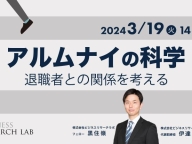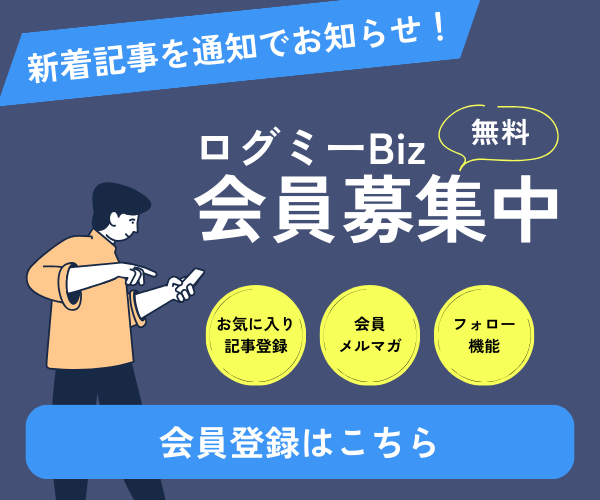私はとても身体的な人間
――ちょっと戻りますが、昨日あなたが他のカメラマンとスチール撮影をしているのを見ました。あなたはジャズをかけていましたね。それはほとんど音楽的体験のようでした。あなたにとってなぜ音楽が重要なのですか?
カルメン:音楽は神経をリラックスさせてくれるの。それから、音楽は感情の中心を打つの。それはダンスから来ているものよ。私はとても身体的な人間なの。後になって学んだことなんだけど。
土曜日の絵画教室に行くために母が私をベッドから連れ出してくれたところまで戻らないといけないわね。その絵画教室が終わったら、母は私をプールのあるパークセントラルホテルまで連れて行っていたの。母は泳ぐのが好きだったから。もちろん私も、私が産まれたウェルフェア島のイースト川に入れてもらった時からこのかた、ずっと泳ぎは続けていたわ。ウェルフェア島は今はルーズベルト島と呼ばれているわね。1931年の頃は、市立病院だったのよ。
このプールとホテルを経営していた女性が、私が泳ぐのを見たの。彼女は母に、「あなたの娘さんは水泳の才能がありますよ、ここに連れてきてくれませんか、私がコーチしますから」と言ったのよ。その女性はオリンピックで優勝したエセルダ・ブレイブトリーだったの。彼女が私を鍛えてくれた。私はそれが大好きだったわ。
もちろん、それはつまり、私がベッドから出ることができたということよ。そう、私は週に4回ベッドから出ることができた。医者の命令に背いてね。でも泳げば泳ぐほど、私の心臓は健康になっていったわ。彼女は私を水泳へと大きく引き入れてくれた。
――リハビリのようなものだったんですね。
カルメン:1948年のオリンピックに向けてトレーニングしていたの。選抜テストも受けたわ。その頃には私はAAU(アマチュア運動連合)の水泳選手だったの。西海岸でもう1人の女の子と競争しなければならなかった。でもその頃にしては、私の記録は速かったわよ。タイムは聞かないで。50メートル自由形でね。その時みんなが、私は背泳ぎもできるってことを知ったのよ。あらまあ、何の話だったかしら? 完全にそれちゃったわね。
――話を戻しましょう。寒かったりしないですか? 何か必要なものはありますか?
カルメン:ちょっと肌寒くなってきたわ。多分、少しね。
――少し温度を上げますね。
カルメン:ああ、あなたはそんなことないといいんだけど。あなたのために私のセクシーな靴を履かせてもらうわね。私、何か話そうとしていたんだけど。何の話をしていたかしら?
――ジャズ、水泳……ええと、ジャズ、水泳、オリンピックです。
カルメン:そうね。私たちがアストリアに住んでいた頃、無原罪の御宿りの教会とカトリックの教義を知った頃、全部私の人生のこの時期のことだけど、私はアストリアのプールに行ったの。そのプールは1931年だったか、確かにはわからないけど、オリンピックのために建てられたものだった。そのオリンピックはそのスタジアムで行われたのよ。
そこには3つのプールがあった。飛び込みプールが1つと…そのプールはすごく大きくて、プールショーのためにモーターボートを入れてウォータースキーを乗り回させたのよ。それから一番奥には子供用プールがあったわ。
6歳までに、私はそこでプールショーを運営していたヴィグ・ゾベルに目をつけられたの。彼はこう言ったの。あなたの娘さんは……あれはエセルダ・ブレイブトリーよりも前のことだったわ。話が逆になっちゃったわね。思い出がいつも時系列になってるわけじゃないから。本当にごめんなさいね。
ヴィグ・ゾベルが母のところへ来て言ったのよ。あなたがこのお嬢さんのお母様ですね。私のプールショーに、彼女を参加させてもかまいませんか、とね。母はもちろんです、と言ったわ。私たちはもう一度、無料で入場することができたの。私はその頃にはもう、3メートルの飛び込み台から飛び降りていたわ。
そのプールショーでの私の出番だけど、スタジアムみたいな感じの、立派なコンクリート製の観覧席で観客と一緒に座っていたの。全部コンクリートでできている16フィート(約4.9メートル)の台が1つ、26フィート(約7.9メートル)の台が2つあったわ。一番上には30フィート(約9.1メートル)の台が1つあった。ええと、私は観客の中で座っていて、6歳か7歳かそこらの子供だったわ。7歳以上ではなかったってことは断言できる。私の人生だからね。ゴリラが観客の中に乱入してきて、そこから私を引っぱり出して肩に担ぎ、一番上の台まで連れて行って放り投げたのよ。
――つまり、ジョークだったわけですね。
カルメン:慎重に投げてくれたわよ、もちろん。でもそれは私の母の能力なのよ。母は一風変わったステージママでね。彼女はもちろん…。
――彼女はあなたにパフォーマンスをさせて、それで彼女は…。
カルメン:そう。それは母を喜ばせ、母と一緒に過ごした私の人生を楽にしてくれたわ。母には私しかいなかったから。母は、とても一生懸命に働いていて、家に帰ってきた時は疲れていたわ。私は母の足をもんであげていた。私たちはそうやって共生していたのよ。