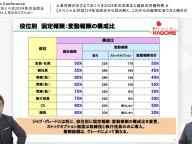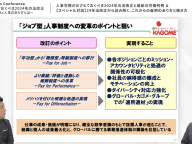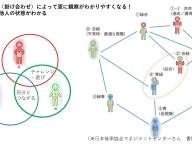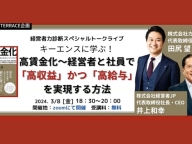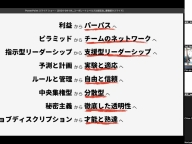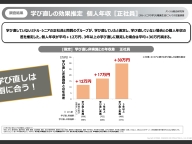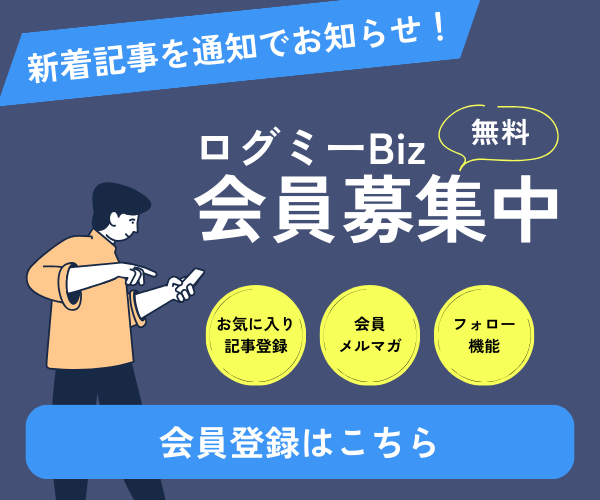西頭氏が追っているテーマとは
大堀航氏(以下、大堀氏):では、次は西頭さんについて聞いていきたいと思います。最近気になってるものとかキーワードとか、何かあれば教えてください。
西頭恒明氏(以下、西頭):自分は記者としてやってるときからずっと、ライフワークじゃないですけども、テーマにしてきたことがあって。どの業界を担当するときも1本軸にして考えていたのは、人材育成というところに興味があったんですね。
どうやって人を育てるのか、あるいは組織力を高めるのかっていう。そういうテーマの特集ってずっと意図的にアイデア出しして、やってきました、それでデスクのころにも、そういう企画のときには結構関わってきたので。人の育成とか働き方ですね。
今やっぱり、働き方ってすごく転換期にきてて、その部分はずっと永遠のテーマとしてありますね。人の育て方とか人事制度とかそういうものって、1つの正解がある話ではなくて、時代時代によって、結構揺れ動いてるものなんですね。成果主義だって走るときもあれば、成果主義はダメだから見直そうっていうふうになったりとかですね。1つの答えがあるわけではないので、永遠にテーマであり続けるっていうところに、若いときから関心があって。
今は別の働き方、ダイバーシティとか、本当にやらなければいけない局面にきていて。今までのダイバーシティって、結局いろんな従業員にいろんな環境作ってあげるっていうような考えのもとに経営者が取り組んできたんだけれども。
これからはそういうことに本当に、経営課題として、それがないと商品も売ることができない、お客さんもついてくれないっていう。社員のためにダイバーシティっていうだけじゃなくなってきてると思うんですね。
そのために働き方をどういうふうに見直さなくちゃいけないのかとかいう問題も当然あがってくると思うので、そこは今っていうよりも、ずっと関心を持ってきてるテーマなんですね。
それともう1つは、今日IT関係の方多いんで、AIとかIoTとか、そういう部分の進歩がどういうふうにビジネスを変えていくのかなっていうのは、興味がありますね。
大堀:そういう興味がある分野の情報とか、関連する取り組みをしてる会社は、自然と目がいかれるんですか?
西頭:やっぱり最近は、自分の足で稼いで取材する機会よりも、記者が書いた原稿を見るっていうことが多いので、一次的に情報を得るっていうよりも、記者の記事を通して、あるいは記者の話を通じて得ることが多いんです。最先端の動きをどれだけ把握できてるのかっていうのはありますね。
大堀:情報収集のされ方というのは、どういう感じでしょうか。新聞を毎朝全紙読むとか、どういう情報収集されていますか?
西頭:これも人によりけりなんだと思うんですけど、私は全紙は読んでません (笑)。見出しは他の競合誌のものは当然見ますよね。どういう見だしでどういうことやってるのかっていうのは。
大堀:ちなみに競合誌で取り上げていたものはやらないというのはありますか?
西頭:先に出されてしまうとちょっと時間を置くとか。あと、調べますね。さっきも言いましたけど、この時期にこれがあるからっていうので何か企画を打つ場合って、必ず他の競合社もそれを見てるはずだから。
なので、競合社が本当にそれをやろうとしてるのか、やろうとしてるんだったらいつ頃にそれをやろうとしてるのか。うちのほうが先にやるのか後にやるのかとか、そこらへんはいろいろ探ってはいますよね。
想いを伝える姿勢と視点
大堀:ありがとうございます。あと20分くらい時間があるんですけど、皆さんでこれだけは聞いておきたいっていうのは全部、お話しいただきたいなと思うので。先に質問ある方?
質問者:ありがとうございました。お話の中で、2.5人称っていう言葉がありました。要は会社として伝えたいことと、それが世の中的にどう伝わるかを聞いてみるっていうことだと思います。
記者さんは当然ずっとそういうふうにされてると思うんですけど、どうしても企業の広報にいると、プレッシャーというか重みがあって(笑)。それが濁っちゃったり、ないしは「これなら絶対通るだろう」と思って自信満々で2.5人称とか考えてもズレていたりとか、よくあるなと思っていて。
そこを鍛えるというか、チェックするなり、こういう考え方をしてるんだっていうのがもしあれば、教えていただきたいなと。
西頭:正解なんてないかもしれないんですが、そういう視点を持たなきゃって意識してるだけでも違うと思うんですね。だからそう思ってやってるんだけどズレちゃったりっていうのも、それに気づいてることだけでも、会社の論理だけで右から左に流してるのとは違うと思うんで。
そうやってるうちにだんだん、ブレとかズレがだんだん小さくなっていくんじゃないのかな。
私自身の1つの方法っていうか、原稿を出すときに余裕があるときにやってたのは、やっぱり記者ってすっごい夜型で、取材して夕方夜に帰ってきてから、ちょっと電話かかってきたり「ちょっと打ち合わせいい?」って声かけられるんです。それでどうしても原稿を書くのが夜になってしまうんですね。
夜書き始めて、うわーって書いて2時3時。そのままそれをデスクに送るんじゃなくて、寝かせて翌朝、もう1回冴えた頭で読み直して。それで修正して出すようにしてましたね。
やっぱり2時3時のときって、だんだん視野が狭くなっていくんですね。夜中に書いたラブレターがすごいラブレターになってしまうっていうようなノリで(笑)。1回寝かせて、もう1回冷静な目で読み直して出すっていうようなところは1つ言えるのかなと思いますね。
質問者:大丈夫です。ありがとうございます。
大堀:他にご質問のある方、いらっしゃいますか。
質問者:記者としての感覚といいますか、想いをどうやって表現されるか興味があるのですが。
西頭:誰もが想いないわけじゃないと思うんですね。この記者っていう仕事、あるいは広報の仕事と考えたときに、その仕事に対して自分なりの考え方っていうのは持ってはいると思うんです。
これはストレートな回答じゃないと思うんですけど、私自身はやっぱり、どんなものに対してもおもしろがる、まずおもしろがってみようって思うことを大事にしてみようと。記者に対しても、まずはおもしろがれって言っています。
それは、自分はこれが書きたいっていう想いがあって、それをそのまま書ける機会っていうのは、そんなに毎回毎回あるわけじゃないんですね。毎回毎回自分の書きたい思いで原稿書くには、フリーランスになればいい。
我々は会社の中で、組織の中で記者をしている、編集者をしているっていう以上は、その中でアサインされてやる企画もある。そういうものであっても、それを自分がやりたいと思ってやった仕事と同じようにおもしろがる。最終的にはおもしろがれなくても、おもしろがろうとするかどうかということが大事なのかなと。
おもしろがろうとすると、最初はおもしろくなさそうだなって思ってたものがおもしろくなってくることってあると思いますし。
最初から斜に構えてると、それはいい記事が書けない、いい取材もできないんじゃないかな。記者に対しても、おもしろがれと。おもしろがってたらおもしろい仕事になると思うし。
おもしろい仕事はあるけれども、毎回おもしろい仕事にあうとも限らないということですね。そういうものがあるからこそ、そのうち自分の想いを込められるようになって、そこで独りよがりじゃない、2.5人称の視点を持てば、読者にも伝わるんじゃないかなと思いますね。
質問者:どういうふうに2.5人称を伝えれば記事にしてもらえるんでしょうか。
西頭:経営者の人とかトップは、2.5人称は必要ないと思うんですね。広報の仕事というところで、あるいはその事業に携わっている人もそうですけれども、その経営者の想いとか事業に携わっている人の想いを伝えるとき。
経営者や携わっている人たちはストレートに自分の想いを伝えていただければいいと思うんだけれども、広報っていうのは、それが外に出るっていう時にある種フィルターの役割を果たしているわけですから。
そのときに「その想いをこういうふうにしてみるともっとよく伝わるんじゃないですか」とか、あるいは「外から見ればそれはこういうふうに受け止められてしまうんじゃないですか」っていうような視点を、広報の方は持つことが大事だなっていう。
でも、トップなり取材を受ける人そのものは、別に2.5人称とかを考えながら話す必要はないと思います。想いの丈を語れば、そこに経営者の魅力とか出てくると思いますし、その事業でのキーパーソンの方の仕事にかける、サービスにかける想いとか、事業の立て直しに対する想いっていうのが伝わってくるんじゃないかな。
質問者:ありがとうございます。
大堀:聞きたかったことの1つでした。思いが記者さんに伝わるのか、伝わるべきなのか。非常に、広報としては悩ましいのかなあと思いました。ありがとうございます。
時流に乗っているものだけが「なぜ今」ではない
質問者:ちょっとまだまだまとまってないかもしれないんですけれども、2.5人称の考え方、仰るとおりだなと思っていて、話を持っていくときに、「なぜ今」を考えなきゃいけないじゃないですか。自分が今やっていて、確かにそのサービスが生まれた背景が明確にあると「なぜ今」をきちんと語りやすいなと思っているんですけど。
今の時流だったりとかビジネスというところにおいて、「なぜ今」を第三者視点で上手く持っていけてないなっていうところをすごく感じていて。なので、ネタになりそうだな、記事になりそうだなって思ったときに、皆さんは「なぜ今」を、どういうところから引っ張ってきて形作って記事にしていくのかなっていうところに対してのアドバイスがあれば、ぜひお伺いしたいなと思っているんですけれども。
大堀:難しい質問ですね(笑)。
西頭:我々にとっての「なぜ今」っていうのは、まずその企画を通すときの必須条件なんですよね。だから記事そのものの中に、「今だからこれを書いてるんですよ」っていうのを、ストレートにぶつけてるわけではない。
ただ、それは伝わらないと読者は分からないでしょうから。今だからこれなんですよって言わないにしても、時代背景と繋げてみたりとか、今の課題と結びつけてみたりとか。
あるいは、世の中で今こういうものが流行っていると、必ずしもそれに乗っかるものである必要はなくて。今こういう世の中の流れなんだけど、それなのに今こういうことを始めるところがあるっていうのも、「なぜ今」になるんですよ。
世の中の先端をいってるものを取り上げることもあれば、あえて逆張りっていうのもあって。新聞と雑誌の違うところって、雑誌って逆張り好きなんです。新聞は順張りが多いんですけど。新聞は「今、世の中こうなってます」っていうものを伝える。それに対して雑誌は、「今こう言われてるけど、本当はこうなんじゃないの?」って。そういうのを出すと、結構通りやすいんですね。
だから、「なぜ今」の立て方もいろいろあると思うんです。必ずしもこの先こういうことがあるから、これが流行ってるから、だけじゃなくて、今世の中みんなこういうふうに思ってるけど、こうなんですよ。うちはこういうことやってるんですと。そういうこともあると思いますし、設定の仕方って多様にあるのかなって。今「逆張り」とか言ったんですけど、雑誌的な視点でいくつか話してて。すみません。
雑誌の視点でよく言うのは、「誰もが知ってる会社の知られざる真実」っていうのは雑誌的だと。それから「誰も知らない会社のすごいところ」。だれも知らないけどこんなすごい会社がありますっていうのが、雑誌的な感覚なんですね。
さっきの逆張りで言うと、雑誌はニュースをひっくり返して見てみる。ある出来事があれば、それをひっくり返して見ればどう見えるか、横から見ればどう見えるか、斜めから見ればどうなるのか。そういう視点から書くのが雑誌的なスタイルだっていうふうに言われてますね。
大堀:確かにそういうのよく見かけます。
西頭:多分、Webの記事ってそういう傾向がますます強くなってきてるのかなっていう気がしますね。あとちょっと言いそびれてたんですけど、さっきの数字の問題でいうと、これからちょっと変わってくるかもしれないんですけど、紙とWebっていろいろと、制約の度合いが違っていて。
あんまりオンラインのほうが、数字がどうだってギリギリギリギリやらないで、取り上げやすいですね。現時点では。そこでまだ紙との違いがあるのかなと。
オンラインってすごくおもしろい、ユニークなものがあれば、別にきちんとそこで全部アップしなくたって、「こんなサービスがあります」っていう一発芸的なものでも通ることはありますし。あともう1つ、日経ビジネスオンラインでは、「記者の眼」というコラムがあります。それは、さっきの質問にもありましたけど、ものすごく記者の想いが反映します。通常の記事では書けない、書かないスタイルの記事で、それも記者が「私は個人的にこう思います」というものです。
ただ、特集でA社をとりあげて、そのA社に対する特集の記事は、さっきの2.5人称なんだけれども、「記者の眼」はもろ1人称で書くっていうこともありますね。そうすると、そこも紙とオンラインの役割分担のところかもしれないけど、この特集でこの記事書いた記者は、この会社に対してこんな思い入れとか思い込みがあって書いてたのかっていうのも分かったりするっていう。
「記者の眼」を読んで、この記者にコンタクトさせてくださいっていうのは、結構多いんですね。そこは「この記者さんって、こういうことに関心があるんだ」というのがストレートに出てるから、「じゃあうちも同じこういうことやってるんで、ちょっと話聞いてもらえませんか」みたいな。
なので、日経ビジネスの記者の特徴を知りたかったら、「記者の眼」を読んでみてもらうと、その記者の個性が分かるかもしれないですね。どんな分野に関心があって、どんな分野を取材して、どんな個人的な意見書くかって。
質問者:ありがとうございます。
ラインナップは発売3ヶ月前に決まっていた
大堀:では最後、手が挙がっているおふたりで終了したいと思います。
質問者:貴重なお話ありがとうございます。やっぱり週刊誌の場合、発売をして拝見した際に、「よくここまで細かな記事提供できたな」とか、「自分の連携不足がなければ、何かしらこの中に入り込めたのかな」って思うこともよくあって。
毎月2回のそういうアイデア会があるって仰ってたかと思うんですけれども、そういった特集を決めるとき、例えばどれくらい前に、例えば10月のだったら10月の前半にしたアイデア会の特集は、いつ発売の号に大体反映されるのかっていうところをちょっとお伺いしたいなと思いまして。ご質問させていただきました。
西頭:逆に、それをひっくり返して言うとですね。今1月のラインナップ等は、ほぼほぼ固まっています。2月以降は仮置きしてる。つまりアイデア会議で出た企画を仮置きしてるけれども、1月25日号まではほぼ決まってます。ただ週刊誌なんで、その間に何か突発的に大きなことが起こると、それを間に挟み込んで、1号ずつ後ろにずらすっていうことはあるんですけど。
なので、だいたい2〜3ヶ月先ぐらいまでの企画は、どういう企画を誰が担当するのかっていうのは決まってます。
そこから動き出すんですが、やっぱり今オンラインもやったり、記者の負荷が、我々が記者だった頃に比べればだいぶ増えてるんで、キックオフのミーティングがだいたい2ヶ月くらい前にあって、実際の取材活動っていうのは、だいたい1ヶ月間くらいなんですね。
最初にスケルトンっていうもの、大体の構成、メインタイトル案、サブタイトル案、1章2章3章をどういうふうにするのかっていうのを、特集のチームでキックオフの頃から作り上げていって。
特集が出るっていう原稿の締め切りの3週間前、4週間前くらいか、校了の4週間前くらいに編集長が揉みます。その時点で、このスケルトンではこういうところが足りないからこういうところ加えてよとか、ここはそんなに割かなくて良いんじゃないかっていうのを編集長と話し合って、そこから少し軌道修正して。
当然のことながら最初のスケルトンのときにこういうのを立てたけれども、実際に取材してみたら違ってました、だから大幅に変えますっていうこともあります。Aだと思ってたらBでしたとか、A´でしたっていうのは変えていきます。
最初からこうと決めたらこうでいくっていうものではないんですけども、それも2ヶ月くらい前に作ったものを調整しながら進んでいく。
わりと多いのは、ここのところフォーカスするよりもっとこっちを膨らませてねってなったときに、最初ある程度フォーカスするはずだったところが、ボリュームが少なくなって。4社取材してたんだけども、そこの中に放り込むとしたら2社しか放り込めないなっていうことで、取材をさせてもらったけれども、残りの2社の事例っていうのは、紙のほうでは落とさざるをえない。それはオンラインに移しますよっていうことにならざるをえない。
これをもっと言えば、全然論がひっくり返っちゃって、それに当てはまらなくなってしまったから、ちょっとこの企画では使えないなんてこともあります。その場合でもそのネタ自体がおもしろい、取り上げる価値があれば、この特集には上手く当てはまらないんだけれども、上手く抜き出して、例えばレポートで出そうとか、もうちょっと追加取材させてもらって、企業研究として2ヶ月後に出しましょうとかいうこともあります。
あるいは、もう特集に使うはずだったけど、「ちょっとこれはニュース性が高いから、先出ししたい」って言って、それだけ特集の前に出してしまうなんてこともあります。
ですから、大体2、3ヶ月先ぐらいまでを考えながら動いてるんだけれども、途中で微調整しながらいくんで、変わる可能性もあるという感じです。
質問者:わかりました、ありがとうございます。
掲載記事のトラブル。そのとき広報は
大堀:では、最後の方。
質問者:お話ありがとうございました。最後の質問で、私的で若干ネガティブな質問で申し訳ないんですけど。
西頭:いえいえ(笑)。
質問者:過去にインシデントがあったとか、そういうネガティブな要素を、その後の社長取材とかでどこまで隠すかっていうのをお聞きしたいです。隠すというか、どこまでお話するべきなのか、そこら辺のコミュニケーションの方法をずっと悩んでまして。
弊社も以前、インシデントがあったんですね。今までの会社のヒストリーを話してくるときに、必ずしもそのインシデントを話すこと自体がネガティブにならないケースと、そこを引っ張られてタイトルに付けられちゃうとか、そういうふうに転じてしまう場合と2つパターンがあって。
タイトルに付けられてしまうくらいまでいってしまうと怖いので、やっぱり「自分の口からは言わないでください」っていうふうに社長にコミュニケーションをとったりすることが多いんですね。
ただ、記者さんとか媒体とか読者の方のことを考えると、「少しそういうマイナスなときがあったけど、こうなりました」って言ったほうがいいのかなっていうのがありまして。どういうスタンスで、ネガティブな要素を取り扱いしているかとか、そこらへんをお聞きしたいんです。
西頭:その内容にもよると思うんで、ちょっと一般的な話しになってしまうかもしれないんですが。記者の方から問われたら、その話っていうのはこのときは確かにこういうことがあって、それに対してこういうふうに対処したとか、今はこういうふうに変わってますっていうことを、伝える必要はあると思うんですね。
逆に記者の方から全然その話に触れなかったら、こちらから触れたいんであればそれは触れてもいいんでしょうけど、全くそれについて聞いてこないんだったら、あえてその話を持ち上げる必要はないのかなと思います。
ちょっとそれと同じ事例なのかわからないのですが、今年に入ってから1回私が見た原稿で、そういうトラブルがありました。過去に事故を起こして、公取委から指摘を受けたっていう事例があるんですけど。
そういうトラブルが起こってどうしなくちゃいけないかっていうときに、その会社の企業理念が、その後立て直すときの指針になったっていうような話を書いてたんですね。
その話は実際の取材のときにも出てたんですけども、それを記事にするときに、やっぱり不祥事のときのクレド(経営理念)が指針になってて、その会社にとってクレドがどんなに大事なのかを記事の中で盛り込みたいっていう内容の話だったので、「不祥事のときクレドが指針になった」っていうのを、メインタイトルに入れたんです。
そしたら、その話があったのも事実だし、その話もしたけれども、何でメインタイトルにまで入れたんだっていう抗議を受けたんですね。
それに対して我々は、タイトルっていうのは編集権だと。要するに「どんなタイトルを付けるかっていうのは、記事を作る側にとっての1番のポイントになるところで、今回こういう内容を書きたくて、その内容を最も的確に伝えるためには、このタイトルが我々としてはふさわしいと考えたので、これがこういうふうになりました。申し訳ないけれども、訂正とか撤回というのはできません」というかたちで、押し通しました。
でも、結果的にはいい形として、その過去の問題があったっていうことがそこで再度明らかになっても、結果的にはよく取られるていうことは、あると思うんですね。
今私が話した具体的な事例って、多分その広報の方は2.5人称の視点じゃなくて(笑)。1人称2人称の視点、私にとって、私の会社がっていう部分が強かったんだと思うし、そうやって抗議受けたときにわかったのは、社長がすごい怒ってたと。でも、その社長が話した話なんですけれどね。
(会場笑)
西頭:ちょっと脱線するんですけど。よく広報から抗議受けるんですよ。日経ビジネスって抗議受ける回数がすごく多い雑誌なんじゃないかと思いますし、本当に半年間出入り禁止って言われることもあるんですね。
抗議を受けて、もちろん本当に間違ってるときは訂正しますし、やるんだけれども。やっぱりそこは広報の人たちとの人間関係とか繋がりがあって、さっき言ったような社長がすごく激昂してると。広報としては立場上抗議して、何らかの措置を、対応をしましたっていうことを言わなくちゃいけないっていうことはあるのは、私たちは十分理解しています。
だから、抗議に来られたら、対応はもちろんするんです。だけどそこで、これは修正しなくちゃいけないなっていうときはしますけど、「これは断固として修正は拒否します」と言って、「じゃあしばらく取材は控えてくださいね」となるときもあります。
逆にこちらが「もっと上の責任者の人に直接挨拶しに行きますから、説明しますから、そういう機会を作ってください」って言って、その社長なりあるいは役員の人に、「今回こちらとしてはこういう意図で書いたんだけれども、それがそちらの意に沿わなかったのは申し訳ないと思います。ただ、我々としてはこういう想いで書いてるんで、そこは理解してもらいたい」っていう対応をすることはやります。
広報としては、何か問題が起こったときにマスコミやメディアに対して抗議をしたり、そういうアクションをしたりっていうのは、当然会社の論理で動かなくちゃいけないっていうのはあると思うのでわかってますし、それで関係がお互いに悪くなるっていうことはないと思いますね。そこのところは、安心して欲しいなっていうふうに思います。
だから、「この記事は意に沿わなかったんだけど、抗議したり文句言ったら2度とうちの会社取り上げてくれなくなっちゃうだろう」とか、そういう心配は無用だと思いますし、もしそういう対応をするメディアがあったとしたら、そのメディアとは付き合う必要はないのかなって思いますね。
質問者:ベンチャーだと、やはりまだまだ取り上げてもらうのに必死なので……。1回そういうこと言ったらもう付き合わないとか、そうされるのかなっていう勝手な意識がすごい強かったので、ちょっと安心しました。ありがとうございます。
西頭:良かったです。
大堀:じゃあお時間もそろそろなので、一旦ここで締めさせていただきます。本日は西頭さん、どうもありがとうございました。
西頭:ありがとうございました。