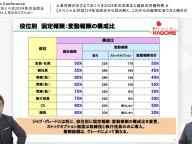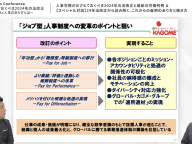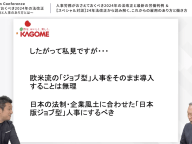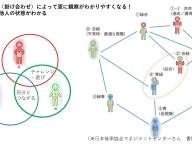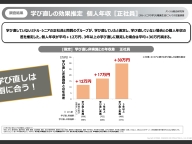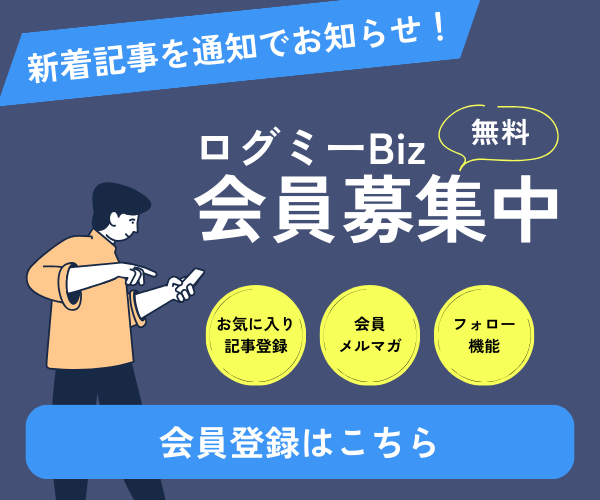物語に起きた一番の悲劇とは、文字の発明である
ギャレス・エドワーズ氏(以下、エドワーズ):人がなぜ、どのように物語を語るかということには、実はあまり違いはありません。僕はその理由は、人間という種が実は、不死であることにあると思っています。人間は個々では死んでしまいますし、繁殖を行い、自らのクローンである子孫を作りますよね。しかし、自分の経験だけは、コピーも繁殖もできません。良い意味で、まっさらなものです。
人間の身体はハードウェアです。そして僕が思うに、物語というものはソフトウェアであり、新たに子どもたちにダウンロードしていくものです。物語というものは、ポケットに入れて持ち運べるような小型サイズの、人生で得た教訓です。僕たちは、それを記録するのです。
物語では、ヒーローが誰も言ったことのない場所に行き、女性に出会い、悪人を倒し、村のためになにかを持ち帰ることについて語られます。僕たちが常にハッピーエンドに心惹かれるのは、いざ自分たちにその番が来た時に、そういった成功体験が役に立つからです。
僕にこんなことを教えてくれた人がいました。「物語に起きた一番の悲劇とは、文字の発明である」。
長い年月の間、人づてに伝えられた物語は、聞いた人がおもしろいと思った部分は残り、つまらない部分は切り捨てられます。さらに人に伝えられる折には、語り手がおもしろいと思ったことが少しづつ加えられていきます。このような繰り返しにより、物語はさらに進化を遂げ改良を増し、すべての人が聞きたいと思う話へと変貌を遂げるのです。
僕はこれにとても共感し、映画制作をできる限りオーガニックに保ちたいと思いました。そこで、脚本を書く時に、半分は楽をしたいからだったのですが、いつも心がけていたことがあります。
映画の登場人物に身体的に起こったことと、内面で感情的に起こったこととを結びつけようとしたのです。たとえば、なにもない場所にぽつんとある駅が舞台で、周りがとても騒々しい中でのセンチメンタルなシーンでは、そのままを書くのはいやだと思いました。もう少し柔軟性を持ちたいと思ったのです。
そこで、映画の登場人物に身体的に起こったことを黒インクで、感情的に起こったことを青インクで書きました。
僕たちはホイットニーをオースティンで拾い、メキシコまでドライブしました。メキシコ、ベリーズ、グアテマラ、コスタリカ、テキサスと周りました。行った先々で僕たちは「この場所で、興味深いものが見られるのはどこですか?」と尋ねました。「向こうでは洪水が起こっている、ダウンタウンでデモが行われている、建物が解体されている」等々、なんでもありです。
僕たちは実際にそういった場所に行き、身体的になにが起きるかを実際に試してみました。「すばらしい。これはストーリーに取り入れよう」。そして、今度は感情的になにが起きるかを試しました。そういったことを、行く先々で探して周りました。それは今までにない、すばらしい経験でした。
人生をかけたSXSWでの上映
僕は、役者と共に2ヶ月近く、運搬車で移動しましたが、これほどまでに過酷な時間を過ごしたことはありませんでした。さまざまなことを、急速に学び、適切な対応をする必要がありました。
なにもない渓谷のシーンだった場合、なんのシーンで、なにをやるべきかをわざわざ話す必要はなく、フォースのように伝えることができるようになるのです。イーブル・クニーブル(アメリカのスタントマン、グランドキャニオンを飛び越えるパフォーマンスを行った)のように、グランドキャニオン渓谷を飛ぶシーンであれば、谷を繋げる装置を作るだけでよいのです。シーンへの軌道を用意してあげれば、役者は自分たちの力で理解し、飛び立ちます。僕たちはフォローしてあげるだけです。
役者たちにバックグラウンドのストーリーや、存在理由、これからやろうとしていること、やってはいけないことを話し、あとの仕事は任せておけばよいのです。これがたいへんうまく行きました。
やがて映画は完成し、ありとあらゆる映画祭、クリスマス前から現在に至るまでに開催予定のある、大きな映画祭すべてにエントリーさせました。そしてすべての映画祭のエントリーに落ちました。
ところがありがたいことに、SXSWにおいて、特にティム・リーグ(配給会社「アラモ・ドラフトハウス」創設者)のおかげで……(素早く水を飲む)スティーブ・ジョブスはプレゼンテーションのプロですね。
(会場笑)
おかげで作品が上映されることになりました。未完成だったのでそのまま提出を余儀なくされました(『モンスターズ/地球外生命体(2010)』ギャレス・エドワーズ初監督長編作品)。
モンスターの映画でモンスターが登場するのですが、僕自身がVFXを手がけ、間に合わないので、本来であればVFXが入るべき箇所に「モンスター、ここで攻撃」などというテキストを、やむなくスクリーンに挿入しました。
SXSWでの上映が許可され、「アラモ・ドラフトハウス」のティム・リーグに、飛行機を降りたところで出迎えられました。僕はワールド・プレミアに出席するかのように、とても緊張していました。ティムは「ちゃんと完成させて、テキストを差し替えたかい?」と聞いてくれました。「もちろん! 心配しないでくれ。ずっときれいなフォントに変えたから」。
(会場笑)
もちろん、映画は完成していました。今ではこうしてジョークにできますが、当時は本当にがちがちに緊張していました。僕にとってはワールド・プレミアのような舞台に、人生をかけていたのです。当時の僕は35歳。このわすかな時間に、すべての有り金と、VFXのキャリアをかけていました。
時間が足りず、急いでいてプリントもなにもできなかったので、作品は、安物のテープ上にダビングされていました。すべてがこの瞬間にかかっていました。上映1時間で、テープが壊れました。ちくしょう!
あと20分というところでした。やがてエディターから「あと4秒!」と電話が入り、再スタートしたのです。
エージェントとの出会い
無事に終演し、その後Q&Aを行いました。僕が会場に降りてくると、大勢の人が次々と来て握手を求め「よかったよ」などと言葉をかけてくれました。1人が映画のプロデューサーだと自己紹介し、名刺をくれました。「映画プロデューサーだって! すごいじゃないか」と僕は思いました。また別の人が名刺をくれて、その後何人かと握手し、終わりました。
ここでどっとアンチ・クライマックスの波が襲いました。「これで終わり? 名刺2枚のために、僕は人生を投げ打ったのか? ギャレス、お前は35年間もなにをしていたのか。なにを期待していたのか。ユニコーンでも来てくれると思ったのか、僕は?」。何色のユニコーンかはわかりませんがブルーかピンクか、虹色でしょうか?
私はまた車に乗り込み、役者たちと共にホテルに戻ろうとしました。すると、映画プロデューサーらしき人が僕のそばに立っていました。「ああ失礼、このタクシーに乗ろうとしていらっしゃったのですか」「いいえ、私は役者さんの友人です。同じフロアに泊まっていたので、一緒に映画祭に来ていたのです」。
僕は「なんだ。この人は映画プロデューサーではなかったのか」とがっかりしました。「まったくの時間の無駄だった」。翌朝起きて会場に戻ると、僕は聞いたことのないWebサイトのインタビューを受け「これでおしまいなんだな」と思いました。
インタビューが終了すると、魔法で出てきたかのように、そばに男性が立っていました。「こんにちは。少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。昨晩、あなたの作品を見ました。お話をさせていただきたいのですが」「もちろんけっこうです」。そこで僕たちは話をしました。確かボーリング場かなにかだったと思います。オースティン出身の方であれば、ご存じの場所だと思います。
「私は、ハリウッドのエージェントです。映画について少しお話を聞かせてください。これまでどんなお仕事をされていたのでしょうか」。僕は「ドキュメンタリーを製作していました」と答えました。相手は、僕が良い人間か、悪い人間かを判別しようとしているわけですよね。そこで「どんなドキュメンタリーを製作されたのですか」と聞かれた僕は「孤児と里親制度についての作品です。アフリカ系アメリカ人家庭が、子どもを養子に迎えるドキュメンタリーを撮りました」と答えました。
「とてもすてきな話ですね。考えさせられるテーマだ。それでそのドキュメンタリーはどうなったのでしょうか」「さあわかりません」。
(会場笑)
彼はたいへん聡明な人で、「なんでこんな人がエージェントをやっているんだろう」と思いました。それに僕の方がずっと年上でした。
最後に彼は言いました。「私は映画監督の代行を行うエージェントですが、僕の担当している監督の名前はご存じでしょうか」。僕が「存じ上げません」と言いますと「クエンティン・タランティーノ、ティム・バートン、ウェス・クレイヴン、ジョン・ウーなどです。ぜひ、あなたの代行もさせていただきたい」。
彼の名前はマーク・シンプソン、オースティン出身です。前列のこちらの席にいらっしゃいます。
(会場拍手)
上映会でタランティーノにかけられた言葉は…
そこが僕の人生の分岐点でした。それ以降起こったことはすべて、いろいろな人々のおかげです。こういったスタジオのシステムを解説はしませんが、簡単に流れを説明しますと、まずアレーに行きます。自分の作品は、エージェンシーのプライベートなスクリーンで、いろいろな作品と一緒に上映されます。上映回数は3回です。
初回はプロデューサーを招待して上映されますが、大抵は来ません。アシスタントが来ます。そこに僕たち監督は行きません。アシスタントは、帰社して上司に推薦します。すると2回目にその上司が来ます。気に入られると、3回目に大手のハリウッドの配給会社が来ます。ですから監督は3回目に行くとよいのです。
(エドワーズ氏、水を飲む)
会場のみなさん、僕がなにかおもしろいジョークを言ったかのように笑ってください。
(会場笑)
なんだか僕は、水を飲むタイミングが下手になってきましたね。
さて僕は、この会場の4分の1くらいの規模の、こじんまりとした劇場に行くわけです。満席ではありません。そこで観客に自分の作品紹介と自己紹介をするのです。「僕はギャレス・エドワーズ、イギリス出身です。低予算映画を製作してきました。VFXは自分で担当しました」。
ふと見ると、2列目か3列目にボブ・ワインスタイン(旧ミラマックスフィルム創設者)がいます。さらに壇上で話し続けふと見ると、その隣にクエンティン・タランティーノがいて、僕は「うわあ!」などと驚くわけです。
食物を取りに出て「最後まで見届けなくては!」とエージェントの1人のリッチー・クッキーと急いで会場に戻り、映写室の窓から会場のリアクションを見ていると、ボブ・ワインスタインが立ち上がり、出て行ってしまいました。僕はがっかりしました。
さらに彼は、壁を殴りつけ、悪態をついているようでした。建物の外に出て行った彼は、やがて戻って来ました。そして誰かがギャレスが映写室にいると教えたらしく、こちらに来るではありませんか。彼が言うには「途中で邪魔が入った。映画を最後までぜひ見たいのだが、もう私は行かなくてはならない」。僕が「今晩にでも、またお会いするか作品を送るかしましょうか」と言いますとボブ・ワインスタインは「ぜひそうしてくれ!」。
僕は作品のコピーも、DVDも持っていなかったので「エージェントが送ってくれると思いますよ」と伝えました。やがて業界人たちがぞろぞろと会場から出て来ました。マイクが、僕が『レザボア・ドッグス(1992)』の大ファンで、劇場で7回も鑑賞したことを知っていたので、クエンティン・タランティーノ監督を連れて来てくれました。過去15年間、僕が壁に飾っていた唯一のポスターは、タランティーノ監督のサイン入りの『レザボア・ドッグス』のものなのです。
監督が僕に話しかけてくれたのですが、「クエンティン・タランティーノだ!」と、ぼうっとしていた僕の耳に聞こえたのは「ふぁふぁふぁふぁ」という音だけでした。彼が握手をして行ってしまうと、周りの人が集まって来て「どんなことを言われた? 彼はなんと言った?」と口々に尋ねました。僕は「わからない」と答えました。
(会場笑)
たぶんなのですが、「映画は駄作だけど、よく頑張った」というようなことを言われた気がします。
(会場笑)