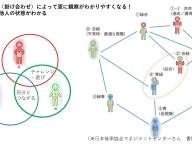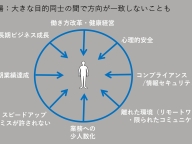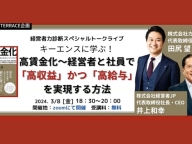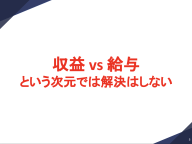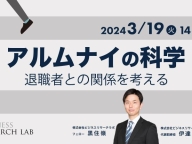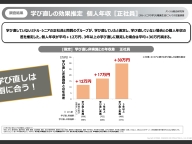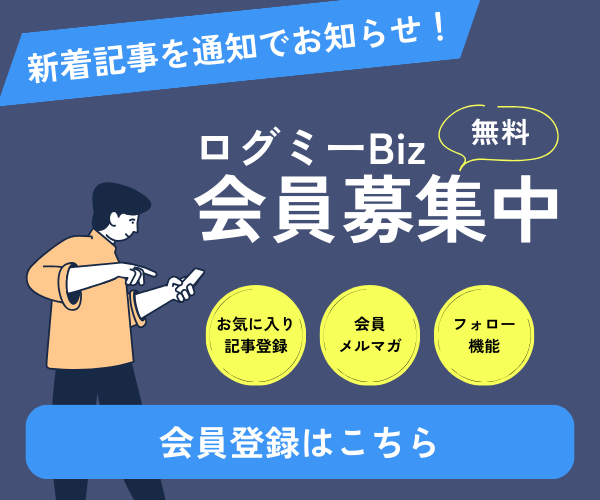日本彫刻のルネサンス時代
カリン・ユエン氏:絵巻と呼ばれる着彩された巻物は、この鎌倉時代を通じて制作されますが、この時代はとりわけ「日本彫刻のルネサンス時代」とみなされたように、彫刻が特徴的です。慶派の仏師たちは、奈良に拠点を構えていて、戦争の影響を受けた寺院の彫刻の再建と修復に重要な役割を果たしました。
この流派は、平安時代の仏師定朝の遺産でもあり、より写実的な新しい様式の彫刻を生み出しました。この流派の重要人物は、康慶とその息子の運慶と快慶です。工房は慶派の名前を継ぐ家業として営まれ、彼らは鎌倉時代のもっとも革新的で、熟達した仕事の責任者でもありました。
「寄木造(よせぎづくり)」と呼ばれる複数の木の塊を用いる技法を継承し、彼らは奈良時代初期の仏像の傑作と、宋王朝の彫刻と絵画を研究していました。そして、感情の表出や、堅牢さや動きといった特質を復活させたのです。彼らは木材や金属を素材として選択し、粘土や乾漆像、金属浮き出しや素焼きの陶土は復活させませんでした。
源平の争乱の後、最初の数年間は再建事業が最優先事項の1つでした。国の伝統的な仏教基盤を再び活性化し、戦争中に損害を受けて破壊された仏教寺院を再建し、新たに現れた需要や趣向に応じるべく、現存する仏教施設を刷新したかったのです。
この優先事項の1つに、高く崇められた古代寺院である、奈良の東大寺の再建事業がありました。再建の任を担ったのが、俊乗坊重源(しゅんじゅうぼうちょうげん)という僧侶です。仏教の修行のために3回以上も中国を訪れ、同時代の中国の建築を学んだことは、大仏様と呼ばれる再建時の審美面に影響を与えました。
この重源の肖像彫刻は、おごそかで写実的な当時の様式を伝えています。おそらく1206年の死後まもなく制作され、彼の名誉を追悼するものとして用いられました。体をわずかに前に傾け、念仏を唱える姿勢で座る年老いた男の像です。念仏の間じゅう、手にした数珠によって数を数えています。桧の寄木造で彫られ、肌の肉色と、衣の黒で簡単に彩色されています。
彫刻は、突出した頬骨、皺だらけの肌、すぼめた唇、骨ばった眉毛の下にある深くくぼんだ眼、といった顔面の細部に注意を払っています。これは、肉体的にも精神的にも強靭で、心のうちから宗教的な使命に身を捧げた、老いた僧侶の像なのです。
運慶と快慶の金剛力士像
東大寺には、この時代を通じて運慶と快慶のもっとも名高い作品である、巨大な対の金剛力士像が保存されています。南大門にある2体の仁王像は、この時代のダイナミックで写実的な傑作の例です。約8メートル、26フィートの高さの彫刻は、寄木造で制作され完成に3ヵ月を要し、職人たちが1人の親方の監督で仕事をする、洗練された工房のシステムを示しています。
これらの仁王像と呼ばれる仏像たちは、寺院の入り口の正門を守っています。右の阿形(あぎょう)は口を開き、左の吽形(うんぎょう)は口を閉じ、生と死、始まりと終わりを表象していると言われています。恐ろしく威圧するような外観は、悪霊を追い払い、寺院の土地に悪魔や盗賊が入らないようにするためです。
2体の守護神は、ドラマティックに腰をあげた姿勢で、一瞬の動きを止めた印象を与えています。上げられた腕は力強く、護衛するような動作で、衣服の布は片側に翻っています。三次元的な特長や動きの感覚を強調するように、力強く彫り込まれています。8世紀の奈良時代の彫刻の知識をもとに、時代にふさわしい新たな様式で作り直されたのです。その写実主義は、誇張されたある1点を強調し、演劇的な意味を高めています。
運慶の成熟した作例は、興福寺の境内の北円堂、つまり北に位置する八角形の講堂に見出されます。中心にある弥勒如来像は(将来の仏陀の姿)、元々は二体の菩薩像と四天王像(4人の守護神)、そして2体のインドの羅漢像を伴っていましたが、今日これらのうち現存するのは弥勒如来像と2体の羅漢像のみです。
弥勒如来像は、八角形の台座の上に足を組み坐していて、その丹念な透かし細工の背光は、頭の後ろから出ています。この彫刻は、仏陀の将来の姿を現していて、運慶はこの作品によってプロポーション(人体比例)の新しい釣り合いに到達したのです。これは平安時代に定朝が平等院の阿弥陀如来像で達したプロポーションと近いものです。
この仏像の頭部は、そこまで重い外観ではありません。顔面の表情と衣襞はより深く刻まれ、より自然な見せかけを与えています。眼球は水晶がはめこまれ(注:彫眼と記述されているものもある)、これは12世紀後期に共通する技法でした。瞳はやや下方に向けられ、憂鬱な表現をほのめかしています。外見は少し親しみやすく柔和で、礼拝者が対話を交わしたいと願うような、人間的な神の姿をしています。
仏教では、羅漢は完全なる悟りには達していない修行者ですが、そこに至る道のりを長く歩んでいて、輪廻転生から解脱した存在です(注:とする説もある)。羅漢像として無著と世親の兄弟が表現されています。(注:無著と世親は紀元5世紀に北インドで法相教学を確立した兄弟)無著像は、弟よりも痩せた人物像で、聖遺物箱が布でくるまれた円筒形の物体を手に持っています。世親像の手は、話しているような動作をしています。
無著はより思慮深く内省的ですが、もう1人の世親は観者と目を交わすように外交的な印象を持ちます。両僧侶の衣服は、深く刻みこまれ、不規則に折り畳まれ落ちています。彼らの見かけは、非常に自然主義的で、自立的であり、正面だけの姿勢をしていません。
漫画にも似た華厳縁起絵巻
とりわけ印象的な仏像は、運慶の息子である康勝の作品「空也上人立像」です。空也上人は阿弥陀如来の教えを広めるため本州各地を旅しました。彼は鹿を殺した、自分の非動さを実感したことがきっかけで、仏門に帰依します。あちこちの村や町で念仏を唱える教えを続け(口称念仏)、礼拝の儀式では鐘や鈴にあわせて踊りながら念仏を唱えました(注:踊念仏の開祖ともいわれるが、空也自身が実践したことは証明されていない)。
鹿の枝角が歩行杖に取り付けられ、彼が僧侶になったきっかけを思い起こさせます。康勝の彫刻は、歩きだす動作の姿勢した、胸に銅羅を下げ、くびきを肩にかけた男の像です。僧侶の口から出ている針金には、6つの阿弥陀仏の像が貼り付けられ、6つの名号(南無阿弥陀仏)の音が象徴されています。これらは彼の信仰と献身を反映しています。
源平の争乱の後、明恵上人という僧侶が、華厳宗を復活させようとしました。奈良時代は重要な宗派の1つだったのですが、浄土教全盛期の時代に苦戦しました。平氏の父と藤原氏の家系の母から生まれ、彼は源平の争乱初期に孤児となり、神護寺の仏僧をしていた叔父に引き取られました。
明恵上人は、世捨て人のようであり、再建事業には興味を持たず、その代わりに真言宗と華厳宗の両方の要素を組み合わせ、新しい仏教の教義を形成することに心血を注ぎました。
華厳縁起絵巻「華厳宗祖師絵伝」は2つの物語絵巻で成り立ちます。新羅時代の朝鮮の僧、義湘(ぎしょう)と元暁(げんぎょう)の人生が描写されています。2人は新羅華厳宗の開祖であり、ここから日本の華厳宗がもたらされました。物語は、2人の僧侶が、共に中国を旅しようと朝鮮半島の新羅王国を出発するところから始まります。
2人は雨をしのぐために最初の夜を埋葬用の洞窟で過ごし、身の毛もよだつような、角を持つ悪魔を見た後、元暁は最善の方策を熟考します。そして、旅をするという計画自体をあきらめます。ところが義湘は、中国へと歩を進め、そして一団の冒険仲間を得ます。
彼が新羅に戻る前に、善明という美しい女性と出会い、恋に落ちます。達磨の教えに心酔する彼は、彼女の親切を無視しますが、彼女は彼の宗教心を受け入れざるを得ませんでした。彼が故国に戻る時、彼女は海に身を投げ、船を龍として守ります。いや、正しくは龍になったのです。愛のためにできないことはないですね。
この絵巻は、鎌倉時代の大衆に普及した仏教の傾向を示す、すばらしい一例でもあります。女性信者のために、女性が学ぶことが制限されていた、漢字の使用が部分的に抑えられ、支援者としての善明の役割が強調され、幅広い階層の人びとに向けて制作されていたことがわかります。
この物語は、長い旅と痛切な恋愛譚が含まれ、叙事詩的な小説のように読めます。そして発話は登場人物の真横に文字で書かれ、今日の漫画に似ています。